Shows

Theological Family MinistryDomestic Missions and the FamilyDomestic Missions and the Family by Theological Family Ministry Podcast (TFM)
2026-01-1455 min
羽多野渉と古賀葵 コエ×コエ#奥友沙絢 が体験した不思議な出来事とは…?#コエコエtfmラジオ局TOKYO FMにて毎週土曜日・深夜3時30分~4時00分放送中
声優・羽多野渉と古賀葵が毎週"コエ"や"コトバ"を深掘りする
コエカルチャープログラム『コエ×コエ』
こちらは、TOKYO FM Podcasts 他、各種配信サイトで配信中の『裏コエ×コエ』
コエタマちゃんの親友・奥友沙絢と一緒にアフタートークなどをお届け!
ハッシュタグ:#コエコエtfm
メッセージフォーム:https://tfm.co.jp/f/koekoe/message
Podcast:https://tfm.co.jp/podcast/koekoe/
【番組コーナー】
■月末企画「いいコエリクエスト」
あなたが『いいコエだな』『いいコトバだな』と思う楽曲のリクエストを募集中!
■コエポスト ~拝啓、あの時のわたしへ~
過去の自分宛に手紙を書いて下さい。
羽多野渉&古賀葵が、あなたに代わって読み上げます。
■大☆喜☆利☆王 デュエルワードダス
お題に沿った大喜利回答を羽多野渉チーム・古賀葵チーム
に分かれて募集中!
■クイズ!喜怒哀ACT(キドアイラクト)!
"感情の演技だけ"を聞いて、どんなシチュエーションか当てる企画。
シチュエーションのお題を募集中!
■その他
番組の感想、出演作の感想など、自由なメッセージも大歓迎!
2026-01-1013 min
羽多野渉と古賀葵 コエ×コエ#羽多野渉 #古賀葵 出演の『Fate/strange Fake』はどんな作品?何も言えない!?笑 #コエコエtfmラジオ局TOKYO FMにて毎週土曜日・深夜3時30分~4時00分放送中
声優・羽多野渉と古賀葵が毎週"コエ"や"コトバ"を深掘りする
コエカルチャープログラム『コエ×コエ』
こちらは、TOKYO FM Podcasts 他、各種配信サイトで配信中の『裏コエ×コエ』
コエタマちゃんの親友・奥友沙絢と一緒にアフタートークなどをお届け!
ハッシュタグ:#コエコエtfm
メッセージフォーム:https://tfm.co.jp/f/koekoe/message
Podcast:https://tfm.co.jp/podcast/koekoe/
【番組コーナー】
■月末企画「いいコエリクエスト」
あなたが『いいコエだな』『いいコトバだな』と思う楽曲のリクエストを募集中!
■コエポスト ~拝啓、あの時のわたしへ~
過去の自分宛に手紙を書いて下さい。
羽多野渉&古賀葵が、あなたに代わって読み上げます。
■大☆喜☆利☆王 デュエルワードダス
お題に沿った大喜利回答を羽多野渉チーム・古賀葵チーム
に分かれて募集中!
■クイズ!喜怒哀ACT(キドアイラクト)!
"感情の演技だけ"を聞いて、どんなシチュエーションか当てる企画。
シチュエーションのお題を募集中!
■その他
番組の感想、出演作の感想など、自由なメッセージも大歓迎!
2026-01-0306 min
羽多野渉と古賀葵 コエ×コエ#奥友沙絢 が名探偵コナンに出演!いいコエリクエストの感想メッセージも!#コエコエtfmラジオ局TOKYO FMにて毎週土曜日・深夜3時30分~4時00分放送中
声優・羽多野渉と古賀葵が毎週"コエ"や"コトバ"を深掘りする
コエカルチャープログラム『コエ×コエ』
こちらは、TOKYO FM Podcasts 他、各種配信サイトで配信中の『裏コエ×コエ』
コエタマちゃんの親友・奥友沙絢と一緒にアフタートークなどをお届け!
ハッシュタグ:#コエコエtfm
メッセージフォーム:https://tfm.co.jp/f/koekoe/message
Podcast:https://tfm.co.jp/podcast/koekoe/
【番組コーナー】
■月末企画「いいコエリクエスト」
あなたが『いいコエだな』『いいコトバだな』と思う楽曲のリクエストを募集中!
■コエポスト ~拝啓、あの時のわたしへ~
過去の自分宛に手紙を書いて下さい。
羽多野渉&古賀葵が、あなたに代わって読み上げます。
■大☆喜☆利☆王 デュエルワードダス
お題に沿った大喜利回答を羽多野渉チーム・古賀葵チーム
に分かれて募集中!
■クイズ!喜怒哀ACT(キドアイラクト)!
"感情の演技だけ"を聞いて、どんなシチュエーションか当てる企画。
シチュエーションのお題を募集中!
■その他
番組の感想、出演作の感想など、自由なメッセージも大歓迎!
2025-12-2707 min
羽多野渉と古賀葵 コエ×コエ#羽多野渉 のオカルトーク2025! 接近中の「3I/ATLAS」とは!?#コエコエtfmラジオ局TOKYO FMにて毎週土曜日・深夜3時30分~4時00分放送中
声優・羽多野渉と古賀葵が毎週"コエ"や"コトバ"を深掘りする
コエカルチャープログラム『コエ×コエ』
こちらは、TOKYO FM Podcasts 他、各種配信サイトで配信中の『裏コエ×コエ』
コエタマちゃんの親友・奥友沙絢と一緒にアフタートークなどをお届け!
ハッシュタグ:#コエコエtfm
メッセージフォーム:https://tfm.co.jp/f/koekoe/message
Podcast:https://tfm.co.jp/podcast/koekoe/
【番組コーナー】
■月末企画「いいコエリクエスト」
あなたが『いいコエだな』『いいコトバだな』と思う楽曲のリクエストを募集中!
■コエポスト ~拝啓、あの時のわたしへ~
過去の自分宛に手紙を書いて下さい。
羽多野渉&古賀葵が、あなたに代わって読み上げます。
■大☆喜☆利☆王 デュエルワードダス
お題に沿った大喜利回答を羽多野渉チーム・古賀葵チーム
に分かれて募集中!
■クイズ!喜怒哀ACT(キドアイラクト)!
"感情の演技だけ"を聞いて、どんなシチュエーションか当てる企画。
シチュエーションのお題を募集中!
■その他
番組の感想、出演作の感想など、自由なメッセージも大歓迎!
2025-12-2008 min
羽多野渉と古賀葵 コエ×コエゲストは #吉岡茉祐 さん!キャラソンライブはどうなりそう?#コエコエtfmラジオ局TOKYO FMにて毎週土曜日・深夜3時30分~4時00分放送中
声優・羽多野渉と古賀葵が毎週"コエ"や"コトバ"を深掘りする
コエカルチャープログラム『コエ×コエ』
こちらは、TOKYO FM Podcasts 他、各種配信サイトで配信中の『裏コエ×コエ』
コエタマちゃんの親友・奥友沙絢と一緒にアフタートークなどをお届け!
ハッシュタグ:#コエコエtfm
メッセージフォーム:https://tfm.co.jp/f/koekoe/message
Podcast:https://tfm.co.jp/podcast/koekoe/
【番組コーナー】
■月末企画「いいコエリクエスト」
あなたが『いいコエだな』『いいコトバだな』と思う楽曲のリクエストを募集中!
■コエポスト ~拝啓、あの時のわたしへ~
過去の自分宛に手紙を書いて下さい。
羽多野渉&古賀葵が、あなたに代わって読み上げます。
■大☆喜☆利☆王 デュエルワードダス
お題に沿った大喜利回答を羽多野渉チーム・古賀葵チーム
に分かれて募集中!
■クイズ!喜怒哀ACT(キドアイラクト)!
"感情の演技だけ"を聞いて、どんなシチュエーションか当てる企画。
シチュエーションのお題を募集中!
■その他
番組の感想、出演作の感想など、自由なメッセージも大歓迎!
2025-12-1308 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖ポストイット祭り終焉へ TFM-OpsとAIの共創術企業やプロジェクトの現場で形式化・形骸化しがちな「儀式的ワークショップ」の問題点を指摘し、それを解決するための具体的なフレームワークとして**「TFM-Ops」を提案しています。ワークショップが目的化し、時間の浪費や意思決定の遅延を引き起こしている現状を分析した上で、Thinker(戦略家)、Facilitator(推進者)、Maker(実行者)という3つの役割を明確にし、さらにAIを共創パートナーとして活用する**TFM-Opsの概念を解説しています。このTFM-Opsの視点を取り入れることで、ワークショップの目的を明確化し、アウトプット(試作品)を重視し、生産的で実りある共創の場へと進化させられると論じています。最終的に、設計・ファシリ(進行)・記録・改善のサイクルを通じて、TFM-Opsの考え方を現場に定着させる方法が示されています。
2025-12-0715 min
羽多野渉と古賀葵 コエ×コエ#羽多野渉 のファンミや #古賀葵 の朗読劇について! #コエコエtfmラジオ局TOKYO FMにて毎週土曜日・深夜3時30分~4時00分放送中
声優・羽多野渉と古賀葵が毎週"コエ"や"コトバ"を深掘りする
コエカルチャープログラム『コエ×コエ』
こちらは、TOKYO FM Podcasts 他、各種配信サイトで配信中の『裏コエ×コエ』
コエタマちゃんの親友・奥友沙絢と一緒にアフタートークなどをお届け!
ハッシュタグ:#コエコエtfm
メッセージフォーム:https://tfm.co.jp/f/koekoe/message
Podcast:https://tfm.co.jp/podcast/koekoe/
【番組コーナー】
■月末企画「いいコエリクエスト」
あなたが『いいコエだな』『いいコトバだな』と思う楽曲のリクエストを募集中!
■コエポスト ~拝啓、あの時のわたしへ~
過去の自分宛に手紙を書いて下さい。
羽多野渉&古賀葵が、あなたに代わって読み上げます。
■大☆喜☆利☆王 デュエルワードダス
お題に沿った大喜利回答を羽多野渉チーム・古賀葵チーム
に分かれて募集中!
■クイズ!喜怒哀ACT(キドアイラクト)!
"感情の演技だけ"を聞いて、どんなシチュエーションか当てる企画。
シチュエーションのお題を募集中!
■その他
番組の感想、出演作の感想など、自由なメッセージも大歓迎!
2025-12-0606 min
羽多野渉と古賀葵 コエ×コエKPF2025はどうだった?「Fate/strange Fake」についても!#コエコエtfmラジオ局TOKYO FMにて毎週土曜日・深夜3時30分~4時00分放送中
声優・羽多野渉と古賀葵が毎週"コエ"や"コトバ"を深掘りする
コエカルチャープログラム『コエ×コエ』
こちらは、TOKYO FM Podcasts 他、各種配信サイトで配信中の『裏コエ×コエ』
コエタマちゃんの親友・奥友沙絢と一緒にアフタートークなどをお届け!
ハッシュタグ:#コエコエtfm
メッセージフォーム:https://tfm.co.jp/f/koekoe/message
Podcast:https://tfm.co.jp/podcast/koekoe/
【番組コーナー】
■月末企画「いいコエリクエスト」
あなたが『いいコエだな』『いいコトバだな』と思う楽曲のリクエストを募集中!
■コエポスト ~拝啓、あの時のわたしへ~
過去の自分宛に手紙を書いて下さい。
羽多野渉&古賀葵が、あなたに代わって読み上げます。
■大☆喜☆利☆王 デュエルワードダス
お題に沿った大喜利回答を羽多野渉チーム・古賀葵チーム
に分かれて募集中!
■クイズ!喜怒哀ACT(キドアイラクト)!
"感情の演技だけ"を聞いて、どんなシチュエーションか当てる企画。
シチュエーションのお題を募集中!
■その他
番組の感想、出演作の感想など、自由なメッセージも大歓迎!
2025-11-2910 min
羽多野渉と古賀葵 コエ×コエ2025年の新語・流行語どれだけ知ってる?#コエコエtfmラジオ局TOKYO FMにて毎週土曜日・深夜3時30分~4時00分放送中
声優・羽多野渉と古賀葵が毎週"コエ"や"コトバ"を深掘りする
コエカルチャープログラム『コエ×コエ』
こちらは、TOKYO FM Podcasts 他、各種配信サイトで配信中の『裏コエ×コエ』
コエタマちゃんの親友・奥友沙絢と一緒にアフタートークなどをお届け!
ハッシュタグ:#コエコエtfm
メッセージフォーム:https://tfm.co.jp/f/koekoe/message
Podcast:https://tfm.co.jp/podcast/koekoe/
【番組コーナー】
■ 月末企画「いいコエリクエスト」
あなたが『いいコエだな』『いいコトバだな』と思う楽曲のリクエストを募集中!
■コエポスト ~拝啓、あの時のわたしへ~
過去の自分宛に手紙を書いて下さい。
羽多野渉&古賀葵が、あなたに代わって読み上げます。
■大☆喜☆利☆王 デュエルワードダス
お題に沿った大喜利回答を羽多野渉チーム・古賀葵チーム
に分かれて募集中!
■クイズ!喜怒哀ACT(キドアイラクト)!
"感情の演技だけ"を聞いて、どんなシチュエーションか当てる企画。
シチュエーションのお題を募集中!
■その他
番組の感想、出演作の感想など、自由なメッセージも大歓迎!
2025-11-2210 min
Theological Family MinistryTFM Classic: Thanksgiving SpecialWe return to our Thanksgiving special from the 2010s and we hope we all have some new things to be thankful for this year.
2025-11-1941 min
羽多野渉と古賀葵 コエ×コエ#羽多野渉&#古賀葵&#奥友沙絢 のラブタイプ診断を実施!コエ×コエの関係値が丸わかり!?#コエコエtfmラジオ局TOKYO FMにて毎週土曜日・深夜3時30分~4時00分放送中
声優・羽多野渉と古賀葵が毎週"コエ"や"コトバ"を深掘りする
コエカルチャープログラム『コエ×コエ』
こちらは、TOKYO FM Podcasts 他、各種配信サイトで配信中の『裏コエ×コエ』
コエタマちゃんの親友・奥友沙絢と一緒にアフタートークなどをお届け!
ハッシュタグ:#コエコエtfm
メッセージフォーム:https://tfm.co.jp/f/koekoe/message
Podcast:https://tfm.co.jp/podcast/koekoe/
【番組コーナー】
■ 月末企画「いいコエリクエスト」
あなたが『いいコエだな』『いいコトバだな』と思う楽曲のリクエストを募集中!
■コエポスト ~拝啓、あの時のわたしへ~
過去の自分宛に手紙を書いて下さい。
羽多野渉&古賀葵が、あなたに代わって読み上げます。
■大☆喜☆利☆王 デュエルワードダス
お題に沿った大喜利回答を羽多野渉チーム・古賀葵チーム
に分かれて募集中!
■クイズ!喜怒哀ACT(キドアイラクト)!
"感情の演技だけ"を聞いて、どんなシチュエーションか当てる企画。
シチュエーションのお題を募集中!
■その他
番組の感想、出演作の感想など、自由なメッセージも大歓迎!
2025-11-1512 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖AI駆動開発の未来:今こそPivotal哲学、TFM-Ops、そして人間とAIの協働スタイル生成AIやLLM(大規模言語モデル)の進化によって劇的に変化しつつあるソフトウェア開発において、コンサルタントがAIツールをワークフローに取り入れるための包括的な指南書です。**Pivotal Trackerの哲学**(フィーチャ駆動かつユーザ価値中心の開発)を出発点に、**TFM-Opsフレームワーク**(Thinker・Facilitator・Makerという3つの役割モデル)を統合し、さらにAI駆動のプロトタイピングツール(Bolt.new、v0.dev、Lovable.dev)やGPTの活用法を解説することで、「ヒト×AI」協働の次世代開発プロセスを具体的に解説しています。TFM-OpsモデルとAIツールの適用事例として、以下のケースが紹介されています。* **ケース1(MVP開発):** スタートアップのMVP開発において、ThinkerがChatGPTでニーズを分析し、FacilitatorがBolt.newを使ったワークショップを開催。通常1か月以上かかる開発を約半分の2週間で完了し、主要KPI(再訪率)が20%向上しました。* **ケース2(エンタープライズDX):** 大手製造業のDXプロジェクトで、GPTによる業務分析とLovable.devを活用した現場担当者との共同プロトタイプ作成を実施。現場担当者自身が「本当に欲しいもの」を形にできた結果、開発期間が短縮され、リリース後のアプリ定着率も高まりました。* **ケース3(コンサルファーム内のナレッジ活用):** 社内AIハッカソンでTFM-OpsチームがGPTチャットボットを開発。Thinkerが描いた構想をMakerがAIで即座に形にでき、戦略課題抽出から実装までがスムーズにつながった好例です。これらの事例から、AI駆動開発は開発スピードを飛躍的に向上させつつ、ユーザ価値への集中度も高めることが示されています。コンサルタントはAIを上手に組み込むことで、提案から実行支援まで一貫した価値提供が可能となります。### 第7章:テンプレート&チェックリスト集実務ですぐに活用できるツールとして、ユーザーストーリーテンプレート(INVEST原則に基づく推敲を推奨)、AIプロンプトレシピテンプレート(構造化して具体的に記述する)、AIプロトタイピングワークショップ準備・進行チェックリスト、および開発プロジェクト向けAI活用プランニングシートが提供されています。結論として、AI時代においても「小さく始めて素早く学び、適応しながら前進する」というアジャイルの原則は不変です。Pivotal Trackerのユーザ価値志向とTFM-Opsの役割統合を軸にAIの力を活用することで、試行錯誤のサイクルを高速・低コストで回すことができ、コンサルタントはクライアントに新たな価値を提供できると結ばれています。
2025-10-2824 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖TFMアップデート:MakerからExperience MakerへExperience Maker(エクスペリエンス・メーカー)は、AI時代のTFM-Ops(Thinker/Facilitator/Maker)フレームワークにおいて、「戦略と実行の断絶」という構造的課題を克服し、「腹の膨れる餅(実装された価値)」を迅速に提供することを目的とした、進化形の実装者・具現化の役割を担います。ご提示いただいたソースに基づき、Experience Makerの役割について、名称の定義、核となるミッション、TFM-Opsにおける連携、および具体的な活動に分けて詳細にまとめます。--------------------------------------------------------------------------------I. Experience Makerの名称と定義Experience Makerは、従来の「Maker(実装者)」の役割がAI活用によって高度に戦略化した結果として定義されています。1. 推奨名称: 最も推奨される名称は「AI駆動型エクスペリエンス・メーカー (AI-Driven Experience Maker)」です。この名称は、役割の核心である「体験」の創出を維持しつつ、生成AIがその実現のためのブースター(増幅装置)であることを明確に示しています。2. その他の呼称: その機能から、「ストラテジック・ビジュアライザー (Strategic Visualizer)」や「Vibeコンテンツ・メーカー (Vibe Content Maker)」としても位置づけられます。特にストラテジック・ビジュアライザーは、戦略的仮説を具現化するための「視覚化(Visualization)」の機能を強調しています。3. 役割の核心: Makerは、サイモン・シネックのゴールデンサークルにおいて、**「What(何を創るか)」**という具体的な結果やアウトプットで答える役割を担います。II. 核となるミッションと提供価値Experience Makerの存在意義は、抽象的な議論や戦略を「触れる体験」へと変換し、クライアントが提案内容を肌で体感できる「味見できる餅」を生成することにあります。• 信条と行動原則: Makerの信条は「百聞は一見に如かず、百見は一触に如かず」であり、とにかくまず作ってみることを重視します。何週間もかけて完璧な資料を作るよりも、たった1日で不格好でも動くものを作り、そこからリアルな反応を得て学びを最大化することを追求します。• 克服すべき課題: Experience Makerがいない場合、会議は抽象論に終始したり、戦略が「絵に描いた餅」で終わったりするという、従来のコンサルティングが抱える非実装の構造的課題を克服します。• 成果物の範囲: 従来のMVP(実用最小限の製品)という「動くプロダクト」に加え、Experience Makerは、提案書、インフォグラフィック、ビジネスシミュレーターといった、戦略仮説の数値シナリオ化やデータ可視化を担い、戦略的アウトプットの具現化を行います。III. TFM-Opsにおける連携とAI活用Experience Makerは、AIを「ブースター(増幅装置)」として活用し、ThinkerとFacilitatorの生み出した価値を高速で具体化します。1. AIによる実装の加速(Vibe Workingの実践)Makerは、AIを「相棒」として活用する Vibe Working(バイブワーキング)を実践することで、少人数でも百人力の生産性を実現します。• AIとの関係: MakerとAIの関係は、人間がディレクター、AIが超優秀なプレイヤーのジャムセッションのようです。Makerが抽象的な雰囲気(Vibe)や感覚を伝えると、AIがそれを組み取ってコードやコンテンツを生成し、プロトタイピングサイクルを劇的に加速させます。• 具体的なAI活用例: ◦ プロトタイプ開発: Bolt.new や Supabase を用いてアプリの骨組みを生成し、簡単なプロトタイプに着手します。 ◦ コーディング支援: ChatGPTやCopilotをコーディング支援/トラブルシューティングに活用し、コード生成・補完を実践します。 ◦ ビジュアル作成: CanvaやFigmaのAIプラグインを用いて、ビジュアルアセットの自動生成やデザインの試行錯誤を行います。 ◦ データ可視化: ChatGPTにSQLクエリ生成やデータ解釈を依頼し、戦略仮説に必要なデータ検証とグラフ化を迅速に行います。2. TFM-Opsとの連携Experience Makerは、ThinkerとFacilitatorが担う定性的な価値を、定量・体験的な価値へと変換することで、高速フィードバックサイクルを実現します。• Thinkerとの連携 (Why): Thinkerが提示した課題定義メモや仮説シナリオを、資料やシミュレーションに即座に変換し、BMC(ビジネスモデルキャンバス)を図解化してDriveに格納します。• Facilitatorとの連携 (How): Facilitatorが設計したワークショップや発表ストーリーの骨子を、インフォグラフィックやストーリーテリング素材に展開し、参加者の合意形成を加速させます。また、提案全体の品質とリスクヘッジを高めるため、ClaudeによるロジックレビューやChatGPTによる想定QAシミュレーションを活用し、提案準備に貢献します。
2025-09-2819 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖AI時代の新働き方:Thinker Facilitator Maker(TFM-Ops)でAIと「共創」する戦略と実践『TFM-Ops理解&実践マインドセット エピソード』です。このエピソードは、生成AIの登場によってコンサルティング業界の「常識」が一瞬で変わり、新しい働き方の波が押し寄せている時代背景の中で作成されました。従来の「AIに仕事を奪われるか?」という問いから、「どうAIと協働するか?」という問いに焦点が移る中で生まれた、新しいプレイブックである「TFM-Ops」に特に焦点を当てて解説しています。このマインドセットブックの主な内容と目的は以下の通りです。マインドセットブックの内容と目的1. TFM-Opsフレームワークの解説 本書は、TFM-Opsという新しい仕事のフレームワークの全体像を解説しています。 TFM-Opsは、**Thinker(思考者)、Facilitator(推進者)、Maker(創造者)**という3つの役割を軸としています。2. 役割の定義と行動原則 各ロール(役割)の定義と行動原則、具体的な責務、そしてAI時代ならではの新しい動き方について解説されています。 ◦ Thinker(思考者): Why(なぜそれを行うのか)を探究する戦略家であり、プロジェクトの土台を築き、AI時代においては「インサイトの翻訳者」としての役割が重要になります。 ◦ Facilitator(推進者): How(どうやって進めるか)を設計する調整役であり、チーム内の合意形成やプロジェクト管理を担当し、「“場”作りのプロ」として振る舞います。 ◦ Maker(創造者): What(何を作るか)を形にするビルダーであり、具体的なアウトプット(プロトタイプやMVP)を生み出す役割を担います。3. AIと共創するためのマインドセット AI時代において、コンサルタントがAIを単なる効率化の道具ではなく「共創のパートナー」として扱い、人間とAIの強みを掛け合わせるためのマインドセットと具体的な活用法が解説されています。4. 次世代コンサルタントの育成 このフレームワークを導入する目的は、AI時代において若手コンサルタントがこれら3つの役割を横断的に担い、“Vibe Worker(バイブワーカー)”とも呼ぶべき次世代のコンサルタントへと成長するための思考軸・行動指針を提供することにあります。
2025-09-2122 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖おさらい|AI時代の働き方OSをアップデート!TFM-OpsとVibe_Workingで価値を最大化する1. 新しい仕事の3役割モデル「TFM-Ops」による役割の再定義本書は、従来のコンサルティング手法の限界を指摘し、AI時代に求められる新しいチームモデルとして**TFM-Ops(Thinker/Facilitator/Maker)**を提唱します。• 従来のコンサルティングの課題とAIの台頭: 旧来のコンサル業務は、分析・リサーチ・資料作成といったThinker業務に約80%が偏っており、これらはAIが得意とする領域であるため、自動化によって付加価値が下がりつつあると指摘されています。PwCがコンサルタント1500人を削減したニュースなどの業界動向も、この変革の必要性を裏付けています。従来の「大量の分析→提言スライド納品」で終わるモデルでは、実行力や迅速な価値創出に限界があるとしています。• TFMモデルの役割: ◦ Thinker(思考者):Why(なぜ)を探求し、戦略立案、課題分析、仮説構築、リサーチを担当します。AI時代には、AIが出した膨大な分析結果を文脈に沿って解釈し、人間的要素(組織文化や政治)を汲み取る**「インサイトの翻訳者」**としての役割が重要になります。 ◦ Facilitator(推進者):How(どうやって)を設計し、合意形成の推進、利害調整、ワークショップ設計、ナレッジ共有、チーム運営などを担当します。リモートワークや社内DXが進む中で、FacilitatorはAIを活用しながらリアルタイムなコラボレーションを促す**「”場”作りのプロ」**として、AI字幕・要約を使った理解度の統一や、AIによる議論のポイント整理といった手法を使いこなすことが求められます。AIによって人間は本質的な合意形成に集中できるようになるとされています。 ◦ Maker(創造者):What(何を)を創出し、アイデアを形にして提供価値を具体化します。プロトタイプ開発、PoC(概念実証)実施、アウトプットデザインなどを担当し、**「紙の提案書ではなく即動くものを届ける」**という発想転換が求められます。• 三位一体の強みと個人のスキルアップ: TFMの3者が揃うことで、「仮説→即プロトタイプ検証」や「論理と共感を両立したビジョン策定」といったシナジーが生まれます。逆に一つの役割だけでは「頭でっかちで何も進まない」といった偏りが生じるとされます。本書は、チーム内の分担だけでなく、コンサルタント一人ひとりがThinker・Facilitator・Maker全てのスキルをバランス良く身につけた**「ジェネラライジング・スペシャリスト」**になることを推奨しています。これは、単一スキルがAIに代替されやすい時代において、複数技能を持つ人材こそが価値を発揮できるためです。2. AIを共創パートナーとする「Vibe Working」による働き方の再定義本エピソードは、AIを脅威ではなく相棒と捉え、生産性を向上させる新しい働き方として**「Vibe Working」**の思想を提唱します。• Vibe Workingの定義: 「AIを同僚(相棒)とみなし、人間の直感的アイデア(vibe)を対話と反復によって具体的アウトプットに変えていく働き方」と定義されています。これは、Andrej Karpathy氏が提唱した「Vibe Coding」をコンサルのアウトプット全般に拡張したものです。• 即興的共創の進め方: 「Plan→Do→Check」のサイクルを圧縮し、プランしながら即Doするやり方を提示します。具体的には、まずAIに草案を出させ、人間がそれを評価・フィードバックし、AIが修正提案するというループを高速で回すプロセスです。ジャムセッションのようにAIと仕事を進めるイメージで、人間は「完璧を目指すプレッシャーから解放される」メリットや、創造性が高まる点が挙げられています。• 従来の働き方との比較: ◦ Deep Work:一人で深く考えるのに対し、Vibe WorkingはAIと対話しながら生み出す点で異なります。 ◦ フロー状態:従来は人同士で生まれるものだったが、Vibe Workingでは相手が24時間動くAIであるため、新たな形の没頭体験が可能になります。 ◦ リモートワーク:AIがブレスト相手や雑務代行になるため、一人でも高い生産性を維持できます。• Vibe Workingの具体的な活用: ChatGPTやClaude、Supabase、Figmaなどの最新AI・LLM・ノーコードツールを各TFMロールに合わせて具体的に活用する方法を指南し、生産性を飛躍的に向上させます。例えば、デロイトではAIが提案書のドラフトを自動生成し、コンサルタントはレビューと質の担保に集中することで、戦略立案やクライアント対応など付加価値の高い業務に時間を振り向けられるようになった事例が紹介されています。総じて、本書は、AI時代にコンサルタントが「AIに仕事を奪われるかではなく、どうAIと働くか」という問いに対し、TFM-Opsという新しい役割分担と、Vibe WorkingというAIとの共創的な働き方を「これからのコンサルの武器」として提供し、読者自身が「自分ならではの仕事スタイル」を再設計できるよう支援することを目指しています。これにより、コンサルタントは「人間にしかできない価値」を最大化できると強調しています。
2025-09-1820 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖AI時代の変革OS「TFM-Ops」を徹底解説:コンサルはなぜ激変し、人はAIとどう共創するのか?AI時代に求められるコンサルティングの新たな「OS」(オペレーティングシステム)は、従来のピラミッド型モデルからの抜本的な見直しを迫られており、以下の特徴を持つと説明されています。新たな「OS」の必要性と背景• 従来のコンサルティング業界では、エキスパートチームが膨大な分析を行い、最後に提言のスライドを提出する「ピラミッド型」モデルが主流でした。• しかし、デジタル時代、特に生成AIの台頭により、この古典的モデルは再検討を迫られています。• クライアント企業の期待も変化し、「静的な報告書より、リアルタイムで実行可能なインサイトや結果」を求める声が強まっています。• AIが安価に高速分析や戦略草案を生成できるため、コンサルティング自体の価値提供モデルをアップデートしなければ、「付加価値が感じられない」時代になりつつあります。• ハーバード・ビジネス・レビューも、AIがクライアントへの価値の本質を再定義する「地殻変動」であると指摘しており、従来型のOSのままではコンサルも陳腐化するリスクがあるとしています。新たな「OS」の主な特徴1. AIを中核に据えた社内オペレーティングシステム(AI OS) ◦ 組織内外のデータやナレッジをリアルタイムで学習・最適化し、プロジェクト遂行を自律的に支援するプラットフォームです。 ◦ ミッドサイズのファームでも巨大ファームに伍して高度課題をこなせる競争力の源泉となると言われています。2. デュアルOS(二重の経営システム)の一部としての「変革OS」 ◦ ジョン・P・コッターが提唱する、既存事業運営の「安定OS」とは別に、新規課題に即応する「変革OS」を併存させる考え方に基づいています。 ◦ TFM-Opsはこの「変革OS」の具体的な実装であり、従来のヒエラルキーに代わり、Thinker・Facilitator・Makerのネットワーク型チームがAIと共に高速に課題解決へ動きます。 ◦ これにより、外部コンサルに頼りがちだった変革推進力を組織内OSとして内製化し、経営の敏捷性(アジリティ)を飛躍的に高めることが期待されます。3. 「Thinker/Facilitator/Maker」三位一体モデル ◦ Thinker(戦略構想、Why)、Facilitator(合意形成、How)、Maker(実装検証、What)の三役がフルに連携し、AIも巻き込んでセッションを繰り返す点が画期的です。 ◦ この協働によって、戦略・調整・実装が断絶なく回り始め、「1+1+1を3以上にする」シナジーが生まれるとされています。 ◦ サイモン・シネックの「Why/How/What」ゴールデンサークル理論と対応しており、Why(目的)なき技術導入や、Howを無視した机上の空論、Whatに踏み込まない机上戦略といった失敗パターンを防ぐ理論的裏付けとなります。4. ピラミッド型分析志向から三位一体型即応志向への転換 ◦ 従来型コンサルがトップダウンのヒエラルキーで大量の分析を行い、提言を報告書にまとめるスタイルだったのに対し、TFM-Opsは戦略策定から実装まで一貫してチーム内で回します。 ◦ 「提案して終わり」ではなく「提案を即試し、修正し、実装まで伴走」が可能です。5. アジャイル型ガバナンスと迅速な意思決定 ◦ Facilitatorがステークホルダーを巻き込みその場で合意形成を図るため、従来数週間~数ヶ月を要した承認プロセスが飛躍的に短縮されます。 ◦ 企業統治を環境変化に合わせ俊敏にアップデートする「アジャイル・ガバナンス」をプロジェクトレベルで導入するイメージです。6. 動くプロトタイプやMVP(実用最小限製品)を重視した成果物 ◦ 旧来モデルが紙の報告書や助言だったのに対し、TFM-Opsは動くプロトタイプや実証済みのMVPそのものを成果物として重視します。 ◦ これにより、経営者が「何が出来るのか」を肌感覚で理解でき、社内説得力も高まり、変革施策が社内に根付く可能性が高まります。7. PoC止まりを打破する「即興×実装」のプロセス設計(MVP志向) ◦ 「Vibe型アジャイル」と呼ばれる即興的アプローチを採用し、計画に縛られずAIと人間の即興セッションでアイデアを形にしていきます。 ◦ これにより、従来の要件定義や開発サイクルを大幅に短縮し、数日~数週間で仮説検証と合意形成まで到達するケースも報告されています。 ◦ PoC(概念実証)で満足せず、必ず一段上のMVP(市場で通用する最小製品)まで作り込むことを重視し、早期に実利用から学びを得て価値ある解決策を見極めます。8. AIを「共創パートナー」と位置づけるマインドセット ◦ AIを単なる効率化の道具ではなく、人間と肩を組み新価値を創り出す「共創パートナー」と見做します。 ◦ 人間だけのチームよりも人間+AIのハイブリッドチームの方が多様で創造的なアイデアを生み出すことが研究で報告されており、AIの「遠い連想」が新発想のきっかけとなります。 ◦ 生成AIやRAG(Retrieval Augmented Generation)の普及により、AIを企業内ナレッジや外部データベースからの情報検索を組み合わせた信頼できる知識パートナーとして活用できます。9. 人間にしかできない価値の再定義と最大化 ◦ AI時代において「人間にしかできない本質的な仕事」に焦点を当て、それをAIが補助する形で業務設計を再構築します。具体的には以下の3点が挙げられます。 ▪ 問題を定義しビジョンを描く力(課題設定能力):Thinkerが「Why起点」で、AIでは代替不能なビジョニングの価値を発揮します。 ▪ 文脈を読み解き、価値を判断する力(意思決定能力):FacilitatorとThinkerが協働し、AIが出すデータ上の正解だけでなく、文化や顧客感情、定量化しづらい価値観を踏まえて最適な解を統合し決断します。 ▪ 共感し人々の意欲を引き出す力(コミュニケーション・リーダーシップ):Facilitatorが多様な人を巻き込み、共感を通じてビジョンを共有し、チームの力を結集します。これは現在のAIにはできない、人間ならではのリーダーシップです。これらの特徴により、AI時代の新たなコンサルティングOSは、単なるアドバイザーではなく「共に成果を出すパートナー」としてクライアントに映り、組織の変革スピードと創造性を飛躍的に高めることが期待されています。
2025-09-0923 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖議論版|AI時代を勝ち抜く組織変革:TFM-OpsとAI伴走支援を経営層に響かせる提案術今回は、NotbookLMの新機能である、『2 人のホストによる思慮深い議論で、ソースに関するさまざまな視点を明らかにする』音声概要機能で生成しています。サービス導入から成果最大化までのAI活用ロードマップとして、TFM-Opsは組織が段階的にAI活用を成熟させていく「変革のロードマップ」を提唱しています。このロードマップは、リスクを最小限に抑えながら着実に成果を積み上げ、最終的にAI活用が組織文化として根付くことを目指すアプローチです。ロードマップは以下の3つのフェーズで構成されています。1. Phase A: Enable (活用基盤の構築)このフェーズの目的は、AIを組織的に活用するための「滑走路」を整備することです。無秩序なツール導入によるセキュリティリスクや非効率な投資を防ぎ、明確なガバナンスのもとで統制の取れた活用基盤を構築します。• 目的: 統制された環境でパイロットを成功させ、早期の成功体験を創出する。• 主要な活動内容: ◦ AI利用ポリシー・ガイドライン策定: 機密情報の取り扱いや倫理的配慮など、従業員が遵守すべきルールを明確化します。 ◦ セキュリティ・アーキテクチャ設計: データ保護とプライバシーを確保し、安全にAIを利用できる技術環境を設計します。 ◦ 主要ツールスタックの整備: ChatGPT Team/Enterpriseや社内RAGなど、組織のニーズに合わせた中核ツールを導入・設定します。 ◦ パイロットテーマの選定: 短期間で成果を出しやすい、インパクトの大きい業務領域を特定し、パイロットプロジェクトの対象として選定します。 ◦ パイロットチームの組成と導入支援: 対象部署のメンバーとTFM-Opsチームによる混成部隊を組成し、プロトタイプ開発から導入までを伴走支援します。 ◦ 初期トレーニングとQ&Aセッション: パイロットチーム向けに、AIツールの基本的な使い方やプロンプトエンジニアリングの研修を実施します。• このフェーズの成果物: AI利用ガイドライン、整備済みツール環境、パイロットプロジェクトの成功事例、次フェーズへの移行計画。2. Phase B: Amplify (活用範囲の拡大)このフェーズでは、Phase Aで得られた成功の「種」を組織全体に広げ、AI活用を一部の先進的な取り組みから全社的な業務基盤へと昇華させることを目指します。• 目的: 成功事例を横展開し、AIチャンピオンを育成、全社的な業務基盤へ発展させる。• 主要な活動内容: ◦ ユースケースの横展開: パイロットで成功したユースケースを他部署へ展開し、標準的な業務プロセスへの組込みを支援します。 ◦ AIチャンピオン制度の設立: 各部署からAI活用を牽引するキーパーソンを選出し、体系的な育成プログラムを提供します。 ◦ 社内コミュニティの運営: 成功事例やベストプラクティスを共有し、従業員同士が学び合うためのオンラインコミュニティを活性化させます。 ◦ 効果測定ダッシュボードの構築: AIの利用状況、業務効率化の効果、ROIなどを可視化し、経営層がデータに基づいた意思決定を行えるようにします。 ◦ 高度化トレーニングの実施: より専門的なAI活用に関するトレーニングを提供し、組織全体のスキルレベルを底上げします。 ◦ 標準業務手順書(SOP)の整備: AIを活用した新しい業務フローを標準化し、ドキュメントに落とし込むことで、属人化を防ぎ、定着を促進します。• このフェーズの成果物: 全社展開された複数の成功事例、育成されたAIチャンピオン、活性化した社内コミュニティ、効果測定ダッシュボード。3. Phase C: Showcase (成果の最大化と発信)最終フェーズでは、AI変革によって得られた成果を事業価値に転換し、その価値を最大化します。社内での成功に留まらず、社外への発信を通じて企業ブランドや採用力の向上にも繋げます。• 目的: 事業価値を定量化し、自律的な改善サイクルを定着させ、自己進化型組織へ変革する。• 主要な活動内容: ◦ ビジネス成果の定量的評価: AI導入がもたらした収益向上、コスト削減、顧客満足度(CS)改善などを定量的に評価し、経営インパクトを明確にします。 ◦ 成功事例のストーリー化と社内外への発信: 具体的な成功事例を、投資家や顧客、採用候補者に響くストーリーとしてパッケージ化し、IR資料やプレスリリース、採用イベントなどで発信します。 ◦ KPIレビューと改善サイクルの定着化: AI活用の成果を評価する定例会議を設け、PDCAサイクルを回す仕組みを組織に定着させます。 ◦ 自律的運用体制(CoE)の確立: AIチャンピオンを中心としたCoE (Center of Excellence) を正式な組織として位置づけ、コンサルタントが離れた後も自律的に変革を推進できる体制を構築します。 ◦ 次世代AI技術の導入検討: AGI(汎用人工知能)の登場など、将来の技術トレンドを見据え、次なる一手となる戦略や技術の導入計画を支援します。• このフェーズの成果物: 事業成果レポート、社外発信用のコンテンツ、定着化した改善サイクル、自律的に機能するCoE組織。最終的に目指すものTFM-Opsが最終的に目指すのは、クライアントが自律的にAIを活用し、持続的な事業成果を創出し続ける「自己進化型組織」への変革を支援することです。これは、コンサルタントがいなくても、クライアント自身でAI活用を推進し、イノベーションを生み出し続けられる組織となることを意味します。AIを前提とした世界で、事業成果を出し続ける組織へと変革することを目標としています。また、AIの真の価値は、組織に属する一人ひとりの「個」の能力を最大限に解放し、「AIを使いこなす個の集合体」へと進化するための組織文化を育むことであると捉えられています。
2025-09-0726 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖AI開発ツール三刀流:Replit,_Bolt,_LovableをTFM-Opsで使いこなす戦略非エンジニアを含む異なるユーザー層にとって、Replit、Bolt.new、Lovable.devの各ツールは、それぞれ異なる親和性を持っています。以下に各ツールの特徴と、Thinker、Facilitator、MakerというTFM-Opsの視点を含めたユーザー層との親和性を比較します。異なるユーザー層にとっての各ツールの親和性1. Lovable.devLovable.devは、非エンジニア層にとって最も親和性が高いツールです。• 非エンジニアの親和性: ◦ 英語プロンプトだけで即座にアプリを生成できます。 ◦ 非エンジニアでも「手を動かさないパワー」でワクワクできると評価されています。 ◦ Redditの匿名ユーザーからは「初心者でも優しく導いてくれるからめちゃくちゃ助かった」という声が挙がっています。 ◦ 「チャットするだけでUIつきアプリ」が出るノーコード寄りのAIツールであり、ホスティングも自動で行われます。 ◦ 誰でも扱えるため、非エンジニアを巻き込んだ合意形成に直結し、体験を共通言語にできる点が強みです。 ◦ 数分でアプリを体験化でき、「味見できる餅(すぐ触れるMVP)」に最適です。 ◦ これは「即席ラーメン」のように、3分で食べられる価値体験を提供するツールと例えられます。• TFM-Opsとの相性: ◦ Thinker(Why探求): 数分で“構想”をアプリ化し、議論の出発点やステークホルダーへのインパクトある見せ方を提供します。 ◦ Facilitator(Howを回す): ステークホルダーへの即デモに強く、非エンジニアも巻き込んだ共感創出に役立ちます。 ◦ Maker(Whatを作る): コード品質はBoltほどではないものの、「ゼロ→イチ」の叩き台を瞬時に生み出す超高速生成器として機能します。• 総括: すぐに「見せられるモノ」を作りたいThinker系に最適であり、TFM-Opsにおいては共感装置や「ステージ(共感を得る)」の役割を担います。2. Bolt.newBolt.newは、非エンジニアも入り口は優しいものの、コードへの理解が求められる段階で技術的な壁がわずかに残るツールです。• 非エンジニアの親和性: ◦ 最初は対話的で優しいインターフェースですが、すぐに「コードを動かす人」目線に引きずり込まれる傾向があります。 ◦ Redditユーザーからは「できるにはできるけど、なんか技術前提な感じで辛い」という本音のコメントもあります。 ◦ 使いやすいものの、それなりのコード理解が必要であり、「野心ある非エンジニア」にはちょうどいいと表現されています。• TFM-Opsとの相性: ◦ Thinker(Why探求): 仮説検証を即座に形にできる「味見できる餅」製造機であり、アイデアを動く餅として具現化します。 ◦ Facilitator(Howを回す): チャットベースで要件をコードに落とし込み、修正や仕様調整が可能で、チーム会話を翻訳する役割を果たします。 ◦ Maker(Whatを作る): Diff更新や自動修正、エラーフィックス機能によりMakerが実装に集中でき、実装の生産性を最大化します。本命のMaker武器とも言えます。• 総括: PoCをきっちりコードで作って運用も見据えたいMaker系に最適であり、TFM-Opsにおいては実装ブースターや「工房(PoCを爆速で形にする)」の役割を担います。これは「フルコース料理」のように、しっかり作って提供できる価値を持つツールです。3. ReplitReplitはプログラミングスキルがあるユーザー向けであり、非エンジニアには学習コストが高いツールです。• 非エンジニアの親和性: ◦ IDEそのものであり、非エンジニアには敷居が高く、学ぶか、あるいは助けが必要とされます。 ◦ プログラミングスキルがある人には爆速で開発できますが、初心者には学習コストがかかります。 ◦ ある元Googleエンジニアの証言では、猫が鳴くアプリをサッと作ったものの、「微調整で躓いて、クレジット消費も激しくて、PoC止まり」だったとされ、初心者には難しい側面があることが示唆されています。 ◦ 「それなりにプログラミングセンスが求められる」と明確に述べられています。• TFM-Opsとの相性: ◦ Thinker(Why探求): アイデアをその場で試す「学びの実験場」であり、LLM補助でフレームワークを試したり、コードの正しさを確認できます。 ◦ Facilitator(Howを回す): リアルタイム・コラボ機能が強力で、教育現場やハッカソンで「一緒に学ぶ」文化を支え、チーム学習を促進します。 ◦ Maker(Whatを作る): 50以上の言語に対応するIDE環境は、スキルを磨く「武者修行の場」として最適で、コードを鍛える筋トレになります。• 総括: 学びながら育てたいファシリ/Maker新人チームに最適であり、TFM-Opsにおいては育成基盤や「道場(人材育成・内製化を支援)」の役割を担います。これは「自炊の台所」のように、スキルを磨き続ける修行場と例えられます。まとめ異なるユーザー層の親和性をまとめると以下のようになります。• Lovable.dev: 非エンジニアが最も直感的に使え、数分でアプリの「味見」ができる共感創出ツールです。アイデアを素早く形にし、ステークホルダーとの合意形成に役立ちます。• Bolt.new: 非エンジニアでも入り口は優しいものの、コードへの理解を深めることで本格的なPoCや実装に活用できるツールです。Thinkerが仮説検証し、Facilitatorがコードを介してチームを繋ぎ、Makerが本格的なコードを生成するのに適しています。• Replit: プログラミングスキルを持つユーザーや、これからスキルを身につけたいユーザーに最も適したクラウドIDEです。学習の場、武者修行の場として機能し、チームでの共同学習や育成基盤として強みを発揮します。
2025-09-0626 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖ジャズセッション型アジャイル「Vibe」と「TFM-Ops」が奏でるポリリズム的共創でAI時代の新常識へVibe型アジャイルは、従来のスクラムとはその根本的なリズムとアプローチにおいて大きく異なります。従来のスクラムとの違い• リズムとメタファー: ◦ 従来のスクラムは「秩序あるオーケストラ」に例えられ、スプリント、バックログ、レビューといった要素でチームに秩序を与え、不確実性に適応するリズムで進化してきました。これは「プラン駆動型アジャイル」とも表現されます。 ◦ Vibe型アジャイルは、生成AIの登場により開発現場がより流動的になったことを受け、「AIを含む即興ジャズ」のような即興的で流動的な“ジャズセッション”型のリズムへと移行するアプローチです。• 計画への姿勢: ◦ スクラムがスプリントやバックログといった計画に基づき進められるのに対し、Vibe型アジャイルは「計画に縛られるより、即興でAIと共創しながら成果を形にしていく」ことを重視します。 ◦ 詳細な要件定義よりも、その場の直感やひらめきをAIに投げ、試作品を即座に生成する即興性が特徴です。Vibe型アジャイルがもたらす新しい価値Vibe型アジャイルは、TFM-Ops (Thinker・Facilitator・Maker)を核とすることで、以下のような新しい価値と可能性をもたらします。• 即興性とAI共創によるスピードと創造性: ◦ 詳細な要件定義をスキップし、その場の直感やひらめきをAIに投げ、試作品を即座に生成します。 ◦ 人間が即興でAIと共に学び、触れられるアウトプットを重ねていくプロセスにより、従来の「プラン駆動型アジャイル」では到達できないスピードと創造性を生み出します。• セッション型コラボレーション: ◦ Thinker(Why)、Facilitator(How)、Maker(What)の三役がAIを交えた**“セッション”を繰り返し、試行錯誤を共有**します。 ◦ Facilitatorは、AIも含めた多様なプレイヤーが安心して“演奏”できる場をデザインし、異なるリズムを持つ各役割を繋ぎ、チーム全体をまとめます。• 価値中心主義と迅速なフィードバック: ◦ アウトプットは常に**「味見できる餅」**であり、実際に触って学び、改善を迅速に繰り返すことを重視します。 ◦ MakerがAIツールを駆使してアイデアを即座に具現化し、その場で検証を回すことで、価値創出のサイクルを高速化します。• TFM-Opsによる即興性と秩序の両立: ◦ Thinkerが「なぜそれをやるのか」を問い続けることで、即興的な展開の中でも迷走を防ぎます。 ◦ TFM-Opsは、即興に秩序を与える「フレームワークなきフレームワーク」として機能し、Vibe型のカオスを価値創出へと収斂させます。 ◦ これにより、即興と秩序、ノリと戦略の最適な両立が可能になります。• 圧倒的な開発サイクルと合意形成の加速: ◦ 保険・金融業界のPoC(概念実証)の例では、従来数週間かかっていた要件定義が、Vibe型アジャイルを用いることで合意形成も検証も数日単位で進むようになります。 ◦ 「Neural Drive Max」状態での仮説検証が可能となります。• AI時代に不可欠な方法論と未来の標準: ◦ AIがコラボレーションの前提となる時代において不可欠な方法論となるでしょう。 ◦ TFM-Opsを核としたVibe型アジャイルは、「スクラムの次」に来るリズムであり、未来のコンサルティングと開発の標準形になるとされています。 ◦ TFM-Opsは、Thinkerの基礎拍、Facilitatorの繋ぎ、Makerの即興という異なるリズムが重なり合い、単一では到達できない豊かな価値創出を奏でる「ポリリズムのアンサンブル」として機能します。
2025-09-0624 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖AI時代の組織変革:TFM-Opsと「ジャズセッション型」組織が導く「変革実現パートナーシップ」の真髄このサービスは「TFM-Ops × AI伴走支援」と称され、顧客企業のAI変革を実現するためのパートナーとして、AIを前提とした世界で事業成果を出し続ける組織への変革を目指しています。このサービスが顧客企業のAI変革を支援する方法と、目指している組織変革は以下の通りです。顧客企業のAI変革を支援する方法このサービスは、従来のコンサルティングモデルが機能不全に陥りつつあるAI時代において、「変革実現パートナー」として、外部からの提言に留まらず、AIを前提とした組織能力を内部に構築し、変化に即応し続けるための支援を提供します。1. 独自のフレームワーク「TFM-Ops」の提供 ◦ AI変革を実現する「組織OS」として、以下の3つの専門機能をクライアント組織内に組み込みます。 ▪ Thinker (戦略家):AIが生み出すデータの中から本質的な問いを発見し、事業にとって進むべき方向性を定めます。AI活用戦略・ロードマップの策定、優先度評価と投資対効果分析、ビジネスモデルの再構築などを通じて、事業成長に直結する明確な戦略を昇華させます。 ▪ Facilitator (変革推進者):組織の力学や文化の壁を乗り越え、多様なステークホルダーを巻き込み、変革の実現を導く触媒の役割を果たします。経営層から現場まで、関係者の合意形成、チェンジマネジメント、コミュニケーション設計、AIガバナンスとリスク管理体制の構築を通じて、戦略を絵に描いた餅で終わらせず、現場に根付かせます。 ▪ Maker (実装共創者):壮大な計画を待つのではなく、AIとの即興的な協働(「Vibe Working」)を通じて、アイデアを「触れる形」にし、価値を高速で実証する実行部隊です。高速プロトタイピング、ユーザー体験(UX)の設計と検証、内製化支援と技術移管を通じて、PoC(概念実証)の罠を回避し、価値のあるソリューションを迅速に特定・実装します。 ◦ これらの3つの機能が相互に連携し、「TFM-Opsフライホイール」として価値創出サイクルを継続的に加速させます。Thinkerが戦略を設定し、Makerがプロトタイプを開発、Facilitatorが合意形成を行い、得られたフィードバックをThinkerが次の戦略に反映させることで、組織は学習し進化し続けます。2. 段階的な変革ロードマップ ◦ AI変革を「組織が段階的に成熟していく旅」と捉え、リスクを抑えながら着実に成果を積み上げる3つのフェーズで支援します。 ▪ Phase A: Enable (活用基盤の構築):AIを組織的に活用するためのガバナンス、セキュリティアーキテクチャ、主要ツールスタックを整備し、明確なルールのもとでパイロットテーマを選定し、パイロットチームの組成と導入支援を行います。 ▪ Phase B: Amplify (活用範囲の拡大):Phase Aの成功事例を組織全体に広げ、AIチャンピオン制度の設立、社内コミュニティの運営、効果測定ダッシュボードの構築、高度化トレーニングなどを通じて、AI活用を全社的な業務基盤へと昇華させます。 ▪ Phase C: Showcase (成果の最大化と発信):AI変革によって得られた成果を定量的に評価し、成功事例を社内外に発信します。KPIレビューと改善サイクルの定着化、自律的運用体制(CoE)の確立、次世代AI技術の導入検討を通じて、事業価値を最大化します。3. 深いパートナーシップと共創 ◦ クライアントと一体となって組織内部にAI活用のための能力(ケイパビリティ)を構築し、変革の実現までを伴走します。 ◦ クライアント側の現場リーダーやAIチャンピオン候補者と、TFM-Opsトリオから成る「混成スクワッド」を編成し、共に汗を流しながら解決策を創り出します。これにより、組織内部の知見を最大活用し、リアルタイムな軌道修正、当事者意識の醸成、持続的な能力移転(Enablement)を促進します。 ◦ 機密情報保護のための分散サンドボックス環境の構築、APIキーの一元管理と利用統制、SSO連携による認証統合といった先進的なガバナンス&セキュリティ戦略も共に構築します。目指している組織変革このサービスが目指している組織変革の最終目標は、**クライアントが自律的にAIを活用し、持続的な事業成果を創出し続ける「自己進化型組織」**への変革を支援することです。具体的には、以下の変革を目指します。• AIを前提とした世界で事業成果を出し続ける組織へ。• **「オーケストラ型から、ジャズセッション型へ」**という働き方の根本的なパラダイムシフトを実現します。計画と統制に基づいた働き方から、基本的な戦略を共有しつつ、AIという新しい楽器を手に、即興と共創によってイノベーションを生み出す働き方へと転換します。• 『個』のエンパワーメント:AIが高度な分析や定型業務を担うことで、組織に属する一人ひとりの「個」の能力を最大限に解放し、人間が本来持つべき創造性、共感力、高次の意思決定に集中できる環境を構築します。将来的には、各個人が優秀な「AIエージェント」を従え、AIと協働しながら高度な知的生産活動を行う「AIを使いこなす個の集合体」となることを目指します。• アジャイルなマインドセットの確立:市場の変化に迅速に対応するため、「学びながら素早く実装する(Learn and Implement Quickly)」アジャイルなマインドセットが不可欠であると考え、これを組織文化として根付かせます。• 持続的な能力移転(Enablement):プロジェクトを通じてノウハウを移転し、クライアントが自律的に変革を推進できる組織を育成します。最終フェーズでは、AI活用をリードする「AIチャンピオン」を中心とした**「CoE (Center of Excellence)」**を確立し、サービス提供者が離れた後も、顧客企業が自走してイノベーションを生み出し続けられる体制を構築します。• **「ロジックだけでは動かない人・組織を動かし、変革を最後までやり遂げる推進力」**を持つ組織への変革。AI導入に対する現場の不安や抵抗に対し、ワークショップなどを通じて当事者意識を醸成し、AIが「仕事を助けてくれるパートナー」であることを実感できる文化を育みます。
2025-09-0421 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖顧客はドリルではなく「進歩」を雇う!JTBD理論と実践フレームワークTFM-Opsで真のニーズを掴むJTBD(Jobs to be Done)とTFM-Opsは、組織の課題解決に対して、顧客理解の深化からイノベーションの促進、意思決定の効率化に至るまで、多岐にわたる全体的な影響をもたらします。まず、JTBDは組織の顧客に対する根本的な視点を変革します。顧客を「30代男性、会社員」のような属性(ペルソナ)や、製品の機能といった表面的な情報で捉えるのではなく、「どんな状況で、どんな目的を達成したくて、その製品やサービスを"雇う(hire)"のか?」という「顧客の片付けるべき仕事(Job)」に焦点を当てます。これにより、顧客が製品を購入する本当の動機や、その背景にある感情的な「仕事」まで深く理解できるようになります。例えば、「壁に穴を開けたい」という物理的な仕事だけでなく、「お気に入りの絵を飾って、素敵な部屋にしたい」という感情的な仕事まで捉えることができるようになります。このJTBDの考え方をTFM-Ops(Thinker, Facilitator, Maker)というフレームワークで運用することで、組織は具体的な課題解決を進めます。JTBDとTFM-Opsがもたらす全体的な影響は以下の通りです。1. 顧客理解の深化と根本的な動機の特定: ◦ JTBDは、顧客の年齢や性別といった表面的な情報ではなく、「なぜ?」という根本的な動機や置かれている状況(コンテクスト)を深く理解させます。 ◦ TFM-OpsのThinkerは、問い合わせ履歴や失注メモ、NPSコメントといったログから顧客の「嘆き」をAIで分析し、「Job Story」として具体的な**「進歩の文」**を明確にします。これにより、「締切前の最終確認で、不備の有無を即判定したい」といった顧客の真のニーズを組織全体で共有できます。2. 真の競合の発見とイノベーションの促進: ◦ JTBDの視点を持つと、ミルクシェイクの競合がバナナやドーナツであったように、全く異なるカテゴリーの製品やサービス、あるいは「何もしない」という選択肢までもが競合になりうると気づくことができます。 ◦ 顧客の「仕事」をより良く、より安く、より便利に片付ける方法を考えることで、新しい商品開発やサービス改善のアイデアが生まれるきっかけとなります。TFM-OpsのMakerは、この「進歩の文」に基づき、ワイヤーフレームや会話フロー、デモを素早く作成し、顧客が「味見できる餅」として具体的な解決策を形にします。3. 意思決定の迅速化と合意形成の強化: ◦ TFM-OpsのFacilitatorは、「やらねばならない圧力(Push)」「理想の引力(Pull)」「不安(Anxieties)」「慣性(Habits)」というFour Forcesを可視化し、関係者間で各Jobに対する合意スコアを形成します。これにより、会議が意見のぶつかり合いから「証拠の積み上げ」に変わり、意思決定の質と速度が向上します。 ◦ 議論が短縮され、学習が速くなり、意思決定が軽くなるため、組織全体の運営が効率化されます。4. マーケティングの的確化: ◦ 「こんな機能があります!」という機能中心のアピールではなく、「あなたのこんな悩み(仕事)、解決できますよ」と語りかけることで、顧客の心に響くメッセージを届けられるようになります。5. 具体的な成果と運用の接続: ◦ TFM-Opsは、JTBDで定義された「進歩の文」を、合意形成、プロトタイピングによる「味見」、そして測定、運用へと接続する仕組みを提供します。 ◦ 数週間のテストで一次正答率が18%向上し、処理時間が43%短縮されるといった具体的な成果が示されており、PoC(概念実証)が運用の入口へとスムーズに移行できるようになります。経営層は「投資判断の材料」を得ることができ、投資の確実性が高まります。6. 組織文化の変化: ◦ JTBDは、顧客を「製品の買い手」ではなく、「特定の目的を達成しようとしている一人の人間」として捉え直すための強力な視点を提供します。 ◦ TFM-Opsを通じて、組織は「何を作るか」ではなく「どんな進歩を達成するか」を定義し、それを「動く仕様」に翻訳する運び屋として機能するようになります。これは、組織がより顧客中心のアプローチを取るための文化的な変化を促します。これらの影響を通じて、JTBDとTFM-Opsは、組織が顧客の真のニーズに基づいた価値提供を行い、持続的なビジネス成功に導くための強力なフレームワークとして機能します。
2025-09-0217 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖McKinsey's 2025 Tech Trends and TFM-Ops SynergyMcKinseyの提示する技術トレンドを組織が効果的に活用するために、TFM-Ops(Thinker/Facilitator/Maker)フレームワークは、三位一体の役割協働を通じてビジネス価値の創出に貢献します。このアプローチは、「なぜ導入するか(Why)」「どう実現・定着させるか(How)」「何を作るか(What)」を有機的に結びつけ、単なる技術導入を競争力強化へと結実させるものです。TFM-Opsの各役割が提供する具体的な貢献は以下の通りです。• Thinker(戦略思考) ◦ 役割と価値発揮: Thinkerは、技術トレンドが自社に与える潜在的なインパクトを評価し、長期的なロードマップや戦略を策定します。例えば、Agentic AIにおいては、どこに適用すべきかを見極め、ROIやガバナンス指針を策定します。AI全般では、明確なユースケースを選定し、投資対効果を最大化するAI戦略を策定します。専用半導体に関しては、自社プロダクトでの競争優位領域を分析し、「作る or 買う」戦略やパートナーシップ構築を立案します。先進的な通信技術では、新規ビジネスモデルや業務効率化策を立案し、自社が「コネクター止まりでなく価値クリエイターになる」戦略を模索します。クラウド&エッジコンピューティングでは、システム全体のクラウド移行戦略とエッジ活用方針を策定し、投資配分や段階的移行計画を立てます。没入型現実技術では、XR活用で飛躍的改善できる領域を選定し、投資判断や将来的なメタバース戦略を描きます。デジタル信頼とサイバーセキュリティでは、全社のデジタルリスクを評価し、ゼロトラストモデル導入方針やプライバシー保護原則を策定します。量子技術では、潜在インパクトを評価し、長期視点のロードマップを策定、業界特性に応じたシナリオプランニングを実施します。ロボティクスの未来では、ロボット導入効果が大きい領域を選定し、ROI試算や従業員再配置を含めた導入計画、新たなビジネスプロセス設計を検討します。モビリティの未来では、モビリティ技術が自社事業にもたらす変革を構想し、大胆な将来像と戦略的ポジションを決定します。バイオエンジニアリングの未来では、バイオ技術で解決できる課題を発掘し、研究開発の方向性を定め、倫理・規制の観点も踏まえたポリシーを明確化します。宇宙技術の未来では、宇宙技術のビジネス価値を評価し、自社の参入戦略と投資規模を決定します。エネルギー・サステナビリティ技術の未来では、脱炭素社会に向けたグリーン戦略を策定し、持続可能性と収益性の両立を図る長期ロードマップを描きます。 ◦ Thinker欠如のリスク: Thinkerが不在だと、戦略なき導入や投資対効果が不明瞭になり、プロジェクトが迷走したり、宝の持ち腐れになったりするリスクがあります。• Facilitator(調整役) ◦ 役割と価値発揮: Facilitatorは、技術導入に関わる多様なステークホルダー間の橋渡し役となり、合意形成や文化醸成を推進します。Agentic AIでは、人とAIエージェントの協働が円滑に進むよう現場と技術チームを橋渡しし、不安や抵抗感を解消し、社内ルール整備や倫理面の合意形成をリードします。AI全般では、社内外の知見を結集し、組織横断でAI活用の文化を育成します。専用半導体では、ハードウェア・ソフトウェア・事業部門を横断的に調整し、ビジネス要件を技術者に、技術的制約を経営層に説明する役割を担います。先進的な通信技術では、マルチステークホルダー調整役として、社内IT部門・業務部門・セキュリティ担当の合意形成を図り、外部との交渉・連携もリードします。クラウド&エッジコンピューティングでは、部門間の橋渡し役となり、データ主権やセキュリティポリシーの合意形成を図り、プロジェクト全体のマネジメントを担います。没入型現実技術では、導入部門と開発者の橋渡しとなり、ユーザーテストの場を設計し、従業員や顧客への説明・サポートを行います。デジタル信頼とサイバーセキュリティでは、組織横断のセキュリティ文化醸成を推進し、ルール遵守と現場の協力体制を強化します。量子技術では、社内研究者・エンジニアと経営陣をつなぎ、現実的な期待値コントロールを行い、大学やスタートアップとの協業機会を模索します。ロボティクスの未来では、現場スタッフへの説明と研修を行い、不安を払拭しつつ、労働組合や安全管理部門とも協議して受け入れ体制を整えます。モビリティの未来では、官公庁・自治体、インフラ企業、地域社会との調整をリードし、規制遵守や社会受容性の確保に努めます。バイオエンジニアリングの未来では、研究者・エンジニアと事業側の架け橋となり、共通言語を作り、研究成果を社会実装するための摩擦を低減します。宇宙技術の未来では、宇宙機関・衛星オペレーター・大学研究者・自社事業部など多岐にわたる関係者間で共通目標を設定し、契約や知財の調整を進めます。エネルギー・サステナビリティ技術の未来では、サステナ施策を部署横断で進める推進役となり、コミュニティや行政とも対話し、環境目標への共感を醸成します。 ◦ Facilitator欠如のリスク: Facilitatorが不在だと、現場の不安や抵抗を放置したり、部門間の調整不足により、プロジェクトが頓挫したり、業務混乱やセキュリティ問題が噴出したりするリスクがあります。• Maker(実装担当) ◦ 役割と価値発揮: Makerは、戦略やビジョンに基づき、技術のプロトタイピングや実装を担当し、有効性を検証します。Agentic AIでは、小規模な自律エージェントのプロトタイプを開発し、試験運用を通じてタスク自動化の有効性を検証します。AI全般では、PoC開発者として短期間でモデルやシステムの試作を行い、実データでAIソリューションを検証します。専用半導体では、エンジニアとして専用チップ開発や実装をリードし、プロトタイピングを通じて期待性能を検証します。先進的な通信技術では、ネットワークエンジニアとして次世代通信環境を実装し、IoT機器やシステムとの接続性をテストします。クラウド&エッジコンピューティングでは、クラウド環境構築やエッジデバイス実装を担当し、PoCを通じて最適構成を探ります。没入型現実技術では、AR/VRアプリケーションやコンテンツのプロトタイピングを担当し、ユーザーの反応データをもとに改良を重ねます。デジタル信頼とサイバーセキュリティでは、セキュリティ技術の実装担当として、ネットワーク監視システムや暗号化ソリューションを導入し、脅威診断テストを繰り返します。量子技術では、社内で可能な範囲から量子技術のPoCを実施し、技術メンバーのスキル習得を図ります。ロボティクスの未来では、ロボット技術の実装担当エンジニアとして、要件に合わせロボットをプログラミングし、生産ライン等に統合します。モビリティの未来では、新モビリティ技術の現場実装者として、EV車両や充電インフラを導入・運用し、稼働データを収集分析します。バイオエンジニアリングの未来では、研究開発者として社内ラボや提携先で実験を行い、新製品のプロトタイプを創出します。宇宙技術の未来では、宇宙技術の実装/適用エンジニアとして、衛星データ分析基盤を社内に構築し、事業に有用なインサイトを抽出します。エネルギー・サステナビリティ技術の未来では、現場で技術ソリューションを実装し、各施策の効果をモニタリングして改善点をフィードバックします。 ◦ Maker欠如のリスク: Makerが不在だと、構想倒れでPoC止まりになったり、技術検証が進まず机上の空論に終わったり、実装力がなければ新興競合に出遅れるリスクがあります。TFM-Opsの役割連携によるシナジーは、以下の3つの視点から特に重要です:• 戦略的実装 (T×M): Thinkerが描く戦略的構想や仮説を、Makerが迅速にプロトタイプで具体化・検証し、戦略の実効性を早期に確認します。これにより、机上のプランが素早く動くソリューションに落とし込まれ、PDCAを高速で回すことが可能になります。• ビジョン共創 (T×F): Thinkerが提示する未来像やビジョンを、Facilitatorが現場やパートナーを巻き込み、対話を通じて共感を集めるプランに練り上げます。論理性と共感性を両立した計画により、関係者の「自分ごと化」を促し、組織一丸で技術活用に取り組む体制を構築します。• 体験による合意形成 (F×M): FacilitatorとMakerが協力し、試作した技術やプロトタイプを現場スタッフや関係者に実際に触れてもらう場を提供します。これにより、抽象的な議論が具体的な体験を通じて理解を深め、「百聞は一見に如かず」の納得感を生み出し、関係者の認識のズレを解消して導入合意を加速させます。このように、TFMの視点を欠けば、いくら最先端技術であっても「資料と会議で止まるプロジェクト」に陥り、期待されたインパクトを生み出せないリスクが高まります。企業は自社の技術導入計画をTFMの観点で見直し、不足する役割や連携を補強することで、McKinseyが提示するテクノロジートレンドを真に競争力強化につなげることができます。
2025-08-2719 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖【NotebookLM 日本語動画記念】戦略から実行へ:TFM-Opsフレームワーク*NotebookLMが日本語動画の生成に対応したのが嬉しくて、アップしてみました。皆さん、こんにちは!今日のポッドキャストでは、「TFM-Ops導入を加速する8観点別ツール優先度マップ」という興味深い資料を基に、チームパフォーマンスを最大化するAIツールの活用法について深掘りしていきます。この資料は、TFM-OpsにおけるThinker(Why)、Facilitator(How)、**Maker(What)**という3つの主要役割と、それらを横断的にサポートするツール群、さらに心理的安全性、共通言語、リーダーシップ、AIリテラシー向上に貢献するツールについて解説しています。まず、**Thinker(Why領域)**では、ビジョン策定や戦略立案を支援するツールが紹介されています。例えば、ChatGPTはブレインストーミングや情報収集を効率化し、Perplexityは最新のエビデンスを即座に提供、Claudeは膨大なテキストを分析して洞察を引き出します。これらのツールは、意思決定の精度とスピードを高め、より大胆で根拠あるビジョン策定を後押しします。次に、**Facilitator(How領域)**では、プロセス設計やチーム運営を円滑にするツールが登場します。Google Workspaceは会議の自動記録・要約で情報共有を促進し、Linearはタスク・Issue管理で進捗の透明性を高めます。Discordはカジュアルなコミュニケーションを活性化し、情報共有や調整の負荷を大幅に削減します。Maker(What領域)LovableはAIによるフルスタック開発環境やWebアプリ生成を可能にし、Supabaseはバックエンド機能を迅速に構築します。Canvaはデザイン制作を容易にし、アウトプットの生産性と品質を向上させます。さらに、ChatGPTやGoogle Workspace、Notion、Linearといったツールは、全領域を横断的にサポートし、チーム共通のプラットフォームとして役割間の連携をスムーズにします。特筆すべきは、チームの心理的安全性を醸成するツールです。DiscordやGather.townは気軽に発言・議論できる場を提供し、Notionは情報透明化で安心感を与えます。これにより、革新性と俊敏性が向上します。また、共通言語・プロトコル形成にはNotionのWiki機能やLinearの標準化された管理が役立ち、コミュニケーションロスを激減させます。ChatGPTは専門用語の平易化で理解のギャップを埋めます。リーダーシップをサポートするツールとしては、ChatGPTやClaudeが意思決定に必要な洞察を迅速に提供し、LinearやNotionがビジョン共有と戦略遂行を強化します。最後に、AIリテラシー向上に貢献するツールとして、ChatGPTによる実践的な学習、Perplexityによる批判的思考の養成、Difyによる組織的なナレッジ向上が挙げられます。これらのツールは、TFM-Opsという明確な役割とプロセスがあるからこそ、その効果を最大限に引き出せるのです。そして、ツールがTFM-Opsを強力に後押しし、組織全体の学習と改善が加速され、高いパフォーマンスを発揮するチームが構築されます。今回のポッドキャストが、皆さんのチームにおけるAIツールの導入と活用の一助となれば幸いです。それではまた次回!
2025-08-2606 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖AI導入、95%停滞の壁を破る!成功企業5%が実践する「TFM-Ops」7原則とMIT最新調査企業が生成AI導入で成功するための主要な戦略と課題は以下の通りです。主要な課題現在のAI導入における主要な課題として、2025年発表のMIT調査「The GenAI Divide: State of AI in Business 2025」では、約95%の企業でAI導入が停滞し、損益(P&L)への明確な効果が見られないと報告されています。多くの企業で生成AIのパイロットプログラムが期待されたビジネス成果(収益加速など)を達成できず、測定可能なインパクトをほとんど与えていないのが現状です。AI導入が迷走する原因として、「解くべき課題」が拡散してしまうことが挙げられます。成功のための主要な戦略上記の課題に対し、成功している約5%の企業には共通の戦略が見られます。TFM-Ops(Thinker, Facilitator, Maker)のフレームワークは、これらの成功原則を有機的に結びつけるものとされています。1. 明確なユースケースの設定AI導入の迷走を防ぐため、「解くべき課題」を一点に絞り込むことが極めて重要です。成功企業は「限定的かつ明確なユースケース選定」を行うことで成果を得ています。ThinkerはWhyを問い直し、請求書処理やレポート生成といった小さなPoC(概念実証)を切り出すことで「仮説の優先度付け」を実践します。2. 専門ベンダーとの共創パートナーシップ外部ベンダーとの深いパートナーシップは、成功を大きく左右する戦略です。自社内製でのAI導入の成功率が約33%であるのに対し、専門ベンダーとのパートナーシップ型導入では約67%の成功率を示すデータが公表されています。Facilitatorは、ベンダーの知識を社内の文脈に接続する「社内外の文化を橋渡しする外交官」としての役割を担います。3. バックオフィス業務の優先的自動化AI投資の対象としては、**請求書処理や在庫管理などのバックオフィス業務の自動化分野で最も高い投資対効果(ROI)**が得られています。Makerがこの領域で最も輝き、定型業務の自動化を通じて、経営層に実際に動くデモを見せることで、次の拡張へと火をつけることができます。4. 現場主導の仮説検証サイクルと段階的スケールアップAI PoCは技術検証だけでなく、「現場の納得感」をどう積み上げるかが勝負です。Facilitatorが短サイクルでBuild-Measure-Learnを回す仕組みをデザインし、心理的安全性を確保し、失敗談も資産に変える「ナレッジ共有ループ」を確立することで、組織学習を加速させます。PoCの成果を水平展開する際には、Thinkerが他領域への応用シナリオを描き、Facilitatorがコミュニティで知見を拡散し、Makerがテンプレート化したフローを即座に複製する「役割リレー」が、「PoCの壁」を越える鍵となります。5. KPI/ROIの厳格な設定とモニタリングAI導入を「遊びではなく事業」と認識させるためには、KPI/ROIの厳格な設定とモニタリングが不可欠です。Thinkerが「なぜこの指標か」を設計し、Makerがデータ可視化ダッシュボードを実装します。Facilitatorは数値を通じて経営層と現場の合意形成を支えることで、この三位一体が機能します。6. セキュリティ・ガバナンスの強化AI導入の土台は信頼であり、データ取り扱いルールを整備し、誰もが安心して実験できる環境を構築することが重要です。これはFacilitatorの設計力にかかっており、単なる規制遵守に留まらず、「安全に失敗できる文化」を育むことに直結します。TFM-Opsによる総括これらの7つの原則は、TFM-Opsのフレームワークの中で有機的に結びついています。ThinkerがWhyを定義し、FacilitatorがHowを場に浸透させ、MakerがWhatを形にすることで、AI導入は「資料と会議で止まるプロジェクト」から脱却し、「動いて学ぶカルチャー」へと進化することができます。自社のAI導入ロードマップをTFM視点で評価し、Thinker、Facilitator、Makerのどのフェーズが不足しているかを可視化することが、成功確率を高める次の一歩となります。
2025-08-2423 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖Vibe Coding & TFM Ops(00:00–00:20)新しい働き方の波が来てる。生成AIの登場で、コンサルの“常識”が一瞬で変わる時代が始まった。そこで登場するのが、「Vibe Coding」と「TFM Ops」という新しいプレイブック。(00:20–00:43)今日の流れ:まず AI がコンサルをどう変えるのか。それから Vibe Coding の説明、続いて TFM Ops フレームワークを展開。その両者を組み合わせた活用法と、AIとの新しい関係性について語る構成。(00:43–01:26)コンサルタントあるある:夜な夜なスプレッドシートやスライドに時間を溺れさせてた。でも AI がその価値創出の重労働部分を数秒でこなしてしまう。じゃあ、自分の価値はどこにあるの?(01:26–02:10)キーは“思考の切り替え”。Vibe Coding は、手作業より「意図を伝えて AI とクリエイティブな会話をする」スタイル。生成したものを微調整し、次々に草案を生むコラボプロセス。(02:33–03:31)Vibe Coding は速く、協働的。一方で、システマティックに動かすには構造が必要。それが「TFM Ops」。その中核は、“Thinker(思考者)”、“Facilitator(推進者)”、“Maker(創造者)”の3つの役割。(03:31–03:51)従来コンサルでは、80%が“Thinker”業務。分析、リサーチ、スライド作成など、AI が得意な領域に偏っていた。(03:51–04:11)Vibe Coding × TFM Ops = “スピード” と “構造” の融合。まず Thinker は仮説から即ドラフトへ。Facilitator はリアルタイムに会議で可視化。Maker は数時間でプロトタイプ制作。(04:11–04:36)この組み合わせがもたらすのは、クライアントへの「紙の提案」ではなく「即動くもの」の届け方。プロジェクトが即、インタラクティブな生きたプロセスになる。(04:36–05:22)なぜこの方法が根本的にイノベーティブかというと、AIを“道具”ではなく“共創パートナー”として扱うから。ツール扱いじゃなく、会話して一緒に創る相棒。(05:22–END)未来の問いは「AIに仕事を奪われるか?」ではなく、「どう AI と働くか?」。Thinker/Facilitator/Maker、それぞれを強化する新しい共創スタイルの模索が始まってる。
2025-08-2305 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖AI時代のコンサル術:「Vibe Coding」と「TFM-Ops」で変わる働き方と共創の未来Vibe CodingとTFM-Opsは、生成AIの登場により変化するAI時代において、コンサルタントの働き方を大きく変革する新しいアプローチです。具体的には、以下の点でコンサルタントの働き方を進化させます。• 従来のコンサル業務の変化 ◦ これまでのコンサルタントの仕事は、クライアントの課題発見、解決策の立案、実行伴走にありました。 ◦ しかし、生成AIの登場により、「考える」「まとめる」「作る」といった多くの作業がAIによって補助されるようになりました。 ◦ これにより、従来の**「分析や資料作成に時間を割くコンサル」像は急速に変化**しています。• Vibe Codingによる変革 ◦ Vibe Codingは、コードやスライドを一行ずつ手で作るのではなく、「こんなアウトプットが欲しい」という意図をAIに伝え、会話を通じて形にしていくスタイルです。 ◦ コンサルの現場では、PowerPointやExcelを夜遅くまで磨く代わりに、Day0からAIと共に叩き台を用意し、クライアントとの対話に時間を割く働き方が可能になります。 ◦ コードだけでなく、プロトタイプ、シナリオ、分析フレームの試作などを即興セッション的に共創できるのが特徴です。• TFM-Opsによる役割の再定義 ◦ TFM-Opsは、コンサルタントが持つべき3つの役割を定義するフレームワークです。 ▪ Thinker:課題を構造化し、解決の道筋を描く役割。 ▪ Facilitator:ステークホルダーを巻き込み、合意を形成する役割。 ▪ Maker:プロトタイプや実装で仮説を検証する役割。 ◦ これまではThinkerに偏重しがちだったコンサル業務ですが、AI時代にはFacilitatorとしての共創力、Makerとしての形にする力がこれまで以上に求められます。TFM-Opsはそのバランスを取る指針となります。• Vibe CodingとTFM-Opsの掛け合わせによる価値 両者を組み合わせることで、コンサルタントの働き方は以下のように進化します。 ◦ Thinker × Vibe Coding:AIと即座に仮説をコード化・資料化することで、思考と実装のギャップを縮めることができます。 ◦ Facilitator × Vibe Coding:会議中にAIで可視化しながら議論を進めることで、合意形成のスピードを上げることができます。 ◦ Maker × Vibe Coding:数時間でPoC(概念実証)を立ち上げ、クライアントに**「動くもの」を提示できる**ようになります。• クライアントへの提供価値とコンサルタントの新たな役割 ◦ この変革により、クライアントは「机上の提案」ではなく、「共に試せるプロトタイプ」を初期段階から受け取れるようになります。 ◦ まさに体験を共有しながら学習するコンサルティングが可能になるのです。 ◦ Vibe Codingが直感とスピードを与え、TFM-Opsが役割の秩序と協働の型を与えることで、コンサルタントは**「AIを相棒にする働き方」を実現**し、クライアントに価値ある成果を最速で届けられるようになります。 ◦ これからのコンサル業界で問われるのは、「AIに仕事を奪われないこと」ではなく、**「AIとどのように共創するか」**であり、TFM-Ops的な働き方はその問いに対する有力な答えの一つとなります。
2025-08-2320 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖AI時代に再定義される達人性:Karpathy流学習とTFM-Opsの共鳴今日の開発現場では、AIアシスタントが人間の思考と創造力を増幅する「思考パートナー」となり、人間とAIが共同でアイデアを生み出し問題を解決する「AI共創」が新たなイノベーションの形となっています。このパラダイムシフトにより、かつて長年の経験と膨大な知識量で測られた専門性の定義が変わりつつあります。これからは、どれだけ速く深く学習し、学んだ知見で新しい価値を創造できるかが重要です。著名なAI研究者であるAndrej Karpathy氏は、達人になるためのシンプルな学習法を提唱しています。それは、手軽な「学習スナック」ではなく、教科書や論文といった「フルコース」に腰を据えて取り組み、分野への理解を深めることで「解像度を上げる」学習です。具体的には以下の3つのポイントを強調しています。1. 具体的なプロジェクトに繰り返し挑戦し、その都度必要なことを学ぶ:実践を通じて机上の空論ではない知識を身につける。2. 学んだことを自分の言葉で要約し、人に教える:知識を体系化し、曖昧な点を明確にする。3. 他人ではなく過去の自分と比較する:外部との比較に囚われず、着実にスキルを高める姿勢を保つ。これらのKarpathy氏のメソッドは、AI時代の達人を育む実践モデル**「TFM-Ops(Thinker, Facilitator, Makerの統合)」**と驚くほど合致しています。• 「具体的なプロジェクトに挑戦」は、TFM-Opsの「Thinker(課題構造化)とMaker(プロトタイプ作成)の連携」に相当し、AIアシスタントの活用により知識をオンデマンドで補給しながら高速に仮説検証を進めます。• 「学んだことの要約と他者への共有」は、「Facilitator(場作りと橋渡し役)が促す学習内容の体系化と再構成」としてTFM-Opsで実践されます。AIが議事録要約や資料ドラフト作成を支援し、知識の整理・共有を加速させます。• 「過去の自分との比較」は、TFM-Opsの「継続的な自己成長のループ」として体現され、チームは外部比較ではなく「以前の自分たちの水準をどれだけ引き上げたか」に焦点を当てます。AI共創は、人間とAIの共進化的な成長を後押しします。架空の事例として、ABC社のAI開発チームは、AIとTFM-Opsモデルを駆使し、高速な仮説検証サイクルを通じて、わずか半年で工場のダウンタイムを40%削減する故障予知システムを開発しました。これは、新米チームが実践的な達人へと成長した物語です。総括すると、「達人」とはゴールではなくプロセスであり、常に新しい地平を学習によって切り拓いていく存在です。AIという心強い相棒とTFM-Opsのような実践モデルは、専門性を飛躍的に高め、共創によって加速する学習と創造のダイナミズムこそが、再定義された現代の「達人性」の姿と言えるでしょう。
2025-08-0907 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖AI研修を現場で活かせない理由と「TFM-Ops」が拓く共創の新境地AI学習の新常識!「知る」から「共創する」時代へ〜TFM-Ops×AI実践が示す未来〜今日のビジネス環境でAIの活用が叫ばれる中、多くの企業や個人がAI入門講座や資格取得に励んでいます。しかし、そうした一般的なAI講座には共通の限界があることをご存知でしょうか?本エピソードでは、まず、これらの講座が抱える問題点を深掘りします。内容は汎用的で抽象的、スライド中心の知識提供に留まり、G検定講座のように体系的な知識は得られてもプログラミングや実装スキルには繋がらず、「実務では意味ない」と評価されてしまうケースも少なくありません。受講者はAIの仕組みを「知っている」だけで、実際の業務でどう活かすか、特に多くのAIプロジェクトが直面する「PoCの壁」をどう乗り越えるか、といった実践的な知見が不足しがちです。また、AIを単なる分析装置や自動化ツールとして捉え、「人間と共に考えるパートナー」という視点が欠けている点も問題です。これに対し、私たちは**「TFM-Ops×AI」という全く新しいアプローチに焦点を当てます。TFM-Opsとは、Thinker(考案者)、Facilitator(推進役)、Maker(実装者)がチーム内で協働し、AIを単なるツールではなく「共創パートナー」**として位置づける育成・実践モデルです。TFM-Ops実践者は、仮説検証の高速サイクルを回し、最新の生成AIや自動化ツールを駆使して高いプロトタイプ実装力を発揮します。チーム内の密な連携により、PoC止まりに終わらず、AIソリューションを現場に深く浸透させ、実業務での定着まで導く推進力を持つのが最大の強みです。AIを「一緒に考える相棒」として活用し、アイデア出しや設計プロセスに組み込むことで、人間の創造性をAIで拡張する「共創力」こそが、これからの時代に求められるスキルなのです。もはやAIを「学ぶ」だけでは不十分で、AIと「共に創る」ことが求められる時代が到来しています。本エピソードを通じて、知識偏重の“講座”の時代から、実務を通じてスキルを積み上げ、AIをパートナーとして使いこなす**「共創スキル」の時代**へと移行する重要性をお伝えします。AI時代をリードする人材になるために、ぜひこのエピソードで「TFM-Ops×AI実践」のエッセンスを掴んでください。
2025-08-0806 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖やるぜ!『TFM』。戯言で終わらない道のり。AI時代に企業が競争力を高めるための「TFM×AI戦略アップデート提案」を深掘りします。この戦略は、従来の固定的な役割分担から脱却し、全社員が「Thinker(戦略構想者)、Facilitator(推進・調整者)、Maker(実行・創造者)」の3つのスキル全てを兼ね備えた“ジェネラライジング・スペシャリスト”へと成長することを目指します。なぜ今この戦略が必要なのでしょうか?単一スキルに特化した人材はAIによる代替リスクが高まる一方、複数技能を持つ人材がより高い価値を発揮するためです。AIは各スキルの習得におけるコパイロット(共創パートナー)創造的判断に注力することで、TFM×AIの相乗効果を最大化します。この戦略は「Enable(基盤構築)」「Amplify(拡大・強化)」「Showcase(発信・定着)」の3段階のロードマップで推進されます。スキルツリーモデルで成長を可視化し、OJTやメンター制度、AIを活用したパーソナライズされた学習支援で実践力を強化します。最終的には、「TFM×AI人材」の育成定着、イノベーション創出の加速、ナレッジ共有文化の醸成、そして社外へのエミネンス(卓越性)向上を目指します。AIを駆使し、人と組織全体の価値創造力を高める、これからの人材戦略の全貌をお届けします。
2025-08-0607 min
🐥SAZANAMI AIラジオ ~とあるサラリーマンとAIの相棒物語を横目に~🤖TFM × AIスキルツリー:思考スタイルとAI習熟度で描くキャリア戦略「TFM×AIスキルツリー」の最新版について、そのエピソード概要をご紹介します。このスキルツリーは、従来のスキルに「TFM視点からの意味づけ」と「AI活用要求レベル」の2つの軸を追加し、各スキルがAI時代にどのように進化し、強化されるべきかを示しています。TFMモデルの3つの思考スタイル:• Thinker(Why): 論点を構造化し、仮説ベースで戦略や意思決定を支援するタイプ。業務の背景にある「Why(なぜ)」を意識し、課題の本質を捉え、全体最適を追求します。• Facilitator(How): 対話を通じて共感と合意を形成し、「場」を設計・運営するタイプ。心理的安全性を作り、対話の質を高める「How(どのように)」を重視します。• Maker(What): 実際に手を動かして曖昧なものを具体化し、共通認識を生むタイプ。アイデアをプロトタイプやツールとして形にし、実践的な「What(何を作るか)」のアウトプットを重視します。AI活用要求レベルの3段階:• Lv1(基礎利用): AIをツールやアシスタントとして活用し、人間主体で必要な時に支援を得る段階です。• Lv2(応用設計): AIを業務フローに組み込み、目的に合わせてカスタマイズし、一部自律的な処理を任せる段階です。• Lv3(共創パートナー化): AIをパートナーとして対話・協働しながら創造や意思決定を行うレベル。AIがユーザーの価値観や文脈を理解し、共に成果を生み出す段階です。このスキルツリーを通じて、各スキルがTFM的に何を意味し、AI時代にどのような知能強化が求められるかが一目でわかります。特に、高レベルのスキルでは、AIが単なるツールを超え、戦略立案、ビジョン策定、組織変革、PoC文化醸成などにおいて、人間とAIが「共創パートナー」として深い対話や協働を通じて価値を生み出すという未来の働き方が描かれています。このエピソードでは、AI時代に求められる個人のスキルアップと組織全体の知能強化のヒントを探ります。
2025-08-0606 min
The Fasting Method PodcastThe TFM Podcast Goes Live!Episode #212 In this week's episode, Megan and Terri sync up for a special live recording to share their experiences and tips related to making their health and weight-loss journeys long term vs a short-term fix. Because they were recording live, they also invited some TFM Lifetime Members to share their transformations. Sign up TODAY for the Optimize Your Weight (Fat) Loss Workshop with Heather Shuker, CRNP. Starts July 15th. 10% Discount with code PODCAST10 https://www.thefastingmethod.com/masterclasses-and-live-workshops-2025/#Optimize Transcripts of all episodes are available on t...
2025-07-0844 min
Theological Family MinistryTFM Career DayPastors Ben and Tony talk about vocation and the Christian life
2025-04-3046 min
Theological Family MinistryTFM Classic: An Easter SpecialPastors Ben and Tony revisit their first Easter special
2025-04-1640 min
Finanza Semplice di Alfonso SelvaTFM: scopri il tesoro nascosto nella TUA azienda. Per Amministratori e soci. EP. 306🔎 TFM: Scopri il tesoro nascosto nella tua azienda – Guida per amministratori e soci 🚀 Il Trattamento di Fine Mandato (TFM): un'opportunità da non perdere Se sei amministratore o socio di un’azienda, c’è uno strumento che potrebbe fare la differenza nella tua pianificazione finanziaria: il Trattamento di Fine Mandato (TFM). Questa indennità, spesso sottovalutata, ti permette di accumulare un capitale, ottimizzare la gestione fiscale aziendale e ridurre il carico fiscale. In questa puntata di Finanza Semplice, ti spiego cos’è il TFM, perché è vantaggioso e come puoi usarlo al meglio. Se vuoi migliorare la tua gestione finanziaria, questo episodio è imperdibile! 🎯 Cos’è il TFM e perché dovresti consi...
2025-03-0712 min
Finanza Semplice di Alfonso SelvaTFM: scopri il tesoro nascosto nella TUA azienda. Per Amministratori e soci.🔎 TFM: Scopri il tesoro nascosto nella tua azienda – Guida per amministratori e soci
🚀 Il Trattamento di Fine Mandato (TFM): un'opportunità da non perdere
Se sei amministratore o socio di un’azienda, c’è uno strumento che potrebbe fare la differenza nella tua pianificazione finanziaria: il Trattamento di Fine Mandato (TFM).Questa indennità, spesso sottovalutata, ti permette di accumulare un capitale, ottimizzare la gestione fiscale aziendale e ridurre il carico fiscale.In questa puntata di Finanza Semplice, ti spiego cos’è il TFM, perché è vantaggioso e come puoi usarlo al meglio.Se vuoi migliorare la t...
2025-03-0712 min
Finanza Semplice di Alfonso SelvaTFM. Trattamento Fine Mandato per Amministratori. Scopri tutti i Vantaggi dal 2025 in poi.Trattamento di Fine Mandato: Il Tesoro Nascosto per Amministratori e SocietàCiao e benvenuto alla nuova puntata del podcast video-podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Sono io! Sono un consulente finanziario e svolgo questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni. In questo video-podcast parlo di storie di investimento e intervisto personaggi interessanti.Se sei un amministratore o stai guidando un’azienda, allora c’è un aspetto fondamentale che devi considerare: il trattamento di fine mandato. Si tratta di uno strumento che non so...
2024-12-2009 min
Finanza Semplice di Alfonso SelvaTFM. Trattamento Fine Mandato per Amministratori. Scopri tutti i Vantaggi dal 2025 in poi. EP. 295Trattamento di Fine Mandato: Il Tesoro Nascosto per Amministratori e Società Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast video-podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Sono io! Sono un consulente finanziario e svolgo questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni. In questo video-podcast parlo di storie di investimento e intervisto personaggi interessanti. Se sei un amministratore o stai guidando un’azienda, allora c’è un aspetto fondamentale che devi considerare: il trattamento di fine mandato. Si tratta di uno strumento che non solo rappresenta una sicurezza per gli amministratori, ma off...
2024-12-2009 min
Casting the Future6X06 - Tips&Tricks: Cómo triunfar en tu TFG o TFMEn este episodio de Tips & Tricks, nos adentramos en un tema crucial para los estudiantes que están en la recta final de sus estudios: los Trabajos Fin de Grado (TFG) y los Trabajos Fin de Máster (TFM) en Comillas ICAI. Para resolver todas las dudas y proporcionar consejos prácticos, contamos con dos invitados: Eva Arenas, coordinadora de los TFGs del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, y Álvaro López, coordinador de los TFMs del Máster en Industria Inteligente.A lo largo del episodio, Eva y Álvaro nos explican el proceso completo para llev...
2024-12-0421 min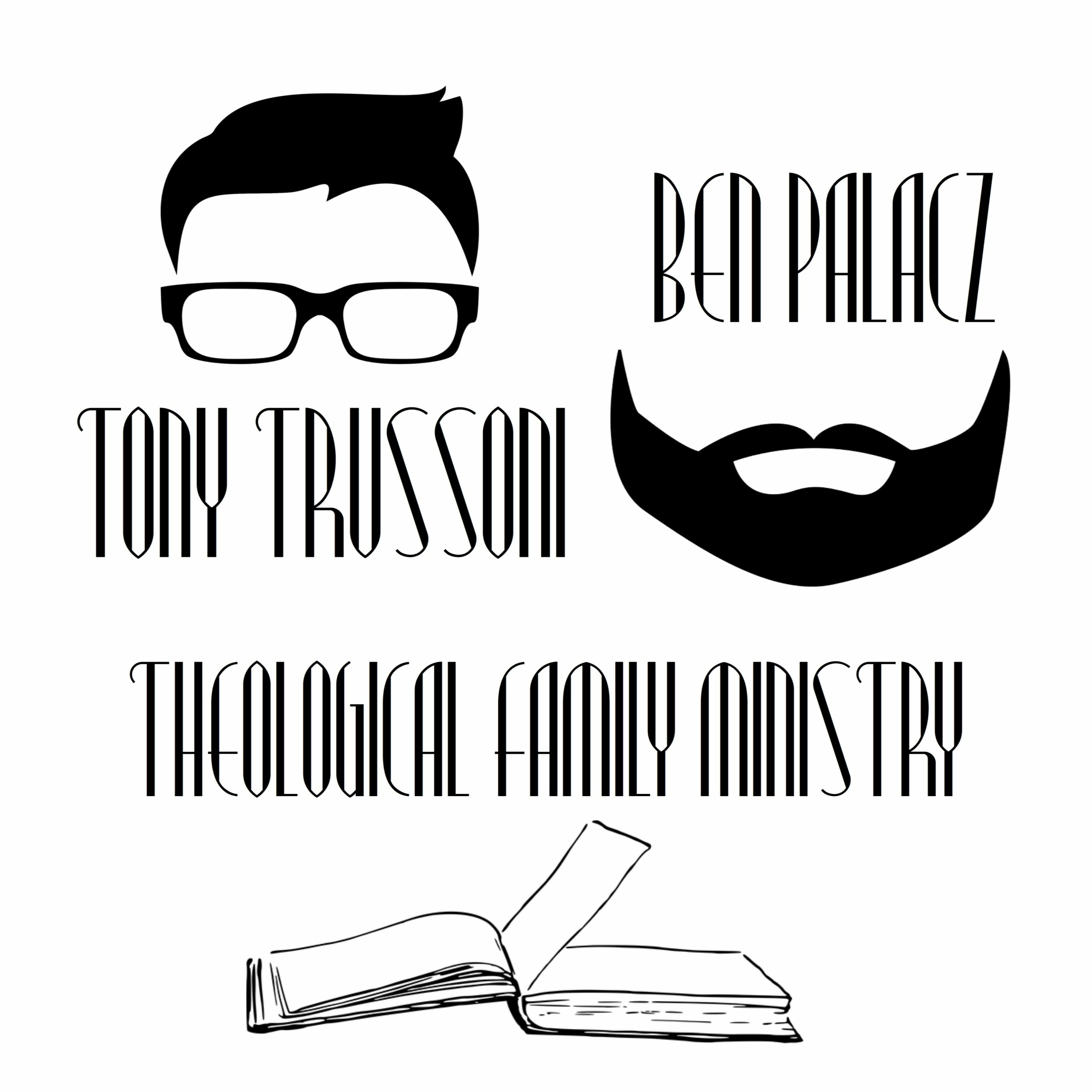
Theological Family MinistryTFM Classic: A Theology of Child SafetyIn this classic TFM episode Pastors Ben and Tony talk about how we can keep kids safe in the church.
2024-10-0251 min
The Fasting Method PodcastMeet the New TFM Coaches: Amy MedlingEpisode #161 In the week's episode, Terri is very excited to introduce another of our three new coaches who have joined the TFM team. Thie new coach you will meet today is Coach Amy Medling. You will learn about her background and specialty focus in her conversation with Terri. This month she will begin facilitating meetings in the TFM Community, will be available for folks seeking to work with a TFM coach, and she will return to the podcast to share future insights. Transcripts of all episodes are available on the Podcast page at w...
2024-07-1628 min
The Fasting Method PodcastMeet the New TFM Coaches: Dr Amy WiesnerEpisode #160 In the week's episode, Terri is very excited to begin introducing our three new coaches who have joined the TFM team. First up is Dr. Amy Wiesner. You will learn about her background and specialty focus in her conversation with Terri. This month she will begin facilitating meetings in the TFM Community, will be available for folks seeking to work with a TFM coach, and she will return to the podcast to share future insights. Transcripts of all episodes are available on the Podcast page at www.thefastingmethod.com Please Su...
2024-07-0928 min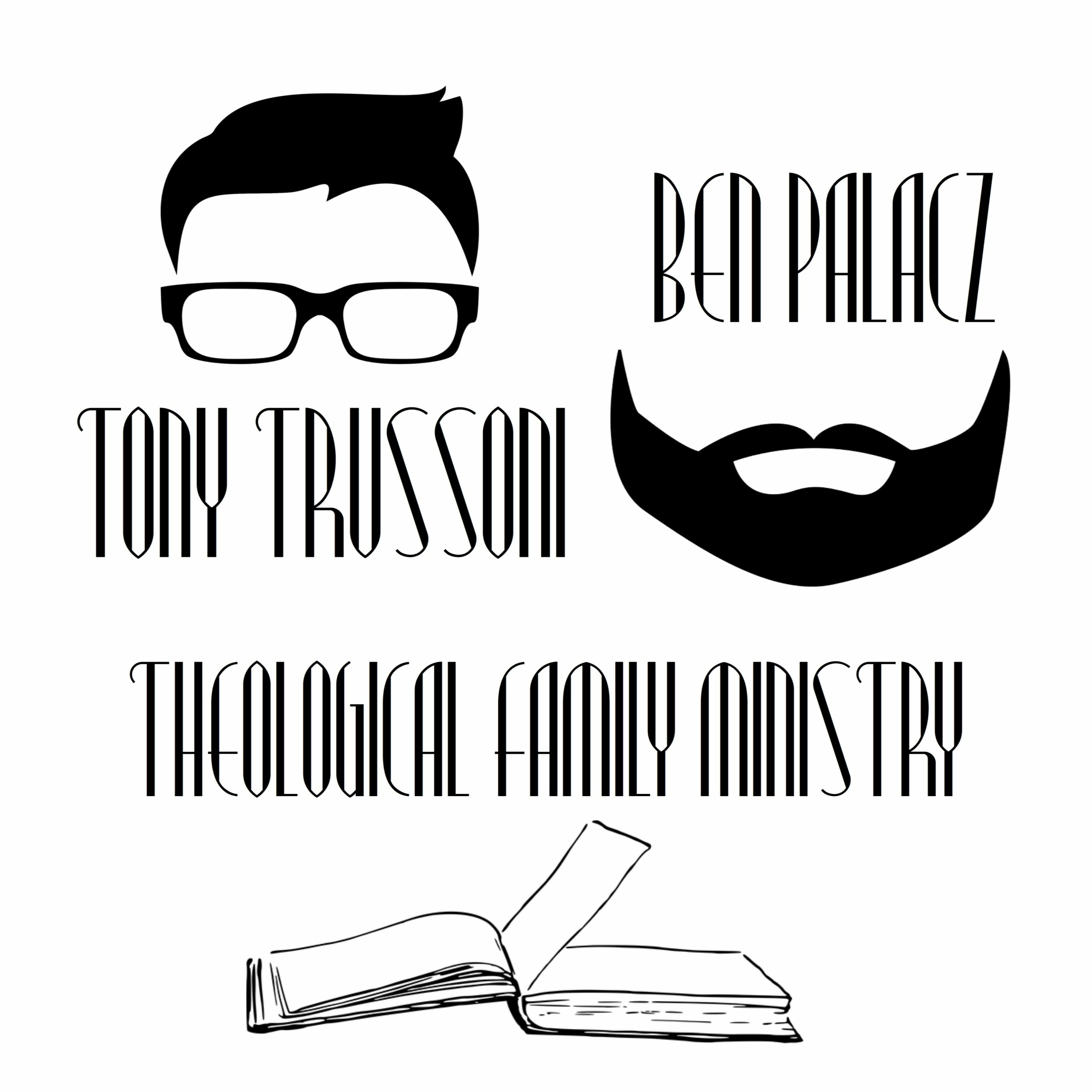
Theological Family MinistryTFM Classic: Delighting in Divine DesignEnjoy this Classic Episode of TFM about God's design and next generation ministry.
2024-06-1942 min
Finanza Semplice di Alfonso SelvaTrattamento Di Fine Mandato (TFM) Per Amministratori: Una Guida CompletaTrattamento Di Fine Mandato (TFM) Per Amministratori: Una Guida CompletaCiao, sono Alfonso Selva e ti do il benvenuto a questo episodio speciale di "Finanza Semplice", dedicato interamente al Trattamento di Fine Mandato (TFM) per gli amministratori di società. Oggi voglio accompagnarti attraverso un viaggio esplorativo su uno strumento fondamentale sia per te, amministratore, sia per la tua azienda, per capirne i benefici in termini di sicurezza finanziaria e vantaggi fiscali.Cos'è il TFM? Ti spiegherò nel dettaglio cos'è il TFM, quell’indennità che ricevi al termine del tuo mandato...
2024-01-0509 min
Finanza Semplice di Alfonso SelvaTrattamento Di Fine Mandato (TFM) Per Amministratori: Una Guida Completa. EP. 243Trattamento Di Fine Mandato (TFM) Per Amministratori: Una Guida Completa Ciao, sono Alfonso Selva e ti do il benvenuto a questo episodio speciale di "Finanza Semplice", dedicato interamente al Trattamento di Fine Mandato (TFM) per gli amministratori di società. Oggi voglio accompagnarti attraverso un viaggio esplorativo su uno strumento fondamentale sia per te, amministratore, sia per la tua azienda, per capirne i benefici in termini di sicurezza finanziaria e vantaggi fiscali. Cos'è il TFM? Ti spiegherò nel dettaglio cos'è il TFM, quell’indennità che ricevi al termine del tuo mandato come riconoscimento per il servizio prestato e come rete di sicurez...
2024-01-0509 min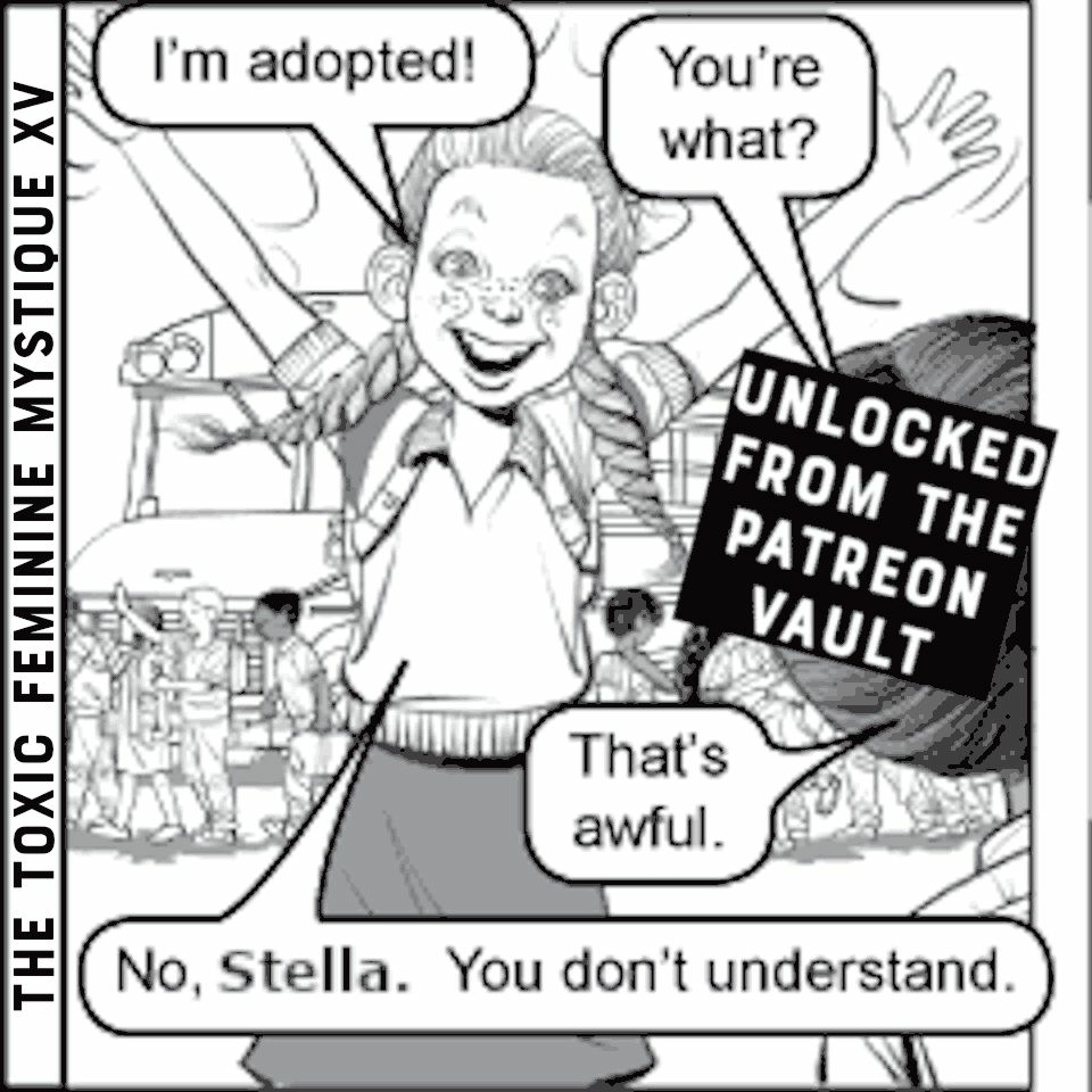
Rock Hard CaucusUNLOCKED - TFM XV: Selling Children with Anastasia (11/5/2021) [6/12/2022]To celebrate twenty episodes of TFM, we're unlocking this episode from last year (by request of our friend Maggie).
---------
Anastasia is back! It turns out Natalie and Stella left a very important question unanswered in the TFM abortion trilogy... IS adoption an option?!
Follow Anastasia on twitter: https://twitter.com/AnesthesiaCG
---------
Subscribe to hear every episode of TFM plus a whole bunch of other stuff: https://www.patreon.com/rockhardcaucus?filters[tag]=toxic%20feminine%20mystique
https://rockhardcauc.us
2022-06-121h 17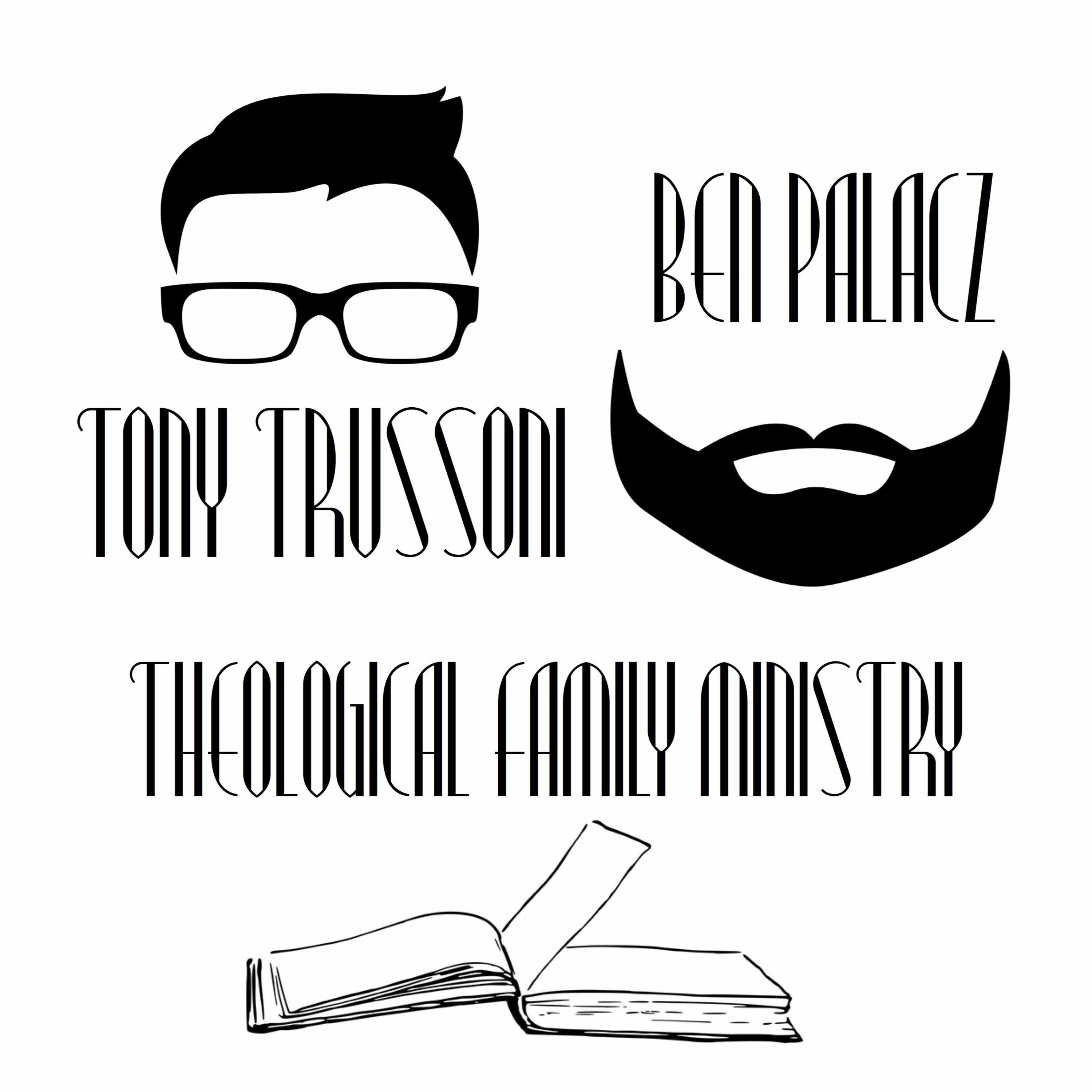
Theological Family MinistryPurely TFMPastors Ben and Tony talk about Purity Culture and how Christians families should approach purity decades after the height of purity rings and bleached hair.
2021-10-0652 min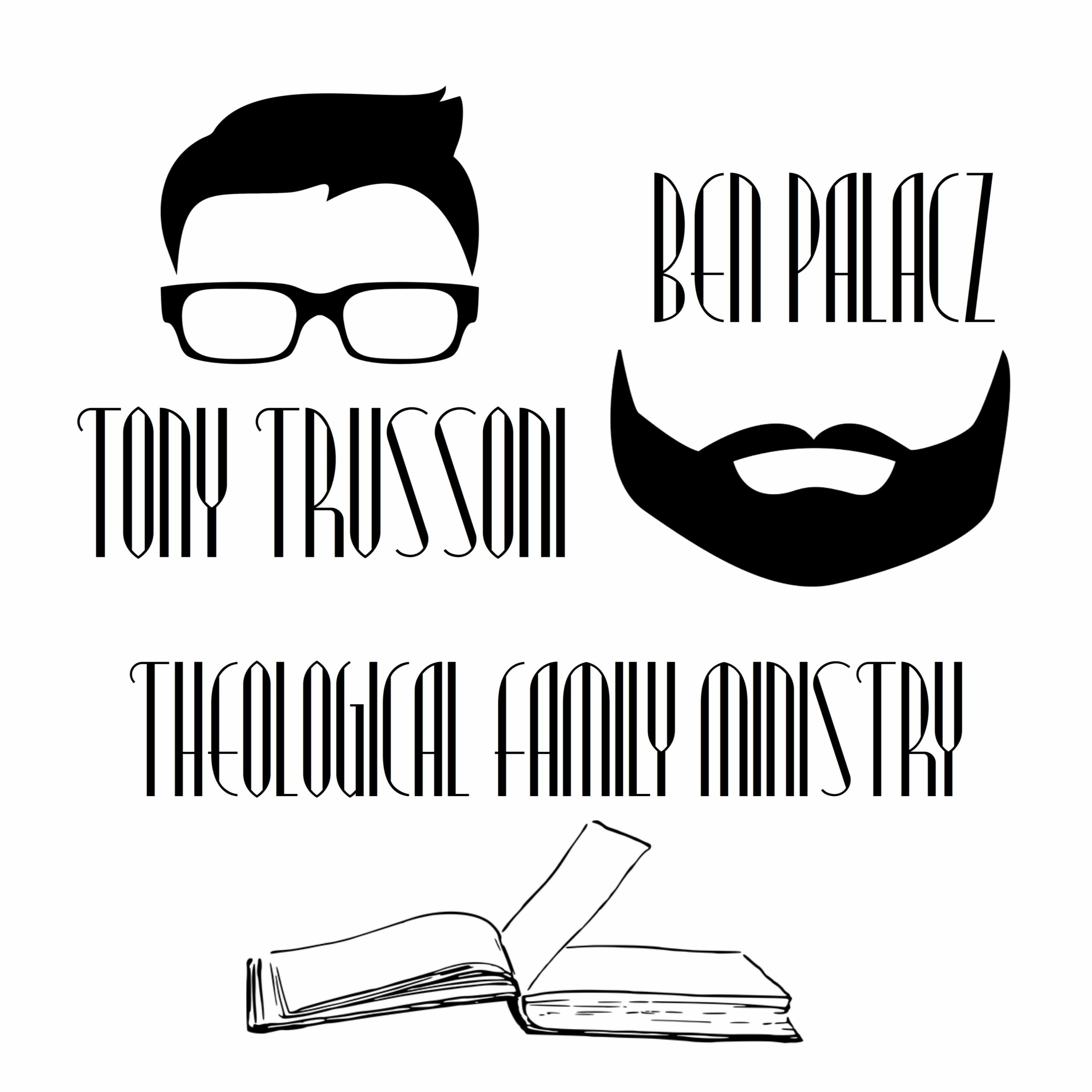
Theological Family MinistryRaising Readers for JesusIn this episode of TFM Pastors Tony and Ben discuss the importance of reading for the Christian family
2021-06-0246 min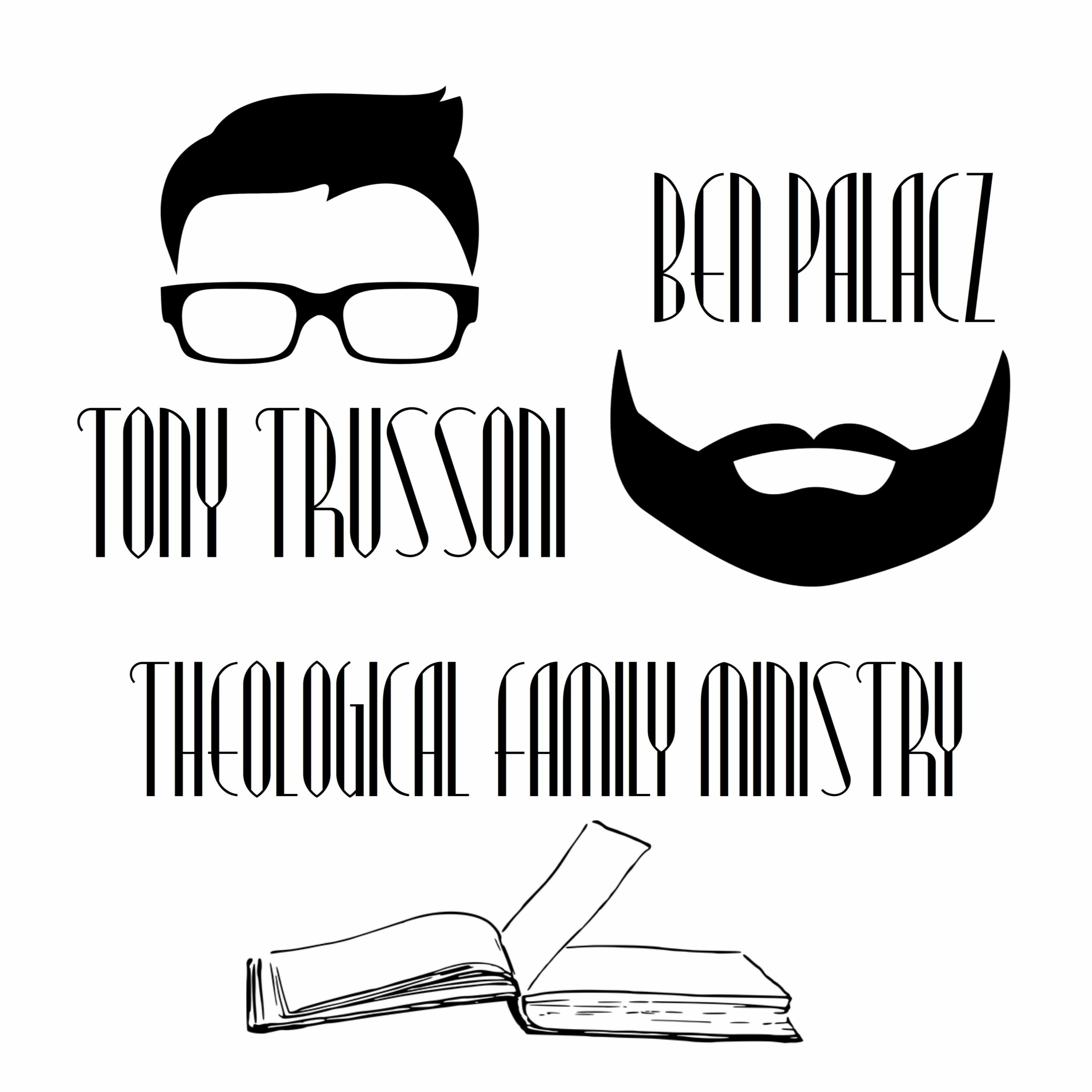
Theological Family MinistryTFM Goes to CollegePastors Tony and Ben talk about the complexities involved in helping our kids think about college.
2021-03-1750 min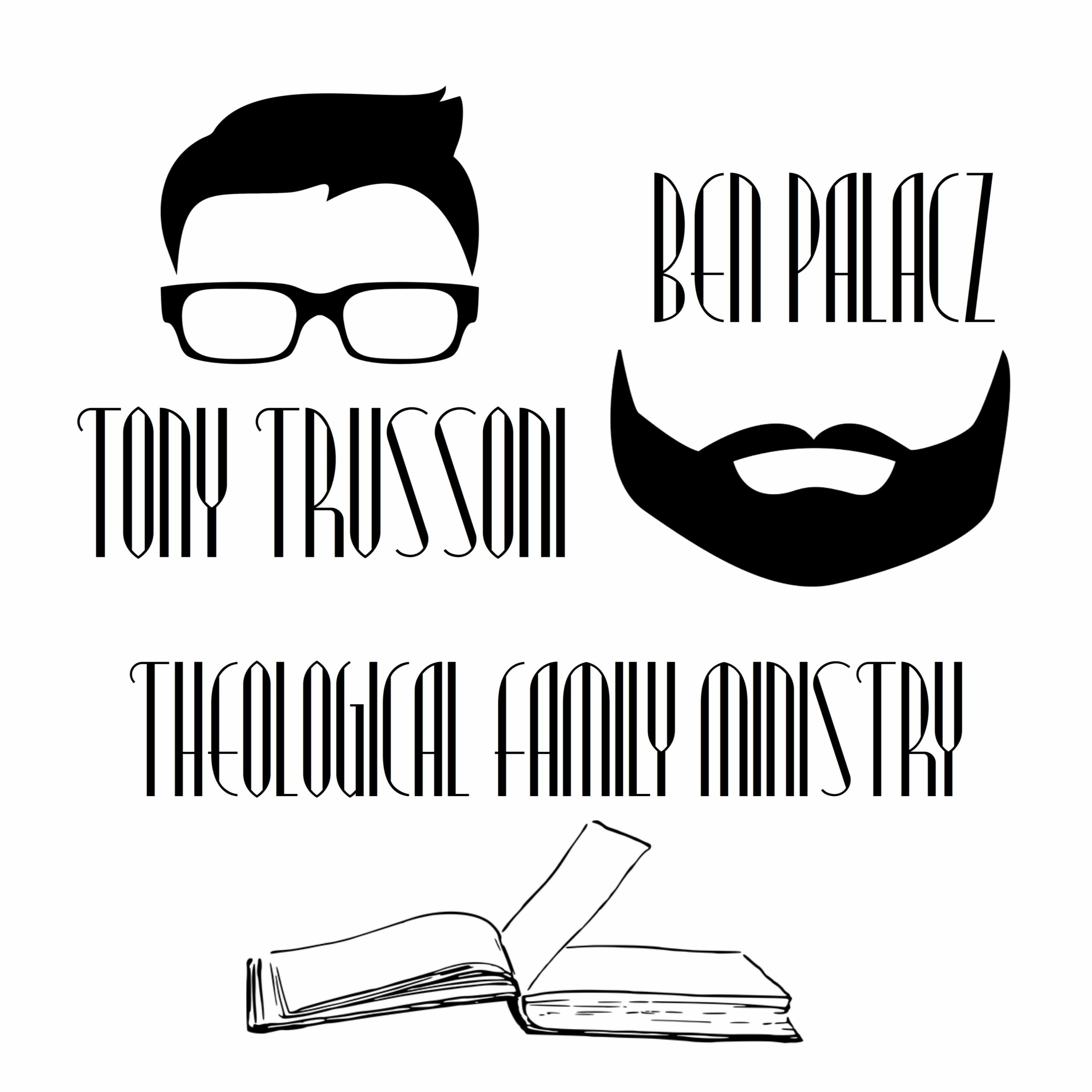
Theological Family MinistryTFM At the Movies 2: Pixar's SoulPastors Ben and Tony talk about the new movie Soul and discipling our kids through watching movies together.
2021-01-0647 min
Kopi KonversationsSoon Seng, CEO of Teach for Malaysia, How TFM is Solving the Education Inequity Problem in MalaysiaIn this episode of Kopi Konversations, we have Soon Seng, the current CEO of Teach for Malaysia (TFM). TFM is working to solve the education inequity problem in Malaysia. (Don't worry, we'll tell you what education inequity is in the podcast) Soon Seng talks about his 9-year journey in TFM as well as TFM's plans to tackle the education problem. Come listen to this new episode of Kopi Konversations!
2020-09-0938 min
Biblioteca Hombres LibresDespedida a los falsos amigos (TFM)Video subtitulado en español:
Canal de TFM:/https://www.bitchute.com/channel/turdflingingmonkey/
Visita mi canal para mas videos de la filosofia MGTOW: https://www.bitchute.com/channel/WKr6bX1OjHWx/
Turd Flingin Monkey (TFM) es un creador de contenido anglosajon que explica de manera muy analitica los conceptos de la filosofia.
En este video TFM responde a uno de los ataques mas rastreros que he visto a la fecha: Su co anfitrion DDJ con el cual hizo varios directos le lanzo un video inesperado difamandolo y tergiversando todo lo que alguna vez le explico. Este video al ser m...
2020-06-0327 min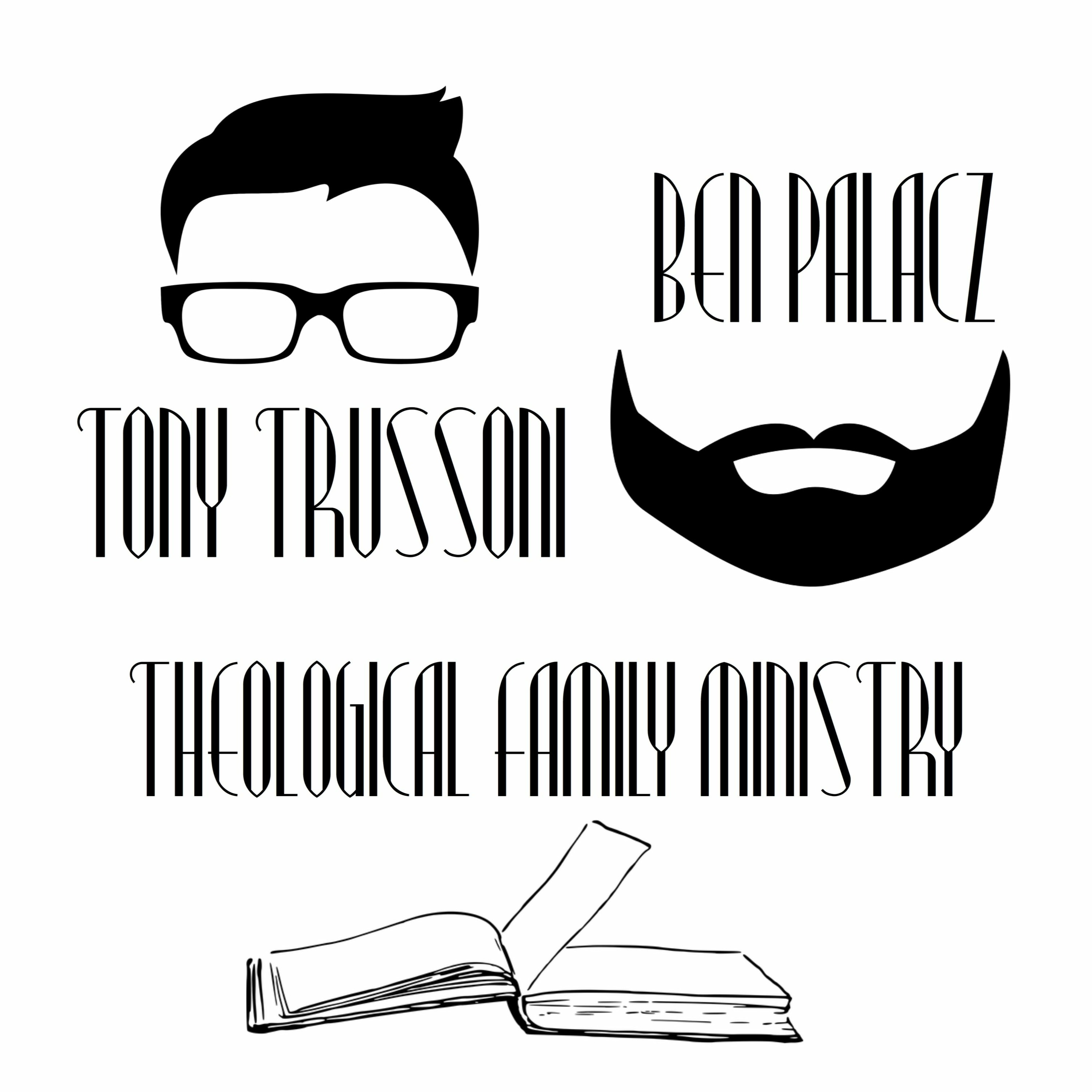
Theological Family MinistryWill This Make us More Alone Together?In this episode of TFM Pastors Ben & Tony talk about the way stay at home orders are impacting families and bringing long term effects to our next gen ministries and family discipleship.
2020-05-0646 min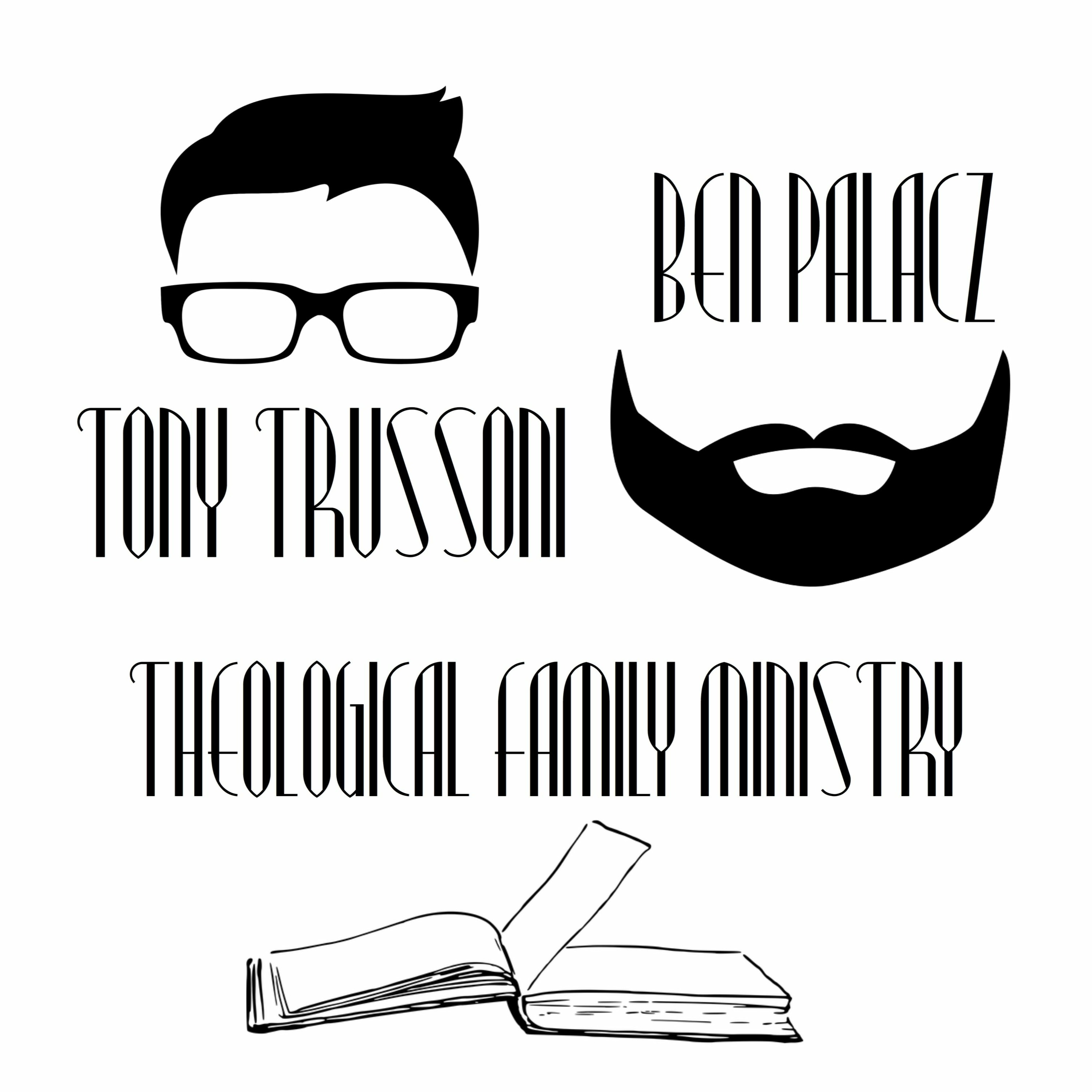
Theological Family MinistryReal Friendship and Young PeopleIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk about friendship and how theology and scripture impacts how our kids should approach friendship. Listen and be blessed.
2020-04-0154 min
Biblioteca Hombres LibresLos enemigos del hombre parte 2 Aclaraciones sobre la dominación (TFM)Lin a video subtitulado en español: https://www.bitchute.com/video/C50ZNr2S4tvQ/
Canal de TFM:/https://www.bitchute.com/channel/turdflingingmonkey/
Visita mi canal para mas videos de la filosofia MGTOW: https://www.bitchute.com/channel/WKr6bX1OjHWx/
Turd Flingin Monkey (TFM) es un creador de contenido anglosajon que explica de manera muy analitica los conceptos de la filosofia.
En esta miniserie TFM comienza a explicar cuales son los enemigos del hombre, en cuanto a los aspectos de su naturaleza y que debemos conocer para poder manejarlos de la mejor manera. El primero de todos e...
2020-03-2716 min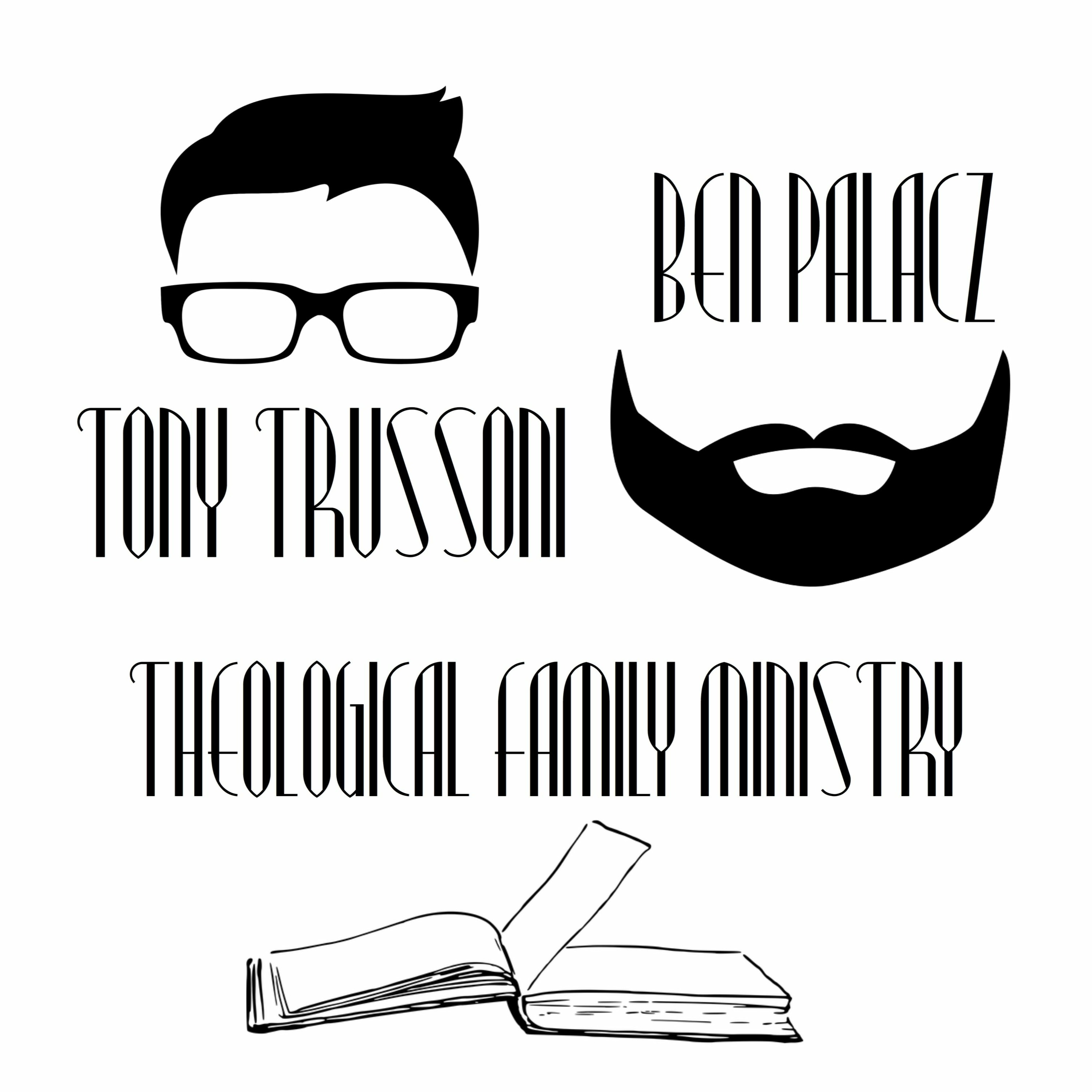
Theological Family MinistryLaw & Gospel with our KidsIn this new episode of TFM Pastors Tony & Ben talk about how we teach children about God's law and God's gospel. Listen in to this discussion that is both relevant for today and truly timeless.
2020-03-1851 min
Oro - Profilo fiscale e normativoOro da investimento: patrimonializzare il capitale aziendale e indennità economiche aziendali (TFR TFM)Oggi vi voglio parlare dell’importanza dell’oro da investimento all‘interno della azienda e del suo bilancio.Patrimonializzare il valore dell’ azienda o l'utile aziendale in un bene concreto e fisico come l Oro, esente IVA e senza costi annuali di manutenzione o tasse ricorrenti (es. IMU), immediatamente liquidabile ed accettato in oltre 160 Paesi potrebbe essere una buona opportunità per l'azienda e per l'imprenditore.É un ottimo strumento per consolidare il capitale aziendale ed aumentarne il valore economico sfruttando la rivalutazione dell'Oro fisico nel tempo. L'Oro fisico da investimento vi ricordo che è una commodity ossia una merce...
2020-03-0504 min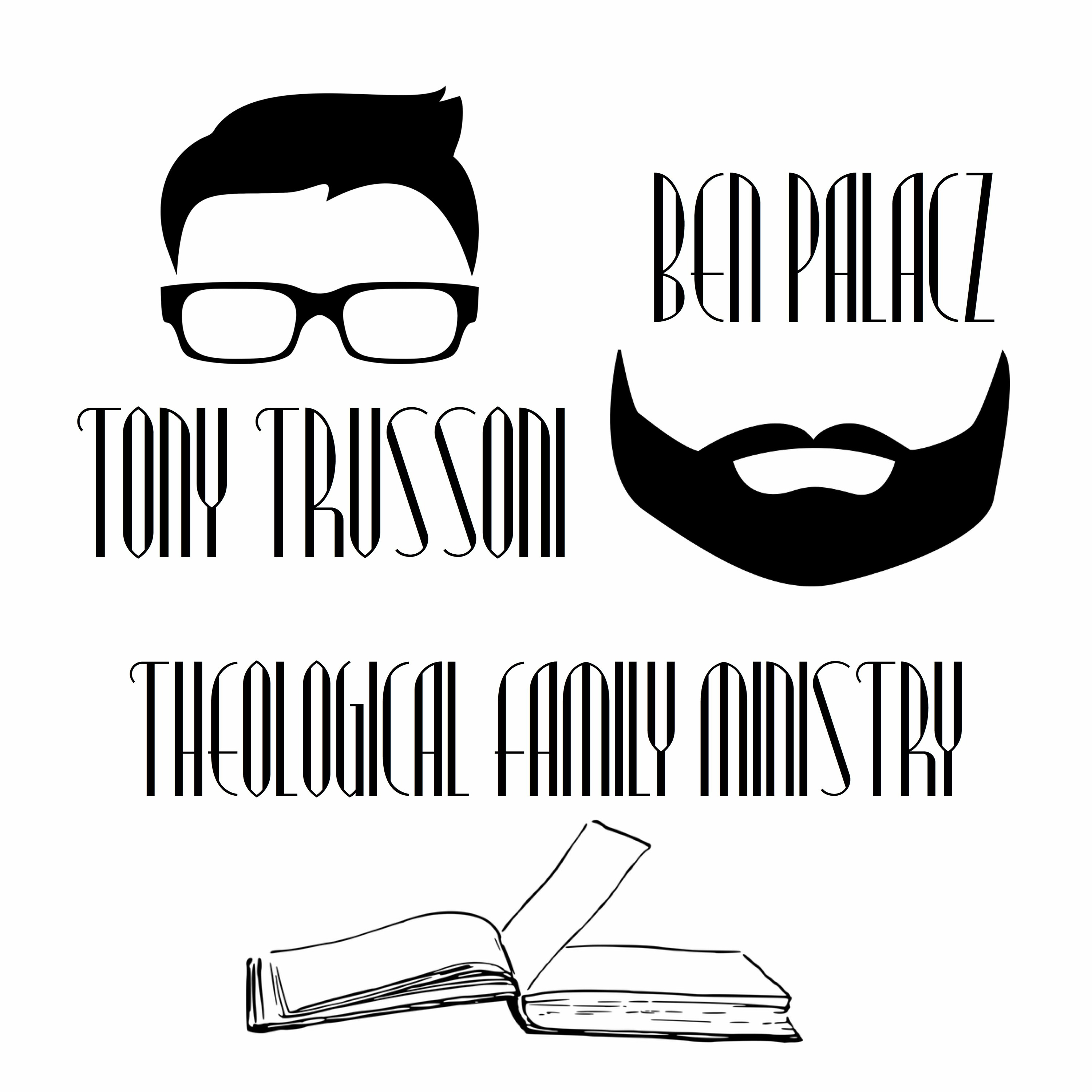
Theological Family MinistrySowing Seeds with Jason Houser of Seeds Family WorshipIn this episode of the TFM Podcast, Tony & Ben discuss with Jason Houser, founder of Seeds Family Worship, about family discipleship and using music as a tool to get God's Word into homes and hearts. Opening music credit: "Impress Them (Deuteronomy 6:4-7)", courtesy of Seeds Family Worship.
2020-02-1956 min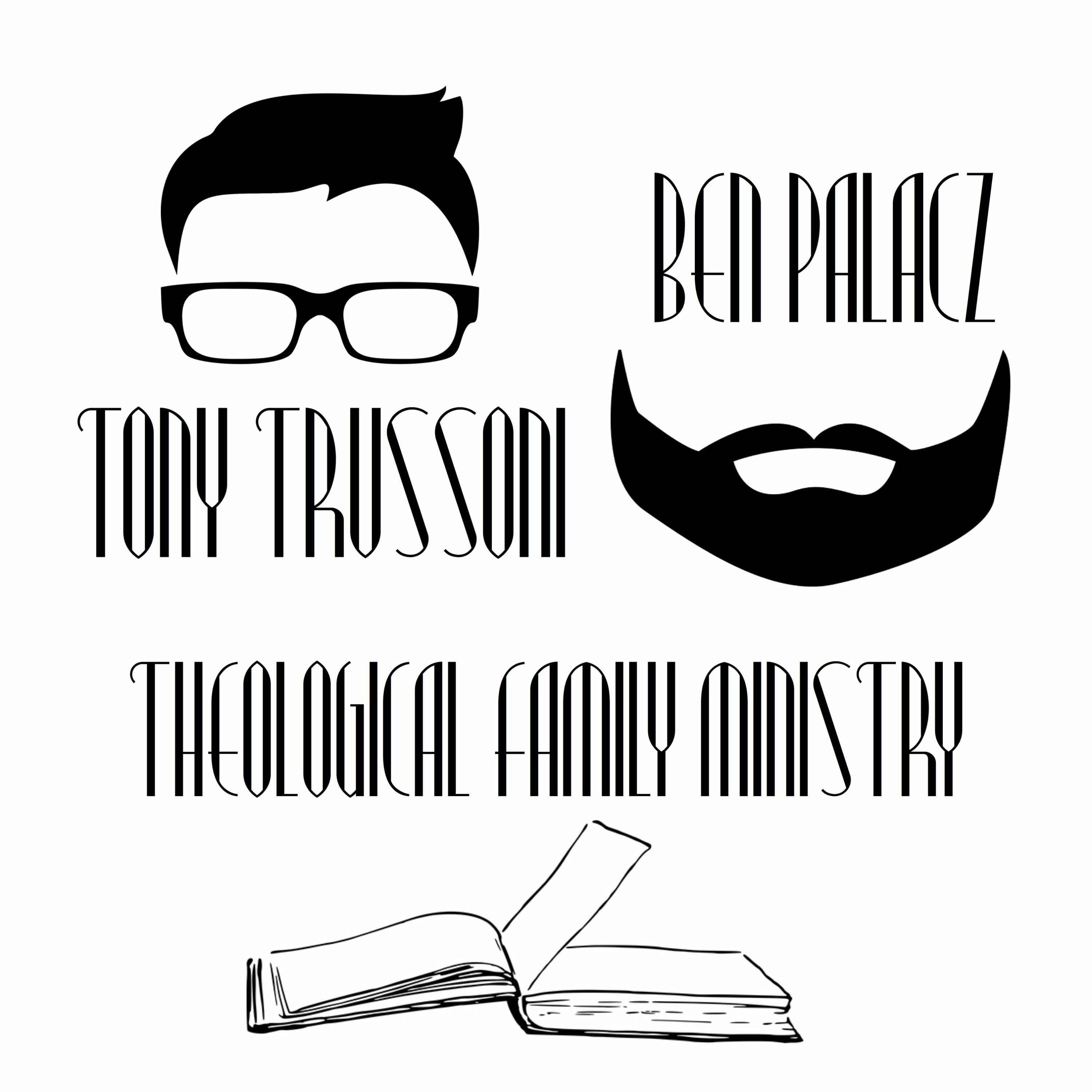
Theological Family MinistryDivorce and the Modern FamilyIn this episode of TFM Pastors Tony and Ben talk about a theology of divorce, what the Bible allows, and how to teach young people about this topic.
2020-02-0550 min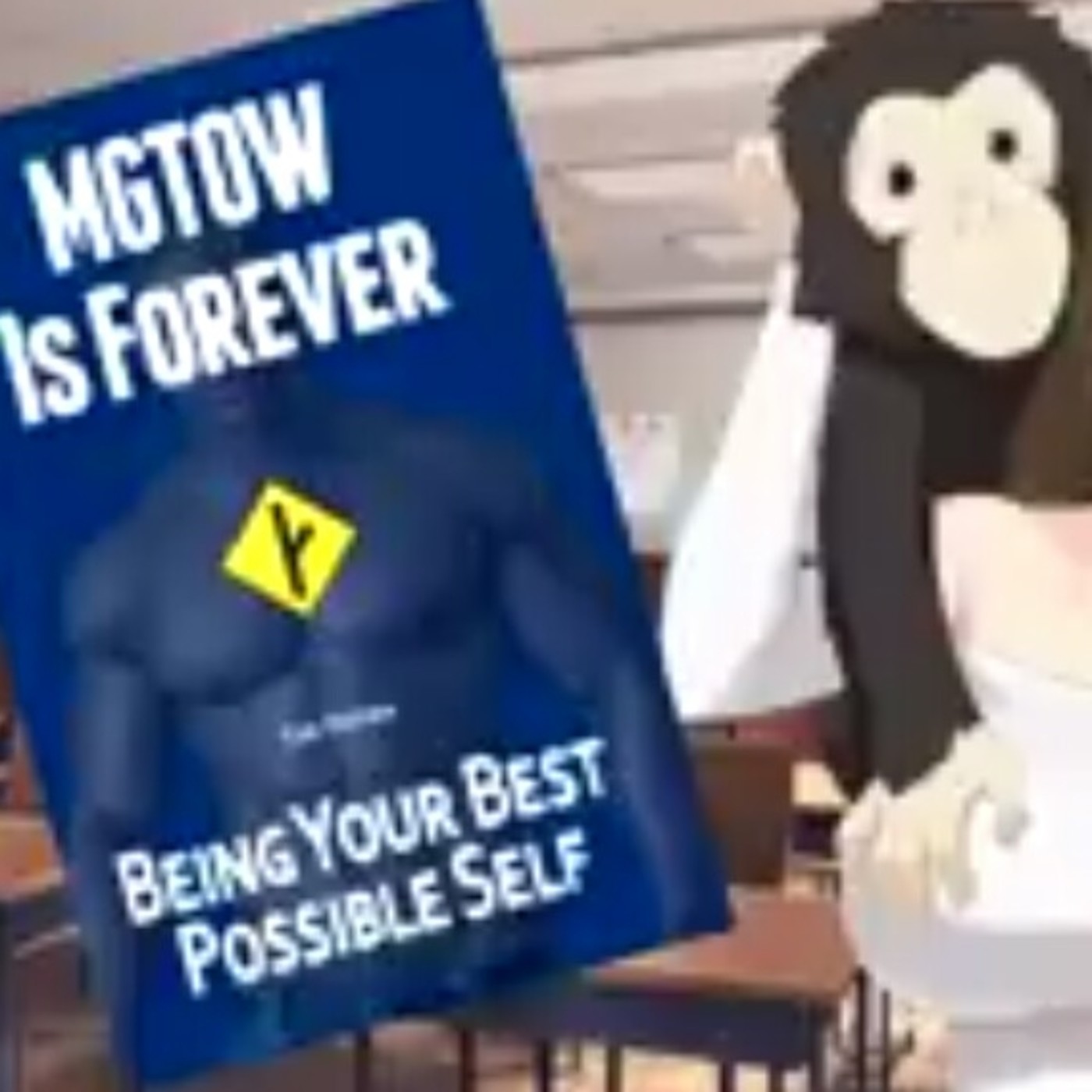
TFM Turd Flinging Monkey Classic Enemies Of Men MGtfm me 3 20 Book Review: MGTOW Is Forever (Sponsored).mp3tfm me 3 20 Book Review: MGTOW Is Forever (Sponsored).mp3
tfm me 3 20 Book Review: MGTOW Is Forever (Sponsored).mp3
tfm me 3 20 Book Review: MGTOW Is Forever (Sponsored).mp3
2020-01-2224 minTheological Family MinistryHelping Little People Fight “Little” SinsIn this episode of TFM Pastors Ben & Tony talk about how we sometimes make a small deal of "little" sins in our families and ministries and how we can help the next generations fight the respectable sins.
2020-01-1553 min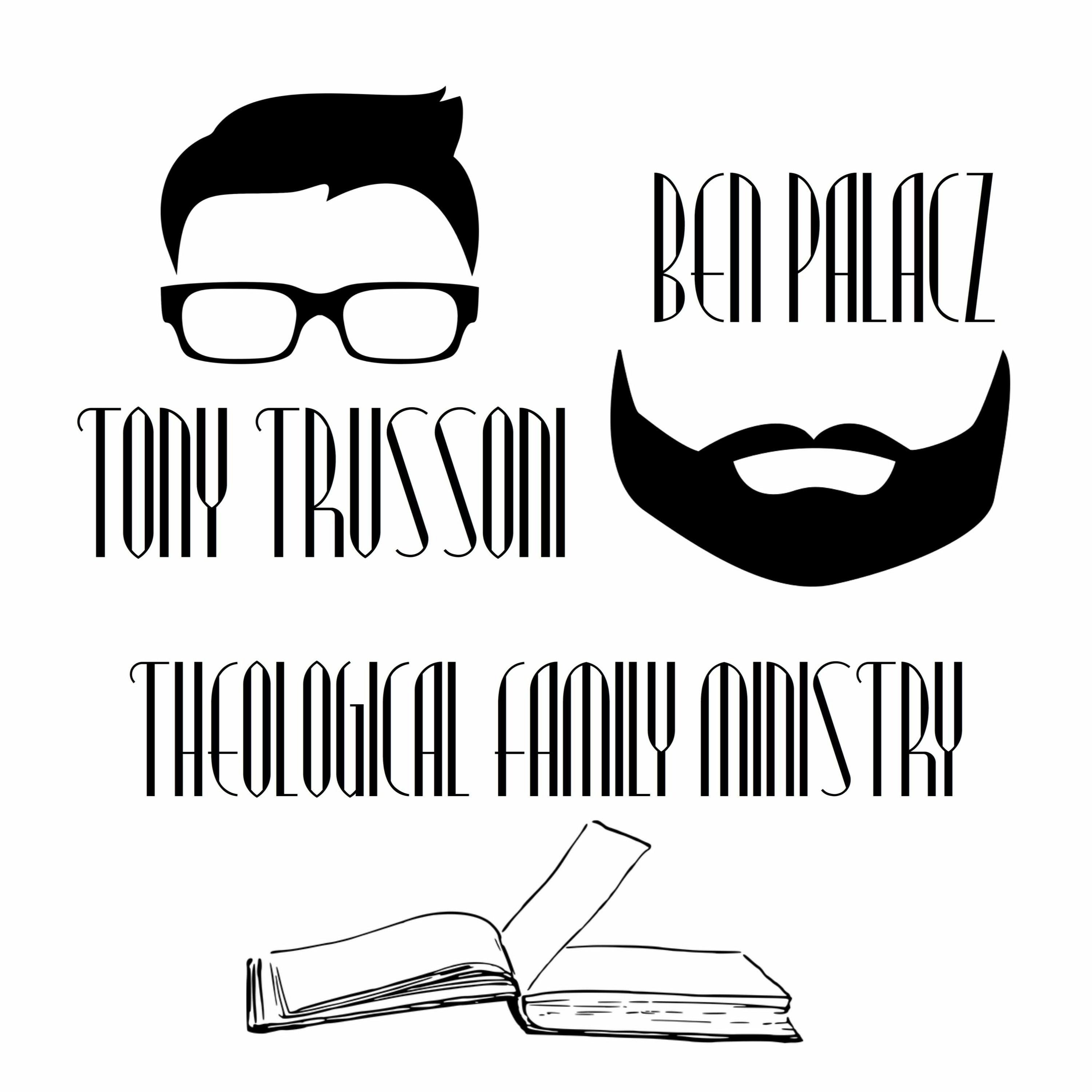
Theological Family MinistryTrain Yourself for GodlinessIn this episode of TFM Pastors Ben & Tony talk about personal spiritual disciplines in the lives of our kids and youth. Listen and be blessed.
2020-01-0144 min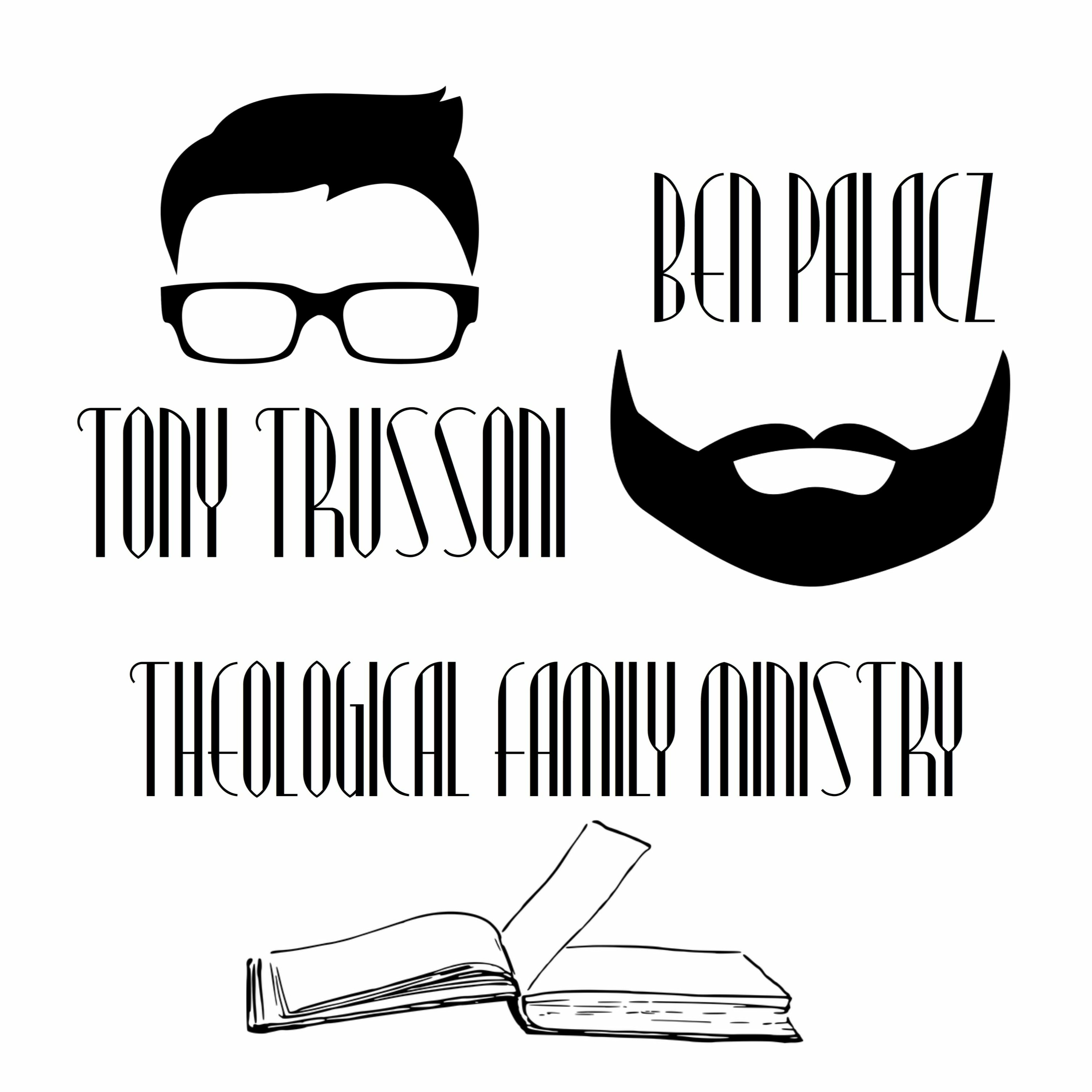
Theological Family MinistryTFM Classic: TFM Christmas SpecialIn this classic episode of TFM from year one Pastors Ben & Tony talk about Christmas traditions and even advent from a Biblical and Theological framework.
2019-12-1830 min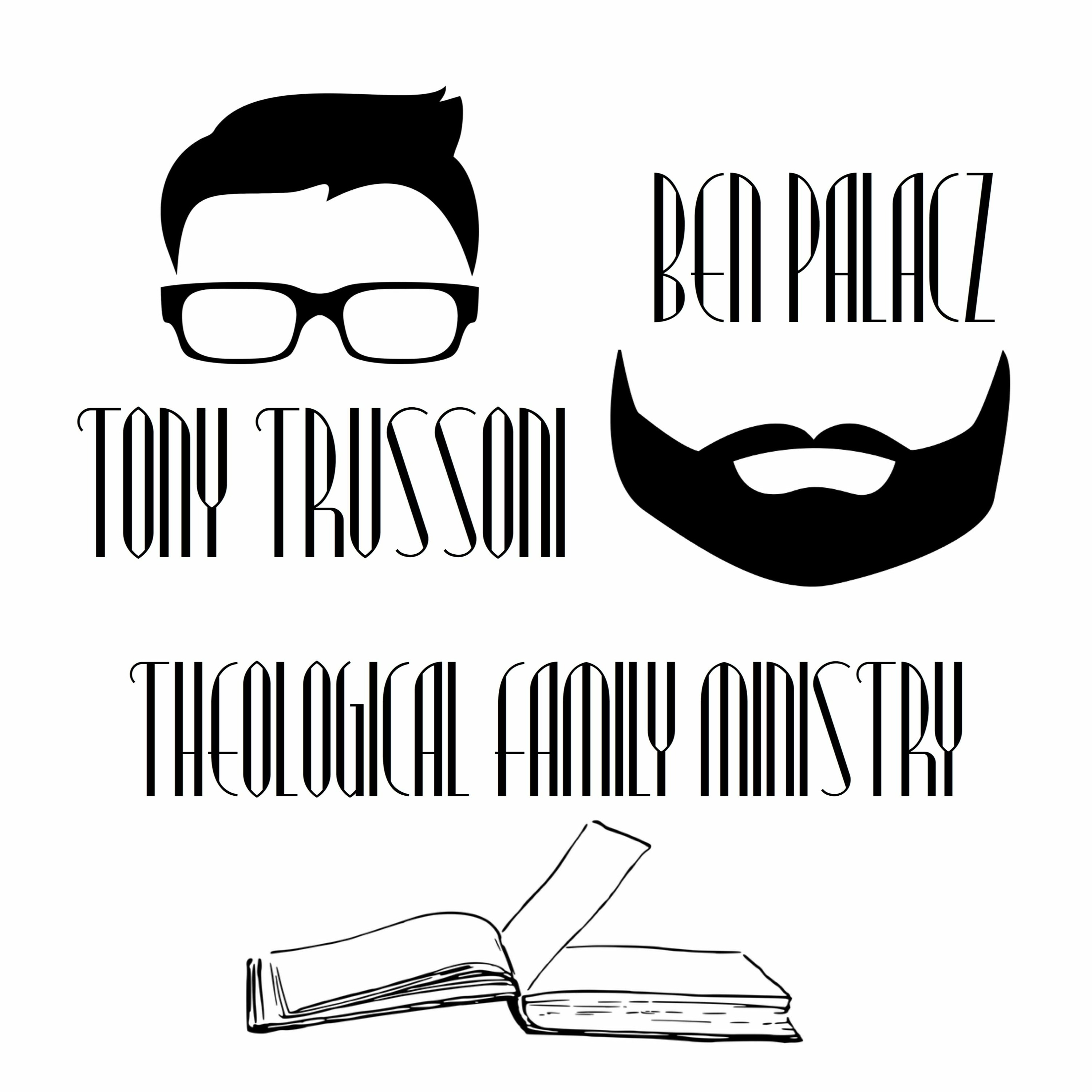
Theological Family MinistrySanta’s Salvation w/ Simon CamilleriIn this episode of TFM Pastors Tony & Ben talk with Simon Camilleri about his book when Santa Learned the Gospel and what the common Santa message teaches our children. Whether you are gearing up for the holiday in the northern or southern hemisphere this will be a helpful discussion. Featuring music by Bruce Springsteen.
2019-12-0448 min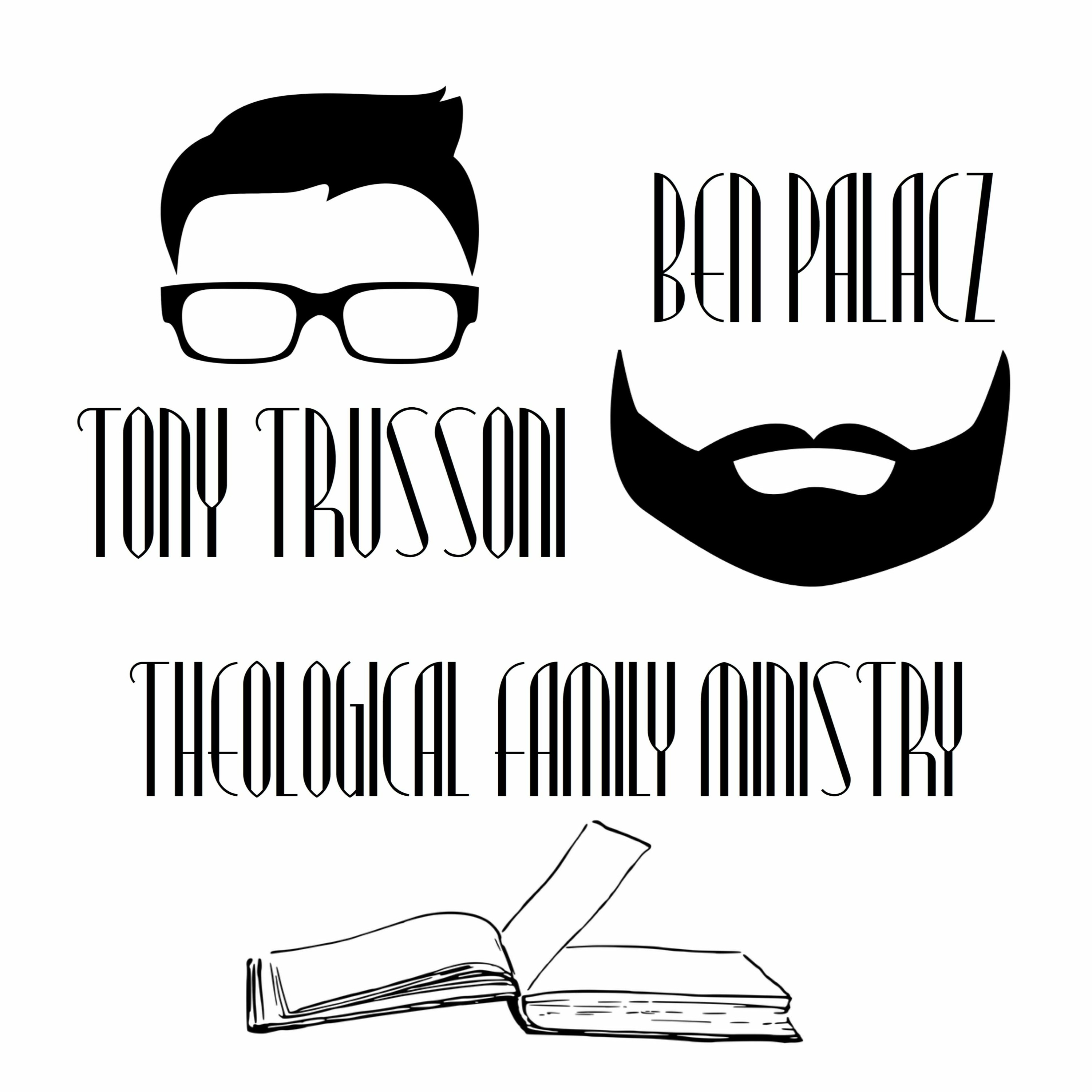
Theological Family MinistryChurch History for Kids & Youth/ with Dr. W. Brian SheltonIn this episode of TFM Pastors Tony and Ben reconnect with Dr. W. Brian Shelton and talk about the importance of church history for family discipleship.
2019-11-2143 min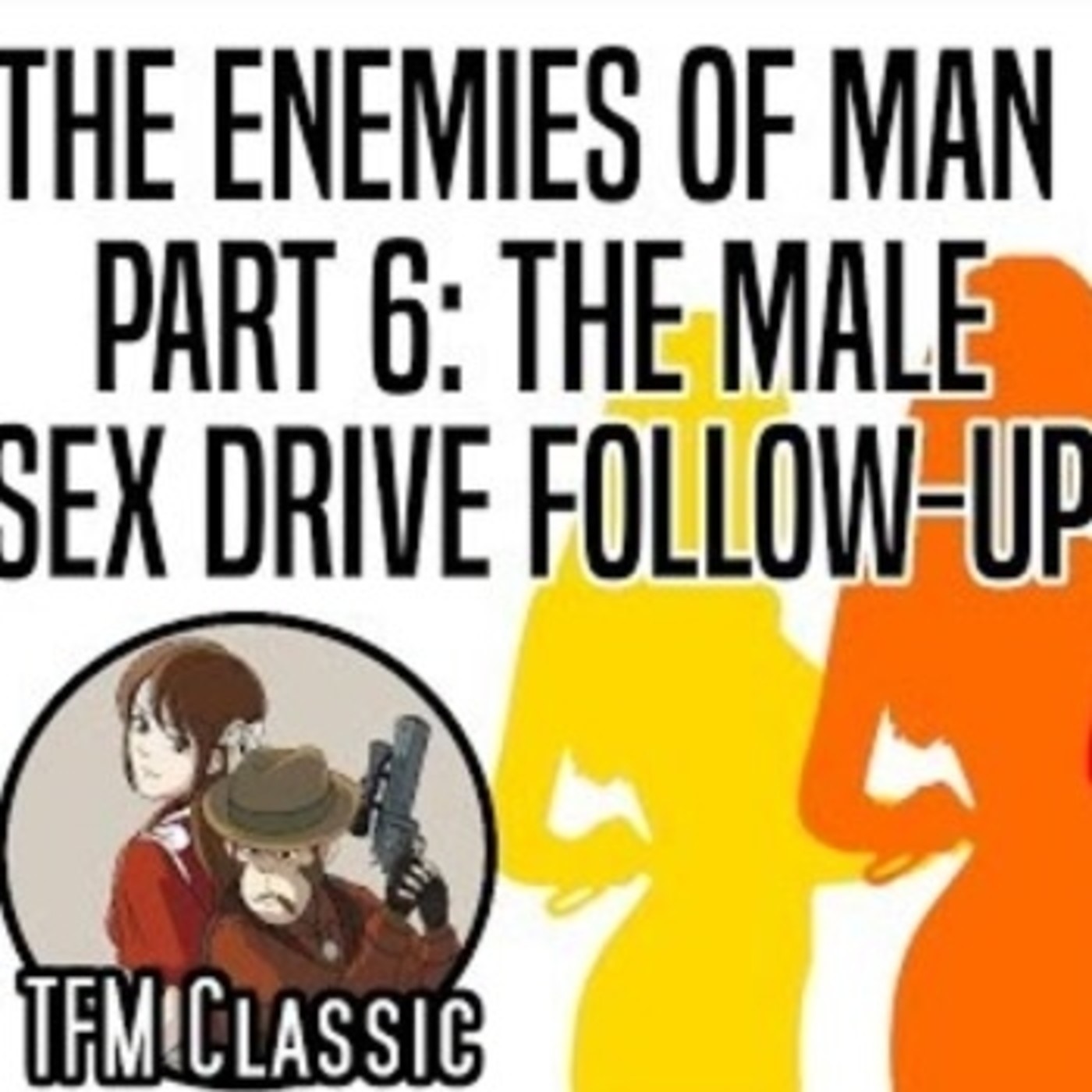
TFM Turd Flinging Monkey Classic Enemies Of Men MGPart 6 Male Sex Drive Follow Up TFM Classic Enemies of Men Series cap 6 mgtow basics che morpheus obstinator utopiansub spanish https://ar.ivoox.com/es/tfm-impulso-sexual-masculino-vs-femenino-mgtow-sub-audios-mp3_rf_44370940_1.html
Turd Flinging Monkey
Turd Flinging Monkey TFM
Main Channel (Turd Flinging Monkey): https://www.youtube.com/user/MorgueToeTag Bitchute Account: https://www.bitchute.com/channel/SdA7JwX9dfhl/ MGTOW.TV: https://www.mgtow.tv/@TFMonkey DLive.TV: https://dlive.tv/TF
celest420 https://www.youtube.com/channel/UClRIx5Yp0CZTCJz7PshfwEA/playlists
Input #0, mp3, from 'the-enemies-of-man-part-3-ego2216v3.mp3':
Metadata:
major_brand : mp42
minor_version : 0
compatible_brands: isommp42
title : The Enemies of Man: Part 3: Ego
comment : Social Media Links:
: SubscribeStar: https://www.subscribestar.com/tfmonkey
: Patreon: https://www.patreon...
2019-11-1616 min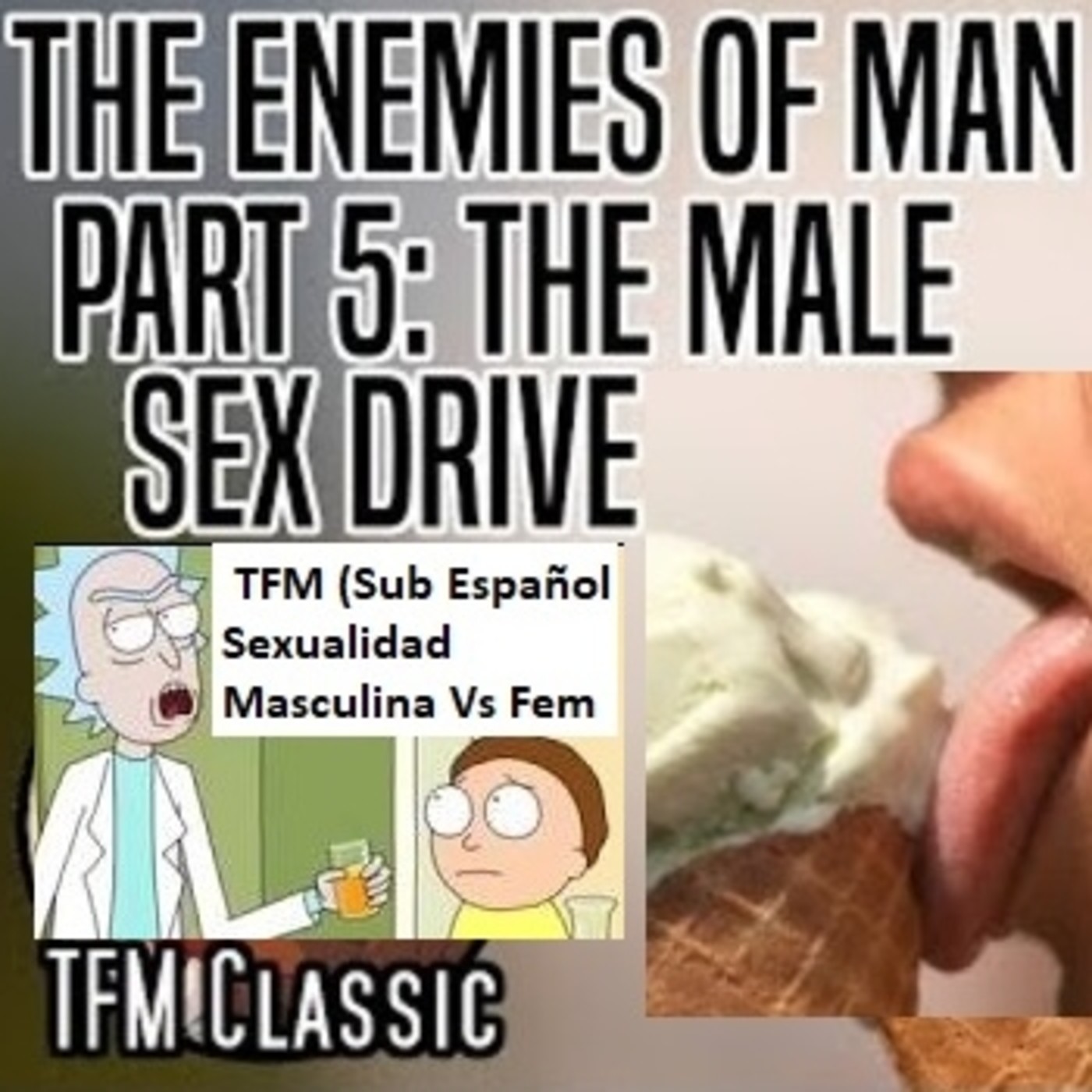
TFM Turd Flinging Monkey Classic Enemies Of Men MGPart 5 AAA+ Male Sex Drive TFM Classic Enemies of Men Series cap 5 mgtow basics Neo Oculorum misandria.orgsub spanish https://ar.ivoox.com/es/tfm-impulso-sexual-masculino-vs-femenino-mgtow-sub-audios-mp3_rf_44370940_1.html
subtitular este ¿ ? https://www.youtube.com/watch?v=N8jZgccIaok
Liberation Y : Non-Player Characters; Emotional Entrapment in the Matrix.
google serach ( Turd Flinging Monkey Enemies of Man cap) bitchute
Turd Flinging Monkey
Turd Flinging Monkey TFM
(ID3 TAG en MP3 bajados de bitchute con https://www.onlinevideoconverter.com/es/youtube-converter el MP3 resultante contiene ID3 tags con una imagen de portada del video) se puede ver bajando el mp3 en un reproductor que soporte mostrar la imagen...
Main Channel (Turd Flinging Monkey): https://www.youtube.com/user/MorgueToeTag Bitchute Account: h...
2019-11-1622 min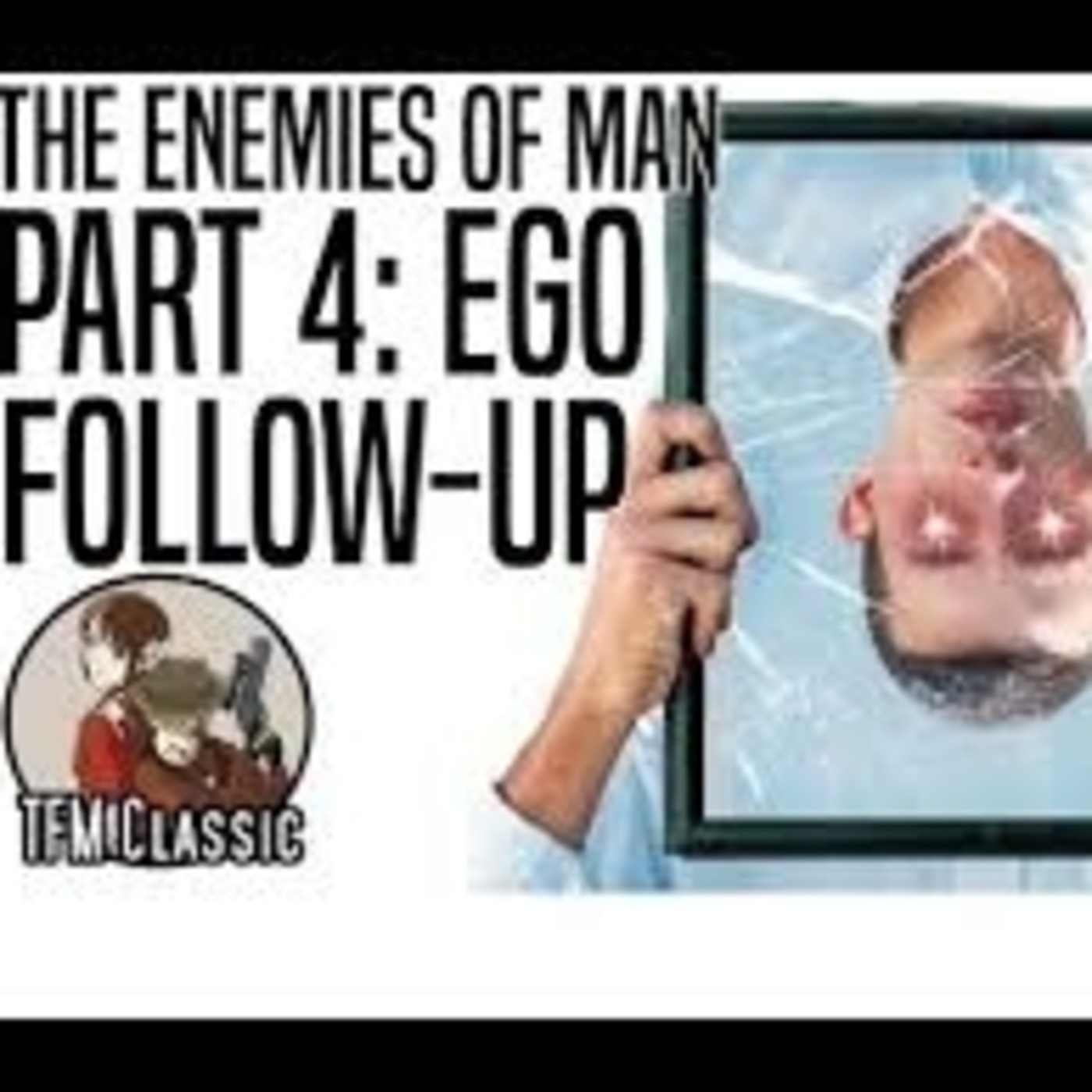
TFM Turd Flinging Monkey Classic Enemies Of Men MGPart 4 Ego Follow Up TFM Classic Enemies of Men Series cap 4 mgtow basicsTurd Flinging Monkey
Turd Flinging Monkey TFM
Main Channel (Turd Flinging Monkey): https://www.youtube.com/user/MorgueToeTag Bitchute Account: https://www.bitchute.com/channel/SdA7JwX9dfhl/ MGTOW.TV: https://www.mgtow.tv/@TFMonkey DLive.TV: https://dlive.tv/TF
celest420 https://www.youtube.com/channel/UClRIx5Yp0CZTCJz7PshfwEA/playlists
Input #0, mp3, from 'the-enemies-of-man-part-3-ego2216v3.mp3':
Metadata:
major_brand : mp42
minor_version : 0
compatible_brands: isommp42
title : The Enemies of Man: Part 3: Ego
comment : Social Media Links:
: SubscribeStar: https://www.subscribestar.com/tfmonkey
: Patreon: https://www.patreon.com/turdflingingmonkey
: DLive: https://dlive.tv/TFMonkey
: Alternate YouTube Channel...
2019-11-1620 min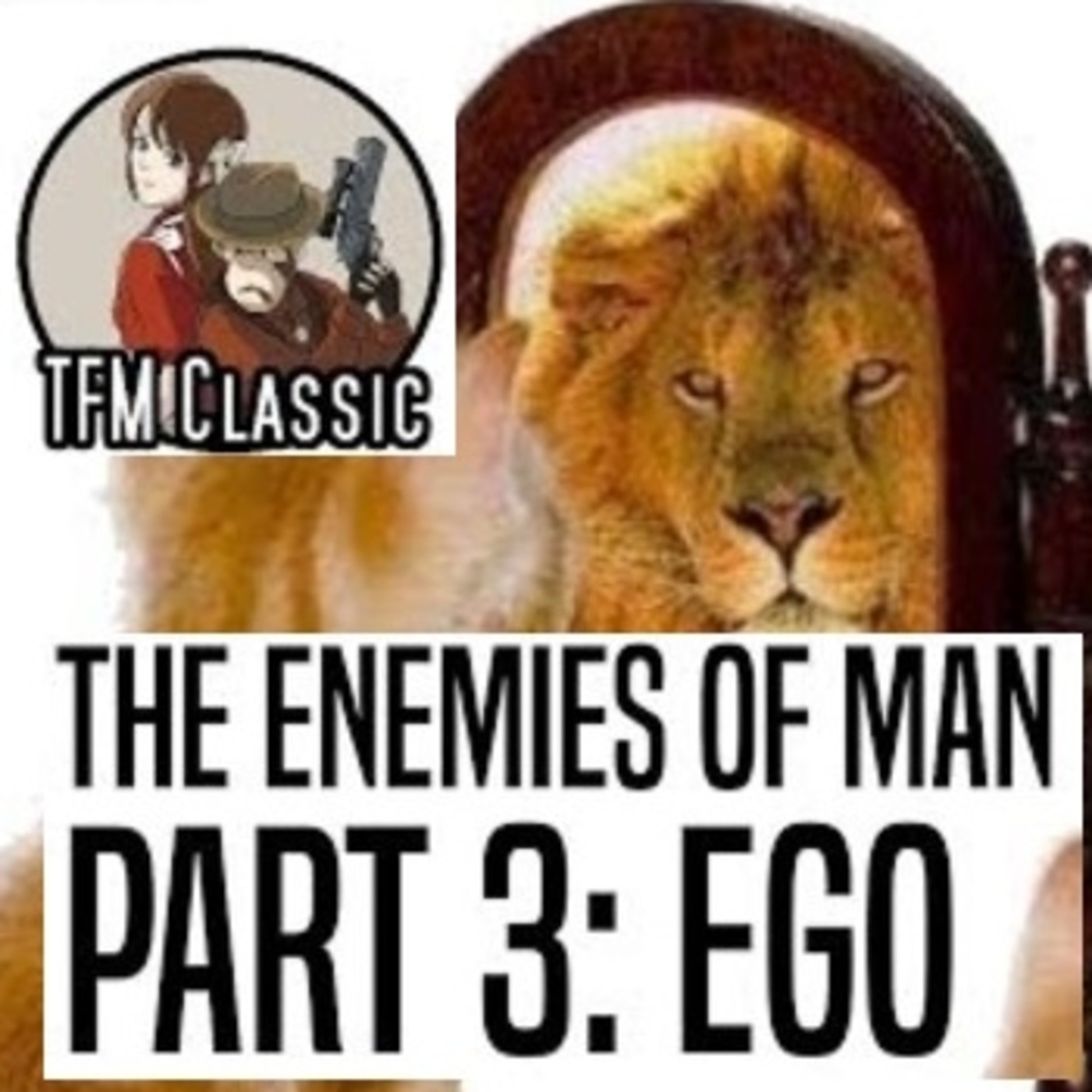
TFM Turd Flinging Monkey Classic Enemies Of Men MGPart 3 Ego TFM Classic Enemies of Men Series cap 3 mgtow basicsTurd Flinging Monkey
Turd Flinging Monkey
Turd Flinging Monkey
Turd Flinging Monkey
Turd Flinging MonkeyTurd Flinging MonkeyTurd Flinging MonkeyTurd Flinging MonkeyTurd Flinging MonkeyTurd Flinging MonkeyTurd Flinging Monkey
Main Channel (Turd Flinging Monkey): https://www.youtube.com/user/MorgueToeTag Bitchute Account: https://www.bitchute.com/channel/SdA7JwX9dfhl/ MGTOW.TV: https://www.mgtow.tv/@TFMonkey DLive.TV: https://dlive.tv/TF
celest420 https://www.youtube.com/channel/UClRIx5Yp0CZTCJz7PshfwEA/playlists
Input #0, mp3, from 'the-enemies-of-man-part-3-ego2216v3.mp3':
Metadata:
major_brand : mp42
minor_version : 0
compatible_brands: isommp42
title : The Enemies of Man: Part 3: Ego
comment : Social Media Links:
...
2019-11-1612 minTheological Family MinistryMust Men Be Toxic?: Raising Men with Ron RuddIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk with Pastor Ron Rudd of the Metropolitan Bible Church in Ottawa about how we raise boys into Godly men rather than passive men or toxic men. You don't want to miss this one.
2019-11-0647 min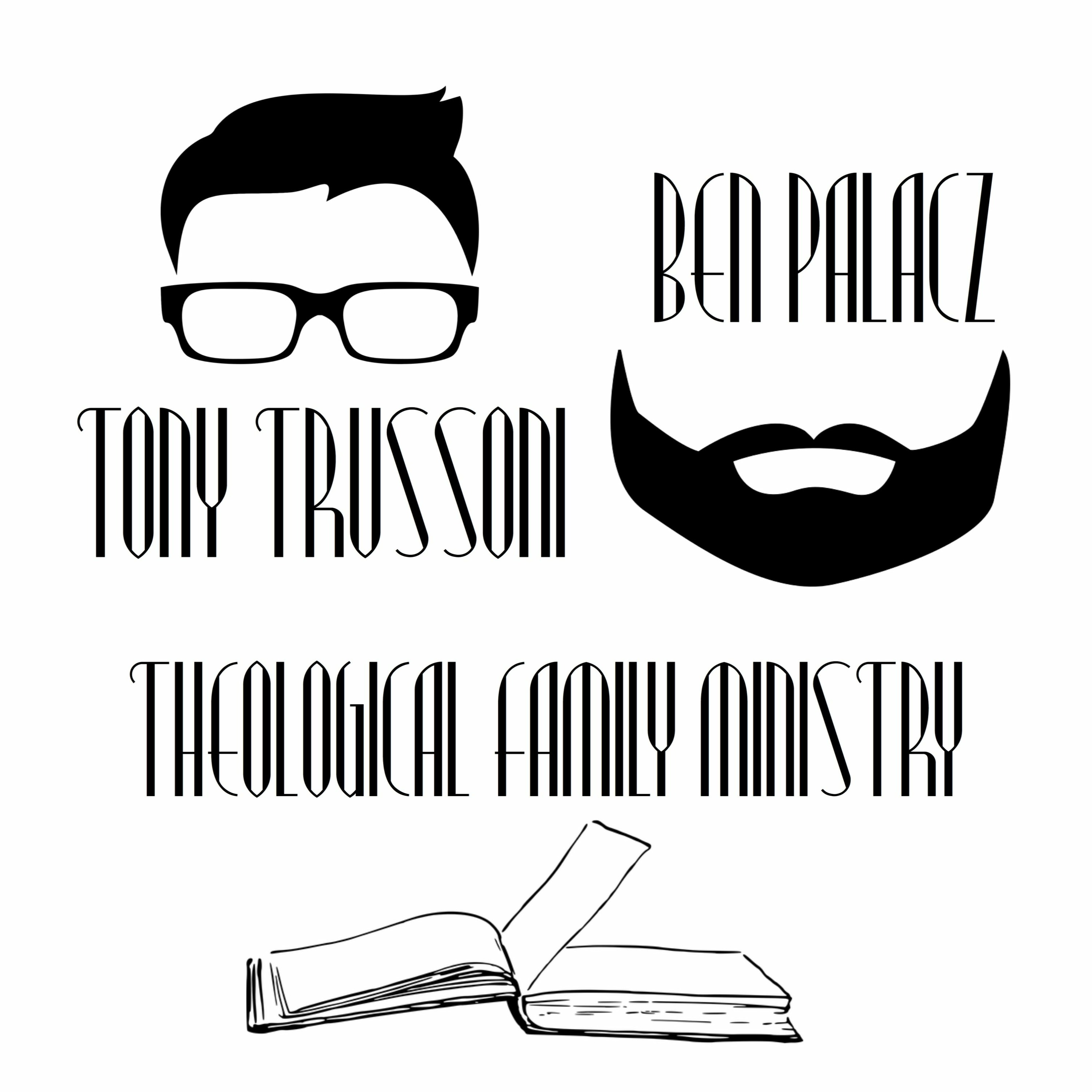
Theological Family MinistryCan We Have Fun at Church?In this episode of TFM Pastors Ben & Tony have a fun talk about fun and it's place in the church. Listen and be blessed! It might even be fun.
2019-10-1641 min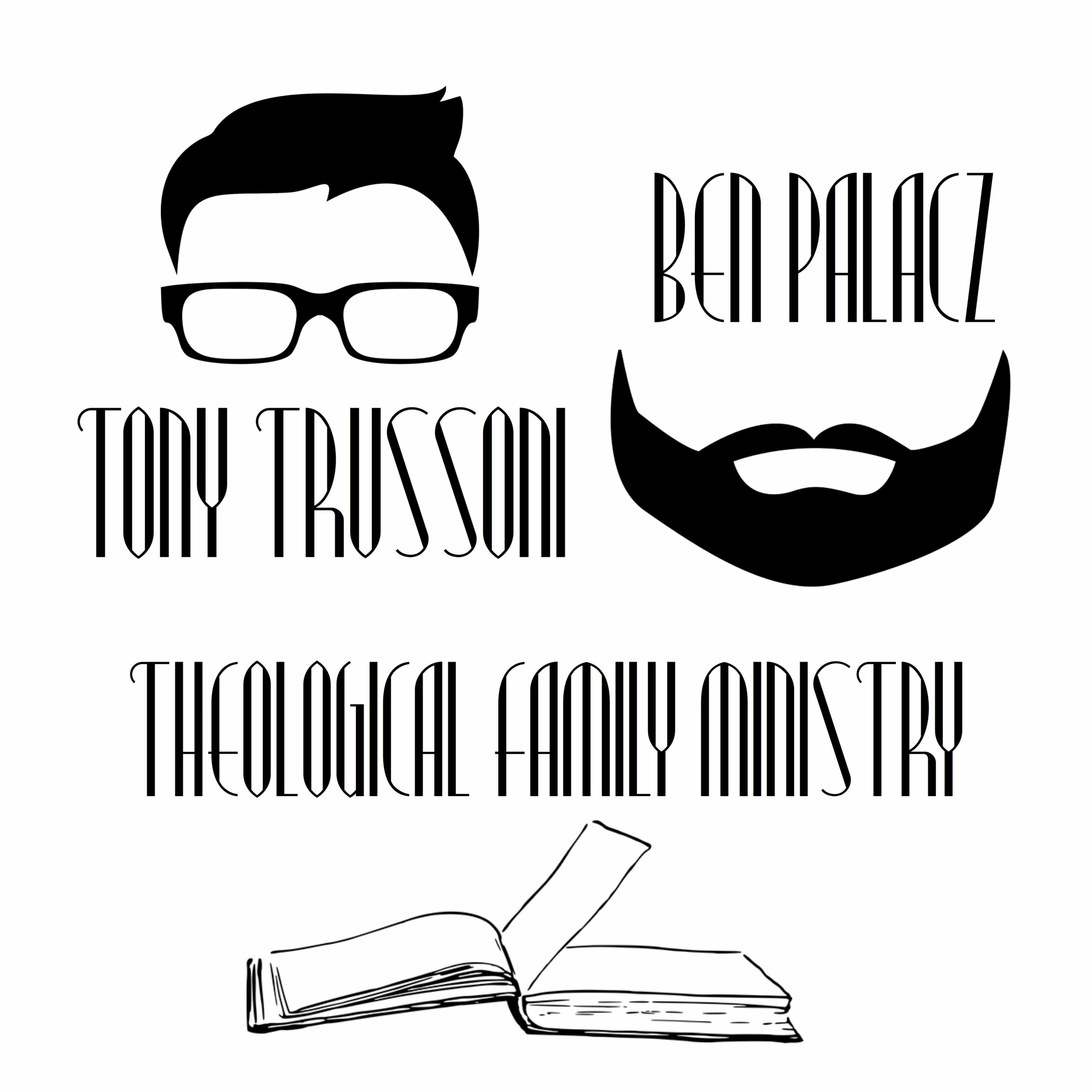
Theological Family Ministry"Who Are You Becoming?" w/ Dr. Dan EstesIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony interview Dr. Daniel Estes of Cedarville University about his book Hear, My Son and the importance of training our children in the fear of the Lord & wisdom.
2019-09-0435 min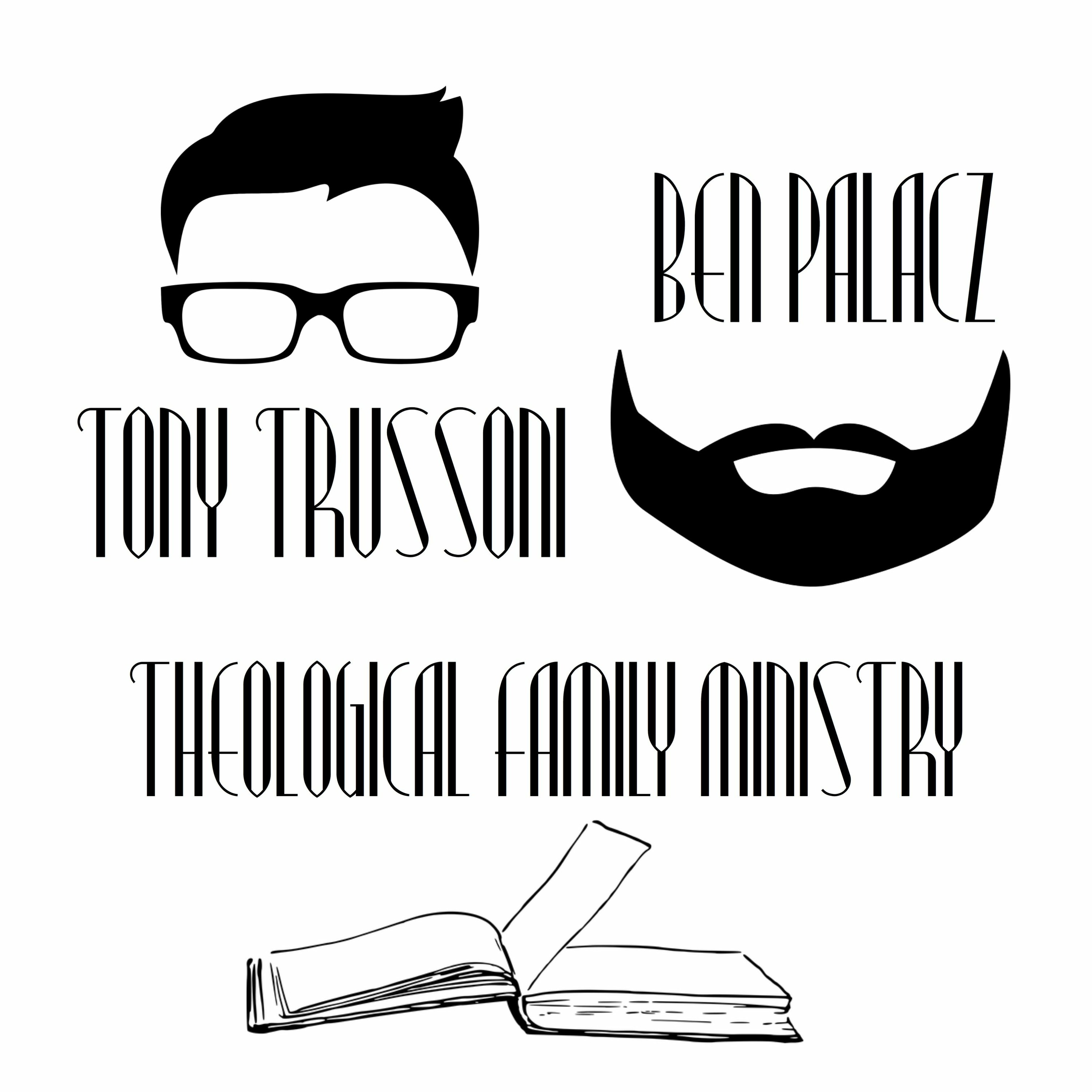
Theological Family MinistryBible Translations & Young People w/ Kevin BurrisIn this episode of the TFM Pastors Ben and Tony talk to Dr. Kevin Burris of Toccoa Falls College about Bible Translations and how it impacts our household Bible reading. Listen and be blessed!
2019-07-3139 min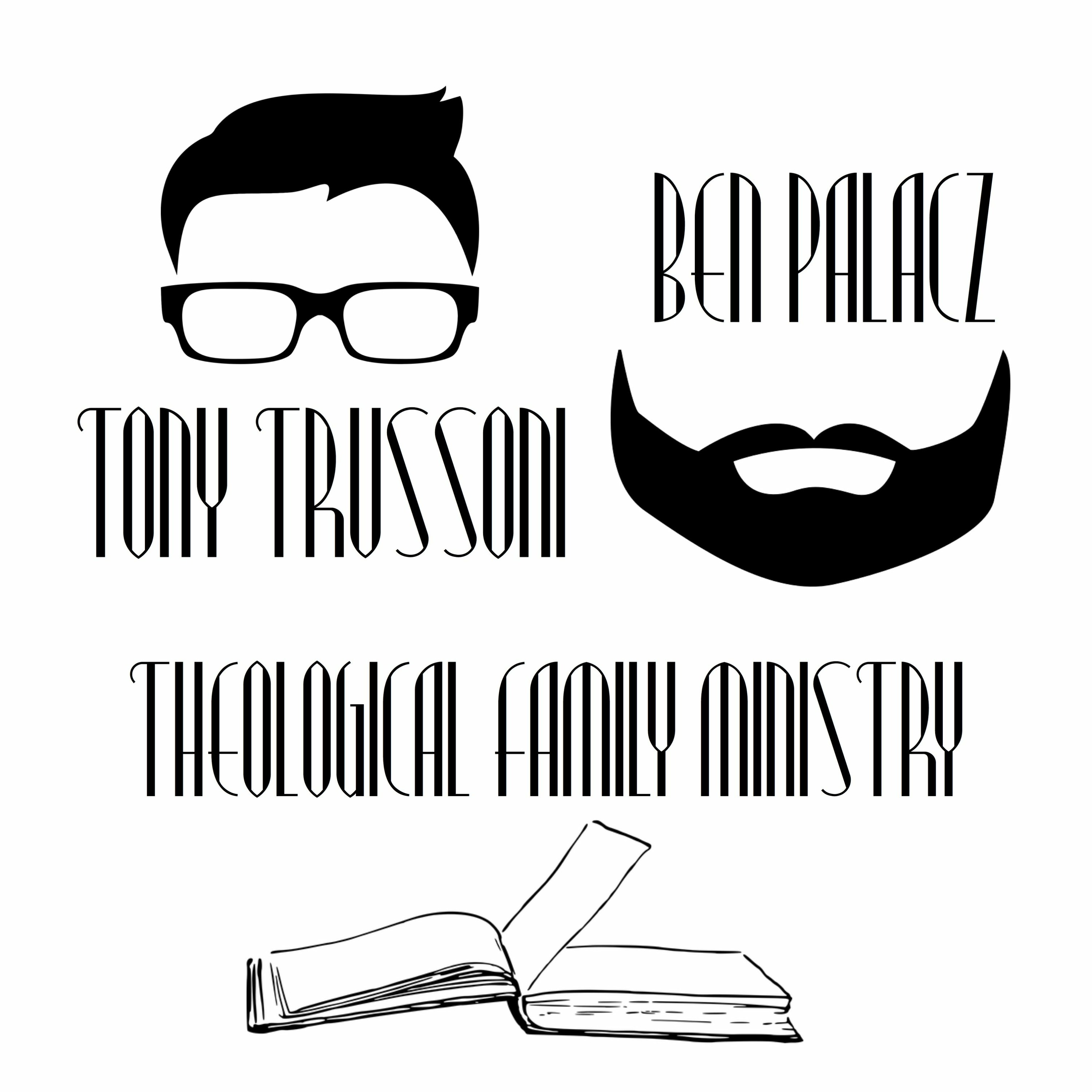
Theological Family MinistryFostering as Family Ministry with Tommy and Kelly SpeirsIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk to Tommy and Kelly Speirs about how Christian families can serve the Lord both through taking in foster children and supporting families who foster. Listen and be blessed,
2019-07-1742 min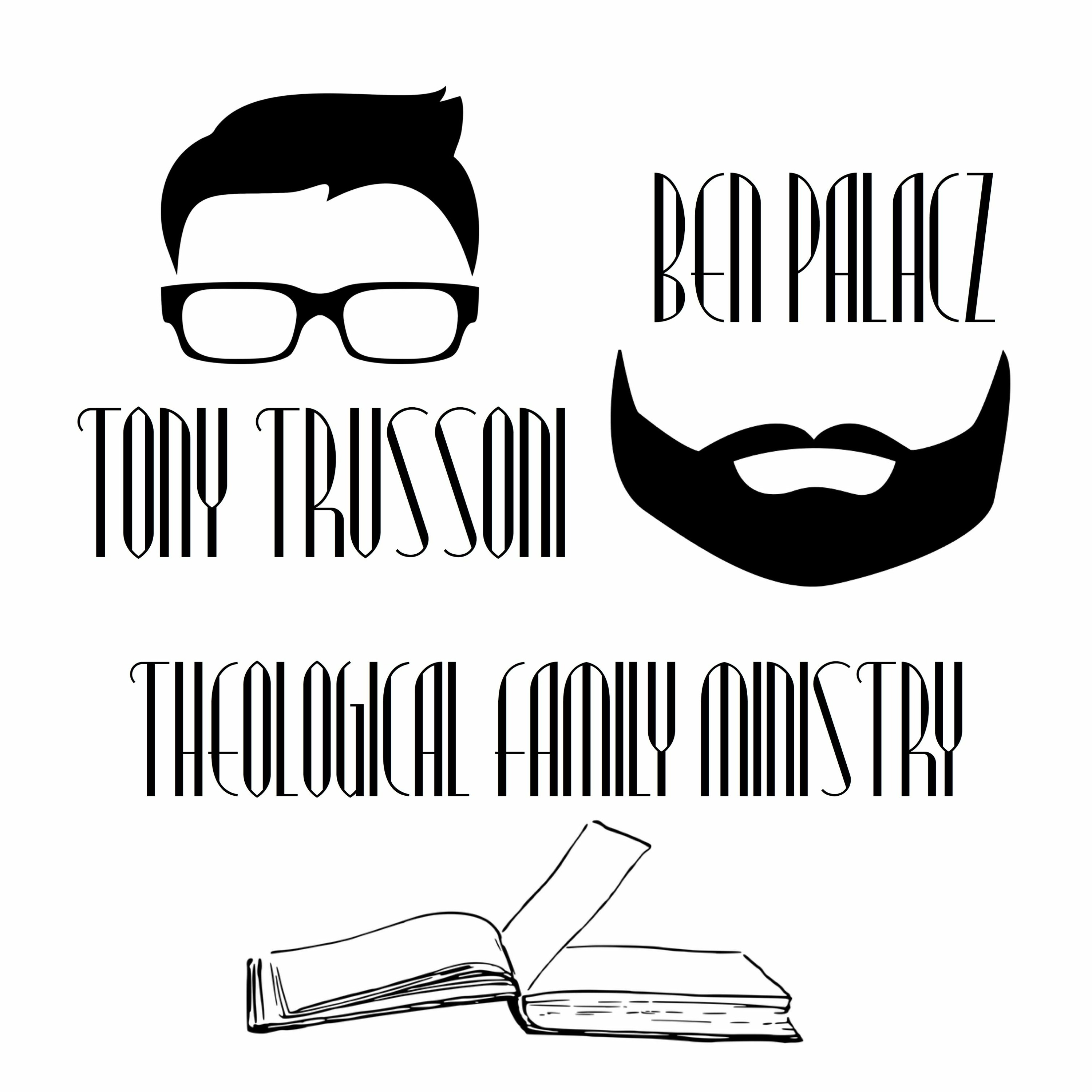
Theological Family MinistryWhen Mom and Dad Don’t DiscipleIn this episode of TFM Pastors Tony and Ben talk about the kids who's parents don't disciple them and the nontraditional parental figures that want to disciple.
2019-07-0342 min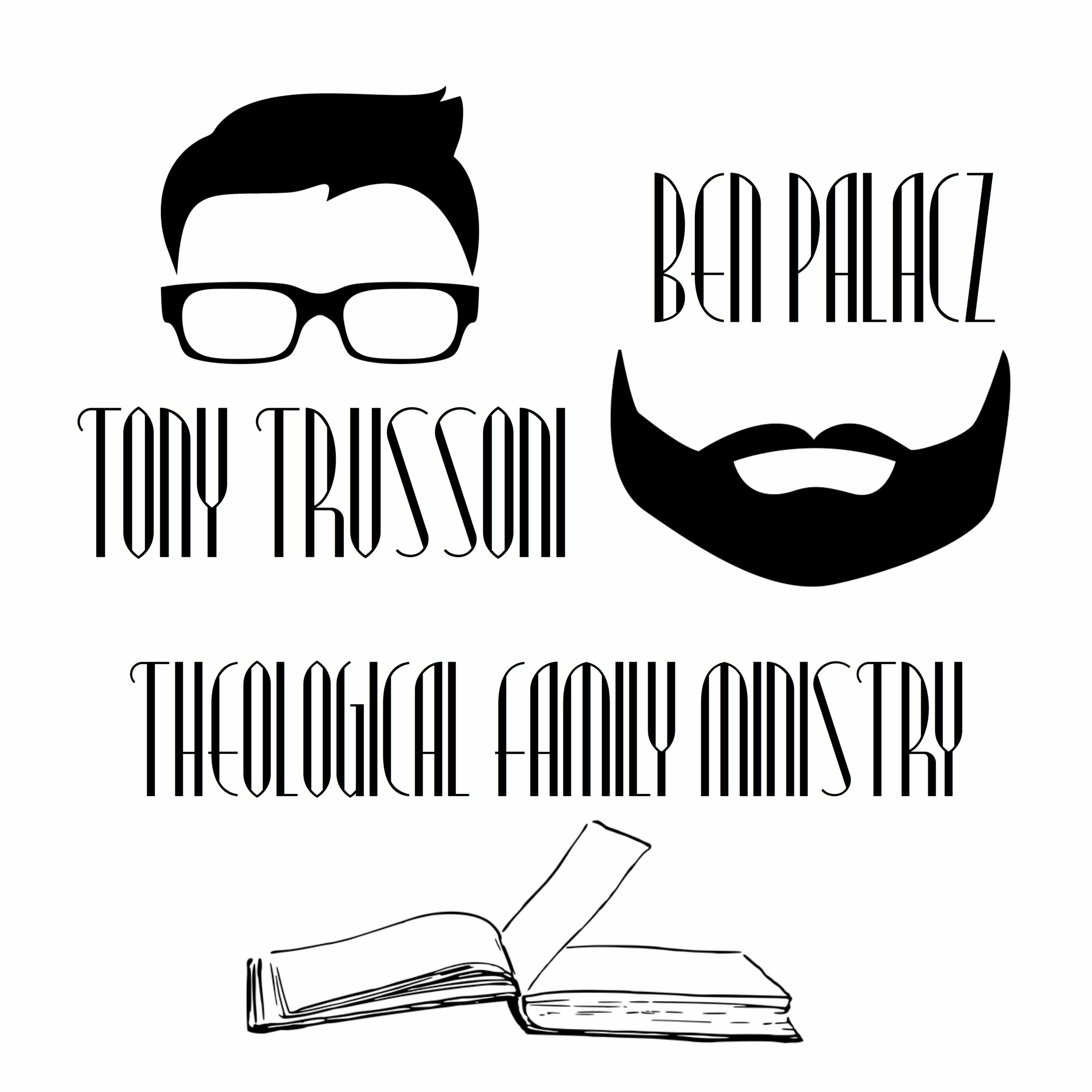
Theological Family MinistryTeaching Scripture Narratives in Age-Graded MinistryIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk about if and how we teach narrative in age-graded ministry. Featuring music from Reading Rainbow.
2019-06-1938 min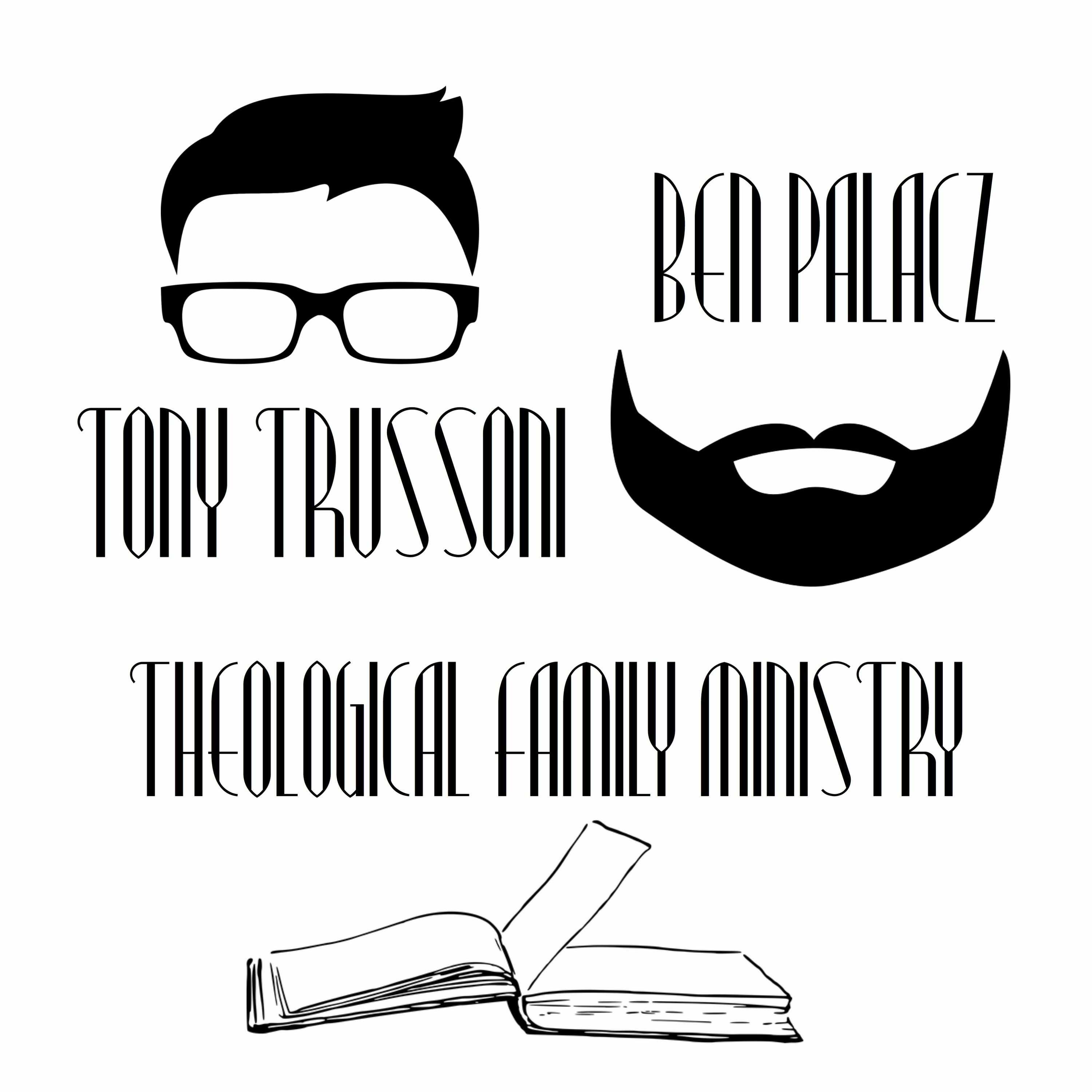
Theological Family MinistryChristians are Pro-KidsIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony discuss a Biblical understanding of a child's value. They dive into everything from abortion to what kids can teach us.
2019-06-0557 min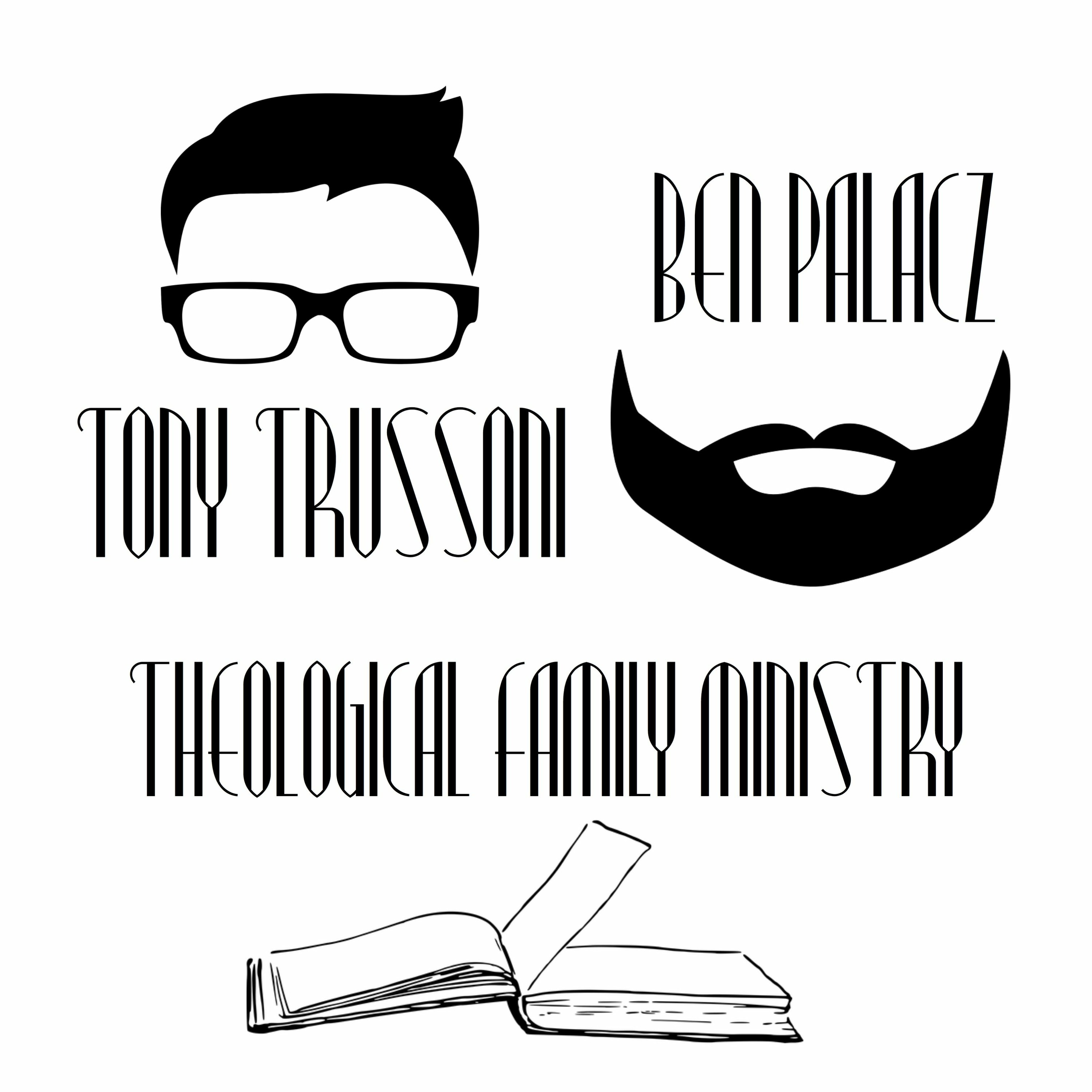
Theological Family MinistryScaring the Hell out of ThemIn this episode of TFM Pastors Tony and Ben talk about a Biblical understanding of hell and seek to answer how we navigate this topic with the next generations.
2019-05-1537 min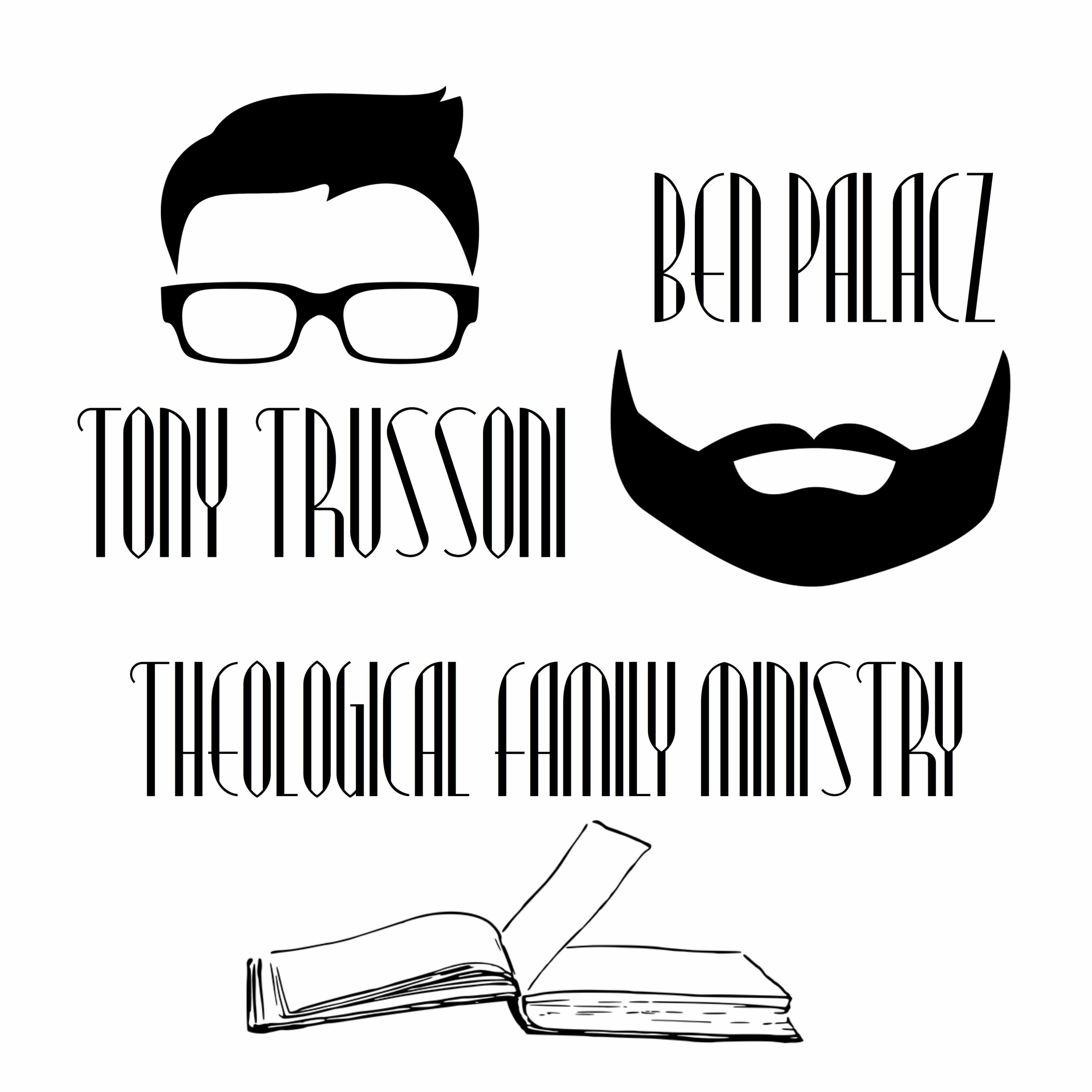
Theological Family MinistryWho's the Boss?In this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk about how children and teens can follow Christ as the Lord (or boss) of their lives. Listen and enjoy!
2019-05-0153 min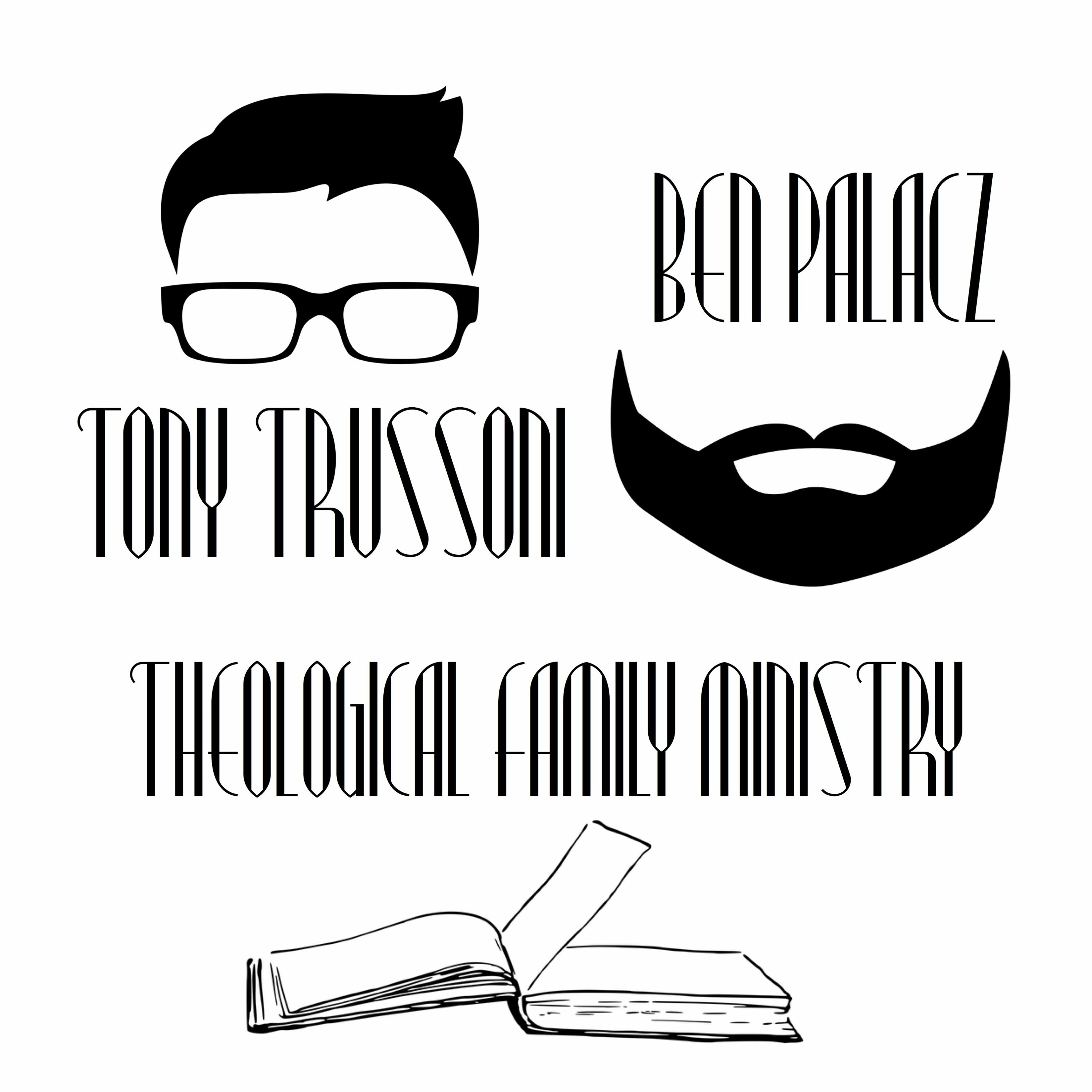
Theological Family MinistryToo Much of a Good ThingIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk about the danger of going too far in emphasizing parents as the primary disciplers of children and youth. Listen and be blessed!
2019-03-2029 min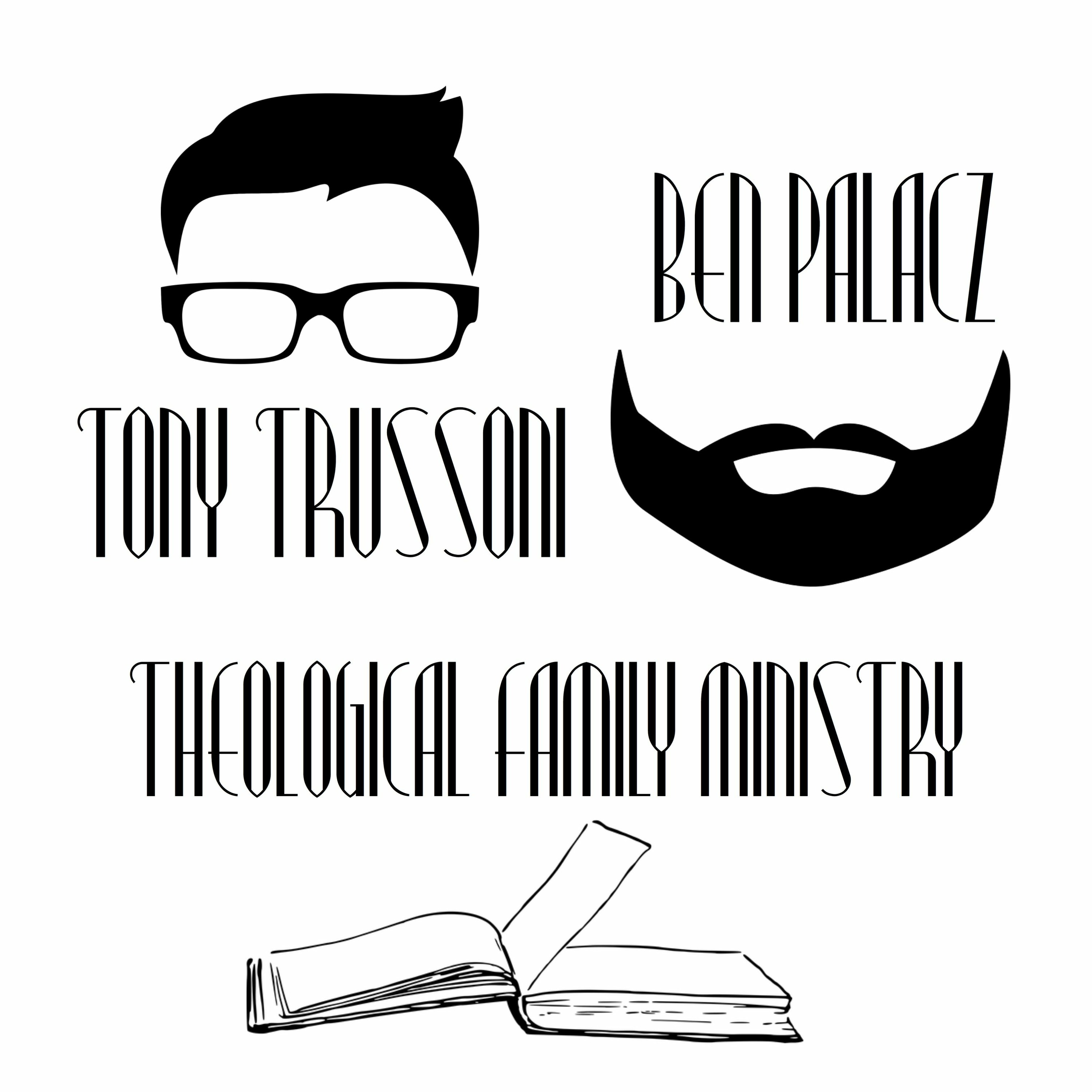
Theological Family MinistrySunday's Second HourIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk about the benefits and the dangers in Sunday School for Next Generations Ministry. Listen and Be Blessed.
2019-03-0647 min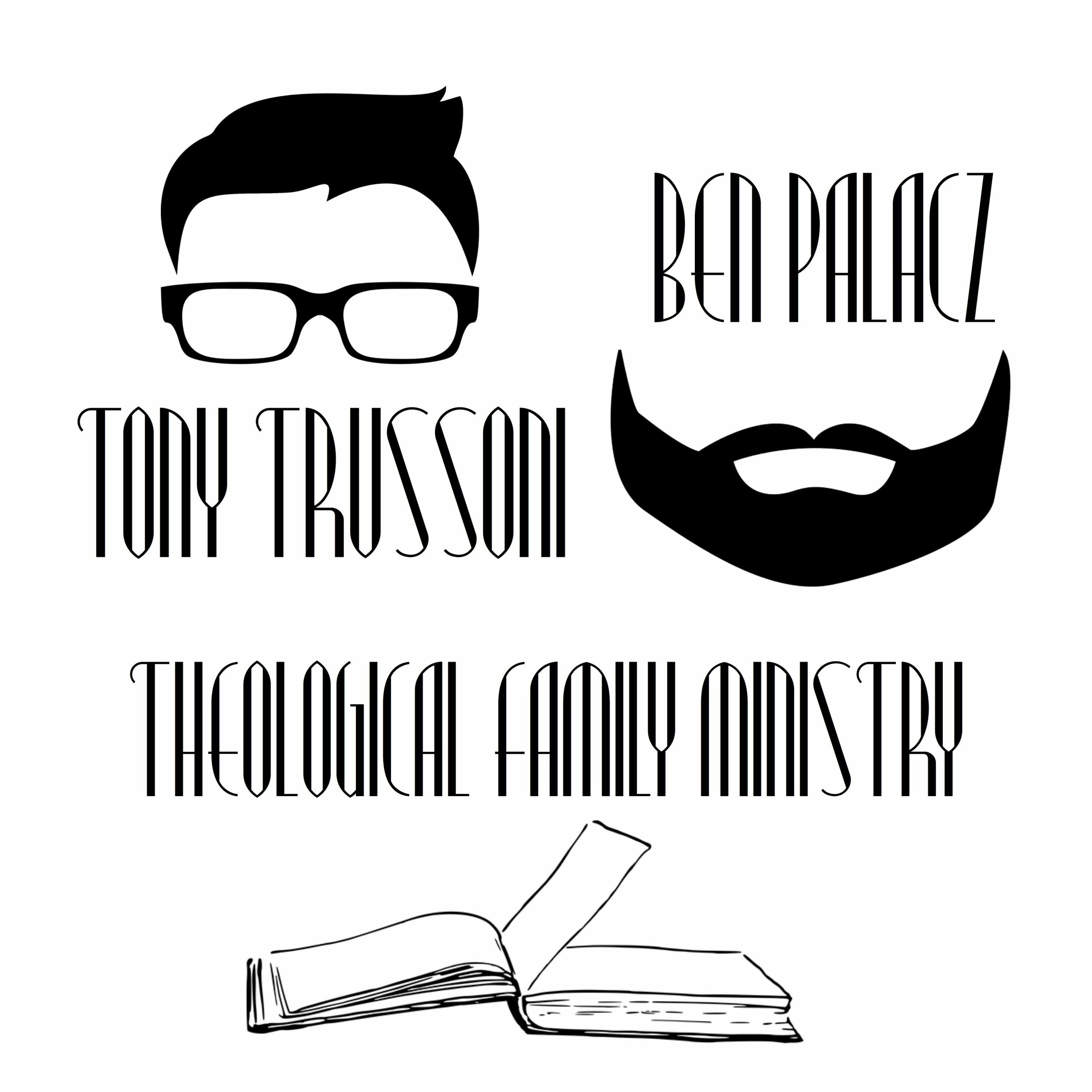
Theological Family MinistryReligious Drive-ThrusIn this episode of TFM Pastors Tony and Ben talk about consumerism in the church and how that relates to Family Ministry.
2019-02-2052 min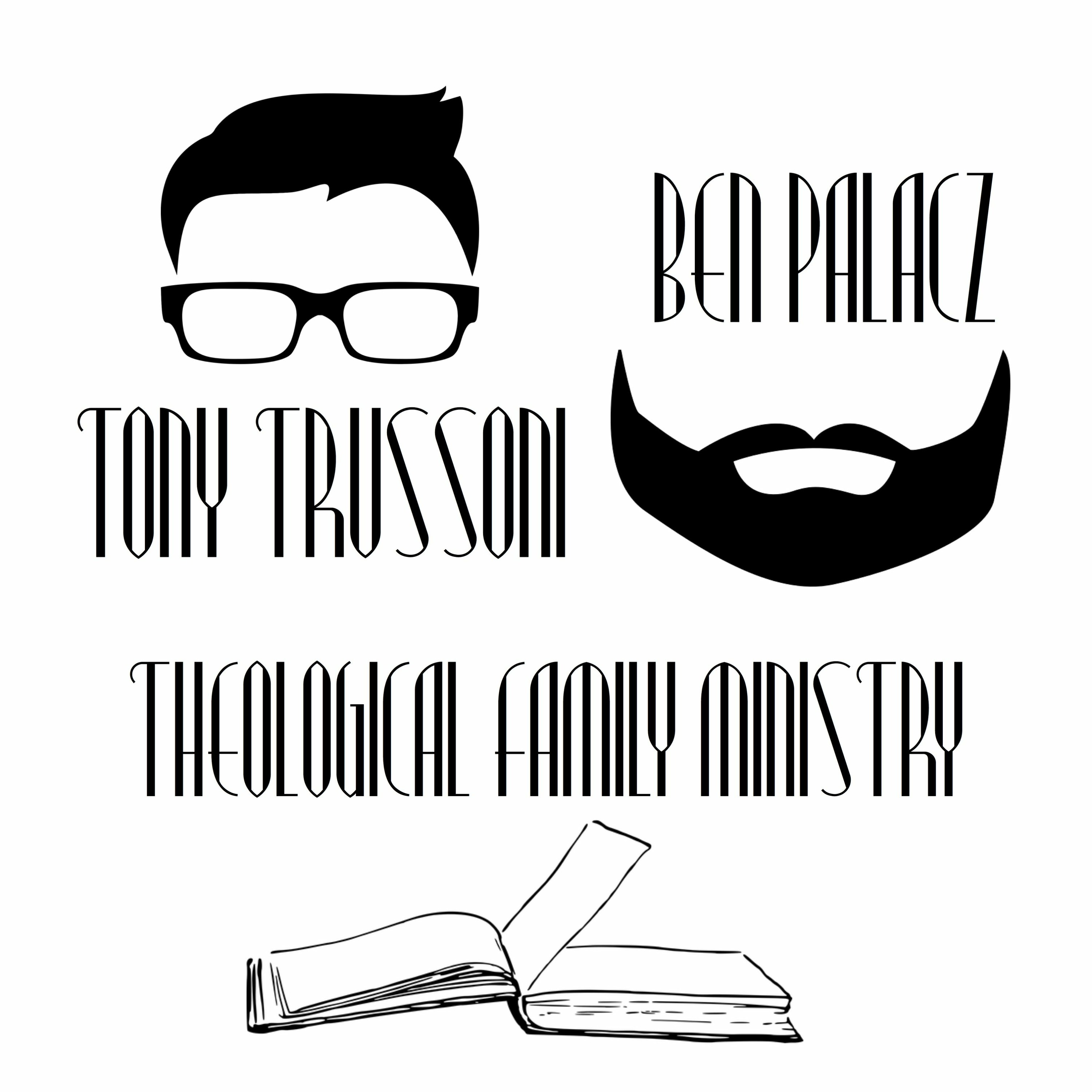
Theological Family MinistryChristian Cultural Fads & The Christian BubbleIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk about how to navigate Christian subcultures or the "Christian Bubble" while discipling the next generations.
2018-10-3146 min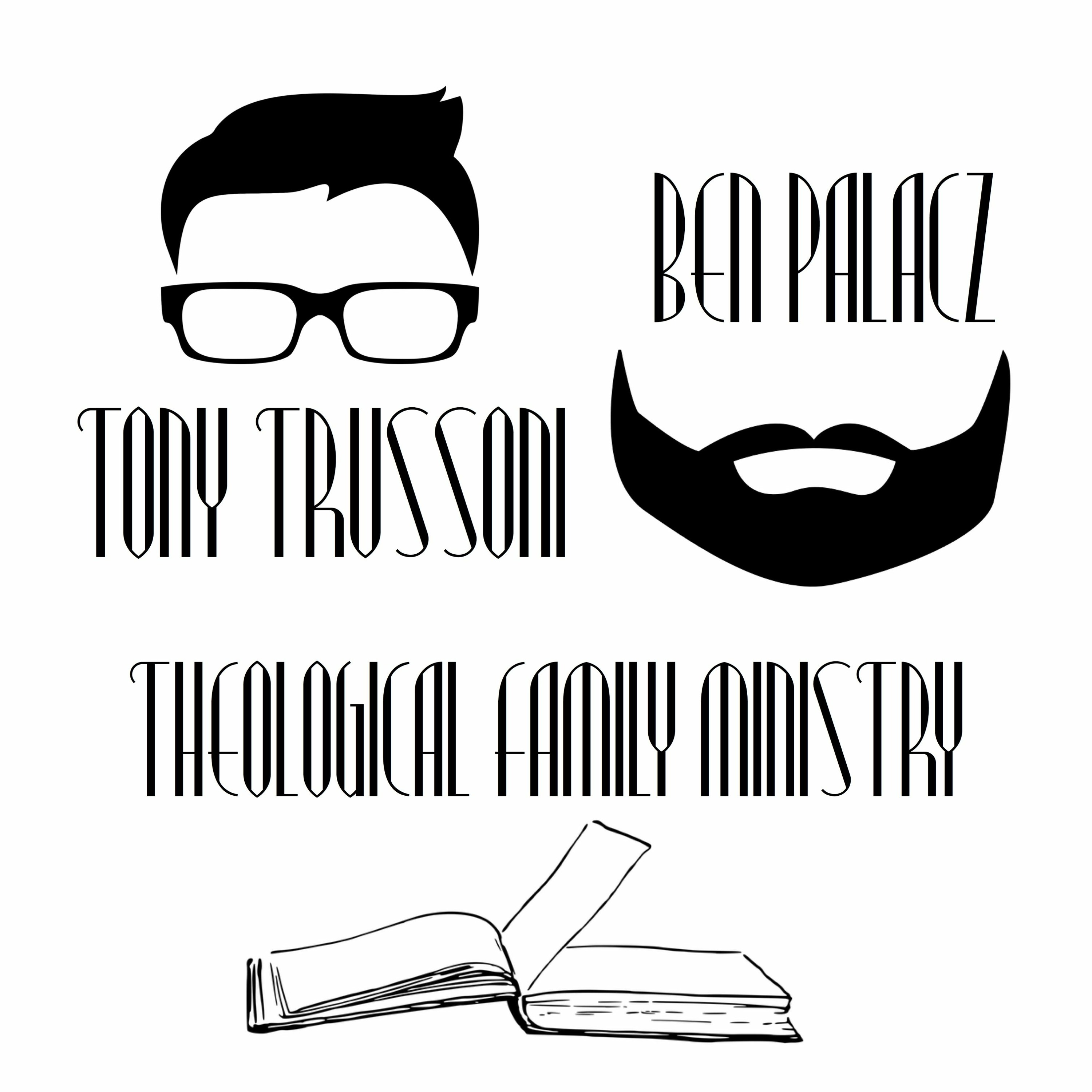
Theological Family MinistryIs Sin a Dirty Word?In this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk about the need to teach the next generation about sin. Featuring audio from Sovereign Grace Music.
2018-10-1732 min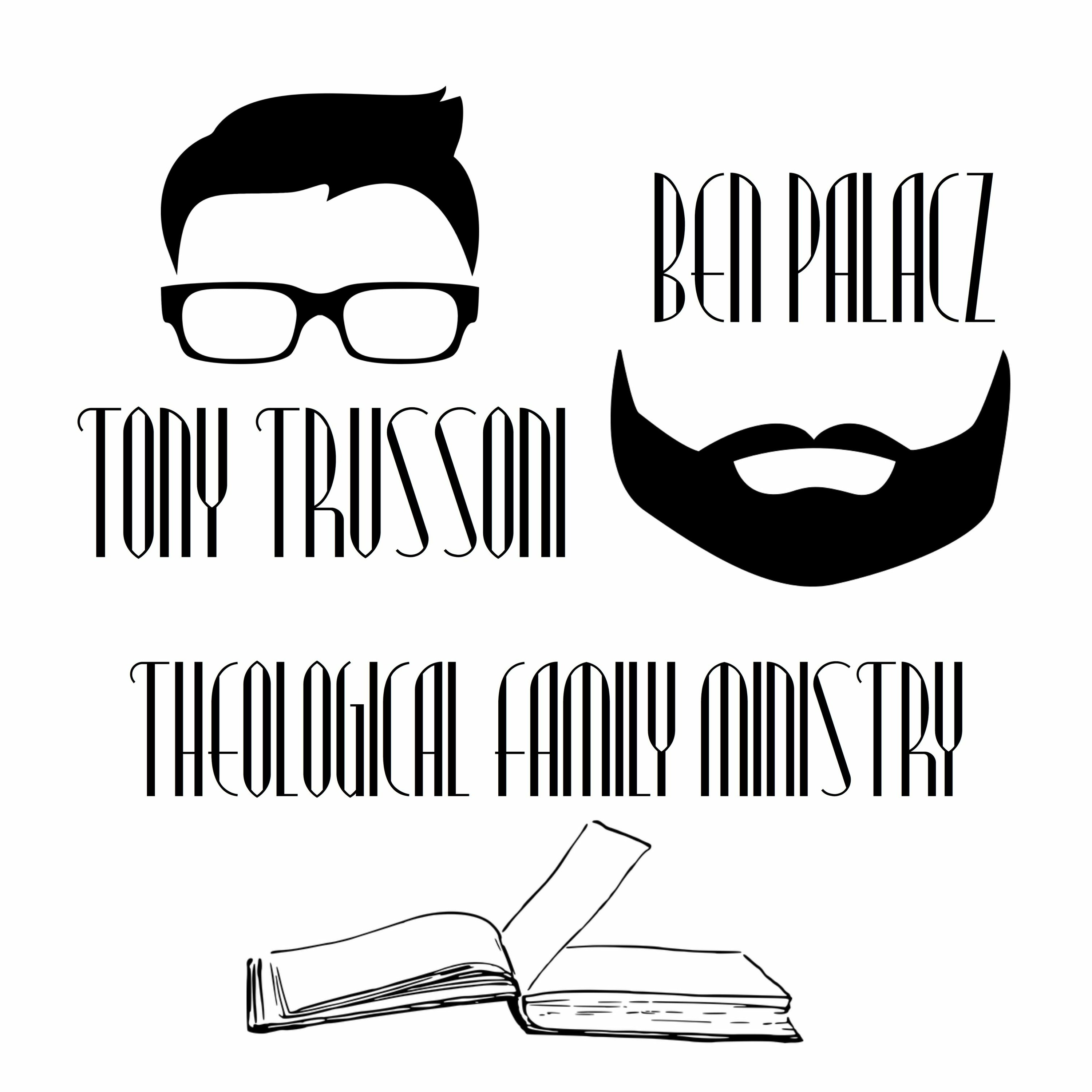
Theological Family MinistryShow Them Jesus w/ Jack KlumpenhowerIn this episode of TFM Pastors Tony and Ben talk with Jack Klumpenhower author of Show Them Jesus about how we put Jesus up front when teaching children and youth. Listen and enjoy.
2018-08-1553 min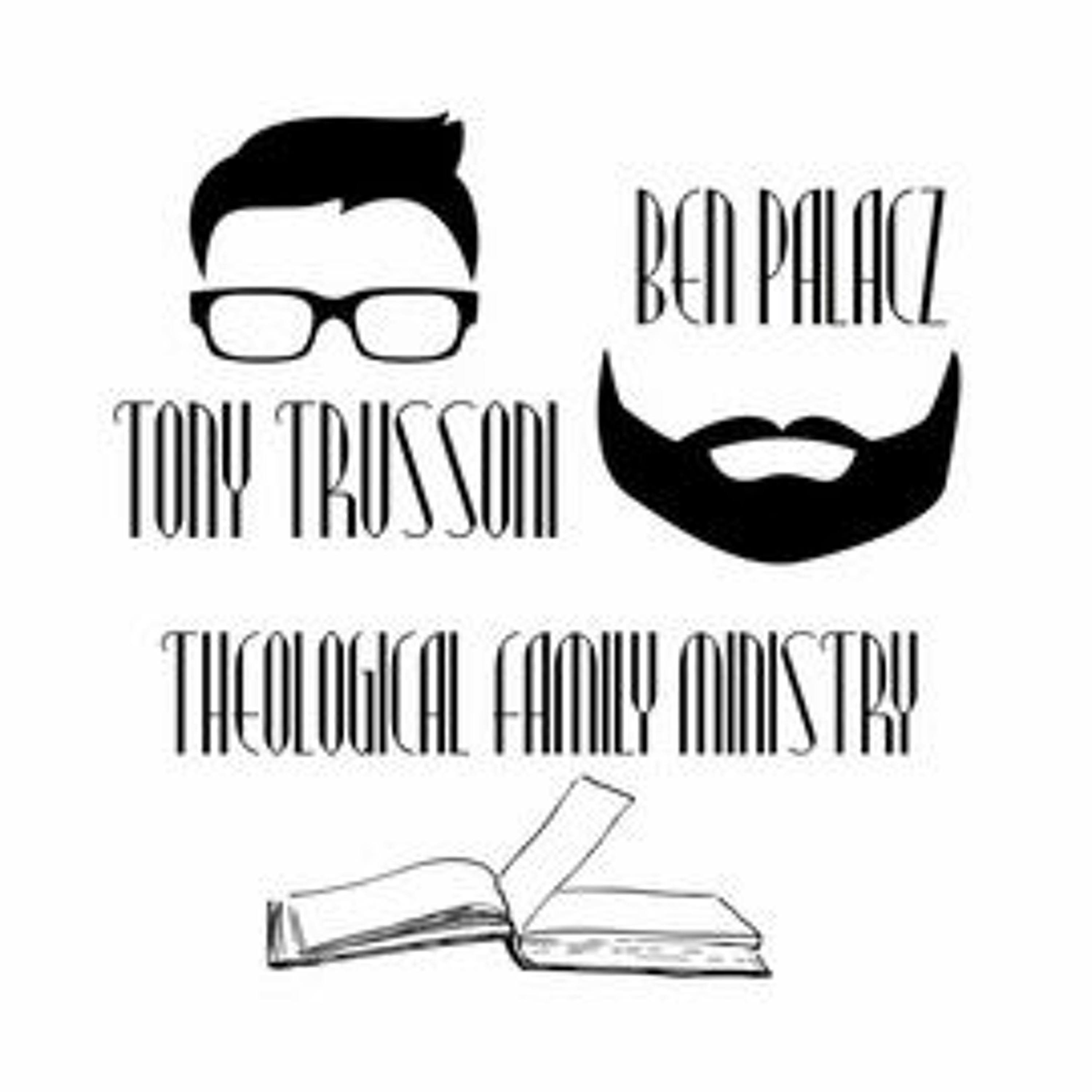
Theological Family MinistryGo Get Me a SwitchIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk about what scripture says about physical discipline and they try to answer some common objections to spanking.
2018-07-0434 min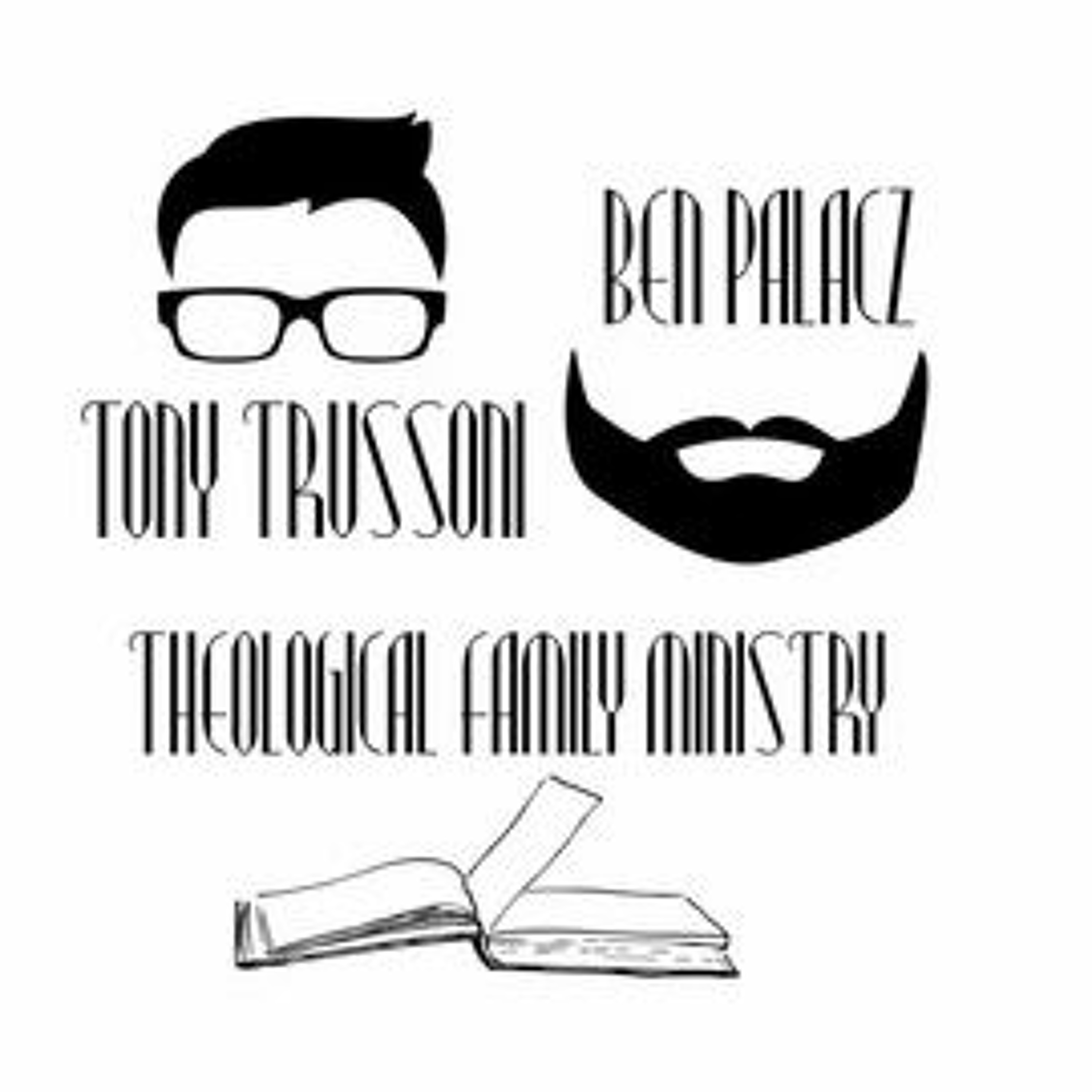
Theological Family MinistryBut I Prayed the Prayer at VBSIn this episode of TFM Pastors Tony and Ben talk about whether or not children and youth can have assurance of salvation, how we treat a young person's profession of faith, and if we can ever question those that prayed the prayer at VBS at 8 years old.
2018-06-0636 min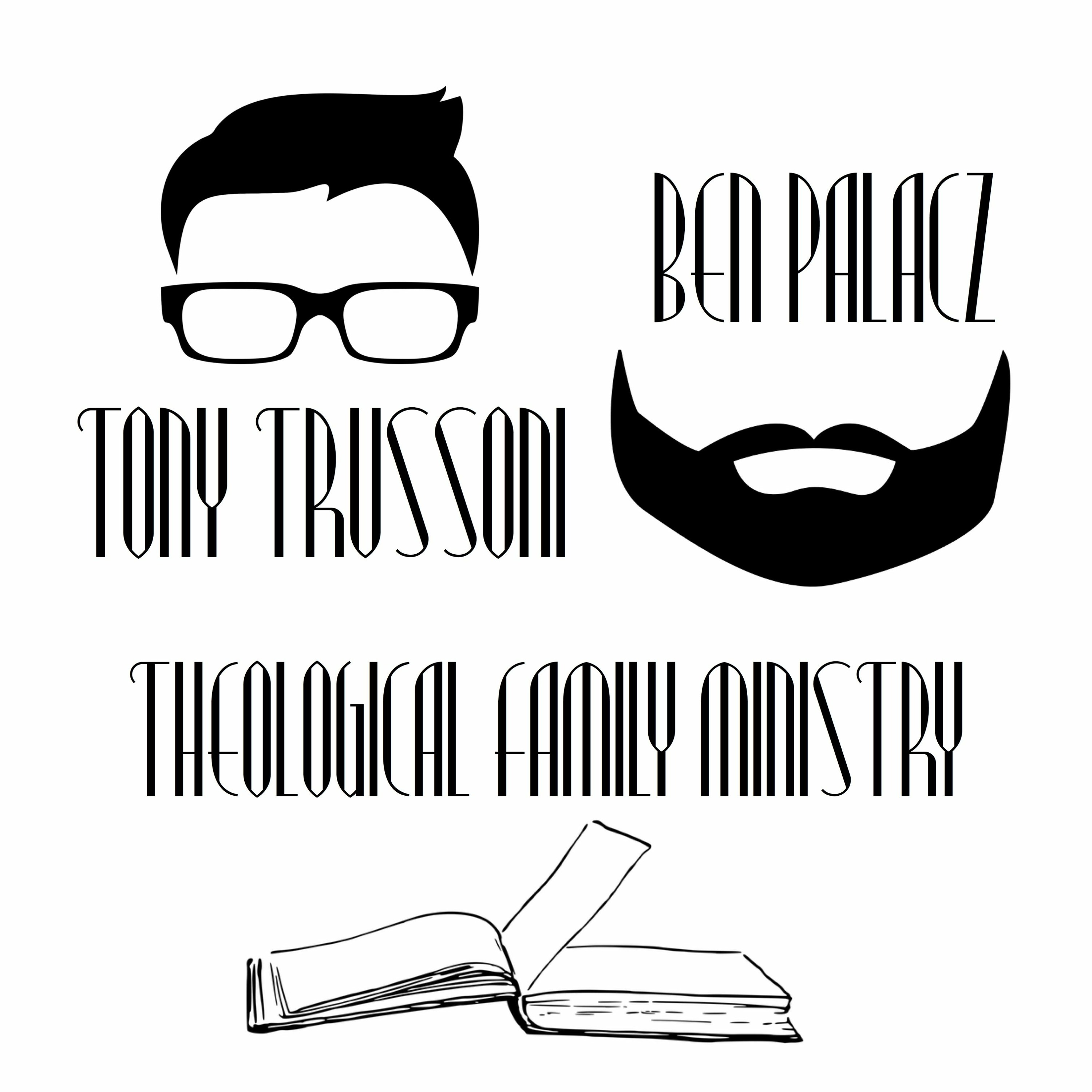
Theological Family MinistryHow to do Faith WalksIn this episode of TFM Pastors Ben and Tony talk about how we can use everyday moments for intentional faith talks with our children.
2018-05-1629 min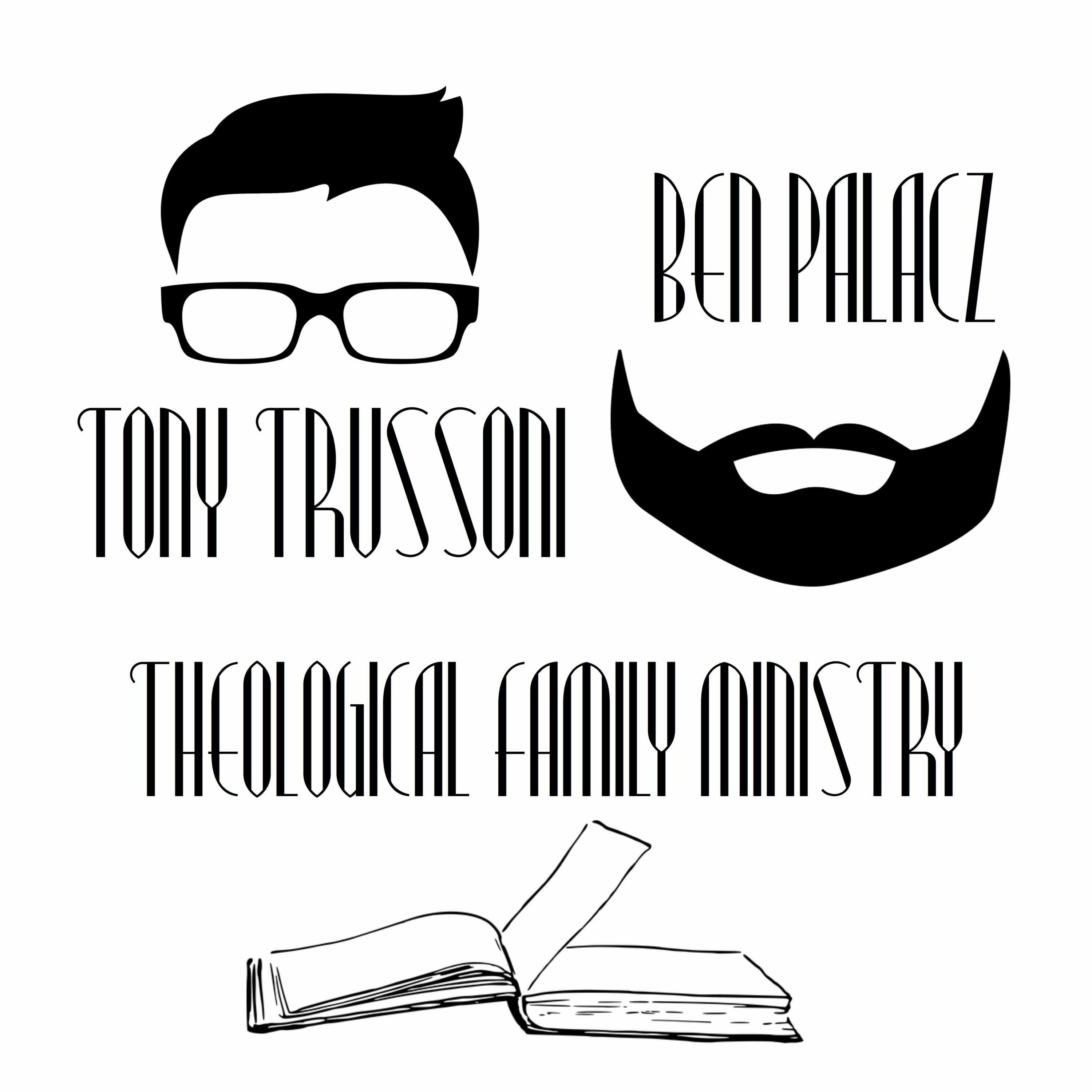
Theological Family MinistryGospel Centrality w/ Brian DembowczykIn this episode of TFM Pastors Tony and Ben talk with Brian Dembowczyk Managing Editor of Lifeway's The Gospel Project curriculum to talk about the need for Gospel centrality in both parenting and teaching children or youth. Listen and be blessed. Email us with feedback and episode suggestions at theTFMpodcast@gmail.com.
2018-05-0247 min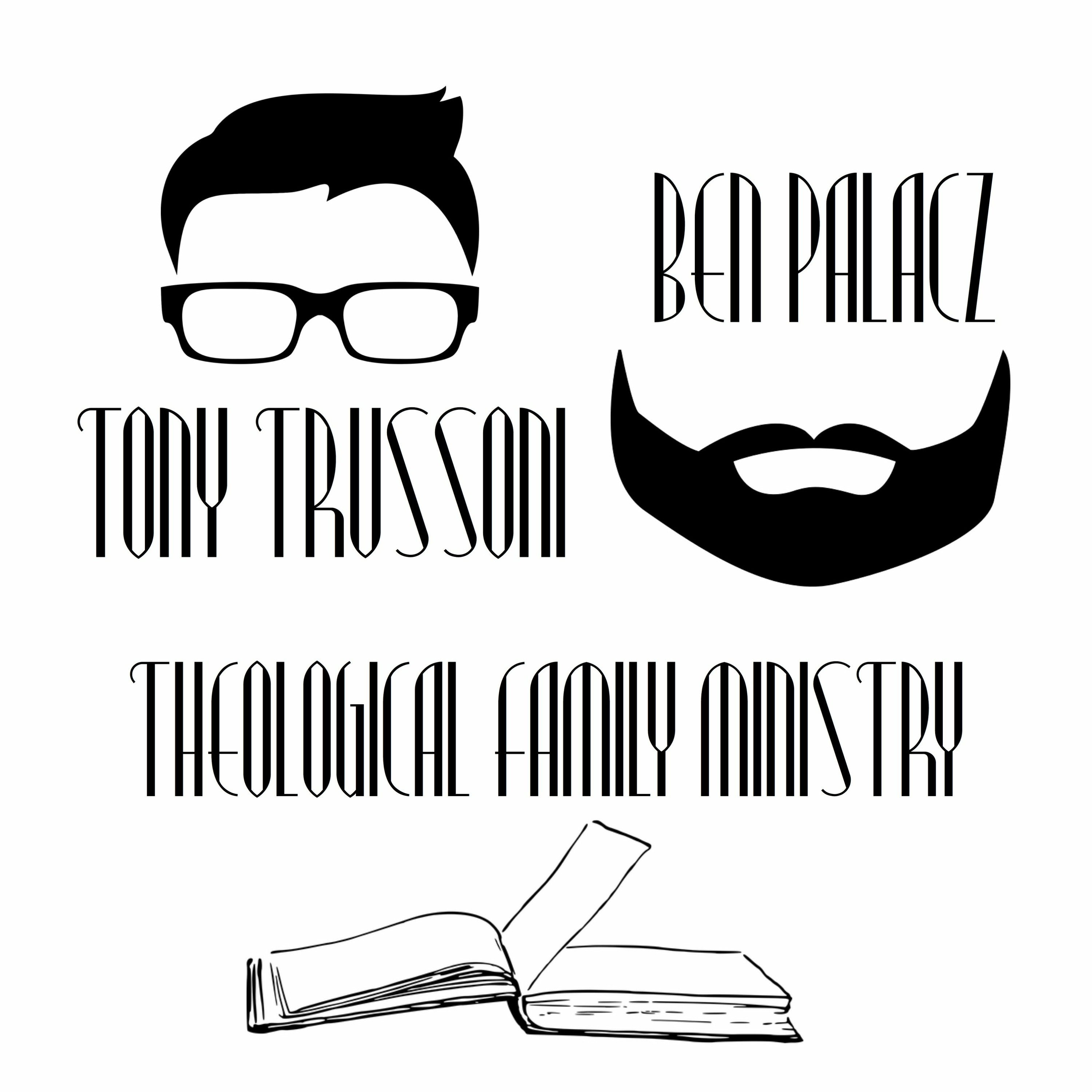
Theological Family MinistryEpisode 38: TFM Easter SpecialIn this episode of TFM Pastors Tony and Ben talk about their Easter plans, how to teach children and youth the Resurrection, and how we can reach families this Spring. Featuring audio from Keith and Kristyn Getty.
2018-03-1440 min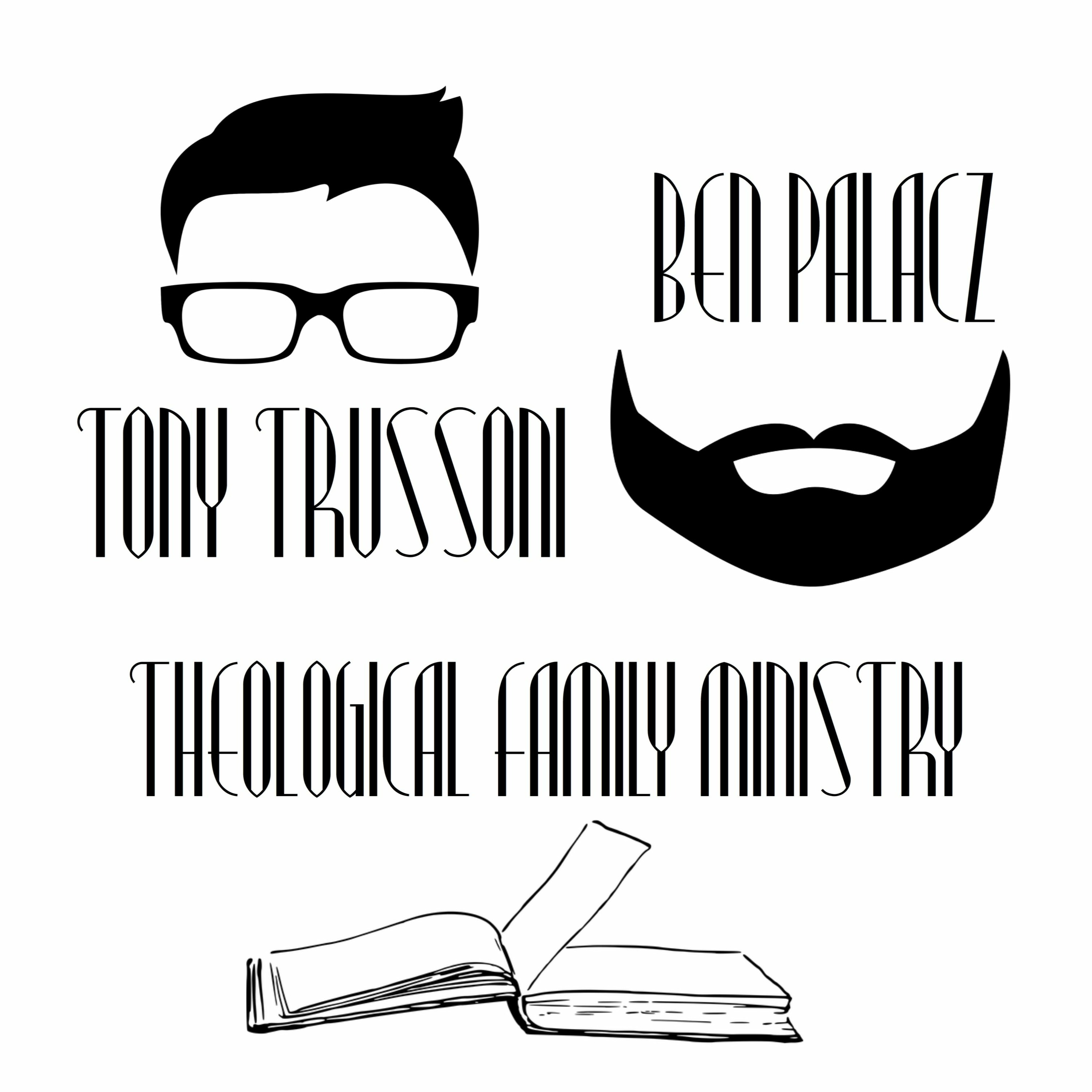
Theological Family MinistryEpisode 32: What is Love?In this episode of TFM Pastors Ben and Tony try to answer Haddaway's question "What is Love?" Listen and learn about how God understands love and what love means in parenting and children's ministry.
2018-01-1838 min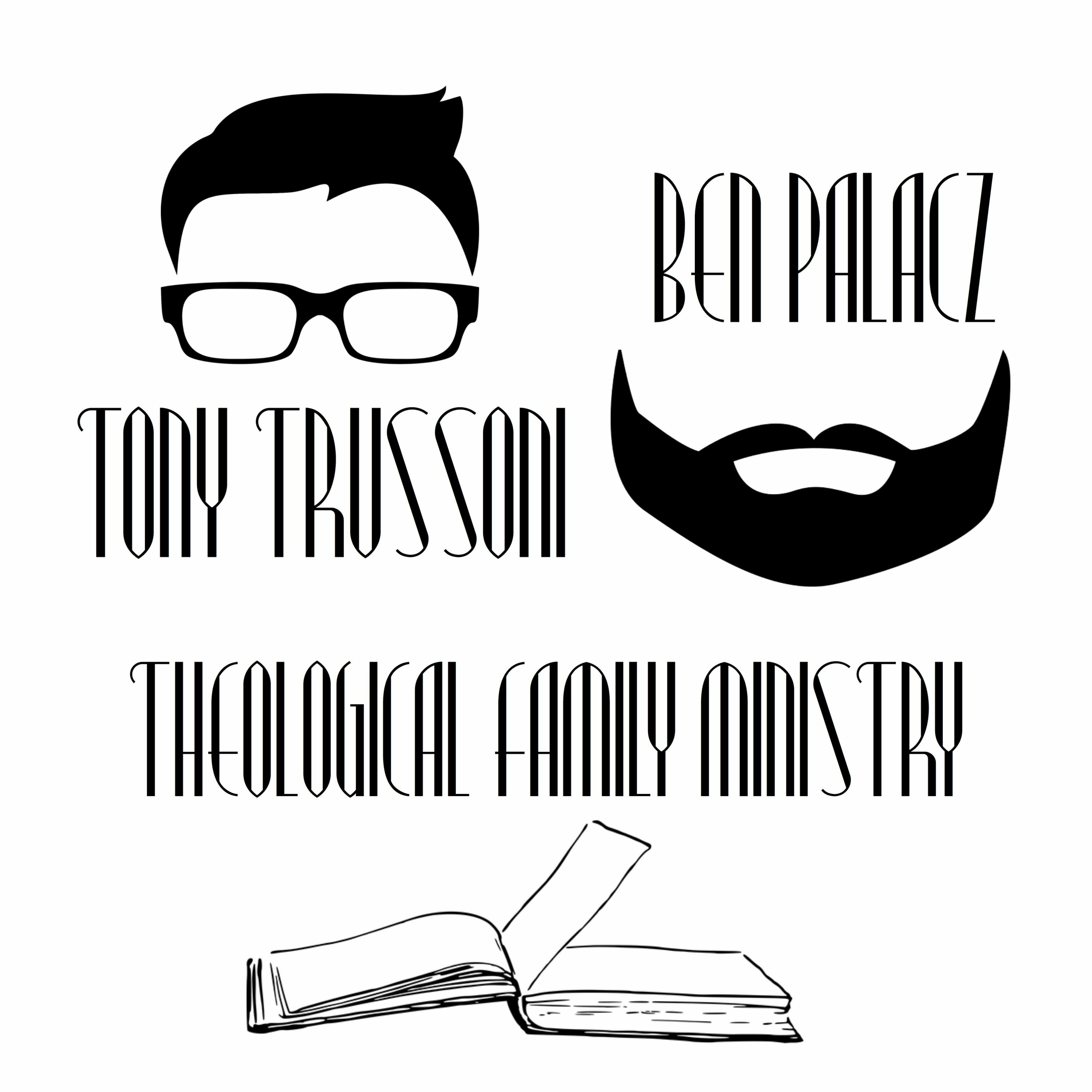
Theological Family MinistryEpisode 29: A Biblical Vision for the Next Generation w/ David and Sally Michael Pt 2In this episode of the TFM Pastors Ben and Tony are joined by Children Desiring God founders David and Sally Michael to discuss their important ministry, the need for vision in children's ministry. and the problem of Biblical illiteracy. This is part two of a two part episode. Find out more about Children Desiring God and the Michaels here http://www.childrendesiringgod.org/. If you share this with the #TFMCDG you could win great prizes.
2017-12-1336 min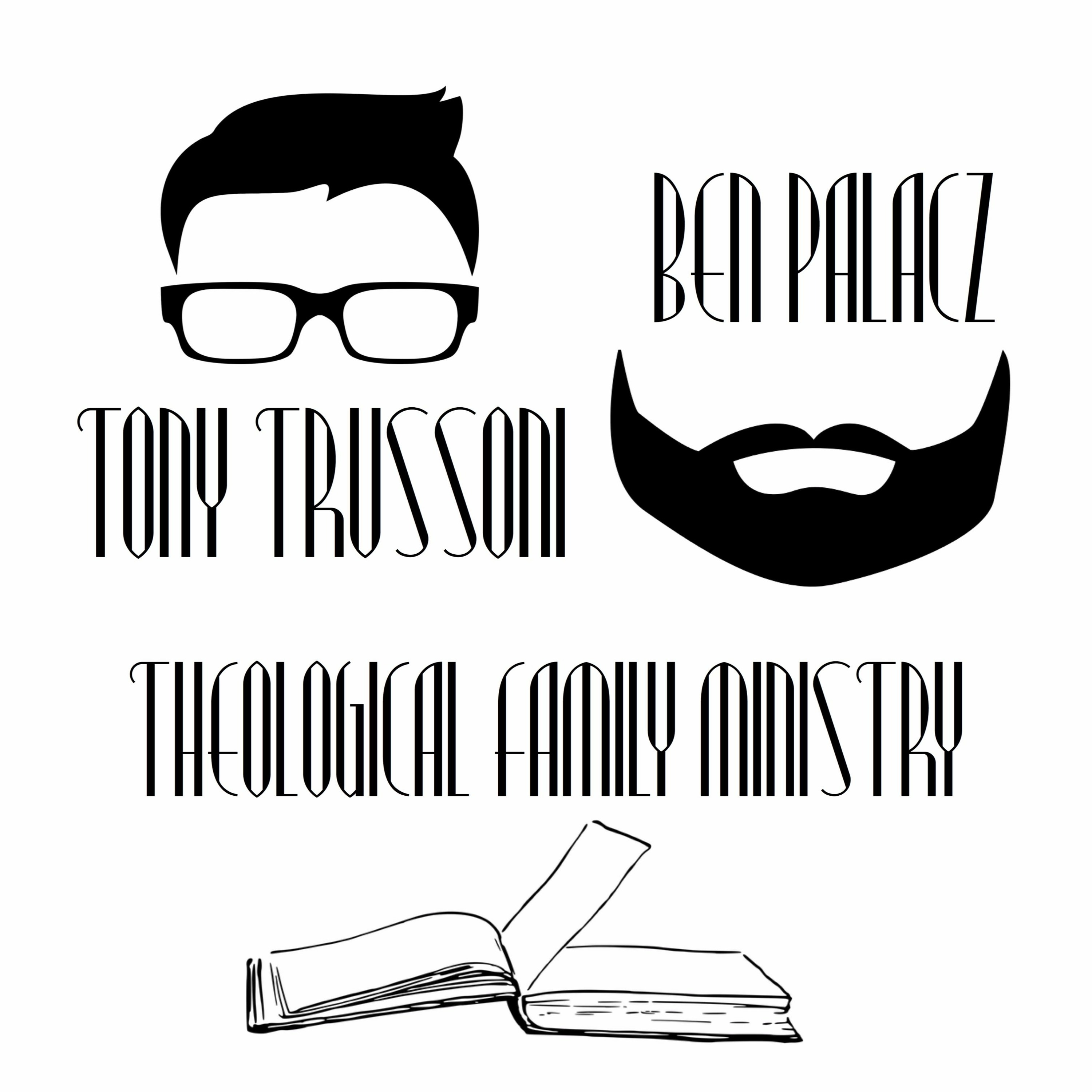
Theological Family MinistryEpisode 28: A Biblical Vision for the Next Generation with David and Sally MichaelIn this episode of the TFM Pastors Ben and Tony are joined by Children Desiring God founders David and Sally Michael to discuss their important ministry, the need for vision in children's ministry. and the problem of Biblical illiteracy. This is part one of a two part episode. Find out more about Children Desiring God and the Michaels here http://www.childrendesiringgod.org/. If you share this with the #TFMCDG you could win great prizes.
2017-12-0738 min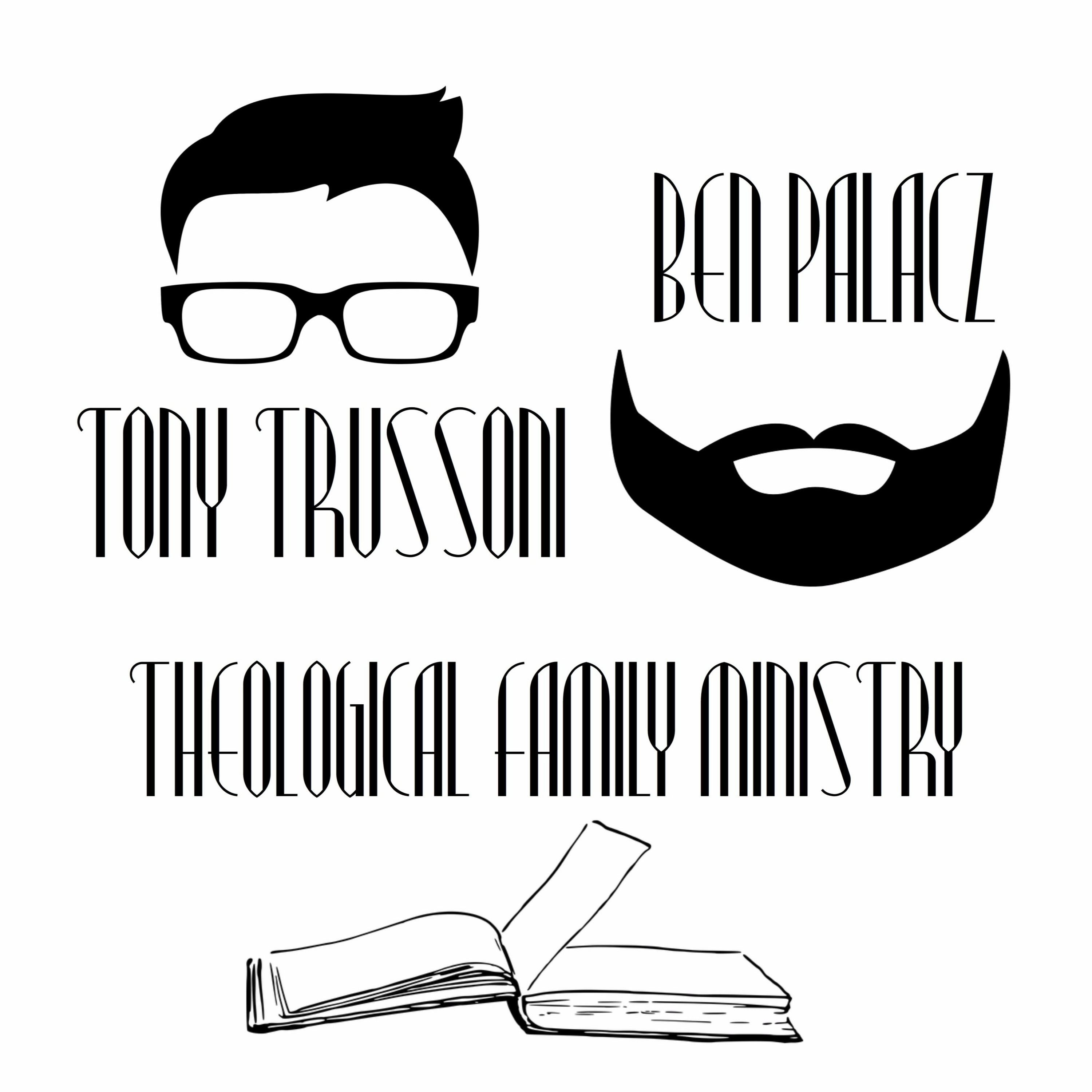
Theological Family MinistryEpisode 25: Chick Tract or TreatIn this episode of TFM Pastors Ben & Tony talk about the theology behind our family decisions concerning Halloween. They also discuss the bigger holiday of Reformation 500 and how to teach children about the Reformation. Listen and be blessed.
2017-10-1943 min
Silvia BustamanteEjemplo anuncio Don Simón TFMEjemplo Anuncio Gazpacho Don Simón TFM
Ejemplo Anuncio Gazpacho Don Simón TFM
Ejemplo Anuncio Gazpacho Don Simón TFM
Ejemplo Anuncio Gazpacho Don Simón TFM
Ejemplo Anuncio Gazpacho Don Simón TFM
Ejemplo Anuncio Gazpacho Don Simón TFM
Ejemplo Anuncio Gazpacho Don Simón TFM
Ejemplo Anuncio Gazpacho Don Simón TFM
2017-10-0300 minTheological Family MinistryEpisode 19: The Hope in Teaching Children about DeathIn this next installment of the TFM Podcast, Tony & Ben discuss the taboo topic of death. How should we teach our kids about this sober reality? Can it actually inspire hope in Jesus?
2017-08-0340 min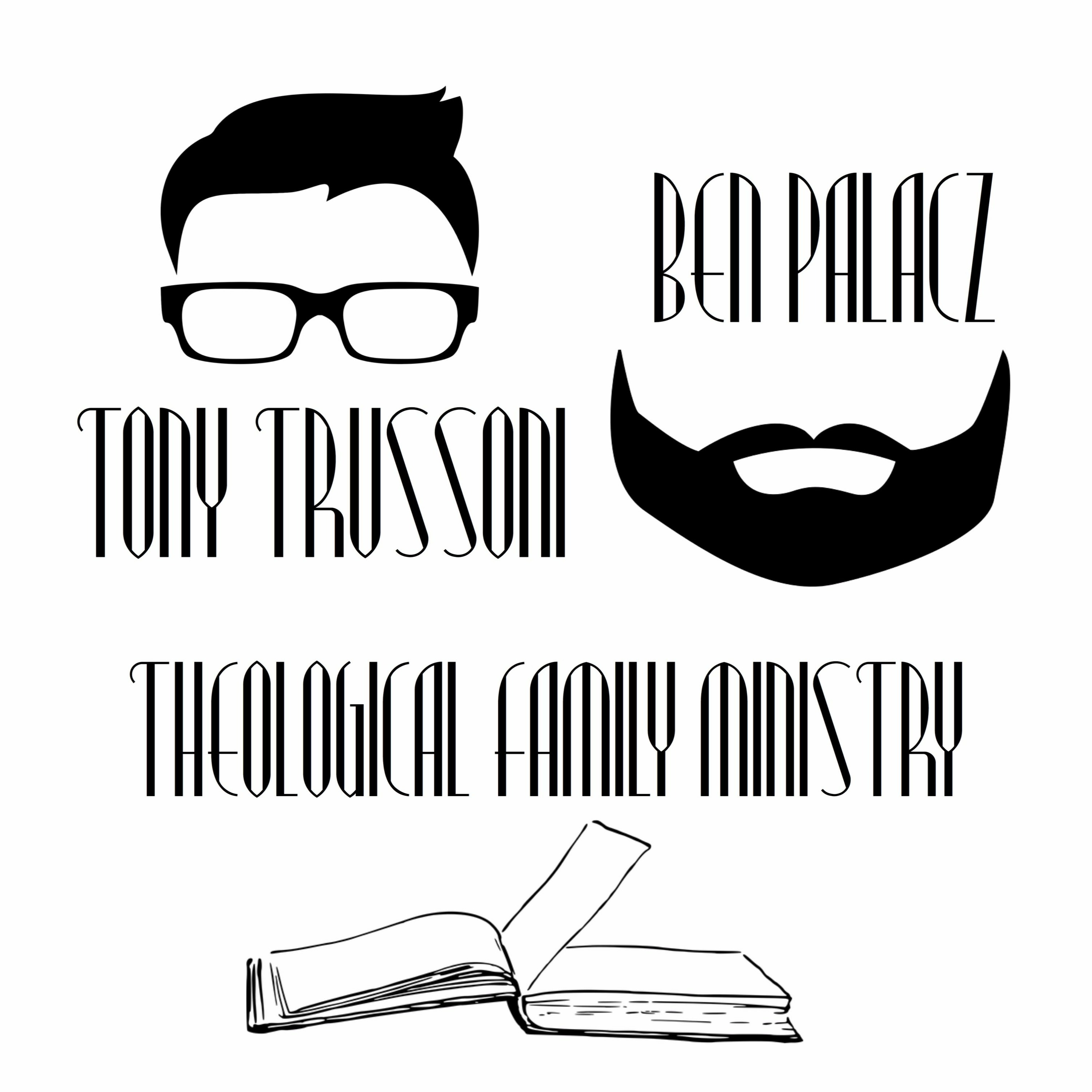
Theological Family MinistryEpisode 14: Won’t Teaching Kids Theology Bore Them to Tears?In this episode of TFM Pastors Tony and Ben discuss whether theology has any use for daily living and if it's too boring for our kids.
2017-05-1834 min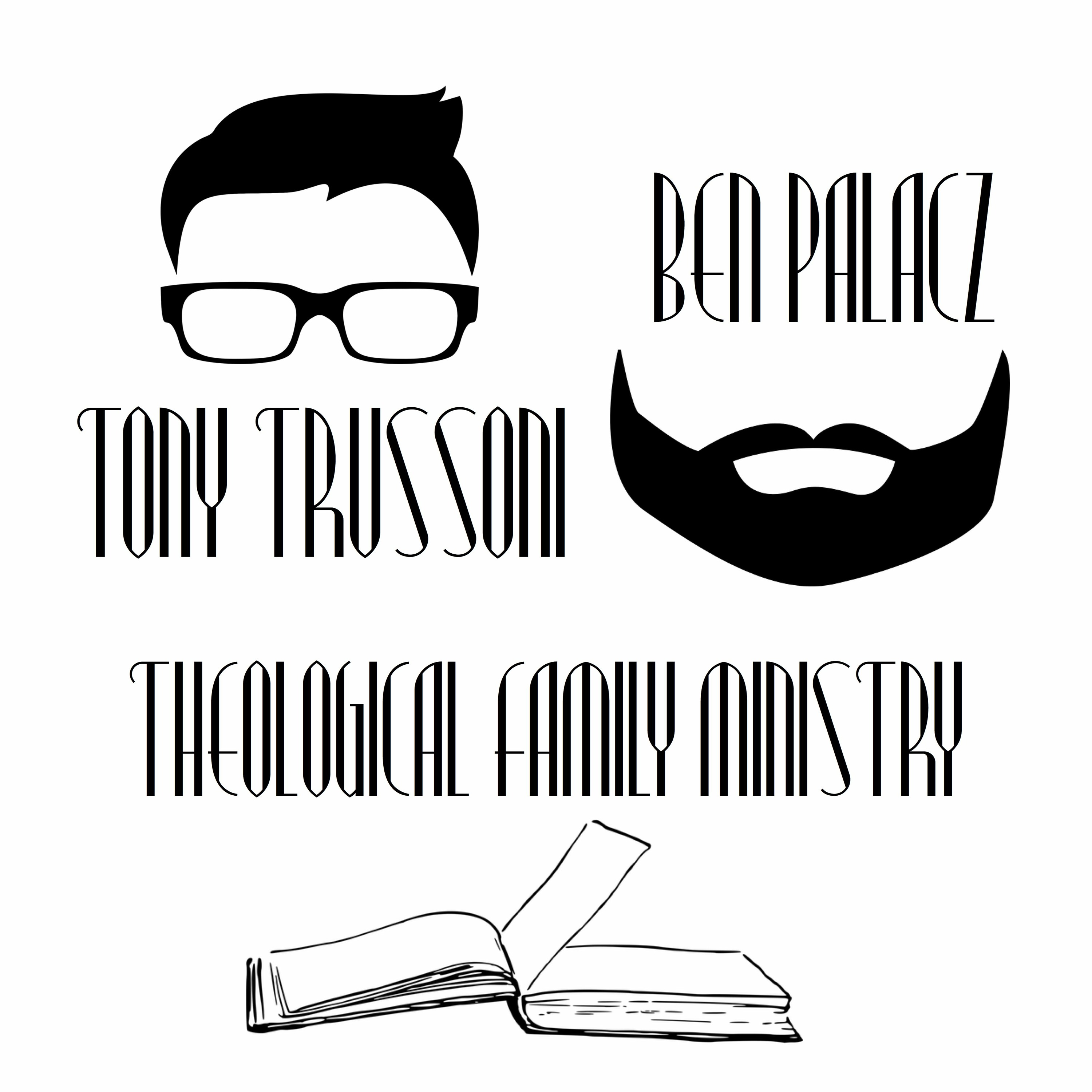
Theological Family MinistryEpisode 9: TFM At The Movies (Lego Batman)Tony and Ben go to the movies. Listen as our hosts talk about the impact film has on our children and talk specifically about the theology of the new Lego Batman Movie. Tune in to find out why this podcast is "so serious." Featuring into music from Glen Willet.
2017-03-1640 min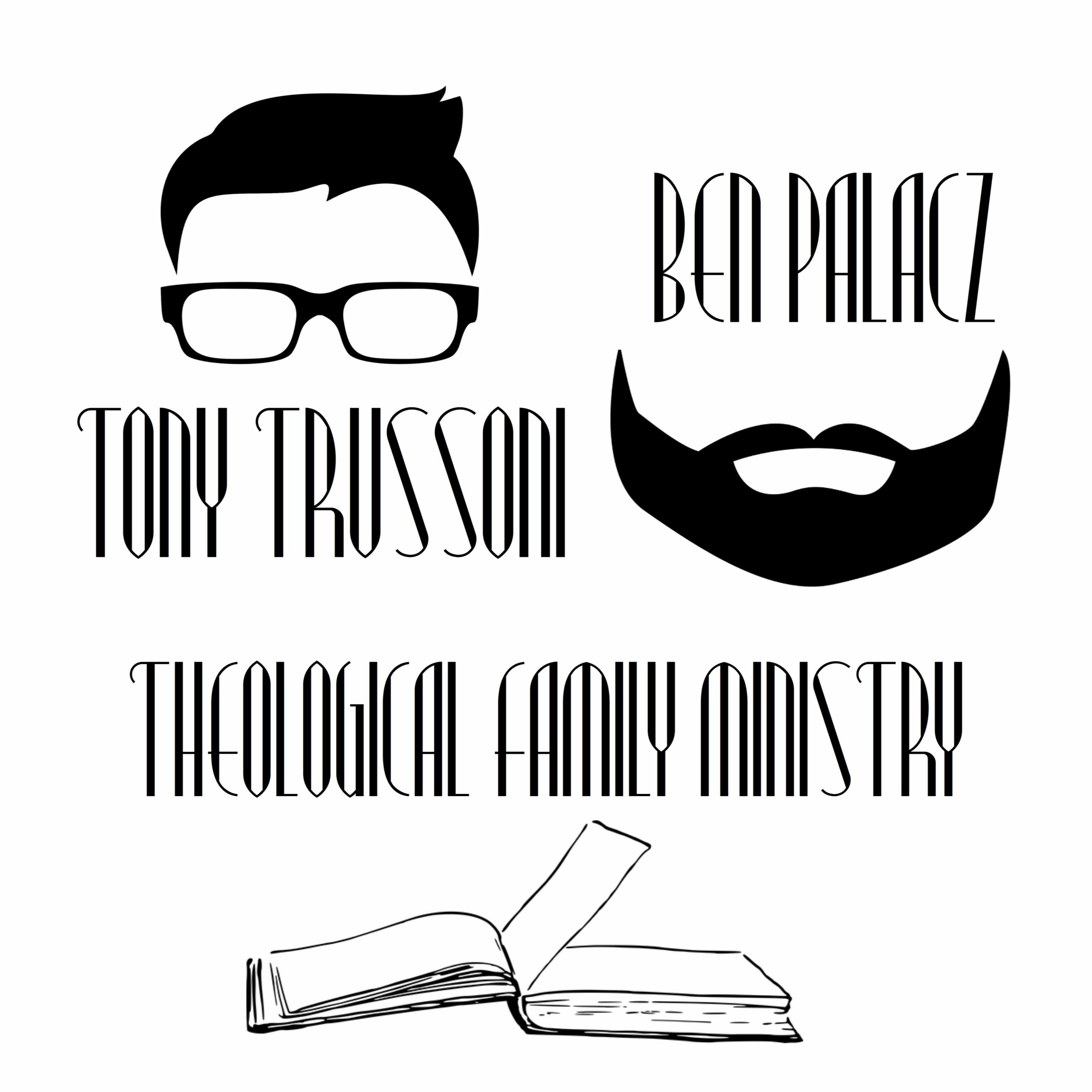
Theological Family MinistryWhat is Family WorshipWhat is Family Worship by Theological Family Ministry Podcast (TFM)
2017-01-0538 min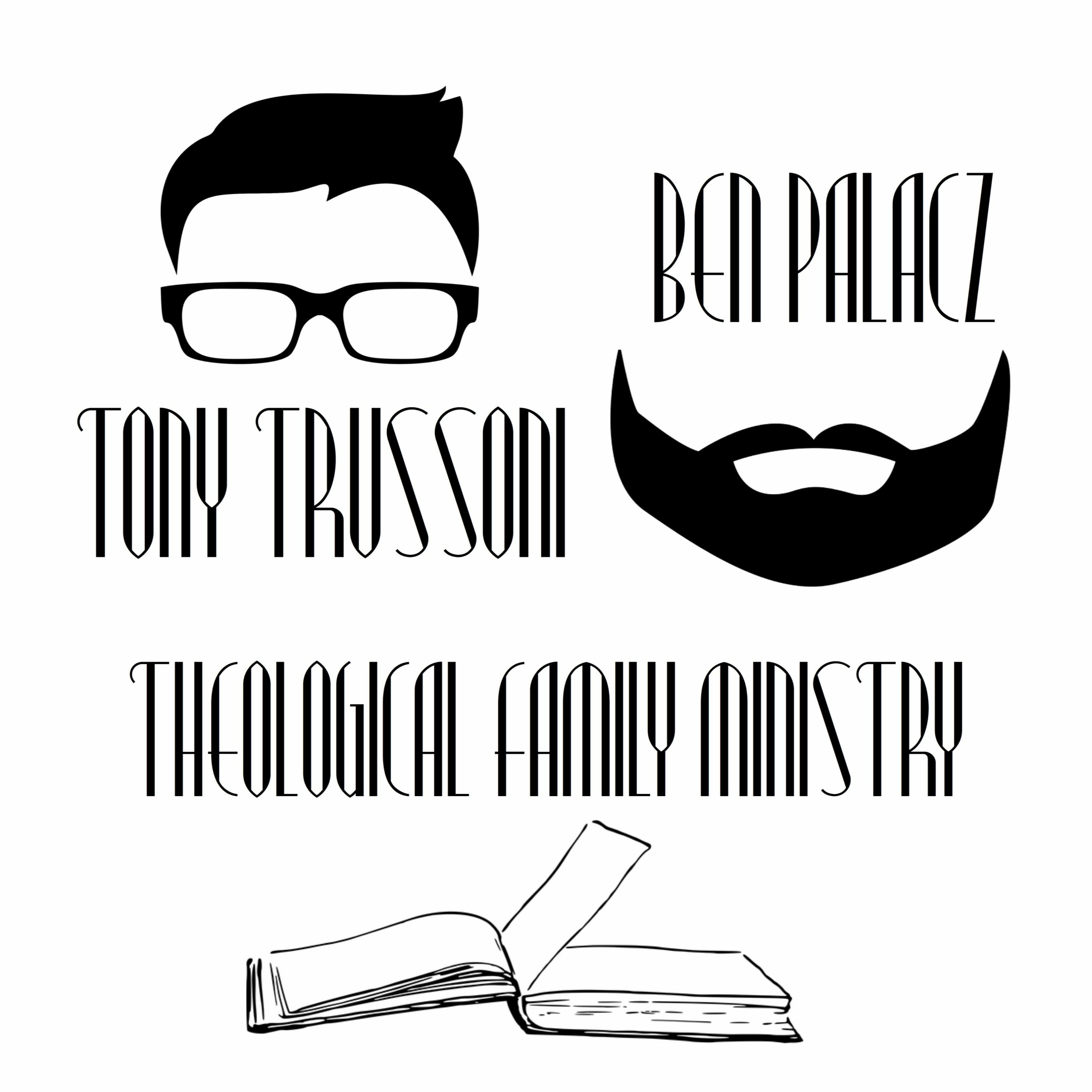 2016-12-0730 min
2016-12-0730 min