Shows
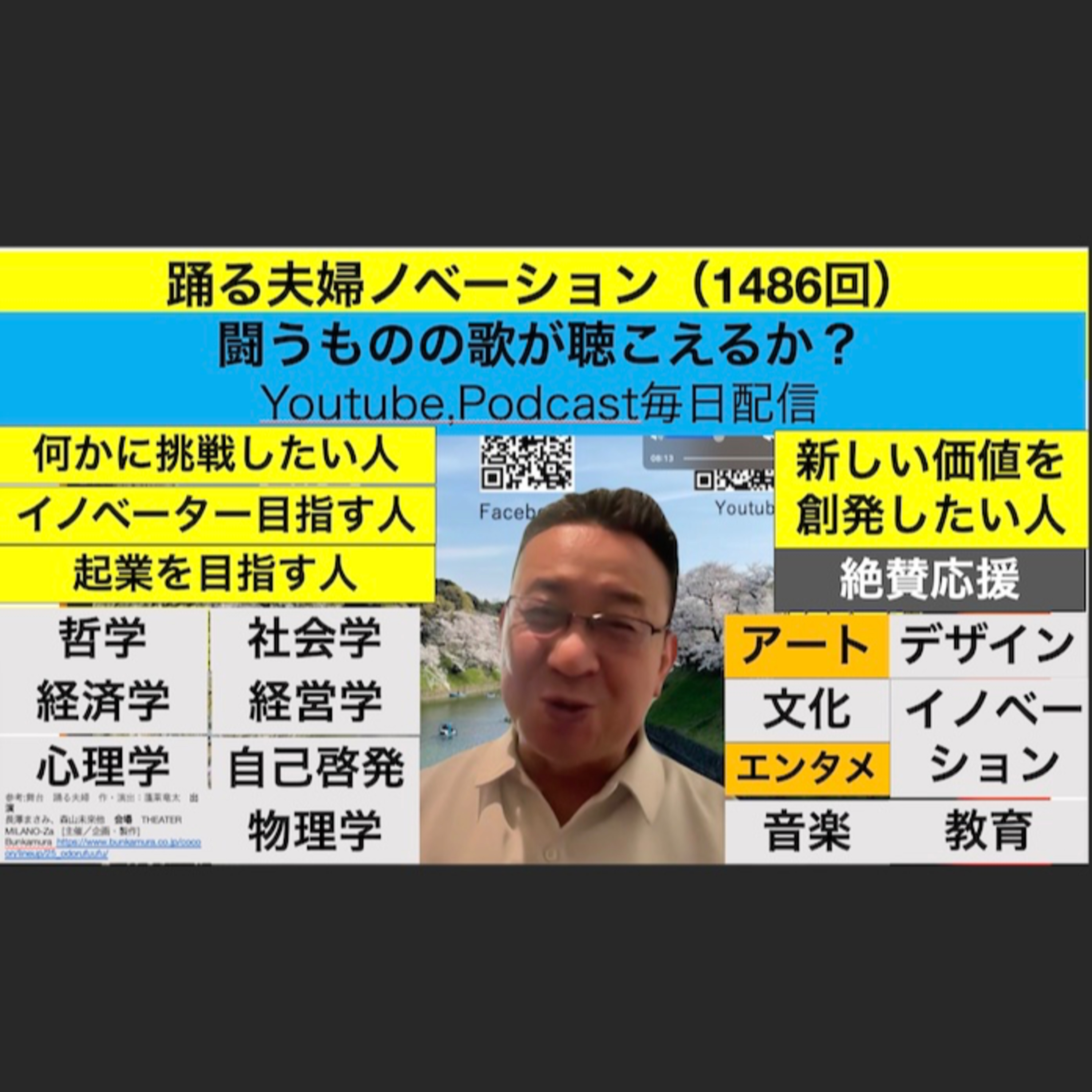 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"踊る夫婦ノベーション(1486回)森山未來さんと長澤まさみさんという、二代俳優が主演の舞台、「踊る夫婦」に感動し、作•演出の蓬莱竜太さんの言葉に考えさせられました曰く"夫婦、というのは一体なんだろうか。もっと激しい感じなのだろうか。もっと空気みたいな感じなのだろうか。""きっとそれぞれ、それぞれ、違うのでしょう。不穏な世界を共に近くで生きる、ただ共に生きる。そういう当たり前の営みの中で、それ自体を慈しみ、それ自体の奇跡を感じるような、そんな瞬間を舞台上にのせられたら、そんな思いでこの作品に向かっています。"私は思いました1、曖昧性2、ただ共に生きること3、日常にある奇跡への気づきまさに今をときめく二大俳優の森山未來さんと、長澤まさみさんの、自然な夫婦の演技と、飾り気のない舞台にほんの少しの小道具を、役者の皆さんが自在に動かしながら、さらには、舞台中央の主的な演技者と、その周りを取り囲む脇的な演技者の捌けない構造がとても不思議で面白い空間を作っていました1、曖昧性淡々と続く日々の中で、強烈な恋愛体験があるわけでもない2人が、自然に一緒になって、そして日々ぶつかりながらも共に生きていく姿が、とてもリアリティあるものとして感じましたそこには先日お話しした受信者型責任言語である、日本語に特有の、あえて曖昧にしておくことで、あえて相手の意を伺いながら、その関係を気持ちの良いものとしていく、そんな夫婦もいていいのかもしれないなあと思いました別に秘密を持ってるわけではないけども、全てを理解し合うなんて、絶対に思ってもいないし、そこに期待をしないけども、たまにはわかって欲しい的な、そんな関係も良いのかもなあと思いましたそれはイノベーションの世界で言えば、ネガティヴケイパビリティに似ていて、わからない答えをわからないけどそれがわかる時が来るまで、探し続ける、そんなことも思いました2、ただ共に生きること結婚という形式は、書類を役所に出すか出さないか、だけの違いで、実はお互いの関係性には、何も変わるものがないのだけれどもそこから共に生きていく時間の中で、一緒にいることの意味というのが、生まれてくるものなのかもなあと思いましたにとは必ず1人で生まれて1人で逝くわけですが、それでも、結婚や契約などの形式的なものとは別に、一緒にいたということが、とても意味を持ってくるのかもなあと、それはアドラーさんのいうところの、共同体感覚をどこかでは求めている、それだけでとても素敵なことなのかもしれないとも思いました3、日常にある奇跡への気づき外から見るとよくあるお話でも、当事者にとってみると、それは大事件なことというものが、実はたくさんあって、それは良きにつけ悪しきにつけ、日常における奇跡のように、感じることができるなあと思いましたイノベーションの世界でも、日常の中にある何気ない素敵なことや、もしくは違和感などに、いかに気づいていくかということが、イノベーションの種を作る上ではとても大切なので、日々の当たり前なことにこそ、問いを持ったり、感動を持てるような、そんな日々になればいいなあと思いました米国の哲学者のジョン・デューイは、『Art as Experience(経験としての芸術)』の中で、「創造性とは、見慣れたものに新しい光を当てることだ。日常の中にこそ、驚きの種がある」と言われています今回の、踊る夫婦、もそんな新しい光を、長澤まさみさん、森山未來さん、そして蓬莱竜太さんから、頂いた気がしました日常の一瞬一瞬を大切にしていきたいと、そんなことを思いました。そして、特に最後の場面は、これまでいろんなことに、踊らされていた夫婦のようなものが、自らが、踊る夫婦、になっていったような、そんなメッセージも感じました一言で言うならば、踊らされるのではなく踊る夫婦ノベーションそんなことを思いました^^参考:舞台 踊る夫婦 作・演出:蓬莱竜太 出演長澤まさみ、森山未來他 会場 THEATER MILANO-Za [主催/企画・製作] Bunkamura https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/25_odorufuufu/2025-05-1513 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"踊る夫婦ノベーション(1486回)森山未來さんと長澤まさみさんという、二代俳優が主演の舞台、「踊る夫婦」に感動し、作•演出の蓬莱竜太さんの言葉に考えさせられました曰く"夫婦、というのは一体なんだろうか。もっと激しい感じなのだろうか。もっと空気みたいな感じなのだろうか。""きっとそれぞれ、それぞれ、違うのでしょう。不穏な世界を共に近くで生きる、ただ共に生きる。そういう当たり前の営みの中で、それ自体を慈しみ、それ自体の奇跡を感じるような、そんな瞬間を舞台上にのせられたら、そんな思いでこの作品に向かっています。"私は思いました1、曖昧性2、ただ共に生きること3、日常にある奇跡への気づきまさに今をときめく二大俳優の森山未來さんと、長澤まさみさんの、自然な夫婦の演技と、飾り気のない舞台にほんの少しの小道具を、役者の皆さんが自在に動かしながら、さらには、舞台中央の主的な演技者と、その周りを取り囲む脇的な演技者の捌けない構造がとても不思議で面白い空間を作っていました1、曖昧性淡々と続く日々の中で、強烈な恋愛体験があるわけでもない2人が、自然に一緒になって、そして日々ぶつかりながらも共に生きていく姿が、とてもリアリティあるものとして感じましたそこには先日お話しした受信者型責任言語である、日本語に特有の、あえて曖昧にしておくことで、あえて相手の意を伺いながら、その関係を気持ちの良いものとしていく、そんな夫婦もいていいのかもしれないなあと思いました別に秘密を持ってるわけではないけども、全てを理解し合うなんて、絶対に思ってもいないし、そこに期待をしないけども、たまにはわかって欲しい的な、そんな関係も良いのかもなあと思いましたそれはイノベーションの世界で言えば、ネガティヴケイパビリティに似ていて、わからない答えをわからないけどそれがわかる時が来るまで、探し続ける、そんなことも思いました2、ただ共に生きること結婚という形式は、書類を役所に出すか出さないか、だけの違いで、実はお互いの関係性には、何も変わるものがないのだけれどもそこから共に生きていく時間の中で、一緒にいることの意味というのが、生まれてくるものなのかもなあと思いましたにとは必ず1人で生まれて1人で逝くわけですが、それでも、結婚や契約などの形式的なものとは別に、一緒にいたということが、とても意味を持ってくるのかもなあと、それはアドラーさんのいうところの、共同体感覚をどこかでは求めている、それだけでとても素敵なことなのかもしれないとも思いました3、日常にある奇跡への気づき外から見るとよくあるお話でも、当事者にとってみると、それは大事件なことというものが、実はたくさんあって、それは良きにつけ悪しきにつけ、日常における奇跡のように、感じることができるなあと思いましたイノベーションの世界でも、日常の中にある何気ない素敵なことや、もしくは違和感などに、いかに気づいていくかということが、イノベーションの種を作る上ではとても大切なので、日々の当たり前なことにこそ、問いを持ったり、感動を持てるような、そんな日々になればいいなあと思いました米国の哲学者のジョン・デューイは、『Art as Experience(経験としての芸術)』の中で、「創造性とは、見慣れたものに新しい光を当てることだ。日常の中にこそ、驚きの種がある」と言われています今回の、踊る夫婦、もそんな新しい光を、長澤まさみさん、森山未來さん、そして蓬莱竜太さんから、頂いた気がしました日常の一瞬一瞬を大切にしていきたいと、そんなことを思いました。そして、特に最後の場面は、これまでいろんなことに、踊らされていた夫婦のようなものが、自らが、踊る夫婦、になっていったような、そんなメッセージも感じました一言で言うならば、踊らされるのではなく踊る夫婦ノベーションそんなことを思いました^^参考:舞台 踊る夫婦 作・演出:蓬莱竜太 出演長澤まさみ、森山未來他 会場 THEATER MILANO-Za [主催/企画・製作] Bunkamura https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/25_odorufuufu/2025-05-1513 min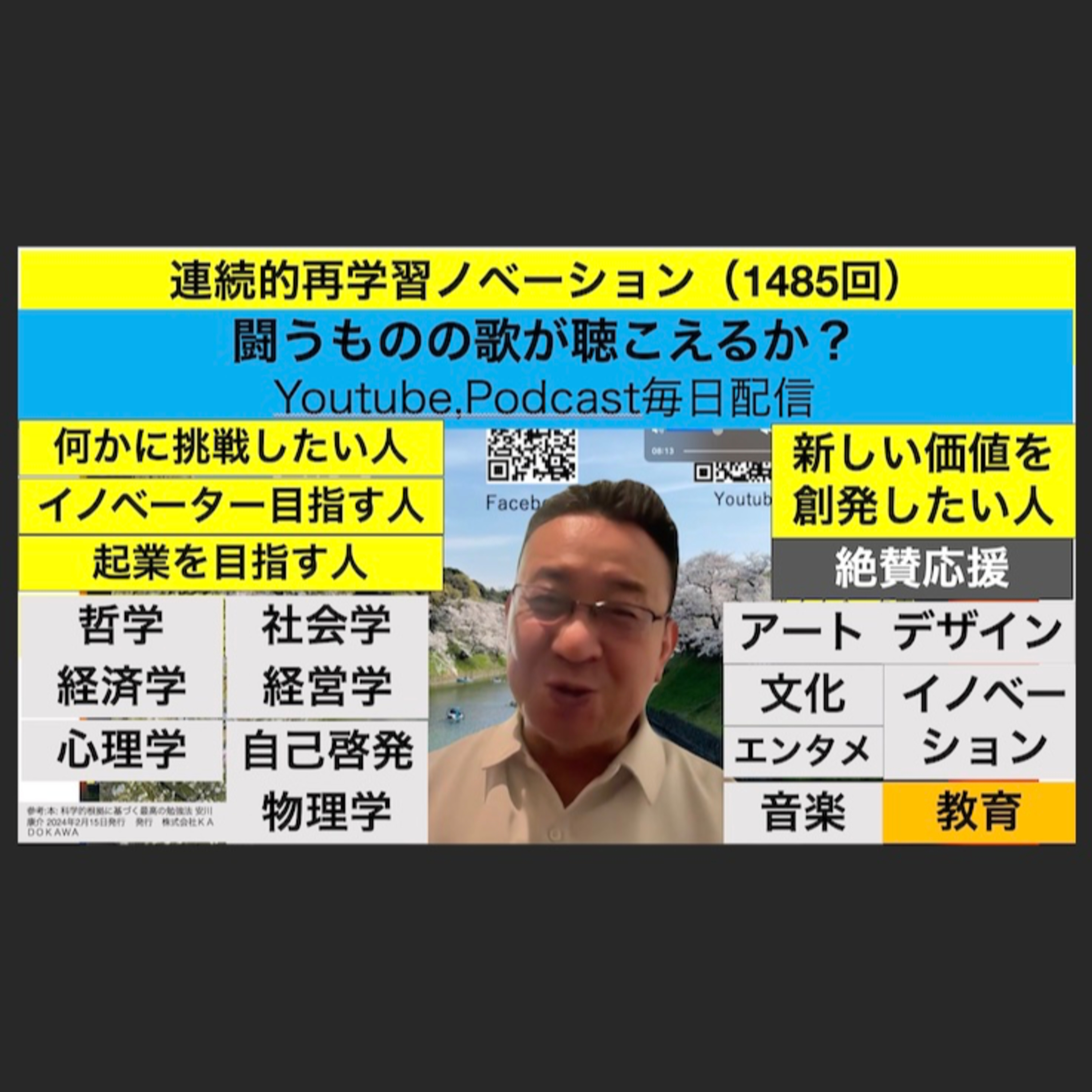 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"連続的再学習ノベーション(1485回)トップ1%以内でアメリカの医師国家試験に合格した勉強法として、現役医師の安川康介さんから教えて頂いた内容に感動しました"アクティブリコール+分散学習=連続的再学習"アクティブリコールとは"実は、これまでの学習に関する数多くの研究から、何かを記憶するためには、それを積極的に思い出す作業や、脳みそから頑張って取り出す作業こそが、決定的に重要だということが明らかになっています。""つまり、アクティブリコールをしたグループは勉強直後は、他の勉強方法で勉強した人たちに比べて一番自信がなかったのです。実際は一番効果がなさそうだと評価されたアクティブリコールが、一番効果があったというわけです。"分散学習(間隔反復)とは"『記憶について─実験心理学への貢献』という1885年に書かれた本の中で、エビングハウスは以下のように語っています[39]。 「多くの繰り返しを行う際には、それらを一度にまとめて行うよりも、時間を分散させて行うほうが、明らかに有利である」"連続的再学習とは"アクティブリコールと間隔反復、この2つを組み合わせた勉強法が、現代の学習の科学的根拠に基づく、誰でも実践可能で効果の高い方法だと考えます。"ここから私は思いました1、手応えバイアス2、再構築力3、定着と掛け合わせ私は受験勉強の時は、ひたすら書いて覚える、と言うことで、とにかく朝から晩まで書きまくってましたが、それは実は効果が薄いと言うことに衝撃を受けましたそして、こんな勉強法のコツを知っていたら、もしかしたら、もっと早くいろんなノウハウを身につけられてなのかも、と思いつつ、いやいや、今からだってやっていこう!と思わせて頂ける方法でした1、手応えバイアス一番驚いたのが、アクティブリコールと言う、方法が、感覚的には、そんなに効率がいい方法に思えないのに、実は一番効果的と言うことです。こらは、言って見れば、手応えバイアスと言ってもいいかもしれないと思いました。つまり、手応えが一番あると思い込んでる方法が、効果的ではないといくことの気づきは衝撃的でした例えば、筋トレを毎日やりすぎてしまうと、実は筋肉が痩せてしまう、または、糖質を制限し過ぎるとリバウンドが実は激しく起きる、みたいな、自分の実感と、効果ということが、必ずしも一致しないということが、あるのだと改めて肝に銘じました2、再構築力アクティブリコールとは、私の理解では、アウトプットをたくさんすることで、脳に刻み込まれるということかと思いました以前、私の好きな本の、アウトプット大全の際、でもお話ししましたが、インプットをたくさんするためには、実はアウトプットをたくさんすることが重要、というお話と、とてもシナジーがあるなあと思いましたアウトプットするということは、実は覚えたことをそのまま写す行為ではなく、自分の中で様々な要素を再構成して話さなければならない、ということが言えると思いますすなわちそれは、よく言語化するといわれたりしますが、一旦抽象的に理解したものを、もう一度、言葉という具現化する作業をしてることと同じだと思います。そしてその作業は、実は、イノベーション活動にも欠かせないことであって、例えば、違う業界で行われていることを抽象化してその価値を、自分たちの業界で展開するとどうなるか、みたいな再構築によって、新たなアイデアが生まれたりしますつまり、アクティブリコールは、再構築力を鍛えてくれるので、イノベーションを起こすための重要なスキルを鍛えてくれる方法とも言っていいのかもしれません3、定着と掛け合わせ夏休みの宿題は、必ず一夜漬け、試験においても同じなので、試験が終わったらすぐに忘れてしまう、そんなことを繰り返している私の学生時代でしたしかしそれは、この時間を味方にすると言ってもいい、分散学習の効果がどれほど高いのか、これを認識できていなかったから、なのかもしれないなあと思いました私は自称、ものすごく覚えが遅いのですが、今の自分を振り返ると、実は曲の歌詞を覚える時だけは、毎日毎日少しずつ覚えていかないと、絶対に覚えられないことが経験的にわかっているので、一ヶ月かけて、一曲覚えたりしてますそして不思議なことに一回これで覚えると、大体後々まで覚えていると、いう結果に結びついてるので、実感としても、分散学習という方法があって良かった、つくづくおもいますこれをイノベーションの文脈で捉えてみると、京都大学の苧坂直之先生のデフォルトモードネットワークの話を思い出します散歩やお風呂などの、実は休んでいるときにこそ、脳は活性化して、さまざまな組み合わせを生み出すというお話ですが、その前提として、さまざまな情報が頭の中にあるということが必要かと思いますそのためにも、日々積み重ねていくからこそ、新たな掛け合わせのネタが蓄積されていくことになるのかもしれないなあと思います分散学習は、試験対策でもありますが、日々のデフォルトモードネットワークのスパークを生み出す秘訣なのかもしれないそんなことも思いましたということで、最強の学習法である、アクティブリコールと分散学習を組み合わせた、連続的再学習は、実はイノベーション力を育てるのにも、効果を発揮する、そんなことを思いました一言で言えば連続的再学習ノベーションそんな話をしています^^参考:本: 科学的根拠に基づく最高の勉強法 安川 康介 2024年2月15日発行 発行 株式会社KADOKAWA2025-05-1416 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"連続的再学習ノベーション(1485回)トップ1%以内でアメリカの医師国家試験に合格した勉強法として、現役医師の安川康介さんから教えて頂いた内容に感動しました"アクティブリコール+分散学習=連続的再学習"アクティブリコールとは"実は、これまでの学習に関する数多くの研究から、何かを記憶するためには、それを積極的に思い出す作業や、脳みそから頑張って取り出す作業こそが、決定的に重要だということが明らかになっています。""つまり、アクティブリコールをしたグループは勉強直後は、他の勉強方法で勉強した人たちに比べて一番自信がなかったのです。実際は一番効果がなさそうだと評価されたアクティブリコールが、一番効果があったというわけです。"分散学習(間隔反復)とは"『記憶について─実験心理学への貢献』という1885年に書かれた本の中で、エビングハウスは以下のように語っています[39]。 「多くの繰り返しを行う際には、それらを一度にまとめて行うよりも、時間を分散させて行うほうが、明らかに有利である」"連続的再学習とは"アクティブリコールと間隔反復、この2つを組み合わせた勉強法が、現代の学習の科学的根拠に基づく、誰でも実践可能で効果の高い方法だと考えます。"ここから私は思いました1、手応えバイアス2、再構築力3、定着と掛け合わせ私は受験勉強の時は、ひたすら書いて覚える、と言うことで、とにかく朝から晩まで書きまくってましたが、それは実は効果が薄いと言うことに衝撃を受けましたそして、こんな勉強法のコツを知っていたら、もしかしたら、もっと早くいろんなノウハウを身につけられてなのかも、と思いつつ、いやいや、今からだってやっていこう!と思わせて頂ける方法でした1、手応えバイアス一番驚いたのが、アクティブリコールと言う、方法が、感覚的には、そんなに効率がいい方法に思えないのに、実は一番効果的と言うことです。こらは、言って見れば、手応えバイアスと言ってもいいかもしれないと思いました。つまり、手応えが一番あると思い込んでる方法が、効果的ではないといくことの気づきは衝撃的でした例えば、筋トレを毎日やりすぎてしまうと、実は筋肉が痩せてしまう、または、糖質を制限し過ぎるとリバウンドが実は激しく起きる、みたいな、自分の実感と、効果ということが、必ずしも一致しないということが、あるのだと改めて肝に銘じました2、再構築力アクティブリコールとは、私の理解では、アウトプットをたくさんすることで、脳に刻み込まれるということかと思いました以前、私の好きな本の、アウトプット大全の際、でもお話ししましたが、インプットをたくさんするためには、実はアウトプットをたくさんすることが重要、というお話と、とてもシナジーがあるなあと思いましたアウトプットするということは、実は覚えたことをそのまま写す行為ではなく、自分の中で様々な要素を再構成して話さなければならない、ということが言えると思いますすなわちそれは、よく言語化するといわれたりしますが、一旦抽象的に理解したものを、もう一度、言葉という具現化する作業をしてることと同じだと思います。そしてその作業は、実は、イノベーション活動にも欠かせないことであって、例えば、違う業界で行われていることを抽象化してその価値を、自分たちの業界で展開するとどうなるか、みたいな再構築によって、新たなアイデアが生まれたりしますつまり、アクティブリコールは、再構築力を鍛えてくれるので、イノベーションを起こすための重要なスキルを鍛えてくれる方法とも言っていいのかもしれません3、定着と掛け合わせ夏休みの宿題は、必ず一夜漬け、試験においても同じなので、試験が終わったらすぐに忘れてしまう、そんなことを繰り返している私の学生時代でしたしかしそれは、この時間を味方にすると言ってもいい、分散学習の効果がどれほど高いのか、これを認識できていなかったから、なのかもしれないなあと思いました私は自称、ものすごく覚えが遅いのですが、今の自分を振り返ると、実は曲の歌詞を覚える時だけは、毎日毎日少しずつ覚えていかないと、絶対に覚えられないことが経験的にわかっているので、一ヶ月かけて、一曲覚えたりしてますそして不思議なことに一回これで覚えると、大体後々まで覚えていると、いう結果に結びついてるので、実感としても、分散学習という方法があって良かった、つくづくおもいますこれをイノベーションの文脈で捉えてみると、京都大学の苧坂直之先生のデフォルトモードネットワークの話を思い出します散歩やお風呂などの、実は休んでいるときにこそ、脳は活性化して、さまざまな組み合わせを生み出すというお話ですが、その前提として、さまざまな情報が頭の中にあるということが必要かと思いますそのためにも、日々積み重ねていくからこそ、新たな掛け合わせのネタが蓄積されていくことになるのかもしれないなあと思います分散学習は、試験対策でもありますが、日々のデフォルトモードネットワークのスパークを生み出す秘訣なのかもしれないそんなことも思いましたということで、最強の学習法である、アクティブリコールと分散学習を組み合わせた、連続的再学習は、実はイノベーション力を育てるのにも、効果を発揮する、そんなことを思いました一言で言えば連続的再学習ノベーションそんな話をしています^^参考:本: 科学的根拠に基づく最高の勉強法 安川 康介 2024年2月15日発行 発行 株式会社KADOKAWA2025-05-1416 min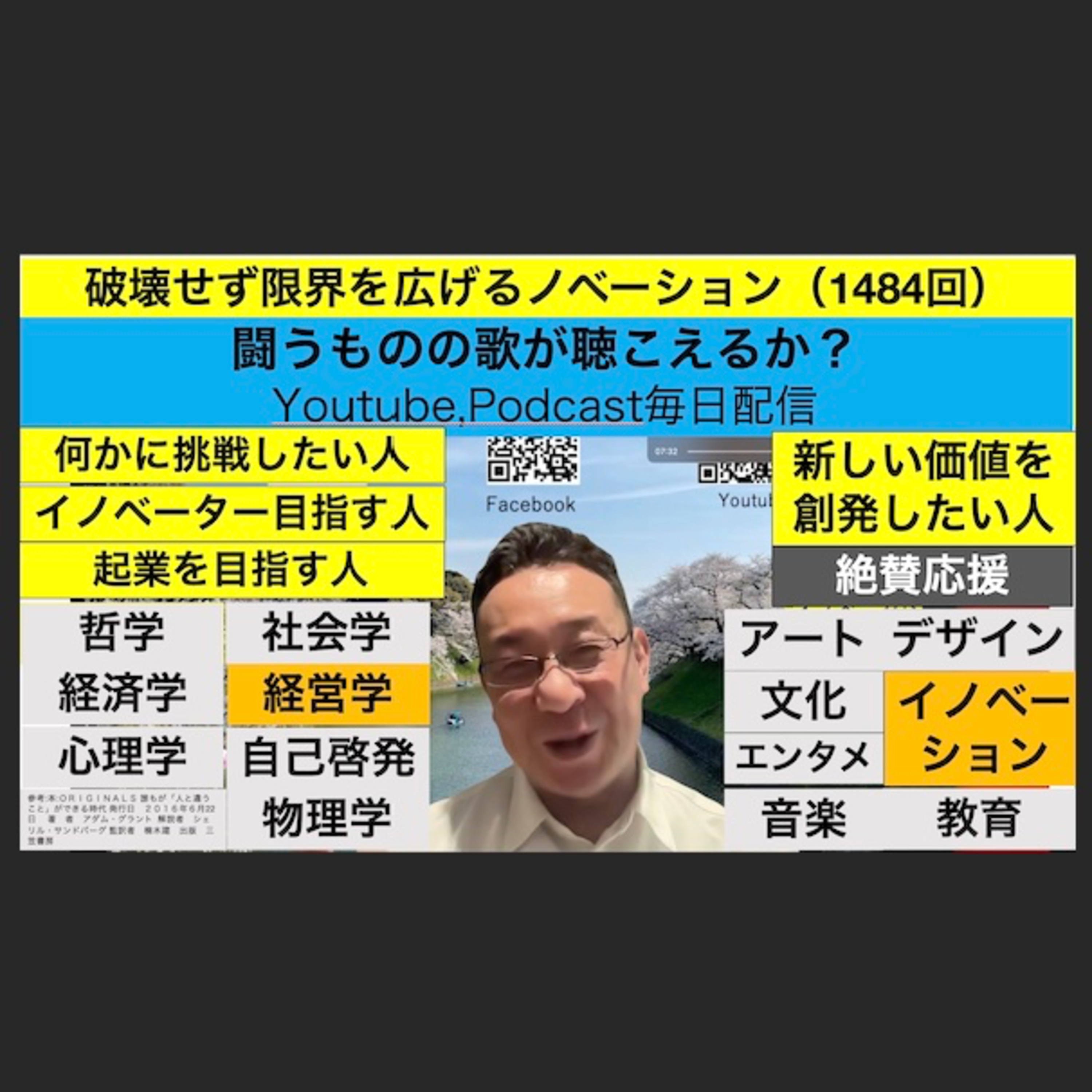 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"破壊せず限界を広げるノベーション(1484回)アダムグラントさんのオリジナルズより、とんがったソリューションをどうやって普及させるか?への学びをいただきました曰く"他者の価値観を変えさせるのはむずかしいが、自分たちの価値観と相手がすでにもっている価値観の共通点を探し、結びつけるほうがずっと簡単である。""仲間に引き込む相手とは正直に接したいところであろうが、時として、自分のアイデアを聴衆受けするものに「構成し直す」必要がある。"ライオンキングのミンコフ監督からは"「誰もがオリジナリティを求めているものですが、最適なツボというものがある。とがったオリジナリティがある程度ないと、つまらなくなります。逆にオリジナリティが強すぎると、周囲が理解するのがむずかしくなることもある。目標は限界の枠を広げることであって、限界を破壊することではないのです」 "とのこのです。そしてまとめると1、価値観の共通点を探す2、聴衆受けに構成し直す3、破壊せず枠を広げるかなと思いましたそして、ここから私は思いました1、相手の頭で考える2、限界の枠を広げる3、最適なツボから攻める1、相手の頭で考えるイノベーションの定説として、最初は上司には相談するな、というのがありますが、まさにこの罠にハマってる気がしますイノベーターたるもの、世の中にない仕組みを思いついたことで、ワクワクがとまらなくなっており、相手のことはさておいて、自分のアイディアがいかに素晴らしいかを、等々と述べる、私もよくやってしまってましたその結果、上司は頭が硬い、上司が変わらない限り、うちの会社は変われない、などという結果になることもよくあるのではないかと思いました実は、オリジナルなアイデアすごいでしょ?ということも気持ちはわかりますが、進めるための壁を乗り越えるために何が必要かを考えるということが、まずは必要と思いましたそのためには、プレゼンの極意でもありますが、まずは相手の頭の中を考えて、そしてその中にあるメリットといかにシナジーするかを、訴えるべき、というのは忘れがちだけど大切なことだなあと思いました2、限界の枠を広げる私が2013年にオープンイノベーション事業創発室を立ち上げた頃から、欧米ではFintechということが出てきていて、金融業界をディスラプトしていくと、いわれていましたその数年後、ロンドンのイベントに行った時に、衝撃を受けたのが、デイスラプティブはもう古い、これからは融合だ、的な話に大きく風向きが変わったことを思い出します今はほとんどFintech自体あまり聞かなくなりましたが、ある意味、破壊する方向から融合・融和する方向で、Fintechが金融の限界の枠を広げていくことになっていった、そんなことなのかなあと思いましたつまり、普及・浸透のためには、破壊よりも、限界を広げる戦法が、一つの有効な手段であるということかもしれないなあと思いました3、最適なツボから攻めるどのツボが最適なのかなんて最初からはわからないと思うので、結局はまずはぶち当たってから、みたいなことになるかとは思いながら私が新入社員の頃にやっていた画像通信サービスみたいに、めちゃくちゃ早かったインターネットサービスみたいなことが、死屍累々とあるもんだと思います内田和成さんの、イノベーション・トライアングルのように、技術、社会構造、心理変化が、バランスよく埋まっていかないと、うまくサービスが続かないということになると思いました早すぎても受け入れられない、遅いと先を越されている、なので、ある意味、その見極めと、Fail Fastが求められるかなとも思いましたそれでも、きっとオリジナルでイノベーターは、現状に寄り添いながらも、限界の枠を広げながらも、誰にも見えてない未来に到達するまで、諦めないのだろうなあとそんなことを思いました一言で言うとオリジナルな人は限界を破壊しない限界を広げるノベーションそんなことを思いました^^参考:本:ORIGINALS 誰もが「人と違うこと」ができる時代 発行日 2016年6月22日 著 者 アダム・グラント 解説者 シェリル・サンドバーグ 監訳者 楠木建 出版 三笠書房2025-05-1319 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"破壊せず限界を広げるノベーション(1484回)アダムグラントさんのオリジナルズより、とんがったソリューションをどうやって普及させるか?への学びをいただきました曰く"他者の価値観を変えさせるのはむずかしいが、自分たちの価値観と相手がすでにもっている価値観の共通点を探し、結びつけるほうがずっと簡単である。""仲間に引き込む相手とは正直に接したいところであろうが、時として、自分のアイデアを聴衆受けするものに「構成し直す」必要がある。"ライオンキングのミンコフ監督からは"「誰もがオリジナリティを求めているものですが、最適なツボというものがある。とがったオリジナリティがある程度ないと、つまらなくなります。逆にオリジナリティが強すぎると、周囲が理解するのがむずかしくなることもある。目標は限界の枠を広げることであって、限界を破壊することではないのです」 "とのこのです。そしてまとめると1、価値観の共通点を探す2、聴衆受けに構成し直す3、破壊せず枠を広げるかなと思いましたそして、ここから私は思いました1、相手の頭で考える2、限界の枠を広げる3、最適なツボから攻める1、相手の頭で考えるイノベーションの定説として、最初は上司には相談するな、というのがありますが、まさにこの罠にハマってる気がしますイノベーターたるもの、世の中にない仕組みを思いついたことで、ワクワクがとまらなくなっており、相手のことはさておいて、自分のアイディアがいかに素晴らしいかを、等々と述べる、私もよくやってしまってましたその結果、上司は頭が硬い、上司が変わらない限り、うちの会社は変われない、などという結果になることもよくあるのではないかと思いました実は、オリジナルなアイデアすごいでしょ?ということも気持ちはわかりますが、進めるための壁を乗り越えるために何が必要かを考えるということが、まずは必要と思いましたそのためには、プレゼンの極意でもありますが、まずは相手の頭の中を考えて、そしてその中にあるメリットといかにシナジーするかを、訴えるべき、というのは忘れがちだけど大切なことだなあと思いました2、限界の枠を広げる私が2013年にオープンイノベーション事業創発室を立ち上げた頃から、欧米ではFintechということが出てきていて、金融業界をディスラプトしていくと、いわれていましたその数年後、ロンドンのイベントに行った時に、衝撃を受けたのが、デイスラプティブはもう古い、これからは融合だ、的な話に大きく風向きが変わったことを思い出します今はほとんどFintech自体あまり聞かなくなりましたが、ある意味、破壊する方向から融合・融和する方向で、Fintechが金融の限界の枠を広げていくことになっていった、そんなことなのかなあと思いましたつまり、普及・浸透のためには、破壊よりも、限界を広げる戦法が、一つの有効な手段であるということかもしれないなあと思いました3、最適なツボから攻めるどのツボが最適なのかなんて最初からはわからないと思うので、結局はまずはぶち当たってから、みたいなことになるかとは思いながら私が新入社員の頃にやっていた画像通信サービスみたいに、めちゃくちゃ早かったインターネットサービスみたいなことが、死屍累々とあるもんだと思います内田和成さんの、イノベーション・トライアングルのように、技術、社会構造、心理変化が、バランスよく埋まっていかないと、うまくサービスが続かないということになると思いました早すぎても受け入れられない、遅いと先を越されている、なので、ある意味、その見極めと、Fail Fastが求められるかなとも思いましたそれでも、きっとオリジナルでイノベーターは、現状に寄り添いながらも、限界の枠を広げながらも、誰にも見えてない未来に到達するまで、諦めないのだろうなあとそんなことを思いました一言で言うとオリジナルな人は限界を破壊しない限界を広げるノベーションそんなことを思いました^^参考:本:ORIGINALS 誰もが「人と違うこと」ができる時代 発行日 2016年6月22日 著 者 アダム・グラント 解説者 シェリル・サンドバーグ 監訳者 楠木建 出版 三笠書房2025-05-1319 min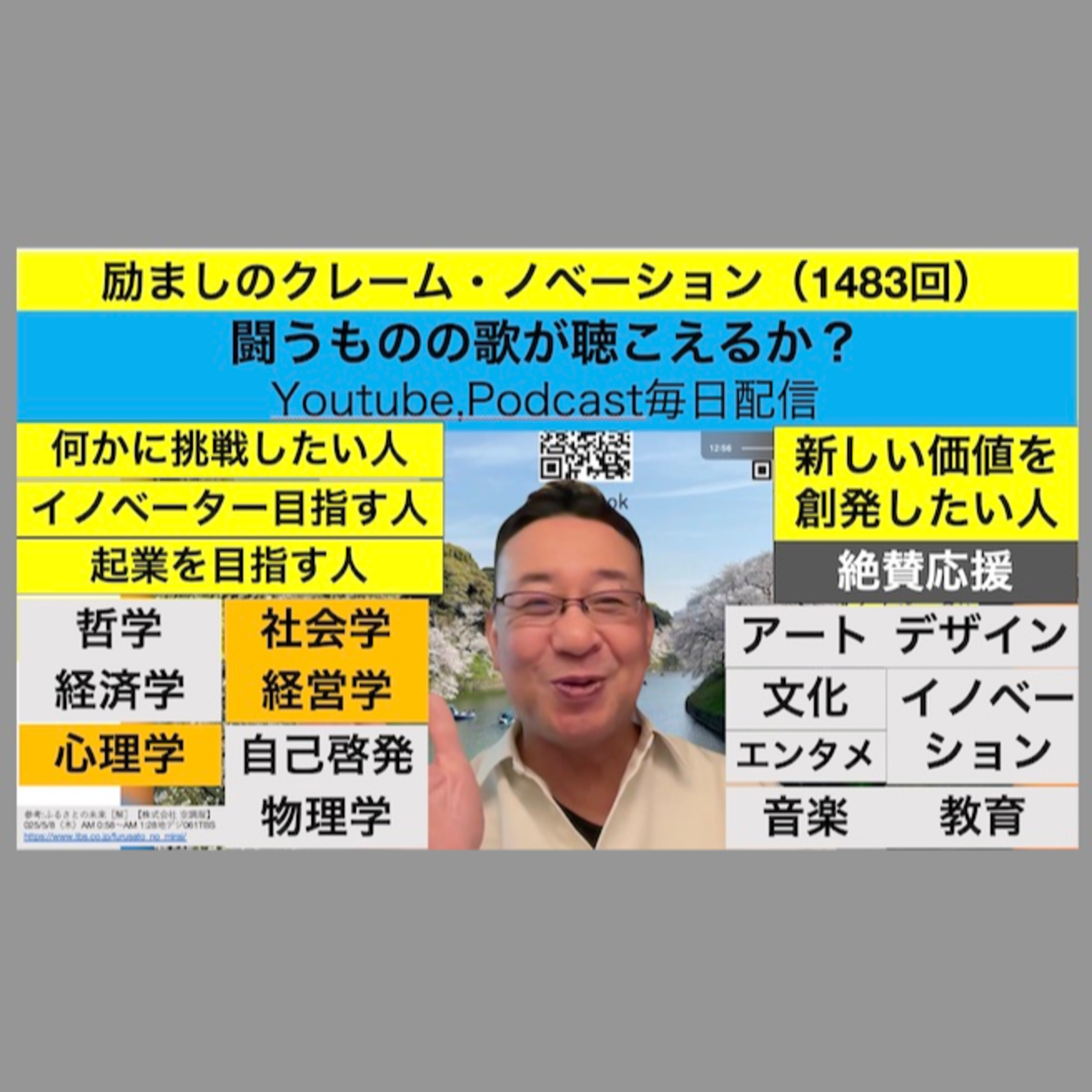 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"励ましのクレーム・ノベーション(1483回)年間100万着を超える大ヒットとなった「空調服」を、当初は売れなかったところから、決して諦めなかった理由に感動しました協力をされている株式会社セフト研究所の取締役 胡桃沢武雄さん曰く"故障で返ってくるものがあるんですよ、いっぱいあるの。ところがそこにみんなメモが書いてあるんだよね。そこに.こんな素晴らしいものはない。もう着たら絶対離せられないと"また、株式会社空調服 代表取締役会長 市ヶ谷弘司さん曰く"これは物凄くいいから、何とかもっと壊れないモノを作ってくれとかですね。励ましのクレームみたいのが多かったんですよね"ここから私は思いました1、クレームはイノベーションの源泉2、共感と愛着が行動を生む3、プロシューマーとの共創上着の中にファンがついていて、それで風を送ることによって、劇的に涼しくなる「空調服」は、今では工事現場などでは、当たり前に見られるようになってますし、普通の方も来てられるのを見かけるようになってきました実は、ソニーから独立されて、開発にものすごく苦労をされていたと言うことに、驚いたと共に、決して諦めなかった秘密を教えて頂き感動しました1、クレームはイノベーションの源泉私は会社員時代に営業をやっていたこともあるのですが、日本全国飛び回ってクレームへの対応もしていました。その頃は自分のことを、謝り侍、と呼んでいたくらい謝り続けていたわけなのですが、でも中には、こっぴどく叱られた後に、飲み会を開いて頂き、期待してるからこその、厳しい言葉なのだ、と言うことを身をもって体験もしました経営学者のピーター・ドラッカーが、『イノベーションと企業家精神』で「イノベーションの機会は、しばしば顧客の声の中に潜んでいる。満足していない顧客ほど、実はその製品を大切に思っている場合がある。」と言われているように、実はその製品のことを思ってくれてるからこその、厳しい言葉がある、と言うことを、意識しておくことも大切だなあと思いましたそして、そこで受けたクレームの中にこそ、これからのステップアップにつながる事柄が宝のように潜んでもいる、そんなことを思いました2、共感と愛着がクレームを生むクレームの中には、感情的に怒られることもあって、精神的にも辛い時もたくさんありました最近では、カスハラ、みたいな話も出てきていて、節度を持つ動きもあったり、アファーメーションのように肯定しながら自分の意見を伝えるような手法も随分浸透してきたように思えますが、心理学者のダニエル・カーネマンが、『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?』にて「人間の判断は感情に大きく依存する。使い慣れたモノに対する感情的価値は、それが合理的かどうか以上に、判断や行動の動機となる」と言われていますように、感情が判断の大きな割合を占めると言うことがあると思いますただ、実はネガティブな感情に見えても、その裏には、実は、期待をしていたかは、または期待をしているからこそ、より強く言われているということも、裏返しとしてあると思いますつまり、感情的にクレームを言われた時には、それだけの期待が込められていると言うことも、実は含まれていると、肯定的に捉えることも大事かなと思いました3、プロシューマーとの共創ずいぶん前に、社会学者のアルビン・トフラー『第三の波』の中で「未来の経済では、消費者自身が生産にも関わる“プロシューマー”となる。企業はこの新しいユーザーの形と協働しなければならない。」ということがもてはやされた時期があったなあと思い出しましたここから、コミュニティの中での意見の収集や一緒に開発することや、クラウドファンディングで応援団を募ることや、少し前には、プロセスエコノミーなどと、作る過程さえも共有して一緒にビジネスへ携わってもらうなども出てきてると思います空調服への励ましのクレームという話は、まさに共に作ってくれるプロシューマー達の声ということも言えると思いましたある意味、ユーザーや消費者を自らの“仲間"に引き込むことができれば、そこに圧倒的な熱狂を作ることができればビジネス的にも精神的にも辛いイノベーション活動には、大きな味方になってもらえると思いましたユーザーの立場から考えると、応援したい人には、励ましのクレームを出すということが、その印になるかもしれないしイノベーション活動で、心が折れそうなクレームをたくさん頂いても、その中には必ず仲間として応援する人が含まれていると思えれば成功したどのイノベーターも必ずいう、諦めなかったから、を実現することができるかもしれないと、思いました一言で言えば励ましのクレーム・ノベーションそんな話をしています^^参考:ふるさとの未来[解]【株式会社 空調服】025/5/8(木)AM 0:58~AM 1:28地デジ061TBShttps://www.tbs.co.jp/furusato_no_mirai/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/powyx2VqorE2025-05-1220 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"励ましのクレーム・ノベーション(1483回)年間100万着を超える大ヒットとなった「空調服」を、当初は売れなかったところから、決して諦めなかった理由に感動しました協力をされている株式会社セフト研究所の取締役 胡桃沢武雄さん曰く"故障で返ってくるものがあるんですよ、いっぱいあるの。ところがそこにみんなメモが書いてあるんだよね。そこに.こんな素晴らしいものはない。もう着たら絶対離せられないと"また、株式会社空調服 代表取締役会長 市ヶ谷弘司さん曰く"これは物凄くいいから、何とかもっと壊れないモノを作ってくれとかですね。励ましのクレームみたいのが多かったんですよね"ここから私は思いました1、クレームはイノベーションの源泉2、共感と愛着が行動を生む3、プロシューマーとの共創上着の中にファンがついていて、それで風を送ることによって、劇的に涼しくなる「空調服」は、今では工事現場などでは、当たり前に見られるようになってますし、普通の方も来てられるのを見かけるようになってきました実は、ソニーから独立されて、開発にものすごく苦労をされていたと言うことに、驚いたと共に、決して諦めなかった秘密を教えて頂き感動しました1、クレームはイノベーションの源泉私は会社員時代に営業をやっていたこともあるのですが、日本全国飛び回ってクレームへの対応もしていました。その頃は自分のことを、謝り侍、と呼んでいたくらい謝り続けていたわけなのですが、でも中には、こっぴどく叱られた後に、飲み会を開いて頂き、期待してるからこその、厳しい言葉なのだ、と言うことを身をもって体験もしました経営学者のピーター・ドラッカーが、『イノベーションと企業家精神』で「イノベーションの機会は、しばしば顧客の声の中に潜んでいる。満足していない顧客ほど、実はその製品を大切に思っている場合がある。」と言われているように、実はその製品のことを思ってくれてるからこその、厳しい言葉がある、と言うことを、意識しておくことも大切だなあと思いましたそして、そこで受けたクレームの中にこそ、これからのステップアップにつながる事柄が宝のように潜んでもいる、そんなことを思いました2、共感と愛着がクレームを生むクレームの中には、感情的に怒られることもあって、精神的にも辛い時もたくさんありました最近では、カスハラ、みたいな話も出てきていて、節度を持つ動きもあったり、アファーメーションのように肯定しながら自分の意見を伝えるような手法も随分浸透してきたように思えますが、心理学者のダニエル・カーネマンが、『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?』にて「人間の判断は感情に大きく依存する。使い慣れたモノに対する感情的価値は、それが合理的かどうか以上に、判断や行動の動機となる」と言われていますように、感情が判断の大きな割合を占めると言うことがあると思いますただ、実はネガティブな感情に見えても、その裏には、実は、期待をしていたかは、または期待をしているからこそ、より強く言われているということも、裏返しとしてあると思いますつまり、感情的にクレームを言われた時には、それだけの期待が込められていると言うことも、実は含まれていると、肯定的に捉えることも大事かなと思いました3、プロシューマーとの共創ずいぶん前に、社会学者のアルビン・トフラー『第三の波』の中で「未来の経済では、消費者自身が生産にも関わる“プロシューマー”となる。企業はこの新しいユーザーの形と協働しなければならない。」ということがもてはやされた時期があったなあと思い出しましたここから、コミュニティの中での意見の収集や一緒に開発することや、クラウドファンディングで応援団を募ることや、少し前には、プロセスエコノミーなどと、作る過程さえも共有して一緒にビジネスへ携わってもらうなども出てきてると思います空調服への励ましのクレームという話は、まさに共に作ってくれるプロシューマー達の声ということも言えると思いましたある意味、ユーザーや消費者を自らの“仲間"に引き込むことができれば、そこに圧倒的な熱狂を作ることができればビジネス的にも精神的にも辛いイノベーション活動には、大きな味方になってもらえると思いましたユーザーの立場から考えると、応援したい人には、励ましのクレームを出すということが、その印になるかもしれないしイノベーション活動で、心が折れそうなクレームをたくさん頂いても、その中には必ず仲間として応援する人が含まれていると思えれば成功したどのイノベーターも必ずいう、諦めなかったから、を実現することができるかもしれないと、思いました一言で言えば励ましのクレーム・ノベーションそんな話をしています^^参考:ふるさとの未来[解]【株式会社 空調服】025/5/8(木)AM 0:58~AM 1:28地デジ061TBShttps://www.tbs.co.jp/furusato_no_mirai/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/powyx2VqorE2025-05-1220 min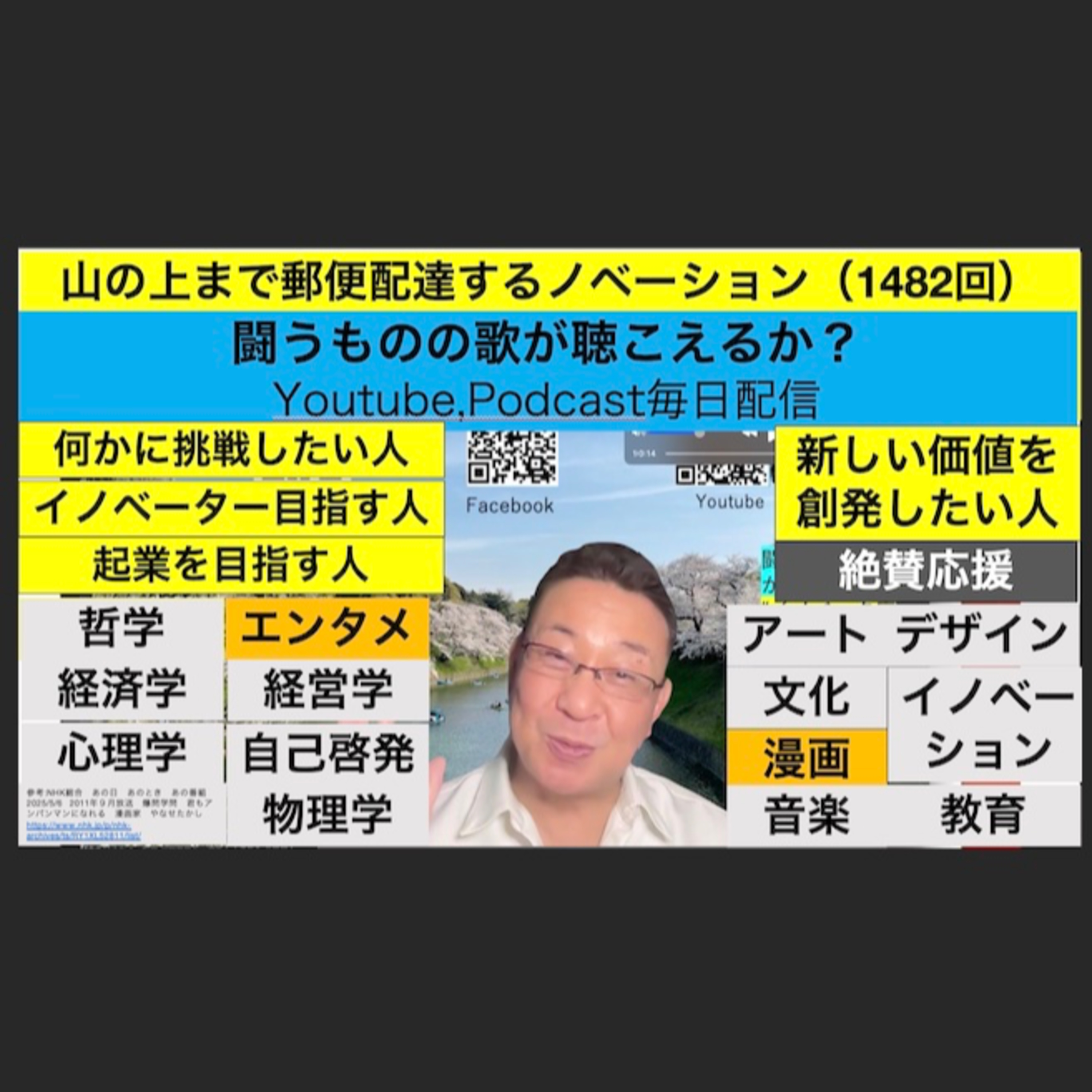 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"山の上まで郵便配達するノベーション(1482回)アンパンマンの作者 漫画家 やなせたかしさんが、作品を作る理由は?への答えに感動しました曰く"僕はですね、山の上までですね、郵便配達する人に会ったことがあるんですよそうしてね、あなたねぇ、大変なんじゃないんですか?山は天気の悪い時もあるしね、そこへですね、山の上に一軒しか家がないんです。そこへだから郵便を配達する、こんなねぇ、仕事をやってあなたいいんですか?あたしはこの仕事が大好きで、他の人はこの山へ登るのにお金払ってくる私はこの山へ登ってお金をもらえる、四季折々楽しめる、そして私が山の上へ行くとですね、そこにいる人がみんなすごい喜ぶっていうねそれは作家にしても何にしても皆、同じなの。全ての芸術全部そうなんだ自分のやったことで人が喜ぶっていうことで、本人が嬉しい"ここから私は思いました1、自己決定理論2、フロー体験3、イノベーター3つのフレーム爆問学問は、めちゃくちゃ好きな番組だったので、爆笑問題とやなせさんのと話を、めちゃくちゃ楽しく思い出させて頂きました。アンパンマンの歌を朗々と歌うやなせさんは、まさにアンパンマンスピリッツそのものを感じてうるうるしてしまいました1、自己決定理論この郵便局員のお話は、給与や損得に関する外発的な動機から逸脱して、自分自身が本当に幸せになれることは何か?という内発的動機から、生まれた行動だなあと思いましたデシ&ライアン(2000)さんの「自己決定理論」では、「自律性・有能感・関係性」が人の内発的動機を高めるとされており、その山に住む人との関係性、そして喜びをつくりだしてる有能感、そこから生まれてくる自律性まさに、自らのパッションの源に沿った自己決定の結果としての行動だなあと思いました。もっと給与が良くて楽できるような仕事はたくさんあるはずなのに、自分が本当に幸せなことは何か?に正直に生きる、そんな生き方ができたら素敵だなあと思いました2、フロー体験挑戦軸とスキル軸を高めていくと、没入していき幸せ感がマシマシになる、チクセントミハイさんの没入するフロー体験のお話は、何度もしていますが、実はそこには、他人が喜んでくれる、ということがもう一つ隠されていますミハイ・チクセントミハイ(1990)『フロー体験 喜びの現象学』によると、「創造的な人々は、自分が愛する行動に没頭し、それが他者にとっても意味を持つと感じることで最も満たされる。」と言われており実は没入体験には、他者を喜ばせるという重要な要素があるので、この郵便局員さんは、実はフロー体験に入ってるということもできると思いました3、イノベーター3つのフレーム私がいつもお話ししている、イノベーターには必ず3つのフレームがあって、まずは自らの情熱で誰かのペインを解決することから始まり、そして1人ではできないことを仲間と共に実施し、最終的にはその人だけではなく、周りの人たちも巻き込んだ幸せを作っていくというフレームに今回の郵便局員さんのお話も、とても親和性が高いなあと思いましたやなせさんが、作家も全ての芸術がそうなのだ、と言われている通り、最初は誰かの郵便物を届けてあげるという情熱の利他パッションから始まり、それを郵便局員という仲間たちとの組織的な活動により、その山の人たちみんなが喜んでくれる活動となっている大義と結びついていくということが、郵便局員さん自身の幸せに通じてるのだと思いましたつまり、誰かに情熱とともき新しい価値を、誰か仲間と共に届けることで、そこにいるいろんな人たちが喜んでもらえる大義になる、それこそが、イノベーターの活動であり、そして、生き甲斐につながる活動になる、そんなことを改めて思いました一言で言うと山の上まで郵便配達するノベーションそんなことを思いました^^参考:NHK総合 あの日 あのとき あの番組 2025/5/6 2011年9月放送 爆問学問 君もアンパンマンになれる 漫画家 やなせたかし https://www.nhk.jp/p/nhk-archives/ts/RY1XL52811/list/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/4NOZ21OJCyk2025-05-1118 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"山の上まで郵便配達するノベーション(1482回)アンパンマンの作者 漫画家 やなせたかしさんが、作品を作る理由は?への答えに感動しました曰く"僕はですね、山の上までですね、郵便配達する人に会ったことがあるんですよそうしてね、あなたねぇ、大変なんじゃないんですか?山は天気の悪い時もあるしね、そこへですね、山の上に一軒しか家がないんです。そこへだから郵便を配達する、こんなねぇ、仕事をやってあなたいいんですか?あたしはこの仕事が大好きで、他の人はこの山へ登るのにお金払ってくる私はこの山へ登ってお金をもらえる、四季折々楽しめる、そして私が山の上へ行くとですね、そこにいる人がみんなすごい喜ぶっていうねそれは作家にしても何にしても皆、同じなの。全ての芸術全部そうなんだ自分のやったことで人が喜ぶっていうことで、本人が嬉しい"ここから私は思いました1、自己決定理論2、フロー体験3、イノベーター3つのフレーム爆問学問は、めちゃくちゃ好きな番組だったので、爆笑問題とやなせさんのと話を、めちゃくちゃ楽しく思い出させて頂きました。アンパンマンの歌を朗々と歌うやなせさんは、まさにアンパンマンスピリッツそのものを感じてうるうるしてしまいました1、自己決定理論この郵便局員のお話は、給与や損得に関する外発的な動機から逸脱して、自分自身が本当に幸せになれることは何か?という内発的動機から、生まれた行動だなあと思いましたデシ&ライアン(2000)さんの「自己決定理論」では、「自律性・有能感・関係性」が人の内発的動機を高めるとされており、その山に住む人との関係性、そして喜びをつくりだしてる有能感、そこから生まれてくる自律性まさに、自らのパッションの源に沿った自己決定の結果としての行動だなあと思いました。もっと給与が良くて楽できるような仕事はたくさんあるはずなのに、自分が本当に幸せなことは何か?に正直に生きる、そんな生き方ができたら素敵だなあと思いました2、フロー体験挑戦軸とスキル軸を高めていくと、没入していき幸せ感がマシマシになる、チクセントミハイさんの没入するフロー体験のお話は、何度もしていますが、実はそこには、他人が喜んでくれる、ということがもう一つ隠されていますミハイ・チクセントミハイ(1990)『フロー体験 喜びの現象学』によると、「創造的な人々は、自分が愛する行動に没頭し、それが他者にとっても意味を持つと感じることで最も満たされる。」と言われており実は没入体験には、他者を喜ばせるという重要な要素があるので、この郵便局員さんは、実はフロー体験に入ってるということもできると思いました3、イノベーター3つのフレーム私がいつもお話ししている、イノベーターには必ず3つのフレームがあって、まずは自らの情熱で誰かのペインを解決することから始まり、そして1人ではできないことを仲間と共に実施し、最終的にはその人だけではなく、周りの人たちも巻き込んだ幸せを作っていくというフレームに今回の郵便局員さんのお話も、とても親和性が高いなあと思いましたやなせさんが、作家も全ての芸術がそうなのだ、と言われている通り、最初は誰かの郵便物を届けてあげるという情熱の利他パッションから始まり、それを郵便局員という仲間たちとの組織的な活動により、その山の人たちみんなが喜んでくれる活動となっている大義と結びついていくということが、郵便局員さん自身の幸せに通じてるのだと思いましたつまり、誰かに情熱とともき新しい価値を、誰か仲間と共に届けることで、そこにいるいろんな人たちが喜んでもらえる大義になる、それこそが、イノベーターの活動であり、そして、生き甲斐につながる活動になる、そんなことを改めて思いました一言で言うと山の上まで郵便配達するノベーションそんなことを思いました^^参考:NHK総合 あの日 あのとき あの番組 2025/5/6 2011年9月放送 爆問学問 君もアンパンマンになれる 漫画家 やなせたかし https://www.nhk.jp/p/nhk-archives/ts/RY1XL52811/list/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/4NOZ21OJCyk2025-05-1118 min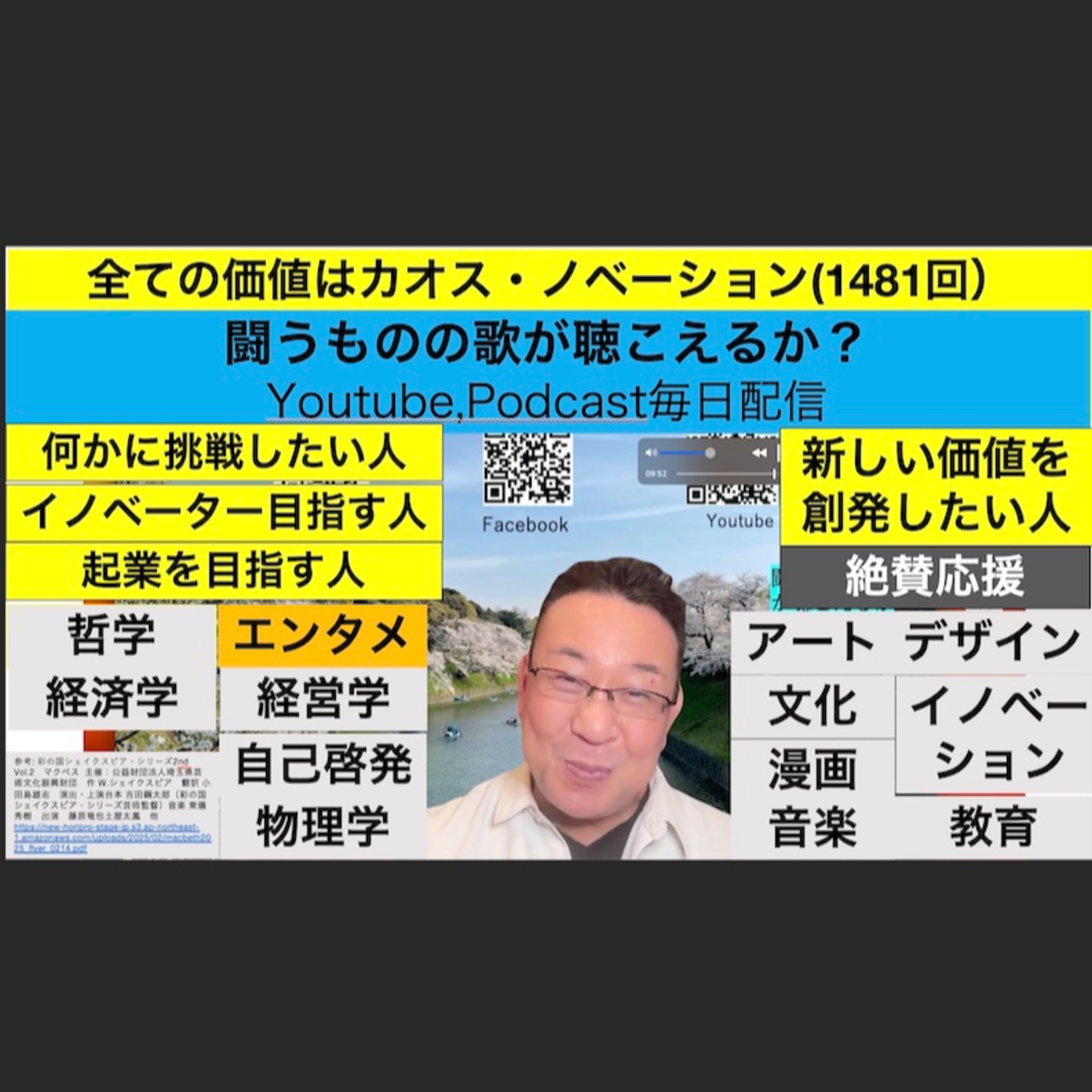 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"全ての価値はカオス・ノベーション(1481回)蜷川幸雄さんが立ち上げられた、彩の国シェイクスピア・シリーズの、後継をされている吉田鋼太郎さん芸術監督のマクベスに、衝撃を受けたと同時に、沢山のことを考えさせられました翻訳を務められた小田島雄志さん曰く"人間が生きていく中で、何か大きな障害やショックを受けるとどうなるか。まず価値観が崩壊します。例えば人殺しは良くないに決まっているけれど、戦争では人を殺すと勲章がもらえる。人を殺すのは良のか、わからなくなる。 本来、自分の中に持っているはずの善悪の価値基準が、わからなくなるわけです。それは「価値の混沌=カオス化」であり、僕は「内的カオス」と呼んでいます。同時に、自分で自分というものがわからなくなってくる。このように何らかのショックを受けて、何がなんだかわからなくなった人間がどう行動するのかを、シェイクスピアは様々に書き分けました。"ここから私は思いました1、真実のカオス2、価値のカオス3、自分のカオス鬼気迫るという言う方が相応しいと思わせて頂いた藤原竜也さんのマクベスは、狂気と迫力と、まさにパッションが弾ける、素晴らしい演技でした。また、それに呼応するように土屋太鳳さんのマクベス夫人は、勝るとも劣らない激情と愛情のパッションが炸裂する、2人で凄まじいドラマを観させて頂き、感動と共に大満足でしたシェークスピアのマクベスという、世界的に王道な演劇を、吉田鋼太郎さん率いるスペシャルな俳優、そして演出、脚本、さらに東儀秀樹さんの音楽で観れたことは、おそらく一生忘れられないほどに、本当に幸せででした翻訳をされた小田島雄志さんの言葉に、マクベスの物語の本質としての、「内的カオス」という、まさに人間の本質が抉り取られてることに、深く考えさせられました1、真実のカオス今も様々な地域で紛争が行われていて、そして様々な書籍やメディアを見るにつれ、本当の真実はどこにあるのか?と、全くわからなくなりますニーチェの解釈論における、真実はない、あるのは解釈だ、ということは理解してるのですが、しかしながら、やってることをやっていない、やっていないことをやっている、ということが捻じ曲げられる世界には、やはりカオスとしか言いようのない憤りを感じますこのマクベスが書かれた時代からそんなことはあたりまえのようにあり、またSNSが発展してリアルに映像が現場から流せるようになったとて、それは全く変わらないということに、人間は変われないのか、という思いと、カオスでどう生きるのかを、考えさせられました2、価値のカオス勧善懲悪な物語は、最後は悪が必ず破れてスッキリするので、そんな映画も大好きなのですが、現実の世界では、完全な悪と思っている方にも、実はそこにいる人たちは自分たちの正義のために真摯に生きている進撃の巨人にしても、レミゼラブルにしても、そこで生きる人たちの苦悩が、とても共感できて、そしてどうしようもなさや、切なさに涙してしまいますでもその違和感に気づくことが、実はイノベーションの種の大きな一つかもしれないと思います。そんな世界の違和感を、仕方がないよね、ではなく、それって何でずっとそうなの?という、Why not yetをいえるかどうか、それが大事だと思いますそれを言えた人から、実は、価値は、世の中に固定されているものではなく、カオスになっているので、いくらでもひっくり返ることもあるし、ひっくり返すこともできる、そこに実は希望があるのかもしれないなあと、思いました3、自分のカオス自分自身が信じていたことが、ある日突然、ひっくり返る、そういうことが、まさにマクベスの時代には、よく起こっていたのかもしれないと思いますしかし、ほんの少し前の現代の日本においても、それは起こっていた訳で、それを知らない世代には、計り知れないショックがあったのだろうなあと、思います自分自身がそんなことに遭遇した際には、どう行動するのかは全く想像もつきません。ヴィクトールフランクの「夜と霧」のように、置かれた状況には必ず意味がある意味があると思いながら、自らのパッションの源を見つめ続けて、そしてそれに固執せずに問い続けて、自分の解釈を最後の1%でも入れていけるかさらには、「弱い責任感」のもとに、信頼のおける仲間をあらかじめ持てるようにしながら、積極的に頼りながらも、同じようにカオスを感じながら、問い続けていく、みたいなことを、考えてました全てはカオスだからこそ、そこに光はある、そんなことを考えさせて頂きました一言で言うと全ての価値はカオス・ノベーションそんなことを思いました^^参考: 彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd Vol.2マクベス 主催:公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 作 W.シェイクスピア 翻訳 小田島雄志 演出・上演台本 吉田鋼太郎(彩の国シェイクスピア・シリーズ芸術監督)音楽 東儀秀樹 出演 藤原竜也土屋太鳳 他 https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/02/macbeth2025_flyer_0214.pdf動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/f-YHwVdNdgQ2025-05-1021 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"全ての価値はカオス・ノベーション(1481回)蜷川幸雄さんが立ち上げられた、彩の国シェイクスピア・シリーズの、後継をされている吉田鋼太郎さん芸術監督のマクベスに、衝撃を受けたと同時に、沢山のことを考えさせられました翻訳を務められた小田島雄志さん曰く"人間が生きていく中で、何か大きな障害やショックを受けるとどうなるか。まず価値観が崩壊します。例えば人殺しは良くないに決まっているけれど、戦争では人を殺すと勲章がもらえる。人を殺すのは良のか、わからなくなる。 本来、自分の中に持っているはずの善悪の価値基準が、わからなくなるわけです。それは「価値の混沌=カオス化」であり、僕は「内的カオス」と呼んでいます。同時に、自分で自分というものがわからなくなってくる。このように何らかのショックを受けて、何がなんだかわからなくなった人間がどう行動するのかを、シェイクスピアは様々に書き分けました。"ここから私は思いました1、真実のカオス2、価値のカオス3、自分のカオス鬼気迫るという言う方が相応しいと思わせて頂いた藤原竜也さんのマクベスは、狂気と迫力と、まさにパッションが弾ける、素晴らしい演技でした。また、それに呼応するように土屋太鳳さんのマクベス夫人は、勝るとも劣らない激情と愛情のパッションが炸裂する、2人で凄まじいドラマを観させて頂き、感動と共に大満足でしたシェークスピアのマクベスという、世界的に王道な演劇を、吉田鋼太郎さん率いるスペシャルな俳優、そして演出、脚本、さらに東儀秀樹さんの音楽で観れたことは、おそらく一生忘れられないほどに、本当に幸せででした翻訳をされた小田島雄志さんの言葉に、マクベスの物語の本質としての、「内的カオス」という、まさに人間の本質が抉り取られてることに、深く考えさせられました1、真実のカオス今も様々な地域で紛争が行われていて、そして様々な書籍やメディアを見るにつれ、本当の真実はどこにあるのか?と、全くわからなくなりますニーチェの解釈論における、真実はない、あるのは解釈だ、ということは理解してるのですが、しかしながら、やってることをやっていない、やっていないことをやっている、ということが捻じ曲げられる世界には、やはりカオスとしか言いようのない憤りを感じますこのマクベスが書かれた時代からそんなことはあたりまえのようにあり、またSNSが発展してリアルに映像が現場から流せるようになったとて、それは全く変わらないということに、人間は変われないのか、という思いと、カオスでどう生きるのかを、考えさせられました2、価値のカオス勧善懲悪な物語は、最後は悪が必ず破れてスッキリするので、そんな映画も大好きなのですが、現実の世界では、完全な悪と思っている方にも、実はそこにいる人たちは自分たちの正義のために真摯に生きている進撃の巨人にしても、レミゼラブルにしても、そこで生きる人たちの苦悩が、とても共感できて、そしてどうしようもなさや、切なさに涙してしまいますでもその違和感に気づくことが、実はイノベーションの種の大きな一つかもしれないと思います。そんな世界の違和感を、仕方がないよね、ではなく、それって何でずっとそうなの?という、Why not yetをいえるかどうか、それが大事だと思いますそれを言えた人から、実は、価値は、世の中に固定されているものではなく、カオスになっているので、いくらでもひっくり返ることもあるし、ひっくり返すこともできる、そこに実は希望があるのかもしれないなあと、思いました3、自分のカオス自分自身が信じていたことが、ある日突然、ひっくり返る、そういうことが、まさにマクベスの時代には、よく起こっていたのかもしれないと思いますしかし、ほんの少し前の現代の日本においても、それは起こっていた訳で、それを知らない世代には、計り知れないショックがあったのだろうなあと、思います自分自身がそんなことに遭遇した際には、どう行動するのかは全く想像もつきません。ヴィクトールフランクの「夜と霧」のように、置かれた状況には必ず意味がある意味があると思いながら、自らのパッションの源を見つめ続けて、そしてそれに固執せずに問い続けて、自分の解釈を最後の1%でも入れていけるかさらには、「弱い責任感」のもとに、信頼のおける仲間をあらかじめ持てるようにしながら、積極的に頼りながらも、同じようにカオスを感じながら、問い続けていく、みたいなことを、考えてました全てはカオスだからこそ、そこに光はある、そんなことを考えさせて頂きました一言で言うと全ての価値はカオス・ノベーションそんなことを思いました^^参考: 彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd Vol.2マクベス 主催:公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 作 W.シェイクスピア 翻訳 小田島雄志 演出・上演台本 吉田鋼太郎(彩の国シェイクスピア・シリーズ芸術監督)音楽 東儀秀樹 出演 藤原竜也土屋太鳳 他 https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/02/macbeth2025_flyer_0214.pdf動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/f-YHwVdNdgQ2025-05-1021 min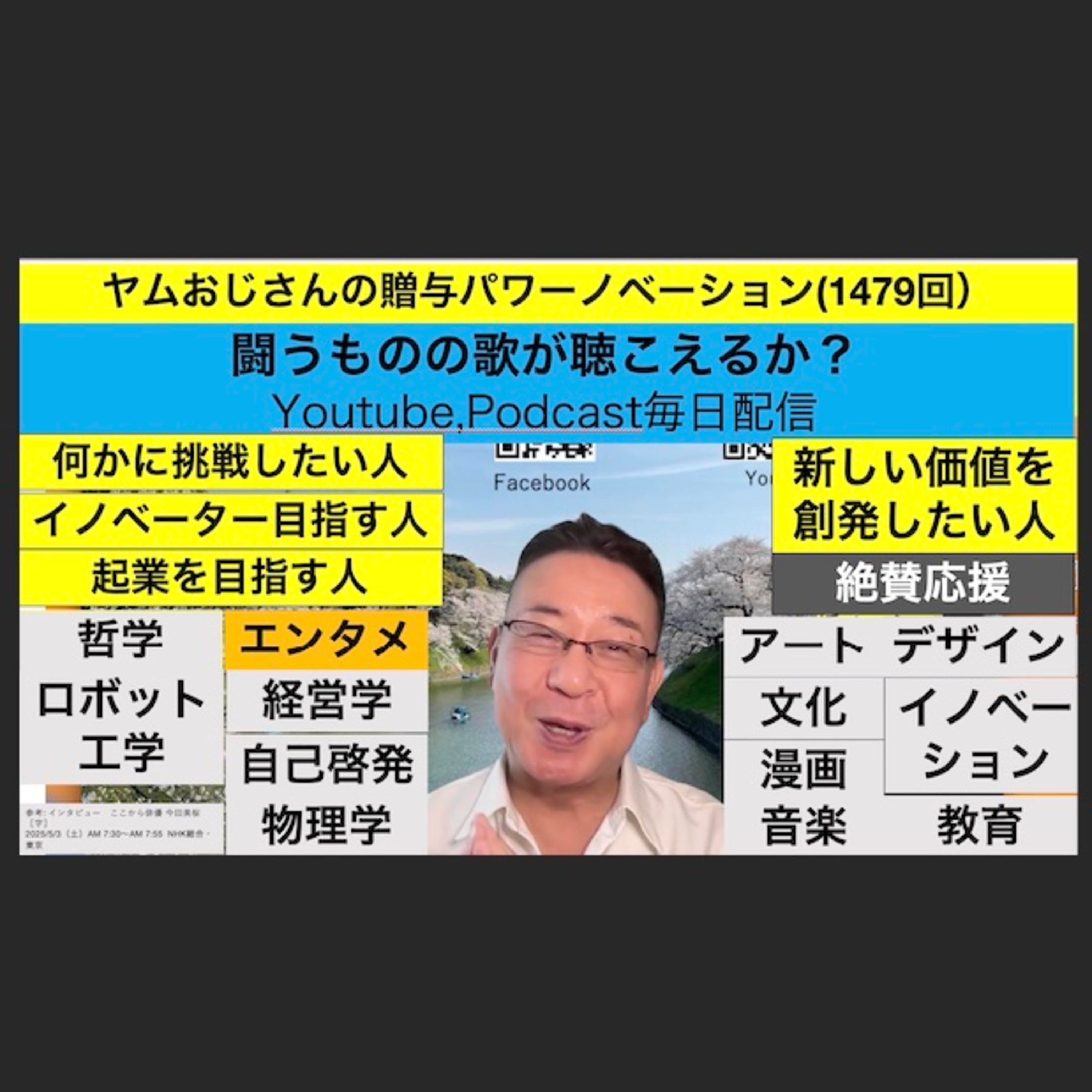 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"子供の力を信じるノベーション(1480回)40周年を迎える名作ミュージカルのアニーに、めちゃくちゃ感動して、学ぶべきところが沢山ありました以下のようなストーリーから始まります"舞台は1933年のニューヨーク。世界大恐慌直後の街は、仕事も住む家もない人であふれていました。誰もが希望を失っているなか、11歳の女の子アニーだけは元気いっぱい。11年前、孤児院の前に置き去りにされたというのに、いつか両親が迎えに来ると信じて、逆境にひるむことなく前向きに生きています。"ここから私は思いました1、希望の力2、選択する力3、子供の力1、希望の力何よりも、子供たちが歌、踊り、そして演技と、素晴らしい活躍を至る所で知りするので、素直でまっすぐな歌声や、一生懸命な姿に、それだけで涙が溢れましたこのミュージカルに貫かれているのは、アニーが大変な境遇におかれながらも、それを楽しもうとしている姿にあって、それは、ありふれた言葉になってしまいますが、"希望"と言うことを、最後まで諦めずに行動したことかと思いました「希望とは、現実的でないことを信じることではなく、未来を形づくる行為そのものである」とは、エルンスト・ブロッホが『希望の原理』で言ってることですがイノベーターは、未来への行動に移せるかどうか、そこに鍵があるそんなことを教えて頂きました2、選択する力◯◯ガチャみたいなことが言われたこともありましたが、誰もがおかれた境遇をよろしくなく思うことがあると思いますが、アニーはそんな境遇や状況をむしろ楽しもうとする、そんなマインドセットが眩しいですニーチェの解釈論のように、最後の選択は、実は自分に委ねられている、真実はなくて、実は解釈しかないのだ、ということを、思い出させてくれます「人間の最大の自由は、自分に与えられた条件の中で、自分の態度を選ぶ自由である」とヴィクトール・フランクルが『夜と霧』で言われています現実の中で自分には自由がある、最後の最後で選択できるか、簡単ではないですが、そんなことを思わせて頂きました3、子供の力このミュージカルには、たくさんの子どもが出てきますが、そのまっすぐな歌声と、懸命な演技、それ自体に涙が出てきました。実は観に行った日は、一つのチームの東京の千穐楽だったので、カーテンコールの後にご挨拶があったのですが、キーマンとなる大人の1人の藤本隆宏さんが、「子供たちが本当に一生懸命頑張った」と言われたところから、舞台上と子供達も、会場もみんな大号泣になるということになってましたもちろん大人の皆さんも素晴らしかったのですが、やはりこのミュージカルは、子供たちが全身全霊をかけて演じでいる姿が、本当に尊いものとしてあるなあと思いました以前、幼稚園の加用先生の、光る泥団子、「子供の熱中は人生初の情熱の源ノベーション(1138回)」のお話をさせて頂きましたが、子供は今ここ、に生きているので、何のためになるとかではなく、とにかく今ここに全力で取り組んだ経験が、とても宝になる、と言うお話を思い出しましただからこそ、子供たちの演技は、光り輝いて、尊く感じたのかなあと、まるでチクセントミハイさんのフロー状態がずっと続いているような、そんな気にさせて頂いた、子供の力は、大人が忘れてることを思い出させてくれる、ある意味、リバースメンタリングな、そんな気持ちになりましたということで、実は子供の頃には誰もが持っていた力である、希望の力や、選択の力、そして今ココの力の、大切さを思い出せて頂きました一言で言うと子供の力を信じるノベーションそんなことを思いました^^参考: 丸美屋食品ミュージカル アニー Annie 2025 4.19(土)〜5.7(水) 新国立劇場 中劇場 制作:日本テレビ 脚本=トーマス・ミーハン 作曲=チャールズ・ストラウス 作詞=マーティン・チャーニン 翻訳=平田綾子 演出=山田和也 音楽監督=小澤時史 https://www.ntv.co.jp/annie/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/OBfmTqBSMFE2025-05-0915 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"子供の力を信じるノベーション(1480回)40周年を迎える名作ミュージカルのアニーに、めちゃくちゃ感動して、学ぶべきところが沢山ありました以下のようなストーリーから始まります"舞台は1933年のニューヨーク。世界大恐慌直後の街は、仕事も住む家もない人であふれていました。誰もが希望を失っているなか、11歳の女の子アニーだけは元気いっぱい。11年前、孤児院の前に置き去りにされたというのに、いつか両親が迎えに来ると信じて、逆境にひるむことなく前向きに生きています。"ここから私は思いました1、希望の力2、選択する力3、子供の力1、希望の力何よりも、子供たちが歌、踊り、そして演技と、素晴らしい活躍を至る所で知りするので、素直でまっすぐな歌声や、一生懸命な姿に、それだけで涙が溢れましたこのミュージカルに貫かれているのは、アニーが大変な境遇におかれながらも、それを楽しもうとしている姿にあって、それは、ありふれた言葉になってしまいますが、"希望"と言うことを、最後まで諦めずに行動したことかと思いました「希望とは、現実的でないことを信じることではなく、未来を形づくる行為そのものである」とは、エルンスト・ブロッホが『希望の原理』で言ってることですがイノベーターは、未来への行動に移せるかどうか、そこに鍵があるそんなことを教えて頂きました2、選択する力◯◯ガチャみたいなことが言われたこともありましたが、誰もがおかれた境遇をよろしくなく思うことがあると思いますが、アニーはそんな境遇や状況をむしろ楽しもうとする、そんなマインドセットが眩しいですニーチェの解釈論のように、最後の選択は、実は自分に委ねられている、真実はなくて、実は解釈しかないのだ、ということを、思い出させてくれます「人間の最大の自由は、自分に与えられた条件の中で、自分の態度を選ぶ自由である」とヴィクトール・フランクルが『夜と霧』で言われています現実の中で自分には自由がある、最後の最後で選択できるか、簡単ではないですが、そんなことを思わせて頂きました3、子供の力このミュージカルには、たくさんの子どもが出てきますが、そのまっすぐな歌声と、懸命な演技、それ自体に涙が出てきました。実は観に行った日は、一つのチームの東京の千穐楽だったので、カーテンコールの後にご挨拶があったのですが、キーマンとなる大人の1人の藤本隆宏さんが、「子供たちが本当に一生懸命頑張った」と言われたところから、舞台上と子供達も、会場もみんな大号泣になるということになってましたもちろん大人の皆さんも素晴らしかったのですが、やはりこのミュージカルは、子供たちが全身全霊をかけて演じでいる姿が、本当に尊いものとしてあるなあと思いました以前、幼稚園の加用先生の、光る泥団子、「子供の熱中は人生初の情熱の源ノベーション(1138回)」のお話をさせて頂きましたが、子供は今ここ、に生きているので、何のためになるとかではなく、とにかく今ここに全力で取り組んだ経験が、とても宝になる、と言うお話を思い出しましただからこそ、子供たちの演技は、光り輝いて、尊く感じたのかなあと、まるでチクセントミハイさんのフロー状態がずっと続いているような、そんな気にさせて頂いた、子供の力は、大人が忘れてることを思い出させてくれる、ある意味、リバースメンタリングな、そんな気持ちになりましたということで、実は子供の頃には誰もが持っていた力である、希望の力や、選択の力、そして今ココの力の、大切さを思い出せて頂きました一言で言うと子供の力を信じるノベーションそんなことを思いました^^参考: 丸美屋食品ミュージカル アニー Annie 2025 4.19(土)〜5.7(水) 新国立劇場 中劇場 制作:日本テレビ 脚本=トーマス・ミーハン 作曲=チャールズ・ストラウス 作詞=マーティン・チャーニン 翻訳=平田綾子 演出=山田和也 音楽監督=小澤時史 https://www.ntv.co.jp/annie/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/OBfmTqBSMFE2025-05-0915 min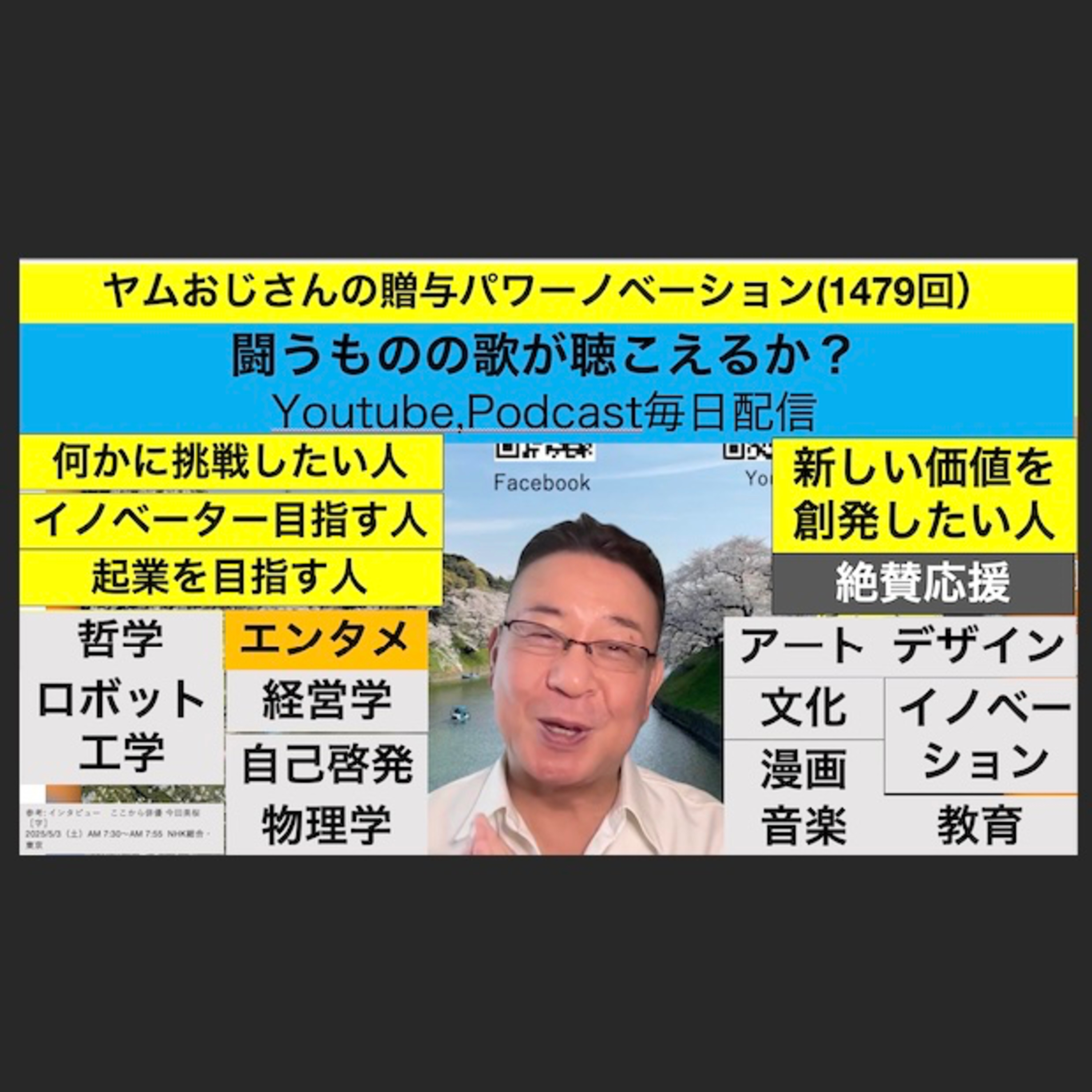 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"やむおじちゃんのあんぱんノベーション(1479回)今田美桜さんのインタビューから、朝ドラを経験しながら、感じている事に、感動させて頂きました。"私自身、いろいろお仕事したり日々生活する中で、楽しむことが一番って思っててなんかもちろん、大変なこととか、すごい泣きたくなる時だってあるしでもそんなことも、それすらも楽しむことが一番と思ってるからあんぱんを撮りながらも、ノブに似てるところももしかしたらあるのなと、思っててやっぱり悩みもあるし、ノブもいろいろノブの人生の中でいろいろ経験しますけどどんなに悲しくて暗い時も、やむおじちゃんのあんぱんを食べて、勇気をもらって、前を向いて生きていくみたいな人の喜びってこう言うことなのかなあって、いうのは感じるようになりました"ここから私は思いました1、逆境を価値に変える→ニーチェの解釈論2、役への没入→チクセントミハイのフロー3、贈与の喜び→近内悠太さんの「世界は贈与でできている」1、逆境を価値に変える朝ドラ「あんぱん」は、毎朝の楽しみとして、今日もめちゃくちゃ泣かせて頂きました、大好きなドラマです。そして、アンパンマンに宿る、やなせたかしさんのスピリッツも、本当に大好きです。その中で、今田美桜さんが、どんな気持ちでこのドラマを演じて、さらには日々感じていることに、めちゃくちゃ感動しました。一つ思ったのは、今田さんには、逆境を価値に変えていく力があるのだなあと思いました。その根底には、ニーチェの解釈論のように「真実はない、あるのは解釈だけだ」というような考え方が流れている気がしましたどんなに悲しいことや、誰が見ても辛いことがあったとしても、最後の1%としても、解釈をする余地が自分には残されているということかと思います。みうらじゅんさんが、地方の謎のキャラクターを、ゆるキャラと、名付けたことによって、可愛くないかもしれないけど、逆に面白い、そんな解釈を生む余地を産んでくれたみたいなことを、自分自身の中で、最後の1%のところで、どう解釈するかは自分次第、ということを思い出すことができれば、今田美桜さんのように、楽しむことに、解釈して進むことができるのかもしれない、と思いました2、役への没入私がドラマを見ている中では、ノブさんと、今田さんは、完全に一致して見てますが、今田さんの中でも、そんな気持ちでやられてるのだなあと、思いましたそれは、ある意味、その役に没入することで、ノブさんと同じ人生を歩んでいるということに、ほぼ同じ気持ちなのかもなあと私は俳優をやったことがないので、その気持ちは分かりませんが、チクセントミハイさんの言われるフロー状態になることに近いのかなあと思いました朝ドラという挑戦軸と、そして俳優というスキル軸の、両方を限りなくストレッチして臨まれているからこそ、その役に没入してやることができてるのかもしれないと自分の場合であれば、例えば曲を作ってるときなどは、いい感じの曲になってくると、ワクワクが止まらなくて、自分天才じゃないかと思い始めて、寝るのも仕事するのも全て吹っ飛ばして、やってしまうことも、たまにありますこんな状態でずっといられたら、どんなに幸せかと思うのですが、できた曲を翌朝聴くと、なんか違うみたいなことで、愕然とするみたいな、そんな繰り返しですでもそんなフローな時間ができるだけ多い人生になればいいなあと、思ったりしますので、今田さんは、まさに今が、そうなのかもしれないなあと思いました3、贈与の喜び朝ドラ「あんぱん」の見どころは、何といっても、端々に出てくる、やなせたかしさんの精神を切り取ったかのような言葉だと思いますその中でも、今田さんが言われてる通り、ヤムおじちゃんからの言葉や、行動、そしてあんぱんをくれる事、それが、悪態をつきながら、悪口を言いながら、やってくれる、そこに感動してしまいますそれは、哲学者の近内悠太さんの大好きな本「世界は贈与でできている」を思い出させてくれました。徘徊を繰り返す母が、実は子供時代の自分をお迎えするために毎日毎日繰り返していた、ということを、ある日偶然知ることになって、母の贈与に初めて気づいたようなそれで今度はそれを、他の誰かに、人知れずお返しをしてあげるような、そんな贈与で実は世界は回ってるのだ、ということを、思い出しましたヤムおじちゃんも、やなせたかしさんも、アンパンマンも、そして朝ドラ「あんぱん」も、全ては、贈与で回っている、そんなことが、今田さんが言われる通り、"人の喜びってこういうことなのかなあ"それが全て、やむおじちゃんのあんぱんに込められている、そんなあったかい気持ちにさせて頂きました一言で言うとやむおじちゃんのあんぱんノベーションそんなことを感じました^^参考: インタビュー ここから俳優 今田美桜[字]2025/5/3(土)AM 7:30~AM 7:55 NHK総合・東京 https://www.nhk.jp/p/a-holiday/ts/M29X69KZ1G/episode/te/Q875V33VYG/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/OBfmTqBSMFE2025-05-0819 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"やむおじちゃんのあんぱんノベーション(1479回)今田美桜さんのインタビューから、朝ドラを経験しながら、感じている事に、感動させて頂きました。"私自身、いろいろお仕事したり日々生活する中で、楽しむことが一番って思っててなんかもちろん、大変なこととか、すごい泣きたくなる時だってあるしでもそんなことも、それすらも楽しむことが一番と思ってるからあんぱんを撮りながらも、ノブに似てるところももしかしたらあるのなと、思っててやっぱり悩みもあるし、ノブもいろいろノブの人生の中でいろいろ経験しますけどどんなに悲しくて暗い時も、やむおじちゃんのあんぱんを食べて、勇気をもらって、前を向いて生きていくみたいな人の喜びってこう言うことなのかなあって、いうのは感じるようになりました"ここから私は思いました1、逆境を価値に変える→ニーチェの解釈論2、役への没入→チクセントミハイのフロー3、贈与の喜び→近内悠太さんの「世界は贈与でできている」1、逆境を価値に変える朝ドラ「あんぱん」は、毎朝の楽しみとして、今日もめちゃくちゃ泣かせて頂きました、大好きなドラマです。そして、アンパンマンに宿る、やなせたかしさんのスピリッツも、本当に大好きです。その中で、今田美桜さんが、どんな気持ちでこのドラマを演じて、さらには日々感じていることに、めちゃくちゃ感動しました。一つ思ったのは、今田さんには、逆境を価値に変えていく力があるのだなあと思いました。その根底には、ニーチェの解釈論のように「真実はない、あるのは解釈だけだ」というような考え方が流れている気がしましたどんなに悲しいことや、誰が見ても辛いことがあったとしても、最後の1%としても、解釈をする余地が自分には残されているということかと思います。みうらじゅんさんが、地方の謎のキャラクターを、ゆるキャラと、名付けたことによって、可愛くないかもしれないけど、逆に面白い、そんな解釈を生む余地を産んでくれたみたいなことを、自分自身の中で、最後の1%のところで、どう解釈するかは自分次第、ということを思い出すことができれば、今田美桜さんのように、楽しむことに、解釈して進むことができるのかもしれない、と思いました2、役への没入私がドラマを見ている中では、ノブさんと、今田さんは、完全に一致して見てますが、今田さんの中でも、そんな気持ちでやられてるのだなあと、思いましたそれは、ある意味、その役に没入することで、ノブさんと同じ人生を歩んでいるということに、ほぼ同じ気持ちなのかもなあと私は俳優をやったことがないので、その気持ちは分かりませんが、チクセントミハイさんの言われるフロー状態になることに近いのかなあと思いました朝ドラという挑戦軸と、そして俳優というスキル軸の、両方を限りなくストレッチして臨まれているからこそ、その役に没入してやることができてるのかもしれないと自分の場合であれば、例えば曲を作ってるときなどは、いい感じの曲になってくると、ワクワクが止まらなくて、自分天才じゃないかと思い始めて、寝るのも仕事するのも全て吹っ飛ばして、やってしまうことも、たまにありますこんな状態でずっといられたら、どんなに幸せかと思うのですが、できた曲を翌朝聴くと、なんか違うみたいなことで、愕然とするみたいな、そんな繰り返しですでもそんなフローな時間ができるだけ多い人生になればいいなあと、思ったりしますので、今田さんは、まさに今が、そうなのかもしれないなあと思いました3、贈与の喜び朝ドラ「あんぱん」の見どころは、何といっても、端々に出てくる、やなせたかしさんの精神を切り取ったかのような言葉だと思いますその中でも、今田さんが言われてる通り、ヤムおじちゃんからの言葉や、行動、そしてあんぱんをくれる事、それが、悪態をつきながら、悪口を言いながら、やってくれる、そこに感動してしまいますそれは、哲学者の近内悠太さんの大好きな本「世界は贈与でできている」を思い出させてくれました。徘徊を繰り返す母が、実は子供時代の自分をお迎えするために毎日毎日繰り返していた、ということを、ある日偶然知ることになって、母の贈与に初めて気づいたようなそれで今度はそれを、他の誰かに、人知れずお返しをしてあげるような、そんな贈与で実は世界は回ってるのだ、ということを、思い出しましたヤムおじちゃんも、やなせたかしさんも、アンパンマンも、そして朝ドラ「あんぱん」も、全ては、贈与で回っている、そんなことが、今田さんが言われる通り、"人の喜びってこういうことなのかなあ"それが全て、やむおじちゃんのあんぱんに込められている、そんなあったかい気持ちにさせて頂きました一言で言うとやむおじちゃんのあんぱんノベーションそんなことを感じました^^参考: インタビュー ここから俳優 今田美桜[字]2025/5/3(土)AM 7:30~AM 7:55 NHK総合・東京 https://www.nhk.jp/p/a-holiday/ts/M29X69KZ1G/episode/te/Q875V33VYG/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/OBfmTqBSMFE2025-05-0819 min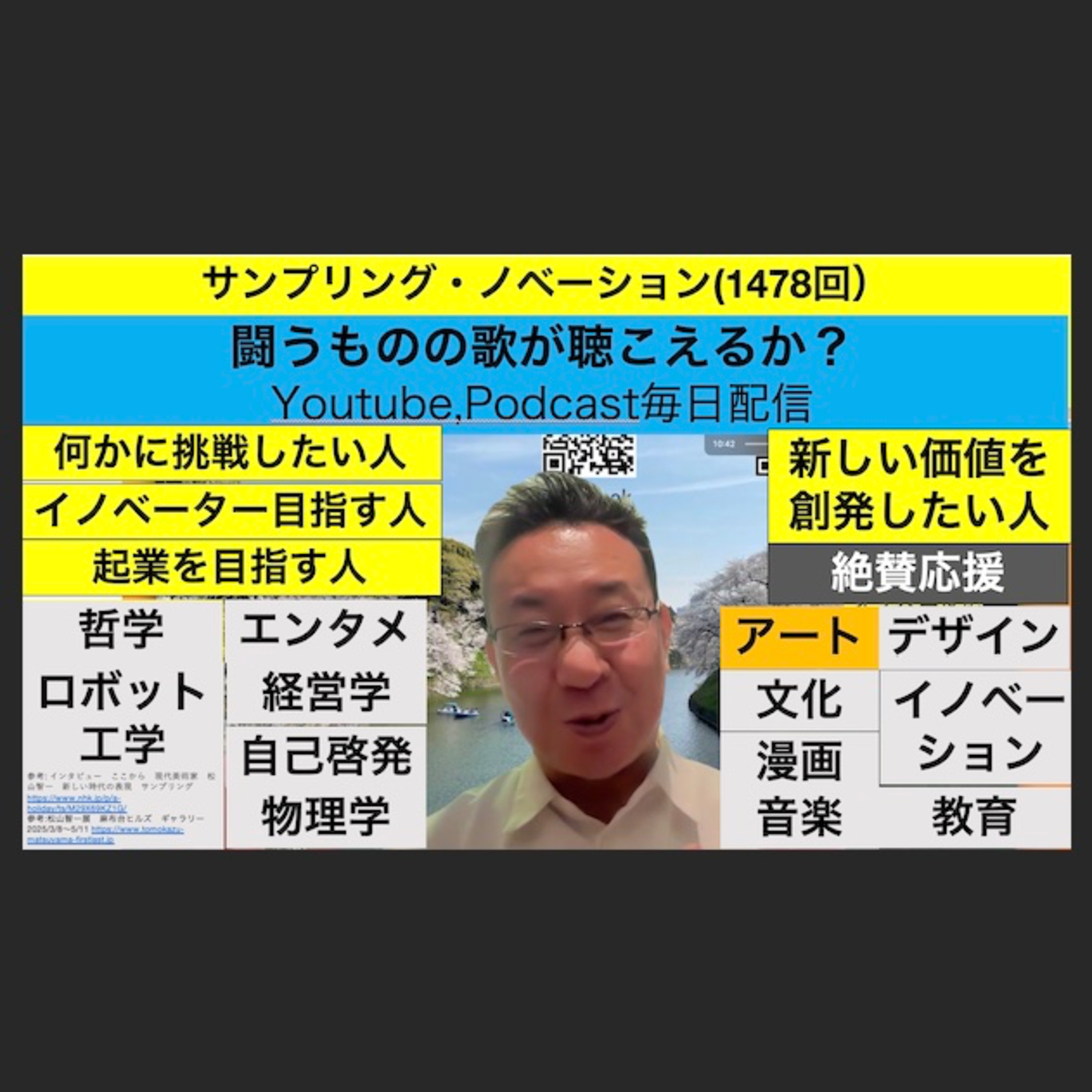 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"サンプリング・ノベーション(1478回)現代美術家の松山智一さんのサンプリング技法に至った経緯にイノベーターを感じました"未来は見えてるんですよ。それができてる人を見てるんで、成功例を見るとあ、この表現方法は絶対僕らが新しくつくった世代の言語だと思ったんですおそるおそるやってみると、そこにみんな反応しだすんですよ、鑑賞者が、面白いっておそるおそるやってくうちに、これ堂々とやっていいんだなって、自信がついてきたんですもっともっともっといううちに、それが5になって10、何十になってこれがこう折り重なった時に初めて、異国情緒とかどこの国なのか、いつの時代なのかわからなくって今の多様化された僕のアイデンティティを象徴してるようだって言ってもらえるようになって僕の鏡だったのが、ある時から作品が、鑑賞者の鏡になり出したんですよ"ここから私は思いました1、わくわくベスプラ2、おそるおそるリーン3、掛け合わせ積み重ね1、わくわくベスプラ松山さんの作品は、色彩がとても豊かで見てるだけで気持ちが昂ったり、癒されたりするめちゃくちゃ素敵な作品ですが、実はその中に込められているメッセージもとても深くで、いろんな気持ちを呼び起こしてくれるので、大好きです。それがサンプリング技法という、さまざまなものを幾重にも掛け合わせるという手法ということも、今回初めて知り、まさにイノベーション手法そのものだなあと思いましたそれは音楽やアートにおける先人たちのサンプリング手法に触れた時に、「新しい自分たちの言語だ」という、大好きパッションが炸裂したところから、始まったのだろうなあと思いましたイノベーションの世界では、ベストプラクティス略してベスプラとよく言われますが、これはなんで素敵なんだろう、何が自分の琴線に触れるのだろう、みたいなことから、表面的な手法だけでなく、その中に内在してる価値を自分なりに理解できた時に、それが自分の中に息づいて自分ならこうやってみたい、これを別のやり方で、別の分野で、さらにこうやったらもっと面白いかも、みたいなことから、パッションの源に火がつき始める、そんなことかと思いました2、おそるおそるリーン松山さんは当初はスノボの選手を目指していて、その後、単身でニューヨークに渡って絵を描かれて、ある壁画のアートから注目を集めるようになったとのことでしたが、自分の未開の地に行動できる力に、驚愕でしたでもこのインタビューで言われた通り、おそるおそる始められていた、という言葉を聞くと、イノベーターと言われる人も、最初は、おそるおそるなんだなあと、とても勇気をもらえる気がしましたそれはイノベーションの世界では、リーンスタートアップや、リーンアンドスケールみたいなことで、まずは仮説をもとに検証してみるということと、やり方は同じだなあと思いましたおそるおそるだけど、行動してみる。むしろ早く失敗することで、次の道を見出していく、FastFailの精神がイノベーターにはあるのだなあと改めて思いました3、掛け合わせ積み重ねその上でもちろん上手くいく、いかないことがきっと沢山あられたのだと思いますが、その成功も失敗も積み重ねることによって、"5になって10になって、、、"と掛け合わせ経験が蓄積していくことが大切だなあと思いましたイノベーションプロジェクトでも、この積み重ねが、一つのプロジェクトの中でも、上手く積み重ねることによって、素晴らしいゴールに辿り着くチームをいくつもみていますまた、実はチーム内にこれがとどまるのがとてももったいなくて、幾つものプロジェクトの積み重ねを、複数プロジェクトのみんなが体感できる、さらには、年数を重ねてどんどん蓄積していくと同時に、それらを新しい人も積み重なりを感じて、そこから始められるそんな風な仕掛けづくりと、仲間づくりが、組織におけるイノベーションにはとても大切かもしれないなあと思いました松山さんも実はチームとして活動していて、絵を描く人やリサーチャーという仲間の中で、たくさんの蓄積をしながらされているのだなあと思いましたまとめるとサンプリングという新たな言語に魅了され、パッションの源に火がついて、おそるおそるだけど行動して、FastFailしながら、それを継続することで、仲間とともに、積み重ねることによって、新しい多様性や、異国情緒という、みんなが素敵に思う大義に辿り着いた、まさにイノベーター3つのフレームに沿った、現代のイノベーターだなあと、改めて思いました一言で言えば、サンプリングという、アートにおける、時代も、境界も、思想も、すべてを、究極の掛け合わせることで、新たなイノベーションを生み出すサンプリング・ノベーションそんなことを思いました^^参考: インタビュー ここから 現代美術家 松山智一 新しい時代の表現 サンプリング https://www.nhk.jp/p/a-holiday/ts/M29X69KZ1G/参考:松山智一展 麻布台ヒルズ ギャラリー2025/3/8~5/11 https://www.tomokazu-matsuyama-firstlast.jp2025-05-0720 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"サンプリング・ノベーション(1478回)現代美術家の松山智一さんのサンプリング技法に至った経緯にイノベーターを感じました"未来は見えてるんですよ。それができてる人を見てるんで、成功例を見るとあ、この表現方法は絶対僕らが新しくつくった世代の言語だと思ったんですおそるおそるやってみると、そこにみんな反応しだすんですよ、鑑賞者が、面白いっておそるおそるやってくうちに、これ堂々とやっていいんだなって、自信がついてきたんですもっともっともっといううちに、それが5になって10、何十になってこれがこう折り重なった時に初めて、異国情緒とかどこの国なのか、いつの時代なのかわからなくって今の多様化された僕のアイデンティティを象徴してるようだって言ってもらえるようになって僕の鏡だったのが、ある時から作品が、鑑賞者の鏡になり出したんですよ"ここから私は思いました1、わくわくベスプラ2、おそるおそるリーン3、掛け合わせ積み重ね1、わくわくベスプラ松山さんの作品は、色彩がとても豊かで見てるだけで気持ちが昂ったり、癒されたりするめちゃくちゃ素敵な作品ですが、実はその中に込められているメッセージもとても深くで、いろんな気持ちを呼び起こしてくれるので、大好きです。それがサンプリング技法という、さまざまなものを幾重にも掛け合わせるという手法ということも、今回初めて知り、まさにイノベーション手法そのものだなあと思いましたそれは音楽やアートにおける先人たちのサンプリング手法に触れた時に、「新しい自分たちの言語だ」という、大好きパッションが炸裂したところから、始まったのだろうなあと思いましたイノベーションの世界では、ベストプラクティス略してベスプラとよく言われますが、これはなんで素敵なんだろう、何が自分の琴線に触れるのだろう、みたいなことから、表面的な手法だけでなく、その中に内在してる価値を自分なりに理解できた時に、それが自分の中に息づいて自分ならこうやってみたい、これを別のやり方で、別の分野で、さらにこうやったらもっと面白いかも、みたいなことから、パッションの源に火がつき始める、そんなことかと思いました2、おそるおそるリーン松山さんは当初はスノボの選手を目指していて、その後、単身でニューヨークに渡って絵を描かれて、ある壁画のアートから注目を集めるようになったとのことでしたが、自分の未開の地に行動できる力に、驚愕でしたでもこのインタビューで言われた通り、おそるおそる始められていた、という言葉を聞くと、イノベーターと言われる人も、最初は、おそるおそるなんだなあと、とても勇気をもらえる気がしましたそれはイノベーションの世界では、リーンスタートアップや、リーンアンドスケールみたいなことで、まずは仮説をもとに検証してみるということと、やり方は同じだなあと思いましたおそるおそるだけど、行動してみる。むしろ早く失敗することで、次の道を見出していく、FastFailの精神がイノベーターにはあるのだなあと改めて思いました3、掛け合わせ積み重ねその上でもちろん上手くいく、いかないことがきっと沢山あられたのだと思いますが、その成功も失敗も積み重ねることによって、"5になって10になって、、、"と掛け合わせ経験が蓄積していくことが大切だなあと思いましたイノベーションプロジェクトでも、この積み重ねが、一つのプロジェクトの中でも、上手く積み重ねることによって、素晴らしいゴールに辿り着くチームをいくつもみていますまた、実はチーム内にこれがとどまるのがとてももったいなくて、幾つものプロジェクトの積み重ねを、複数プロジェクトのみんなが体感できる、さらには、年数を重ねてどんどん蓄積していくと同時に、それらを新しい人も積み重なりを感じて、そこから始められるそんな風な仕掛けづくりと、仲間づくりが、組織におけるイノベーションにはとても大切かもしれないなあと思いました松山さんも実はチームとして活動していて、絵を描く人やリサーチャーという仲間の中で、たくさんの蓄積をしながらされているのだなあと思いましたまとめるとサンプリングという新たな言語に魅了され、パッションの源に火がついて、おそるおそるだけど行動して、FastFailしながら、それを継続することで、仲間とともに、積み重ねることによって、新しい多様性や、異国情緒という、みんなが素敵に思う大義に辿り着いた、まさにイノベーター3つのフレームに沿った、現代のイノベーターだなあと、改めて思いました一言で言えば、サンプリングという、アートにおける、時代も、境界も、思想も、すべてを、究極の掛け合わせることで、新たなイノベーションを生み出すサンプリング・ノベーションそんなことを思いました^^参考: インタビュー ここから 現代美術家 松山智一 新しい時代の表現 サンプリング https://www.nhk.jp/p/a-holiday/ts/M29X69KZ1G/参考:松山智一展 麻布台ヒルズ ギャラリー2025/3/8~5/11 https://www.tomokazu-matsuyama-firstlast.jp2025-05-0720 min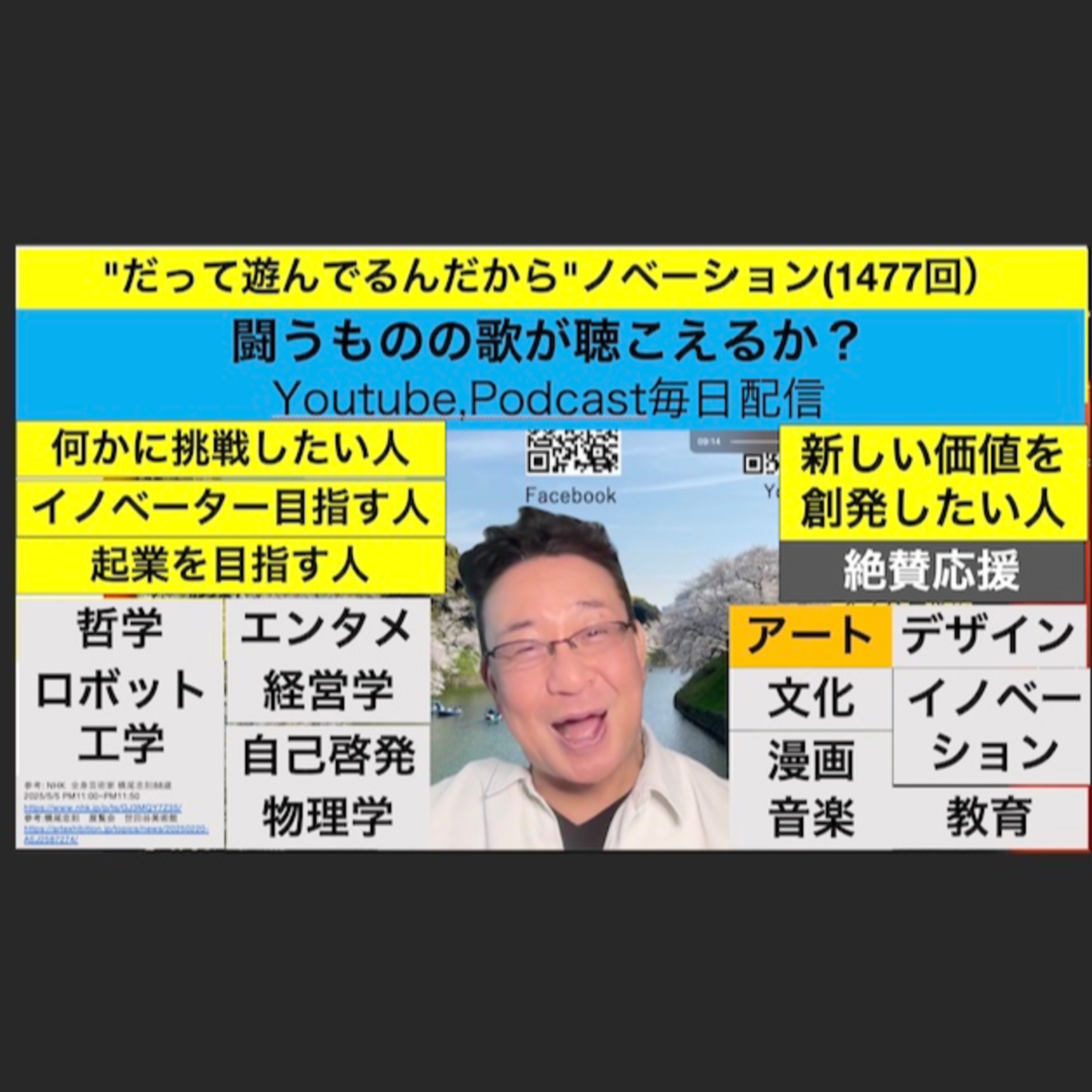 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""だって遊んでるんだから"ノベーション(1477回)世田谷美術館で展覧会を開催中の横尾忠則さんの、絵画を描く姿勢に、真のイノベーターの姿を見た気がしました曰く"これは当てずっぽうで、こんな風なものを描こうと思ってないからさま、決まってるのは、電車のとこの鉄橋ね、あと何にも決まってない決まらないと描けない人は多いかもしれないけど、決めてしまって描いたら、面白くないからねだって遊んでるんだから"ここから私は思いました1、当てずっぽうを楽しむ→セレンディピティで自分の超える2、決まらないから面白い→ネガティヴケイパビリティ3、仕事で遊ぶ→フロー1、当てずっぽうを楽しむ展覧会の一年前から取材されていたそうですが、横尾さんの創作のパワーと情熱に圧倒されっぱなしでした。まずは絵画を描く際に、当てずっぽう、で描くものを決めずに描いていくと言うことに衝撃を受けました。これはある意味、自ら、偶然の中に幸運を見つけるセレンディピティを創られているのかなあと思いましたし、そこで生まれた偶然を、横尾さんなりに解釈して新たな創作としていくと言うやり方なのかと思いましたそれは、まるで、当てずっぽう×横尾忠則さんの感性、と言う新しい組み合わせによって、横尾さんご自身でさえ、想像だにしていなかった、イノベーティブな作品を作る秘訣なのかもしれないと、思いました2、決まらないから面白いすでに展覧会の日時は決まっていて、締切も決まっているのに、そのゴールへ向けての道筋をつけることはせずに、その状況を楽しむことができると言うことに、また驚きをいただきました。これはある意味、ネガティヴケイパビリティのように、答えが見つからない状況をいかにキープし続けられるかと言う、真の答えに辿り着こうとする人たちには、大事な考え方だなあと思いましたイノベーションの世界でも、これはとても重要で、安易な答えに飛びつかない、と言うことが求められます。本当の課題を見つけることは、苦難の道のりなので、それをよしとして、問い続けられるかそれをむしろ楽しむ気持ちを持つと言うのは、とても大事な事だなあと思いました3、仕事で遊ぶ横尾さんにとって絵を描くことは、ある意味、展覧会と言う舞台へ向けての仕事なのかなと思うわけですが、にも関わらず、遊んでんだから、といることが、素晴らしいと思いましたこれは、もしかすると、ミハイ・チクセントミハイさんの、フロー状態に常にあるからなのではないかとも思いました。技術軸と挑戦軸を、どちらかでも登って両方がピークに達すると、とにかく没入して、そしてそれが楽しくて仕方がないと言うことになるそれはもはや仕事だろうが遊びだろうが、関係なく、やりたくて仕方がなくなり、究極まで極めたくなる、それが情熱の源に火が燃えている状態と思いますそこまで打ち込めるものがある人生は本当に幸せだろうなと思いましたということで、まとめると当てずっぽうというセレンディピティを創り出し掛け合わせて、決まらないと言うネガティヴケイパビリティにも耐え、そしてフロー状態になるほどに、挑戦と技術を身につけていくそれこそが真のイノベーターのあり方かもしれないそこには情熱の源に沿った生き方をされているイノベーターがいる一言で言うと"遊んでるんだから"ノベーションそんなことを思いました^^参考: NHK 全身芸術家 横尾忠則88歳2025/5/5 PM11:00~PM11:50 https://www.nhk.jp/p/ts/GJ3MQY7Z35/参考:横尾忠則 展覧会 世田谷美術館 https://artexhibition.jp/topics/news/20250220-AEJ2587274/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/KeVzlcdRWAU2025-05-0614 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""だって遊んでるんだから"ノベーション(1477回)世田谷美術館で展覧会を開催中の横尾忠則さんの、絵画を描く姿勢に、真のイノベーターの姿を見た気がしました曰く"これは当てずっぽうで、こんな風なものを描こうと思ってないからさま、決まってるのは、電車のとこの鉄橋ね、あと何にも決まってない決まらないと描けない人は多いかもしれないけど、決めてしまって描いたら、面白くないからねだって遊んでるんだから"ここから私は思いました1、当てずっぽうを楽しむ→セレンディピティで自分の超える2、決まらないから面白い→ネガティヴケイパビリティ3、仕事で遊ぶ→フロー1、当てずっぽうを楽しむ展覧会の一年前から取材されていたそうですが、横尾さんの創作のパワーと情熱に圧倒されっぱなしでした。まずは絵画を描く際に、当てずっぽう、で描くものを決めずに描いていくと言うことに衝撃を受けました。これはある意味、自ら、偶然の中に幸運を見つけるセレンディピティを創られているのかなあと思いましたし、そこで生まれた偶然を、横尾さんなりに解釈して新たな創作としていくと言うやり方なのかと思いましたそれは、まるで、当てずっぽう×横尾忠則さんの感性、と言う新しい組み合わせによって、横尾さんご自身でさえ、想像だにしていなかった、イノベーティブな作品を作る秘訣なのかもしれないと、思いました2、決まらないから面白いすでに展覧会の日時は決まっていて、締切も決まっているのに、そのゴールへ向けての道筋をつけることはせずに、その状況を楽しむことができると言うことに、また驚きをいただきました。これはある意味、ネガティヴケイパビリティのように、答えが見つからない状況をいかにキープし続けられるかと言う、真の答えに辿り着こうとする人たちには、大事な考え方だなあと思いましたイノベーションの世界でも、これはとても重要で、安易な答えに飛びつかない、と言うことが求められます。本当の課題を見つけることは、苦難の道のりなので、それをよしとして、問い続けられるかそれをむしろ楽しむ気持ちを持つと言うのは、とても大事な事だなあと思いました3、仕事で遊ぶ横尾さんにとって絵を描くことは、ある意味、展覧会と言う舞台へ向けての仕事なのかなと思うわけですが、にも関わらず、遊んでんだから、といることが、素晴らしいと思いましたこれは、もしかすると、ミハイ・チクセントミハイさんの、フロー状態に常にあるからなのではないかとも思いました。技術軸と挑戦軸を、どちらかでも登って両方がピークに達すると、とにかく没入して、そしてそれが楽しくて仕方がないと言うことになるそれはもはや仕事だろうが遊びだろうが、関係なく、やりたくて仕方がなくなり、究極まで極めたくなる、それが情熱の源に火が燃えている状態と思いますそこまで打ち込めるものがある人生は本当に幸せだろうなと思いましたということで、まとめると当てずっぽうというセレンディピティを創り出し掛け合わせて、決まらないと言うネガティヴケイパビリティにも耐え、そしてフロー状態になるほどに、挑戦と技術を身につけていくそれこそが真のイノベーターのあり方かもしれないそこには情熱の源に沿った生き方をされているイノベーターがいる一言で言うと"遊んでるんだから"ノベーションそんなことを思いました^^参考: NHK 全身芸術家 横尾忠則88歳2025/5/5 PM11:00~PM11:50 https://www.nhk.jp/p/ts/GJ3MQY7Z35/参考:横尾忠則 展覧会 世田谷美術館 https://artexhibition.jp/topics/news/20250220-AEJ2587274/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/KeVzlcdRWAU2025-05-0614 min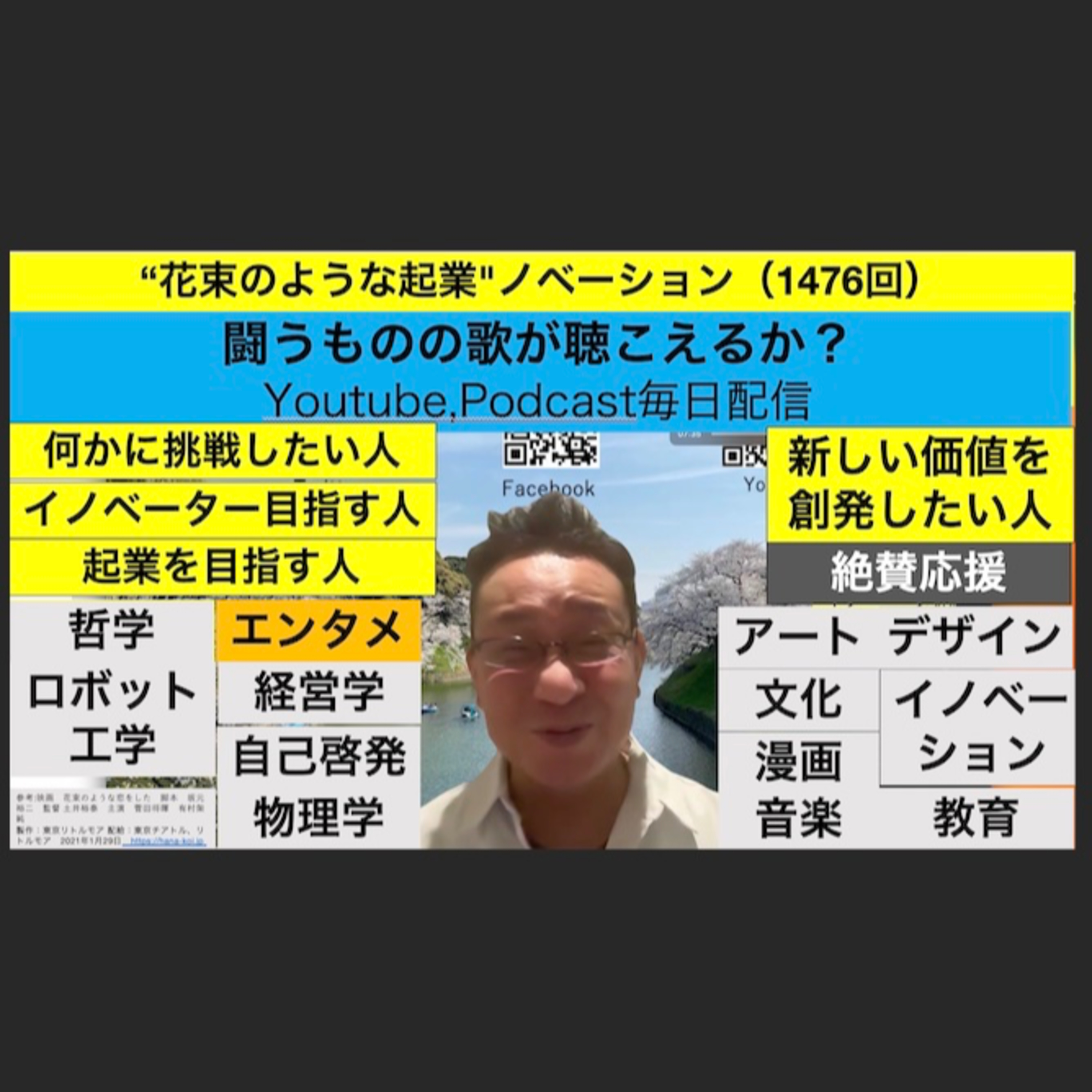 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""花束のような起業"ノベーション(1476回)坂元裕二さん脚本、土井裕泰さん監督の、「映画:花束みたいな恋をした」に感動し、たくさんの気づきを頂きました素敵なキャッチコピーが"東京・明大前駅で終電を逃し偶然に出会った、麦と絹。バイト、同棲、就活。いつでも二人で一緒にいた20代のぜんぶが、ずっと楽しかった。猛スピードで加速する恋の忘れられないく最高の5年間>を描く、不滅のラブストーリー誕生。"ここから私は思いました1、3デクワス理論2、出会いのパッション3、人生のゴール1、3デクワス理論大勢の飲み会が得意じゃなくて、実はマニアックで夢中になれることがあって、明確な夢とかあるわけじゃないけど、なんとなく目指したいこともあるみたいな、絹と麦の現実を生きてる姿に、めちゃくちゃ共感して、感動して、涙しました坂元さんの脚本は本当に現実の生活や、その時にある感情を、ありありと思い浮かべさせてくれて、自分がまるでその中に生きていると言うか、生きていたかのような気持ちにさせてくれましたあまりにも共通点が多かったり、偶然が重なることで、ついつい運命の出会いに違いないとか、赤糸が見えた、みたいな気持ちになるよなあと思ったのと同時に以前お話しした小西利行さんから教えて頂いた "3デクワス理論"を思い出しました。"つまり3回以上「買う理由」に出会えば「買う」わけだ"もちろん、恋愛は買うわけではありませんが、3つ以上の偶然や共感があれば、もしかしてこれって運命?みたいな気持ちになると言うのも、ロマンチックではなくなるかもしれませんが、心理としてはあるよなあと思いますそれは、言い方を変えると、セレンディピティで、その幸運を拾うかどうかは、本人次第、と言うこともあるので、実はイノベーションの種を拾う時も同じようなデクワスをいかに高めるかと言うことも、イノベーターを目指す人には大切だし、私は今回の映画を見て、積極的に恐れずに、拾っていきたいなあと思わせて頂きました2、出会いのパッションそしてそんな時の心の高まりは、それこそ、誰もが一生のうちに一度は経験したことのある、パッションの源に炎が灯った瞬間だなあと思います何に情熱が生まれるのか、わからないと言うお話も、よく聞きますが、その感覚は、まさに、この恋愛が始まった瞬間、それは、自分だけの勘違いかもしれないけれども、居ても立っても居られない、そんなことが起きたら、とにかくそれに乗っかってみると言うことが、どんな種類のものであれ、自らのパッションの源に沿って生きると言うことにつながると思いますそれが、自分の気持ちの高まりから、誰かと共にと言う気持ちが、仲間が生まれ、さらにはもっとたくさんの人たちのためにというところから、大義が生まれ、それがイノベーションにつながっていく、そう言う感覚はさの始まりは、恋愛と同じそう考えると、誰もがイノベーターに実はなれる可能性があると言うふうにも思いました3、人生のゴール今回の映画のタイトルにある、花束のような恋、が何を指しているのかは、明確に語られていませんが、私の想像では衝撃の出会いがあり、始める時には勇気を奮って、花束をお送りする時のような、そして驚きと共に華やかに始まり、さらに輝く恋、そしてそれは時と共に、永遠に美しいものではないかもしれない、でも、そこで生まれた気持ちは永遠に美しいものとして、残していくことができるそんなふうに考えると、イノベーション活動も、同じような、新鮮な驚きから、それを始める勇気と、そこからの成長の喜びがあり、でももしかしたらうまくいかないかもしれない、でもそこでやってきたことは、とても美しい自分の人生の一部になってくれる三木清さんの、人生のゴールは、成功ではなく、失敗のようないろどりもふくめての、幸せである、そんな言葉が、恋にも、イノベーション活動も、同じだなあと、つくづく思いましたそういう意味を込めて一言で言うと"花束のような"起業ノベーションそんなことを思いました^^参考:映画 花束のような恋をした 脚本 坂元裕二 監督 土井裕泰 主演 菅田将暉 有村架純 製作:東京リトルモア 配給:東京チアトル、リトルモア 2021年1月29日 https://hana-koi.jp 動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/vEnOo6x29C02025-05-0522 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""花束のような起業"ノベーション(1476回)坂元裕二さん脚本、土井裕泰さん監督の、「映画:花束みたいな恋をした」に感動し、たくさんの気づきを頂きました素敵なキャッチコピーが"東京・明大前駅で終電を逃し偶然に出会った、麦と絹。バイト、同棲、就活。いつでも二人で一緒にいた20代のぜんぶが、ずっと楽しかった。猛スピードで加速する恋の忘れられないく最高の5年間>を描く、不滅のラブストーリー誕生。"ここから私は思いました1、3デクワス理論2、出会いのパッション3、人生のゴール1、3デクワス理論大勢の飲み会が得意じゃなくて、実はマニアックで夢中になれることがあって、明確な夢とかあるわけじゃないけど、なんとなく目指したいこともあるみたいな、絹と麦の現実を生きてる姿に、めちゃくちゃ共感して、感動して、涙しました坂元さんの脚本は本当に現実の生活や、その時にある感情を、ありありと思い浮かべさせてくれて、自分がまるでその中に生きていると言うか、生きていたかのような気持ちにさせてくれましたあまりにも共通点が多かったり、偶然が重なることで、ついつい運命の出会いに違いないとか、赤糸が見えた、みたいな気持ちになるよなあと思ったのと同時に以前お話しした小西利行さんから教えて頂いた "3デクワス理論"を思い出しました。"つまり3回以上「買う理由」に出会えば「買う」わけだ"もちろん、恋愛は買うわけではありませんが、3つ以上の偶然や共感があれば、もしかしてこれって運命?みたいな気持ちになると言うのも、ロマンチックではなくなるかもしれませんが、心理としてはあるよなあと思いますそれは、言い方を変えると、セレンディピティで、その幸運を拾うかどうかは、本人次第、と言うこともあるので、実はイノベーションの種を拾う時も同じようなデクワスをいかに高めるかと言うことも、イノベーターを目指す人には大切だし、私は今回の映画を見て、積極的に恐れずに、拾っていきたいなあと思わせて頂きました2、出会いのパッションそしてそんな時の心の高まりは、それこそ、誰もが一生のうちに一度は経験したことのある、パッションの源に炎が灯った瞬間だなあと思います何に情熱が生まれるのか、わからないと言うお話も、よく聞きますが、その感覚は、まさに、この恋愛が始まった瞬間、それは、自分だけの勘違いかもしれないけれども、居ても立っても居られない、そんなことが起きたら、とにかくそれに乗っかってみると言うことが、どんな種類のものであれ、自らのパッションの源に沿って生きると言うことにつながると思いますそれが、自分の気持ちの高まりから、誰かと共にと言う気持ちが、仲間が生まれ、さらにはもっとたくさんの人たちのためにというところから、大義が生まれ、それがイノベーションにつながっていく、そう言う感覚はさの始まりは、恋愛と同じそう考えると、誰もがイノベーターに実はなれる可能性があると言うふうにも思いました3、人生のゴール今回の映画のタイトルにある、花束のような恋、が何を指しているのかは、明確に語られていませんが、私の想像では衝撃の出会いがあり、始める時には勇気を奮って、花束をお送りする時のような、そして驚きと共に華やかに始まり、さらに輝く恋、そしてそれは時と共に、永遠に美しいものではないかもしれない、でも、そこで生まれた気持ちは永遠に美しいものとして、残していくことができるそんなふうに考えると、イノベーション活動も、同じような、新鮮な驚きから、それを始める勇気と、そこからの成長の喜びがあり、でももしかしたらうまくいかないかもしれない、でもそこでやってきたことは、とても美しい自分の人生の一部になってくれる三木清さんの、人生のゴールは、成功ではなく、失敗のようないろどりもふくめての、幸せである、そんな言葉が、恋にも、イノベーション活動も、同じだなあと、つくづく思いましたそういう意味を込めて一言で言うと"花束のような"起業ノベーションそんなことを思いました^^参考:映画 花束のような恋をした 脚本 坂元裕二 監督 土井裕泰 主演 菅田将暉 有村架純 製作:東京リトルモア 配給:東京チアトル、リトルモア 2021年1月29日 https://hana-koi.jp 動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/vEnOo6x29C02025-05-0522 min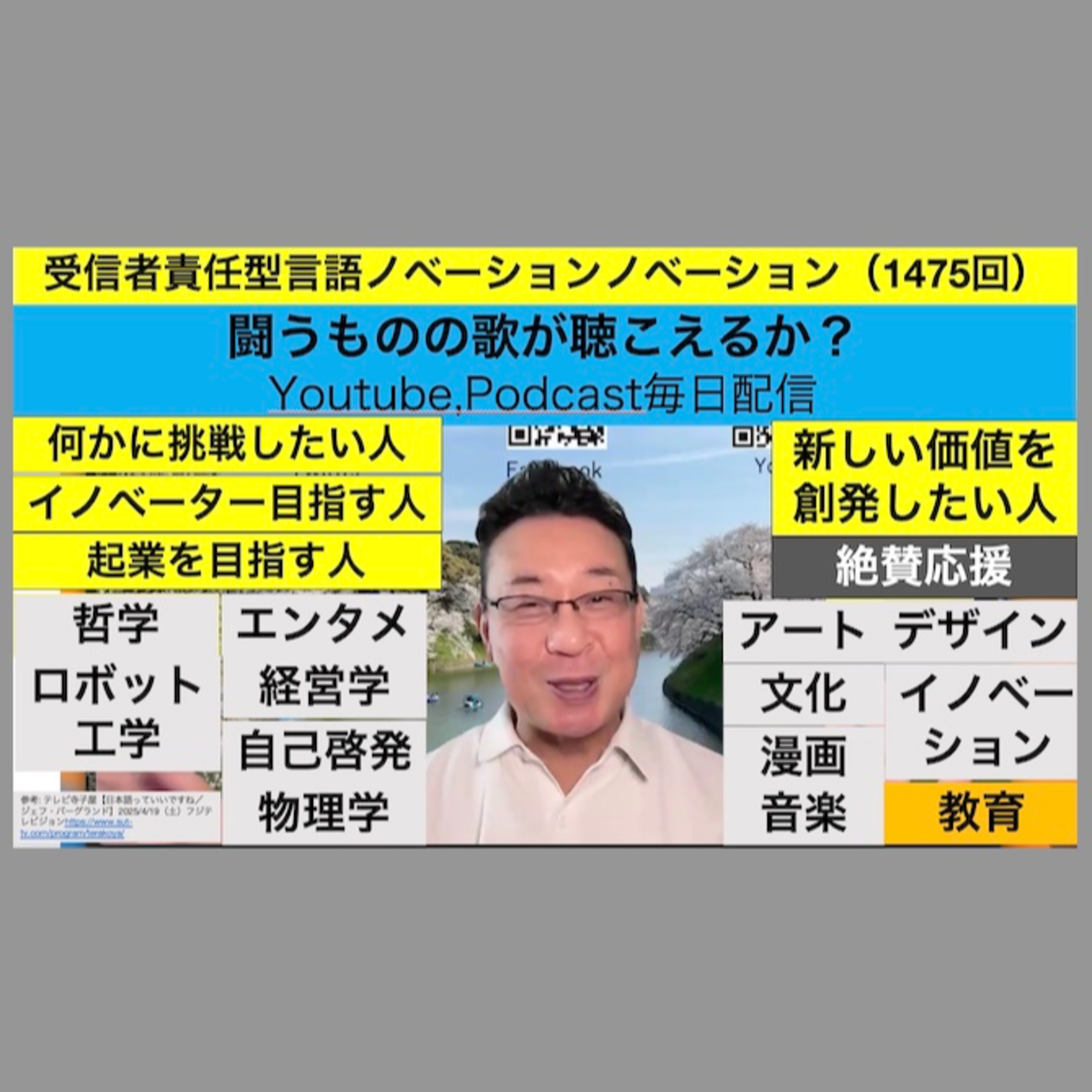 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"受信者責任型言語ノベーションノベーション(1475回)京都外国語大学教授のジェフ・バーグランドさんのお話に勇気を頂きました"英語は発信者責任型言語。発信する方が責任持ってはっきりしないといけないんです。キーン(ドナルドキーン)さんが、日本語っていいですね。自由自在に読む人が自分で解読したらいいんだと。これが僕にとっては一番日本語の特徴なんです。日本語は受信者責任型言語。自由自在に解読ができる。""実は、この受信者責任型言語というのが、他の文化を吸収していくのに大事な力なんです。だから日本人ってのは、結構受け入れる心が大きいんです。あんまり否定しないんです。全然違うもんでも、それもありかなあと、これが日本人の日本語からくる受信力だと思うんです"ここから私は思いました1、余白文化2、共創促進文化3、高コンテクスト文化1、余白文化日本語が受信者責任型言語というのは、わかりやすい視点だなと思いました。鈴木孝夫さんが『ことばと文化』(1973)の中でもお話しされているようですが、確かに、主語がなくても、下手をすれば、咳払いだけで通じるなんてのも、受け取る側が解釈できるよね、から、受け取る側で慮ることが普通に行われるなあと思いますその反面、日本人は発言しないとか、グローバルな世界では積極的な発言がないといないと同じだ、みたいなネガティヴなことも言わがちで、さらに萎縮してしまうみたいなことも感じてますでも実は悪い面だけではなく、とても良い面もたくさんあるというジェフさんのお話に勇気を頂きました。受け取る側にある程度を委ねるという意味では、受け取る側の判断、解釈を入れて初めて成立するという意味で、余白文化、といってもいいかと思いました。そして、余白があるからこそ、ずらした解釈が生まれる、誤読が生まれる、ある意味ボケが生まれる、こういったてんについては、発信した側にも、あ、そういう解釈も面白い、と受けることで、様々なものが掛け合わされる、とてもイノベ〜ディブな文化ということも言えるのかもしれないと思いました2、共創促進文化受信者責任言語においては、受け取った側の解釈を改めて発信者側に確認する行為というのが、必ず必要となると思いますそれが、まどろっこしい、もっとはっきりいってくれないから勘違いした、みたいなデメリットもありますが、それもポジティブな面から見ると、コミュニケーションを促進する構造になっている、ということも言える気がしました受信者側からの確認行為があり、さらにそこに発信者側からのさらなる発信が起き、このコミュニケーションが促進することで、実は"仲間"とのさらなるイノベーティブな意見交換ができるという意味では、これも日本文化の良い面かもしれないと思いました3、高コンテクスト文化エドワード・T・ホールさんが「高コンテクスト文化では、メッセージの多くが言語以外の手段、すなわち沈黙、間、表情、背景的状況に託される。日本はその典型である。」と言われた通り、日本では、言語以外の伝える方法を大切にしてるのかなと思います原始の時代からの、ものを叩く、声を高低で話す、物音を聞く、気配を感じる、目や仕草で伝えるという、言語を持ってしまったがために失われたことを、日本はとても大切にしてきたのかもしれないなとそしてそれは、とても豊かなコミュニケーションであり、そこから生じる豊かな感性や感情なども、大切にし続けた文化なのかと思いますそれは、きっと日本人の中に、様々な刺激や感覚、違和感や伝え方伝わり方、さらには味わい方、触れ方、見え方、聞こえ方、など、バラエティで繊細な感覚を養ってくれてるのかなあと、そんなことを思いました余白を大切にし、共創をより良しとし、様々な感じ方、伝え方を育んできた、日本文化は、とてもイノベーティブな環境であり、そんな人々が集う土地であり、これからも、そんなイノベーションをたくさん産む可能性がたくさんある、そんな土地に生まれてるのかもしれないそんなことを思いました一言で言うと受信者責任型言語ノベーションそんなことを思いました参考: テレビ寺子屋【日本語っていいですね/ジェフ・バーグランド】2025/4/19(土)フジテレビジョンhttps://www.sut-tv.com/program/terakoya/2025-05-0414 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"受信者責任型言語ノベーションノベーション(1475回)京都外国語大学教授のジェフ・バーグランドさんのお話に勇気を頂きました"英語は発信者責任型言語。発信する方が責任持ってはっきりしないといけないんです。キーン(ドナルドキーン)さんが、日本語っていいですね。自由自在に読む人が自分で解読したらいいんだと。これが僕にとっては一番日本語の特徴なんです。日本語は受信者責任型言語。自由自在に解読ができる。""実は、この受信者責任型言語というのが、他の文化を吸収していくのに大事な力なんです。だから日本人ってのは、結構受け入れる心が大きいんです。あんまり否定しないんです。全然違うもんでも、それもありかなあと、これが日本人の日本語からくる受信力だと思うんです"ここから私は思いました1、余白文化2、共創促進文化3、高コンテクスト文化1、余白文化日本語が受信者責任型言語というのは、わかりやすい視点だなと思いました。鈴木孝夫さんが『ことばと文化』(1973)の中でもお話しされているようですが、確かに、主語がなくても、下手をすれば、咳払いだけで通じるなんてのも、受け取る側が解釈できるよね、から、受け取る側で慮ることが普通に行われるなあと思いますその反面、日本人は発言しないとか、グローバルな世界では積極的な発言がないといないと同じだ、みたいなネガティヴなことも言わがちで、さらに萎縮してしまうみたいなことも感じてますでも実は悪い面だけではなく、とても良い面もたくさんあるというジェフさんのお話に勇気を頂きました。受け取る側にある程度を委ねるという意味では、受け取る側の判断、解釈を入れて初めて成立するという意味で、余白文化、といってもいいかと思いました。そして、余白があるからこそ、ずらした解釈が生まれる、誤読が生まれる、ある意味ボケが生まれる、こういったてんについては、発信した側にも、あ、そういう解釈も面白い、と受けることで、様々なものが掛け合わされる、とてもイノベ〜ディブな文化ということも言えるのかもしれないと思いました2、共創促進文化受信者責任言語においては、受け取った側の解釈を改めて発信者側に確認する行為というのが、必ず必要となると思いますそれが、まどろっこしい、もっとはっきりいってくれないから勘違いした、みたいなデメリットもありますが、それもポジティブな面から見ると、コミュニケーションを促進する構造になっている、ということも言える気がしました受信者側からの確認行為があり、さらにそこに発信者側からのさらなる発信が起き、このコミュニケーションが促進することで、実は"仲間"とのさらなるイノベーティブな意見交換ができるという意味では、これも日本文化の良い面かもしれないと思いました3、高コンテクスト文化エドワード・T・ホールさんが「高コンテクスト文化では、メッセージの多くが言語以外の手段、すなわち沈黙、間、表情、背景的状況に託される。日本はその典型である。」と言われた通り、日本では、言語以外の伝える方法を大切にしてるのかなと思います原始の時代からの、ものを叩く、声を高低で話す、物音を聞く、気配を感じる、目や仕草で伝えるという、言語を持ってしまったがために失われたことを、日本はとても大切にしてきたのかもしれないなとそしてそれは、とても豊かなコミュニケーションであり、そこから生じる豊かな感性や感情なども、大切にし続けた文化なのかと思いますそれは、きっと日本人の中に、様々な刺激や感覚、違和感や伝え方伝わり方、さらには味わい方、触れ方、見え方、聞こえ方、など、バラエティで繊細な感覚を養ってくれてるのかなあと、そんなことを思いました余白を大切にし、共創をより良しとし、様々な感じ方、伝え方を育んできた、日本文化は、とてもイノベーティブな環境であり、そんな人々が集う土地であり、これからも、そんなイノベーションをたくさん産む可能性がたくさんある、そんな土地に生まれてるのかもしれないそんなことを思いました一言で言うと受信者責任型言語ノベーションそんなことを思いました参考: テレビ寺子屋【日本語っていいですね/ジェフ・バーグランド】2025/4/19(土)フジテレビジョンhttps://www.sut-tv.com/program/terakoya/2025-05-0414 min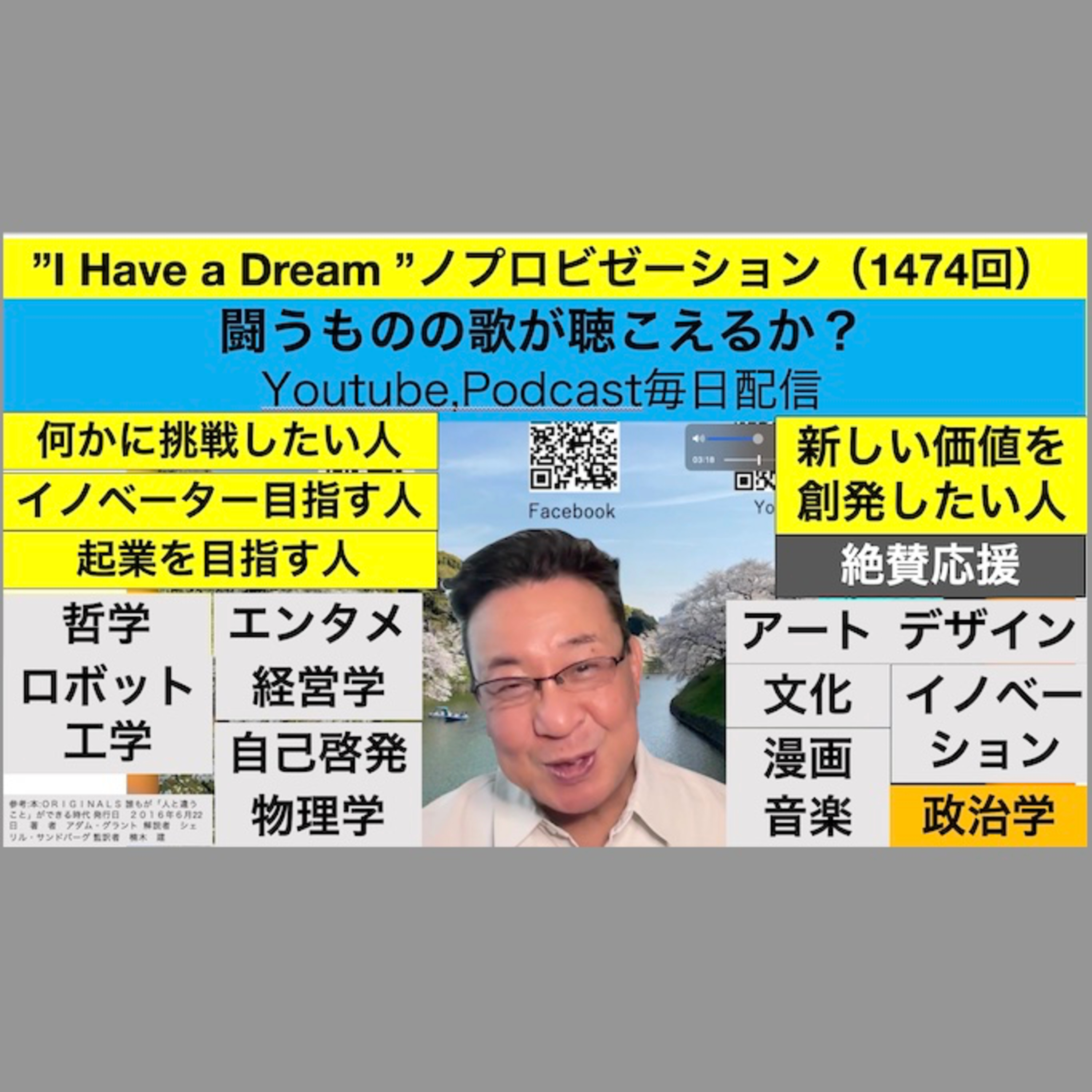 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"”I Have a Dream ”ノプロビゼーション(1474回)アダム・グラントさんより、"I Have a Dream"の歴史的演説を行ったマーティン・ルーサー・キング牧師の、その演説の秘密、に衝撃を頂きました"演説をするために壇上へ向かっているときも、さらにはマイクに近づいているときですら、キング牧師は、演説を書き直していた。 ゴスペル歌手のジャクソンがキング牧師に夢を語れとうながしたのは、演説がはじまって11分が経過したころだった。キング牧師にジャクソンの声が聞こえていたのかどうかは定かではないが、「突然、そうしようと思った」とキング牧師はのちに語っている。""オリジナリティを大いに発揮する人は、大いに先延ばしもするが、まったく計画をしないわけではない。戦略的に先延ばしをし、さまざまな可能性を試し、改良することによって少しずつ進めていく。"ここから私は思いました1、先延ばし戦略2、仲間との共鳴3、準備×即興性1、先延ばし戦略"I Have a Dream"の演説が素晴らしいと感じるのは、キング牧師の心の底から出てきている声と、誰もが希望を持ちたい"大義"を語ったからだと、私は思いますどんなに推敲を重ねた原稿だったのだろうと勝手に考えていましたが、実は当日まで全然書いておらず、先延ばしにして、その朝に実は原稿ができたとのお話に驚愕でした夏休みの宿題は、早くやっちゃいなさいとよく叱られたものですが、自分が納得できるまで最後の最後まで粘るグリッド、ネガティヴケイパビリティとして最後まで答えを追い求める力が、イノベーターなのかもしれないと思いました2、"仲間"との共鳴ジャクソンさんが言われた言葉が聞こえたのかどうかは、わかりませんが、こういった自分を応援してくれてる"仲間"がいるからこそ、共鳴が生まれてもしかしたら、自分1人だけでは思いつかなかったかのようなフレーズができたのかもしれない、と思いましたそれは、常日頃から、共鳴できる"仲間"を作っておくということがとても大切なのかと思いました。壁打ちさせてくれる仲間、深夜まで議論してくれる仲間、厳しいけれども応援してくれる、そんな人たちを日々意識して大切にしてるからこそ"仲間"とのシンパシーのある言葉が生まれたのかもしれない、そんなことを思いました3、準備×即興性そして最大の驚きだったのが、あの有名なセリフはその場で思いついたことだったのか!ということです音楽の世界では即興と言いますが、実は素敵な即興をするためには、事前の準備がめちゃくちゃ大切なことになります。このコード進行で使えるスケールのパターンは?みたいな理論的なことから、自らの手癖や、それを瞬時にキャッチして出させるようにする練習など、果てしなく準備が必要な中でそして本番当時の、メンバーの演奏、観客の反応、自分の体調、感情、最も大切なのは自分のパッション、全てが絡み合って、さらには、勇気を持ってこれまでにない即興に挑む。実はめちゃくちゃイノベータースピリッツの結果として即興が生まれてると思います。それと同様のことが、キング牧師の演説には、起こっていたのではないか、そんなことを思いました。奇跡のような即興音楽だったのではないか、そんな風に思いました私も実は世界20都市のコンテストで、最初にお話しと東京音頭と歌おうと思ったのは、実はステージに立った時でした。ということでまとめると、あの奇跡の演説は、ネガティヴケイパビリティとグリッドを使って最後の最後まで粘り強く考え、そしてこれまでの"仲間"との共鳴を通じて自分を超えたお話を、その場の雰囲気そして最後は、自らのパッションの源に従って、あの"I Have a Dream"が生まれたのかと感動してしまいました一言で言うと"I Have a Dream"ノプロビゼーション当社の名前は、イノベーションとインプロビゼイションを掛け合わせて、イノプロビゼイション(即興革新)といってますので、乗っからせて頂きました^ ^少しでも参考になりましたら、幸いです。参考:本:ORIGINALS 誰もが「人と違うこと」ができる時代 発行日 2016年6月22日 著 者 アダム・グラント 解説者 シェリル・サンドバーグ 監訳者 楠木 建動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/_Yc0wmZFKUM2025-05-0321 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"”I Have a Dream ”ノプロビゼーション(1474回)アダム・グラントさんより、"I Have a Dream"の歴史的演説を行ったマーティン・ルーサー・キング牧師の、その演説の秘密、に衝撃を頂きました"演説をするために壇上へ向かっているときも、さらにはマイクに近づいているときですら、キング牧師は、演説を書き直していた。 ゴスペル歌手のジャクソンがキング牧師に夢を語れとうながしたのは、演説がはじまって11分が経過したころだった。キング牧師にジャクソンの声が聞こえていたのかどうかは定かではないが、「突然、そうしようと思った」とキング牧師はのちに語っている。""オリジナリティを大いに発揮する人は、大いに先延ばしもするが、まったく計画をしないわけではない。戦略的に先延ばしをし、さまざまな可能性を試し、改良することによって少しずつ進めていく。"ここから私は思いました1、先延ばし戦略2、仲間との共鳴3、準備×即興性1、先延ばし戦略"I Have a Dream"の演説が素晴らしいと感じるのは、キング牧師の心の底から出てきている声と、誰もが希望を持ちたい"大義"を語ったからだと、私は思いますどんなに推敲を重ねた原稿だったのだろうと勝手に考えていましたが、実は当日まで全然書いておらず、先延ばしにして、その朝に実は原稿ができたとのお話に驚愕でした夏休みの宿題は、早くやっちゃいなさいとよく叱られたものですが、自分が納得できるまで最後の最後まで粘るグリッド、ネガティヴケイパビリティとして最後まで答えを追い求める力が、イノベーターなのかもしれないと思いました2、"仲間"との共鳴ジャクソンさんが言われた言葉が聞こえたのかどうかは、わかりませんが、こういった自分を応援してくれてる"仲間"がいるからこそ、共鳴が生まれてもしかしたら、自分1人だけでは思いつかなかったかのようなフレーズができたのかもしれない、と思いましたそれは、常日頃から、共鳴できる"仲間"を作っておくということがとても大切なのかと思いました。壁打ちさせてくれる仲間、深夜まで議論してくれる仲間、厳しいけれども応援してくれる、そんな人たちを日々意識して大切にしてるからこそ"仲間"とのシンパシーのある言葉が生まれたのかもしれない、そんなことを思いました3、準備×即興性そして最大の驚きだったのが、あの有名なセリフはその場で思いついたことだったのか!ということです音楽の世界では即興と言いますが、実は素敵な即興をするためには、事前の準備がめちゃくちゃ大切なことになります。このコード進行で使えるスケールのパターンは?みたいな理論的なことから、自らの手癖や、それを瞬時にキャッチして出させるようにする練習など、果てしなく準備が必要な中でそして本番当時の、メンバーの演奏、観客の反応、自分の体調、感情、最も大切なのは自分のパッション、全てが絡み合って、さらには、勇気を持ってこれまでにない即興に挑む。実はめちゃくちゃイノベータースピリッツの結果として即興が生まれてると思います。それと同様のことが、キング牧師の演説には、起こっていたのではないか、そんなことを思いました。奇跡のような即興音楽だったのではないか、そんな風に思いました私も実は世界20都市のコンテストで、最初にお話しと東京音頭と歌おうと思ったのは、実はステージに立った時でした。ということでまとめると、あの奇跡の演説は、ネガティヴケイパビリティとグリッドを使って最後の最後まで粘り強く考え、そしてこれまでの"仲間"との共鳴を通じて自分を超えたお話を、その場の雰囲気そして最後は、自らのパッションの源に従って、あの"I Have a Dream"が生まれたのかと感動してしまいました一言で言うと"I Have a Dream"ノプロビゼーション当社の名前は、イノベーションとインプロビゼイションを掛け合わせて、イノプロビゼイション(即興革新)といってますので、乗っからせて頂きました^ ^少しでも参考になりましたら、幸いです。参考:本:ORIGINALS 誰もが「人と違うこと」ができる時代 発行日 2016年6月22日 著 者 アダム・グラント 解説者 シェリル・サンドバーグ 監訳者 楠木 建動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/_Yc0wmZFKUM2025-05-0321 min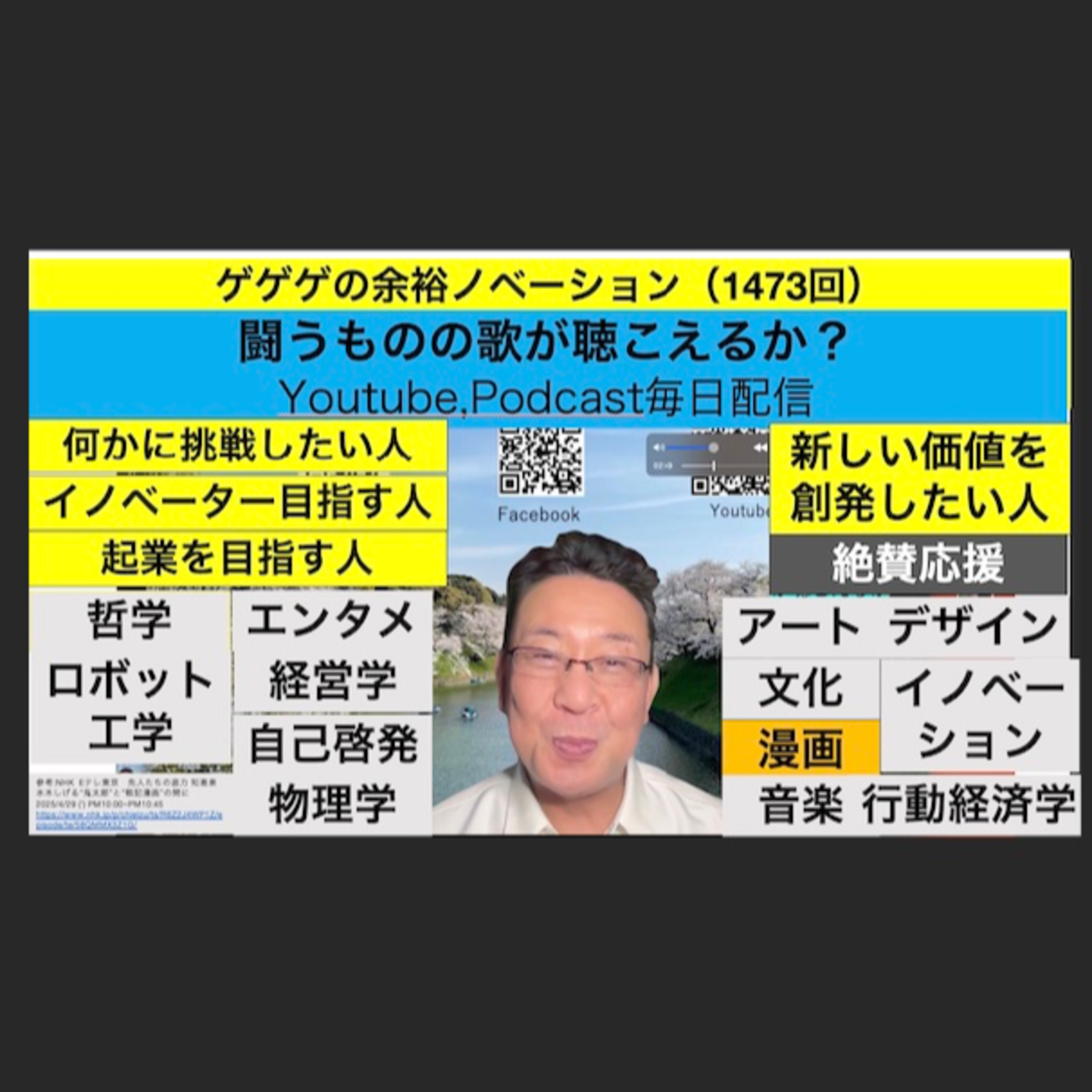 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"ゲゲゲの余裕ノベーション(1473回)ゲゲゲの鬼太郎の作者の水木しげるさんについて、語られた荒俣さんの言葉が染み渡りました荒俣さん曰く"自分の道を突き進むためには、捨てられるものは捨てる、妥協できるものは妥協するって言う余裕がないといけないんで他の人と違うのは、水木さんこの余裕があったんですよだから最後に、面白いことを書いたり、あるいは今の戦争の漫画でも、あのリアルな背景や描写をちょっと飛び越えて、人間はそれぞれちょっとコミカルな関係にあると言うあの余裕作ってたとこが、水木さんの知恵の1番大きなもの。"ここから私は思いました1、内面の余裕2、対象との余裕3、常識からの余裕1、内面の余裕小さい頃から、アニメでゲゲゲの鬼太郎は、本当によく観てたのですが、おかげで夜にトイレに行く時などは、どこかに妖怪が隠れてるのでは?とすっかり怖くなっていたことを思い出しますそれでも、目玉おやじや、ネズミ男など、個性が強いキャラが大好きで、笑えるけれども感動してスカッとできて、そして怖い、いろんな感情のスイッチを入れてくれる作品だったと思いますそんな水木さんと親交があられた荒俣宏さんからの言葉は、イノベーター水木さんを表してるなあと思いました一つは、内面の余裕、のことを思いました。これは、アドラーさんの言うところの、課題の分離、ができるかどうかに、大きく関わる気がしました。告白した彼女からの返事がなぜないのか?みたいなとこをずっと考えていても意味がないわけで、自分のコントロールできることに、集中できるかどうかというのは、心の中の時間と空間を空けてくれるものになると思います。そんな心の中の余裕があるからこそ、イノベーティブな作品を考えられる、隙間を生み出していたのだろうなあと思いました2、対象との余裕また、外部の人との間における、余裕というのもとても大事だなあと思いました。以前、精神科の先生から聞いた話ですが、あんまり親身になって聞きすぎると、心を持ってかれることがあるとつまり、精神科の先生ですら、外部の人との間に、ある程度の距離感を保っておくことを意識しないと、いけないということでした。人に共感できて、人の痛みを自分の痛みのように感じられる人は素晴らしいなあと思いますが、それが度を越してしまうと、自分自身を他人の気持ちに持ってかれるということがあるので、自分と他人の間に、ある程度の余裕を持たせた距離感というのも、大事かもしれない、そんなことを思いました3、常識からの余裕また水木さんの作品は、鬼太郎にしても、戦記にしても、これまでの常識を打ち破る作品ばかりだと思いますこれはイノベーターにも関連することですが、常識に対して、あまりも固定的に狭く捉えてしまうと、面白く無くなってしまうので、ある程度、常識の枠を広げてみる、ある意味、少し抽象化して見てみる、そんなことが大切かと思いましたそれは、イノベーションにおけるブレイクザバイアスの基本的なスタンスとして、常識を疑う、ということがありますが、もう少し抽象化して考えて見ると、また全然違う常識が含まれてくるということがあると思いますそこの部分を新たなソリューションで攻めていく、そんなことがイノベーターには大切かと思いましたということで、荒俣さんが言われたところの、水木さんの、余裕、というものについて、私なりに考えて見ましたそれこそが水木さんのイノベーションの現存ということで一言で言うとゲゲゲの余裕ノベーションそんな話をしています^ ^参考:NHK Eテレ東京 先人たちの底力 知恵泉 水木しげる“鬼太郎”と“戦記漫画”の間に 2025/4/29 (') PM10:00~PM10:45 https://www.nhk.jp/p/chieizu/ts/R6Z2J4WP1Z/episode/te/58QMMX3Z1G/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/LhRMk8-NDm02025-05-0218 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"ゲゲゲの余裕ノベーション(1473回)ゲゲゲの鬼太郎の作者の水木しげるさんについて、語られた荒俣さんの言葉が染み渡りました荒俣さん曰く"自分の道を突き進むためには、捨てられるものは捨てる、妥協できるものは妥協するって言う余裕がないといけないんで他の人と違うのは、水木さんこの余裕があったんですよだから最後に、面白いことを書いたり、あるいは今の戦争の漫画でも、あのリアルな背景や描写をちょっと飛び越えて、人間はそれぞれちょっとコミカルな関係にあると言うあの余裕作ってたとこが、水木さんの知恵の1番大きなもの。"ここから私は思いました1、内面の余裕2、対象との余裕3、常識からの余裕1、内面の余裕小さい頃から、アニメでゲゲゲの鬼太郎は、本当によく観てたのですが、おかげで夜にトイレに行く時などは、どこかに妖怪が隠れてるのでは?とすっかり怖くなっていたことを思い出しますそれでも、目玉おやじや、ネズミ男など、個性が強いキャラが大好きで、笑えるけれども感動してスカッとできて、そして怖い、いろんな感情のスイッチを入れてくれる作品だったと思いますそんな水木さんと親交があられた荒俣宏さんからの言葉は、イノベーター水木さんを表してるなあと思いました一つは、内面の余裕、のことを思いました。これは、アドラーさんの言うところの、課題の分離、ができるかどうかに、大きく関わる気がしました。告白した彼女からの返事がなぜないのか?みたいなとこをずっと考えていても意味がないわけで、自分のコントロールできることに、集中できるかどうかというのは、心の中の時間と空間を空けてくれるものになると思います。そんな心の中の余裕があるからこそ、イノベーティブな作品を考えられる、隙間を生み出していたのだろうなあと思いました2、対象との余裕また、外部の人との間における、余裕というのもとても大事だなあと思いました。以前、精神科の先生から聞いた話ですが、あんまり親身になって聞きすぎると、心を持ってかれることがあるとつまり、精神科の先生ですら、外部の人との間に、ある程度の距離感を保っておくことを意識しないと、いけないということでした。人に共感できて、人の痛みを自分の痛みのように感じられる人は素晴らしいなあと思いますが、それが度を越してしまうと、自分自身を他人の気持ちに持ってかれるということがあるので、自分と他人の間に、ある程度の余裕を持たせた距離感というのも、大事かもしれない、そんなことを思いました3、常識からの余裕また水木さんの作品は、鬼太郎にしても、戦記にしても、これまでの常識を打ち破る作品ばかりだと思いますこれはイノベーターにも関連することですが、常識に対して、あまりも固定的に狭く捉えてしまうと、面白く無くなってしまうので、ある程度、常識の枠を広げてみる、ある意味、少し抽象化して見てみる、そんなことが大切かと思いましたそれは、イノベーションにおけるブレイクザバイアスの基本的なスタンスとして、常識を疑う、ということがありますが、もう少し抽象化して考えて見ると、また全然違う常識が含まれてくるということがあると思いますそこの部分を新たなソリューションで攻めていく、そんなことがイノベーターには大切かと思いましたということで、荒俣さんが言われたところの、水木さんの、余裕、というものについて、私なりに考えて見ましたそれこそが水木さんのイノベーションの現存ということで一言で言うとゲゲゲの余裕ノベーションそんな話をしています^ ^参考:NHK Eテレ東京 先人たちの底力 知恵泉 水木しげる“鬼太郎”と“戦記漫画”の間に 2025/4/29 (') PM10:00~PM10:45 https://www.nhk.jp/p/chieizu/ts/R6Z2J4WP1Z/episode/te/58QMMX3Z1G/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/LhRMk8-NDm02025-05-0218 min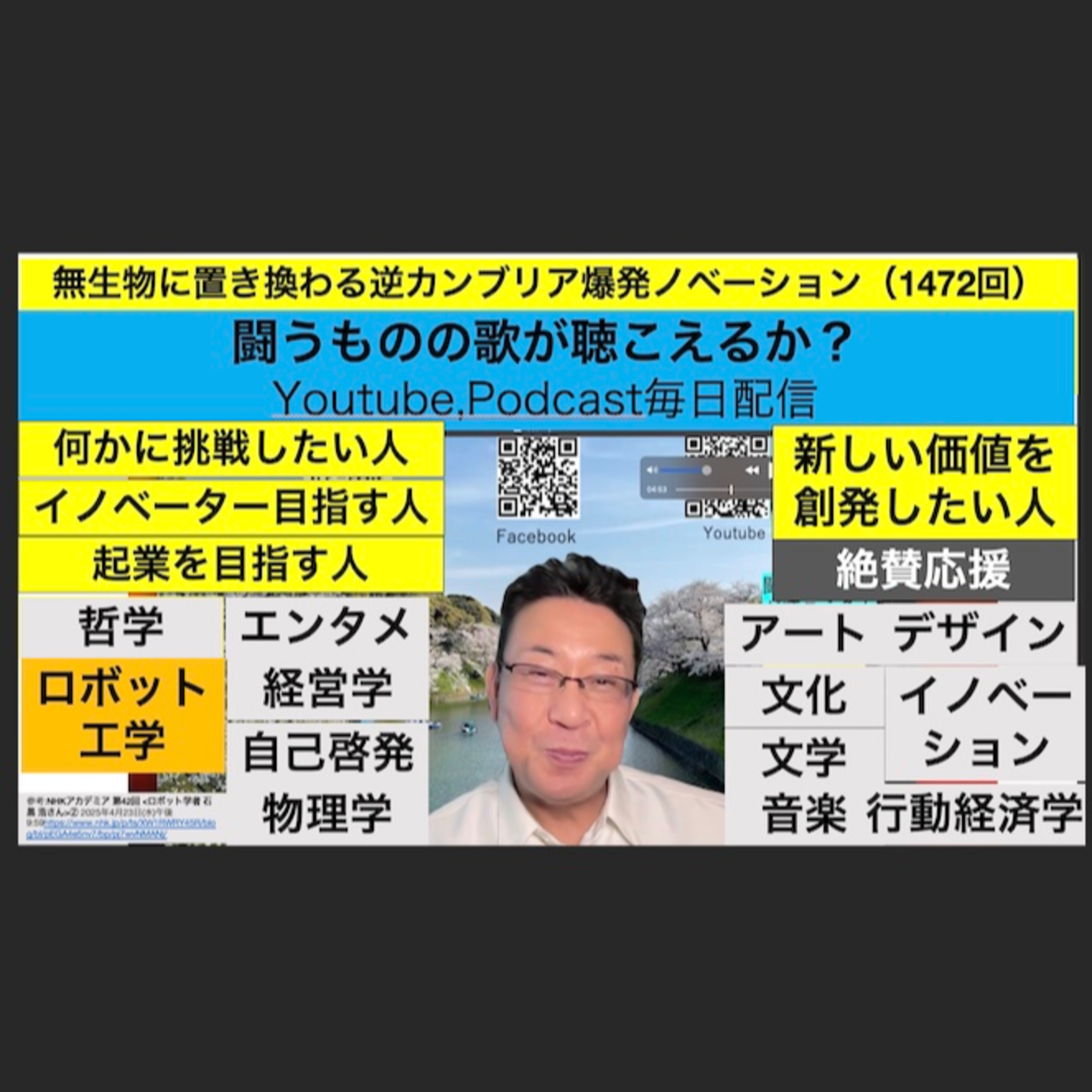 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"無生物に置き換わる逆カンブリア爆発ノベーション(1472回)ロボット研究の世界的な第一人者の石黒浩さんの、未来を見通す目に、驚愕しました"進化というのは、多様性に支えられてきたものなんですよね。動物の進化も人間の進化もそうです。いろんな形の動物を生み出して、その中で環境に適応したものが生き残ってきた。機械の体になること、テクノロジーによって体を機械に置き換える、無生物に置き換えることに、もし大きな意味があるとすると再びカンブリア爆発のような大きな進化を我々は成し遂げることができるのではないかなということであります"ここから私は思いました1、人類が進化の加速装置2、生物×無生物の掛け合わせ3、逆カンブリア爆発1、人類が進化の加速装置地球が何十万年もかけて進化の形を作り出してきたことを、人類は技術革新やイノベーションを通じて、数年単位で急速に成長を遂げてきてることを考えると地球にとっては、望まれたのか望まれてないのかは知りませんが、人類は地球における進化の加速装置として出現したと言ってもいいのかもしれないと思いましたそれが地球にとって良い方向へ進むのか?どうか?についても、また果たして進化なのか?衰退なのか?と言うことについては、後々の歴史に聞くしかないので分かりませんがもしかしたら、我々は地球から見ると、これまでの進化のスピードを加速するモノタチという見え方をしてるのかもしれないなあと思いました2、生物×無生物の掛け合わせそして石黒先生の未来を見通す目に驚愕したのが、今起きているロボティクス化というこは、人類が無生物に置き換わることであり、それは、ある意味、これまでの生物同士の掛け算だった時代から、ついに無生物との掛け算を始めているということなのかもしれないと、思いましたその掛け算のイノベーションの先がどこへ向かっていくのか、まさに前人未到の世界への第一歩に今自分たちはいるのかもしれないと思いました3、逆カンブリア爆発そう考えると、カンブリア爆発が、静物の多様性の根本となっていることを考えると、ここから生まれる生物と無生物の掛け算によって、新たな進化の系図として、生物と無生物のピラミッドができていくということなのかもしれないと思いましたそれは、カンブリア爆発が、無生物から生物の多様性の大元だったとすると、今この時は、生物から無生物へ向かう多様性のツリーの始まりの時として、言ってみれば逆カンブリア爆発なのかもしれない、そんなことを思いましたそしてその先は、どこへ行くのかがとても気になりますが、これから地球環境がもっと悪くなって、他の星へ住むようなことにならざるを得なくなれば進化論の適用条件によって、もしかしたら、生物側が淘汰されることになり、無生物側が進化の適応側として生き残っていく、そんな未来がもしかしたら本当にあるような気がしてきましたでもそれは、ディストピアなのか?ということに関しては、もしかしたら、今の人類が当たり前の生活をしながら当たり前の幸せを求めてるように、何も変わらずに幸せを求めている存在なだけかもしれない、そんなことも思いました実は今は本当に地球史上、大きな進化の爆発の地点にいるのかもしれない未来から見ると実は今は、無生物に置き換わる重要な転換点として無生物に置き換わる逆カンブリア爆発ノベーションそんなことを思いました参考:NHKアカデミア 第42回 ② 2025年4月23日(水)午後9:59https://www.nhk.jp/p/ts/XW1RWRY45R/blog/bl/pEGA4e5nv7/bp/pj7wvNMANj/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/VkQJbH5nUOg2025-05-0117 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"無生物に置き換わる逆カンブリア爆発ノベーション(1472回)ロボット研究の世界的な第一人者の石黒浩さんの、未来を見通す目に、驚愕しました"進化というのは、多様性に支えられてきたものなんですよね。動物の進化も人間の進化もそうです。いろんな形の動物を生み出して、その中で環境に適応したものが生き残ってきた。機械の体になること、テクノロジーによって体を機械に置き換える、無生物に置き換えることに、もし大きな意味があるとすると再びカンブリア爆発のような大きな進化を我々は成し遂げることができるのではないかなということであります"ここから私は思いました1、人類が進化の加速装置2、生物×無生物の掛け合わせ3、逆カンブリア爆発1、人類が進化の加速装置地球が何十万年もかけて進化の形を作り出してきたことを、人類は技術革新やイノベーションを通じて、数年単位で急速に成長を遂げてきてることを考えると地球にとっては、望まれたのか望まれてないのかは知りませんが、人類は地球における進化の加速装置として出現したと言ってもいいのかもしれないと思いましたそれが地球にとって良い方向へ進むのか?どうか?についても、また果たして進化なのか?衰退なのか?と言うことについては、後々の歴史に聞くしかないので分かりませんがもしかしたら、我々は地球から見ると、これまでの進化のスピードを加速するモノタチという見え方をしてるのかもしれないなあと思いました2、生物×無生物の掛け合わせそして石黒先生の未来を見通す目に驚愕したのが、今起きているロボティクス化というこは、人類が無生物に置き換わることであり、それは、ある意味、これまでの生物同士の掛け算だった時代から、ついに無生物との掛け算を始めているということなのかもしれないと、思いましたその掛け算のイノベーションの先がどこへ向かっていくのか、まさに前人未到の世界への第一歩に今自分たちはいるのかもしれないと思いました3、逆カンブリア爆発そう考えると、カンブリア爆発が、静物の多様性の根本となっていることを考えると、ここから生まれる生物と無生物の掛け算によって、新たな進化の系図として、生物と無生物のピラミッドができていくということなのかもしれないと思いましたそれは、カンブリア爆発が、無生物から生物の多様性の大元だったとすると、今この時は、生物から無生物へ向かう多様性のツリーの始まりの時として、言ってみれば逆カンブリア爆発なのかもしれない、そんなことを思いましたそしてその先は、どこへ行くのかがとても気になりますが、これから地球環境がもっと悪くなって、他の星へ住むようなことにならざるを得なくなれば進化論の適用条件によって、もしかしたら、生物側が淘汰されることになり、無生物側が進化の適応側として生き残っていく、そんな未来がもしかしたら本当にあるような気がしてきましたでもそれは、ディストピアなのか?ということに関しては、もしかしたら、今の人類が当たり前の生活をしながら当たり前の幸せを求めてるように、何も変わらずに幸せを求めている存在なだけかもしれない、そんなことも思いました実は今は本当に地球史上、大きな進化の爆発の地点にいるのかもしれない未来から見ると実は今は、無生物に置き換わる重要な転換点として無生物に置き換わる逆カンブリア爆発ノベーションそんなことを思いました参考:NHKアカデミア 第42回 ② 2025年4月23日(水)午後9:59https://www.nhk.jp/p/ts/XW1RWRY45R/blog/bl/pEGA4e5nv7/bp/pj7wvNMANj/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/VkQJbH5nUOg2025-05-0117 min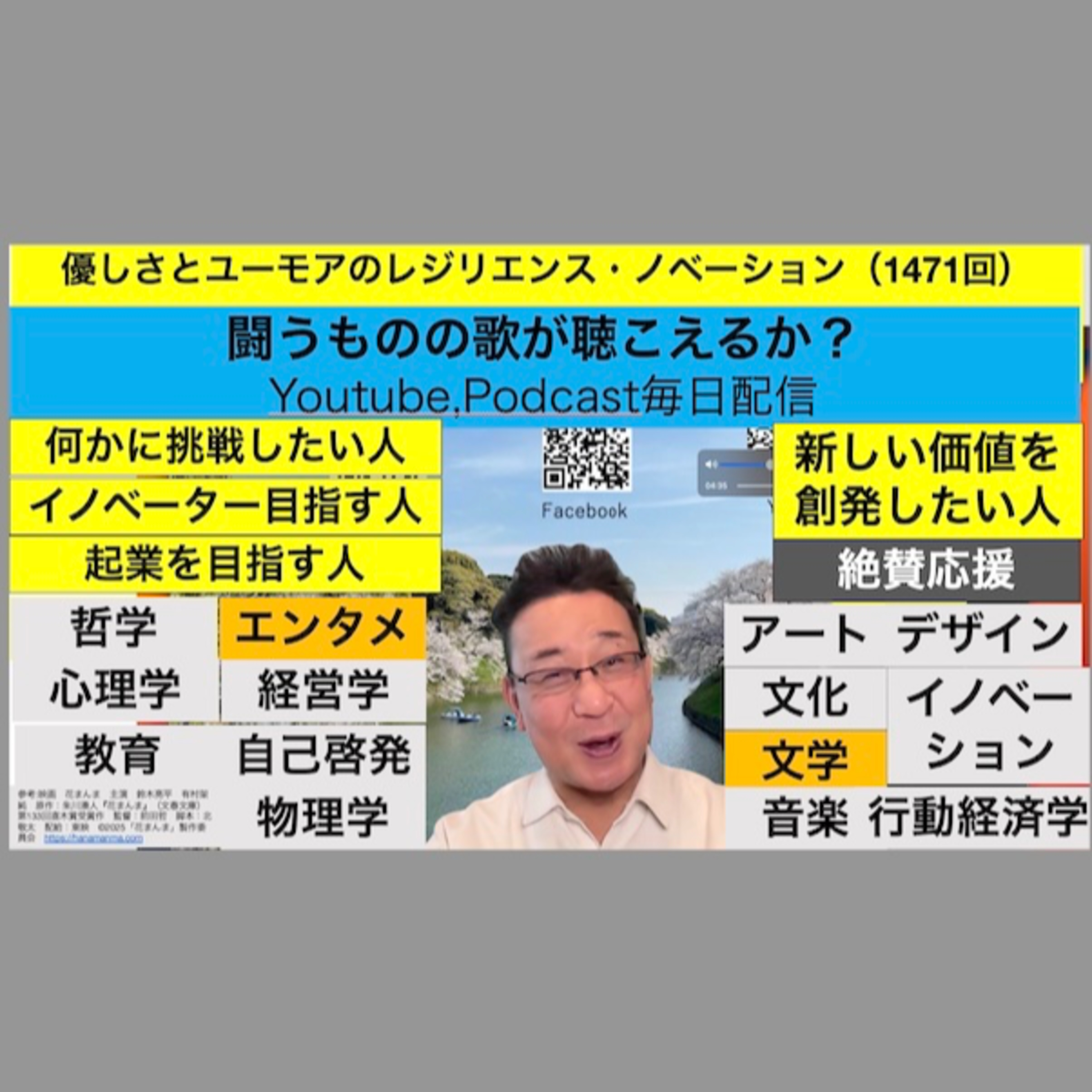 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"優しさとユーモアのレジリエンス・ノベーション(1471回)大号泣の"映画 花まんま"における、前田哲監督の思いに感動しました"舞台となる大阪という土壌の気質もあるのかもしれませんが、朱川作品の魅力は、笑いと悲しみが表裏一体なことです。怖いけど優しい。せつないけれど希望がある。泣けるのに笑え、笑えるのに泣ける。過酷な状況こそ茶化し、ユーモアで対抗する。お上を信用しない大阪人の反骨心に通じるバイタリティと、弱者への優しい視線ではないかと思います。人生は、残酷だからこそ、ユーモアが必要。そういう部分は、私の映画作りともフィットしている。"(パンフレットより)ここから私は思いました1、逆境からのレジリエンス2、弱者への優しさ3、反骨心からのユーモア1、逆境からのレジリエンスこの物語は、ある意味、残酷な逆境に陥った人たちのレジリエンスの物語なのかなあと思いました。どんな人においても、突然の逆境は、訪れることがあって、それをどうやって乗り越えるのか?と言う問いかけをしてくれてる気がしましたイノベーションにおいては、それこそ、逆境だらけなわけですが、この映画に出てくるような人生の逆境の人たちがひたむきに、自らの人生や周りの仲間と正直にぶつかり合いながら、生きていく姿は、決して諦めないと言う、勇気と希望を頂きました2、弱者への優しさテレビやメディアで流される国内外の弱者と言われる人たちを、普段はのんびり見ている自分たちも、ある時から突然弱者になる可能性があると言うことを、常日頃感じてることは大事だと思いましたそう考えると、そんな弱者と言われている人たちへの、自分と同じ人たちなんだと感じることから生じる新しい見え方を、とても優しい描き方で教えてくれた気がしましたイノベーションにおいては、情熱の源は、自分や誰かの強烈な痛み(ペイン)を、自分毎に感じることができたときに、灯火として燃え始めると思います。そう言う視点を常日頃持てるのかと言うことが、実はイノベーターとして生きていく覚悟があるのか、と追うことと、とても同じなのかもしれないと、そんなことを思わせて頂きました3、反骨心からのユーモア池田監督が言われているように、大阪の皆様には、逆境へのレジリエンス力が風土や文化として、とてもタフネスにある気がしましたそれがなぜなのかは分かりませんが、一番感じるのは、強烈な反骨心(私の中ではロックスピリッツ)と、それを直接ぶつけることよりも、ユーモアで面白くしながら、笑いながら変えていってやろう、と言うことが、とても素敵だなあと思いました現実はとてつもなく残酷なことがある中で、だからこその、それに負けてたまるかスピリッツとしての、しかもさらに上をいくユーモアで対抗する、これは究極のレジリエンスであり、復活の狼煙になるなあと、そしてそれこそが、号泣する感動にもつながると、そんなことを思わせて頂きましたそれはイノベーションでも全く同じで、辛い現実が続くからこその、ユーモアを持ったポジティブシンキングで、決して諦めない、だからこそ、成功した起業家は、成功の理由を、諦めなかったから、と言えるし私が歌っているアカペラも、元々はゴスペルから始まったいますが、苦役や辛い労働の中でも、負けるもんか魂で、みんなで歌って踊って、全てを吹き飛ばしながら、前へ向くパワーをもらっていくそんなことらがとても共通してるなあと思いましたヴィクトール・フランクルの『夜と霧』で言われていた「ユーモアは、困難な状況においても人々が希望を見出し、前向きに生きる力を与える。」が、心に沁みてきたそんなこんなで号泣が止まらない映画でしたが、一言で言うと優しさとユーモアのレジリエンス・ノベーションそんなことを感じました^ ^参考:映画 花まんま 主演 鈴木亮平 有村架純 原作:朱川湊人『花まんま』(文春文庫)第133回直木賞受賞作 監督:前田哲 脚本:北敬太 配給:東映 ©2025「花まんま」製作委員会 https://hanamanma.com2025-04-3020 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"優しさとユーモアのレジリエンス・ノベーション(1471回)大号泣の"映画 花まんま"における、前田哲監督の思いに感動しました"舞台となる大阪という土壌の気質もあるのかもしれませんが、朱川作品の魅力は、笑いと悲しみが表裏一体なことです。怖いけど優しい。せつないけれど希望がある。泣けるのに笑え、笑えるのに泣ける。過酷な状況こそ茶化し、ユーモアで対抗する。お上を信用しない大阪人の反骨心に通じるバイタリティと、弱者への優しい視線ではないかと思います。人生は、残酷だからこそ、ユーモアが必要。そういう部分は、私の映画作りともフィットしている。"(パンフレットより)ここから私は思いました1、逆境からのレジリエンス2、弱者への優しさ3、反骨心からのユーモア1、逆境からのレジリエンスこの物語は、ある意味、残酷な逆境に陥った人たちのレジリエンスの物語なのかなあと思いました。どんな人においても、突然の逆境は、訪れることがあって、それをどうやって乗り越えるのか?と言う問いかけをしてくれてる気がしましたイノベーションにおいては、それこそ、逆境だらけなわけですが、この映画に出てくるような人生の逆境の人たちがひたむきに、自らの人生や周りの仲間と正直にぶつかり合いながら、生きていく姿は、決して諦めないと言う、勇気と希望を頂きました2、弱者への優しさテレビやメディアで流される国内外の弱者と言われる人たちを、普段はのんびり見ている自分たちも、ある時から突然弱者になる可能性があると言うことを、常日頃感じてることは大事だと思いましたそう考えると、そんな弱者と言われている人たちへの、自分と同じ人たちなんだと感じることから生じる新しい見え方を、とても優しい描き方で教えてくれた気がしましたイノベーションにおいては、情熱の源は、自分や誰かの強烈な痛み(ペイン)を、自分毎に感じることができたときに、灯火として燃え始めると思います。そう言う視点を常日頃持てるのかと言うことが、実はイノベーターとして生きていく覚悟があるのか、と追うことと、とても同じなのかもしれないと、そんなことを思わせて頂きました3、反骨心からのユーモア池田監督が言われているように、大阪の皆様には、逆境へのレジリエンス力が風土や文化として、とてもタフネスにある気がしましたそれがなぜなのかは分かりませんが、一番感じるのは、強烈な反骨心(私の中ではロックスピリッツ)と、それを直接ぶつけることよりも、ユーモアで面白くしながら、笑いながら変えていってやろう、と言うことが、とても素敵だなあと思いました現実はとてつもなく残酷なことがある中で、だからこその、それに負けてたまるかスピリッツとしての、しかもさらに上をいくユーモアで対抗する、これは究極のレジリエンスであり、復活の狼煙になるなあと、そしてそれこそが、号泣する感動にもつながると、そんなことを思わせて頂きましたそれはイノベーションでも全く同じで、辛い現実が続くからこその、ユーモアを持ったポジティブシンキングで、決して諦めない、だからこそ、成功した起業家は、成功の理由を、諦めなかったから、と言えるし私が歌っているアカペラも、元々はゴスペルから始まったいますが、苦役や辛い労働の中でも、負けるもんか魂で、みんなで歌って踊って、全てを吹き飛ばしながら、前へ向くパワーをもらっていくそんなことらがとても共通してるなあと思いましたヴィクトール・フランクルの『夜と霧』で言われていた「ユーモアは、困難な状況においても人々が希望を見出し、前向きに生きる力を与える。」が、心に沁みてきたそんなこんなで号泣が止まらない映画でしたが、一言で言うと優しさとユーモアのレジリエンス・ノベーションそんなことを感じました^ ^参考:映画 花まんま 主演 鈴木亮平 有村架純 原作:朱川湊人『花まんま』(文春文庫)第133回直木賞受賞作 監督:前田哲 脚本:北敬太 配給:東映 ©2025「花まんま」製作委員会 https://hanamanma.com2025-04-3020 min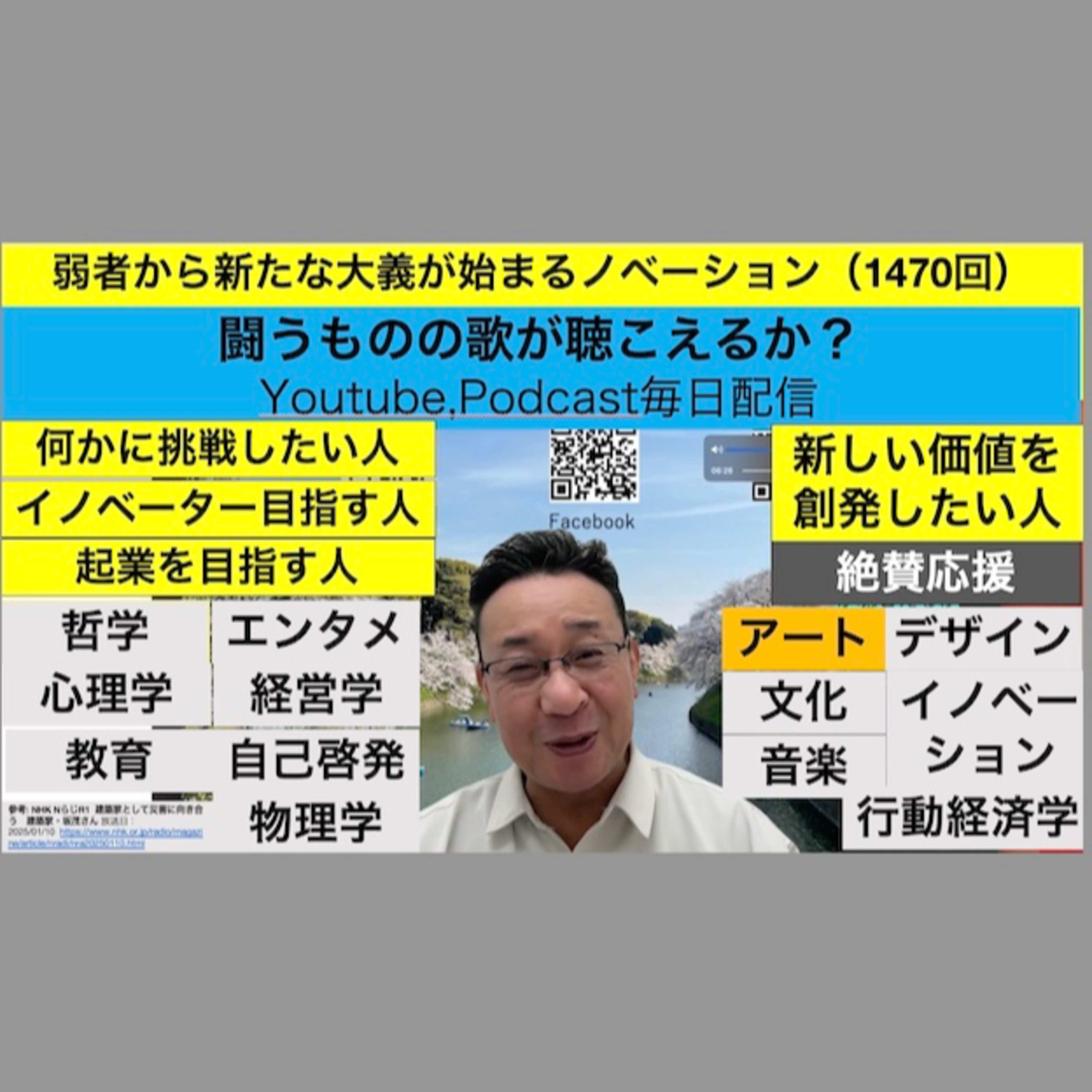 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"弱者から新たな大義が始まるノベーション(1470回)建築分野の国際的な賞であるプリツカー賞を受け、また日本人として初めてマザーテレサ社会正義賞を受賞された、坂茂の言葉に震えました曰く"それは、建築の仕事を10年くらいやってみてわかったのですけれど、われわれ建築家というのはあまり社会の役に立っていないんですよ。なぜかというと、われわれのクライアントはみんな特権階級ですね。財力があったり政治力があったり。それがすごくむなしく感じ始めましてね。特に地震のあとに気がついたんですけれど、地震で人が死ぬわけではないんですよ。建築が崩れて人が死ぬんですね。だから、われわれ建築家の責任であるにも関わらず、そのあと街が復興するとき、また新しい仕事が来るわけですよ。ところが、街が復興する前に避難所や仮設住宅という非常に劣悪な住環境に、みなさん追いやられるわけですね。それを改善するのも、僕ら建築家の責任ではないかなと思って始めたんです。"ここから私は思いました1. 社会的弱者への視点2. 既存のシステムの歪み3. 行動からの新たな大義1. 社会的弱者への視点イノベーションには、必ず起点となる真の課題があると思いますが、社会において最もペインの強い課題を持たれているのが、期せずして社会的弱者という立場になってしまった人かもしれないなあと思いました阪さんが、被災地に行かれた際に、その違和感が強烈に巻き起こって、そして自らの建築家としてのあり方にまで、当事者意識で捉えられていったのかなあと思いますこれはまさに、イノベーションにおける、現場100回行くことによって、その場にいる人たちの本当の痛みを知って、自らであれば何ができるか、というインサイトに繋がる行動とまさに同じだなあと感じました2. 既存のシステムの歪みまた、これまで数々の賞を受賞されてきたにもかかわらず、その社会的なシステムに違和感を投げかけることができる姿勢にも、とても感動しました成功体験を追随するのではなく、これまでの在り方に、本当にそれでいいのか?という問いを常に持ちつづけられてるのだろうなあと、そしてある意味、特権階級へのロックスピリッツを、強烈に感じましたヨーゼフボイスさんの社会彫刻ではありませんが、建築家として、社会システム全体に実は歪みがあることを発見し、それを再構築する必要があるという、大きな意味での建築家としてのパッションが炸裂し始めているように思いました3. 行動からの新たな大義阪さんの本当にすごいなあと思うのは、その違和感に飛び込んで、まさに、自ら実現しようと、具体的な行動を起こされていることかと思います最初はもしかすると大変な活動と思われたところが、現場の仲間との行動を進めていくようになって、次第にそれ自身が、自らがやるべきこと、つまり自らの新しい大義として、感じられる活動になったからこそ、これまでの建築家としての活動と、並行して実施されることができる出るのかもしれないこれまで培ってきた素晴らしい活動や大義にとどまらずに、常に新たな違和感からの、さらなる新たな大義を作り出し向かわれる姿勢は、真のイノベーターそのものだなあと思いました今回の事例から一言で言うと弱者から新たな大義が始まるノベーションそんなことを思いました^ ^参考: NHK NらじR1 建築家として災害に向き合う 建築家・坂茂さん 放送日:2025/01/10 https://www.nhk.or.jp/radio/magazine/article/nradi/nra20250110.html2025-04-2917 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"弱者から新たな大義が始まるノベーション(1470回)建築分野の国際的な賞であるプリツカー賞を受け、また日本人として初めてマザーテレサ社会正義賞を受賞された、坂茂の言葉に震えました曰く"それは、建築の仕事を10年くらいやってみてわかったのですけれど、われわれ建築家というのはあまり社会の役に立っていないんですよ。なぜかというと、われわれのクライアントはみんな特権階級ですね。財力があったり政治力があったり。それがすごくむなしく感じ始めましてね。特に地震のあとに気がついたんですけれど、地震で人が死ぬわけではないんですよ。建築が崩れて人が死ぬんですね。だから、われわれ建築家の責任であるにも関わらず、そのあと街が復興するとき、また新しい仕事が来るわけですよ。ところが、街が復興する前に避難所や仮設住宅という非常に劣悪な住環境に、みなさん追いやられるわけですね。それを改善するのも、僕ら建築家の責任ではないかなと思って始めたんです。"ここから私は思いました1. 社会的弱者への視点2. 既存のシステムの歪み3. 行動からの新たな大義1. 社会的弱者への視点イノベーションには、必ず起点となる真の課題があると思いますが、社会において最もペインの強い課題を持たれているのが、期せずして社会的弱者という立場になってしまった人かもしれないなあと思いました阪さんが、被災地に行かれた際に、その違和感が強烈に巻き起こって、そして自らの建築家としてのあり方にまで、当事者意識で捉えられていったのかなあと思いますこれはまさに、イノベーションにおける、現場100回行くことによって、その場にいる人たちの本当の痛みを知って、自らであれば何ができるか、というインサイトに繋がる行動とまさに同じだなあと感じました2. 既存のシステムの歪みまた、これまで数々の賞を受賞されてきたにもかかわらず、その社会的なシステムに違和感を投げかけることができる姿勢にも、とても感動しました成功体験を追随するのではなく、これまでの在り方に、本当にそれでいいのか?という問いを常に持ちつづけられてるのだろうなあと、そしてある意味、特権階級へのロックスピリッツを、強烈に感じましたヨーゼフボイスさんの社会彫刻ではありませんが、建築家として、社会システム全体に実は歪みがあることを発見し、それを再構築する必要があるという、大きな意味での建築家としてのパッションが炸裂し始めているように思いました3. 行動からの新たな大義阪さんの本当にすごいなあと思うのは、その違和感に飛び込んで、まさに、自ら実現しようと、具体的な行動を起こされていることかと思います最初はもしかすると大変な活動と思われたところが、現場の仲間との行動を進めていくようになって、次第にそれ自身が、自らがやるべきこと、つまり自らの新しい大義として、感じられる活動になったからこそ、これまでの建築家としての活動と、並行して実施されることができる出るのかもしれないこれまで培ってきた素晴らしい活動や大義にとどまらずに、常に新たな違和感からの、さらなる新たな大義を作り出し向かわれる姿勢は、真のイノベーターそのものだなあと思いました今回の事例から一言で言うと弱者から新たな大義が始まるノベーションそんなことを思いました^ ^参考: NHK NらじR1 建築家として災害に向き合う 建築家・坂茂さん 放送日:2025/01/10 https://www.nhk.or.jp/radio/magazine/article/nradi/nra20250110.html2025-04-2917 min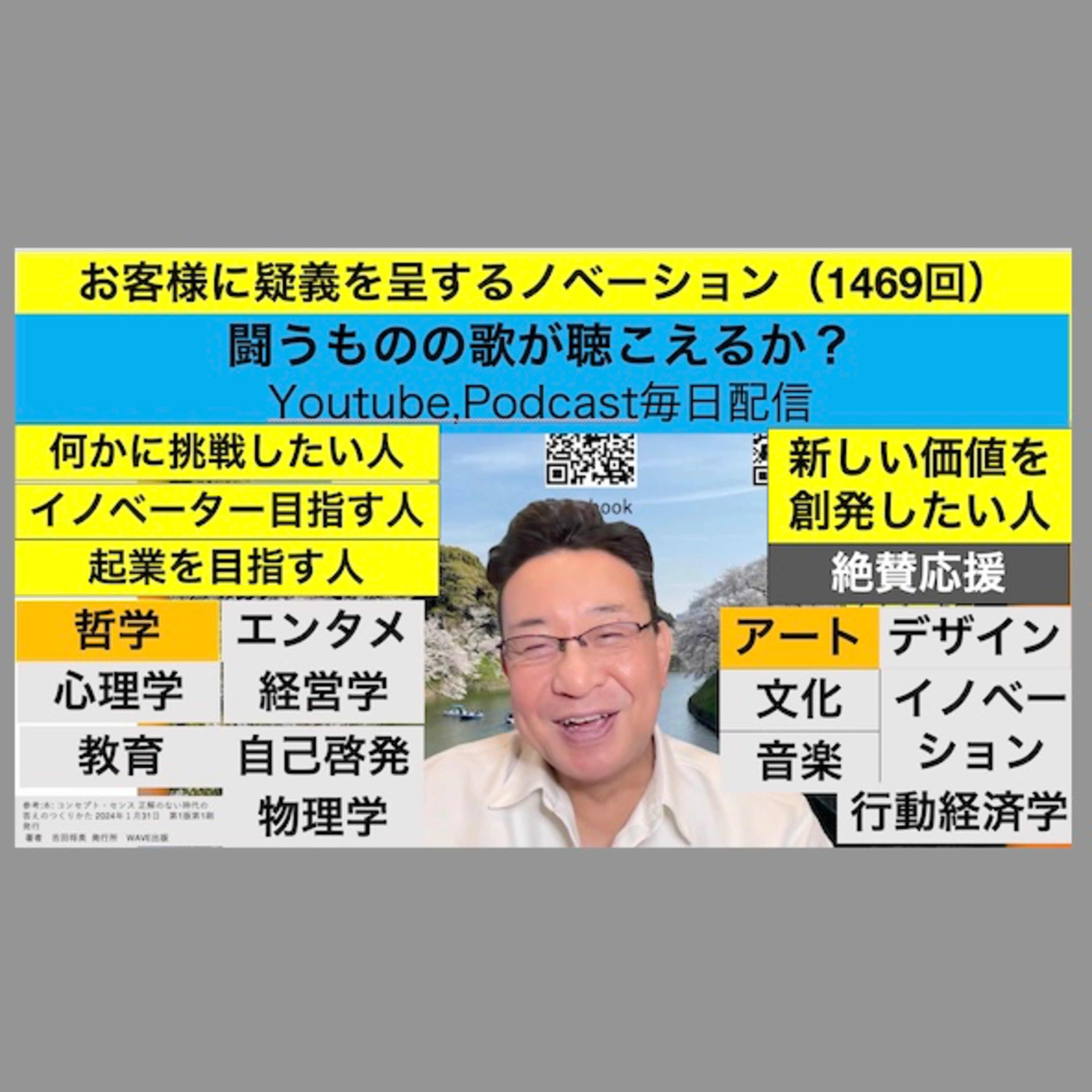 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"お客様に疑義を呈するノベーション(1469回)吉田将英より、岡本太郎さんが、大阪万博の太陽の塔の依頼の受け方に、衝撃をいただきました曰く"太陽の塔は1970年の大阪万博の最大のシンボルの1つとして、岡本太郎に依頼されたものです。大阪万博そのもののコンセプトは「人類の進歩と調和」。当然、岡本太郎はそのコンセプトにそぐうものを期待されたわけですが、そこに彼は疑義を呈します。"岡本太郎さん曰く"つまりは、進歩とは何か。逆に我々、本当の自分の生き方、自分の生命の全体性、それから肉体の全体性を失っていると。私は本当に進歩に疑問を持っている。〜映画「太陽の塔」より〜"ここから私は思いました1、期待を疑い、世界を再定議する→真の課題への疑義2、「人間の未来」への哲学的問い→そもそもの課題への深堀3、あくまでもパッションの源に従う→×お客様の課題の創発1、期待を疑い、世界を再定議する→真の課題への疑義真の営業は、お客様の言葉を鵜呑みにしちゃいかん、とよく叩き込まれましたが、これをやるのは本当に難しいと実感してます。一旦は飲み込んで、そしてそこから、本当の課題はどこにあるのかを探っていく、というやり方をするのですが岡本太郎さんは、そんなまどろっこしいことはせずに、お客様からの依頼を、違う、と返す、そのこと自体に、驚きを関しました。しかしながら、それこそが、実はお客様が気づいていない真の課題であり、価値である可能性があるとすれば、お客様のためにもなるのだ、ということを、このお話は示してくれていると思いましたそしてこれは、スティーブジョブスさんの 「人々は自分たちが欲しいものを知らない。見せてもらうまでは。」という言葉を思い出させてくれました2、「人間の未来」への哲学的問い→そもそもの課題への深堀だとすると何が真の課題なのか、ということに辿り着かねばならないのですが、太郎さんは、そもそも人間はなんのために生きるのか?という根源的な哲学的なところまで、深く掘りながらその答えを待つようとされてるのかもしれないと思いましたこれは、お客様の課題に対する問い、そのものを疑っていくという、ラテラルシンキングを繰り返しているようにも思いましたそもそも人はなんのために生き、そしてどんな未来が在るべきなのか、そこまで深く哲学的に考えるからこそ、単なる進歩ではなく、縄文時代から続く人間の本質的な価値まで遡って、あの太陽の塔ができたのかと感動しましたそしてこれは、イーロン・マスクさんのおっしゃられた、「人類が多惑星種になること」(=地球外でも生存可能な文明を作る)、という言葉にも通じる、人類の未来に対する究極の哲学的な問いを探る営みだなあと思いました3、あくまでもパッションの源に従う→×お客様の課題の創発これはお客様の逆を行くべきだとか、あえて反論をしてみるなどのテクニック的なことでは、全くなくて、あくまでも、自らのパッションの源に従う、それに忠実であるということが、最も大切なことかと思いますお客様からの依頼がある場合、どうしてもその依頼内容に寄り添ってしまう、ということがあると思いますが、まずは、自らのパッションの源は、どう言ってるのか?それを一旦、見つめて、そこから、お客様の本当に解決すべき課題を見つめるということが大事だと思いましたそれは、自らのパッションの源に、掛けることの、お客様の課題という言い方ができるかと思います。以前から私が言っている、自分軸と他人軸の交わりの創発につなかっていくお話にもなると思いましたパッションの源に従うお話としては、エドワード・デシとリチャード・ライアンの「自己決定理論」が有名かと思います。自己の内発的動機に基づく行動こそが、真の成長と創造につながる、それは、まさにパッションの源にどれだけ準じているか、それが成長とクリエイティブにつながる、イノベーターにつながる、そんなことにもなるかと思いました一言で言うとお客様からの依頼であっても、自らのパッションの源に忠実であれ、そしてそれを掛け合わせてお客様も気づいていない、新たな真の課題に辿り着く、そのためにはお客様に疑義を呈するノベーションそんなことを思いました参考:本: コンセプト・センス 正解のない時代の答えのつくりかた 2024年1月31日 第1版第1刷発行 著者 吉田将英 発行所 WAVE出版2025-04-2821 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"お客様に疑義を呈するノベーション(1469回)吉田将英より、岡本太郎さんが、大阪万博の太陽の塔の依頼の受け方に、衝撃をいただきました曰く"太陽の塔は1970年の大阪万博の最大のシンボルの1つとして、岡本太郎に依頼されたものです。大阪万博そのもののコンセプトは「人類の進歩と調和」。当然、岡本太郎はそのコンセプトにそぐうものを期待されたわけですが、そこに彼は疑義を呈します。"岡本太郎さん曰く"つまりは、進歩とは何か。逆に我々、本当の自分の生き方、自分の生命の全体性、それから肉体の全体性を失っていると。私は本当に進歩に疑問を持っている。〜映画「太陽の塔」より〜"ここから私は思いました1、期待を疑い、世界を再定議する→真の課題への疑義2、「人間の未来」への哲学的問い→そもそもの課題への深堀3、あくまでもパッションの源に従う→×お客様の課題の創発1、期待を疑い、世界を再定議する→真の課題への疑義真の営業は、お客様の言葉を鵜呑みにしちゃいかん、とよく叩き込まれましたが、これをやるのは本当に難しいと実感してます。一旦は飲み込んで、そしてそこから、本当の課題はどこにあるのかを探っていく、というやり方をするのですが岡本太郎さんは、そんなまどろっこしいことはせずに、お客様からの依頼を、違う、と返す、そのこと自体に、驚きを関しました。しかしながら、それこそが、実はお客様が気づいていない真の課題であり、価値である可能性があるとすれば、お客様のためにもなるのだ、ということを、このお話は示してくれていると思いましたそしてこれは、スティーブジョブスさんの 「人々は自分たちが欲しいものを知らない。見せてもらうまでは。」という言葉を思い出させてくれました2、「人間の未来」への哲学的問い→そもそもの課題への深堀だとすると何が真の課題なのか、ということに辿り着かねばならないのですが、太郎さんは、そもそも人間はなんのために生きるのか?という根源的な哲学的なところまで、深く掘りながらその答えを待つようとされてるのかもしれないと思いましたこれは、お客様の課題に対する問い、そのものを疑っていくという、ラテラルシンキングを繰り返しているようにも思いましたそもそも人はなんのために生き、そしてどんな未来が在るべきなのか、そこまで深く哲学的に考えるからこそ、単なる進歩ではなく、縄文時代から続く人間の本質的な価値まで遡って、あの太陽の塔ができたのかと感動しましたそしてこれは、イーロン・マスクさんのおっしゃられた、「人類が多惑星種になること」(=地球外でも生存可能な文明を作る)、という言葉にも通じる、人類の未来に対する究極の哲学的な問いを探る営みだなあと思いました3、あくまでもパッションの源に従う→×お客様の課題の創発これはお客様の逆を行くべきだとか、あえて反論をしてみるなどのテクニック的なことでは、全くなくて、あくまでも、自らのパッションの源に従う、それに忠実であるということが、最も大切なことかと思いますお客様からの依頼がある場合、どうしてもその依頼内容に寄り添ってしまう、ということがあると思いますが、まずは、自らのパッションの源は、どう言ってるのか?それを一旦、見つめて、そこから、お客様の本当に解決すべき課題を見つめるということが大事だと思いましたそれは、自らのパッションの源に、掛けることの、お客様の課題という言い方ができるかと思います。以前から私が言っている、自分軸と他人軸の交わりの創発につなかっていくお話にもなると思いましたパッションの源に従うお話としては、エドワード・デシとリチャード・ライアンの「自己決定理論」が有名かと思います。自己の内発的動機に基づく行動こそが、真の成長と創造につながる、それは、まさにパッションの源にどれだけ準じているか、それが成長とクリエイティブにつながる、イノベーターにつながる、そんなことにもなるかと思いました一言で言うとお客様からの依頼であっても、自らのパッションの源に忠実であれ、そしてそれを掛け合わせてお客様も気づいていない、新たな真の課題に辿り着く、そのためにはお客様に疑義を呈するノベーションそんなことを思いました参考:本: コンセプト・センス 正解のない時代の答えのつくりかた 2024年1月31日 第1版第1刷発行 著者 吉田将英 発行所 WAVE出版2025-04-2821 min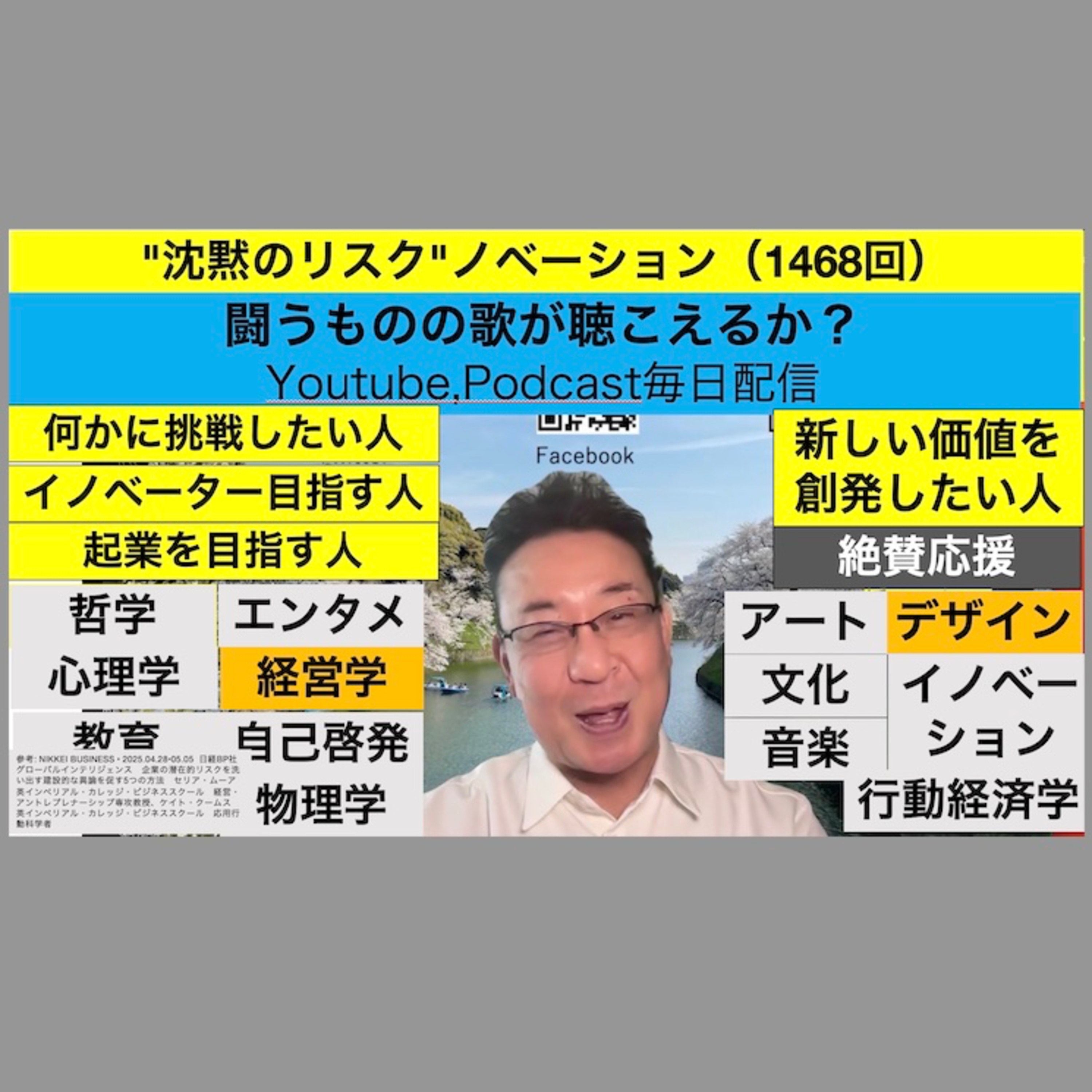 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""沈黙のリスク"ノベーション(1468回)英インペリアル・カレッジ・ビジネススクールのセリア・ムーアさんと、ケイト・クームスさんからのお話に、リーダーのあり方について考えさせられました"リスクに対する組織的な沈黙がもたらす結果は自明の理だ。往々にして悲惨な結末を迎えるにもかかわらず、リーダーの多くはチームメンバーが効果的に異議を申し立てる方法を理解していない。部下が安心して発言できる「心理的安全性」について助言を受けるリーダーは少なくないだろう。だが、その多くは漠然とした内容だ。それではリーダーはチームメンバーから価値ある意見を得る実用的な手法を学べない。""建設的な異議を促す5つの方法①より具体的な質問をする②異議の正当性を認める③双方向かつ友好的な会議にする④決定に十分な時間をかける⑤説明責任の意識を根付かせる"ここから、私はそもそもリーダーがこのような状態に陥る要因とその対策を考えてみました1、自己中心性バイアス2、権力による自己欺瞞3、システム的断絶1、自己中心性バイアスやはりリーダー的な存在になるというのは、ある程度の成功体験とノウハウがある中でなるケースが多いので、どうしてもその分野の専門家になってしまい、自分の意見が1番と、表には絶対に出さないけれども、心の奥底で思ってると言うことがあると思います私自身も、長くその担当にいたり、お客様のことを誰よりも知ってると言う自負が生まれてた時を思い出すと、そんなことを心の中では思ってたなあと、それでかなり強引にことを進めたこともあったなあと、反省しつつ思ったりもします会社ではないサークル的なところでも、ああなんであんな意地張っちゃったんだろうとか、もっと違う象言い方あったなあと思うことも、たくさんあるので、これが必ず自分にあるということを、一つ思っておくことが大切かと思いました2、権力による自己欺瞞これは、ニーチェをはじめとしていろんな方が言われてますが、権力を持つ立場になると、どうしても周りの人たちが気を使い始めて、イエスマンばかりが周りにいると言う状況を、しかも気持ちよくなってしまう、と言うことが起こるかもなあと思います会社における役職なども、人事権を持ってるだけで、みんなが知らない間にイエスマンになってることでさえも気がつかない、やっぱり自分が正しいからだと、思い込んでしまうことが、なかなか恐ろしいはなしかと思います自分自身の立場として、会社だけでなく、サークルや、団体、家族、グループなどでも、どこでもこんなことは起きているので、だからこそ、自分自身にそれを常に問うていることがとても大切かと思いました3、システム的断絶私が独立した理由の一つも実はここにあるのですが、年数を重ねてマネージャーばかりやってると、マネージャーとしてはスペシャルになるにつれて、現場がわからなくなってくることが、とても寂しく、また、怖く思われることがありましたお前はマネージャーなんだから、現場は社員にやらせるのが仕事だと、口酸っぱく言われましたが、そうすると、どんどん現場から離れて、実はあまりわかってない中で判断しなきゃいけないとか、もうわからなくなってしまったみたいなことも、とても悩みました会社の役割分担としては、そうあるべきだと思うのですが、そうすると、実は現場から離れた判断や、行ってきている意味をきちんと把握できてないみたいなことも、リスクとして生じるなあと感じました私は自分がそうなるのが怖かったので、独立して一から全てをこなすようになって、本当に勉強になってると日々感じてますということから、じゃあ、どうすればいいのかも、3つ簡単に考えてみました1、悪魔の代弁者 ディベートではないですが、仕掛けとしてこう言う役割の人、または全くヒエラルキーに関係のない外部者、一言ものを必ず言ってくる人を入れるということもありかと思います2、なんか嫌と言っていい これは、糸井重里さんの、ボールのような言葉、という書籍の言葉なのですが、理路整然と反論しないと反対できない、みたいな雰囲気を壊すことも、一方では必要かと思いました3、現場回帰 水戸黄門みたいに、社長が、一般になることはできませんが、マネージャーは、小さな組織や単位で、自らがプレイングしなきゃいけない状態と交互に繰り返す、ということもアリではないかと思いましたということで、もし、自分が仕切ってる活動で、沈黙があるみたいな状況は、実はアラート注意報で一言で言えば"沈黙のリスク"ノベーションそれを常に察知することが大切かなと思いましたそんな話をしています^ ^参考: NIKKEI BUSINESS • 2025.04.28•05.05 日経BP社 グローバルインテリジェンス 企業の潜在的リスクを洗い出す建設的な異論を促す5つの方法 セリア・ムーア 英インペリアル・カレッジ・ビジネススクール 経営・アントレプレナーシップ専攻教授、ケイト・クームス 英インペリアル・カレッジ・ビジネススクール 応用行動科学者2025-04-2728 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""沈黙のリスク"ノベーション(1468回)英インペリアル・カレッジ・ビジネススクールのセリア・ムーアさんと、ケイト・クームスさんからのお話に、リーダーのあり方について考えさせられました"リスクに対する組織的な沈黙がもたらす結果は自明の理だ。往々にして悲惨な結末を迎えるにもかかわらず、リーダーの多くはチームメンバーが効果的に異議を申し立てる方法を理解していない。部下が安心して発言できる「心理的安全性」について助言を受けるリーダーは少なくないだろう。だが、その多くは漠然とした内容だ。それではリーダーはチームメンバーから価値ある意見を得る実用的な手法を学べない。""建設的な異議を促す5つの方法①より具体的な質問をする②異議の正当性を認める③双方向かつ友好的な会議にする④決定に十分な時間をかける⑤説明責任の意識を根付かせる"ここから、私はそもそもリーダーがこのような状態に陥る要因とその対策を考えてみました1、自己中心性バイアス2、権力による自己欺瞞3、システム的断絶1、自己中心性バイアスやはりリーダー的な存在になるというのは、ある程度の成功体験とノウハウがある中でなるケースが多いので、どうしてもその分野の専門家になってしまい、自分の意見が1番と、表には絶対に出さないけれども、心の奥底で思ってると言うことがあると思います私自身も、長くその担当にいたり、お客様のことを誰よりも知ってると言う自負が生まれてた時を思い出すと、そんなことを心の中では思ってたなあと、それでかなり強引にことを進めたこともあったなあと、反省しつつ思ったりもします会社ではないサークル的なところでも、ああなんであんな意地張っちゃったんだろうとか、もっと違う象言い方あったなあと思うことも、たくさんあるので、これが必ず自分にあるということを、一つ思っておくことが大切かと思いました2、権力による自己欺瞞これは、ニーチェをはじめとしていろんな方が言われてますが、権力を持つ立場になると、どうしても周りの人たちが気を使い始めて、イエスマンばかりが周りにいると言う状況を、しかも気持ちよくなってしまう、と言うことが起こるかもなあと思います会社における役職なども、人事権を持ってるだけで、みんなが知らない間にイエスマンになってることでさえも気がつかない、やっぱり自分が正しいからだと、思い込んでしまうことが、なかなか恐ろしいはなしかと思います自分自身の立場として、会社だけでなく、サークルや、団体、家族、グループなどでも、どこでもこんなことは起きているので、だからこそ、自分自身にそれを常に問うていることがとても大切かと思いました3、システム的断絶私が独立した理由の一つも実はここにあるのですが、年数を重ねてマネージャーばかりやってると、マネージャーとしてはスペシャルになるにつれて、現場がわからなくなってくることが、とても寂しく、また、怖く思われることがありましたお前はマネージャーなんだから、現場は社員にやらせるのが仕事だと、口酸っぱく言われましたが、そうすると、どんどん現場から離れて、実はあまりわかってない中で判断しなきゃいけないとか、もうわからなくなってしまったみたいなことも、とても悩みました会社の役割分担としては、そうあるべきだと思うのですが、そうすると、実は現場から離れた判断や、行ってきている意味をきちんと把握できてないみたいなことも、リスクとして生じるなあと感じました私は自分がそうなるのが怖かったので、独立して一から全てをこなすようになって、本当に勉強になってると日々感じてますということから、じゃあ、どうすればいいのかも、3つ簡単に考えてみました1、悪魔の代弁者 ディベートではないですが、仕掛けとしてこう言う役割の人、または全くヒエラルキーに関係のない外部者、一言ものを必ず言ってくる人を入れるということもありかと思います2、なんか嫌と言っていい これは、糸井重里さんの、ボールのような言葉、という書籍の言葉なのですが、理路整然と反論しないと反対できない、みたいな雰囲気を壊すことも、一方では必要かと思いました3、現場回帰 水戸黄門みたいに、社長が、一般になることはできませんが、マネージャーは、小さな組織や単位で、自らがプレイングしなきゃいけない状態と交互に繰り返す、ということもアリではないかと思いましたということで、もし、自分が仕切ってる活動で、沈黙があるみたいな状況は、実はアラート注意報で一言で言えば"沈黙のリスク"ノベーションそれを常に察知することが大切かなと思いましたそんな話をしています^ ^参考: NIKKEI BUSINESS • 2025.04.28•05.05 日経BP社 グローバルインテリジェンス 企業の潜在的リスクを洗い出す建設的な異論を促す5つの方法 セリア・ムーア 英インペリアル・カレッジ・ビジネススクール 経営・アントレプレナーシップ専攻教授、ケイト・クームス 英インペリアル・カレッジ・ビジネススクール 応用行動科学者2025-04-2728 min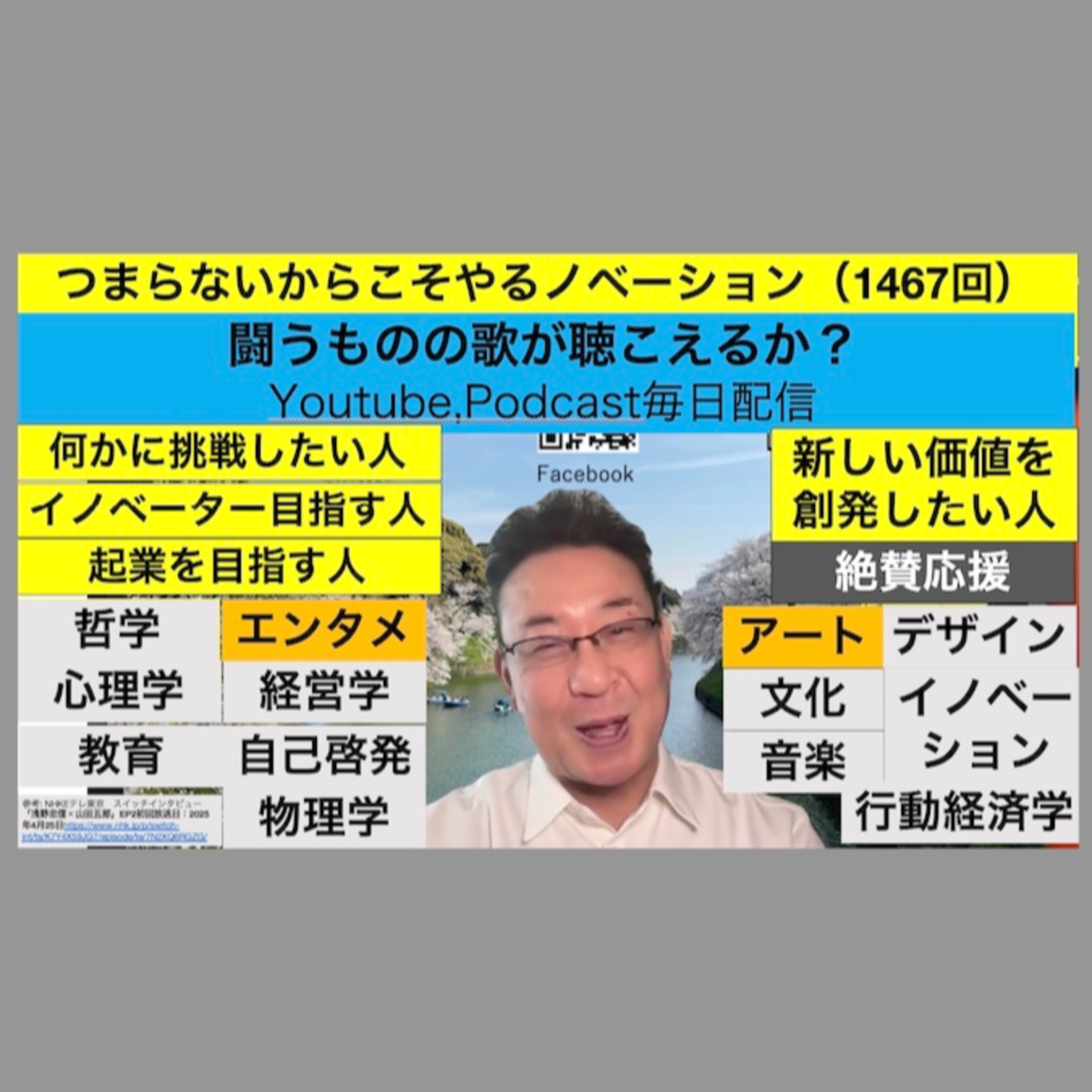 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"つまらないからこそやるノベーション(1467回)SHOGUNで日本人初のゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞された浅野忠信さんの、言葉に痺れました曰く"僕も「修行したいな」っていうのがあったので、言ったら失礼なんですけど、脚本がつまらないとか、そういうものを率先してやるようにしてましたというのは、だから来たんですよねと、面白くして欲しいってことですよね、っていうようなじゃあやってみましょう、僕も修行の身ですから、とことんやってはみ出さないことには進まないんですよね。そのはみ出す練習をさせてもらったというかだから、むちゃな役ほどやってました"ここから私は思いました1、利他パッション→期待値を超える2、成長パッション→コンフォートゾーンを抜け出す3、失敗を恐れないマインドセット→人生の彩り1、利他パッションディズニープラスで何気なく身始めたSHOGUNにめちゃくちゃはまりこんで、これまでみたことのない時代劇のスケールと迫力とストーリーの深淵さに驚愕と感動だったのですがその中でも浅野忠信さんの役どころは、かなりの曲者でありながら人間臭さが滲み出る、物語の鍵となる役割で、まさに浅野さんでしか成り立たない、そんな印象も受けていましたこのインタビューから、その浅野さんの凄さの秘密が垣間見れるような、そんな感動をいただきました"だから来たんですよね"という浅野さんの言葉には、依頼された方の期待を必ず超えてみせる、というロックスピリッツと、頼ってくれてる人への、よっしゃなんとかしましょうという、利他パッションを感じる気がしました私も依頼された件は、できるだけ引き受けるようにしてますが、それは、せっかく頼ってきてくれた人への、できないかもしれないけれどもなんとかしてあげたい気持ちが、共感できる気がしました2、成長パッションそして、"修行の身"さらには、"はみ出さないと進まない"の言葉からは、俳優としてのあくなき成長パッションを感じました。アンダースンさんの"超一流になるためには、才能か努力か"という本の話が好きなのですが、その一つの秘訣として、コンフォートゾーンを抜け出す、ということが出てきます一言でいうと、できないことをやれ、ということなのですが、毎日少しずつでも、少しできないことをやることが、超一流への道とのお話で、まさに今回、浅野さんがゴールデングローブ賞を受賞されたのも、超一流への道のりを歩んでいたんだろうなと思いました3、失敗を恐れないマインドセットそしてもう一つ感じたのは、俳優という、結果がたくさんの人に見られて、さらにはレビュテーションも様々なところから飛んでくる世界において、そのような挑戦をするのは、失敗を恐れないマインドセットがあるのかもしれないなあと思いました哲学者の三木清さんの、"失敗も人生の彩りの一つ"というのがありますが、人生のゴールは成功ではなく幸福である、だから失敗も成功も彩りだという考え方が、私はとても好きですイノベーションの世界で言うと、シリコンバレーなどでよく言われていた、Fast Fail、と言う言葉も好きで、早く失敗することによって、よりゴールへ早く到達できる、と言うこともあります浅野さんの哲学は分かりませんが、結果の見える厳しい世界の中で、これだけのチャレンジをされてるのは、失敗を恐れないマインドセットがあるんだろうなあと思いましたということで、今回の浅野さんのお話から頂いた学びは、浅野さんの言葉を借りながら、まとめると頼ってきた人の期待を越えようとする、利他パッション、あえて厳しい役に挑みコンフォートゾーンを抜け出す、成長パッション、そして、失敗という結果を恐れないマインドセット、そんなことからつまらないからこそやるノベーションそんなことを思いました^ ^参考: NHKEテレ東京 スイッチインタビュー「浅野忠信×山田五郎」EP2初回放送日:2025年4月25日https://www.nhk.jp/p/switch-int/ts/K7Y4X59JG7/episode/te/7N2XQ6RGZG/2025-04-2619 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"つまらないからこそやるノベーション(1467回)SHOGUNで日本人初のゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞された浅野忠信さんの、言葉に痺れました曰く"僕も「修行したいな」っていうのがあったので、言ったら失礼なんですけど、脚本がつまらないとか、そういうものを率先してやるようにしてましたというのは、だから来たんですよねと、面白くして欲しいってことですよね、っていうようなじゃあやってみましょう、僕も修行の身ですから、とことんやってはみ出さないことには進まないんですよね。そのはみ出す練習をさせてもらったというかだから、むちゃな役ほどやってました"ここから私は思いました1、利他パッション→期待値を超える2、成長パッション→コンフォートゾーンを抜け出す3、失敗を恐れないマインドセット→人生の彩り1、利他パッションディズニープラスで何気なく身始めたSHOGUNにめちゃくちゃはまりこんで、これまでみたことのない時代劇のスケールと迫力とストーリーの深淵さに驚愕と感動だったのですがその中でも浅野忠信さんの役どころは、かなりの曲者でありながら人間臭さが滲み出る、物語の鍵となる役割で、まさに浅野さんでしか成り立たない、そんな印象も受けていましたこのインタビューから、その浅野さんの凄さの秘密が垣間見れるような、そんな感動をいただきました"だから来たんですよね"という浅野さんの言葉には、依頼された方の期待を必ず超えてみせる、というロックスピリッツと、頼ってくれてる人への、よっしゃなんとかしましょうという、利他パッションを感じる気がしました私も依頼された件は、できるだけ引き受けるようにしてますが、それは、せっかく頼ってきてくれた人への、できないかもしれないけれどもなんとかしてあげたい気持ちが、共感できる気がしました2、成長パッションそして、"修行の身"さらには、"はみ出さないと進まない"の言葉からは、俳優としてのあくなき成長パッションを感じました。アンダースンさんの"超一流になるためには、才能か努力か"という本の話が好きなのですが、その一つの秘訣として、コンフォートゾーンを抜け出す、ということが出てきます一言でいうと、できないことをやれ、ということなのですが、毎日少しずつでも、少しできないことをやることが、超一流への道とのお話で、まさに今回、浅野さんがゴールデングローブ賞を受賞されたのも、超一流への道のりを歩んでいたんだろうなと思いました3、失敗を恐れないマインドセットそしてもう一つ感じたのは、俳優という、結果がたくさんの人に見られて、さらにはレビュテーションも様々なところから飛んでくる世界において、そのような挑戦をするのは、失敗を恐れないマインドセットがあるのかもしれないなあと思いました哲学者の三木清さんの、"失敗も人生の彩りの一つ"というのがありますが、人生のゴールは成功ではなく幸福である、だから失敗も成功も彩りだという考え方が、私はとても好きですイノベーションの世界で言うと、シリコンバレーなどでよく言われていた、Fast Fail、と言う言葉も好きで、早く失敗することによって、よりゴールへ早く到達できる、と言うこともあります浅野さんの哲学は分かりませんが、結果の見える厳しい世界の中で、これだけのチャレンジをされてるのは、失敗を恐れないマインドセットがあるんだろうなあと思いましたということで、今回の浅野さんのお話から頂いた学びは、浅野さんの言葉を借りながら、まとめると頼ってきた人の期待を越えようとする、利他パッション、あえて厳しい役に挑みコンフォートゾーンを抜け出す、成長パッション、そして、失敗という結果を恐れないマインドセット、そんなことからつまらないからこそやるノベーションそんなことを思いました^ ^参考: NHKEテレ東京 スイッチインタビュー「浅野忠信×山田五郎」EP2初回放送日:2025年4月25日https://www.nhk.jp/p/switch-int/ts/K7Y4X59JG7/episode/te/7N2XQ6RGZG/2025-04-2619 min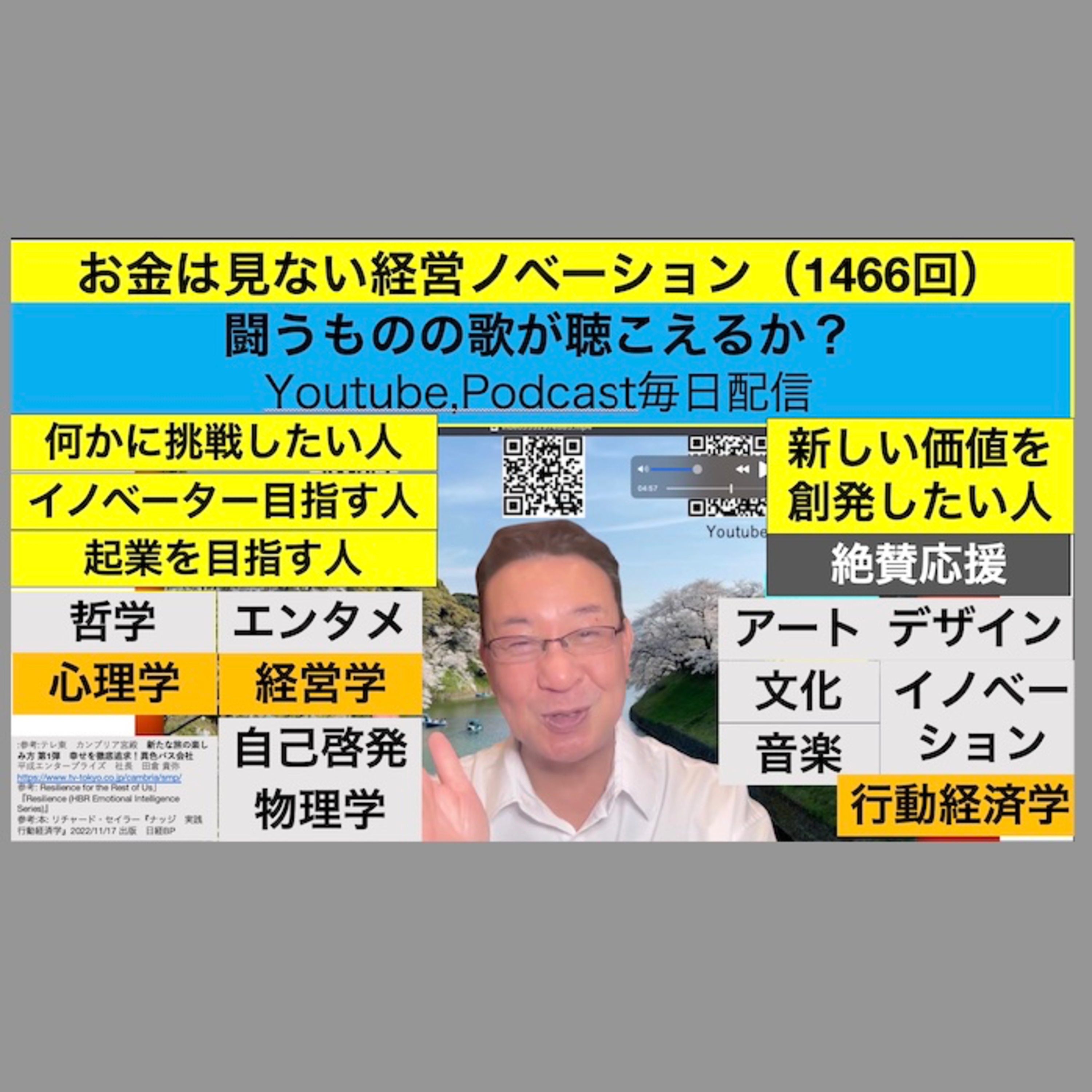 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"お金は見ない経営ノベーション(1466回)めちゃくちゃイノベーティブなバスツアーなどを企画されてる平成エンタープライズの田倉貴弥社長の考え方に目から鱗が落ちました曰く"経営は父をよく見ていて、これをしちゃいけない”というのがあった。父はお金に困って、年中“金策”をしていたので、僕は会社を始めたら、お金を一切触るのをやめようと思って、お金は今でも 一切触らない会社の通帳も見ない。経理の人に任せて、僕はお金を見ないで生きている社長。お金を気にすると営業ができない。お金を見ちゃうので。お金が今ないとなったら、脳が「お金に困った」となってモチベーションが下がる。お金を見ないモチベーションのまま行く"ここから私は思いました1、未来志向2、レジリエンス経営3、行動デザイン1、未来志向広くてリクライニングでリラックスできる深夜バスと、そのVIPラウンジを作ったり、トンネルで頭スレスレのルーフトップバスのスリリングなツアー、さらにはお寿司屋さんと自らが育ててる苺狩りのセットツアーなどなど、イノベーティブな企画満載にまずは、度肝を抜かれ、その発想の原点をことインタビューから、頂いた気がしましたまずは、徹底的な未来志向なのだなあと言うことを思いました。以前、名和高司さんのお話から”未来志向のパーパス”ノベーション(1461回)のお話をしましたが、現状の制約条件を一旦取っ払うことで、本当に未来でありたい姿を、創発することができる、と言うことだと思いました特にお金の問題は、一番現実に引き戻される話なので、そこをあえて考えずに、未来の企画を次々と打っていくと言うのは、真にイノベーティブな経営には必要だなあと思いました2、レジリエンス経営また、これは、ある意味、レジリエンス経営の一つでもあるかとも思いました。米国の心理学者のダニエル・ゴールマンさんがHBRで言われた「レジリエンスとは、困難な状況に直面した際、感情的な動揺を最小限に抑え、状況に柔軟に対応する能力である。」ということから、自らの感情的な動揺を最小限に抑える中で、新たな打ち手を考える為には、ある程度、お金のことは、経理に任せて、自らは新たな企画に専念するというのは、一つのレジリエンスへの対応なのかもしれないもちろん、最後の責任を取るのは、社長なので、ある意味、経費や財務を担当してる社員を、本気で信じている、と言うことの裏返しかもしれないとも思いました。3、行動デザインそう考えると、このやり方こそが、平成エンタープライズにおける、レジリエンス高い経営のやり方ということで、行動デザインがされているとも考えられるなと思いました行動デザインというと、ナッジの研究等でノーベル経済学賞を取られたリチャード・セイラー教授が、ナッジ『実践 行動経済学』で言われているとおり「私たちの行動は、目に入る情報や環境によって大きく左右される。不要な情報を遮断することは、意図的な選択行動を支える強力な手段である。」とのことなので、田倉社長があえてお金のことを目に入らない情報として、新たなイノベーティブに企画を繰り出し、そしてお金の業務は、経理、財務が責任を持って、信頼関係をもって担うそんな行動デザインが、組織として出来上がってるのかもしれないなと思いましたこのデザインは、その会社一人一人の特性によって全然違うものになるべきなので、他から見てもイノベーティブでも、当該企業においては普通のことである、そんなデザインが大切だなあと、つくづく思いましたということで、今回の考え方の象徴的な表現として、一言でいうとお金は見ない経営ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:テレ東 カンブリア宮殿 新たな旅の楽しみ方 第1弾 幸せを徹底追求!異色バス会社 平成エンタープライズ 社長 田倉 貴弥 https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/smp/参考: Resilience for the Rest of Us」『Resilience (HBR Emotional Intelligence Series)』参考:本: リチャード・セイラー『ナッジ 実践 行動経済学』2022/11/17 出版 日経BP動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/IAsISc2YejE2025-04-2514 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"お金は見ない経営ノベーション(1466回)めちゃくちゃイノベーティブなバスツアーなどを企画されてる平成エンタープライズの田倉貴弥社長の考え方に目から鱗が落ちました曰く"経営は父をよく見ていて、これをしちゃいけない”というのがあった。父はお金に困って、年中“金策”をしていたので、僕は会社を始めたら、お金を一切触るのをやめようと思って、お金は今でも 一切触らない会社の通帳も見ない。経理の人に任せて、僕はお金を見ないで生きている社長。お金を気にすると営業ができない。お金を見ちゃうので。お金が今ないとなったら、脳が「お金に困った」となってモチベーションが下がる。お金を見ないモチベーションのまま行く"ここから私は思いました1、未来志向2、レジリエンス経営3、行動デザイン1、未来志向広くてリクライニングでリラックスできる深夜バスと、そのVIPラウンジを作ったり、トンネルで頭スレスレのルーフトップバスのスリリングなツアー、さらにはお寿司屋さんと自らが育ててる苺狩りのセットツアーなどなど、イノベーティブな企画満載にまずは、度肝を抜かれ、その発想の原点をことインタビューから、頂いた気がしましたまずは、徹底的な未来志向なのだなあと言うことを思いました。以前、名和高司さんのお話から”未来志向のパーパス”ノベーション(1461回)のお話をしましたが、現状の制約条件を一旦取っ払うことで、本当に未来でありたい姿を、創発することができる、と言うことだと思いました特にお金の問題は、一番現実に引き戻される話なので、そこをあえて考えずに、未来の企画を次々と打っていくと言うのは、真にイノベーティブな経営には必要だなあと思いました2、レジリエンス経営また、これは、ある意味、レジリエンス経営の一つでもあるかとも思いました。米国の心理学者のダニエル・ゴールマンさんがHBRで言われた「レジリエンスとは、困難な状況に直面した際、感情的な動揺を最小限に抑え、状況に柔軟に対応する能力である。」ということから、自らの感情的な動揺を最小限に抑える中で、新たな打ち手を考える為には、ある程度、お金のことは、経理に任せて、自らは新たな企画に専念するというのは、一つのレジリエンスへの対応なのかもしれないもちろん、最後の責任を取るのは、社長なので、ある意味、経費や財務を担当してる社員を、本気で信じている、と言うことの裏返しかもしれないとも思いました。3、行動デザインそう考えると、このやり方こそが、平成エンタープライズにおける、レジリエンス高い経営のやり方ということで、行動デザインがされているとも考えられるなと思いました行動デザインというと、ナッジの研究等でノーベル経済学賞を取られたリチャード・セイラー教授が、ナッジ『実践 行動経済学』で言われているとおり「私たちの行動は、目に入る情報や環境によって大きく左右される。不要な情報を遮断することは、意図的な選択行動を支える強力な手段である。」とのことなので、田倉社長があえてお金のことを目に入らない情報として、新たなイノベーティブに企画を繰り出し、そしてお金の業務は、経理、財務が責任を持って、信頼関係をもって担うそんな行動デザインが、組織として出来上がってるのかもしれないなと思いましたこのデザインは、その会社一人一人の特性によって全然違うものになるべきなので、他から見てもイノベーティブでも、当該企業においては普通のことである、そんなデザインが大切だなあと、つくづく思いましたということで、今回の考え方の象徴的な表現として、一言でいうとお金は見ない経営ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:テレ東 カンブリア宮殿 新たな旅の楽しみ方 第1弾 幸せを徹底追求!異色バス会社 平成エンタープライズ 社長 田倉 貴弥 https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/smp/参考: Resilience for the Rest of Us」『Resilience (HBR Emotional Intelligence Series)』参考:本: リチャード・セイラー『ナッジ 実践 行動経済学』2022/11/17 出版 日経BP動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/IAsISc2YejE2025-04-2514 min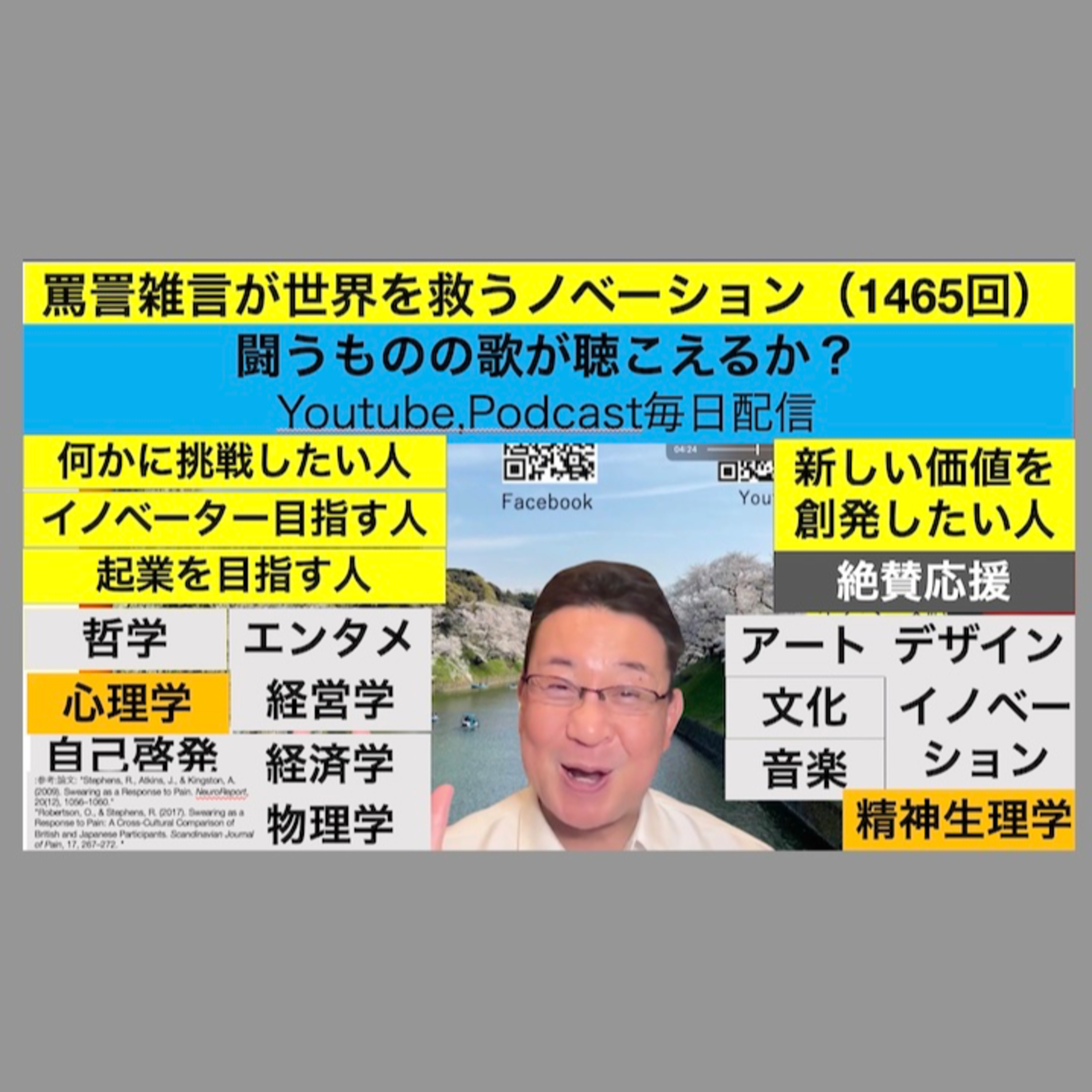 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"罵詈雑言が世界を救うノベーション(1465回)英国キール大学のリチャード・ステファンズ教授が行った、冷水に手を浸す「cold pressor test(冷水圧迫試験)」で、罵詈雑言(スワリング)を吐きながらやる人と、やらない人の結果に、衝撃を受けました"結果1、痛みの耐性: スワリング群は、対照群に比べて平均で約40秒長く手を氷水に浸すことができました。2、痛みの知覚: スワリング群は、痛みの強さを対照群よりも低く評価しました。3、心拍数: スワリング群では心拍数の増加が見られ、これは交感神経系の活性化を示唆しています。""理論的背景1. 情動の喚起2. 交感神経系の活性化3. 注意の分散"ここから私は思いました1、バイアスの破壊2、逆転の発想3、だとしたらアイディエーション1、バイアスの破壊まずは、この実験をしようと思ったことに衝撃を受けました。仮説として、罵詈雑言を吐くと痛みが和らぐのでは?"と言うことにどう着目したのかと。世の中的には、小さい子供とかが、お家で汚い言葉を使ってると怒られたり、まして公共の場では、絶対に使っては行けない言葉なので、ある意味、タブーへの挑戦なのかとも思いました。イノベーションの世界では、タブーやサンクチュアリなことの中に、実は長年の課題で解けないものの理由がある、と言うこともあるので、あえてそこへ挑戦したと言うイノベーションスピリッツに感動しました2、逆転の発想そしてこれは、以前、"常識変換法"で誰もがイノベーターになれるノベーション(1443回)でお話ししたクリエイティブ・ディレクターの西島知宏さんの、"常識変換法"に繋がるなあと思いましたまずは、常識を洗い出してみて、その反対を考えてみる、それだけで実は、逆転の発想に繋がる、とてもイノベーティブなアイディアが生まれる方法、と言うことで、とても感動したのですがとても辛い時に、やっては行けない、言っては行けないことを、しかも、叫ぶと言うことは、公の場でやると、きっと通報されかねない、そんなことを、逆にそれが良いのかもしれないと言う、逆転の発想で、やってみる、そこへ辿りつく勇気なのか、面白がりなのか、わかりませんが、素晴らしいと思いました3、だとしたらアイディエーションそして、この衝撃的な発見は、実験だけの世界で終わらせては、行けないと思うのが、またイノベーターなのかなとも思いました例えば、実はたくさんの痛みを普段から我慢して持ち続けているからこそ、さまざまな組織や団体や国間で、イライラが募り対立を生むのではないか?みたいな仮説から、罵詈雑言のツボ、みたいなのを一家に一台、ゆくゆくは1人一壺持つことによって、精神的な排泄ではないですが、代謝を高めることを仕組みするソリューション見たいなのもあっても良いかもしれないまた、懺悔の部屋、みたいな、罵詈雑言を叫ぶ部屋、みたいなものを、家庭や、会社や、果ては政府機関などに設置ことによって、精神の健康的な代謝を高めていくことでストレス、イライラ、悲しみ、憎しみ、いろんな精神的な痛みを緩和してくれるのではないか、そしてそれが、世の中のあらゆる対立を解消することにつながったのです、めでたしめでたし、みたいな妄想から、実は世の中を変えるソリューションができるかもしれない、そんなことを思いましたこの発見は単なるイグノーベル的なものでは決してなくて、世界の平和を本当に実現するかもしれない一言で言うと罵詈雑言が世界を救うノベーションそんなことを思いました^ ^参考:論文: "Stephens, R., Atkins, J., & Kingston, A. (2009). Swearing as a Response to Pain. NeuroReport, 20(12), 1056–1060.""Robertson, O., & Stephens, R. (2017). Swearing as a Response to Pain: A Cross-Cultural Comparison of British and Japanese Participants. Scandinavian Journal of Pain, 17, 267–272. "動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/-9NV71MzwOI2025-04-2420 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"罵詈雑言が世界を救うノベーション(1465回)英国キール大学のリチャード・ステファンズ教授が行った、冷水に手を浸す「cold pressor test(冷水圧迫試験)」で、罵詈雑言(スワリング)を吐きながらやる人と、やらない人の結果に、衝撃を受けました"結果1、痛みの耐性: スワリング群は、対照群に比べて平均で約40秒長く手を氷水に浸すことができました。2、痛みの知覚: スワリング群は、痛みの強さを対照群よりも低く評価しました。3、心拍数: スワリング群では心拍数の増加が見られ、これは交感神経系の活性化を示唆しています。""理論的背景1. 情動の喚起2. 交感神経系の活性化3. 注意の分散"ここから私は思いました1、バイアスの破壊2、逆転の発想3、だとしたらアイディエーション1、バイアスの破壊まずは、この実験をしようと思ったことに衝撃を受けました。仮説として、罵詈雑言を吐くと痛みが和らぐのでは?"と言うことにどう着目したのかと。世の中的には、小さい子供とかが、お家で汚い言葉を使ってると怒られたり、まして公共の場では、絶対に使っては行けない言葉なので、ある意味、タブーへの挑戦なのかとも思いました。イノベーションの世界では、タブーやサンクチュアリなことの中に、実は長年の課題で解けないものの理由がある、と言うこともあるので、あえてそこへ挑戦したと言うイノベーションスピリッツに感動しました2、逆転の発想そしてこれは、以前、"常識変換法"で誰もがイノベーターになれるノベーション(1443回)でお話ししたクリエイティブ・ディレクターの西島知宏さんの、"常識変換法"に繋がるなあと思いましたまずは、常識を洗い出してみて、その反対を考えてみる、それだけで実は、逆転の発想に繋がる、とてもイノベーティブなアイディアが生まれる方法、と言うことで、とても感動したのですがとても辛い時に、やっては行けない、言っては行けないことを、しかも、叫ぶと言うことは、公の場でやると、きっと通報されかねない、そんなことを、逆にそれが良いのかもしれないと言う、逆転の発想で、やってみる、そこへ辿りつく勇気なのか、面白がりなのか、わかりませんが、素晴らしいと思いました3、だとしたらアイディエーションそして、この衝撃的な発見は、実験だけの世界で終わらせては、行けないと思うのが、またイノベーターなのかなとも思いました例えば、実はたくさんの痛みを普段から我慢して持ち続けているからこそ、さまざまな組織や団体や国間で、イライラが募り対立を生むのではないか?みたいな仮説から、罵詈雑言のツボ、みたいなのを一家に一台、ゆくゆくは1人一壺持つことによって、精神的な排泄ではないですが、代謝を高めることを仕組みするソリューション見たいなのもあっても良いかもしれないまた、懺悔の部屋、みたいな、罵詈雑言を叫ぶ部屋、みたいなものを、家庭や、会社や、果ては政府機関などに設置ことによって、精神の健康的な代謝を高めていくことでストレス、イライラ、悲しみ、憎しみ、いろんな精神的な痛みを緩和してくれるのではないか、そしてそれが、世の中のあらゆる対立を解消することにつながったのです、めでたしめでたし、みたいな妄想から、実は世の中を変えるソリューションができるかもしれない、そんなことを思いましたこの発見は単なるイグノーベル的なものでは決してなくて、世界の平和を本当に実現するかもしれない一言で言うと罵詈雑言が世界を救うノベーションそんなことを思いました^ ^参考:論文: "Stephens, R., Atkins, J., & Kingston, A. (2009). Swearing as a Response to Pain. NeuroReport, 20(12), 1056–1060.""Robertson, O., & Stephens, R. (2017). Swearing as a Response to Pain: A Cross-Cultural Comparison of British and Japanese Participants. Scandinavian Journal of Pain, 17, 267–272. "動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/-9NV71MzwOI2025-04-2420 min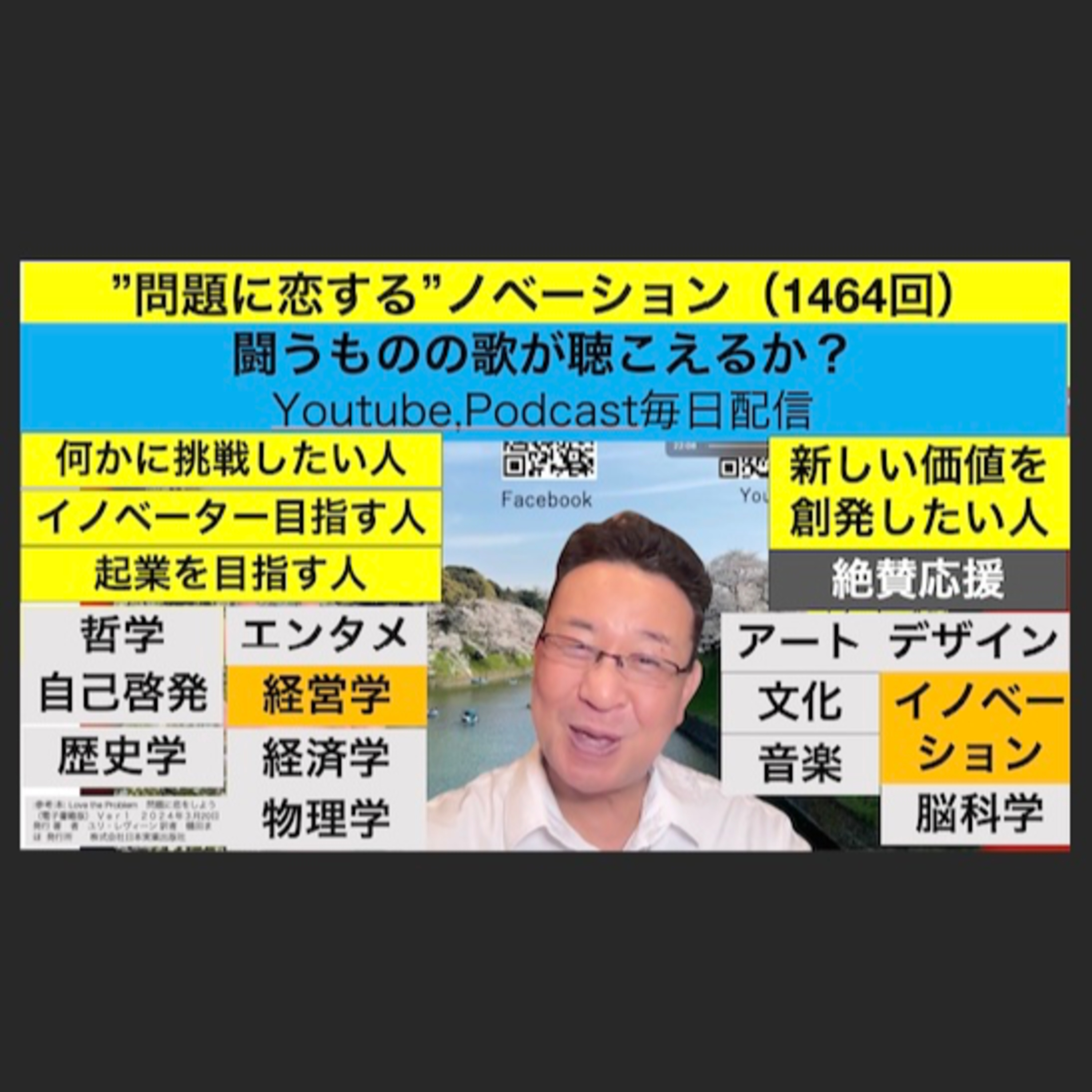 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"”問題に恋する”ノベーション(1464回)連続起業家であるユリ・レヴィーンさんより、共同創業者のスティーブ・ウォズニアックさんが、お話し頂いてる話に、めちゃくちゃ感動しました曰く"起業家なら、プロダクトと会社への強い情熱が必要なことはわかっているだろう。ユリは、これを「問題に恋をする」と表現する。お金や自分自身などに恋をするのではない。そして、問題への恋を誰もが経験したことのある個人的な人間関係と結びつける。問題に恋をすることは、起業家自身のアイデアやプロダクトを大事にすることではなく、エンドユーザーを大事にすることなのだ。ここに成功のカギがある。私自身、いつもそれを信じてきた。"ここから私は思いました1、問題に恋をする2、お客様に恋をする3、情熱の源が回り始める1、問題に恋をするイノベーションには、「情熱」が必要だ、とは、私もいつも言っているお話しなのですが、その「情熱」っていったいなんなの?ということが、なかなかピンとこないこともあるし、そんな暑苦しいことは好きじゃないんだよなーと、クールに返されてしまうこともありますしかし、「情熱」ってのは、恋するってことだよ。と言ってもらえると、凄くピンとくる気がしました。恋した時は、相当昔だろうが、今は推し活専門だろうが、誰にでもその気持ちはわかると思います誰かのことが昼夜問わずに気になって仕方がない、寝てる時でさえ考えてる、寝食を忘れてしまう、熱が出てきてほとんど病気かもしれない、そんなことが、恋ですがそれと同様のなんらかの、その人にとってはものすごく大切な、"問題"のことを、恋しちゃった状態に陥る、これこそが、その人に、イノベーターとしての「情熱」が宿った瞬間だと、物凄く分かりやすく伝わるなあと感動致しました2、お客様に恋をするそして実は、それが自分毎ならば、自分だけが我慢すれば良い"問題"ならば、すぐに忘れてしまうのですがそれが実はいろんな人が困ってる"問題''かもしれない、今ここで自分が声をあげなければ葬り去ってしまわれるようなことなのだとしたらそれを解決してあげることは、自分だけじゃなく、その周りの人たちのためにもなる、「大義」に結びつくものなのではないか?そう思ったときから、その人たちのためにもなんとかしたいという、その人たち=お客様にも、恋をすることになるのだと思いますまた、サラリーマンや、コンサルタントならば、大切なお客様が元々おられて、その人たちのことがとっても好きで、その人たちのためならば、なんでもしてあげたい、その人たちが困ってるなら、なんとか助けてあげたい、そんな気持ちが炸裂した時に、お客様に恋をしてる、それももはや盲目の状態まで行けた時に、イノベーションプロジェクトが起きる種になる、そんなことも思いました3、情熱の源が回り始める実は、私がいつも言っている、情熱のポートフォリオも、1番わかりやすい事例として、恋愛のことを言っていました縦軸にポジティブネガティヴ、横軸にオープンクローズをとると、左上から右回りに、大好き→利他→個性→成長と象限があるのですが、人を好きになる時にはまず、大好きになって、その人のために何かしてあげたくなって、でもライバルとの差をつけたくなって、さらに、もっと自分が成長しなきゃ、と頑張る、そしてますます好きになっていく、このサイクルがぐるぐる回るのが、情熱の源の典型例という話をしていましたつまり、情熱と恋は、ほとんど一緒なものなので、イノベーションにおける、情熱を理解するためには、自分の恋を思い出せばいいそしてイノベーションのパッションの根っこにあるのは、自分や誰かを助けたい、ペインを解消したい、ということにあるので、そのペインそのもの、問題を朝から晩まで考えてる状態つまり、問題に恋をしている、それこそが、パッションに火が灯った瞬間なのかなと、思いました一言で言うと”問題に恋する”ノベーションそんなことを話しています^ ^参考:本: Love the Problem 問題に恋をしよう(電子書籍版) Ver1 2024年3月20日発行 著 者 ユリ・レヴィーン 訳者 樋田まほ 発行所 株式会社日本実業出版社2025-04-2328 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"”問題に恋する”ノベーション(1464回)連続起業家であるユリ・レヴィーンさんより、共同創業者のスティーブ・ウォズニアックさんが、お話し頂いてる話に、めちゃくちゃ感動しました曰く"起業家なら、プロダクトと会社への強い情熱が必要なことはわかっているだろう。ユリは、これを「問題に恋をする」と表現する。お金や自分自身などに恋をするのではない。そして、問題への恋を誰もが経験したことのある個人的な人間関係と結びつける。問題に恋をすることは、起業家自身のアイデアやプロダクトを大事にすることではなく、エンドユーザーを大事にすることなのだ。ここに成功のカギがある。私自身、いつもそれを信じてきた。"ここから私は思いました1、問題に恋をする2、お客様に恋をする3、情熱の源が回り始める1、問題に恋をするイノベーションには、「情熱」が必要だ、とは、私もいつも言っているお話しなのですが、その「情熱」っていったいなんなの?ということが、なかなかピンとこないこともあるし、そんな暑苦しいことは好きじゃないんだよなーと、クールに返されてしまうこともありますしかし、「情熱」ってのは、恋するってことだよ。と言ってもらえると、凄くピンとくる気がしました。恋した時は、相当昔だろうが、今は推し活専門だろうが、誰にでもその気持ちはわかると思います誰かのことが昼夜問わずに気になって仕方がない、寝てる時でさえ考えてる、寝食を忘れてしまう、熱が出てきてほとんど病気かもしれない、そんなことが、恋ですがそれと同様のなんらかの、その人にとってはものすごく大切な、"問題"のことを、恋しちゃった状態に陥る、これこそが、その人に、イノベーターとしての「情熱」が宿った瞬間だと、物凄く分かりやすく伝わるなあと感動致しました2、お客様に恋をするそして実は、それが自分毎ならば、自分だけが我慢すれば良い"問題"ならば、すぐに忘れてしまうのですがそれが実はいろんな人が困ってる"問題''かもしれない、今ここで自分が声をあげなければ葬り去ってしまわれるようなことなのだとしたらそれを解決してあげることは、自分だけじゃなく、その周りの人たちのためにもなる、「大義」に結びつくものなのではないか?そう思ったときから、その人たちのためにもなんとかしたいという、その人たち=お客様にも、恋をすることになるのだと思いますまた、サラリーマンや、コンサルタントならば、大切なお客様が元々おられて、その人たちのことがとっても好きで、その人たちのためならば、なんでもしてあげたい、その人たちが困ってるなら、なんとか助けてあげたい、そんな気持ちが炸裂した時に、お客様に恋をしてる、それももはや盲目の状態まで行けた時に、イノベーションプロジェクトが起きる種になる、そんなことも思いました3、情熱の源が回り始める実は、私がいつも言っている、情熱のポートフォリオも、1番わかりやすい事例として、恋愛のことを言っていました縦軸にポジティブネガティヴ、横軸にオープンクローズをとると、左上から右回りに、大好き→利他→個性→成長と象限があるのですが、人を好きになる時にはまず、大好きになって、その人のために何かしてあげたくなって、でもライバルとの差をつけたくなって、さらに、もっと自分が成長しなきゃ、と頑張る、そしてますます好きになっていく、このサイクルがぐるぐる回るのが、情熱の源の典型例という話をしていましたつまり、情熱と恋は、ほとんど一緒なものなので、イノベーションにおける、情熱を理解するためには、自分の恋を思い出せばいいそしてイノベーションのパッションの根っこにあるのは、自分や誰かを助けたい、ペインを解消したい、ということにあるので、そのペインそのもの、問題を朝から晩まで考えてる状態つまり、問題に恋をしている、それこそが、パッションに火が灯った瞬間なのかなと、思いました一言で言うと”問題に恋する”ノベーションそんなことを話しています^ ^参考:本: Love the Problem 問題に恋をしよう(電子書籍版) Ver1 2024年3月20日発行 著 者 ユリ・レヴィーン 訳者 樋田まほ 発行所 株式会社日本実業出版社2025-04-2328 min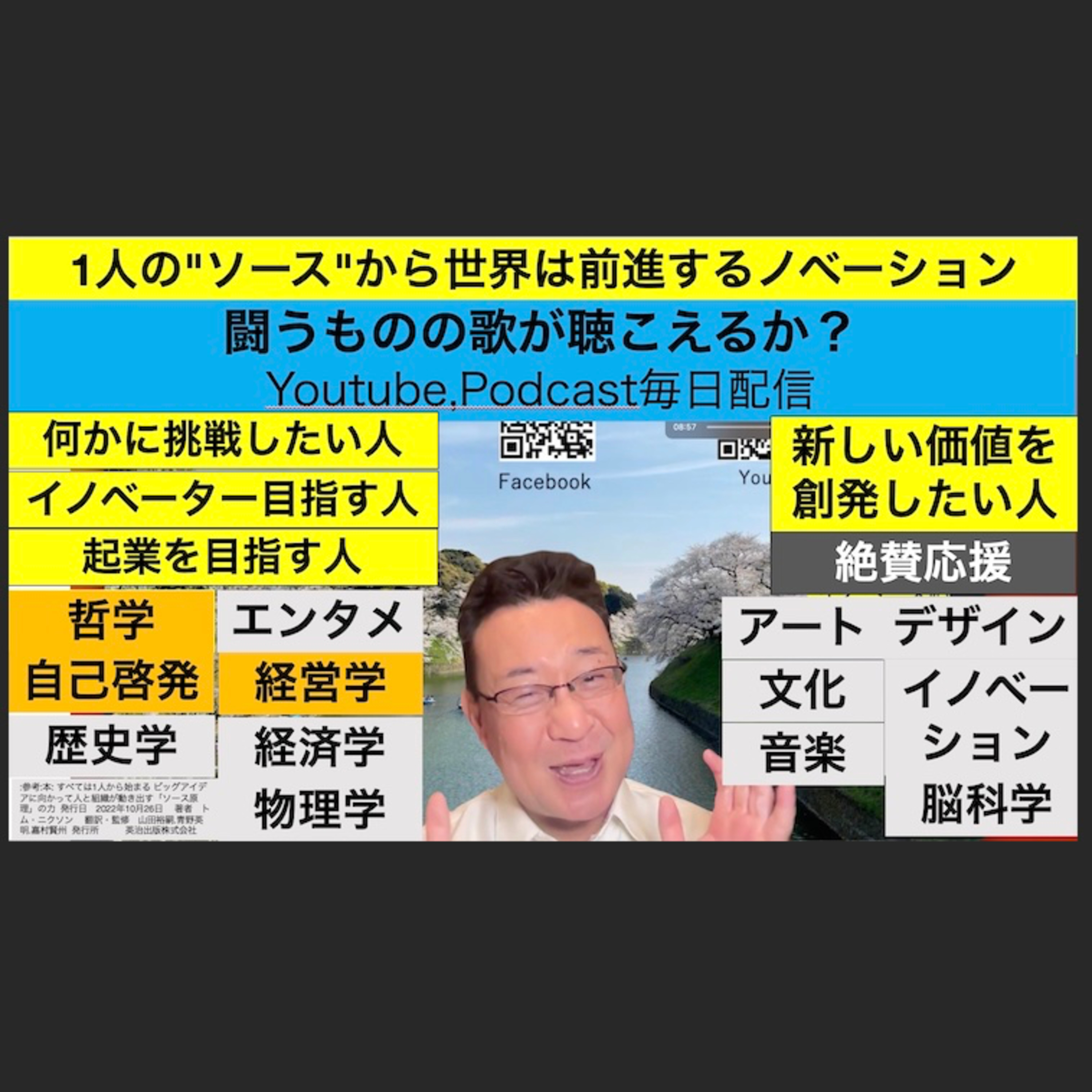 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"1人の"ソース"から世界は前進するノベーション(1463回)トムニクソンさんより、ピーター・カーニックさんの"ソース原理"を教えて頂き、衝撃をうけました曰く"クリエイティブな力がどこから来たとしても、私たちは誰にでも、この特別な力を自分の中から呼び覚ますポテンシャルがある。独創的な思想家のピーター・カーニックは、これを〈ソース〉と呼ぶ。""ソースたる人は、まだ存在しない未来を思い描き、それを現実化させる人間のすばらしい力(本書ではこの力を「創造力」と呼ぶ)を発揮する。'."まさに今この瞬間、充実して生き、存分に創造性を発揮している──そしてそれを楽しんでいる人なのだ。""誰のなかにも存在するソースを呼び起こし育んでいくことで、大胆なアイデアを思い描いて実現させることができる─それは一個人に留まるアイデアではなく、地球上の何十億もの生き物につながる人類として、世界全体が前進するために必要なアイデアだ。""ソースはビジョンのオーサーシップを部分的に他者と分かち合うこともできる。""サブソースは、イニシアチブ全体のソースの言いなりどころか、この役割は天職だと感じながら生き生きと活動するものだ。なぜなら、たんに自分の天職を誰かの大きなイニシアチブのなかに見出しただけだからだ。"ここから私は思いました1、ソースは充実の源 パッション2、1人のソースが世界を前進させる 大義3、ソースは分かち合える 仲間1、ソースは充実の源"ソース"は、特別な人だけにあるのではなく、誰の心の中にでもあり、それに気がつくこと、または、それを発動させることが、すべての新たな価値を創る活動の源である、ということかと、私なりに解釈しましたこれは、わたしのいうところの、イノベーター3つのフレームにおける、パッション、仲間、大義の、最も重要な肝となる部分である、パッションから全ては始まるということに、とても符合していて、激しく共感しましたそしてその"ソース"は、決して名誉や金銭などではなく、自らの人生を充実させるものであるということを、認識することが大切だと思いました自分の心が震えてしまうこと、なぜかワクワクすること、そういうことを、ある意味改めて思い出す、再認識することで、自分の中にある"ソース"を確認するということが大事だと思いましたパッションの源で言えば、縦軸にポジティブ・ネガティヴ、横軸にオープン・クローズを取った上で、大好きなこと、利他なこと、個性出したいこと、成長したいこと、各々に何があるのか、今忘れていたけれども、自分の人生を欠けるべきパッションがなんだったのかを探る、そんなことと、とても同じ気がしました2、1人のソースが世界を前進させる そしてその"ソース"こそが、実は、自らの自己実現につながるだけではなく、世界を前進させている原動力なのだというお話にも、とても共感しましたこれは先ほどの、イノベーター3つのフレームにおける3つ目の、大義、に当たるものかもしれないとも思いました"ソース"自身は自分の中での、もしかしたら自己満足かもしれないけれども、それがどんどん外に開いていくことによって、誰もがワクワクする、誰もが喜んでくれることに昇華していく、それこそが、大義として、たくさんの人たちを仲間に連れてきてくれるそして、本当に世界を変えるための原動力になる、そんなことを思いました3、"ソース"は分かち合えるイノベーションプロジェクトをやるときに、パッションの源から、実現したい大義を、個人個人で考えてみるセッションをやるのですがこれをチームでやっていく場合に、得てしてあるのが、声の大きい人の意見に、決まっちゃう、または、時間内にできそうなことに飛びついちゃう、そんなことをよくみる気がします今回の大きな学びとして、実は"ソース"は分かち合える、ということに、新たな気づきをいただきました。つまり、自分自身が"ソース"とならなくとも、自分自身が他の人の"ソース"に共感して、自分だったら、さらにこんなことができると思う、とか、更にこんなふうになって欲しい、みたいな"サブソース"が、他の人の"ソース"によって引き起こされるそんなことが理想的なチーミングにもつながるし、ある意味、VUCA的な組織へ向かう第一歩にもなりうるかもしれないなあと、そんなことを思いましたこれはイノベーター3つのフレームにおける、実は、仲間をどう集めるのか?さらにどう拘っていくのか?ということに対するとても大きなヒントになると思いました自分の"ソース"を諦めるわけではない、"サブソース"として新たなワクワクを得る、こんなことになれると良いチーミングで、良いソリューションへ向かえるのではないか、そんなことを思いましたこの"ソース"の考えは、イノベーションだけではなく、音楽家やアーティスト、または何かを推進する役目の人には、非常に役に立つお話だなあと改めて思いました一言で言うと1人のソースから世界は前進するノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: すべては1人から始まる ビッグアイデアに向かって人と組織が動き出す「ソース原理」の力 発行日 2022年10月26日 著者 トム・ニクソン 翻訳・監修 山田裕嗣.青野英明.嘉村賢州 発行所 英治出版株式会社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/udgiIb9XQDA2025-04-2216 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"1人の"ソース"から世界は前進するノベーション(1463回)トムニクソンさんより、ピーター・カーニックさんの"ソース原理"を教えて頂き、衝撃をうけました曰く"クリエイティブな力がどこから来たとしても、私たちは誰にでも、この特別な力を自分の中から呼び覚ますポテンシャルがある。独創的な思想家のピーター・カーニックは、これを〈ソース〉と呼ぶ。""ソースたる人は、まだ存在しない未来を思い描き、それを現実化させる人間のすばらしい力(本書ではこの力を「創造力」と呼ぶ)を発揮する。'."まさに今この瞬間、充実して生き、存分に創造性を発揮している──そしてそれを楽しんでいる人なのだ。""誰のなかにも存在するソースを呼び起こし育んでいくことで、大胆なアイデアを思い描いて実現させることができる─それは一個人に留まるアイデアではなく、地球上の何十億もの生き物につながる人類として、世界全体が前進するために必要なアイデアだ。""ソースはビジョンのオーサーシップを部分的に他者と分かち合うこともできる。""サブソースは、イニシアチブ全体のソースの言いなりどころか、この役割は天職だと感じながら生き生きと活動するものだ。なぜなら、たんに自分の天職を誰かの大きなイニシアチブのなかに見出しただけだからだ。"ここから私は思いました1、ソースは充実の源 パッション2、1人のソースが世界を前進させる 大義3、ソースは分かち合える 仲間1、ソースは充実の源"ソース"は、特別な人だけにあるのではなく、誰の心の中にでもあり、それに気がつくこと、または、それを発動させることが、すべての新たな価値を創る活動の源である、ということかと、私なりに解釈しましたこれは、わたしのいうところの、イノベーター3つのフレームにおける、パッション、仲間、大義の、最も重要な肝となる部分である、パッションから全ては始まるということに、とても符合していて、激しく共感しましたそしてその"ソース"は、決して名誉や金銭などではなく、自らの人生を充実させるものであるということを、認識することが大切だと思いました自分の心が震えてしまうこと、なぜかワクワクすること、そういうことを、ある意味改めて思い出す、再認識することで、自分の中にある"ソース"を確認するということが大事だと思いましたパッションの源で言えば、縦軸にポジティブ・ネガティヴ、横軸にオープン・クローズを取った上で、大好きなこと、利他なこと、個性出したいこと、成長したいこと、各々に何があるのか、今忘れていたけれども、自分の人生を欠けるべきパッションがなんだったのかを探る、そんなことと、とても同じ気がしました2、1人のソースが世界を前進させる そしてその"ソース"こそが、実は、自らの自己実現につながるだけではなく、世界を前進させている原動力なのだというお話にも、とても共感しましたこれは先ほどの、イノベーター3つのフレームにおける3つ目の、大義、に当たるものかもしれないとも思いました"ソース"自身は自分の中での、もしかしたら自己満足かもしれないけれども、それがどんどん外に開いていくことによって、誰もがワクワクする、誰もが喜んでくれることに昇華していく、それこそが、大義として、たくさんの人たちを仲間に連れてきてくれるそして、本当に世界を変えるための原動力になる、そんなことを思いました3、"ソース"は分かち合えるイノベーションプロジェクトをやるときに、パッションの源から、実現したい大義を、個人個人で考えてみるセッションをやるのですがこれをチームでやっていく場合に、得てしてあるのが、声の大きい人の意見に、決まっちゃう、または、時間内にできそうなことに飛びついちゃう、そんなことをよくみる気がします今回の大きな学びとして、実は"ソース"は分かち合える、ということに、新たな気づきをいただきました。つまり、自分自身が"ソース"とならなくとも、自分自身が他の人の"ソース"に共感して、自分だったら、さらにこんなことができると思う、とか、更にこんなふうになって欲しい、みたいな"サブソース"が、他の人の"ソース"によって引き起こされるそんなことが理想的なチーミングにもつながるし、ある意味、VUCA的な組織へ向かう第一歩にもなりうるかもしれないなあと、そんなことを思いましたこれはイノベーター3つのフレームにおける、実は、仲間をどう集めるのか?さらにどう拘っていくのか?ということに対するとても大きなヒントになると思いました自分の"ソース"を諦めるわけではない、"サブソース"として新たなワクワクを得る、こんなことになれると良いチーミングで、良いソリューションへ向かえるのではないか、そんなことを思いましたこの"ソース"の考えは、イノベーションだけではなく、音楽家やアーティスト、または何かを推進する役目の人には、非常に役に立つお話だなあと改めて思いました一言で言うと1人のソースから世界は前進するノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: すべては1人から始まる ビッグアイデアに向かって人と組織が動き出す「ソース原理」の力 発行日 2022年10月26日 著者 トム・ニクソン 翻訳・監修 山田裕嗣.青野英明.嘉村賢州 発行所 英治出版株式会社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/udgiIb9XQDA2025-04-2216 min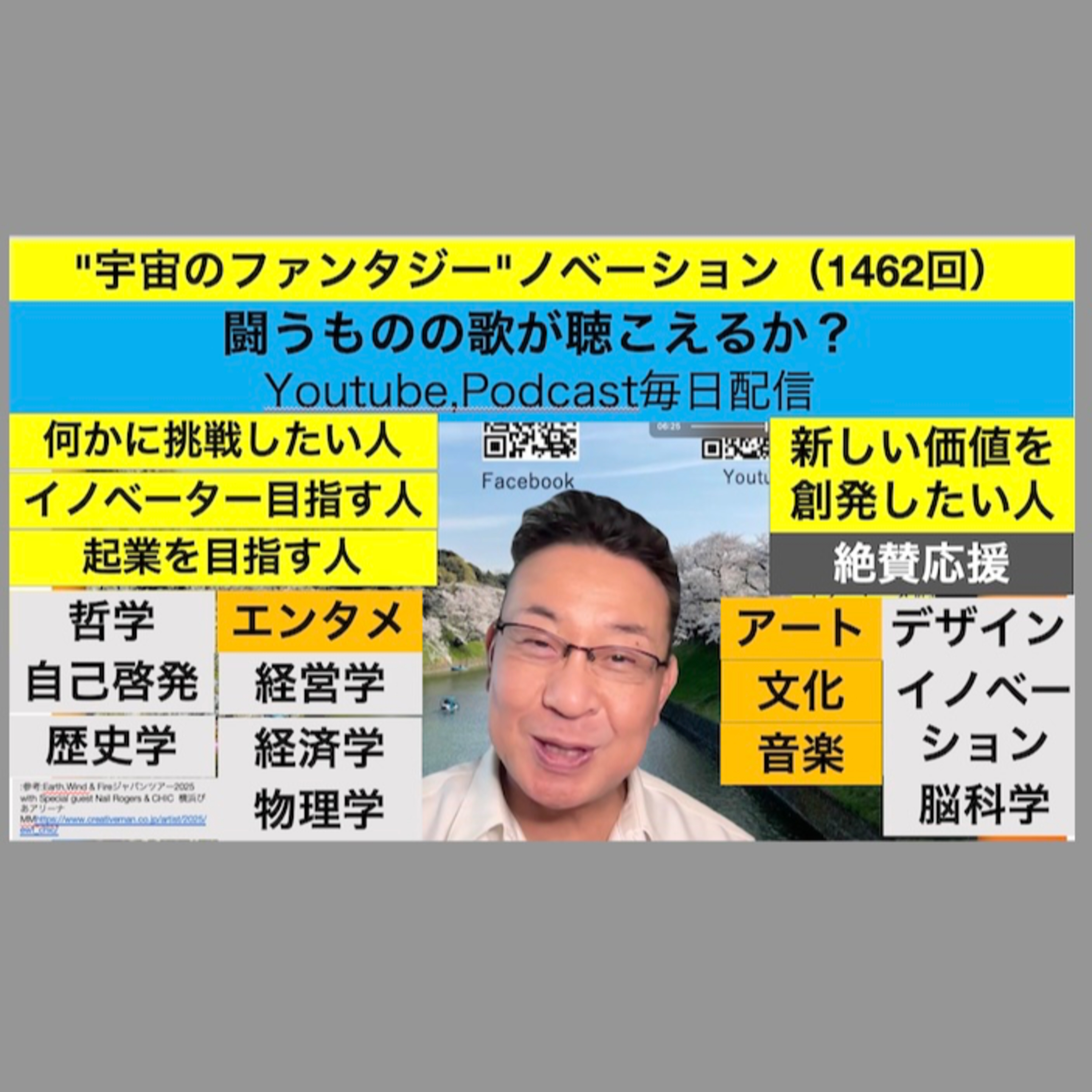 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""宇宙のファンタジー"ノベーション(1462回)8年ぶり来日のアース・ウィンド&ファイヤーのライブは、ナイル・ロジャース&シックとの共演という夢の掛け合わせと共に、限りない幸せを沢山届けてくれましたそして宇宙のファンタジーが流れた際には私の涙も流れましたが、改めて歌詞の内容に、イノベーター3つのフレームそのものだと感動しました私は思いました1、"パッション"の源は誰にもある2、"仲間"と共に一つとして生きる3、「ファンタジー」という"大義"の地へ向かう1、"パッション"の源は誰にもあるオリジナルメンバーのフィリップ・ベイリーは73歳にしてこのファラセットを出せるのか!ということにも大号泣で、どんだけトレーニングしてるだということにも大感動だったわけですがそのファラセットが輝きまくる"宇宙のファンタジー"の歌詞に、イノベーター3つのフレームそのものが埋め込まれるということに、気がついて、私の中にアースが生きていたのかもしれない、とまた号泣でしたその歌詞の部分を引用させて頂くと、冒頭のEvery man has a placeIn his heart there’s a spaceAnd the world can’t erase his fantasies 誰もが心の中に、自分だけの場所を持っている。その空間にある幻想は、世界がどうあっても消すことはできない。 これは私の解釈では、誰もが心の中に人それぞれの"パッションの源"があって、そしてそれを冒すことは誰にもできない、ということを歌ってるのかと思いますジャケットにも沢山採用されているエジプトのピラミッドや、アンク(生命の象徴)、ホルスの目など、モーリス・ホワイトが古代エジプト文明やアフリカのルーツを大切にされていることからも、自らのパッションや魂の源を、とても意識してたんだなあと改めて感じました2、"仲間"と共に一つとして生きるそして、この曲の中で、誰もが、人差し指を真上に突き上げて"🎵ONE〜〜〜"と叫ぶシーンで、また号泣しながら私も突き上げていたわけですが、ここの歌詞が本当に泣けますAnd we will live togetherUntil the twelfth of neverOur voices will ring forever as one そして僕らは共に生きる。永遠に続くその日まで。僕たちの声は、ひとつになって永遠に響き渡る。この歌詞は、誰もが心の中に様々な想いを持ってるけれども、声をひとつに歌えるように、共に生きる事ができる、といってるように私には聞こえましたそれは、イノベーター3つのフレームにおける、仲間が、世界と自分を繋ぐ上での、とても大切な要素であることと、とても同じ気がしました3、「ファンタジー」という"大義"の地へ向かうそして、この曲の題名でもある、大サビでは、フィリップ・ベイリーのファラセットによるインプロビゼイションが、超高音で炸裂しながら、は以下のように歌ってますCome see victoryIn the land called “Fantasy”Loving life, a new decreeBring your mind to everlasting liberty 「ファンタジー」と呼ばれる地で、勝利を見よう。人生を愛し、新たな掟のもとで。君の心を、永遠の自由へと導こう。 これは、自らのパッションを見つめながら、そして、仲間と共に、皆が幸せに暮らせる"ファンタジー"という地へ向かおう、その地を仲間と自らで創り上げていこう、そんなふうなメッセージに私は感じましたこれは、イノベーター3つのフレームにおける、"大義"となる地をみんなで実現していこう、ということに繋がってるなあと、まさにイノベーター3つのフレームそのものを歌ってくれているような気がしましたモーリス・ホワイトはこの曲について、「現実からの逃避手段」と言われているようで、ある意味、ゴスペルのように、厳しい現実の中でも心の中で自由を感じることができるという希望を示しているのかなあと、いう気もしましたR&B、ファンク、ジャズ、ロック、ポップなど多様なジャンルの掛け合わせで音楽的なイノベーションと、イノベーター3つのフレームであるパッション、仲間、大義というスピリッツが、EW&Fには、あるからこそ、こんなに感動できるのかもしれない、それが'宇宙のファンタジー"には、如実に表されているなあと、改めて思いましたイノベーターは、常日頃、プレッシャーと失敗の連続にありますけれども、この曲にあるように、誰にも消せない自分のパッション、そしてAs Oneとしてのそれを分かり合えている仲間、さらには、もしかしたらそれはファンタジーなのかもしれない、でも自分たちはそれを目指して決して諦めずに進む、そんな応援歌にも聞こえる、そんな風に思いました一言で言えば"宇宙のファンタジー"ノベーションそんな話をしています^ ^参考:Earth,Wind & Fireジャパンツアー2025 with Special guest Nail Rogers & CHIC 横浜ぴあアリーナMMhttps://www.creativeman2025-04-2119 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""宇宙のファンタジー"ノベーション(1462回)8年ぶり来日のアース・ウィンド&ファイヤーのライブは、ナイル・ロジャース&シックとの共演という夢の掛け合わせと共に、限りない幸せを沢山届けてくれましたそして宇宙のファンタジーが流れた際には私の涙も流れましたが、改めて歌詞の内容に、イノベーター3つのフレームそのものだと感動しました私は思いました1、"パッション"の源は誰にもある2、"仲間"と共に一つとして生きる3、「ファンタジー」という"大義"の地へ向かう1、"パッション"の源は誰にもあるオリジナルメンバーのフィリップ・ベイリーは73歳にしてこのファラセットを出せるのか!ということにも大号泣で、どんだけトレーニングしてるだということにも大感動だったわけですがそのファラセットが輝きまくる"宇宙のファンタジー"の歌詞に、イノベーター3つのフレームそのものが埋め込まれるということに、気がついて、私の中にアースが生きていたのかもしれない、とまた号泣でしたその歌詞の部分を引用させて頂くと、冒頭のEvery man has a placeIn his heart there’s a spaceAnd the world can’t erase his fantasies 誰もが心の中に、自分だけの場所を持っている。その空間にある幻想は、世界がどうあっても消すことはできない。 これは私の解釈では、誰もが心の中に人それぞれの"パッションの源"があって、そしてそれを冒すことは誰にもできない、ということを歌ってるのかと思いますジャケットにも沢山採用されているエジプトのピラミッドや、アンク(生命の象徴)、ホルスの目など、モーリス・ホワイトが古代エジプト文明やアフリカのルーツを大切にされていることからも、自らのパッションや魂の源を、とても意識してたんだなあと改めて感じました2、"仲間"と共に一つとして生きるそして、この曲の中で、誰もが、人差し指を真上に突き上げて"🎵ONE〜〜〜"と叫ぶシーンで、また号泣しながら私も突き上げていたわけですが、ここの歌詞が本当に泣けますAnd we will live togetherUntil the twelfth of neverOur voices will ring forever as one そして僕らは共に生きる。永遠に続くその日まで。僕たちの声は、ひとつになって永遠に響き渡る。この歌詞は、誰もが心の中に様々な想いを持ってるけれども、声をひとつに歌えるように、共に生きる事ができる、といってるように私には聞こえましたそれは、イノベーター3つのフレームにおける、仲間が、世界と自分を繋ぐ上での、とても大切な要素であることと、とても同じ気がしました3、「ファンタジー」という"大義"の地へ向かうそして、この曲の題名でもある、大サビでは、フィリップ・ベイリーのファラセットによるインプロビゼイションが、超高音で炸裂しながら、は以下のように歌ってますCome see victoryIn the land called “Fantasy”Loving life, a new decreeBring your mind to everlasting liberty 「ファンタジー」と呼ばれる地で、勝利を見よう。人生を愛し、新たな掟のもとで。君の心を、永遠の自由へと導こう。 これは、自らのパッションを見つめながら、そして、仲間と共に、皆が幸せに暮らせる"ファンタジー"という地へ向かおう、その地を仲間と自らで創り上げていこう、そんなふうなメッセージに私は感じましたこれは、イノベーター3つのフレームにおける、"大義"となる地をみんなで実現していこう、ということに繋がってるなあと、まさにイノベーター3つのフレームそのものを歌ってくれているような気がしましたモーリス・ホワイトはこの曲について、「現実からの逃避手段」と言われているようで、ある意味、ゴスペルのように、厳しい現実の中でも心の中で自由を感じることができるという希望を示しているのかなあと、いう気もしましたR&B、ファンク、ジャズ、ロック、ポップなど多様なジャンルの掛け合わせで音楽的なイノベーションと、イノベーター3つのフレームであるパッション、仲間、大義というスピリッツが、EW&Fには、あるからこそ、こんなに感動できるのかもしれない、それが'宇宙のファンタジー"には、如実に表されているなあと、改めて思いましたイノベーターは、常日頃、プレッシャーと失敗の連続にありますけれども、この曲にあるように、誰にも消せない自分のパッション、そしてAs Oneとしてのそれを分かり合えている仲間、さらには、もしかしたらそれはファンタジーなのかもしれない、でも自分たちはそれを目指して決して諦めずに進む、そんな応援歌にも聞こえる、そんな風に思いました一言で言えば"宇宙のファンタジー"ノベーションそんな話をしています^ ^参考:Earth,Wind & Fireジャパンツアー2025 with Special guest Nail Rogers & CHIC 横浜ぴあアリーナMMhttps://www.creativeman2025-04-2119 min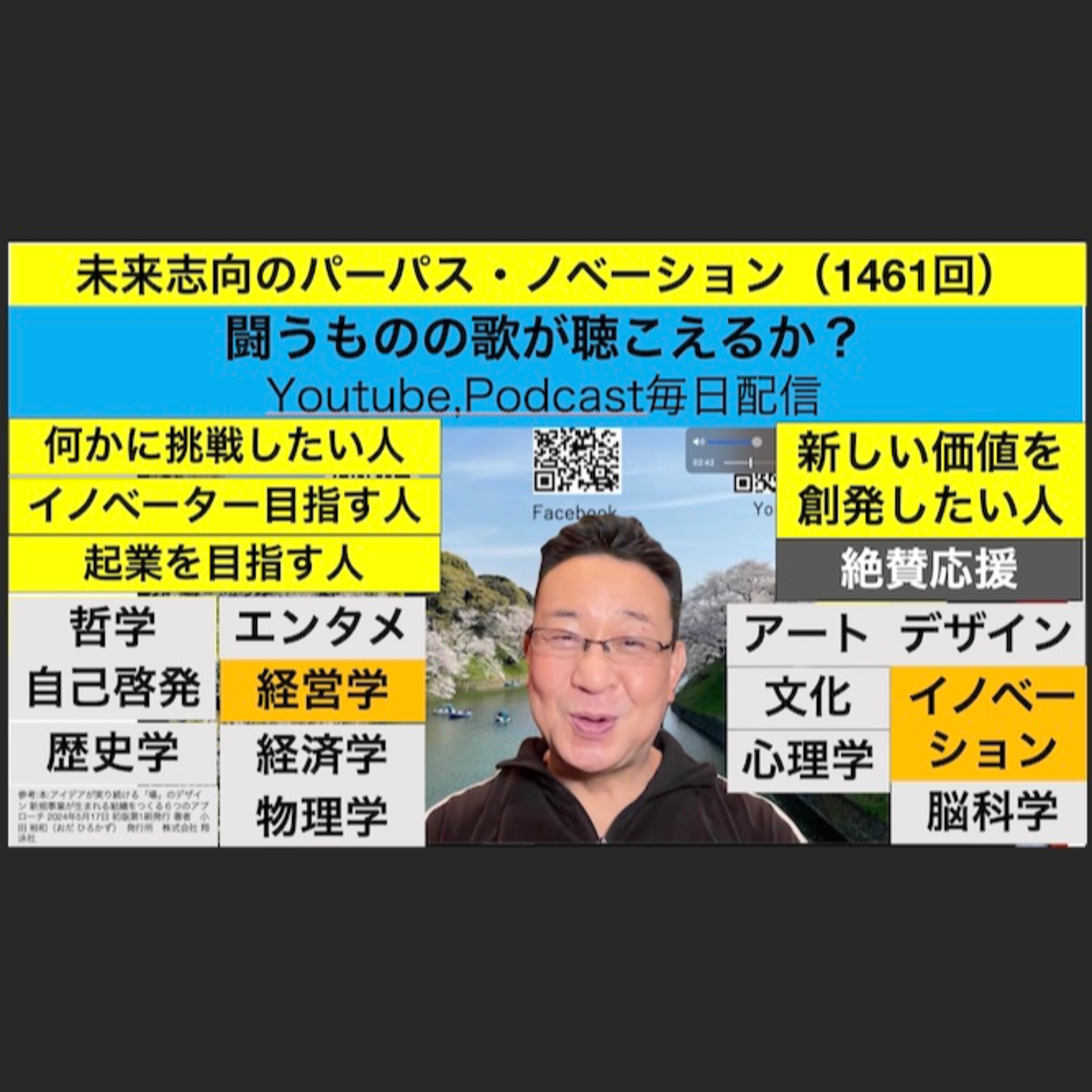 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"”未来志向のパーパス”ノベーション(1461回)株式会社MIMIGURIデザインストラテジスト/リサーチャーの小田 裕和さんと、京都先端科学大学の名和高司さんの対談から、とても深い洞察を勉強させて頂きました。名和さん曰く"パーパスと言えば、「創業の精神」のような、原点思考のイメージがありますが、ここで言っているのは未来志向のパーパスです。よくシリコンバレーでMTPと言っている、Massive Transformative Purpose です。一体我々は、どういう社会、どういう未来をつくりたいのかという「想い」ですね。""自分で何をしたいのか、どういう世の中をつくりたいのかを〝思い詰める〟ことがパーパスなんです。そこに向かっていくときに、もちろん今の持ち物は最大限使いますが、それだけでは足りず、獲得していかなくてはいけない。""そういう意味では、パーパスに紐づいたことをやろうとすると、「足りないものは何なんだ?」と、自分で学習するなり、他者から学習するなりしていかないといけない。""自分の想いが本当に強くて、そこに自分らしさをしっかり描けて、自分らしい能力が裏側についていないと、自分らしい世界にはならない。 当たり前の未来予想図は、ほとんど何も生まないと思っていて、そういう意味で自分の想いはすごく大事なんです。"ここから私は思いました1、全ては想い(パッション)から始まる2、自分らしい世界はなんだ(大義)3、足りないものをどうするか(学習・獲得)1、全ては想い(パッション)から始まる新規事業をやる際に、既存の強みから始めるのか?という内なる力を見るのか、はたまた社会課題という外なる大きな課題からから始めるのか?なかなか迷うことがあるかと思いますが、それに一つの答えを頂いた気がしましたそれは、"想い"(私の解釈における「パッション」)から始めるということかなと、感じました。ここでいう"(想い)は、こうありたい、こういう世界を作りたい、という未来への'想い"なのかと思います。その単位は、会社組織であれば、まさにトップや幹部の"想い"となり、その中の社員であれば、一人一人の"想い"ということになります。理想的には、それが接合した、沢山の"想い"が出現してる、そんな状態が、新しい事業を展開しようとする、パッション溢れた会社ということなのかなあと、思いました2、自分らしい世界はなんだ(大義)そして、その先に、会社でも、個人でも、だとすればこんな世界であって欲しい、だったり、こんな世界を実現したい、という、自らのことだけでなく、世界や社会といった、沢山の人たちが喜ぶであろう、大義、というものを思う描く、ということなのかなあと思いましたよくワークショップなどで、どんな世界、大義のある社会をつくりたいか、やってまでみよう、とすると、みんなが幸せな世界的な、漠然とした大義がよく生まれるのを、体験してますそこから抜け出すのは、最終的には、会社の幹部や、個人における、その人個別の"想い"パッションが、本当に深ぽれているか、ということに尽きるかと思います自らのパッションが生まれるためには、どこかに強烈な自分も含めた人の痛みがある、それを見出すことがとても大切な気がしました3、足りないものをどうするか(学習・獲得)その世界が描けたら、その世界を実現するためには、何が必要なのか?そこで初めて、自分たちの強みでできるのか?ということが生まれてきてさらに、できないのであれば、何が足りないのか?その足りないものをどう調達するのか?学習するのか?オープンイノベーションで獲得するのか?一気にMAをかけるのか?など、さまざまなソリューションへの道筋がみえてくるそんな順番なのかと思いました未来志向のパーパスから始めるために、全ては"想い"パッションから始まり、そして、どんな世界を作りたいのか?という大義を生み出し、その先に足りないものをどうするか?を戦略的に考えていく一言で言うと未来志向のパーパスノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本:アイデアが実り続ける「場」のデザイン 新規事業が生まれる組織をつくる6つのアプローチ 2024年5月17日 初版第1刷発行 著者 小田 裕和(おだ ひろかず) 発行所 株式会社 翔泳社2025-04-2022 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"”未来志向のパーパス”ノベーション(1461回)株式会社MIMIGURIデザインストラテジスト/リサーチャーの小田 裕和さんと、京都先端科学大学の名和高司さんの対談から、とても深い洞察を勉強させて頂きました。名和さん曰く"パーパスと言えば、「創業の精神」のような、原点思考のイメージがありますが、ここで言っているのは未来志向のパーパスです。よくシリコンバレーでMTPと言っている、Massive Transformative Purpose です。一体我々は、どういう社会、どういう未来をつくりたいのかという「想い」ですね。""自分で何をしたいのか、どういう世の中をつくりたいのかを〝思い詰める〟ことがパーパスなんです。そこに向かっていくときに、もちろん今の持ち物は最大限使いますが、それだけでは足りず、獲得していかなくてはいけない。""そういう意味では、パーパスに紐づいたことをやろうとすると、「足りないものは何なんだ?」と、自分で学習するなり、他者から学習するなりしていかないといけない。""自分の想いが本当に強くて、そこに自分らしさをしっかり描けて、自分らしい能力が裏側についていないと、自分らしい世界にはならない。 当たり前の未来予想図は、ほとんど何も生まないと思っていて、そういう意味で自分の想いはすごく大事なんです。"ここから私は思いました1、全ては想い(パッション)から始まる2、自分らしい世界はなんだ(大義)3、足りないものをどうするか(学習・獲得)1、全ては想い(パッション)から始まる新規事業をやる際に、既存の強みから始めるのか?という内なる力を見るのか、はたまた社会課題という外なる大きな課題からから始めるのか?なかなか迷うことがあるかと思いますが、それに一つの答えを頂いた気がしましたそれは、"想い"(私の解釈における「パッション」)から始めるということかなと、感じました。ここでいう"(想い)は、こうありたい、こういう世界を作りたい、という未来への'想い"なのかと思います。その単位は、会社組織であれば、まさにトップや幹部の"想い"となり、その中の社員であれば、一人一人の"想い"ということになります。理想的には、それが接合した、沢山の"想い"が出現してる、そんな状態が、新しい事業を展開しようとする、パッション溢れた会社ということなのかなあと、思いました2、自分らしい世界はなんだ(大義)そして、その先に、会社でも、個人でも、だとすればこんな世界であって欲しい、だったり、こんな世界を実現したい、という、自らのことだけでなく、世界や社会といった、沢山の人たちが喜ぶであろう、大義、というものを思う描く、ということなのかなあと思いましたよくワークショップなどで、どんな世界、大義のある社会をつくりたいか、やってまでみよう、とすると、みんなが幸せな世界的な、漠然とした大義がよく生まれるのを、体験してますそこから抜け出すのは、最終的には、会社の幹部や、個人における、その人個別の"想い"パッションが、本当に深ぽれているか、ということに尽きるかと思います自らのパッションが生まれるためには、どこかに強烈な自分も含めた人の痛みがある、それを見出すことがとても大切な気がしました3、足りないものをどうするか(学習・獲得)その世界が描けたら、その世界を実現するためには、何が必要なのか?そこで初めて、自分たちの強みでできるのか?ということが生まれてきてさらに、できないのであれば、何が足りないのか?その足りないものをどう調達するのか?学習するのか?オープンイノベーションで獲得するのか?一気にMAをかけるのか?など、さまざまなソリューションへの道筋がみえてくるそんな順番なのかと思いました未来志向のパーパスから始めるために、全ては"想い"パッションから始まり、そして、どんな世界を作りたいのか?という大義を生み出し、その先に足りないものをどうするか?を戦略的に考えていく一言で言うと未来志向のパーパスノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本:アイデアが実り続ける「場」のデザイン 新規事業が生まれる組織をつくる6つのアプローチ 2024年5月17日 初版第1刷発行 著者 小田 裕和(おだ ひろかず) 発行所 株式会社 翔泳社2025-04-2022 min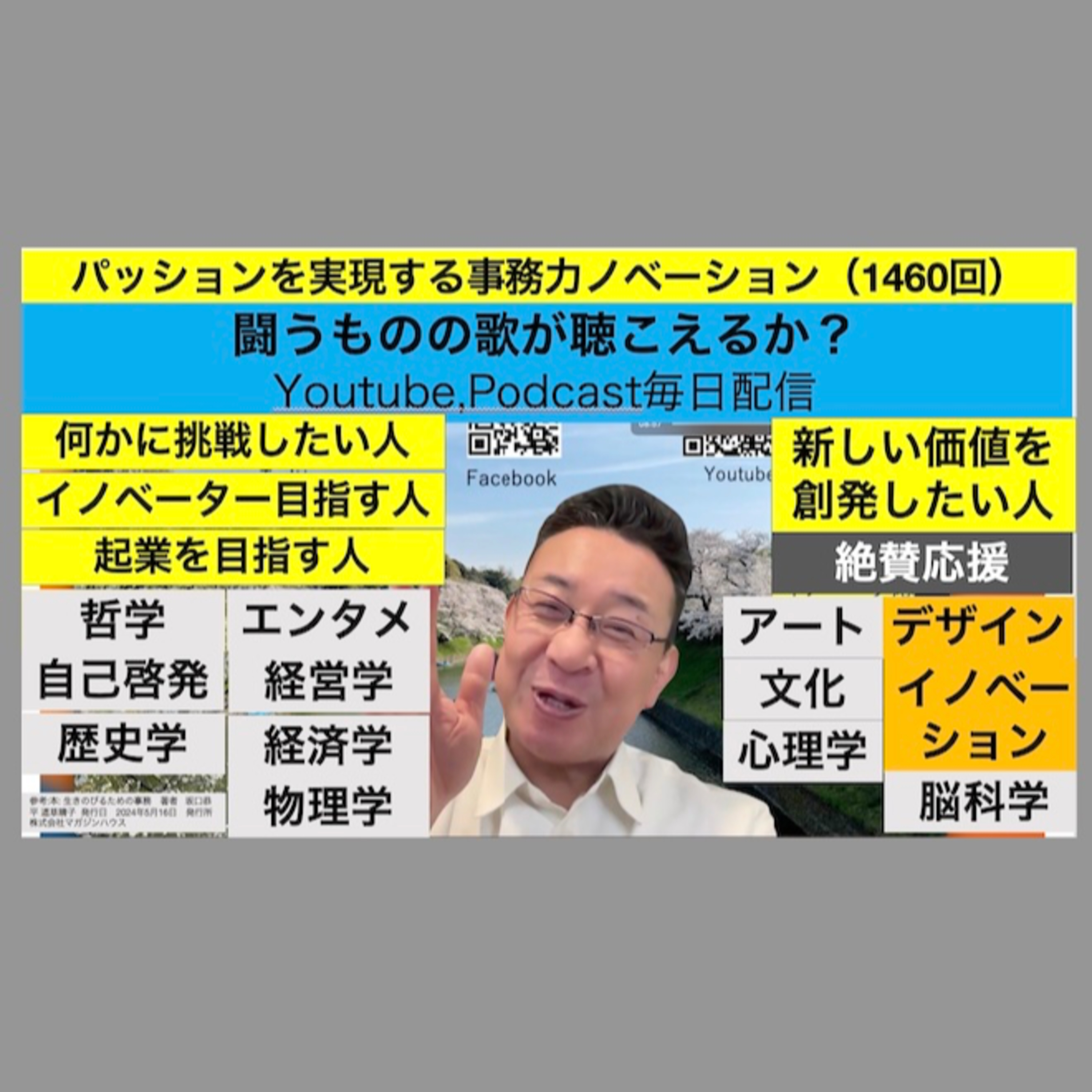 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"パッションを実現する事務力ノベーション(1460回)坂口恭平さん、道草晴子さんが、著されている、"事務"という力を改めて再認識させて頂きました曰く"あなたは自分が作ったものが素晴らしいのか、自分に作家としての《才能》があるかどうか、分からないんです。だからこそ人の意見に引っ張られてしまいます。人は分からないってことに恐怖を覚え、その恐怖を、取り除きたくなります。でも仕事の本当の《評価》なんて時間が経たないと分かりません。人からなんと言われようと、継続していくことが重要です。《事務》は分からないものを明らかにするのではなく、分からないまま仕事を延々と継続するためにあるのです。"ここから私は思いました1、パッションという抽象力2、パッションを仕組み化する事務力3、ネガティブケイパビリティを超える事務力1、パッションという抽象力私はことあるごとにパッション、パッション言ってるので、パッションを持てば全てが上手くいくのか?とも言われることもあるのですが、そういうということでもないということも、よく分かった上で、それでも最初に自らのパッションを知ることは大切だと思ってますそれは課題的なことでなくともよくって、漠然と誰かの役に立ちたい(利他パッション)、AIを使いこなせるようになりたい(成長パッション)など、そのほかに、大好きパッション、個性派パッションなどもあるのですが、今の自分のそれがなんなのかを知っておくことから始めようと、おはなししてます2、パッションを仕組み化する事務力それでも上手くいかないことばかりなので、パッション炸裂しててもダメじゃないかということもあるのですが、そこに必要なのが、仕組み化することで、それを上手くこなしていくのが、事務力かもしれないなあと、感じさせて頂きましたパッションは抽象的なものなので、それを実現するためには、具現化していく力が必要なのだと思います。それは、ひとりでやることもあっていいし、場合によっては、それが得意な仲間と共にやるのも一つの方法かと思います。一時期、風呂敷広げ人(CEO)と風呂敷畳み人(COO)がベンチャーには必要との話がありましたが、まさに畳人こそが、仕組み化し、事務力を高める鍵としての機能だということを改めて教えて頂きました3、ネガティブケイパビリティを超える事務力パッションを実現する活動は、失敗の連続でもあるので、まるで見えない光を暗闇の中で探し続けるような作業と言われることもありますその時に必要なのが、ジョンキーツさんのいう"ネガティブケイパビリティ"として、答えがわからなくても進み続ける力になりますが、これもわかっちゃいるけどなかなか難しいそこで重要となるのが、ここで言われる事務力なのかなと、思いました。つまり、仕組み化をしていることによって、毎日続けることができるというのが、ここで言われている事務力の最大の力なのかと思いました私のこのYoutube、podcastに関しても、実は毎日話す仕組み化、つまり事務に落とし込んでいるので、続けられていると思います。つまり、イノベーションに必要なネガティブケイパビリティを超えるためには、事務力が必須となるということかと思いましたまとめるとまずはある程度抽象的なパッションを認識して、それを具現化するための仕組み化、すなわち事務に落とし込みをする、そうすることによって、一筋の光があるかないかわからない暗闇を走る活動でも、ネガティブケイパビリティを超えることができる一言で言えばパッションを実現する事務力ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 生きのびるための事務 著者 坂口恭平 道草晴子 発行日 2024年5月16日 発行所 株式会社マガジンハウス2025-04-1913 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"パッションを実現する事務力ノベーション(1460回)坂口恭平さん、道草晴子さんが、著されている、"事務"という力を改めて再認識させて頂きました曰く"あなたは自分が作ったものが素晴らしいのか、自分に作家としての《才能》があるかどうか、分からないんです。だからこそ人の意見に引っ張られてしまいます。人は分からないってことに恐怖を覚え、その恐怖を、取り除きたくなります。でも仕事の本当の《評価》なんて時間が経たないと分かりません。人からなんと言われようと、継続していくことが重要です。《事務》は分からないものを明らかにするのではなく、分からないまま仕事を延々と継続するためにあるのです。"ここから私は思いました1、パッションという抽象力2、パッションを仕組み化する事務力3、ネガティブケイパビリティを超える事務力1、パッションという抽象力私はことあるごとにパッション、パッション言ってるので、パッションを持てば全てが上手くいくのか?とも言われることもあるのですが、そういうということでもないということも、よく分かった上で、それでも最初に自らのパッションを知ることは大切だと思ってますそれは課題的なことでなくともよくって、漠然と誰かの役に立ちたい(利他パッション)、AIを使いこなせるようになりたい(成長パッション)など、そのほかに、大好きパッション、個性派パッションなどもあるのですが、今の自分のそれがなんなのかを知っておくことから始めようと、おはなししてます2、パッションを仕組み化する事務力それでも上手くいかないことばかりなので、パッション炸裂しててもダメじゃないかということもあるのですが、そこに必要なのが、仕組み化することで、それを上手くこなしていくのが、事務力かもしれないなあと、感じさせて頂きましたパッションは抽象的なものなので、それを実現するためには、具現化していく力が必要なのだと思います。それは、ひとりでやることもあっていいし、場合によっては、それが得意な仲間と共にやるのも一つの方法かと思います。一時期、風呂敷広げ人(CEO)と風呂敷畳み人(COO)がベンチャーには必要との話がありましたが、まさに畳人こそが、仕組み化し、事務力を高める鍵としての機能だということを改めて教えて頂きました3、ネガティブケイパビリティを超える事務力パッションを実現する活動は、失敗の連続でもあるので、まるで見えない光を暗闇の中で探し続けるような作業と言われることもありますその時に必要なのが、ジョンキーツさんのいう"ネガティブケイパビリティ"として、答えがわからなくても進み続ける力になりますが、これもわかっちゃいるけどなかなか難しいそこで重要となるのが、ここで言われる事務力なのかなと、思いました。つまり、仕組み化をしていることによって、毎日続けることができるというのが、ここで言われている事務力の最大の力なのかと思いました私のこのYoutube、podcastに関しても、実は毎日話す仕組み化、つまり事務に落とし込んでいるので、続けられていると思います。つまり、イノベーションに必要なネガティブケイパビリティを超えるためには、事務力が必須となるということかと思いましたまとめるとまずはある程度抽象的なパッションを認識して、それを具現化するための仕組み化、すなわち事務に落とし込みをする、そうすることによって、一筋の光があるかないかわからない暗闇を走る活動でも、ネガティブケイパビリティを超えることができる一言で言えばパッションを実現する事務力ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 生きのびるための事務 著者 坂口恭平 道草晴子 発行日 2024年5月16日 発行所 株式会社マガジンハウス2025-04-1913 min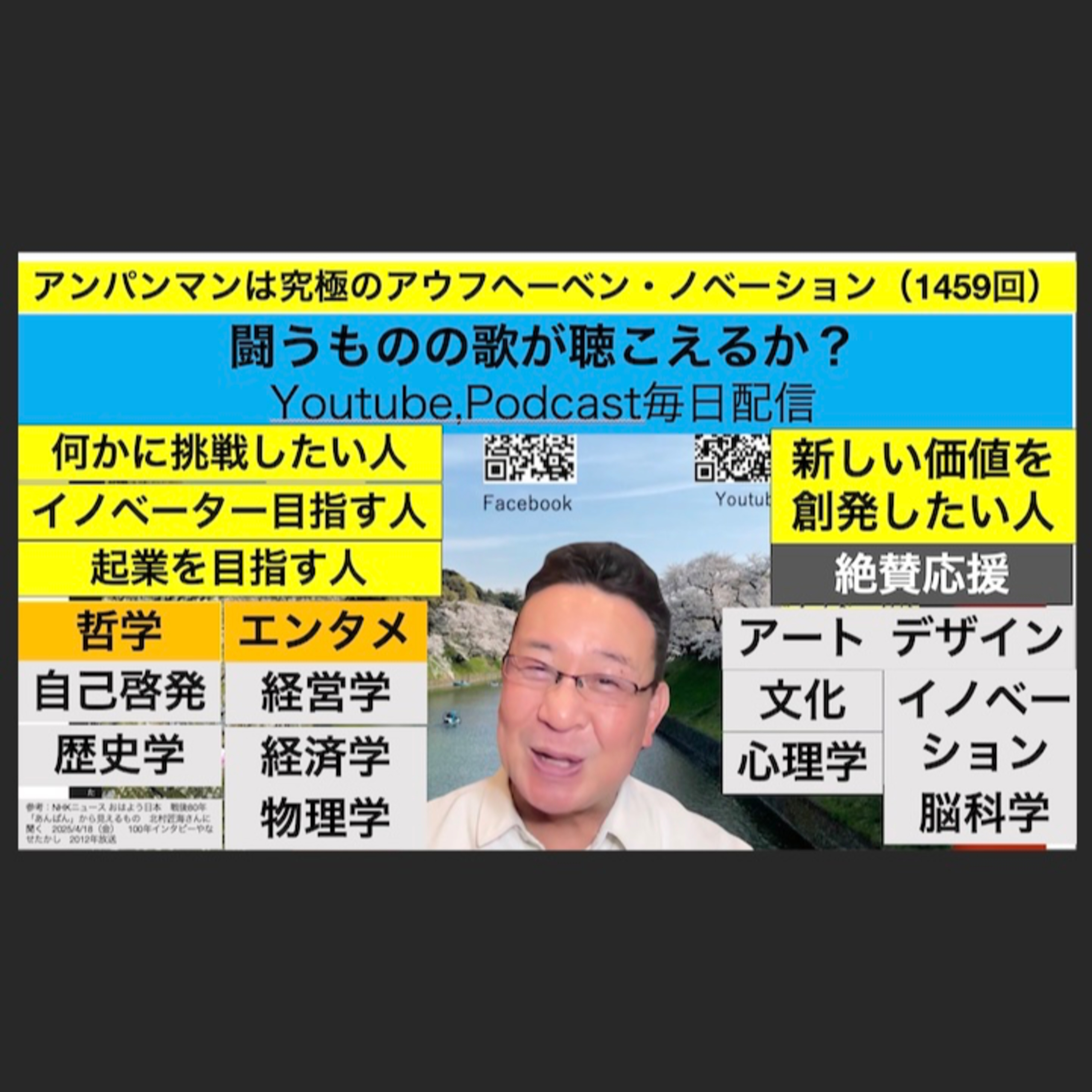 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"アンパンマンは究極のアウフヘーベン・ノベーション(1459回)アンパンマンの作者であるやなせたかしさんの、アンパンマンへの思いに、改めて感動しました曰く"正義の味方なら最初にやらなければいけないのは飢える人を助けることではないか飢えている人にひと切れのパンをあげることはA国へ行こうが B国へ行こうが正しい"ここから私はおもいました1、各々の正義による対立2、アウフヘーベンによる第三の道筋3、自らの身を削るところから始める1、各々の正義による対立対立が起きている組織や国同士にいる方々は、実は片方が悪で片方が善、と言うわけではなく、各々が各々の正義に従って一生懸命生きているだけだと言うことに改めて考えさせられました"進撃の巨人"の壁の中と壁の外の人々、"Les Misérables"のジャンバルジャンと警官、いずれもその各々の正義に従いながら、それでも戦わなければならない現実に苦悩をする、そんな物語が人気があるのは、現実の世界のやるせなさを見事に投影しているから、と言うふうにもおもいます実はこれが、対立を生む、または解消しない、真の課題、なのだと、やなせさんは、特定されたのかなと、イノベーションプロジェクトでも、1番大切なのは、真の課題を突き止めることなので、やなせさんは、それを突き止めたのかなとも思いました2、両方に共通の正義としてのあんぱんその真の課題が、分かったところで、その対立をどのように解消するのか?と言うことについては、ヘーゲルさんのいう、アウフヘーベンを用いてきたのかとおもいますつまり、両方の正義ということを、決して否定せずに、第三の選択肢を設けることによって、対立を解消する方法を、やなせさんは、双方に共通に有る、さらなる真の課題として、"餓え"にあると特定されたのかなと思いました"餓え"というのは、人間に限らず、生きとしいけるもの全てにおいて、共通に存在する、究極の真の課題、といってもいいかもしれないなと、両方に必ずあるペインを"餓え"に設定することで、双方の正義を否定しない、第三の道筋に、光明を見出したのかと思いました3、自らの身を削るところから始めるしかし、それが分かったところで、それを解消するには、どうしたら良いのか?というところに、新しいソリューションが求められると思います例えば、他の人たちが、各々の組織に"餓え"を凌ぐ対策を打ったとして、果たして、各々の正義がなくなるわけではないので、すこから先がなかなか繋げられないかもしれないそこに、やなせさんは、究極のアウフヘーベンのして、まずは、自らの身を削って、相手の"餓え"を解消してあげるのだ、という、画期的なソリューション案を出されたのかと、そしてそれが、自分の顔をちぎって相手の"餓え"を癒してくれる、アンパンマンなのか!と改めて感動しましたつまり、双方の課題が"餓え"だと分かったとして、まずは、自分の方から、あなたのところの"餓え"てる人々に、あんぱんなり食料を差し出す、ということがもしできたとしたら、その対立は自ずと解消されたくる、そんなことを思いましたつまり、世の中の厳しい対立は、各々の正義に基づいるだけであり、中の人はあくまでもなんでもない、そして、その対立を解消するためのアウフヘーベンとして、双方の大きな課題である"餓え"を解消するなんらかのソリューションがあれば、対立は解消できるかもしれないそしてその火蓋を切るのは、実は、自分の顔を差し出すが如く、自らが、対立しているところの"餓え"を解消する施策を、自らに痛みの生じる施策を出す、そこから全ては始まる、とそんなことを思いましたそこまで考えられている、やなせたかしさんのアンパンマンは、対立の真の課題を特定し、アウフヘーベンするための解決策まで、提示している、言ってみれば究極のアウフヘーベンだなあと思いましたなのでアンパンマンは究極のアウフヘーベン・ノベーションそんなことをお話ししています^ ^NHKニュース おはよう日本 戦後80年 「あんぱん」から見えるもの 北村匠海さんに聞く 2025/4/18(金) 100年インタビーやなせたかし 2012年放送2025-04-1819 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"アンパンマンは究極のアウフヘーベン・ノベーション(1459回)アンパンマンの作者であるやなせたかしさんの、アンパンマンへの思いに、改めて感動しました曰く"正義の味方なら最初にやらなければいけないのは飢える人を助けることではないか飢えている人にひと切れのパンをあげることはA国へ行こうが B国へ行こうが正しい"ここから私はおもいました1、各々の正義による対立2、アウフヘーベンによる第三の道筋3、自らの身を削るところから始める1、各々の正義による対立対立が起きている組織や国同士にいる方々は、実は片方が悪で片方が善、と言うわけではなく、各々が各々の正義に従って一生懸命生きているだけだと言うことに改めて考えさせられました"進撃の巨人"の壁の中と壁の外の人々、"Les Misérables"のジャンバルジャンと警官、いずれもその各々の正義に従いながら、それでも戦わなければならない現実に苦悩をする、そんな物語が人気があるのは、現実の世界のやるせなさを見事に投影しているから、と言うふうにもおもいます実はこれが、対立を生む、または解消しない、真の課題、なのだと、やなせさんは、特定されたのかなと、イノベーションプロジェクトでも、1番大切なのは、真の課題を突き止めることなので、やなせさんは、それを突き止めたのかなとも思いました2、両方に共通の正義としてのあんぱんその真の課題が、分かったところで、その対立をどのように解消するのか?と言うことについては、ヘーゲルさんのいう、アウフヘーベンを用いてきたのかとおもいますつまり、両方の正義ということを、決して否定せずに、第三の選択肢を設けることによって、対立を解消する方法を、やなせさんは、双方に共通に有る、さらなる真の課題として、"餓え"にあると特定されたのかなと思いました"餓え"というのは、人間に限らず、生きとしいけるもの全てにおいて、共通に存在する、究極の真の課題、といってもいいかもしれないなと、両方に必ずあるペインを"餓え"に設定することで、双方の正義を否定しない、第三の道筋に、光明を見出したのかと思いました3、自らの身を削るところから始めるしかし、それが分かったところで、それを解消するには、どうしたら良いのか?というところに、新しいソリューションが求められると思います例えば、他の人たちが、各々の組織に"餓え"を凌ぐ対策を打ったとして、果たして、各々の正義がなくなるわけではないので、すこから先がなかなか繋げられないかもしれないそこに、やなせさんは、究極のアウフヘーベンのして、まずは、自らの身を削って、相手の"餓え"を解消してあげるのだ、という、画期的なソリューション案を出されたのかと、そしてそれが、自分の顔をちぎって相手の"餓え"を癒してくれる、アンパンマンなのか!と改めて感動しましたつまり、双方の課題が"餓え"だと分かったとして、まずは、自分の方から、あなたのところの"餓え"てる人々に、あんぱんなり食料を差し出す、ということがもしできたとしたら、その対立は自ずと解消されたくる、そんなことを思いましたつまり、世の中の厳しい対立は、各々の正義に基づいるだけであり、中の人はあくまでもなんでもない、そして、その対立を解消するためのアウフヘーベンとして、双方の大きな課題である"餓え"を解消するなんらかのソリューションがあれば、対立は解消できるかもしれないそしてその火蓋を切るのは、実は、自分の顔を差し出すが如く、自らが、対立しているところの"餓え"を解消する施策を、自らに痛みの生じる施策を出す、そこから全ては始まる、とそんなことを思いましたそこまで考えられている、やなせたかしさんのアンパンマンは、対立の真の課題を特定し、アウフヘーベンするための解決策まで、提示している、言ってみれば究極のアウフヘーベンだなあと思いましたなのでアンパンマンは究極のアウフヘーベン・ノベーションそんなことをお話ししています^ ^NHKニュース おはよう日本 戦後80年 「あんぱん」から見えるもの 北村匠海さんに聞く 2025/4/18(金) 100年インタビーやなせたかし 2012年放送2025-04-1819 min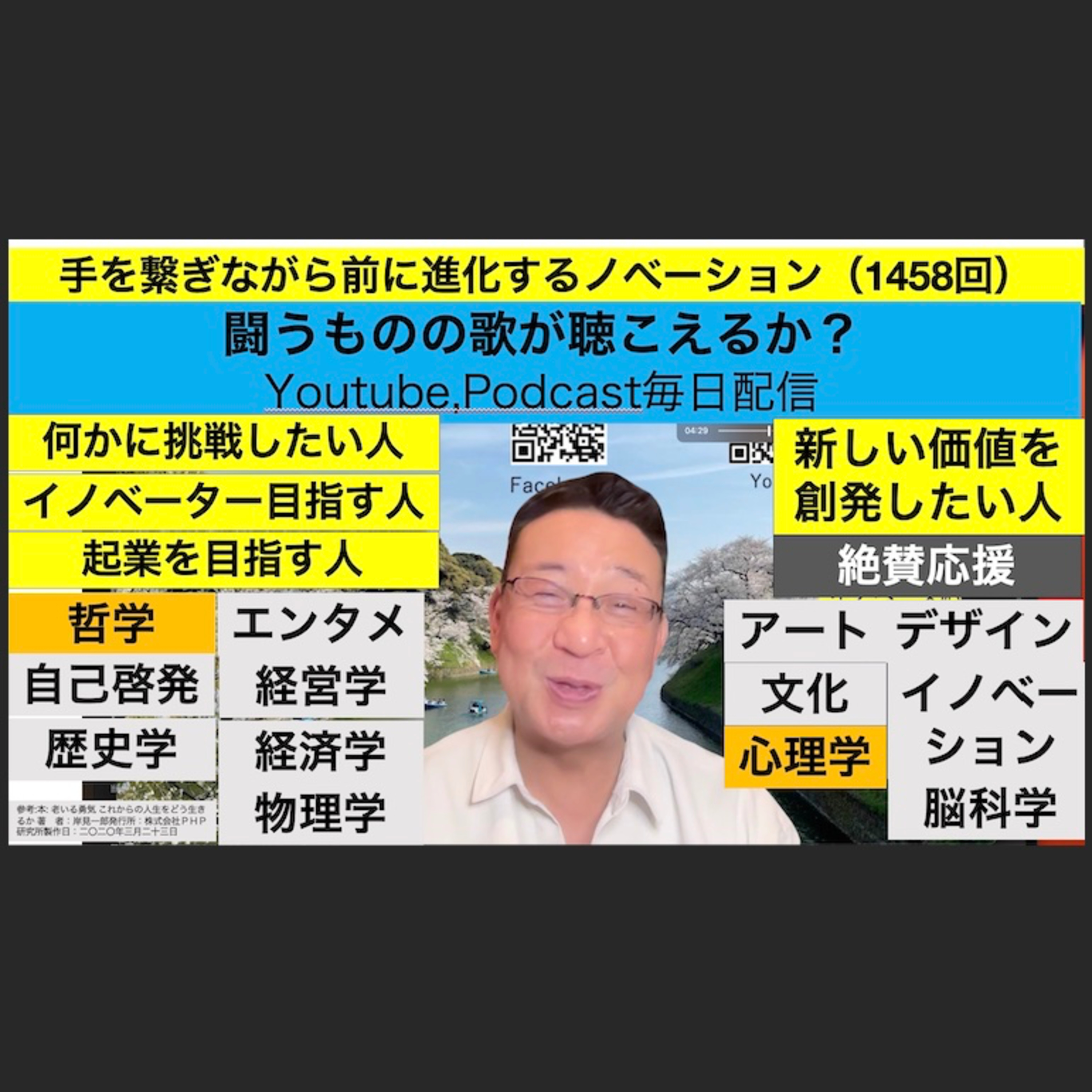 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"手を繋ぎながら前に進化するノベーション(1458回)当社の記念すべき5年目の創立記念日の日に、"嫌われる勇気""幸せになる勇気"など、大ベストセラーを出されている岸見一郎さんより、"老いる勇気"について教えて頂き、目から鱗が落ち感動しました。曰く"アドラーは、「人生は目標に向けての動き」であり、生きることは「進化すること」だと語っています。アドラーのいう進化は、上ではなく「前」に向かっての動きを指しています。つまり、誰かと比べて「上か、下か」という物差しで測るのではなく、現状を変えるために一歩前に踏み出すということです。新しいことにチャレンジするだけでなく、これまでやってきたことをコツコツ続けていくことや、日々の暮らしを楽しくするためのささやかな工夫も、大切な「一歩」です。"ここから私は思いました1、上から前へ2、成果より納得3、誰かに喜んでもらう1、上から前へすっかり今日がInnoProviZationの創立記念日だとは、これを話し始めてから、初めて気がつきました。私の母校でもある北大のクラーク博士の日と、偶然にも同じということで、"大志を抱け"と言われてるような気がする日でもありますそんな中、本日はたまたまですが、大好きな岸見一郎さんの"勇気"シリーズの、更なる一冊について、読ませて頂いて本当に嬉しかったです。私がサラリーマン時代は、まさに「上を」向いて、ずっと働いていた気がします。もちろん自分の成長もあるのですが、同時に昇進したいし、給与高くなりたいし、そのために、上司のゴマ剃ったり、無駄な会議や会合にも沢山でだなあと思い出しました岸見一郎さんが教えてくれたのは、上のベクトルを、前のベクトルに変えるだけで、見える世界が変わってくるよ、と言うことかと思いました2、成果より納得私がベクトルを変えることができたのは、独立したからかもしれないなあとおもいました。最近思うのは、なんらかの成果を出そうと言うことよりも、自分がどれだけ納得した仕事をしたか?と言う方へベクトルが倒れている気がしました。まあ1人の会社なので、昇進や権力などの、誘惑がないこともあるかとおもいますが、今となっては、やはり最後は、自分自身で納得できるものができた時に、最高に嬉しくおもいます。3、誰かに喜んでもらうそして、1.2.の両方ともに、自らのことを語っているのに対して、アドラーの共同体感覚のように、誰かに喜んでもらう、と言うことが、とても大切だなあとおもいましたイノベーター3つのフレームからすらると、パッション、仲間、大義ということで、最終的には、誰かに喜んでもらうと言うことが、本人にフィードバックとなり、それが仲間にもつながっていく誰かに喜んでもらうためには、そこにいるだけでいい、生きているだけでいいと、実はこの本の中に記述があって、それもとても感動しましたこの本のメッセージは、実はシニアの人だけに限らず、自分らしさを生きようとする、全ての人にも繋がる、そんな風にもおもいましたと言うことで一言で言えば手を繋ぎながら前に進化するノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 老いる勇気 これからの人生をどう生きるか 著 者:岸見一郎発行所:株式会社PHP研究所製作日:二〇二〇年三月二十三日動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/GzVAEVChxrY2025-04-1720 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"手を繋ぎながら前に進化するノベーション(1458回)当社の記念すべき5年目の創立記念日の日に、"嫌われる勇気""幸せになる勇気"など、大ベストセラーを出されている岸見一郎さんより、"老いる勇気"について教えて頂き、目から鱗が落ち感動しました。曰く"アドラーは、「人生は目標に向けての動き」であり、生きることは「進化すること」だと語っています。アドラーのいう進化は、上ではなく「前」に向かっての動きを指しています。つまり、誰かと比べて「上か、下か」という物差しで測るのではなく、現状を変えるために一歩前に踏み出すということです。新しいことにチャレンジするだけでなく、これまでやってきたことをコツコツ続けていくことや、日々の暮らしを楽しくするためのささやかな工夫も、大切な「一歩」です。"ここから私は思いました1、上から前へ2、成果より納得3、誰かに喜んでもらう1、上から前へすっかり今日がInnoProviZationの創立記念日だとは、これを話し始めてから、初めて気がつきました。私の母校でもある北大のクラーク博士の日と、偶然にも同じということで、"大志を抱け"と言われてるような気がする日でもありますそんな中、本日はたまたまですが、大好きな岸見一郎さんの"勇気"シリーズの、更なる一冊について、読ませて頂いて本当に嬉しかったです。私がサラリーマン時代は、まさに「上を」向いて、ずっと働いていた気がします。もちろん自分の成長もあるのですが、同時に昇進したいし、給与高くなりたいし、そのために、上司のゴマ剃ったり、無駄な会議や会合にも沢山でだなあと思い出しました岸見一郎さんが教えてくれたのは、上のベクトルを、前のベクトルに変えるだけで、見える世界が変わってくるよ、と言うことかと思いました2、成果より納得私がベクトルを変えることができたのは、独立したからかもしれないなあとおもいました。最近思うのは、なんらかの成果を出そうと言うことよりも、自分がどれだけ納得した仕事をしたか?と言う方へベクトルが倒れている気がしました。まあ1人の会社なので、昇進や権力などの、誘惑がないこともあるかとおもいますが、今となっては、やはり最後は、自分自身で納得できるものができた時に、最高に嬉しくおもいます。3、誰かに喜んでもらうそして、1.2.の両方ともに、自らのことを語っているのに対して、アドラーの共同体感覚のように、誰かに喜んでもらう、と言うことが、とても大切だなあとおもいましたイノベーター3つのフレームからすらると、パッション、仲間、大義ということで、最終的には、誰かに喜んでもらうと言うことが、本人にフィードバックとなり、それが仲間にもつながっていく誰かに喜んでもらうためには、そこにいるだけでいい、生きているだけでいいと、実はこの本の中に記述があって、それもとても感動しましたこの本のメッセージは、実はシニアの人だけに限らず、自分らしさを生きようとする、全ての人にも繋がる、そんな風にもおもいましたと言うことで一言で言えば手を繋ぎながら前に進化するノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 老いる勇気 これからの人生をどう生きるか 著 者:岸見一郎発行所:株式会社PHP研究所製作日:二〇二〇年三月二十三日動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/GzVAEVChxrY2025-04-1720 min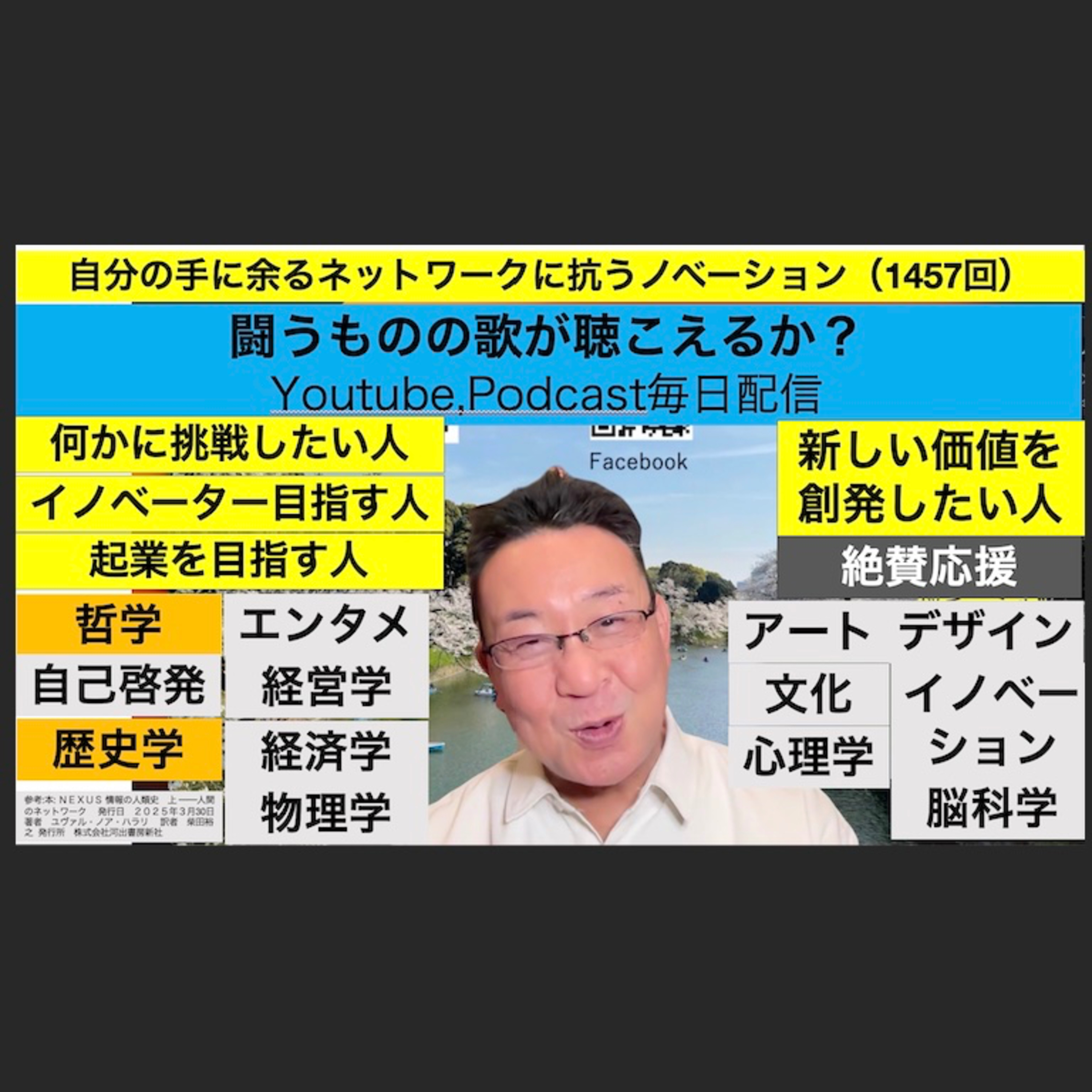 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"自分の手に余るネットワークに抗うノベーション(1457回)ユヴァル・ノア・ハラリさんから、"情報の人類史"の鍵と言えるお話に、衝撃と感動を頂きました曰く"だが、人間社会はなぜ、よりによって最悪の者たちに権力を託したりするのか?たとえば、一九三三年のドイツ人のほとんどは、精神病質者ではなかった。それなのに、なぜ彼らはヒトラーに票を投じたのか? 自分の手に余る力を呼び出す傾向は、個人の心理ではなく、私たちの種に特有の、大勢で協力する方法に由来する。人類は大規模な協力のネットワークを構築することで途方もない力を獲得するものの、そうしたネットワークは、その構築の仕方のせいで力を無分別に使いやすくなってしまっているというのが、本書の核心を成す主張だ。というわけで、私たちの問題はネットワークの問題なのだ。"ここから私は思いました1、"群集心理"2、"揺らぎがあって欲しい"3、"なんだか知らないけど、いやんって言っていい"1、"群集心理"ユヴァル・ノア・ハラリさんの書籍は、いつも壮大な人類の歩んできた道を、わかりやすい事例も用いて、かつ、とても鋭い慧眼で、いつも驚きと感動を頂くのですが、今回も冒頭にとても響く言葉を頂きました"自分の手に余る力'を呼び出すという、まるで魔王の召喚のような表現も、とてもイメージが湧いてきて、それでいて恐ろしく、しかし現実感があるなあと感動しましたそこで思ったのは、ギュスターブ・ル・ボンさんの"群集心理"の話です。名だたる独裁者が実はこの本を読んでいたとかいうお話も聞いた気がするのですが、断言、反復、感染、というこの3段階で、実は人々は容易に操作可能になるとお話しは、まさに、ハラリさんの話とシナジーがあると思いました根拠がないのにとにかく自信を持って"断言"する、そしてそれを、何度も何度も"反復"している、そしていつの間にか、沢山の人々に感染し集う人々が増える、そんなステップを、このネットワークなのか集団に感じたら、あ、今、群集心理に飲み込まれようとしてるな、などと、自分自身にアラートを出すそれを知ってると知らないとでは、全く違ってくるなあと、改めて思いました2、"揺らぎがあって欲しい"これは、先日お話しした(分断を超える"揺らぎ"ノベーション(1455回))、市川沙央さんの言葉ですが、揺るぎない自信や信念、というのは、とても素敵だし、カッコよく魅力的に見えるのですが、でもそれにみんながなんの疑問もなくついていくことに、気色悪さを感じることができるか、ということかと思いましたそこには、ある意味、思考停止して、身を委ねる気持ち良さが潜んでいて、気がつくと戻れないところまで来てしまってる、みたいなことも、ある気がしました。ハラリさんが言われる"自分の手に余る力"自体が、揺るぎあるものとして、機能することができるのか、全てを委ねてしまうほどの力は感じないけれども、常に問いを立てて揺らいでる、そんな方にこそ、真摯さがあるような気がしました3、"なんだか知らないけど、いやんって言っていい"この言葉は、私はとても好きな言葉なのですが、糸井重里さんの"ボールような言葉"という本の中にある言葉で、私の解釈は、理由が今すぐに必ずしもわからなくても、嫌だと言っていいんだ、という、ある意味、コペルニクス的転回な、ことばと思ってます例えば会議の中でこれを使うと、「ちゃんと反論してください」とか、「対案がないなら黙っててください」みたいなことが起きると思うのですが、でもその時は頭が追いつかなかったり、言語化できないんだけど、なんかいや、ってことは、沢山あるように、飲み込んじゃってるよなあと思います自分以外の人が全員賛成だったり、声の強い人が引っ張ってたりすると、そんなことは何回も経験してます。でも、それが実は、逆に声を上げなきゃ行けない場面なのかもしれない、誰もが反論をいえないからこそ、なんか違う!と言わなきゃいけないのかもしれない。むしろ、言っていいんだということに勇気をいただく言葉でしたハラリさんの"自分の手に余る力"を召喚しちゃっても、直感でも、なんか違う、と思ったら、やっぱりそれを言わなきゃいけない、むしろ誰もが言わないからこそ、自分が言わなきゃいけない、そんなことを思いました^ ^さらに時代が進むことによって、このネットワークは、AIが使われ、どんどんアルゴリズム化していくとすると、いかに「揺らぎを持たせるか」、如何に"なんだか知らないけど、いやんって言っていい"となれるのか、その仕組みを入れ込むのが、新たな時代のイノベーションとして求められるのかもしれない一言で言うと自分の手に余るネットワークに抗うノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: NEXUS 情報の人類史 上 ──人間のネットワーク 発行日 2025年3月30日 著者 ユヴァル・ノア・ハラリ 訳者 柴田裕之 発行所 株式会社河出書房新社2025-04-1622 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"自分の手に余るネットワークに抗うノベーション(1457回)ユヴァル・ノア・ハラリさんから、"情報の人類史"の鍵と言えるお話に、衝撃と感動を頂きました曰く"だが、人間社会はなぜ、よりによって最悪の者たちに権力を託したりするのか?たとえば、一九三三年のドイツ人のほとんどは、精神病質者ではなかった。それなのに、なぜ彼らはヒトラーに票を投じたのか? 自分の手に余る力を呼び出す傾向は、個人の心理ではなく、私たちの種に特有の、大勢で協力する方法に由来する。人類は大規模な協力のネットワークを構築することで途方もない力を獲得するものの、そうしたネットワークは、その構築の仕方のせいで力を無分別に使いやすくなってしまっているというのが、本書の核心を成す主張だ。というわけで、私たちの問題はネットワークの問題なのだ。"ここから私は思いました1、"群集心理"2、"揺らぎがあって欲しい"3、"なんだか知らないけど、いやんって言っていい"1、"群集心理"ユヴァル・ノア・ハラリさんの書籍は、いつも壮大な人類の歩んできた道を、わかりやすい事例も用いて、かつ、とても鋭い慧眼で、いつも驚きと感動を頂くのですが、今回も冒頭にとても響く言葉を頂きました"自分の手に余る力'を呼び出すという、まるで魔王の召喚のような表現も、とてもイメージが湧いてきて、それでいて恐ろしく、しかし現実感があるなあと感動しましたそこで思ったのは、ギュスターブ・ル・ボンさんの"群集心理"の話です。名だたる独裁者が実はこの本を読んでいたとかいうお話も聞いた気がするのですが、断言、反復、感染、というこの3段階で、実は人々は容易に操作可能になるとお話しは、まさに、ハラリさんの話とシナジーがあると思いました根拠がないのにとにかく自信を持って"断言"する、そしてそれを、何度も何度も"反復"している、そしていつの間にか、沢山の人々に感染し集う人々が増える、そんなステップを、このネットワークなのか集団に感じたら、あ、今、群集心理に飲み込まれようとしてるな、などと、自分自身にアラートを出すそれを知ってると知らないとでは、全く違ってくるなあと、改めて思いました2、"揺らぎがあって欲しい"これは、先日お話しした(分断を超える"揺らぎ"ノベーション(1455回))、市川沙央さんの言葉ですが、揺るぎない自信や信念、というのは、とても素敵だし、カッコよく魅力的に見えるのですが、でもそれにみんながなんの疑問もなくついていくことに、気色悪さを感じることができるか、ということかと思いましたそこには、ある意味、思考停止して、身を委ねる気持ち良さが潜んでいて、気がつくと戻れないところまで来てしまってる、みたいなことも、ある気がしました。ハラリさんが言われる"自分の手に余る力"自体が、揺るぎあるものとして、機能することができるのか、全てを委ねてしまうほどの力は感じないけれども、常に問いを立てて揺らいでる、そんな方にこそ、真摯さがあるような気がしました3、"なんだか知らないけど、いやんって言っていい"この言葉は、私はとても好きな言葉なのですが、糸井重里さんの"ボールような言葉"という本の中にある言葉で、私の解釈は、理由が今すぐに必ずしもわからなくても、嫌だと言っていいんだ、という、ある意味、コペルニクス的転回な、ことばと思ってます例えば会議の中でこれを使うと、「ちゃんと反論してください」とか、「対案がないなら黙っててください」みたいなことが起きると思うのですが、でもその時は頭が追いつかなかったり、言語化できないんだけど、なんかいや、ってことは、沢山あるように、飲み込んじゃってるよなあと思います自分以外の人が全員賛成だったり、声の強い人が引っ張ってたりすると、そんなことは何回も経験してます。でも、それが実は、逆に声を上げなきゃ行けない場面なのかもしれない、誰もが反論をいえないからこそ、なんか違う!と言わなきゃいけないのかもしれない。むしろ、言っていいんだということに勇気をいただく言葉でしたハラリさんの"自分の手に余る力"を召喚しちゃっても、直感でも、なんか違う、と思ったら、やっぱりそれを言わなきゃいけない、むしろ誰もが言わないからこそ、自分が言わなきゃいけない、そんなことを思いました^ ^さらに時代が進むことによって、このネットワークは、AIが使われ、どんどんアルゴリズム化していくとすると、いかに「揺らぎを持たせるか」、如何に"なんだか知らないけど、いやんって言っていい"となれるのか、その仕組みを入れ込むのが、新たな時代のイノベーションとして求められるのかもしれない一言で言うと自分の手に余るネットワークに抗うノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: NEXUS 情報の人類史 上 ──人間のネットワーク 発行日 2025年3月30日 著者 ユヴァル・ノア・ハラリ 訳者 柴田裕之 発行所 株式会社河出書房新社2025-04-1622 min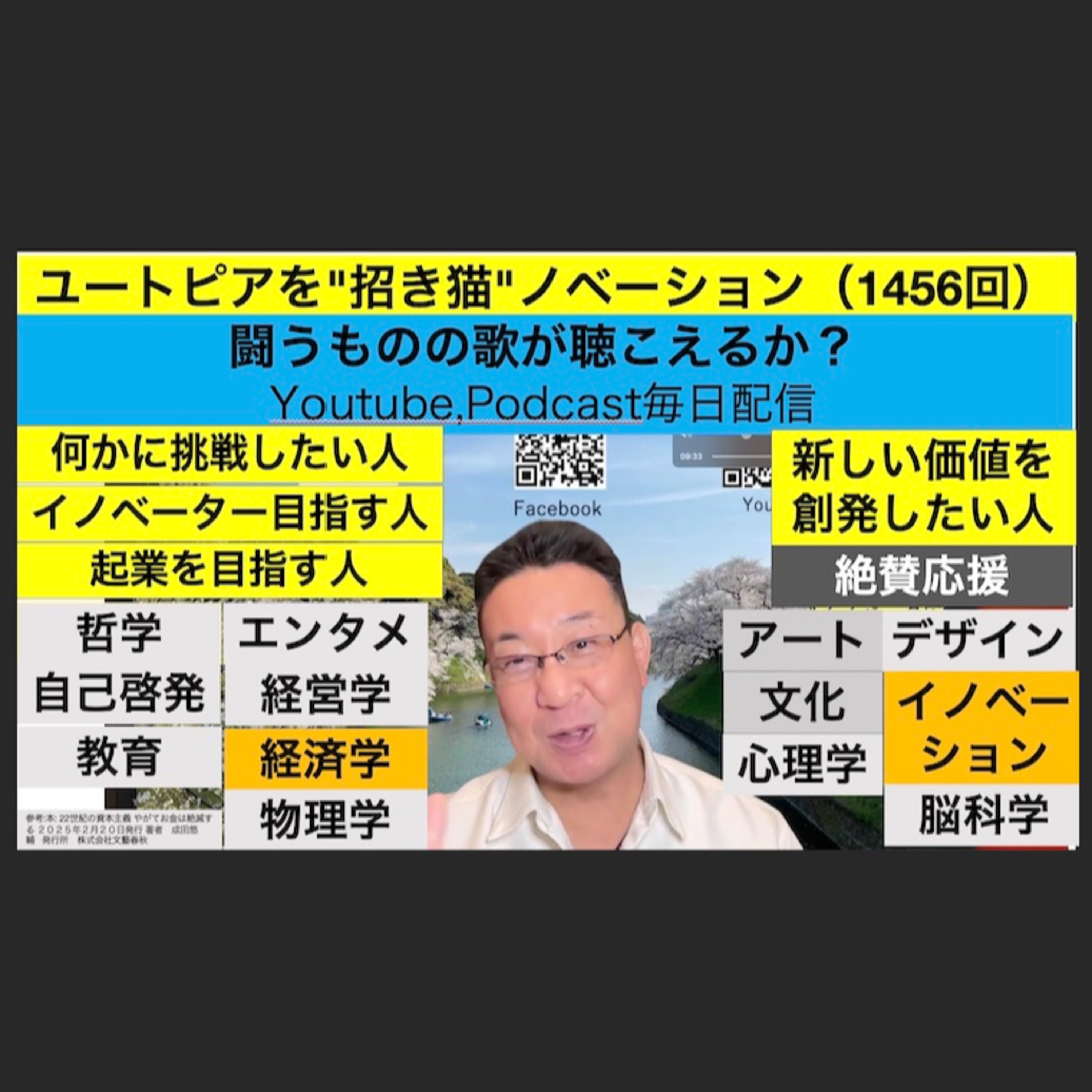 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"ユートピアを"招き猫"ノベーション(1456回)アメリカ人作家が書いた「招き猫(Maneki Neko)」という小説がある※69。日本がまだ未来の香りをまとっていた、そしてまだスマホはなくネットもよちよち歩きだった1997年の短編SFだ。"招き猫は巨大な助けあいネットワークである。人々はポケコンと呼ばれる架空の謎装置で招き猫ネットワークに接続する。主人公の剛が喫茶店でモカ・カプチーノを注文しようとすると、ポケコンが鳴って同じものをもう一つ注文しろという。もう一つテイクアウトして公園に向かい、ポケコンの合図に従って見知らぬ人にモカ・カプチーノを渡す。すると相手は驚きつつ、それが好物だと語る。ポケコンの指揮に導かれて何かのついでに他人にお土産を届けたりもらったり、ささやかな親切をしあう""招き猫ネットワークに繫がった人びとは、それぞれが稼いだお金で空腹をすばやく楽に美味しく満たすだけではない。助けたり助けられたり、人の経験に相乗りして新しい世界を教えてもらったり教えたり。見知らぬ他人同士が親切や贈与をしあうという見果てぬ夢がそこにある。お金や国家と同じくらい大規模で、しかし自発的で匿名な親切網だ。 そんな招き猫をもっと太らせ繁殖させよう(図13)。招き猫たちだけで経済が動き、お金はもういらなくなった世界はないだろうか"ここから私は思いました1、誰かの痛みと解決できる人のマッチング2、イノベーション創発システム3、付加価値と感謝のループが回る1、誰かの痛みと解決できる人のマッチング 成田祐輔さんのぶっ飛んだイノベーティブな思考に目から鱗が落ちまくりでした。そして、なんて素敵な世界が生まれるんだろうと言うことに、希望と共に暖かい未来を想像させて頂きましたモノやコトだけでなく、感情や痛みや感動などの心や気持ちまでが、全てデータ化される未来に、どんなことが起きてほしいか、私の場合、とかくディストピア的な監視社会を思い描きがちですが、なんと素敵なハピネス溢れる世界の可能性があるのかと、感動しました心や気持ちまでもが全てデータ化されたとしたら、その人が抱える痛みや困りごとなどが事細かく分析できる世界が来たとして、その心のデータを招き猫アルゴリズムが読み解いて、その付近にいる解決できるマインドセットとスキルを持ち合わせている人がいたら、そこに何かが起きるきっかけをマッチングしてくれる最初はお互いにに気づかないけど、そのきっかけをもとに新しい付加価値が生まれて、誰かのペインを解決することにつながるかもしれないサンキューポイントなど一時期流行りましたが、それが自動的に促される仕掛けになるのかと思いました。そしてそれは新しい人間関係を生み出すかもしれないし、公にはしたくないマインドの人は贈与的なものにもなるなあと。その付加価値と感謝のループが経済を回すと言うのはとても感動的と思いました2、イノベーション創発システムイノベーションは誰にでもできる。近所の畑の草をむしってあげたり、ヒールが折れた女性の荷物を持ってあげる、みたいに。誰かの困りごとを誰かがなんとかしてあげる、それだけでイノベーションと言っていいのではないかと思ってますそれがさらに仲間とともに沢山の人たちに喜んでもらえるようなものに成長した時に、世の中の人たちが俗に言うイノベーションに育ってったと思うのです。そう考えると、今回の、"招き猫"は、まさに誰かの痛みと解決できる人の自動マッチングということを考えると、まさに小さな付加価値をで依拠する人を創り出す、イノベーション創発システムと言っていいのではないかと思いましたとはいえ、最終的には、その人の選択に委ねられる部分があるので、うまく行く時もあれば、流されてしまうこともあるかもそれませんが、それでもそのイノベーションが生まれる可能性のセレンディピティを極限まで高めてくれる仕組みは、地球上に新しい価値を生み出しまくる例えて言えば、キカイダーの良心回路のような、機械仕掛けなのに、そこに人間のあったかい感情を生み出してくれるような、そんな素敵な未来のソリューションだなあと思いました3、付加価値と感謝の力が経済を回す誰もが付加価値を出せる機会をたくさん増やしてくれる、そんなマッチングソリューションは、そこから出た付加価値に対して、痛みを解除してくれたという、感謝のフィードバックが出てきて、そこに暖かい気持ちを生み出して、さらに次の人たちにその輪が引き継がれていく、そんな幸せのループが回っていくことになるなあと思いましたそして、必ずしも感謝されないこと、または、全く相手が一生気づかないけども、付加価値を提供してあげた場合には、それは贈与として、明確なお返しはないんだけども、贈与した時点で、実は贈与した人が暖かい気持ちを得てるという意味では、フィードバックが回ってるとも思います成田さんが言われているように、"見知らぬ他人同士が親切や贈与をしあうという見果てぬ夢"を実現することが、実は未来に実現できる可能性を我々はすでに持っているということに、感動し勇気をいただきましたそんなユートピアを創れるのが"招き猫アルゴリズム"であると一言で言うとユートピアを"招き猫"ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する 2025年2月20日発行 著者 成田悠輔 発行所 株式会社文藝春秋2025-04-1528 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"ユートピアを"招き猫"ノベーション(1456回)アメリカ人作家が書いた「招き猫(Maneki Neko)」という小説がある※69。日本がまだ未来の香りをまとっていた、そしてまだスマホはなくネットもよちよち歩きだった1997年の短編SFだ。"招き猫は巨大な助けあいネットワークである。人々はポケコンと呼ばれる架空の謎装置で招き猫ネットワークに接続する。主人公の剛が喫茶店でモカ・カプチーノを注文しようとすると、ポケコンが鳴って同じものをもう一つ注文しろという。もう一つテイクアウトして公園に向かい、ポケコンの合図に従って見知らぬ人にモカ・カプチーノを渡す。すると相手は驚きつつ、それが好物だと語る。ポケコンの指揮に導かれて何かのついでに他人にお土産を届けたりもらったり、ささやかな親切をしあう""招き猫ネットワークに繫がった人びとは、それぞれが稼いだお金で空腹をすばやく楽に美味しく満たすだけではない。助けたり助けられたり、人の経験に相乗りして新しい世界を教えてもらったり教えたり。見知らぬ他人同士が親切や贈与をしあうという見果てぬ夢がそこにある。お金や国家と同じくらい大規模で、しかし自発的で匿名な親切網だ。 そんな招き猫をもっと太らせ繁殖させよう(図13)。招き猫たちだけで経済が動き、お金はもういらなくなった世界はないだろうか"ここから私は思いました1、誰かの痛みと解決できる人のマッチング2、イノベーション創発システム3、付加価値と感謝のループが回る1、誰かの痛みと解決できる人のマッチング 成田祐輔さんのぶっ飛んだイノベーティブな思考に目から鱗が落ちまくりでした。そして、なんて素敵な世界が生まれるんだろうと言うことに、希望と共に暖かい未来を想像させて頂きましたモノやコトだけでなく、感情や痛みや感動などの心や気持ちまでが、全てデータ化される未来に、どんなことが起きてほしいか、私の場合、とかくディストピア的な監視社会を思い描きがちですが、なんと素敵なハピネス溢れる世界の可能性があるのかと、感動しました心や気持ちまでもが全てデータ化されたとしたら、その人が抱える痛みや困りごとなどが事細かく分析できる世界が来たとして、その心のデータを招き猫アルゴリズムが読み解いて、その付近にいる解決できるマインドセットとスキルを持ち合わせている人がいたら、そこに何かが起きるきっかけをマッチングしてくれる最初はお互いにに気づかないけど、そのきっかけをもとに新しい付加価値が生まれて、誰かのペインを解決することにつながるかもしれないサンキューポイントなど一時期流行りましたが、それが自動的に促される仕掛けになるのかと思いました。そしてそれは新しい人間関係を生み出すかもしれないし、公にはしたくないマインドの人は贈与的なものにもなるなあと。その付加価値と感謝のループが経済を回すと言うのはとても感動的と思いました2、イノベーション創発システムイノベーションは誰にでもできる。近所の畑の草をむしってあげたり、ヒールが折れた女性の荷物を持ってあげる、みたいに。誰かの困りごとを誰かがなんとかしてあげる、それだけでイノベーションと言っていいのではないかと思ってますそれがさらに仲間とともに沢山の人たちに喜んでもらえるようなものに成長した時に、世の中の人たちが俗に言うイノベーションに育ってったと思うのです。そう考えると、今回の、"招き猫"は、まさに誰かの痛みと解決できる人の自動マッチングということを考えると、まさに小さな付加価値をで依拠する人を創り出す、イノベーション創発システムと言っていいのではないかと思いましたとはいえ、最終的には、その人の選択に委ねられる部分があるので、うまく行く時もあれば、流されてしまうこともあるかもそれませんが、それでもそのイノベーションが生まれる可能性のセレンディピティを極限まで高めてくれる仕組みは、地球上に新しい価値を生み出しまくる例えて言えば、キカイダーの良心回路のような、機械仕掛けなのに、そこに人間のあったかい感情を生み出してくれるような、そんな素敵な未来のソリューションだなあと思いました3、付加価値と感謝の力が経済を回す誰もが付加価値を出せる機会をたくさん増やしてくれる、そんなマッチングソリューションは、そこから出た付加価値に対して、痛みを解除してくれたという、感謝のフィードバックが出てきて、そこに暖かい気持ちを生み出して、さらに次の人たちにその輪が引き継がれていく、そんな幸せのループが回っていくことになるなあと思いましたそして、必ずしも感謝されないこと、または、全く相手が一生気づかないけども、付加価値を提供してあげた場合には、それは贈与として、明確なお返しはないんだけども、贈与した時点で、実は贈与した人が暖かい気持ちを得てるという意味では、フィードバックが回ってるとも思います成田さんが言われているように、"見知らぬ他人同士が親切や贈与をしあうという見果てぬ夢"を実現することが、実は未来に実現できる可能性を我々はすでに持っているということに、感動し勇気をいただきましたそんなユートピアを創れるのが"招き猫アルゴリズム"であると一言で言うとユートピアを"招き猫"ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する 2025年2月20日発行 著者 成田悠輔 発行所 株式会社文藝春秋2025-04-1528 min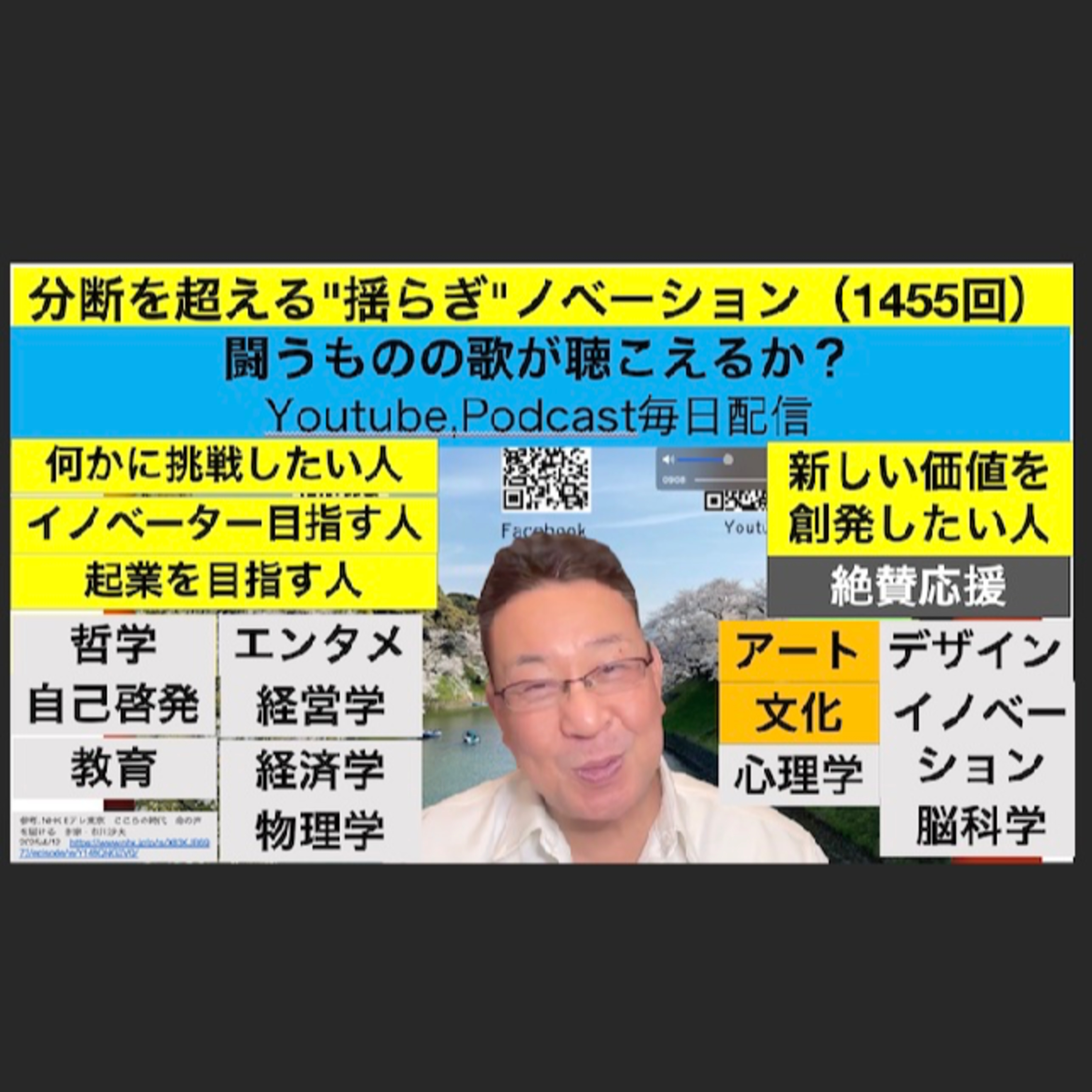 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"分断を超える"揺らぎ"ノベーション(1455回)芥川賞作家の市川沙央さんの、"分断が進む社会に対する"考え方について、心震えました曰く"ナイフを持って目の前に立っているのでないかぎり、意見の違う人とでも友人知人になれるはずだ」が私の信条です。それは私自身がだいぶ危険な人間だからです。というのは冗談ですが。私はいま文芸界というところにいるのだと思いますが、おそらくイデオロギー面では、私は文芸界の主流の人たちとは相反するものを抱えて生きてきた人間でもある。しかし私という人間の考えもモザイク状ですし、多くの人は、けして一色に染まっているわけではなくてモザイク状で、揺らぎがあるはずです。揺らぎがあってほしい。SNSの分断扇動アカウントには揺らぎがなくて気色悪いですよね。みんな、もっと揺らぎを見せてくれ、と思いますね。"ここから私は思いました1、違いは新たな出会い2、分人主義3、揺らぎある信念1、違いは新たな出会い実は以前もこのチャネルで芥川賞をとられた"お話しさせて頂きました市川さんの 『ハンチバック』を読んだ衝撃についてお話をさせて頂いたのですが、最初にナイフの話を持ってくるあたり、今回のお話も更なるロックスピリッツをカッコいいなあと感じさせて頂きました。"意見の違う人"と相対するのは、できるだけ避けたいと思うし、ビビリな私は思わず逃げてしまいがちですが、市川さんの言われるように、必ず友人知人になれるはず、と言う信念を持つことができればそれはまた、これまでと違った人との新たな仲間になれるチャンスと考えることができるので、実は、それはワクワクする出会いが訪れたことだと思うこともできるなあと、ポジティブに捉える方法を教えて頂いた気がしました2、分人主義"モザイク状"の話から、小説家の平野啓一郎の言われる分人主義を思い出しました。実は自分は、各々接する人に合わせて、さまざまな分人に分かれて接している、だから本当の自分なんてない、いやむしろさまざまな自分が本当の自分、と言う話はとても好きなお話です「あなたといる時が本当の自分に感じるの」みたいなセリフもありますが、それも単なる1人の自分。だからこそ、実は自分は"モザイク状"に普通に変化しているし、「私の信念は揺るがない」みたいなことは実はないし、その時々によって、好きな分人と、嫌な分人がいるだけ。できるだけ好きな分人でいる時間が、幸せだなあってことなのかと思います。そう考えると、新しくもしかして意見が違う人が現れた時には、逃げたいなあと思ったら、逃げたい分人が出現し、いやこれから面白くなるぞと思えば、ワクワク分人が出現することもできる、そんな風に思いました3、揺らぎある信念とすると、「揺るぎない信念を持て」といういうのは、一見カッコよく思えなくもないのですが、実は自分の分人を制限しているだけで、本当は別の分人を出すことができるはずなのにやらない信念、みたいなことになっちゃうなあと思ってしまいました誰か知らない人がいたとして、意見が違うことが分かったとしたときに、信念と違う!として、ネガティヴ分人を出してしまうのか、それとも、あ、違うんだあ、そうなんだ、どうして違うんだろうと、ワクワク分人が出動して、どんどん"揺らいで行く"それは優柔不断とは違って、アウフヘーベンのように意見の違いを理解した上で否定なしに、第三の道を探る分人が、大活躍するような、そんな"揺らぎ'分人を積極的に肯定していくお互いがそんな"揺らぎ分人"で揺らぎながらいつのまにか、友人、仲間になっていく、そんなことができる世の中になったら、素敵だなあと、思わせて頂きました一言で言うと分断を超える"揺らぎ"ノベーションそんなことを思いました^ ^参考: NHK Eテレ東京 こころの時代 命の声を届ける 作家・市川沙央 2025/4/12 https://www.nhk.jp/p/ts/X83KJR6973/episode/te/Y148QNGXVQ/2025-04-1420 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"分断を超える"揺らぎ"ノベーション(1455回)芥川賞作家の市川沙央さんの、"分断が進む社会に対する"考え方について、心震えました曰く"ナイフを持って目の前に立っているのでないかぎり、意見の違う人とでも友人知人になれるはずだ」が私の信条です。それは私自身がだいぶ危険な人間だからです。というのは冗談ですが。私はいま文芸界というところにいるのだと思いますが、おそらくイデオロギー面では、私は文芸界の主流の人たちとは相反するものを抱えて生きてきた人間でもある。しかし私という人間の考えもモザイク状ですし、多くの人は、けして一色に染まっているわけではなくてモザイク状で、揺らぎがあるはずです。揺らぎがあってほしい。SNSの分断扇動アカウントには揺らぎがなくて気色悪いですよね。みんな、もっと揺らぎを見せてくれ、と思いますね。"ここから私は思いました1、違いは新たな出会い2、分人主義3、揺らぎある信念1、違いは新たな出会い実は以前もこのチャネルで芥川賞をとられた"お話しさせて頂きました市川さんの 『ハンチバック』を読んだ衝撃についてお話をさせて頂いたのですが、最初にナイフの話を持ってくるあたり、今回のお話も更なるロックスピリッツをカッコいいなあと感じさせて頂きました。"意見の違う人"と相対するのは、できるだけ避けたいと思うし、ビビリな私は思わず逃げてしまいがちですが、市川さんの言われるように、必ず友人知人になれるはず、と言う信念を持つことができればそれはまた、これまでと違った人との新たな仲間になれるチャンスと考えることができるので、実は、それはワクワクする出会いが訪れたことだと思うこともできるなあと、ポジティブに捉える方法を教えて頂いた気がしました2、分人主義"モザイク状"の話から、小説家の平野啓一郎の言われる分人主義を思い出しました。実は自分は、各々接する人に合わせて、さまざまな分人に分かれて接している、だから本当の自分なんてない、いやむしろさまざまな自分が本当の自分、と言う話はとても好きなお話です「あなたといる時が本当の自分に感じるの」みたいなセリフもありますが、それも単なる1人の自分。だからこそ、実は自分は"モザイク状"に普通に変化しているし、「私の信念は揺るがない」みたいなことは実はないし、その時々によって、好きな分人と、嫌な分人がいるだけ。できるだけ好きな分人でいる時間が、幸せだなあってことなのかと思います。そう考えると、新しくもしかして意見が違う人が現れた時には、逃げたいなあと思ったら、逃げたい分人が出現し、いやこれから面白くなるぞと思えば、ワクワク分人が出現することもできる、そんな風に思いました3、揺らぎある信念とすると、「揺るぎない信念を持て」といういうのは、一見カッコよく思えなくもないのですが、実は自分の分人を制限しているだけで、本当は別の分人を出すことができるはずなのにやらない信念、みたいなことになっちゃうなあと思ってしまいました誰か知らない人がいたとして、意見が違うことが分かったとしたときに、信念と違う!として、ネガティヴ分人を出してしまうのか、それとも、あ、違うんだあ、そうなんだ、どうして違うんだろうと、ワクワク分人が出動して、どんどん"揺らいで行く"それは優柔不断とは違って、アウフヘーベンのように意見の違いを理解した上で否定なしに、第三の道を探る分人が、大活躍するような、そんな"揺らぎ'分人を積極的に肯定していくお互いがそんな"揺らぎ分人"で揺らぎながらいつのまにか、友人、仲間になっていく、そんなことができる世の中になったら、素敵だなあと、思わせて頂きました一言で言うと分断を超える"揺らぎ"ノベーションそんなことを思いました^ ^参考: NHK Eテレ東京 こころの時代 命の声を届ける 作家・市川沙央 2025/4/12 https://www.nhk.jp/p/ts/X83KJR6973/episode/te/Y148QNGXVQ/2025-04-1420 min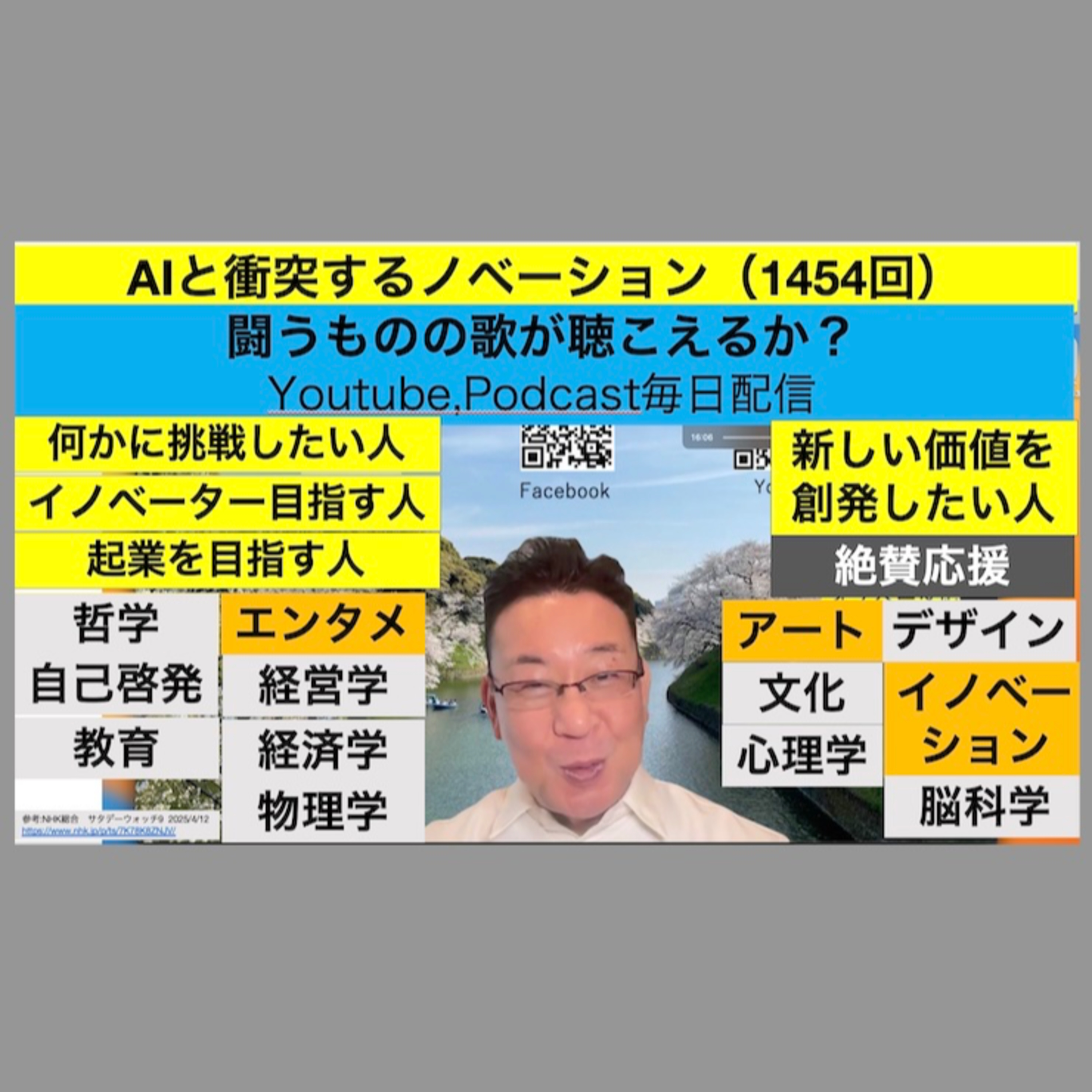 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"AIと衝突するノベーション(1454回)芥川賞作家の九段理恵さんが、AIで小説を書くことに挑戦した結果の言葉が、これからの人間とAIの創造性の差についての示唆に溢れていて感動しました"なんかどこかで見たことのあるような文章なんですよね。ま、新しく創る意味がない。AIってものは、最初から人間の役に立つように設計されているものなので、「AIが自分のために小説を書こう」っていうふうには、やはりならなかったですよね。""(AIには)新しいものを見たいという"欲求"がない人間のクリエイティビティってもっと違うものを見たい、もっと新しいものを見たいか、もっと遠くへ行きたいっていう、"欲求"が今この世界の形をつくっているというふうに私は思うわけですAIと衝突する中で本当に自分が書きたいこと、未知の欲求というものを発見する自分が何をしたいと思ってるのか、結局はそこにつきると思います"ここから私は思いました1、AIにはパッションの源を創れない2、より人間のパッションの源が重要な時代3、AIと衝突して自分のパッションの源を創る1、AIにはパッションの源を創れない今回の九段さんの挑戦は、芥川賞作家というプロフェッショナル中のプロフェッショナルが、現在のAIがどこまでクレイティブになれるのかということを、身をもって体感した結果ということで、私にとってのAIとの付き合い方に、とても大きな示唆を頂きました自分としても急速にAIを使う機会が増えており、文章もさることながら、曲も作ってくれるし、画像や動画まで簡単に創ってくれるので、自分の役割をどのように変化させていく必要があるのか、ということも考えるようになってますその中で今回の九段さんの言葉から、大きなヒントを頂いたのは、今のAIにはパッションの源を創れない、またはそもそもがない、ということでした。だとすると、イノベーター3つのフレームにおける、パッション、仲間、大義における、最初の最も大事な起点となるパッションが創れない、またはない、というところから、AI自身がイノベーターになるということは、あり得ない。ということを学んだ気がしました2、より人間のパッションの源が重要な時代そう考えると、自分自身の役割、または付加価値というのは、AIが創ることのできない、パッションの源をいかに持つことができるか、さらには、いかに他の人にもパッションの源を持ってもらえるように、支援ができるか、そこになるのかもしれないなと思いましたそれは、受託型だろうが、提案型だろうが、どちらにおいても、自らのパッションの源を、その仕事にいかに掛け合わせることによって、自らでしか出せない付加価値を創っていく、そういうことを支援できるようにすることかなと思います九段さんは"欲求"という言い方をされていますが、自身がパッションの源として、大好きなことや、他の人のためにしたいことや、オリジナリティを発揮したいことや、成長したいことなど、自らのパッションの発生する源自体を常に見つめて理解した上で望むことが、自らの付加価値としてより重要になる時代なのかもしれないと思いました3、AIと衝突して自分のパッションの源を創る九段さんの言葉で衝撃だったのは、"AIと衝突する"という言葉で、AIを便利に使うことも大事ですし、AIに使われないようになることも大事な中で最も大事なのは、AIと衝突しながら進んでいくことなのかもしれないなという気づきです。衝突するためには、自分の中に確固たるWill、欲求、パッションの源を持たないと、衝突することができないわけでその中から、これまで自分が気づかなかった自らのパッションの源や、新しいアイディアや発想がさらに拡張していく、そんな形でAIという新しい"仲間"との付き合いが進化していく、そんなことを思いましたということで、AIは、パッションの源を持たない新しいタイプの仲間なのかもしれない、だからこそ、自分のパッションの源をいかに持てるかということが、ますます大切な時代になる、だからこそ、AIという仲間とは、使う使われるではなく、とことんまで衝突する、その中で自らのパッションの源を磨いていく、そんなことを思いました一言で言うと、これからはAIと衝突するノベーションそんなことをおもいました^ ^参考:NHK総合 サタデーウォッチ9 2025/4/12 https://www.nhk.jp/p/ts/7K78K8ZNJV/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/q4YxgdxfI7Y2025-04-1321 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"AIと衝突するノベーション(1454回)芥川賞作家の九段理恵さんが、AIで小説を書くことに挑戦した結果の言葉が、これからの人間とAIの創造性の差についての示唆に溢れていて感動しました"なんかどこかで見たことのあるような文章なんですよね。ま、新しく創る意味がない。AIってものは、最初から人間の役に立つように設計されているものなので、「AIが自分のために小説を書こう」っていうふうには、やはりならなかったですよね。""(AIには)新しいものを見たいという"欲求"がない人間のクリエイティビティってもっと違うものを見たい、もっと新しいものを見たいか、もっと遠くへ行きたいっていう、"欲求"が今この世界の形をつくっているというふうに私は思うわけですAIと衝突する中で本当に自分が書きたいこと、未知の欲求というものを発見する自分が何をしたいと思ってるのか、結局はそこにつきると思います"ここから私は思いました1、AIにはパッションの源を創れない2、より人間のパッションの源が重要な時代3、AIと衝突して自分のパッションの源を創る1、AIにはパッションの源を創れない今回の九段さんの挑戦は、芥川賞作家というプロフェッショナル中のプロフェッショナルが、現在のAIがどこまでクレイティブになれるのかということを、身をもって体感した結果ということで、私にとってのAIとの付き合い方に、とても大きな示唆を頂きました自分としても急速にAIを使う機会が増えており、文章もさることながら、曲も作ってくれるし、画像や動画まで簡単に創ってくれるので、自分の役割をどのように変化させていく必要があるのか、ということも考えるようになってますその中で今回の九段さんの言葉から、大きなヒントを頂いたのは、今のAIにはパッションの源を創れない、またはそもそもがない、ということでした。だとすると、イノベーター3つのフレームにおける、パッション、仲間、大義における、最初の最も大事な起点となるパッションが創れない、またはない、というところから、AI自身がイノベーターになるということは、あり得ない。ということを学んだ気がしました2、より人間のパッションの源が重要な時代そう考えると、自分自身の役割、または付加価値というのは、AIが創ることのできない、パッションの源をいかに持つことができるか、さらには、いかに他の人にもパッションの源を持ってもらえるように、支援ができるか、そこになるのかもしれないなと思いましたそれは、受託型だろうが、提案型だろうが、どちらにおいても、自らのパッションの源を、その仕事にいかに掛け合わせることによって、自らでしか出せない付加価値を創っていく、そういうことを支援できるようにすることかなと思います九段さんは"欲求"という言い方をされていますが、自身がパッションの源として、大好きなことや、他の人のためにしたいことや、オリジナリティを発揮したいことや、成長したいことなど、自らのパッションの発生する源自体を常に見つめて理解した上で望むことが、自らの付加価値としてより重要になる時代なのかもしれないと思いました3、AIと衝突して自分のパッションの源を創る九段さんの言葉で衝撃だったのは、"AIと衝突する"という言葉で、AIを便利に使うことも大事ですし、AIに使われないようになることも大事な中で最も大事なのは、AIと衝突しながら進んでいくことなのかもしれないなという気づきです。衝突するためには、自分の中に確固たるWill、欲求、パッションの源を持たないと、衝突することができないわけでその中から、これまで自分が気づかなかった自らのパッションの源や、新しいアイディアや発想がさらに拡張していく、そんな形でAIという新しい"仲間"との付き合いが進化していく、そんなことを思いましたということで、AIは、パッションの源を持たない新しいタイプの仲間なのかもしれない、だからこそ、自分のパッションの源をいかに持てるかということが、ますます大切な時代になる、だからこそ、AIという仲間とは、使う使われるではなく、とことんまで衝突する、その中で自らのパッションの源を磨いていく、そんなことを思いました一言で言うと、これからはAIと衝突するノベーションそんなことをおもいました^ ^参考:NHK総合 サタデーウォッチ9 2025/4/12 https://www.nhk.jp/p/ts/7K78K8ZNJV/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/q4YxgdxfI7Y2025-04-1321 min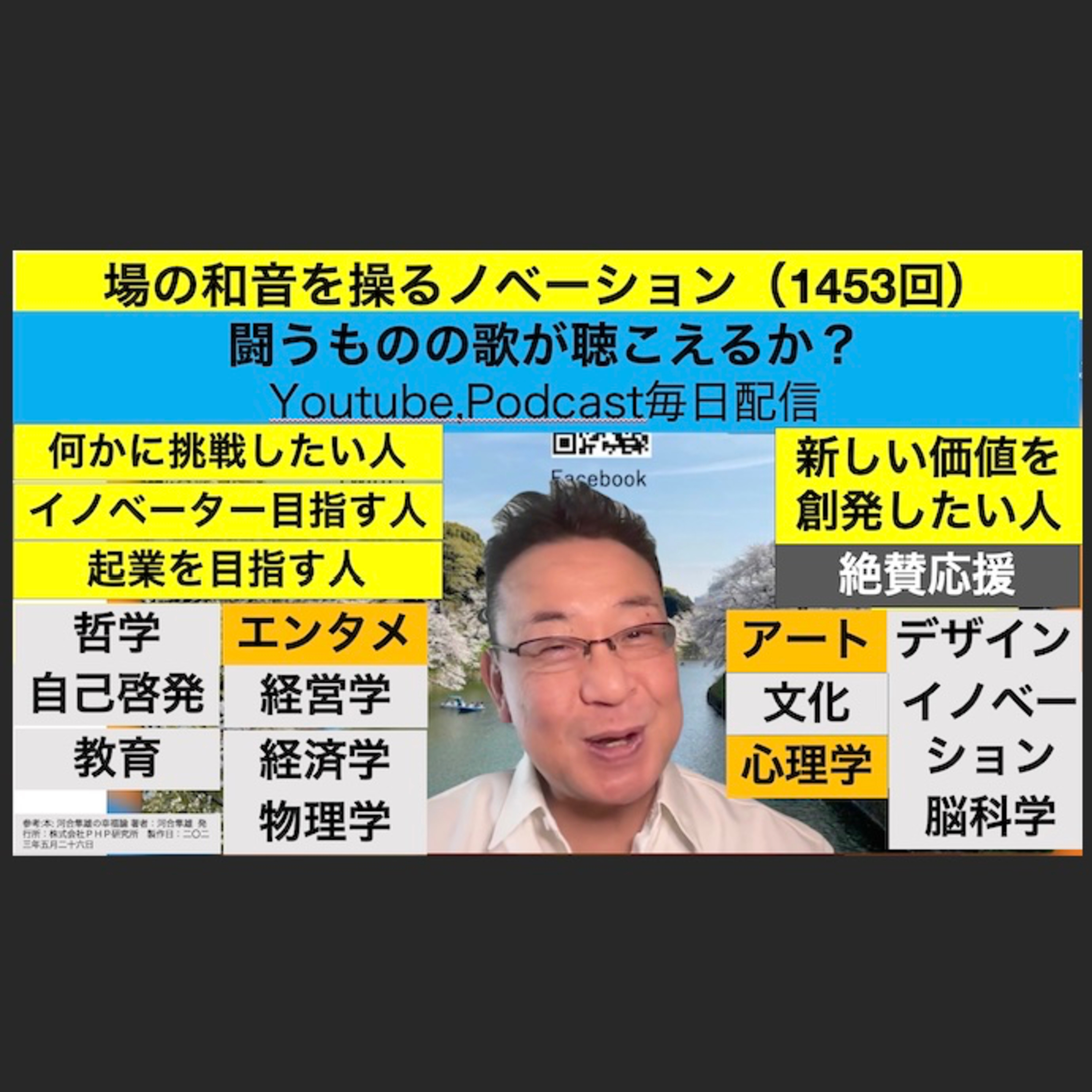 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"場の和音を操るノベーション(1453回)臨床心理学者で京都大学名誉教授の河合隼雄さんから、音楽と人間関係における、目から鱗の気づきを頂きました"フルートはピアノと違って、一度に一つの音しか出せない。従ってメロディーを吹くだけである。よい気になって吹いていると、先生にここの和音はどうなっていますか、と聞かれることがある。つまり、メロディーを吹いていても、その下についている和音がどうなって、どう変化していくかがわかっていないと駄目だというのである。""そのときに鳴っていない音が大切なのである。しかし、考えてみると、このことは人間関係でも大切ではなかろうか。人間の口は一つだから、一度にたくさんのことは言えない。例えば、「悲しいです」としか言えない。しかし、これをメロディーと考えると、同じ「悲しいです」の下に、いろいろな和音があり、それによって随分と味が変わるはずであり、そこには言われていない和音を聴くことが非常に大切ではなかろうか。音のない音に耳を傾ける態度が、他人を深く理解するのには必要であると思われる。"ここから私は思いました1、場の和音は何かを感じること2、場の和音を感じて接すること3、場の和音を創りながら接すること1、場の和音は何かを感じること私の音楽の先生に、アカペラを歌う時に、その時に歌っている音が、和音のどの構成音なのかを感じながら歌うと、全然違うハーモニーとなって聴こえるので、意識した方がいいですよーと、よく言われてましたので、このお話はめちゃくちゃ刺さりましたしかしながら、これがとても難しくて、メロディやアカペラの構成音の一つ一つは、横(時間の流れ)に覚えてしまってるし、その時その時で目まぐるしく自分の音の役割が、ある時は主音、ある時はテンションなどと、目まぐるしく変わるしで論理的思考では全く追いつかない状況に陥るので、それは練習を重ねて自然に感じるところまでいかないといけないなあと、日々思っているところです。それが実は人の人間関係でも全く同じではないか、と言うお話には、目から鱗が落ちる思いでした。今のこの場は、果たしてメジャーな和音がなっている中でのものなのか?マイナーなものなのか?私は上司に相談する際には、必ず秘書に、「今どんな感じ?」と聞いて「上機嫌!」との時にGO!みたいなことを思い出します人間関係やコミュニケーションの際には、この場がどんな和音なのかを感じ取る、もしくは感じ取ろうとすることが、空気を読め、と言うこととではなく、とても大事なセンシングスキルだよなあと思いました2、場の和音を感じて接することその場の和音が何がなってるのか?その感覚をセンシングすることが慣れてくると、きっととても良い関係性を気づくことができるのかもしれないなあと思いましたアドラーさんが言われる通り、「人間の悩みはすべて対人関係の悩みである」と言うことだとすると、今自分が話していること〔メロディ)は、この場では不協和音としてなんか気持ち悪いみたいなセンシングから、感じられることが大切かと思いましたそしてそれが高等になってくると、それはジャズのように、あえてハズした音を奏でることで、よりその場が活性化して、どんどん違う展開を生む、と言うことにも、繋がることが出るんじゃないか?とも思いますいきなり外した音でみんながびっくりだけで終わるのではなく、おっなんだこれは?と思わせたところから、さらなる新たな展開を産める人は、人間関係においてもインプロビゼーション(即興)の名手となれるのではないかと思いました3、場の和音を創りながら接することさらにその先を考えると、その場をどんな和音で行くか?と言うことを、自らがリードしていくと言うことも、大事なのではないかとも思いました今回の会議のテーマは、めちゃくちゃ重いので、あえて、アップテンポのポップな和音で、場の空気を支配していくみたいなことも、できるようになるといいなあと思いました私はよくビジネスコンテストや、幹部の前の発表、みたいな緊張はり詰めてテンションバリバリな際に、あえて揉み手からの民謡歌いながら登場みたいなことを、やったりもしてましたそうするとその場の和音は、民謡で踊りたくなるような和音が続けば、みんなリラックスして楽しくやれる、そんなある意味、心理的安全性を作り出す方法にも、実は繋がるのではないかとも思いましたということで、やはり音楽は人が活動と密接に結びついてるなあと、改めて思ったとともにその場の、和音へのセンサーを磨きながら、自らも素敵な和音を奏でながら、素敵なメロディやハーモニーを叶えられるようになりたいなと思いました一言で言うと場の和音を操るノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 河合隼雄の幸福論 著者:河合隼雄 発行所:株式会社PHP研究所 製作日:二〇二三年五月二十六日 2025-04-1217 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"場の和音を操るノベーション(1453回)臨床心理学者で京都大学名誉教授の河合隼雄さんから、音楽と人間関係における、目から鱗の気づきを頂きました"フルートはピアノと違って、一度に一つの音しか出せない。従ってメロディーを吹くだけである。よい気になって吹いていると、先生にここの和音はどうなっていますか、と聞かれることがある。つまり、メロディーを吹いていても、その下についている和音がどうなって、どう変化していくかがわかっていないと駄目だというのである。""そのときに鳴っていない音が大切なのである。しかし、考えてみると、このことは人間関係でも大切ではなかろうか。人間の口は一つだから、一度にたくさんのことは言えない。例えば、「悲しいです」としか言えない。しかし、これをメロディーと考えると、同じ「悲しいです」の下に、いろいろな和音があり、それによって随分と味が変わるはずであり、そこには言われていない和音を聴くことが非常に大切ではなかろうか。音のない音に耳を傾ける態度が、他人を深く理解するのには必要であると思われる。"ここから私は思いました1、場の和音は何かを感じること2、場の和音を感じて接すること3、場の和音を創りながら接すること1、場の和音は何かを感じること私の音楽の先生に、アカペラを歌う時に、その時に歌っている音が、和音のどの構成音なのかを感じながら歌うと、全然違うハーモニーとなって聴こえるので、意識した方がいいですよーと、よく言われてましたので、このお話はめちゃくちゃ刺さりましたしかしながら、これがとても難しくて、メロディやアカペラの構成音の一つ一つは、横(時間の流れ)に覚えてしまってるし、その時その時で目まぐるしく自分の音の役割が、ある時は主音、ある時はテンションなどと、目まぐるしく変わるしで論理的思考では全く追いつかない状況に陥るので、それは練習を重ねて自然に感じるところまでいかないといけないなあと、日々思っているところです。それが実は人の人間関係でも全く同じではないか、と言うお話には、目から鱗が落ちる思いでした。今のこの場は、果たしてメジャーな和音がなっている中でのものなのか?マイナーなものなのか?私は上司に相談する際には、必ず秘書に、「今どんな感じ?」と聞いて「上機嫌!」との時にGO!みたいなことを思い出します人間関係やコミュニケーションの際には、この場がどんな和音なのかを感じ取る、もしくは感じ取ろうとすることが、空気を読め、と言うこととではなく、とても大事なセンシングスキルだよなあと思いました2、場の和音を感じて接することその場の和音が何がなってるのか?その感覚をセンシングすることが慣れてくると、きっととても良い関係性を気づくことができるのかもしれないなあと思いましたアドラーさんが言われる通り、「人間の悩みはすべて対人関係の悩みである」と言うことだとすると、今自分が話していること〔メロディ)は、この場では不協和音としてなんか気持ち悪いみたいなセンシングから、感じられることが大切かと思いましたそしてそれが高等になってくると、それはジャズのように、あえてハズした音を奏でることで、よりその場が活性化して、どんどん違う展開を生む、と言うことにも、繋がることが出るんじゃないか?とも思いますいきなり外した音でみんながびっくりだけで終わるのではなく、おっなんだこれは?と思わせたところから、さらなる新たな展開を産める人は、人間関係においてもインプロビゼーション(即興)の名手となれるのではないかと思いました3、場の和音を創りながら接することさらにその先を考えると、その場をどんな和音で行くか?と言うことを、自らがリードしていくと言うことも、大事なのではないかとも思いました今回の会議のテーマは、めちゃくちゃ重いので、あえて、アップテンポのポップな和音で、場の空気を支配していくみたいなことも、できるようになるといいなあと思いました私はよくビジネスコンテストや、幹部の前の発表、みたいな緊張はり詰めてテンションバリバリな際に、あえて揉み手からの民謡歌いながら登場みたいなことを、やったりもしてましたそうするとその場の和音は、民謡で踊りたくなるような和音が続けば、みんなリラックスして楽しくやれる、そんなある意味、心理的安全性を作り出す方法にも、実は繋がるのではないかとも思いましたということで、やはり音楽は人が活動と密接に結びついてるなあと、改めて思ったとともにその場の、和音へのセンサーを磨きながら、自らも素敵な和音を奏でながら、素敵なメロディやハーモニーを叶えられるようになりたいなと思いました一言で言うと場の和音を操るノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 河合隼雄の幸福論 著者:河合隼雄 発行所:株式会社PHP研究所 製作日:二〇二三年五月二十六日 2025-04-1217 min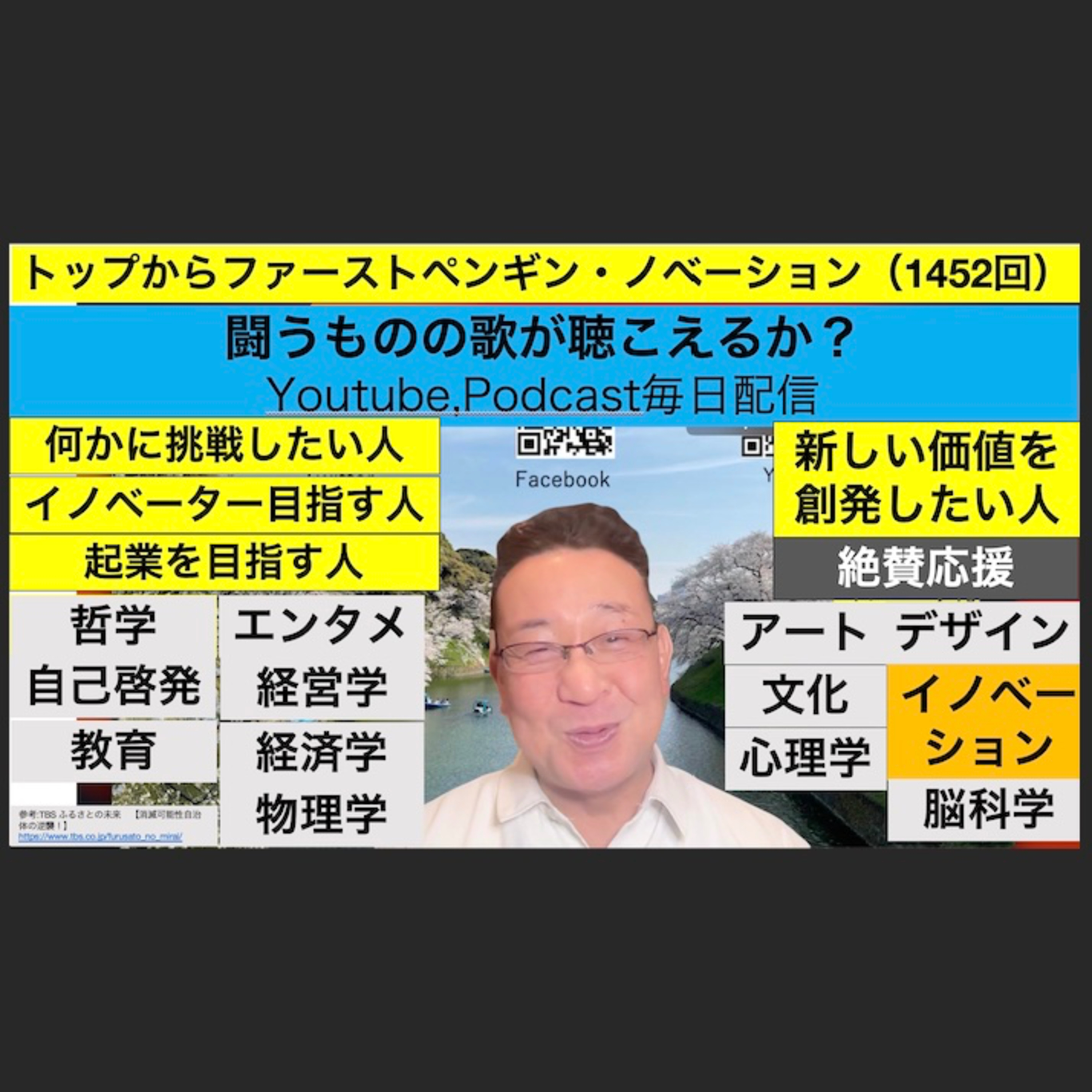 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"トップからファーストペンギン・ノベーション(1452回)石川県加賀市が、'消滅可能性自治体"と言われていたところから、「国家戦略特区」に選定され、数々の画期的なサービスを生み出している中で、宮元陸市長の言葉に心が震えました曰く"いまでもハレーションありますよハレーションの連続みたいなものですただ、どうしても生き残っていくためには、やっぱりファーストペンギンにならざるを得ないんでファーストペンギンをやる大きな目的の内容というのは、ある程度周知されてからでは遅いんですよね先端技術ってそういうものじゃないですか。ブームだってみんなそうじゃないですか。だからそういう意味では、生き残るためには先手を打たなければならない、ということじゃないでしょうか"ここから私はトップの役割を思いました1、先にペインあり2、改善から破壊へ3、事例主義から市場創発へ1、先にペインあり私がイノベーションプロジェクトをご支援している中でも、よくみられるのが、とにかくAIを使って何かやりたい、できたITソリューションをどこかに展開したい、そんなお話を頂くこともあります今回の加賀市のお取り組みで思うのは、まずは課題、徹底的なペインからはじまってるのではないか?ということを感じました。とにかく"消滅可能性自治体"という存続の強烈なペインから始まり、必ずしもスマホを使えない方々、バスやタクシーの人材不足や利用者の高齢化によるマイカー不足、そして郵便局の配送ペイン、あらゆるペインに突き刺さる、新サービスを生み出されているのに驚きましたそこには、もちろん、ITは欠かせないものとしてあるのですが、住民や企業の両方のペインに、着実に突き刺させてるなあというところが、本当に素晴らしいと思いました2、改善から破壊へそしてその時に、必ず生じるのが、ハレーションになると思うのですが、それを受け入れる覚悟と、そして乗り越える覚悟を、半端ない形で持たれた推進をされてるのだなぁとも思いましたイノベーティブであればあるほど、必ず既存のプレイヤーとのハレーションが間違い無く起こるので、逆にハレーションの起こらない改善型では、効果がほとんど見えない、そんなジレンマに陥るのが、社会課題の解決にはなかなか難しいところだと思いますが加賀市は、改善型では無く、ハレーションが起きても、破壊型にて、社会構造自体を180度変えるくらいの覚悟で、やられてるのだなあと、心が震えましただからこそ、宮元市長は、ファーストペンギンで無くてはならないと、言われているのかなと思いました。つまり、改善みたいな悠長なことは言ってる時間はもうない、ハレーションを起こしてでも、早急に進展を促す、そんなまさにFast Failなイノベーティブ思考だなあと思いました3、事例主義から市場創発へ大きな組織の場合、なかなかファーストペンギンに舵を切るのは本当に大変だと思います。まずは、先進事例を調べて、そしてリスクヘッジをしながら少しずつ改革を進める、みたいなことでは間に合わないとそこをあえて、フォロワーではなく、イノベーターとして、ファーストペンギンを目指すのだと、それはある意味、新たな市場を創るという意気込みでもあるかと思いますアメリカ合衆国の第16代大統領エイブラハム・リンカーンが言われた「未来を予測するよりも、未来を自らが創ることだ」ということを、まさに実践している事例やベスプラのフォロワーではなく、ファーストペンギンとしての、ある意味、千三つに挑む、まさにイノベーターそのもののマインドセットだなあと思いましたトップやリーダーに必要な大切なことを教えて頂いた気がしました一言で言うならトップからファーストペンギン・ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:TBS ふるさとの未来 【消滅可能性自治体の逆襲!】 https://www.tbs.co.jp/furusato_no_mirai/2025-04-1123 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"トップからファーストペンギン・ノベーション(1452回)石川県加賀市が、'消滅可能性自治体"と言われていたところから、「国家戦略特区」に選定され、数々の画期的なサービスを生み出している中で、宮元陸市長の言葉に心が震えました曰く"いまでもハレーションありますよハレーションの連続みたいなものですただ、どうしても生き残っていくためには、やっぱりファーストペンギンにならざるを得ないんでファーストペンギンをやる大きな目的の内容というのは、ある程度周知されてからでは遅いんですよね先端技術ってそういうものじゃないですか。ブームだってみんなそうじゃないですか。だからそういう意味では、生き残るためには先手を打たなければならない、ということじゃないでしょうか"ここから私はトップの役割を思いました1、先にペインあり2、改善から破壊へ3、事例主義から市場創発へ1、先にペインあり私がイノベーションプロジェクトをご支援している中でも、よくみられるのが、とにかくAIを使って何かやりたい、できたITソリューションをどこかに展開したい、そんなお話を頂くこともあります今回の加賀市のお取り組みで思うのは、まずは課題、徹底的なペインからはじまってるのではないか?ということを感じました。とにかく"消滅可能性自治体"という存続の強烈なペインから始まり、必ずしもスマホを使えない方々、バスやタクシーの人材不足や利用者の高齢化によるマイカー不足、そして郵便局の配送ペイン、あらゆるペインに突き刺さる、新サービスを生み出されているのに驚きましたそこには、もちろん、ITは欠かせないものとしてあるのですが、住民や企業の両方のペインに、着実に突き刺させてるなあというところが、本当に素晴らしいと思いました2、改善から破壊へそしてその時に、必ず生じるのが、ハレーションになると思うのですが、それを受け入れる覚悟と、そして乗り越える覚悟を、半端ない形で持たれた推進をされてるのだなぁとも思いましたイノベーティブであればあるほど、必ず既存のプレイヤーとのハレーションが間違い無く起こるので、逆にハレーションの起こらない改善型では、効果がほとんど見えない、そんなジレンマに陥るのが、社会課題の解決にはなかなか難しいところだと思いますが加賀市は、改善型では無く、ハレーションが起きても、破壊型にて、社会構造自体を180度変えるくらいの覚悟で、やられてるのだなあと、心が震えましただからこそ、宮元市長は、ファーストペンギンで無くてはならないと、言われているのかなと思いました。つまり、改善みたいな悠長なことは言ってる時間はもうない、ハレーションを起こしてでも、早急に進展を促す、そんなまさにFast Failなイノベーティブ思考だなあと思いました3、事例主義から市場創発へ大きな組織の場合、なかなかファーストペンギンに舵を切るのは本当に大変だと思います。まずは、先進事例を調べて、そしてリスクヘッジをしながら少しずつ改革を進める、みたいなことでは間に合わないとそこをあえて、フォロワーではなく、イノベーターとして、ファーストペンギンを目指すのだと、それはある意味、新たな市場を創るという意気込みでもあるかと思いますアメリカ合衆国の第16代大統領エイブラハム・リンカーンが言われた「未来を予測するよりも、未来を自らが創ることだ」ということを、まさに実践している事例やベスプラのフォロワーではなく、ファーストペンギンとしての、ある意味、千三つに挑む、まさにイノベーターそのもののマインドセットだなあと思いましたトップやリーダーに必要な大切なことを教えて頂いた気がしました一言で言うならトップからファーストペンギン・ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:TBS ふるさとの未来 【消滅可能性自治体の逆襲!】 https://www.tbs.co.jp/furusato_no_mirai/2025-04-1123 min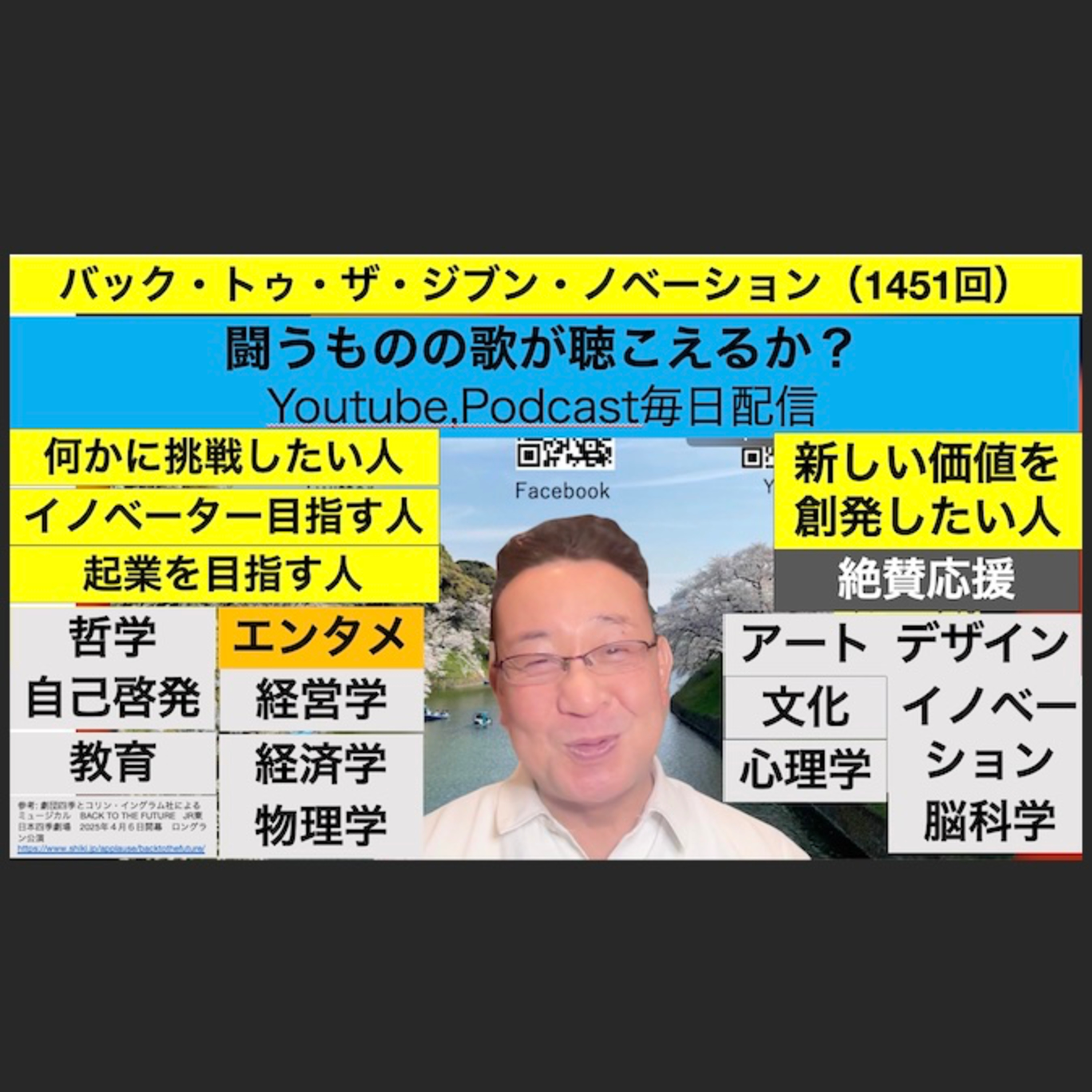 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"バック・トゥ・ザ・ジブン・ノベーション(1451回)劇団四季のバック・トゥ・ザ・フューチャーに感動で最初から号泣しっぱなしで、台本/共同創作者ボブ・ゲイルさんの言葉に、目から鱗の気づきを頂きました。曰く"普遍的な真理というものはあります。その一つがこれだと確信しています。幼少期、私たちは両親が全知全能で、神のような存在であると言じて過ごします。私たちをコントロールするのは彼らであり、私たちの人生におけるあらゆる決断を下すのは彼らである、と。しかしその後、6~10歳の間のどこかで私たちは気づくのです。彼らもかつては子どもだった、ということに。私たちの存在におけるあらゆる側面を支配するその強大な生き物も、かつては私たちと同じように、不器用で、慌ただしく、世間知らずだったのです。学校にも行ったし、いたずらもしたし、間違いを犯すこともありました。むかしむかし、私たちの両親は子ども・だったのです....・そして思春期を迎え、初めてのデートに行き、ファーストキスをして、そして続きはあなたが埋めてください。これは宇宙的大発見です。"ここから私は思いました1、親のパッションの源に触れる2、あの頃の自分のパッションの源に触れる3、そして未来の本当の自分に帰る1、親のパッションの源に触れるもうあの音楽が生オーケストラで始まった時点から感動で号泣な私でしたが、ストーリーもキャストの皆さんも、音楽も、舞台装置も、照明も、全てにおいて凄まじいほどの本気の気迫を感じるほど、私がリアルな世代ということを差し引いても、圧倒的に素晴らしい舞台でした台本/共同創作者ボブ・ゲイルさんの言葉からは、私は自分自身のまさに源である、その大元としての、親のパッションの源に触れるということが、めちゃくちゃ刺さりましたお父さんやお母さんが、若い時に、どんなパッションで生きていたのか?その結果として、自分がいるんだということを、ほんの少しでも知るだけで、自分自身に眠っていた違うパッションの源を気づかせてもらえる、そんな気がしましたそれはすごいご先祖さまがいたとかそういうことではなくて、ボブさんが言われる通り、同じように悩んで同じようにダメダメなとこもあって、それでも懸命に生きてることを想像することで、相変わらず繰り返してるなぁ的に、何か心があったかくなる気がしました2、あの頃の自分のパッションの源に触れるこれは、まさにバック・トウ・ザ・フューチャー・リアルタイム世代だからかもしれないのですが、その頃の自分自身の気持ちも思い出させて頂きました。あの心踊るイントロ、そしてヒューイルイスアンド・ザニュースのツバキの飛びまくるパワーオブラブ、あの頃のダメダメな自分ながらも、好きな子に告白どころか、声をかけることさえも憚れるくせに、何故かなんでもできる感を持ってた気持ちを思い出しましたイノベーター創発WGのセッションでもやることがあるのですが、自分のパッションの源を探る方法として、今の会社にどうして入ったのか?とか、本当はどんな仕事がしたいとおもだていたのか?とか、その会社に入って本当は何をしたかったのか?みたいなことを思い出してみようセッションもやることがありますそうすると忙しさにかまけてて忘れていた自分の本当の情熱の源を思い出すこともあって、この舞台を見てても、あの頃の自分も、こんなこと本当はやりたかったんだよなー、みたいに思い出すきっかけにもなって、改めて自分のパッションの源に出会わせてもらったような気がしました3、そして未来の本当の自分に帰るそんな体験をしてるうちに、自分の未来に自分がもし帰るとしたら、どんな未来に帰るんだろう、みたいなことまで想像したくなりましたイノベーションの世界では、バックキャスト法というやり方で、自分が今、例えば100歳になったとして、今の自分にどんな手紙を書くだろう、みたいなセッションをやることもありますもちろん、どんな自分かなんて、全て想像なんですが、少なくとも今の自分にこれだけは言いたい的に、こんなことやっておいたらよかったのに、みたいに思うことがもしあるんだとすれば、それはなんだろう、みたいなことで、意外とやりたくてもやれなかったことが出てくることもあるしまたは逆に、今の自分の位置から、まだやり残してることって本当にないんだっけと、自分のパッションの源を改めて見直してみて、本当にやりたいけどやれてないリスト作りみたいなことも、同じようなことかと思いますそういう意味では、バック・トゥ・ザ・フューチャーの本当の意味は、自分が本当にありたい自分の未来に帰る一言で言えばバック・トゥ・ザ・ジブン・ノベーションそんなことを思いました^ ^参考: 劇団四季とコリン・イングラム社による ミュージカル BACK TO THE FUTURE JR東日本四季劇場 2025年4月6日開幕 ロングラン公演 https://www.shiki.jp/applause/backtothefuture/2025-04-1024 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"バック・トゥ・ザ・ジブン・ノベーション(1451回)劇団四季のバック・トゥ・ザ・フューチャーに感動で最初から号泣しっぱなしで、台本/共同創作者ボブ・ゲイルさんの言葉に、目から鱗の気づきを頂きました。曰く"普遍的な真理というものはあります。その一つがこれだと確信しています。幼少期、私たちは両親が全知全能で、神のような存在であると言じて過ごします。私たちをコントロールするのは彼らであり、私たちの人生におけるあらゆる決断を下すのは彼らである、と。しかしその後、6~10歳の間のどこかで私たちは気づくのです。彼らもかつては子どもだった、ということに。私たちの存在におけるあらゆる側面を支配するその強大な生き物も、かつては私たちと同じように、不器用で、慌ただしく、世間知らずだったのです。学校にも行ったし、いたずらもしたし、間違いを犯すこともありました。むかしむかし、私たちの両親は子ども・だったのです....・そして思春期を迎え、初めてのデートに行き、ファーストキスをして、そして続きはあなたが埋めてください。これは宇宙的大発見です。"ここから私は思いました1、親のパッションの源に触れる2、あの頃の自分のパッションの源に触れる3、そして未来の本当の自分に帰る1、親のパッションの源に触れるもうあの音楽が生オーケストラで始まった時点から感動で号泣な私でしたが、ストーリーもキャストの皆さんも、音楽も、舞台装置も、照明も、全てにおいて凄まじいほどの本気の気迫を感じるほど、私がリアルな世代ということを差し引いても、圧倒的に素晴らしい舞台でした台本/共同創作者ボブ・ゲイルさんの言葉からは、私は自分自身のまさに源である、その大元としての、親のパッションの源に触れるということが、めちゃくちゃ刺さりましたお父さんやお母さんが、若い時に、どんなパッションで生きていたのか?その結果として、自分がいるんだということを、ほんの少しでも知るだけで、自分自身に眠っていた違うパッションの源を気づかせてもらえる、そんな気がしましたそれはすごいご先祖さまがいたとかそういうことではなくて、ボブさんが言われる通り、同じように悩んで同じようにダメダメなとこもあって、それでも懸命に生きてることを想像することで、相変わらず繰り返してるなぁ的に、何か心があったかくなる気がしました2、あの頃の自分のパッションの源に触れるこれは、まさにバック・トウ・ザ・フューチャー・リアルタイム世代だからかもしれないのですが、その頃の自分自身の気持ちも思い出させて頂きました。あの心踊るイントロ、そしてヒューイルイスアンド・ザニュースのツバキの飛びまくるパワーオブラブ、あの頃のダメダメな自分ながらも、好きな子に告白どころか、声をかけることさえも憚れるくせに、何故かなんでもできる感を持ってた気持ちを思い出しましたイノベーター創発WGのセッションでもやることがあるのですが、自分のパッションの源を探る方法として、今の会社にどうして入ったのか?とか、本当はどんな仕事がしたいとおもだていたのか?とか、その会社に入って本当は何をしたかったのか?みたいなことを思い出してみようセッションもやることがありますそうすると忙しさにかまけてて忘れていた自分の本当の情熱の源を思い出すこともあって、この舞台を見てても、あの頃の自分も、こんなこと本当はやりたかったんだよなー、みたいに思い出すきっかけにもなって、改めて自分のパッションの源に出会わせてもらったような気がしました3、そして未来の本当の自分に帰るそんな体験をしてるうちに、自分の未来に自分がもし帰るとしたら、どんな未来に帰るんだろう、みたいなことまで想像したくなりましたイノベーションの世界では、バックキャスト法というやり方で、自分が今、例えば100歳になったとして、今の自分にどんな手紙を書くだろう、みたいなセッションをやることもありますもちろん、どんな自分かなんて、全て想像なんですが、少なくとも今の自分にこれだけは言いたい的に、こんなことやっておいたらよかったのに、みたいに思うことがもしあるんだとすれば、それはなんだろう、みたいなことで、意外とやりたくてもやれなかったことが出てくることもあるしまたは逆に、今の自分の位置から、まだやり残してることって本当にないんだっけと、自分のパッションの源を改めて見直してみて、本当にやりたいけどやれてないリスト作りみたいなことも、同じようなことかと思いますそういう意味では、バック・トゥ・ザ・フューチャーの本当の意味は、自分が本当にありたい自分の未来に帰る一言で言えばバック・トゥ・ザ・ジブン・ノベーションそんなことを思いました^ ^参考: 劇団四季とコリン・イングラム社による ミュージカル BACK TO THE FUTURE JR東日本四季劇場 2025年4月6日開幕 ロングラン公演 https://www.shiki.jp/applause/backtothefuture/2025-04-1024 min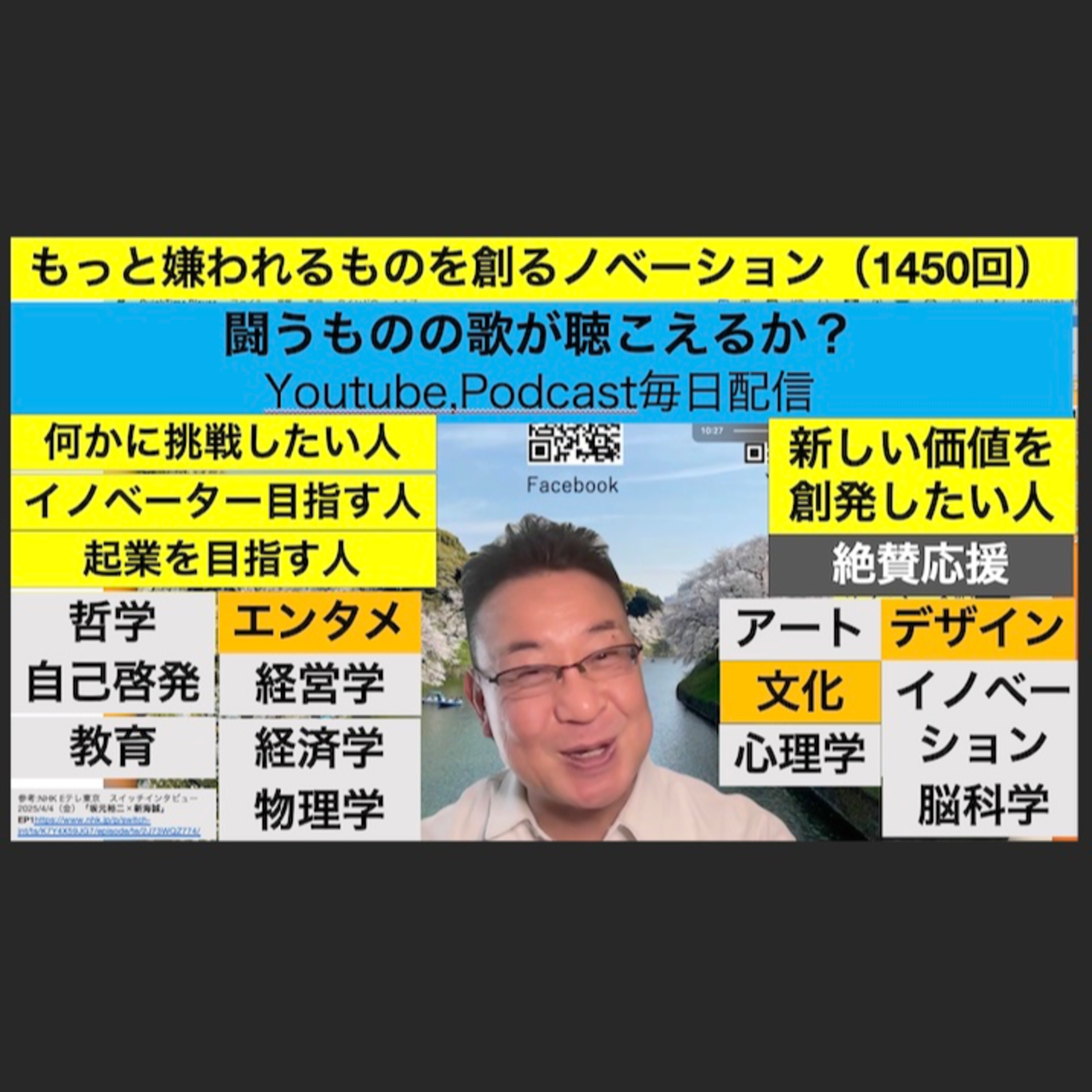 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"もっと嫌われるものを創るノベーション(1450回)今をときめくアニメーション監督の新海誠さんが、大ヒットされた"君の名は"の次の作品"天気の子"をつくるモチベーションにめちゃくちゃイノベーターを感じました曰く"君の名は こんなに嫌われるんだもっと嫌われるものをつくるべきなんじゃないかとは思ったんです君の名は、のような物語が、嫌いだっていう人は、そこに何か動かされてしまったものがきっとあるんだろうから、そこをもっと動かす物語を作りたいとは思ったんですよね僕は自己犠牲を否定する少年に共感してもらえるような物語を作りたかっんですよ「あの少年にこそ、気持ちがわかる」というように、みんなにできればたくさんの人に言って欲しかった"ここから私は思いました1、常識変換法 2、賛成する人がいない、大切な真実 3、嫌われる勇気 1、常識変換法"君の名は"は、めちゃくちゃ好きで、さらに大ヒットされた映画なので、そのファンをさらに拡大する路線で行くのが定石のような気がするのですが、新海誠さんが、それを嫌ってた人に焦点をあてて、次回作の"天気の子"を制作されたことに、衝撃を頂きましたこれは、以前お話しした、クリエイティブ・ディレクターの西島知宏さんの、"常識変換法"に通じるなあと思いました("常識変換法"で誰もがイノベーターになれるノベーション(1443回)https://youtu.be/tw9NX6l-NHY)ある意味、ファンになってくれた人よりも、嫌いに思った人をターゲットとして創るというのは、リスクが高く思えるし、せっかくのファンが離れてしまうのでは?とも思いますがまずは、常識と思われることの反対を考えてみる、そして、そこからアイディエーションをする、それによってこれまでにない新しいものを創発する、という"常識変換法"と、とても考え方が似ていて、イノベーター思考なのだなあと改めて思いました。2、賛成する人がいない、大切な真実 これは、ピーターディールさんが「ゼロトウワン」NHK出版2014/9/25にて言われていたとても有名な言葉ですが、イノベーターは他の人がまだ見えていない真実を見つけている、ということかと思います新海さんは、"君の名は"を嫌う人たちに焦点をあてて、そこに実は誰もが気づいていない、新しい真実の可能性を見えていたのではないか、だからこそ、"君の名は"のファンの方々も、また新しい体験として、更なる大ヒットされたのかなとも思いました3、嫌われる勇気口で言うのは簡単ですが、これを実際に行うためには、今度はヒットしないんじゃないか?そんなリスキーなことをする必要があるのか?みたいな、反対や批判を受けることが、沢山あったのではないかとも思いますそれを乗り越えられるのは、きっと、心理学者のアドラーさんさんからの岸見一郎さんが言われるところの、他の人の評価や批判は気にせずに自らのパッションの源に従うことができる、いわゆる"嫌われる勇気 著者 岸見一郎 2013/12/13 "を持ち合わせているからこそ、できたことなのではないかとも思いましたプロジェクトは、1人でやることではないので、沢山の批判やプレッシャーを浴びながらも、自らのパッションの源に従って貫いくことは、本当に大変なことと思いますおそらく新海さんは、自らの作品に対するパッションの源がはっきりしていて、それに従うことを第一に考えられているのかなあと感じましたたとえばビートルズのようなアーティストが、毎回出すアルバムで、ファンの期待を裏切るアルバムを出しながらも、さらなる賞賛を得ていったような新しい作品を作るためには、嫌われることも聞く厭わないもっといえば、嫌われる作品の創るノベーションそれこそが真のイノベーターなのかもしれないそんなことを思いました^ ^参考:NHK Eテレ東京 スイッチインタビュー 2025/4/4(金)「坂元裕二×新海誠」EP1https://www.nhk.jp/p/switch-int/ts/K7Y4X59JG7/episode/te/2J73WQZ774/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/TgaQ_IKeQ2s2025-04-0917 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"もっと嫌われるものを創るノベーション(1450回)今をときめくアニメーション監督の新海誠さんが、大ヒットされた"君の名は"の次の作品"天気の子"をつくるモチベーションにめちゃくちゃイノベーターを感じました曰く"君の名は こんなに嫌われるんだもっと嫌われるものをつくるべきなんじゃないかとは思ったんです君の名は、のような物語が、嫌いだっていう人は、そこに何か動かされてしまったものがきっとあるんだろうから、そこをもっと動かす物語を作りたいとは思ったんですよね僕は自己犠牲を否定する少年に共感してもらえるような物語を作りたかっんですよ「あの少年にこそ、気持ちがわかる」というように、みんなにできればたくさんの人に言って欲しかった"ここから私は思いました1、常識変換法 2、賛成する人がいない、大切な真実 3、嫌われる勇気 1、常識変換法"君の名は"は、めちゃくちゃ好きで、さらに大ヒットされた映画なので、そのファンをさらに拡大する路線で行くのが定石のような気がするのですが、新海誠さんが、それを嫌ってた人に焦点をあてて、次回作の"天気の子"を制作されたことに、衝撃を頂きましたこれは、以前お話しした、クリエイティブ・ディレクターの西島知宏さんの、"常識変換法"に通じるなあと思いました("常識変換法"で誰もがイノベーターになれるノベーション(1443回)https://youtu.be/tw9NX6l-NHY)ある意味、ファンになってくれた人よりも、嫌いに思った人をターゲットとして創るというのは、リスクが高く思えるし、せっかくのファンが離れてしまうのでは?とも思いますがまずは、常識と思われることの反対を考えてみる、そして、そこからアイディエーションをする、それによってこれまでにない新しいものを創発する、という"常識変換法"と、とても考え方が似ていて、イノベーター思考なのだなあと改めて思いました。2、賛成する人がいない、大切な真実 これは、ピーターディールさんが「ゼロトウワン」NHK出版2014/9/25にて言われていたとても有名な言葉ですが、イノベーターは他の人がまだ見えていない真実を見つけている、ということかと思います新海さんは、"君の名は"を嫌う人たちに焦点をあてて、そこに実は誰もが気づいていない、新しい真実の可能性を見えていたのではないか、だからこそ、"君の名は"のファンの方々も、また新しい体験として、更なる大ヒットされたのかなとも思いました3、嫌われる勇気口で言うのは簡単ですが、これを実際に行うためには、今度はヒットしないんじゃないか?そんなリスキーなことをする必要があるのか?みたいな、反対や批判を受けることが、沢山あったのではないかとも思いますそれを乗り越えられるのは、きっと、心理学者のアドラーさんさんからの岸見一郎さんが言われるところの、他の人の評価や批判は気にせずに自らのパッションの源に従うことができる、いわゆる"嫌われる勇気 著者 岸見一郎 2013/12/13 "を持ち合わせているからこそ、できたことなのではないかとも思いましたプロジェクトは、1人でやることではないので、沢山の批判やプレッシャーを浴びながらも、自らのパッションの源に従って貫いくことは、本当に大変なことと思いますおそらく新海さんは、自らの作品に対するパッションの源がはっきりしていて、それに従うことを第一に考えられているのかなあと感じましたたとえばビートルズのようなアーティストが、毎回出すアルバムで、ファンの期待を裏切るアルバムを出しながらも、さらなる賞賛を得ていったような新しい作品を作るためには、嫌われることも聞く厭わないもっといえば、嫌われる作品の創るノベーションそれこそが真のイノベーターなのかもしれないそんなことを思いました^ ^参考:NHK Eテレ東京 スイッチインタビュー 2025/4/4(金)「坂元裕二×新海誠」EP1https://www.nhk.jp/p/switch-int/ts/K7Y4X59JG7/episode/te/2J73WQZ774/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/TgaQ_IKeQ2s2025-04-0917 min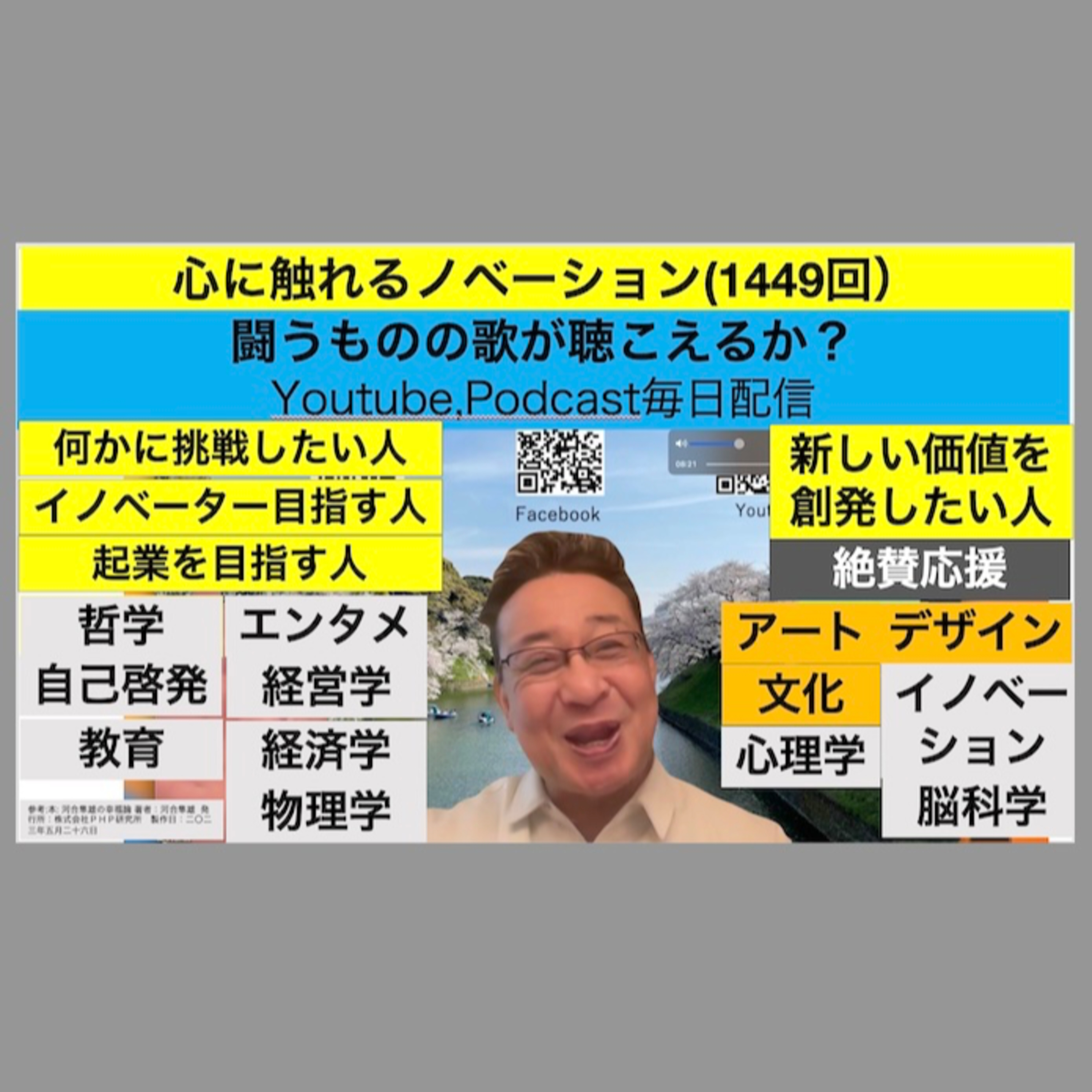 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"心に触れるノベーション(1449回)臨床心理学者の京都大学名誉教授の河合隼雄さんから、詩人の工藤直子さんのエッセイ集『ライオンのしっぽ』(大日本図書)からの一節を教えて頂き、思わず涙してしまいました工藤さんのエッセイより" 「散歩のときに、つないでくれる手。ころんですりむいたヒザに薬をぬってくれる手。服を着せてくれる手。ほうちょうをもってジャガイモをむく手、などなど。」 ""「あのころの風呂は木づくりで、フチが高くて、小さい子は湯船に入りにくい。そんなとき、両脇をかかえあげ、ちゃぽんと入れてくれたのも、父の両手だった。」 "さらに河合さんより"こんなのを読むと、工藤さんは父親の手を「見る」と言っても、そこにいつも「触れる」体験のあったことがわかるし、読むほうのわれわれにも、工藤さんのお父さんの温かい手触りが伝わってくる。 「触れる」ことが、完全に心の接触になっているから、われわれも心を動かされるのだ。"ここから私は思いました1、三現主義2、五感で感じる3、心に触れる1、三現主義自分の父も亡くなっているので、工藤さんのエッセイは、私の父の手の形や節々など、ありありと思い出してしまいました。また私は全身アートピーなので、風呂上がりに毎日薬を塗ってくれたその触感も思い出して、思わず涙してしまいました三現主義は、工学院大学の畑村洋太郎教授が提唱した言葉で、「現場」「現物」「現人(げんにん)」を大切にするという考え方で、トヨタやホンダにおいても実践されている有名な考え方ですがイノベーションにおいても、めちゃくちゃ大事だなあと思ってます。私は、さらには現場100回とも言っているのですが、とかく請負ビジネスに慣れてる場合、この本当の現場へ通い理解することが大事だとはわかっていても、実践できないということによく直面しますお客様の現場に行くと言っても、それが例えば、システム部門のような間接的な課題を理解してる人だったり、本当のエンドーユーザーではないお客様に聞きに行ってたりでこの工藤さんのようなありありとその情景を浮かばせるくらいに、課題を理解するところまで、食い込むことができれば、それだけで新たなイノベーションの種を知ろうことができるよなあとつくづく思いました2、五感で感じるまた工藤さんのエッセイを見て思うのは、五感をフル活用されているのが伝わってくる点です。現場100回でも、行けばいいのかというと、それもまた違っていて、行った上で、五感をフル活用して感じることが大事だと思いますコンサル時代には、「で、使ってみたの?」とよく言われました。「あ、すみません、ヒアリングはしたのですが、ぽりぽり」ということもよくありました。とにかく五感を使って、見る、聞く、触れてみる、やってみる、味わってみる、この工藤さんのエッセイくらいに、情景が思い浮かぶくらいに、突っ込んだ玄蕃100回ができるか、そこが本当に大切だと思いました3、心に触れるそしてその先に、心に触れることができたか、という最終目標が出てくるかと思いました。ある意味それは、五感を超えた、その人の背景だったり、生き様だったり、価値観だったり、その行動の深いところにある、心に触れられるかどうか、ということなのかもしれないなあと思いましたSimon Sineckさんのゴールデンサークルの話のように、それを説明する際に、なぜここに存在してるのか?どんな価値観を持ってそれをしようとしているのか?ということを、掘り下げて感じて、さらにはそれを、適切に伝えることで、初めて真の課題をみんなで共有し、取り組むことができるのかもしれない、とも思いました工藤さんのエッセイは、その時の情景を、読む人がありありと思い浮かばせて、心情面までも伝わり、感動を呼ぶそんなところまで、仲間と共に大義まで形作れたら、イノベーションも深く感動を呼ぶソリューションができるなあと、そんなことを思いました一言で言うと心に触れるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 河合隼雄の幸福論 著者:河合隼雄 発行所:株式会社PHP研究所 製作日:二〇二三年五月二十六日 動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/m_mnP77eQ-U2025-04-0821 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"心に触れるノベーション(1449回)臨床心理学者の京都大学名誉教授の河合隼雄さんから、詩人の工藤直子さんのエッセイ集『ライオンのしっぽ』(大日本図書)からの一節を教えて頂き、思わず涙してしまいました工藤さんのエッセイより" 「散歩のときに、つないでくれる手。ころんですりむいたヒザに薬をぬってくれる手。服を着せてくれる手。ほうちょうをもってジャガイモをむく手、などなど。」 ""「あのころの風呂は木づくりで、フチが高くて、小さい子は湯船に入りにくい。そんなとき、両脇をかかえあげ、ちゃぽんと入れてくれたのも、父の両手だった。」 "さらに河合さんより"こんなのを読むと、工藤さんは父親の手を「見る」と言っても、そこにいつも「触れる」体験のあったことがわかるし、読むほうのわれわれにも、工藤さんのお父さんの温かい手触りが伝わってくる。 「触れる」ことが、完全に心の接触になっているから、われわれも心を動かされるのだ。"ここから私は思いました1、三現主義2、五感で感じる3、心に触れる1、三現主義自分の父も亡くなっているので、工藤さんのエッセイは、私の父の手の形や節々など、ありありと思い出してしまいました。また私は全身アートピーなので、風呂上がりに毎日薬を塗ってくれたその触感も思い出して、思わず涙してしまいました三現主義は、工学院大学の畑村洋太郎教授が提唱した言葉で、「現場」「現物」「現人(げんにん)」を大切にするという考え方で、トヨタやホンダにおいても実践されている有名な考え方ですがイノベーションにおいても、めちゃくちゃ大事だなあと思ってます。私は、さらには現場100回とも言っているのですが、とかく請負ビジネスに慣れてる場合、この本当の現場へ通い理解することが大事だとはわかっていても、実践できないということによく直面しますお客様の現場に行くと言っても、それが例えば、システム部門のような間接的な課題を理解してる人だったり、本当のエンドーユーザーではないお客様に聞きに行ってたりでこの工藤さんのようなありありとその情景を浮かばせるくらいに、課題を理解するところまで、食い込むことができれば、それだけで新たなイノベーションの種を知ろうことができるよなあとつくづく思いました2、五感で感じるまた工藤さんのエッセイを見て思うのは、五感をフル活用されているのが伝わってくる点です。現場100回でも、行けばいいのかというと、それもまた違っていて、行った上で、五感をフル活用して感じることが大事だと思いますコンサル時代には、「で、使ってみたの?」とよく言われました。「あ、すみません、ヒアリングはしたのですが、ぽりぽり」ということもよくありました。とにかく五感を使って、見る、聞く、触れてみる、やってみる、味わってみる、この工藤さんのエッセイくらいに、情景が思い浮かぶくらいに、突っ込んだ玄蕃100回ができるか、そこが本当に大切だと思いました3、心に触れるそしてその先に、心に触れることができたか、という最終目標が出てくるかと思いました。ある意味それは、五感を超えた、その人の背景だったり、生き様だったり、価値観だったり、その行動の深いところにある、心に触れられるかどうか、ということなのかもしれないなあと思いましたSimon Sineckさんのゴールデンサークルの話のように、それを説明する際に、なぜここに存在してるのか?どんな価値観を持ってそれをしようとしているのか?ということを、掘り下げて感じて、さらにはそれを、適切に伝えることで、初めて真の課題をみんなで共有し、取り組むことができるのかもしれない、とも思いました工藤さんのエッセイは、その時の情景を、読む人がありありと思い浮かばせて、心情面までも伝わり、感動を呼ぶそんなところまで、仲間と共に大義まで形作れたら、イノベーションも深く感動を呼ぶソリューションができるなあと、そんなことを思いました一言で言うと心に触れるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 河合隼雄の幸福論 著者:河合隼雄 発行所:株式会社PHP研究所 製作日:二〇二三年五月二十六日 動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/m_mnP77eQ-U2025-04-0821 min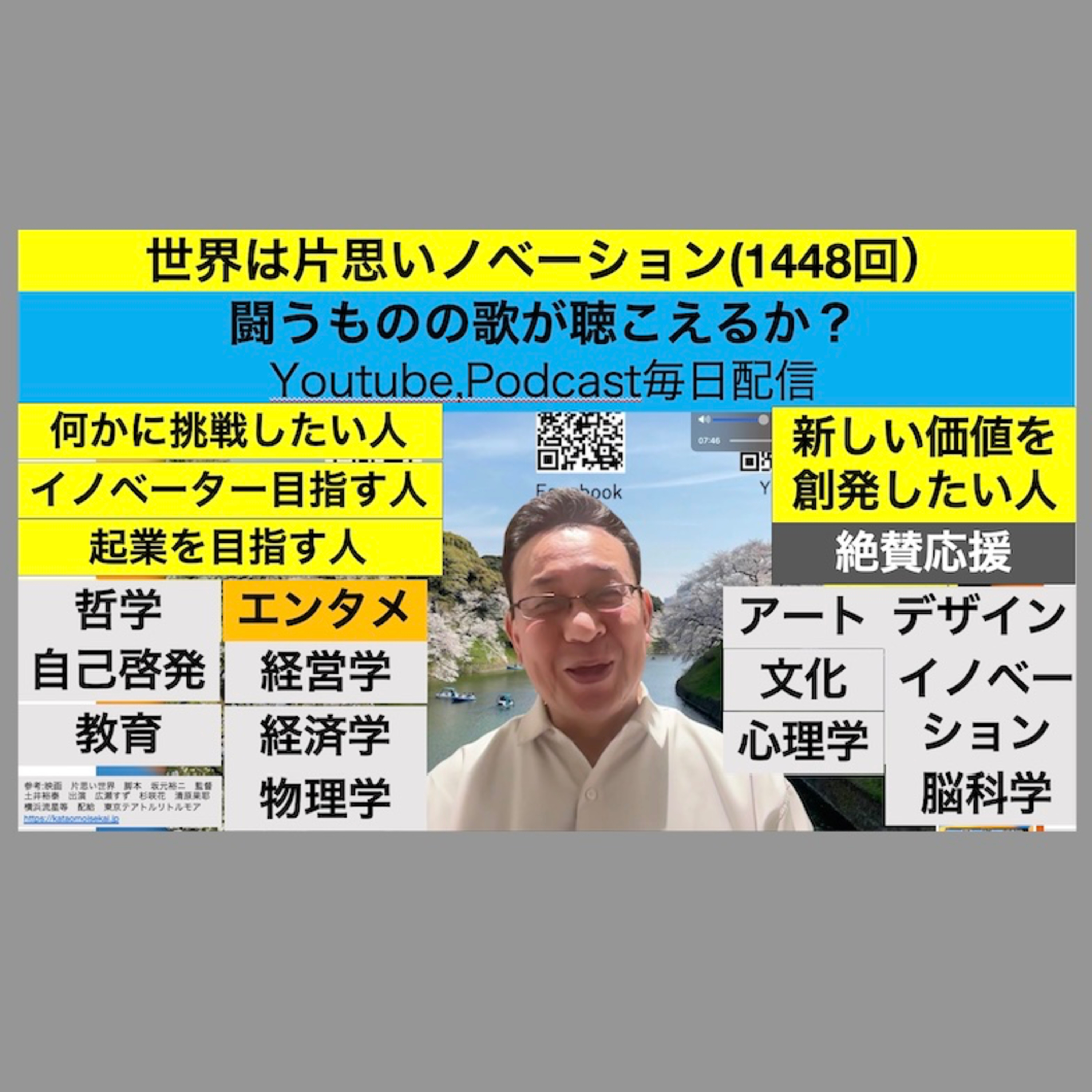 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"世界は片思いノベーション(1448回)今をときめく俳優の広瀬すずさん、杉咲花さん、清原果耶さん、横浜流星さんという4大スターが共演し、めちゃくちゃ感動した映画"片思い世界"の脚本家の坂元裕二さんの言葉に、とても感動しました曰く"過去に自分で書いたセリフでまあまあ気に入ってるのが、「行った旅行も思い出になるけど、行かなかった旅行も思い出になるじゃないですか」(「カルテット」第8話)なんですけど、結果が出ないと失敗って思ったりするじゃないですか。"中略"大事なのは、始まったことだって。そういうふうに思えた方がいいなって思うんです。結果だけに囚われるのは時間というものに縛られ過ぎですよね。物理的なこと、時間のこと、距離のことって、マイナスじゃなくプラスに捉えたいです。"ここからわたしは思いました1、大事なのは始まったこと2、わからないことだらけ3、誰もが片思い合っている1、大事なのは始まったこと衝撃のストーリー展開に、息もつかせぬほどのめり込み、そして三人姉妹の仲の良さにめちゃくちゃほっこりしながら、爽やかな希望と勇気と癒しを頂いた、本当に素晴らしい物語でした"大事なのは、始まったこと"この坂元さんの言葉は、めちゃくちゃ刺さりました。片思い、という言葉には、希望と失望が混在してるなあと思います。例えばこの4月になって、新しいことを始めるとき等でも、必ずこの、希望と失望というものがごちゃ混ぜになって、その一歩を踏み出せるかどうかがとても大事になると思います。イノベーションの世界では、FastFailという言葉をよく使われますが、失望するかもしれないという結果を前向きに捉えて、万が一うまく行かなかったことも、それによって次の方向性が早くわかってよかった、それによって、より自らの進む道がわかってスタートが切れる、そんなことにも通じるなあと思いました2、わからないことだらけ量子力学について、何回聞いても、わかったようなわからないような、煙に巻かれているような気がしてしまう私ですが、実際専門家のお話を伺っても、事情は理解してもその原理がまだ、解明されていないというお話も聞きます対人関係においても、心が通じていると思っていても、本当にどこまで通じているのか?理解し合えているのか?というのは永遠の謎だと思います。アドラーさんの言われる「課題の分離」のように、他の人がどう思うまでいるかは、永遠にわからないので、分離して自分自身がコントロールできることに集中するということが大切だとは思いますが、同時に「共同体感覚」を得たいという渇望も常日頃感じてます"片思い"という言葉には、そんなどこまで行っても、絶対に分かり合えることがない、中でも、それでも思い続けたい、という熱いパッションを感じます。わからないことだらけだからこそ、思い続けることが大切で、それはどんな結果をもたらすかどうかは、ある意味、どうでもいいのだというくらいの、潔さが、とても大切な気がする、そんなことを教えて頂いた気がしました3、誰もが片思い合ってるこの映画を観て思ったのは、誰もがわからないことだらけだからこそ、様々な状況に置かれた結果にいたとしても、それを嘆くのではなく、自分の思いに忠実に、"片思い"をし続けること、その大切さを教えて頂きましたそれは、その先に何が待っていようと、自らのパッションの源に従って進むこと、きっとその先には、自らが思っていなかったような未来が訪れる、それにワクワクして進んでいこう、そんな人には、きっと同じ志の仲間が現れる。全ては分かり合えないかもしれないけど、仲間は必ずどこかにいるパッションはいつまでたっても"片思い"かもしれないけれども世界は片思いノベーションそんなことを思いました^ ^参考:映画 片思い世界 脚本 坂元裕ニ 監督 土井裕泰 出演 広瀬すず 杉咲花 清原果耶 横浜流星等 配給 東京テアトルリトルモア https://kataomoisekai.jp2025-04-0723 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"世界は片思いノベーション(1448回)今をときめく俳優の広瀬すずさん、杉咲花さん、清原果耶さん、横浜流星さんという4大スターが共演し、めちゃくちゃ感動した映画"片思い世界"の脚本家の坂元裕二さんの言葉に、とても感動しました曰く"過去に自分で書いたセリフでまあまあ気に入ってるのが、「行った旅行も思い出になるけど、行かなかった旅行も思い出になるじゃないですか」(「カルテット」第8話)なんですけど、結果が出ないと失敗って思ったりするじゃないですか。"中略"大事なのは、始まったことだって。そういうふうに思えた方がいいなって思うんです。結果だけに囚われるのは時間というものに縛られ過ぎですよね。物理的なこと、時間のこと、距離のことって、マイナスじゃなくプラスに捉えたいです。"ここからわたしは思いました1、大事なのは始まったこと2、わからないことだらけ3、誰もが片思い合っている1、大事なのは始まったこと衝撃のストーリー展開に、息もつかせぬほどのめり込み、そして三人姉妹の仲の良さにめちゃくちゃほっこりしながら、爽やかな希望と勇気と癒しを頂いた、本当に素晴らしい物語でした"大事なのは、始まったこと"この坂元さんの言葉は、めちゃくちゃ刺さりました。片思い、という言葉には、希望と失望が混在してるなあと思います。例えばこの4月になって、新しいことを始めるとき等でも、必ずこの、希望と失望というものがごちゃ混ぜになって、その一歩を踏み出せるかどうかがとても大事になると思います。イノベーションの世界では、FastFailという言葉をよく使われますが、失望するかもしれないという結果を前向きに捉えて、万が一うまく行かなかったことも、それによって次の方向性が早くわかってよかった、それによって、より自らの進む道がわかってスタートが切れる、そんなことにも通じるなあと思いました2、わからないことだらけ量子力学について、何回聞いても、わかったようなわからないような、煙に巻かれているような気がしてしまう私ですが、実際専門家のお話を伺っても、事情は理解してもその原理がまだ、解明されていないというお話も聞きます対人関係においても、心が通じていると思っていても、本当にどこまで通じているのか?理解し合えているのか?というのは永遠の謎だと思います。アドラーさんの言われる「課題の分離」のように、他の人がどう思うまでいるかは、永遠にわからないので、分離して自分自身がコントロールできることに集中するということが大切だとは思いますが、同時に「共同体感覚」を得たいという渇望も常日頃感じてます"片思い"という言葉には、そんなどこまで行っても、絶対に分かり合えることがない、中でも、それでも思い続けたい、という熱いパッションを感じます。わからないことだらけだからこそ、思い続けることが大切で、それはどんな結果をもたらすかどうかは、ある意味、どうでもいいのだというくらいの、潔さが、とても大切な気がする、そんなことを教えて頂いた気がしました3、誰もが片思い合ってるこの映画を観て思ったのは、誰もがわからないことだらけだからこそ、様々な状況に置かれた結果にいたとしても、それを嘆くのではなく、自分の思いに忠実に、"片思い"をし続けること、その大切さを教えて頂きましたそれは、その先に何が待っていようと、自らのパッションの源に従って進むこと、きっとその先には、自らが思っていなかったような未来が訪れる、それにワクワクして進んでいこう、そんな人には、きっと同じ志の仲間が現れる。全ては分かり合えないかもしれないけど、仲間は必ずどこかにいるパッションはいつまでたっても"片思い"かもしれないけれども世界は片思いノベーションそんなことを思いました^ ^参考:映画 片思い世界 脚本 坂元裕ニ 監督 土井裕泰 出演 広瀬すず 杉咲花 清原果耶 横浜流星等 配給 東京テアトルリトルモア https://kataomoisekai.jp2025-04-0723 min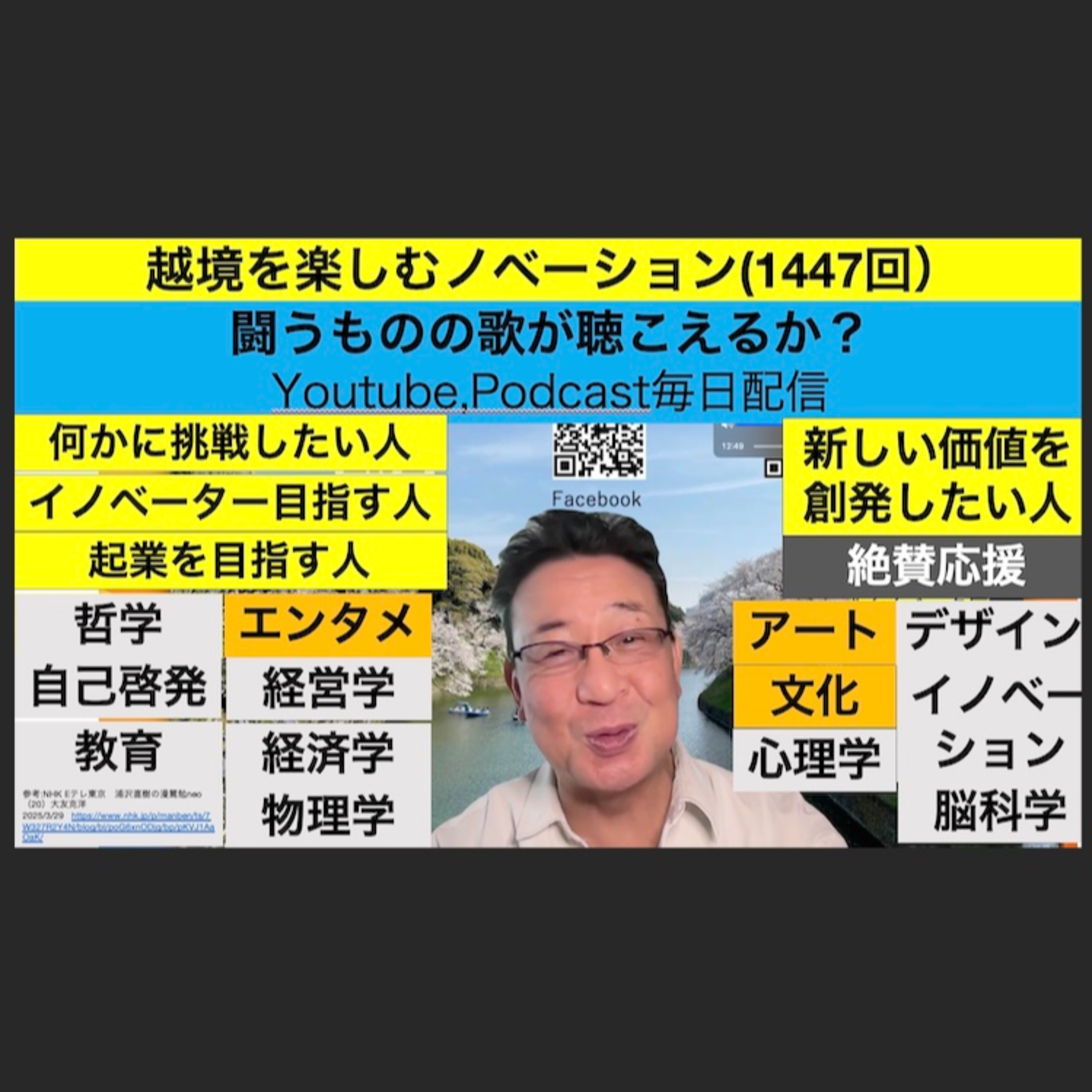 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"越境を楽しむノベーション(1447回)童夢やAKIRAなど、大友克洋前と後の世界を作ったと言われるレジェンドのイノベーションの秘訣を伺わせて頂き、めちゃくちゃ感動しました曰く"そのう、俺の漫画の中にある要素ってのは、映画だったりいろんなファッションであったり、音楽だったりそういうもっといろんなものが、いっぱい入ってきてそっちの方に行くわけよだから、そのみんながやっぱり漫画の中から漫画を作ってるんで、俺、漫画の中だけで漫画を作ってるわけじゃないんだよもっとその世の中のいろんな新しいものを見ながら描いてるわけ"ここから私は思いました1、越境思考2、より離れた異分野との結合3、遊びと創造1、越境思考大友さんの作品からは、圧倒的な力だったり、凄まじいスピード感だったり、躍動感、見たこともない図柄が、あたかも普通のその辺りにいるような人々から繰り出される衝撃などで、何度も見直してしまう凄みを感じていましたその秘密の一端が、映画やファッション、音楽などの、全く違う要素から繰り出されているということに、イノベーションには、越境思考ということが本当に大切なんだなあと思わせて頂きました私がオープンイノベーションを始めた時は、ベンチャーとビジネスはリスクが高いとか、責任が取れるのか?みたいなことを言われながらも、閉塞状況を打ち破るためには、異分子を取り入れるしかないと思って分野も業種も国籍も全然違う様々な方と、会うことから始めたことを思い出しましたTushman & Scanlanさんらの論文によると、越境は、異なる知識体系の橋渡しをする人や行為がイノベーションに寄与する、ということを言われています。まさに大友さんは、自ら様々な分野に越境することで、革新的な作品を作られたのかと思いました2、より離れた異分野との結合その上で、シュンペーターさんが、言われてる新結合として、既存のアイディア同士を掛け合わせること、そしてその既存のアイディアは、離れてれば離れてるほど、面白いアイディアになる、と言えことを実現されていたのかと思いました私がオープンイノベーション活動をした当初でも、今のSEE(Startup Emergence Ecosystem)でも、そうなのですが、出来るだけ離れたものを集めて掛け合わせるというコンセプトを貫いているのですが想定を超えるような新たなイノベーションを起こすためには、効率的に業務・業態を集めるなどではなく、全く違うものがそれによってより新しいものが生まれる、そのような仕掛けを作ることが大切と思います3、遊びと創造大友さんのお話を聞いていると、改めて音楽やファッションや映画から、いろんなものを取り入れようみたいな形ではなく、あたかも遊びのように興味のあること全てに突っ込んで行ってるのではないかとも感じます大阪大学の苧坂直行さんの言われているデフォルトモードネットワークのように、一つのことに集中している状態から、散歩に行ったり音楽を聞いたりと、違う活動をすることによって、実は脳が活性化し新しい考えが浮かぶことがある、とのお話も思い出しましたまた、かのアインシュタインさんが"創造性とは、知性が楽しんでいる状態である"と言われたように、遊びとして様々なものに触れて、体験して、ワクワクすることによって、様々な異分子を楽しんで結合させるそこが出来る、そんなことも感じさせて頂きましたということで、一言で言うと越境を楽しむノベーションそんなことを感じました^ ^参考:NHK Eテレ東京 浦沢直樹の漫勉neo(20)大友克洋 2025/3/29 https://www.nhk.jp/p/manben/ts/7W327R2Y4N/blog/bl/poG6xnODjg/bp/pKVJ1AaOaK/2025-04-0624 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"越境を楽しむノベーション(1447回)童夢やAKIRAなど、大友克洋前と後の世界を作ったと言われるレジェンドのイノベーションの秘訣を伺わせて頂き、めちゃくちゃ感動しました曰く"そのう、俺の漫画の中にある要素ってのは、映画だったりいろんなファッションであったり、音楽だったりそういうもっといろんなものが、いっぱい入ってきてそっちの方に行くわけよだから、そのみんながやっぱり漫画の中から漫画を作ってるんで、俺、漫画の中だけで漫画を作ってるわけじゃないんだよもっとその世の中のいろんな新しいものを見ながら描いてるわけ"ここから私は思いました1、越境思考2、より離れた異分野との結合3、遊びと創造1、越境思考大友さんの作品からは、圧倒的な力だったり、凄まじいスピード感だったり、躍動感、見たこともない図柄が、あたかも普通のその辺りにいるような人々から繰り出される衝撃などで、何度も見直してしまう凄みを感じていましたその秘密の一端が、映画やファッション、音楽などの、全く違う要素から繰り出されているということに、イノベーションには、越境思考ということが本当に大切なんだなあと思わせて頂きました私がオープンイノベーションを始めた時は、ベンチャーとビジネスはリスクが高いとか、責任が取れるのか?みたいなことを言われながらも、閉塞状況を打ち破るためには、異分子を取り入れるしかないと思って分野も業種も国籍も全然違う様々な方と、会うことから始めたことを思い出しましたTushman & Scanlanさんらの論文によると、越境は、異なる知識体系の橋渡しをする人や行為がイノベーションに寄与する、ということを言われています。まさに大友さんは、自ら様々な分野に越境することで、革新的な作品を作られたのかと思いました2、より離れた異分野との結合その上で、シュンペーターさんが、言われてる新結合として、既存のアイディア同士を掛け合わせること、そしてその既存のアイディアは、離れてれば離れてるほど、面白いアイディアになる、と言えことを実現されていたのかと思いました私がオープンイノベーション活動をした当初でも、今のSEE(Startup Emergence Ecosystem)でも、そうなのですが、出来るだけ離れたものを集めて掛け合わせるというコンセプトを貫いているのですが想定を超えるような新たなイノベーションを起こすためには、効率的に業務・業態を集めるなどではなく、全く違うものがそれによってより新しいものが生まれる、そのような仕掛けを作ることが大切と思います3、遊びと創造大友さんのお話を聞いていると、改めて音楽やファッションや映画から、いろんなものを取り入れようみたいな形ではなく、あたかも遊びのように興味のあること全てに突っ込んで行ってるのではないかとも感じます大阪大学の苧坂直行さんの言われているデフォルトモードネットワークのように、一つのことに集中している状態から、散歩に行ったり音楽を聞いたりと、違う活動をすることによって、実は脳が活性化し新しい考えが浮かぶことがある、とのお話も思い出しましたまた、かのアインシュタインさんが"創造性とは、知性が楽しんでいる状態である"と言われたように、遊びとして様々なものに触れて、体験して、ワクワクすることによって、様々な異分子を楽しんで結合させるそこが出来る、そんなことも感じさせて頂きましたということで、一言で言うと越境を楽しむノベーションそんなことを感じました^ ^参考:NHK Eテレ東京 浦沢直樹の漫勉neo(20)大友克洋 2025/3/29 https://www.nhk.jp/p/manben/ts/7W327R2Y4N/blog/bl/poG6xnODjg/bp/pKVJ1AaOaK/2025-04-0624 min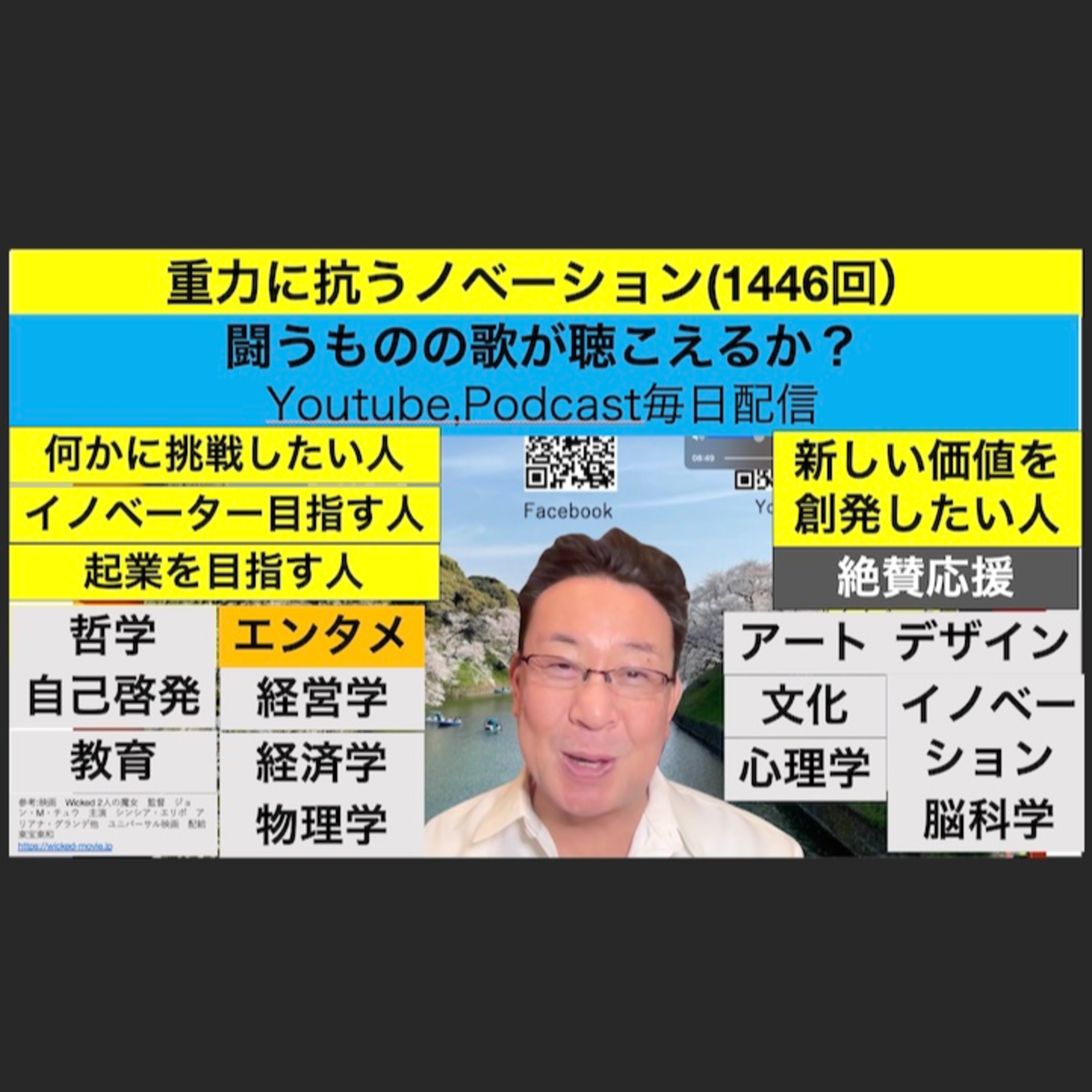 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"重力に抗うノベーション(1446回)アカデミー賞10部門ノミネートのミュージカル映画のウィキッドから、主演のアリアナ・グランデの言葉に震えました曰く"グリンダとエルファバのふたりがすばらしいのは、誰もが彼女たちのなかに小さな「自分の欠片」を見つけることができるところです。複雑な心情と人間らしさを、これでもかというくらい表現してくれます。美しく、新しい感性、愛情、自分の限界への挑戦、愛や意見がもつれたときの複雑さ、正しいことをしようとする勇気も描写されています。これらすべての根底にあるのは“愛”なんです"ここから私は思いました1、個性派「パッション」2、相容れない「仲間」との交流3、自分を超える「大義」あのアリアナ・グランデが、この役をやるために10年も前から志し、そしてクラシックやオペラ手法を改めて学び直したと言うことにも、それだけで涙してしまうしアカデミー賞、エミー賞の主演女優賞を総なめにしているシンシア・エルヴォの魂の演技と歌にも、号泣が止まらない、言葉が見つからないほど素晴らしい映画がウィキッドですがこれはイノベーター3つのフレームでも語りがいのある、イノベーターの物語だと思いました1、個性派「パッション」緑色で生まれて謎の力を持っている自分を持て余すエルファバ(シンシア)は、それをコンプレックスとしてずっと生きてきますが、それが実は自分の個性として、むしろ誰でもないものとして、気づき、そして成長していく、そんな個性派パッションの発現を観させて頂いた気がしました自分も、じっと席に座ってられなかったり、四角のマスの中に字を入れたり絵を描くことができずにどうしてもはみ出してしまうとか、自分が人と違っていて悩んだこと、コンプレックスがあると思い煩っていたことなどを、思い出しました。でもそれは、実はパッションの源の中でも、ものすごく強いパッションになる可能性を秘めていて、そのコンプレックスが、とてつもなく成長する原動力(成長パッション)になったり、他の人とは違うからいいのだと言う(個性派パッション)になったりすることを、改めて思いましたこれまで出会ったイノベーターの中にも、自らが他の人よりも劣っていると思い悩んでた人の話もたくさん伺いました。でもそれは、実はイノベーターになるとても近いところにいる、個性派パッションの源なのだと勇気づけられことを思い出しました2、相容れない「仲間」との交流その自分自身のパッションの源に目覚める一つの重要な鍵として、「仲間」がいるということも、エルファバとグリンダの関係を観させて頂き、改めて思いました全く育った環境も性格も価値観も正反対な2人が、出会うことによって、ものすごく反発し合う2人だけれども、あるきっかけで、お互いの真の姿は自分の中にあるものと共感できることができると分かり合えていく姿はヘーゲルのアウフヘーベンのように、反発し合う二つの対立するものが、共に赦すことで、第三の道を見つけることができるような、そしてだからこそ、強固な「仲間」となれるような、瞬間を観させて頂いた気がしました3、自分を超える「大義」そしてその先に、これまでは自分たちのために、魔法を使えるように考えていたのが、もっと自分を超えたもののために、自分の力を使うことに目覚めていく様子はイノベーターが、自らのパッションに基づいて自分のためにやってたことが、仲間と共に過ごすうちに、たくさんの人たちを喜ばす「大義」へ興味が移っていくように自分を超える「大義」を目指すように育っていく、そんな成長物語であり、そして、イノベーターの物語だなあと、つくづく思いました最後の曲がめちゃくちゃ好きな曲なのですが"Defying Gravity"重力に逆らって、と言うような意味ですが、自分の中の殻に閉じこもる重力、挑戦しないで失敗する重力、世の中の問いや違和感に対して違を唱えない重力、様々な重力から解放されていくのだと言う、決意の曲で、号泣が止まらなくはりましたということでコンプレックスを跳ね除ける「個性パッション」から始まり、全く異なる「仲間」との出会いから、様々な重力に屈服せず、誰かのために世の中を変えていく「大義」を、目指していくイノベーター物語と、私からは見えました一言で言うと重力に抗うノベーションそんなことを思いました^ ^参考:映画 Wicked 2人の魔女 監督 ジョン・M・チュウ 主演 シンシア・エリボ アリアナ・グランデ他 ユニバーサル映画 配給 東宝東和https://wicked-movie.jp2025-04-0530 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"重力に抗うノベーション(1446回)アカデミー賞10部門ノミネートのミュージカル映画のウィキッドから、主演のアリアナ・グランデの言葉に震えました曰く"グリンダとエルファバのふたりがすばらしいのは、誰もが彼女たちのなかに小さな「自分の欠片」を見つけることができるところです。複雑な心情と人間らしさを、これでもかというくらい表現してくれます。美しく、新しい感性、愛情、自分の限界への挑戦、愛や意見がもつれたときの複雑さ、正しいことをしようとする勇気も描写されています。これらすべての根底にあるのは“愛”なんです"ここから私は思いました1、個性派「パッション」2、相容れない「仲間」との交流3、自分を超える「大義」あのアリアナ・グランデが、この役をやるために10年も前から志し、そしてクラシックやオペラ手法を改めて学び直したと言うことにも、それだけで涙してしまうしアカデミー賞、エミー賞の主演女優賞を総なめにしているシンシア・エルヴォの魂の演技と歌にも、号泣が止まらない、言葉が見つからないほど素晴らしい映画がウィキッドですがこれはイノベーター3つのフレームでも語りがいのある、イノベーターの物語だと思いました1、個性派「パッション」緑色で生まれて謎の力を持っている自分を持て余すエルファバ(シンシア)は、それをコンプレックスとしてずっと生きてきますが、それが実は自分の個性として、むしろ誰でもないものとして、気づき、そして成長していく、そんな個性派パッションの発現を観させて頂いた気がしました自分も、じっと席に座ってられなかったり、四角のマスの中に字を入れたり絵を描くことができずにどうしてもはみ出してしまうとか、自分が人と違っていて悩んだこと、コンプレックスがあると思い煩っていたことなどを、思い出しました。でもそれは、実はパッションの源の中でも、ものすごく強いパッションになる可能性を秘めていて、そのコンプレックスが、とてつもなく成長する原動力(成長パッション)になったり、他の人とは違うからいいのだと言う(個性派パッション)になったりすることを、改めて思いましたこれまで出会ったイノベーターの中にも、自らが他の人よりも劣っていると思い悩んでた人の話もたくさん伺いました。でもそれは、実はイノベーターになるとても近いところにいる、個性派パッションの源なのだと勇気づけられことを思い出しました2、相容れない「仲間」との交流その自分自身のパッションの源に目覚める一つの重要な鍵として、「仲間」がいるということも、エルファバとグリンダの関係を観させて頂き、改めて思いました全く育った環境も性格も価値観も正反対な2人が、出会うことによって、ものすごく反発し合う2人だけれども、あるきっかけで、お互いの真の姿は自分の中にあるものと共感できることができると分かり合えていく姿はヘーゲルのアウフヘーベンのように、反発し合う二つの対立するものが、共に赦すことで、第三の道を見つけることができるような、そしてだからこそ、強固な「仲間」となれるような、瞬間を観させて頂いた気がしました3、自分を超える「大義」そしてその先に、これまでは自分たちのために、魔法を使えるように考えていたのが、もっと自分を超えたもののために、自分の力を使うことに目覚めていく様子はイノベーターが、自らのパッションに基づいて自分のためにやってたことが、仲間と共に過ごすうちに、たくさんの人たちを喜ばす「大義」へ興味が移っていくように自分を超える「大義」を目指すように育っていく、そんな成長物語であり、そして、イノベーターの物語だなあと、つくづく思いました最後の曲がめちゃくちゃ好きな曲なのですが"Defying Gravity"重力に逆らって、と言うような意味ですが、自分の中の殻に閉じこもる重力、挑戦しないで失敗する重力、世の中の問いや違和感に対して違を唱えない重力、様々な重力から解放されていくのだと言う、決意の曲で、号泣が止まらなくはりましたということでコンプレックスを跳ね除ける「個性パッション」から始まり、全く異なる「仲間」との出会いから、様々な重力に屈服せず、誰かのために世の中を変えていく「大義」を、目指していくイノベーター物語と、私からは見えました一言で言うと重力に抗うノベーションそんなことを思いました^ ^参考:映画 Wicked 2人の魔女 監督 ジョン・M・チュウ 主演 シンシア・エリボ アリアナ・グランデ他 ユニバーサル映画 配給 東宝東和https://wicked-movie.jp2025-04-0530 min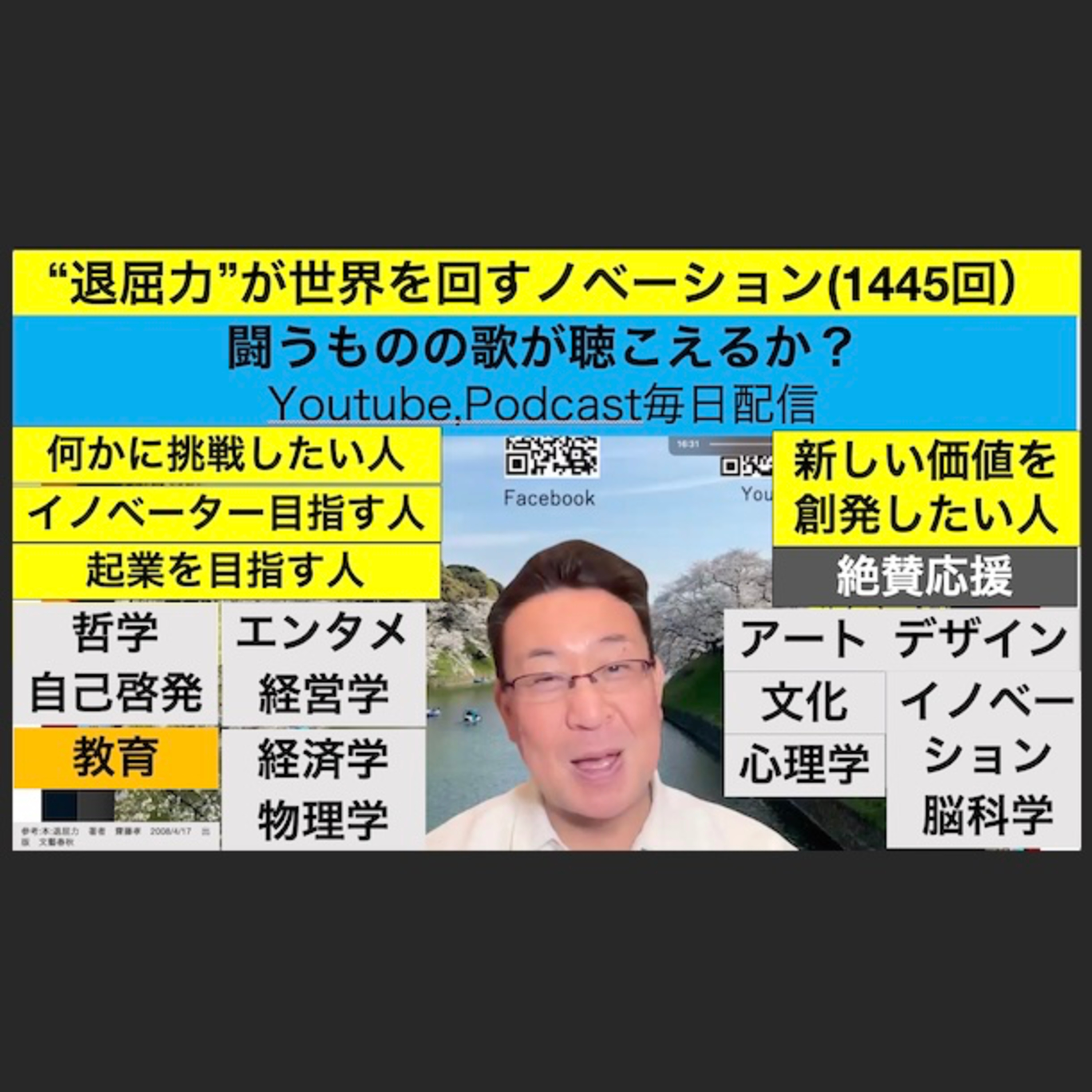 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"”退屈力”が世界を回すノベーション(1445回)齋藤孝さんの”退屈力”の考え方に目から鱗が落ちる思いでした曰く"私が強調したいのは、ある特定の型を身につけるような地道なトレーニングを、ひとつでもきっちり行ってきた人というのは、「退屈力」が備わってると言うことだ。退屈に耐えられる力という意味だけではない。退屈なことを繰り返すことの意味を知っているのだ。昔しっかり野球をやっていて、バットの素振りや1000本ノックの経験がある学生がいたとする。あるいは剣道をやっていて、竹刀の素振りの経験がある学生がいたとする。そうするとそういう学生に読書のことを教えるのは、経験のない学生に教えるより、比較的簡単である。それまで全く本を読んでこなかったとしても、反復練習するメンタリティが身についているからだ。それを思い出させて、要するにその時の心のあり方というのを、ここで応用すればいいんだよ。といえば、「そうか、もう一回素振りなんだ」とわかってくれる。"ここから私は思いました1、技能習得のパラドクス2、コンフォートゾーンを抜け出す体験 3、退屈力が世界を回す1、技能習得のパラドクス私は野球少年で、高校生の頃は、甲子園目指す!とか本気で言っていた熱い青春時代を過ごしていたのですが、今思い出すと毎日素振りやってました。ブンという音がいかに鋭く大きく鳴るかみたいなことや、ピッチャーが直球来た時、とか、カーブだ、とか、イメトレもしながらやっていて、その成果として、本当にヒット打てた時とか、めちゃくちゃ嬉しかったのを思い出しました。伊藤亜沙さんが言われている、技能習得のパラドックスの話が大好きなのですが、逆上がりや、自転車など、頭では出来っこないと思ってることが、体を動かして何度も失敗してるうちに、ある日突然、出来ちゃうようになるこらは、実は頭で考えてることを、身体が越えることがある、それを技能習得のパラドクスと呼ばれてるのかと私は思うのですが、そこには、斉藤孝さんの言われる、退屈力がとても重要な役割かと思いました何度も何度もゴールが見えない、理解できないけど、チャレンジし続けられる人には、きっと退屈力が備わっていて、いつかゴールを切る日が来る、そんなことを思いました2、コンフォートゾーンを抜け出す体験 アンダースンさんの「超一流になるには才能か努力か」から、超一流になる条件として、1最高の先生、2コンフォートゾーンを抜ける、3、自分を信じる、ということが大切という私の解釈ですがその中の、コンフォートゾーンを抜け出すためには、斉藤さんの言われる"退屈力'がとても大切だと感じました。それは、常にできないことを超えていかなければ、ゴールには辿り着けないからで、その見えないゴールをみながら、やり続ける力、すなわち退屈力があるからこそ、みえないゴールに辿り着けるのだろうなあと思いました3、退屈力が世界を回す太刀川さんの進化思考における、進化と適応、この両方とも世の中を回すためには必要なわけですが、この退屈力は、どちらにも必要なのですが、より適応の方面に必要な気がしますそれは、例えば、電車を時間通りに動かすとか、金融ネットワークを滞りなく動かすとか、実は地道な積み重ねの中で、キッチリカッチリできるようになってくるものだからこそ、それは外から見ると華々しくはないけれども、社会の大半はそういうことで動いていると思いますイノベーションというと、華々しく聞こえるけれども、進化型とは、一見逆の方向に見えてても、適応型に必要な退屈力が、実は世界を回している大切な機能だと思いましたそういう意味で一言で言うと”退屈力”が世界を回すノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本:退屈力 著者 齋藤孝 2008/4/17 出版 文藝春秋動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/QyguwdNehBg2025-04-0421 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"”退屈力”が世界を回すノベーション(1445回)齋藤孝さんの”退屈力”の考え方に目から鱗が落ちる思いでした曰く"私が強調したいのは、ある特定の型を身につけるような地道なトレーニングを、ひとつでもきっちり行ってきた人というのは、「退屈力」が備わってると言うことだ。退屈に耐えられる力という意味だけではない。退屈なことを繰り返すことの意味を知っているのだ。昔しっかり野球をやっていて、バットの素振りや1000本ノックの経験がある学生がいたとする。あるいは剣道をやっていて、竹刀の素振りの経験がある学生がいたとする。そうするとそういう学生に読書のことを教えるのは、経験のない学生に教えるより、比較的簡単である。それまで全く本を読んでこなかったとしても、反復練習するメンタリティが身についているからだ。それを思い出させて、要するにその時の心のあり方というのを、ここで応用すればいいんだよ。といえば、「そうか、もう一回素振りなんだ」とわかってくれる。"ここから私は思いました1、技能習得のパラドクス2、コンフォートゾーンを抜け出す体験 3、退屈力が世界を回す1、技能習得のパラドクス私は野球少年で、高校生の頃は、甲子園目指す!とか本気で言っていた熱い青春時代を過ごしていたのですが、今思い出すと毎日素振りやってました。ブンという音がいかに鋭く大きく鳴るかみたいなことや、ピッチャーが直球来た時、とか、カーブだ、とか、イメトレもしながらやっていて、その成果として、本当にヒット打てた時とか、めちゃくちゃ嬉しかったのを思い出しました。伊藤亜沙さんが言われている、技能習得のパラドックスの話が大好きなのですが、逆上がりや、自転車など、頭では出来っこないと思ってることが、体を動かして何度も失敗してるうちに、ある日突然、出来ちゃうようになるこらは、実は頭で考えてることを、身体が越えることがある、それを技能習得のパラドクスと呼ばれてるのかと私は思うのですが、そこには、斉藤孝さんの言われる、退屈力がとても重要な役割かと思いました何度も何度もゴールが見えない、理解できないけど、チャレンジし続けられる人には、きっと退屈力が備わっていて、いつかゴールを切る日が来る、そんなことを思いました2、コンフォートゾーンを抜け出す体験 アンダースンさんの「超一流になるには才能か努力か」から、超一流になる条件として、1最高の先生、2コンフォートゾーンを抜ける、3、自分を信じる、ということが大切という私の解釈ですがその中の、コンフォートゾーンを抜け出すためには、斉藤さんの言われる"退屈力'がとても大切だと感じました。それは、常にできないことを超えていかなければ、ゴールには辿り着けないからで、その見えないゴールをみながら、やり続ける力、すなわち退屈力があるからこそ、みえないゴールに辿り着けるのだろうなあと思いました3、退屈力が世界を回す太刀川さんの進化思考における、進化と適応、この両方とも世の中を回すためには必要なわけですが、この退屈力は、どちらにも必要なのですが、より適応の方面に必要な気がしますそれは、例えば、電車を時間通りに動かすとか、金融ネットワークを滞りなく動かすとか、実は地道な積み重ねの中で、キッチリカッチリできるようになってくるものだからこそ、それは外から見ると華々しくはないけれども、社会の大半はそういうことで動いていると思いますイノベーションというと、華々しく聞こえるけれども、進化型とは、一見逆の方向に見えてても、適応型に必要な退屈力が、実は世界を回している大切な機能だと思いましたそういう意味で一言で言うと”退屈力”が世界を回すノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本:退屈力 著者 齋藤孝 2008/4/17 出版 文藝春秋動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/QyguwdNehBg2025-04-0421 min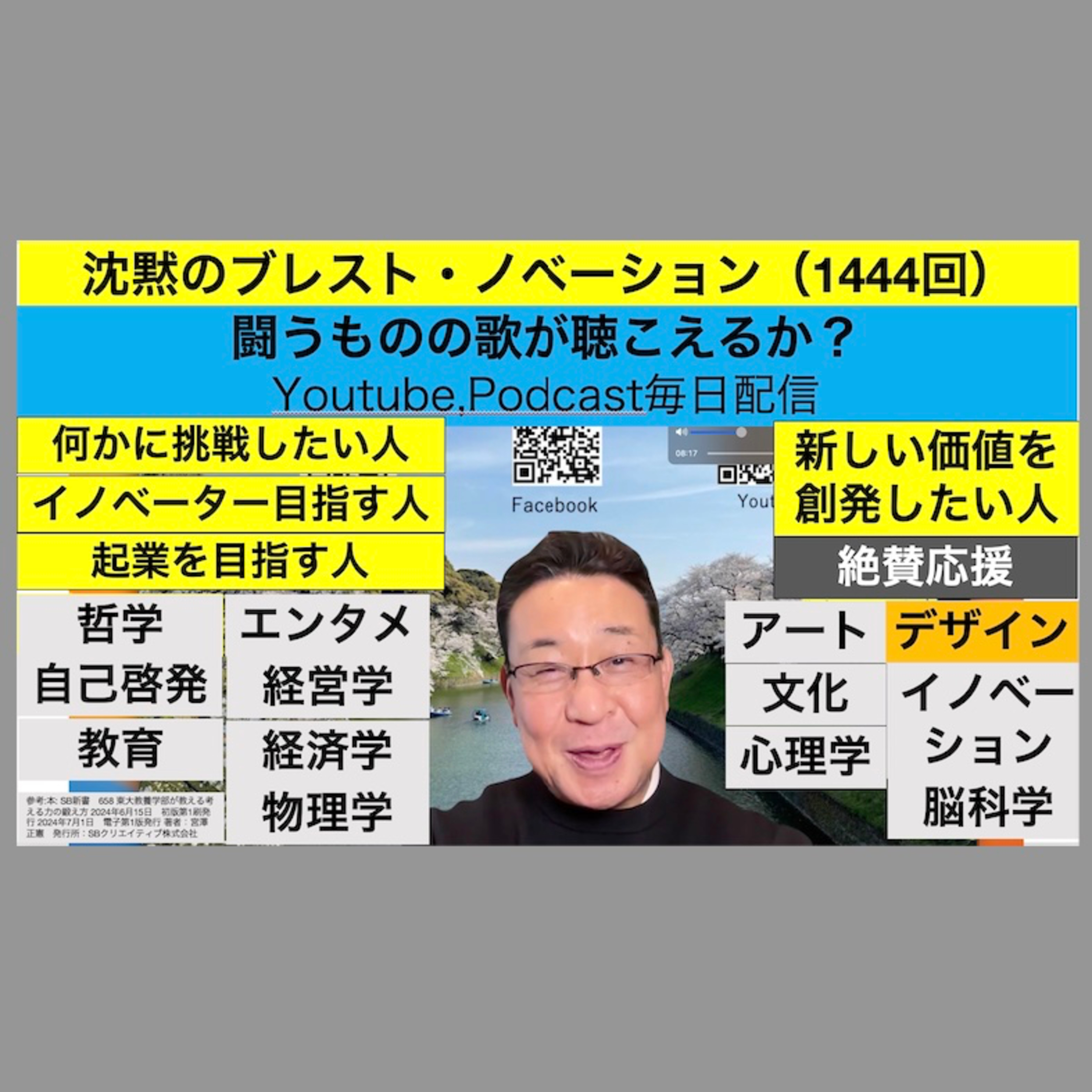 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"沈黙のブレスト・ノベーション(1444回)東京大学教養学部 教養教育高度化機構 特任教授 であり、(株)博報堂 執行役員の宮澤正憲さんから、「ブレインライティング」という強力な発想法を教えて頂きました曰く"1968年にドイツでホリゲルという形態分析法の専門家により開発された、伝統的な強制発想法です。・6人の参加者で6枚のシートを使う ・各自が各回3つずつのアイデアを2分以内に考え、用紙に記入し、隣に回す 「質」よりも「量」を重視して意見を出し合う手法で、議論せずにシートにアイデアを書き出すところが特徴です。全員が無言で集団思考を行うため「沈黙のブレスト」とも呼ばれています。"ここから私は思いました1、1人で考えることができる2、仲間の力を使うことができる3、質より量を実現できる1、1人で考えることができるみんなでアイディエーションやろうとなると、みんなで集まって、付箋を貼り出したり、ホワイトボードでみんなで、ああだこうだ、やり始めてしまうと、意見の強い人や、リーダー的な人が仕切ってしまうケースも多いかと思います。ブレストの強みとも弱みとも思うのは、どうしても声の強い人に引っ張られてしまって、本当は自分がこう思うんだけど、ってことを飲み込んじゃう人が出てくる、ってことな気がしますその点、この方法は、必ず一人一人が書かなくてはならないということが、凄く良いと思いました。プレゼン力は強くなっても、恥ずかしがり屋でも、実はめちゃくちゃ面白いアイディアを持ってることはたくさんあるので、そういう人も、安心してアイディアを出せるのが、本当に良いと思いました2、仲間の力を使うことができるさらに良いのは、前の人の書いたものが、その紙には書いてあるので、それを見ながらの発想もできるというところが、1人で考えながらにして、共同作業になっている、ということが、仕組みがされていて共同することによる、発想の重ねや、飛ばした発想への気づきなども、感じながら、そして自分で考えてアウトプットできる、というのは、秀逸な仕組みと感じました3、質より量を実現できるそういう意味で、1人でやりながら、共同作業の良さを取り入れられるのは、一人一人の意見を沢山収集できることにつながると思いましたアイデエーションでは、1人10個は付箋に書くこと、みたいにやることもありますが、そうすると、慣れている人は沢山書いて、慣れてない人は半ばお任せみたいになるケースもあると思います収集されたアイディアをもとに、さらに投票をすることによって、声の大きい人が誰かわからないアイディアそのものの価値をみんなで考えることができるので、とても平等なやり方だなあと思いましたそういう意味で、沈黙のブレストは、多様性を確保し、フェアネスを実現しながら、量を稼ぐことができる、と言う意味で、素晴らしいアイディエーションツールと思いました一言で言うと沈黙のブレスト・ノベーションそんなことを思いました^^参考:本: SB新書 658 東大教養学部が教える考える力の鍛え方 2024年6月15日 初版第1刷発行 2024年7月1日 電子第1版発行 著者:宮澤正憲 発行所:SBクリエイティブ株式会社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/pJUAmbIf2SA2025-04-0320 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"沈黙のブレスト・ノベーション(1444回)東京大学教養学部 教養教育高度化機構 特任教授 であり、(株)博報堂 執行役員の宮澤正憲さんから、「ブレインライティング」という強力な発想法を教えて頂きました曰く"1968年にドイツでホリゲルという形態分析法の専門家により開発された、伝統的な強制発想法です。・6人の参加者で6枚のシートを使う ・各自が各回3つずつのアイデアを2分以内に考え、用紙に記入し、隣に回す 「質」よりも「量」を重視して意見を出し合う手法で、議論せずにシートにアイデアを書き出すところが特徴です。全員が無言で集団思考を行うため「沈黙のブレスト」とも呼ばれています。"ここから私は思いました1、1人で考えることができる2、仲間の力を使うことができる3、質より量を実現できる1、1人で考えることができるみんなでアイディエーションやろうとなると、みんなで集まって、付箋を貼り出したり、ホワイトボードでみんなで、ああだこうだ、やり始めてしまうと、意見の強い人や、リーダー的な人が仕切ってしまうケースも多いかと思います。ブレストの強みとも弱みとも思うのは、どうしても声の強い人に引っ張られてしまって、本当は自分がこう思うんだけど、ってことを飲み込んじゃう人が出てくる、ってことな気がしますその点、この方法は、必ず一人一人が書かなくてはならないということが、凄く良いと思いました。プレゼン力は強くなっても、恥ずかしがり屋でも、実はめちゃくちゃ面白いアイディアを持ってることはたくさんあるので、そういう人も、安心してアイディアを出せるのが、本当に良いと思いました2、仲間の力を使うことができるさらに良いのは、前の人の書いたものが、その紙には書いてあるので、それを見ながらの発想もできるというところが、1人で考えながらにして、共同作業になっている、ということが、仕組みがされていて共同することによる、発想の重ねや、飛ばした発想への気づきなども、感じながら、そして自分で考えてアウトプットできる、というのは、秀逸な仕組みと感じました3、質より量を実現できるそういう意味で、1人でやりながら、共同作業の良さを取り入れられるのは、一人一人の意見を沢山収集できることにつながると思いましたアイデエーションでは、1人10個は付箋に書くこと、みたいにやることもありますが、そうすると、慣れている人は沢山書いて、慣れてない人は半ばお任せみたいになるケースもあると思います収集されたアイディアをもとに、さらに投票をすることによって、声の大きい人が誰かわからないアイディアそのものの価値をみんなで考えることができるので、とても平等なやり方だなあと思いましたそういう意味で、沈黙のブレストは、多様性を確保し、フェアネスを実現しながら、量を稼ぐことができる、と言う意味で、素晴らしいアイディエーションツールと思いました一言で言うと沈黙のブレスト・ノベーションそんなことを思いました^^参考:本: SB新書 658 東大教養学部が教える考える力の鍛え方 2024年6月15日 初版第1刷発行 2024年7月1日 電子第1版発行 著者:宮澤正憲 発行所:SBクリエイティブ株式会社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/pJUAmbIf2SA2025-04-0320 min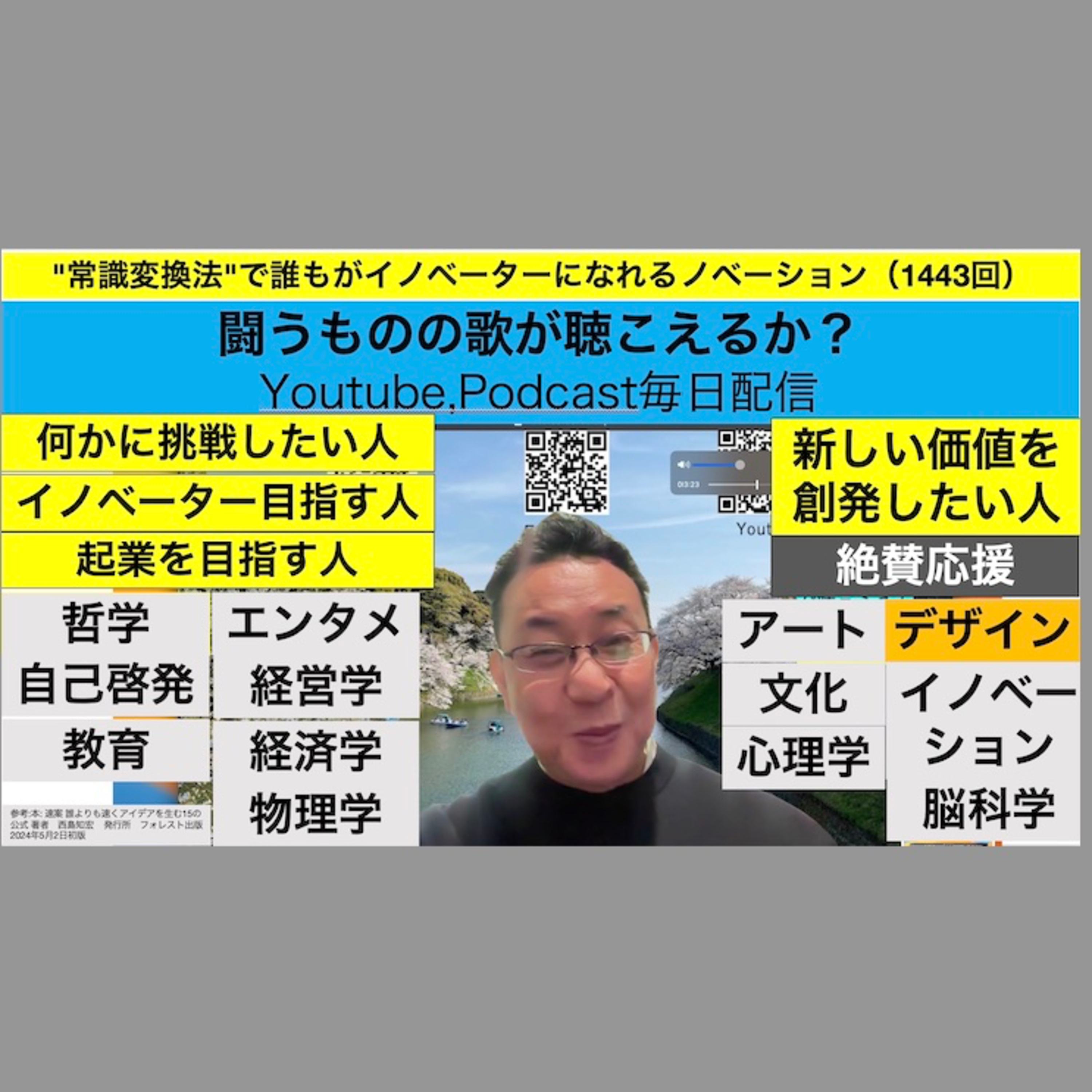 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""常識変換法"で誰もがイノベーターになれるノベーション(1443回)クリエイティブ・ディレクターの西島知宏さんの、"常識変換法"に感動しました曰く"公式 「常識」を書き出す→「常識」を「非常識」に変える""ここで重要なのは、いきなり「新しいアイデアを考えろ」「アイデアをたくさん出せ」と言われると困惑してしまうところを「課題となっているものの常識を書き出し、それを非常識へと変えるプロセス」を経ることで、アイデアが出しやすくなるということをわかってほしかったのです。アイデアが必要な課題に対して、従来の常識を書き出すだけなら誰にでもできますよね。""この世にあふれている、もっともらしく聞こえるアイデアに関するアドバイスが参考にならない理由、それは「実践しにくいから」なのです。 "ここから私はこのやり方の凄さをこう思いました1、常識から始めることができる2、常識を見ながらなら、非常識がわかる3、そこからアイディエーションで誰もが飛べるコロンブスの卵じゃないですけど、答えを知ってしまえば、なんてことはないのが、イノベーティブな考えの特徴でもあるので、まさに、常識変換法は、その差異たるものだと思いました1、常識から始めることができる西嶋さんもおっしゃってる通り、いきなり常識を壊せと言われても、それはわかってるけど、なかなか既存の常識から抜け出すことができない、というのが、いちばんの悩みかと思います。それをこの方法は、誰もができるところから始められるすごいパワーだと思いました2、常識を見ながらなら、非常識がわかるさらには、常識を書き出すからこそ、それの逆の言葉を書くだけで、非常識がわかる、というところも、めちゃくちゃ素晴らしいと思いました。そもそものなにが非常識なのかもわからないのが常識なので、この簡単な方法で、誰もが非常識に到達するできるというのも本当に素晴らしいと思います。3、そこからアイディエーションで誰もが飛べるそして、ここから、その非常識を見ながら、アイデエーションをすることで、まさに常識にとらわれないアイディアが、自ずと出てくるという構造をとることができる。これこそ、真のアイデエーションだなあとつくづく思いました。この凄いツールのことを思って、さらにここからイノベーションツールの大切なことについて思いました1、最高の先生にに学ぶ大切さ2、だれでもできるから共同パワー炸裂3、常識は誰でも壊せる自信となる1、最高の先生にに学ぶ大切さアンダースンさんの「超一流になるためには才能か努力か」の本にあるように、1、最高の先生に習う(2、コンフォートゾーンを抜け出せ、3、自分に自信を持て)という大切さが、今回改めて思いました。野球を習うなら、イチローに習え、ということなのですが、その世界の再興到達点に達した人に学ぶことで、そこまでの最短ルートを教えてもらうことができる、まさにその通りだなあと思いました2、だれでもできるから共同パワー炸裂様々なツールがありますが、何の知識がなくとも、論理的能力が高くなくても、誰もが簡単にできるもので、本当に強力なものはなかなかないなあと思いますその意味でも、斯のツールのように、誰でもできるところから始められるために、だからこそ、さまざまな多様性の考えを爆発させることができるのだなあと、改めて思いました3、常識は誰でも壊せる自信となるこのようなツールで、一度でも、常識を壊すアイディアが出せた経験を積むと、自分にも常識を超えた考え方をすることができる、イノベーターには、誰でもなれる、そんなことを実感してもらえて、それからの生き方も変わっていけるのではないか、そんなことまで思いましたということで一言で言えば"常識変換法"で誰もがイノベーターになれるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 速案 誰よりも速くアイデアを生む15の公式 著者 西島知宏 発行所 フォレスト出版 2024年5月2日初版動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/tw9NX6l-NHY2025-04-0214 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""常識変換法"で誰もがイノベーターになれるノベーション(1443回)クリエイティブ・ディレクターの西島知宏さんの、"常識変換法"に感動しました曰く"公式 「常識」を書き出す→「常識」を「非常識」に変える""ここで重要なのは、いきなり「新しいアイデアを考えろ」「アイデアをたくさん出せ」と言われると困惑してしまうところを「課題となっているものの常識を書き出し、それを非常識へと変えるプロセス」を経ることで、アイデアが出しやすくなるということをわかってほしかったのです。アイデアが必要な課題に対して、従来の常識を書き出すだけなら誰にでもできますよね。""この世にあふれている、もっともらしく聞こえるアイデアに関するアドバイスが参考にならない理由、それは「実践しにくいから」なのです。 "ここから私はこのやり方の凄さをこう思いました1、常識から始めることができる2、常識を見ながらなら、非常識がわかる3、そこからアイディエーションで誰もが飛べるコロンブスの卵じゃないですけど、答えを知ってしまえば、なんてことはないのが、イノベーティブな考えの特徴でもあるので、まさに、常識変換法は、その差異たるものだと思いました1、常識から始めることができる西嶋さんもおっしゃってる通り、いきなり常識を壊せと言われても、それはわかってるけど、なかなか既存の常識から抜け出すことができない、というのが、いちばんの悩みかと思います。それをこの方法は、誰もができるところから始められるすごいパワーだと思いました2、常識を見ながらなら、非常識がわかるさらには、常識を書き出すからこそ、それの逆の言葉を書くだけで、非常識がわかる、というところも、めちゃくちゃ素晴らしいと思いました。そもそものなにが非常識なのかもわからないのが常識なので、この簡単な方法で、誰もが非常識に到達するできるというのも本当に素晴らしいと思います。3、そこからアイディエーションで誰もが飛べるそして、ここから、その非常識を見ながら、アイデエーションをすることで、まさに常識にとらわれないアイディアが、自ずと出てくるという構造をとることができる。これこそ、真のアイデエーションだなあとつくづく思いました。この凄いツールのことを思って、さらにここからイノベーションツールの大切なことについて思いました1、最高の先生にに学ぶ大切さ2、だれでもできるから共同パワー炸裂3、常識は誰でも壊せる自信となる1、最高の先生にに学ぶ大切さアンダースンさんの「超一流になるためには才能か努力か」の本にあるように、1、最高の先生に習う(2、コンフォートゾーンを抜け出せ、3、自分に自信を持て)という大切さが、今回改めて思いました。野球を習うなら、イチローに習え、ということなのですが、その世界の再興到達点に達した人に学ぶことで、そこまでの最短ルートを教えてもらうことができる、まさにその通りだなあと思いました2、だれでもできるから共同パワー炸裂様々なツールがありますが、何の知識がなくとも、論理的能力が高くなくても、誰もが簡単にできるもので、本当に強力なものはなかなかないなあと思いますその意味でも、斯のツールのように、誰でもできるところから始められるために、だからこそ、さまざまな多様性の考えを爆発させることができるのだなあと、改めて思いました3、常識は誰でも壊せる自信となるこのようなツールで、一度でも、常識を壊すアイディアが出せた経験を積むと、自分にも常識を超えた考え方をすることができる、イノベーターには、誰でもなれる、そんなことを実感してもらえて、それからの生き方も変わっていけるのではないか、そんなことまで思いましたということで一言で言えば"常識変換法"で誰もがイノベーターになれるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 速案 誰よりも速くアイデアを生む15の公式 著者 西島知宏 発行所 フォレスト出版 2024年5月2日初版動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/tw9NX6l-NHY2025-04-0214 min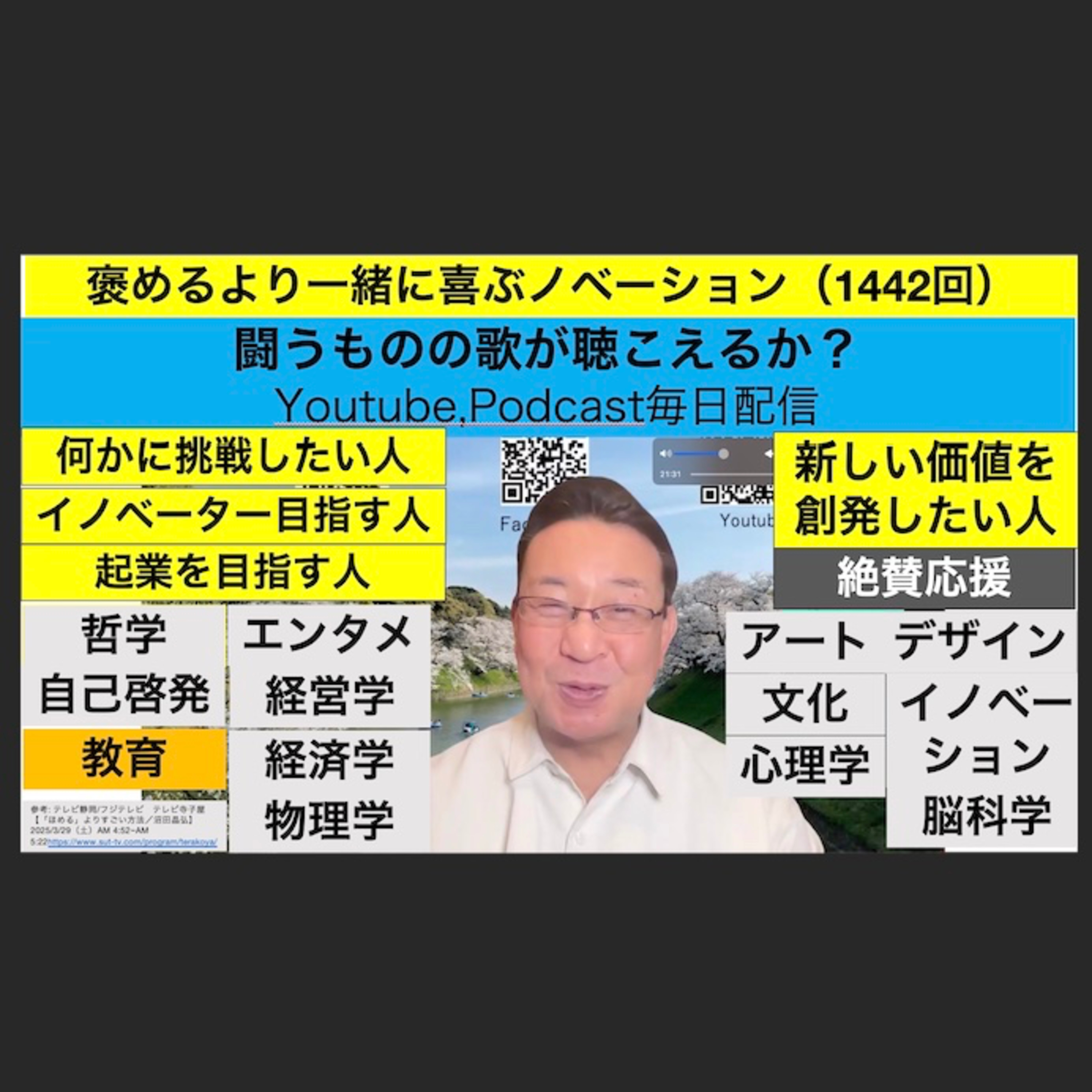 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"褒めるより一緒に喜ぶノベーション(1442回)東京学芸大学附属世田谷小学校 教諭の沼田晶弘さんの、"褒めるよりすごい方法"、に感動しました曰く"褒めるよりすごい方法、喜ぶです。はいこれ、「親が喜ぶ。」漢字テストで満点とってきた時、「すごいじゃな〜い」って褒めるより効果的なのは何かっつったらお母さんが「やった〜!」(ガッツポーズ)「超嬉しんですけどって。」これです。親が喜んでるのが1番なんです。"ここから私は思いました1、インポスター症候群への誘い2、誰かに価値を提供する原始体験3、親を超えて誰かを喜ばせたいへ1、インポスター症候群への誘いこれはとても目から鱗が落ちる話でした。お話の中でもありましたが、日本人は褒められると、「いやいやそんな私なんか」と言ってしまいがちだなあと。それはもしかしたら、インポスター症候群(1978年心理学者のポーリン・R・クランス、スザンヌ・A・アイムスによる)に陥りがちな、謙遜し過ぎて、自分の明らかな成果を、自信を持って次への挑戦の糧にできなくなってしまう、ということにもつながってるかもなと思いました。2、誰かに価値を提供する原始体験確かに親がガッツポーズで喜んでくれたら、下手に褒められるより、子供はめちゃくちゃ嬉しいと思うし、次もまた頑張ろうと思うなあと。これは、もしかすると、誰かを喜ばせることは、とても気持ちがいいことだという原始体験に繋がることにもなるかもとも思いました子供にとっては、特に小さいうちは、親が自分とは違う存在としての、社会との接点の最初の誰か、ということを考えると、自分が頑張る→誰かが喜ぶ、という何らかの価値を自分が生み出して、誰かが喜ぶと、自分が嬉しいという、この体験は、新しい価値を生み出していく人になるための、ファーストステップにもなる、そんなことも思いました3、親を超えて誰かを喜ばせたいへこれが発展していくと、成長していくにつれて、社会の仲間が増えていって、自分が頑張った→その仲間を喜ぶ、という事が快感になるような、クリエイティブな人に育っていくのかもしれないなとそれはまるで、イノベーター3つのフレームにおける、パッション→仲間→大義における、自らのパッションから、仲間と共に、たくさんの人が喜ぶ大義を作りたくなる、イノベーターそのものになっていく教育かもしれないそんなことまで思いました一言で言うと子供が何か素敵なことをしたら、褒めるよりも、とにかく一緒に喜ぶ褒めるよりも一緒に喜ぶノベーションそんなことを思いました^ ^参考: テレビ静岡/フジテレビ テレビ寺子屋【「ほめる」よりすごい方法/沼田晶弘】2025/3/29(土)AM 4:52~AM 5:22https://www.sut-tv.com/program/terakoya/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/ngqAZcYqqq02025-04-0116 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"褒めるより一緒に喜ぶノベーション(1442回)東京学芸大学附属世田谷小学校 教諭の沼田晶弘さんの、"褒めるよりすごい方法"、に感動しました曰く"褒めるよりすごい方法、喜ぶです。はいこれ、「親が喜ぶ。」漢字テストで満点とってきた時、「すごいじゃな〜い」って褒めるより効果的なのは何かっつったらお母さんが「やった〜!」(ガッツポーズ)「超嬉しんですけどって。」これです。親が喜んでるのが1番なんです。"ここから私は思いました1、インポスター症候群への誘い2、誰かに価値を提供する原始体験3、親を超えて誰かを喜ばせたいへ1、インポスター症候群への誘いこれはとても目から鱗が落ちる話でした。お話の中でもありましたが、日本人は褒められると、「いやいやそんな私なんか」と言ってしまいがちだなあと。それはもしかしたら、インポスター症候群(1978年心理学者のポーリン・R・クランス、スザンヌ・A・アイムスによる)に陥りがちな、謙遜し過ぎて、自分の明らかな成果を、自信を持って次への挑戦の糧にできなくなってしまう、ということにもつながってるかもなと思いました。2、誰かに価値を提供する原始体験確かに親がガッツポーズで喜んでくれたら、下手に褒められるより、子供はめちゃくちゃ嬉しいと思うし、次もまた頑張ろうと思うなあと。これは、もしかすると、誰かを喜ばせることは、とても気持ちがいいことだという原始体験に繋がることにもなるかもとも思いました子供にとっては、特に小さいうちは、親が自分とは違う存在としての、社会との接点の最初の誰か、ということを考えると、自分が頑張る→誰かが喜ぶ、という何らかの価値を自分が生み出して、誰かが喜ぶと、自分が嬉しいという、この体験は、新しい価値を生み出していく人になるための、ファーストステップにもなる、そんなことも思いました3、親を超えて誰かを喜ばせたいへこれが発展していくと、成長していくにつれて、社会の仲間が増えていって、自分が頑張った→その仲間を喜ぶ、という事が快感になるような、クリエイティブな人に育っていくのかもしれないなとそれはまるで、イノベーター3つのフレームにおける、パッション→仲間→大義における、自らのパッションから、仲間と共に、たくさんの人が喜ぶ大義を作りたくなる、イノベーターそのものになっていく教育かもしれないそんなことまで思いました一言で言うと子供が何か素敵なことをしたら、褒めるよりも、とにかく一緒に喜ぶ褒めるよりも一緒に喜ぶノベーションそんなことを思いました^ ^参考: テレビ静岡/フジテレビ テレビ寺子屋【「ほめる」よりすごい方法/沼田晶弘】2025/3/29(土)AM 4:52~AM 5:22https://www.sut-tv.com/program/terakoya/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/ngqAZcYqqq02025-04-0116 min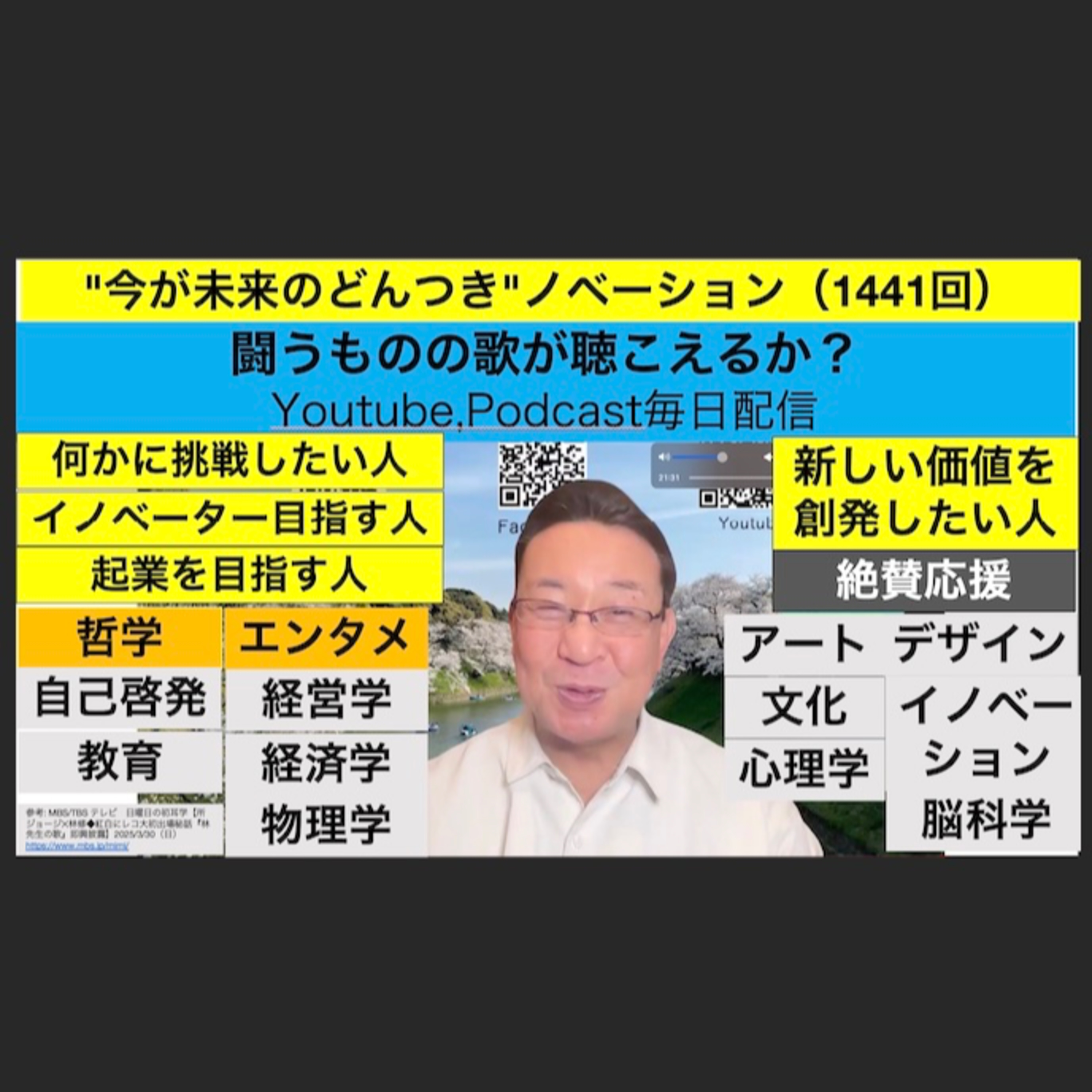 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""今が未来のどんつき"ノベーション(1441回)司会や音楽や世田谷ベースの様々なものづくり活動など、本当にマルチな人生を送られている所ジョージさんの言葉に、感動しました曰く"僕はずっとここまで、何かこう自分なりに満足したときに、これが目標だったって、そんときに思う何か失敗して、変なものできちゃっても、これが目標だったって、言い切って、正解にして、次に行く""未来がすごくなんか遠くとか近くにこう感じたり皆さんするじゃないですかいや、今が未来の"どんつき"だからっていうこの先のことなんかは、そうなってみなきゃわかんないわけで、想像したところでしょうがないだから、今を1番にしてれば、次のステップになるけど、今をなんか良くないよ、未来のこと考えようじゃ、何にも前に進まないだから、今が未来の"どんつき"だと思ってるんで"ここから私は思いました1、光る泥団子 →未来は今の中にしかない2、面白そうなこと全部やっちゃう→行動とゾーン3、結果を見て考える→リーンと失敗の捉え方1、光る泥団子 所さんのお話を聞いてて、以前お話しさせていただきました「子供の熱中は人生初の情熱の源ノベーション(1138回)」の光る泥団子作りを幼稚園でやられた加用先生のことを思い出しました加用先生の"その時がこの時として詰まっていた"そんな経験が子供には大切だというお話しと、とても似ているなあと思いました。子供にとってみれば、未来のことを憂うなんてことはなくて、目の前にあることで、楽しいと思うことに、ひたすらに突き進む、その感覚は、所さんが言われるところの、"今が未来のどんつき"ということにとてもシナジーがあるなあと思いますそれはあたかも、未来は今の中にしかないんだよ、ということを、子供のような心を持ちつづけている所さんから教えて頂いた気がしました2、面白そうなこと全部やっちゃうそんな所さんには、とてもやりたいことが多いのだろうなあと、いやむしろ、常日頃やりたいことが現れてくるのだろうなあと、そんなふうに思いました自分は、やりたい事がたくさん出てくるタイプですが、それでも、これは今はやらずにいつかね、みたいなこともたくさんある気がしますそこを、いや、今やろうよ、というのが所さんなのかなあとも感じました。それは、イノベーターには欠かすことのできない、行動力が半端ないのかもしれないなあと思いましたそしてその行動力があるからこそ、いわゆる作業興奮が起きて、そして、それが次々と面白くなって、やり続けてるうちに、挑戦軸とスキル軸が高まって、チクセントミハイさんのいうゾーンに、幾つも到達しているからこそ、マルチなタレントになられたのかなあとも思いました3、結果を見て考える"今が未来のどんつき''と考えることによって、今起きたことは失敗でも成功でもなくて、未来へ向かうステップに過ぎないと、考えられるのかなとも思いましたまたもしかしたら、それが思ってたものとちがうものができちゃった時の方が、また新しい気づきをもらって、その方がいいじゃんと思えるなあと、そうすると、どんどん自らでさえ思いつかなかったクリエイティブな方向へ向かう事ができるのかもしれないなあと、思いました光る泥団子をとにかく没頭して作り続ける子供達と、今あるもの、今できた事、今やったことを、どんどん面白がって肯定して、前に進む所さんとを考えるにつけ大人になっていろんなことを考え過ぎてしまう自分に、今が未来のどんつき、かなんだから、今をもっと大切にするだけでいいんだよと、軽く言葉をかけていただいたような、心が軽くなった気がしました一言で言えば今が未来のどんつきノベーションそんなことを思いました^ ^参考: MBS/TBS テレビ 日曜日の初耳学【所ジョージ✕林修◆紅白にレコ大初出場秘話『林先生の歌』即興披露】2025/3/30(日)https://www.mbs.jp/mimi/2025-03-3122 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""今が未来のどんつき"ノベーション(1441回)司会や音楽や世田谷ベースの様々なものづくり活動など、本当にマルチな人生を送られている所ジョージさんの言葉に、感動しました曰く"僕はずっとここまで、何かこう自分なりに満足したときに、これが目標だったって、そんときに思う何か失敗して、変なものできちゃっても、これが目標だったって、言い切って、正解にして、次に行く""未来がすごくなんか遠くとか近くにこう感じたり皆さんするじゃないですかいや、今が未来の"どんつき"だからっていうこの先のことなんかは、そうなってみなきゃわかんないわけで、想像したところでしょうがないだから、今を1番にしてれば、次のステップになるけど、今をなんか良くないよ、未来のこと考えようじゃ、何にも前に進まないだから、今が未来の"どんつき"だと思ってるんで"ここから私は思いました1、光る泥団子 →未来は今の中にしかない2、面白そうなこと全部やっちゃう→行動とゾーン3、結果を見て考える→リーンと失敗の捉え方1、光る泥団子 所さんのお話を聞いてて、以前お話しさせていただきました「子供の熱中は人生初の情熱の源ノベーション(1138回)」の光る泥団子作りを幼稚園でやられた加用先生のことを思い出しました加用先生の"その時がこの時として詰まっていた"そんな経験が子供には大切だというお話しと、とても似ているなあと思いました。子供にとってみれば、未来のことを憂うなんてことはなくて、目の前にあることで、楽しいと思うことに、ひたすらに突き進む、その感覚は、所さんが言われるところの、"今が未来のどんつき"ということにとてもシナジーがあるなあと思いますそれはあたかも、未来は今の中にしかないんだよ、ということを、子供のような心を持ちつづけている所さんから教えて頂いた気がしました2、面白そうなこと全部やっちゃうそんな所さんには、とてもやりたいことが多いのだろうなあと、いやむしろ、常日頃やりたいことが現れてくるのだろうなあと、そんなふうに思いました自分は、やりたい事がたくさん出てくるタイプですが、それでも、これは今はやらずにいつかね、みたいなこともたくさんある気がしますそこを、いや、今やろうよ、というのが所さんなのかなあとも感じました。それは、イノベーターには欠かすことのできない、行動力が半端ないのかもしれないなあと思いましたそしてその行動力があるからこそ、いわゆる作業興奮が起きて、そして、それが次々と面白くなって、やり続けてるうちに、挑戦軸とスキル軸が高まって、チクセントミハイさんのいうゾーンに、幾つも到達しているからこそ、マルチなタレントになられたのかなあとも思いました3、結果を見て考える"今が未来のどんつき''と考えることによって、今起きたことは失敗でも成功でもなくて、未来へ向かうステップに過ぎないと、考えられるのかなとも思いましたまたもしかしたら、それが思ってたものとちがうものができちゃった時の方が、また新しい気づきをもらって、その方がいいじゃんと思えるなあと、そうすると、どんどん自らでさえ思いつかなかったクリエイティブな方向へ向かう事ができるのかもしれないなあと、思いました光る泥団子をとにかく没頭して作り続ける子供達と、今あるもの、今できた事、今やったことを、どんどん面白がって肯定して、前に進む所さんとを考えるにつけ大人になっていろんなことを考え過ぎてしまう自分に、今が未来のどんつき、かなんだから、今をもっと大切にするだけでいいんだよと、軽く言葉をかけていただいたような、心が軽くなった気がしました一言で言えば今が未来のどんつきノベーションそんなことを思いました^ ^参考: MBS/TBS テレビ 日曜日の初耳学【所ジョージ✕林修◆紅白にレコ大初出場秘話『林先生の歌』即興披露】2025/3/30(日)https://www.mbs.jp/mimi/2025-03-3122 min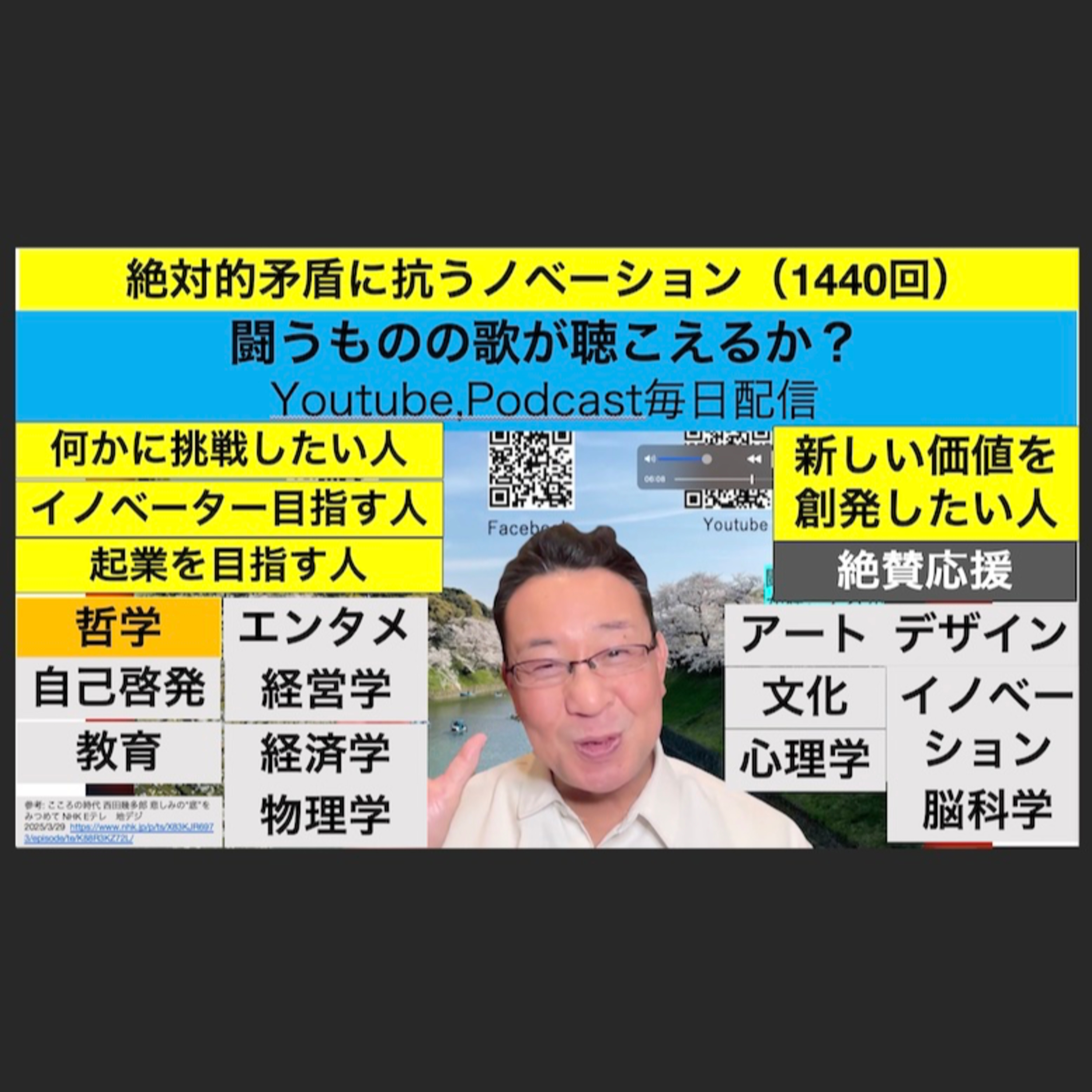 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"絶対的矛盾に抗うノベーション(1440回)日本の哲学者の草分けである西田幾多郎さんの"絶対矛盾的自己同一"に、目から鱗が落ちる思いでした曰く"矛盾的自己同一的現在として、自己自身を形成する世界は、多と一との矛盾的自己同一世界であり、かかる世界の個物として、何処までも自己自身を限定する我々は、無限なる欲求でなければならない。生への意志でなければならない。而して世界は我々を生むと共に、我々を殺すものでなければならない世界は無限なる圧力を以て我々に臨み来るものである、何処までも我々に迫り来るものである。我々は之と戦ふことによって生きるのである。(絶対矛盾的自己同一)"ここから私は思いました1、世界は矛盾が大前提2、生きることは抗うこと3、無から創り出すこと近代日本ではじめて哲学を体系だったものにされた西田幾多郎さんの、お話を能登の皆さんのお話と共にめちゃくちゃわかりやすく解説いただき、とても感動しました1、世界は矛盾が大前提"絶対矛盾的自己同一"という概念がどういうものなのかということが、全てではないのですが、世界は矛盾があることが大前提にあるということを教えて頂いてるのかなと思いました光があれば影があるし、生があれば死がある、そういう意味では、その相反する矛盾する事柄を全て含んでいることが大前提の環境に自分は生きてるんだと思うとなぜ自分だけがこんな目にとか、理不尽に悔し涙を流すとか、いろんなことが起きるけれども、そういうものがあることが大前提で、その裏のことも必ず起きると考えると、とても勇気をもらえる気がしました2、生きることは抗うことその中で、生きることと、死ぬこと、ということも、これも矛盾する大前提で存在しなければならないのだとすると、自分が生きていることということは、必ずしすることということと対になっていて当たり前なのだということが、理解できる気がしましただからこそ、自分が生きる意味は、自分は生まれてしまったものなので、その必ずくる裏の事柄、つまりは死に、抗うということが、生きるという意味の根本にあるのかもしれないと思いました。ある意味ただ生きるということ自体、それに抗うすごいことなのだと、そんなことも感じました3、無から創り出すことさらに世界の中にある無ということについても、その裏にある事柄としては、価値というものがあるのではないかと思いました。そしてそれを、無から価値にすることが、自分に与えられた生きる意味としてある気がしました先日もお話しした京大・ハーバード大学の広中教授がおっしゃるように、編み物をしてあげたこと、それがすでに創造的活動なのだと、私はそこから、誰もが価値を創る存在としているという意味で、誰もがイノベーターと、言いたいと思ってますイノベーター3つのフレームにおいて、自分の中に何かのパッションが芽生えて、そして誰か仲間と共に、誰かのために何かをする、それこそが、イノベーターであり、小さい価値を創るという、自分が生きる意味でもある気がしました世界は矛盾があるからこそ世界であって生まれた自分は生きることで死に抗い、無から価値を創ることで無に抗う、そんな存在なのかなと思いました一言でいうと絶対的矛盾に抗うノベーションそんなことを思いました^_^参考: こころの時代 西田幾多郎 悲しみの“底”をみつめて NHK Eテレ 地デジ 2025/3/29 https://www.nhk.jp/p/ts/X83KJR6973/episode/te/K88R3KZ72L/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/AQqjbE-G5YA2025-03-3016 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"絶対的矛盾に抗うノベーション(1440回)日本の哲学者の草分けである西田幾多郎さんの"絶対矛盾的自己同一"に、目から鱗が落ちる思いでした曰く"矛盾的自己同一的現在として、自己自身を形成する世界は、多と一との矛盾的自己同一世界であり、かかる世界の個物として、何処までも自己自身を限定する我々は、無限なる欲求でなければならない。生への意志でなければならない。而して世界は我々を生むと共に、我々を殺すものでなければならない世界は無限なる圧力を以て我々に臨み来るものである、何処までも我々に迫り来るものである。我々は之と戦ふことによって生きるのである。(絶対矛盾的自己同一)"ここから私は思いました1、世界は矛盾が大前提2、生きることは抗うこと3、無から創り出すこと近代日本ではじめて哲学を体系だったものにされた西田幾多郎さんの、お話を能登の皆さんのお話と共にめちゃくちゃわかりやすく解説いただき、とても感動しました1、世界は矛盾が大前提"絶対矛盾的自己同一"という概念がどういうものなのかということが、全てではないのですが、世界は矛盾があることが大前提にあるということを教えて頂いてるのかなと思いました光があれば影があるし、生があれば死がある、そういう意味では、その相反する矛盾する事柄を全て含んでいることが大前提の環境に自分は生きてるんだと思うとなぜ自分だけがこんな目にとか、理不尽に悔し涙を流すとか、いろんなことが起きるけれども、そういうものがあることが大前提で、その裏のことも必ず起きると考えると、とても勇気をもらえる気がしました2、生きることは抗うことその中で、生きることと、死ぬこと、ということも、これも矛盾する大前提で存在しなければならないのだとすると、自分が生きていることということは、必ずしすることということと対になっていて当たり前なのだということが、理解できる気がしましただからこそ、自分が生きる意味は、自分は生まれてしまったものなので、その必ずくる裏の事柄、つまりは死に、抗うということが、生きるという意味の根本にあるのかもしれないと思いました。ある意味ただ生きるということ自体、それに抗うすごいことなのだと、そんなことも感じました3、無から創り出すことさらに世界の中にある無ということについても、その裏にある事柄としては、価値というものがあるのではないかと思いました。そしてそれを、無から価値にすることが、自分に与えられた生きる意味としてある気がしました先日もお話しした京大・ハーバード大学の広中教授がおっしゃるように、編み物をしてあげたこと、それがすでに創造的活動なのだと、私はそこから、誰もが価値を創る存在としているという意味で、誰もがイノベーターと、言いたいと思ってますイノベーター3つのフレームにおいて、自分の中に何かのパッションが芽生えて、そして誰か仲間と共に、誰かのために何かをする、それこそが、イノベーターであり、小さい価値を創るという、自分が生きる意味でもある気がしました世界は矛盾があるからこそ世界であって生まれた自分は生きることで死に抗い、無から価値を創ることで無に抗う、そんな存在なのかなと思いました一言でいうと絶対的矛盾に抗うノベーションそんなことを思いました^_^参考: こころの時代 西田幾多郎 悲しみの“底”をみつめて NHK Eテレ 地デジ 2025/3/29 https://www.nhk.jp/p/ts/X83KJR6973/episode/te/K88R3KZ72L/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/AQqjbE-G5YA2025-03-3016 min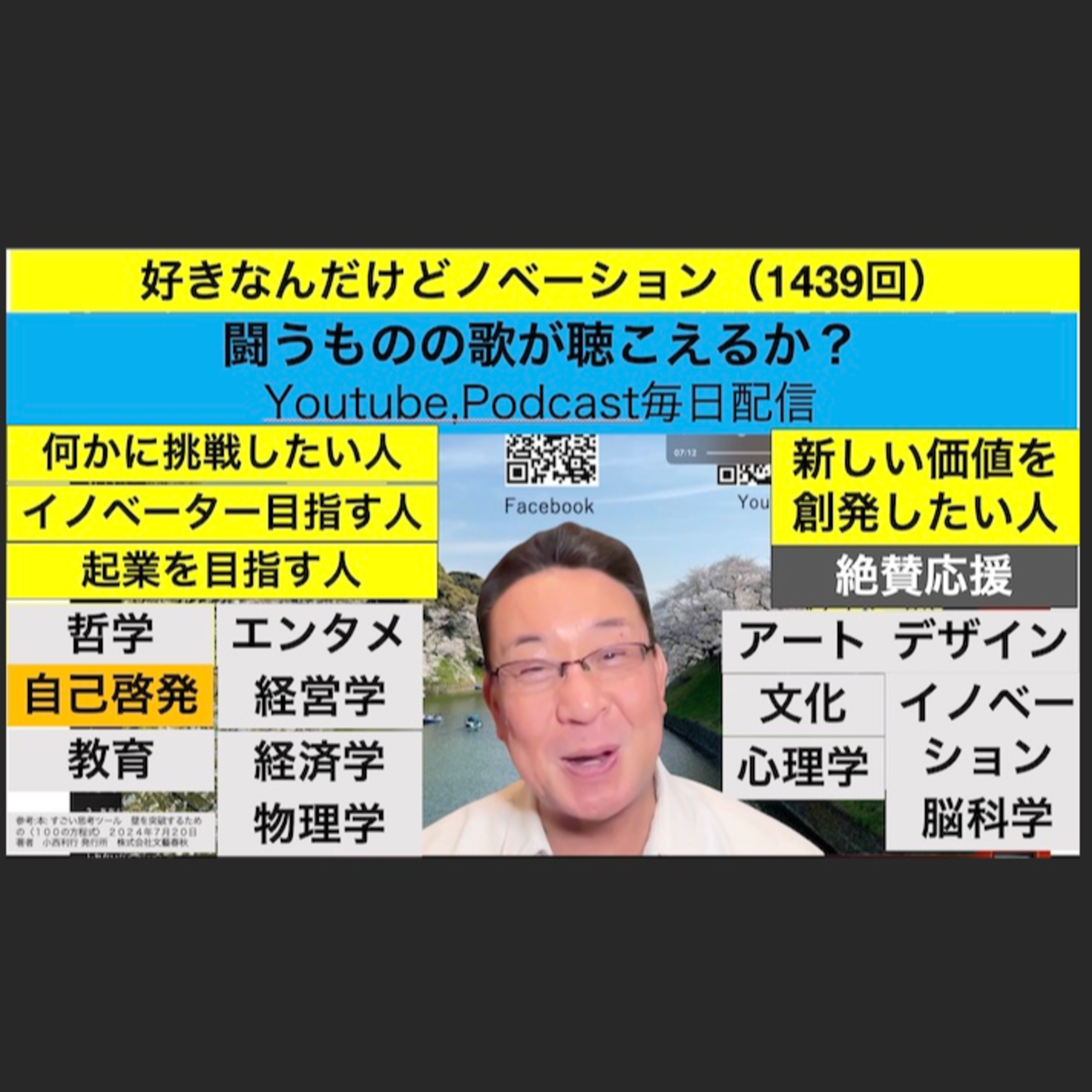 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"好きなんだけどノベーション(1439回)POOL inc.Founderの小西利行 さんから、どの道を進んだらきいのか迷う人に送る言葉に震えました"それは木﨑賢治さんの著書『プロデュースの基本』の中にある、「好きだな、いいな、と感じることは誰にでもあるはずです。ですが、自分がいいと感じたものをつくりたいと思う衝動があるかないか。そこが大切なポイントだと思います」という一節。""「好き!」ではなく「つくってみたい!」「分析しよう!」という気持ちが湧いてくるものこそ、その人がずっと興味を持ち続け、花を咲かせられるたった一つの場所だと思う。"ここから私は思いました1、好きなんだけどここがな〜→パッションの源×課題感2、ああもう私がやるしかないか〜→行動3、もうどうにもとまらない〜→フローいつもパッションの源が大事という話をしている私ですが、そこにステップがあるなあと改めて目から鱗が落ちた思いでした1、好きなんだけどここがな〜パッションの源の4章限より、大好き、利他、個性、成長、のどれでもいいので、当てはまるものがあれば、それを大切に追求してみる、とこれまでは言っておりましたがさらにそこに、でもそれがもっとこうだったらいいのに〜、とか、私だったらこうするのに〜みたいな、課題感を感じているものがあれば、実はそれがもっとも炸裂する可能性のあるパッションなのかもしれない、そんなことを思いました2、ああもう私がやるしかないか〜そして、ああもう誰もやってくれないじゃない、そしたら私がやるしかないか〜、という思いが炸裂してきたら、それはすなわち、パッションの源の導火線に火がついたことになるのかもしれないなと思いましたつまりこれが、思ってる状態から、行動に移してしまった状態への移行で、ここのフェーズが運命の分かれ道になるなあと、思いました。自分なんかができるのかと思いながらも、なんかやってしまった、そんなことがあったら確実にそれは、パッションの源の導火線だと、思いました3、もうどうにもとまらない〜そうなったら、チクセントミハイさんの、フローに突入することが容易になるので、挑戦軸とスキル軸がどんどん高まって、気がつけば、リンダ困っちゃうの、どうにも止まらないに、没入していくことになると思いましたそれこそ、運命の出会いではないですが、まさにその場所こそが自分のいる場所であり、花を咲かせることのできる場所なのだと思えるものになると思いましたということで、道を迷ったときにはパッションの源を確認し、その中でも違和感があって、自分がやることを止められないもの、それに突っ込んでいくと、道は自ずと見えてくるそれが好きなんだけどノベーションそんな話をしています^_^参考:本: すごい思考ツール 壁を突破するための〈100の方程式〉 2024年7月20日 著者 小西利行 発行所 株式会社文藝春秋2025-03-2916 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"好きなんだけどノベーション(1439回)POOL inc.Founderの小西利行 さんから、どの道を進んだらきいのか迷う人に送る言葉に震えました"それは木﨑賢治さんの著書『プロデュースの基本』の中にある、「好きだな、いいな、と感じることは誰にでもあるはずです。ですが、自分がいいと感じたものをつくりたいと思う衝動があるかないか。そこが大切なポイントだと思います」という一節。""「好き!」ではなく「つくってみたい!」「分析しよう!」という気持ちが湧いてくるものこそ、その人がずっと興味を持ち続け、花を咲かせられるたった一つの場所だと思う。"ここから私は思いました1、好きなんだけどここがな〜→パッションの源×課題感2、ああもう私がやるしかないか〜→行動3、もうどうにもとまらない〜→フローいつもパッションの源が大事という話をしている私ですが、そこにステップがあるなあと改めて目から鱗が落ちた思いでした1、好きなんだけどここがな〜パッションの源の4章限より、大好き、利他、個性、成長、のどれでもいいので、当てはまるものがあれば、それを大切に追求してみる、とこれまでは言っておりましたがさらにそこに、でもそれがもっとこうだったらいいのに〜、とか、私だったらこうするのに〜みたいな、課題感を感じているものがあれば、実はそれがもっとも炸裂する可能性のあるパッションなのかもしれない、そんなことを思いました2、ああもう私がやるしかないか〜そして、ああもう誰もやってくれないじゃない、そしたら私がやるしかないか〜、という思いが炸裂してきたら、それはすなわち、パッションの源の導火線に火がついたことになるのかもしれないなと思いましたつまりこれが、思ってる状態から、行動に移してしまった状態への移行で、ここのフェーズが運命の分かれ道になるなあと、思いました。自分なんかができるのかと思いながらも、なんかやってしまった、そんなことがあったら確実にそれは、パッションの源の導火線だと、思いました3、もうどうにもとまらない〜そうなったら、チクセントミハイさんの、フローに突入することが容易になるので、挑戦軸とスキル軸がどんどん高まって、気がつけば、リンダ困っちゃうの、どうにも止まらないに、没入していくことになると思いましたそれこそ、運命の出会いではないですが、まさにその場所こそが自分のいる場所であり、花を咲かせることのできる場所なのだと思えるものになると思いましたということで、道を迷ったときにはパッションの源を確認し、その中でも違和感があって、自分がやることを止められないもの、それに突っ込んでいくと、道は自ずと見えてくるそれが好きなんだけどノベーションそんな話をしています^_^参考:本: すごい思考ツール 壁を突破するための〈100の方程式〉 2024年7月20日 著者 小西利行 発行所 株式会社文藝春秋2025-03-2916 min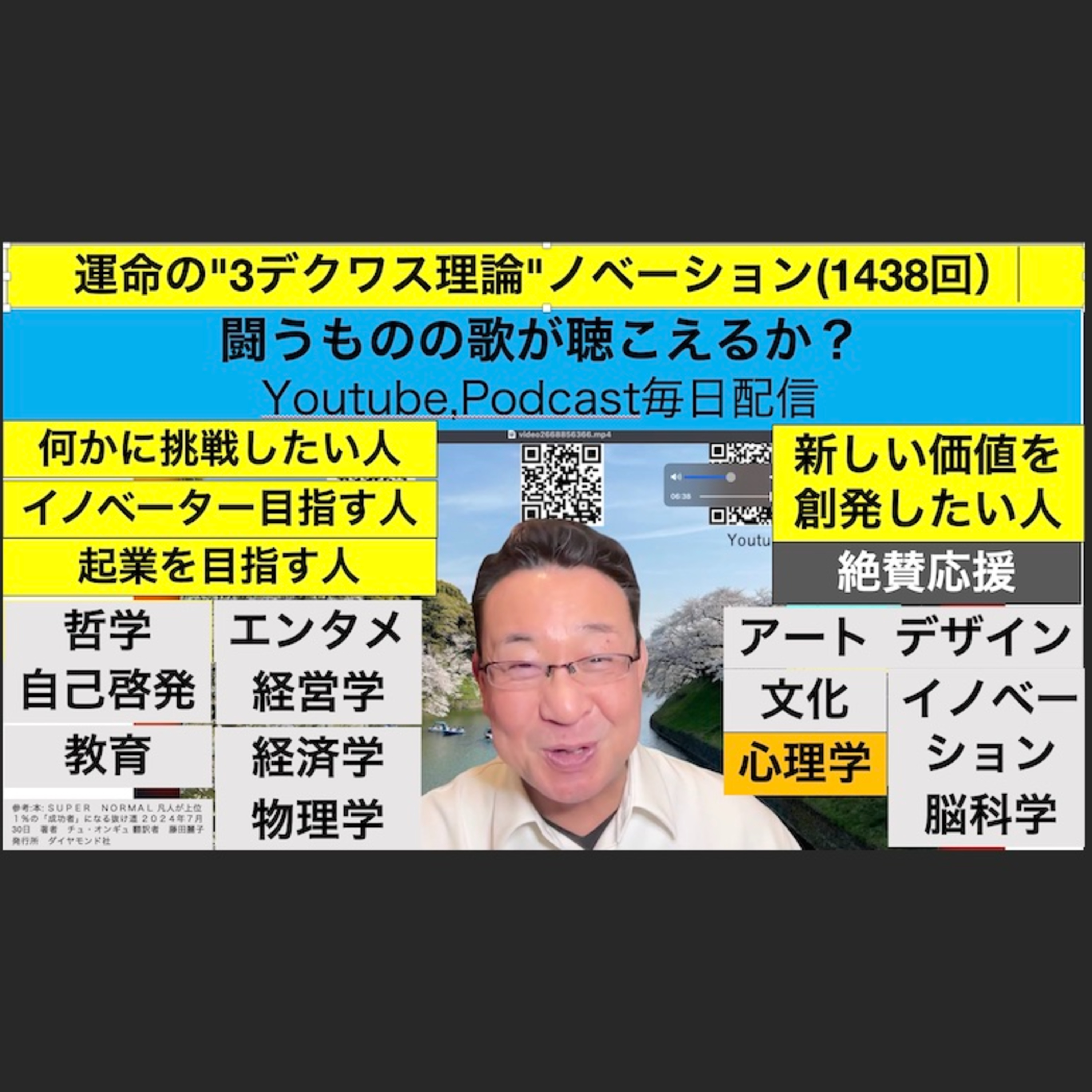 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"運命の"3デクワス理論"ノベーション(1438回)「伊右衛門」「モノより思い出。」等1000を超えるCM・広告作品を出されている、POOL inc.Founderの小西利行 さんの"3デクワス理論"に目から鱗が落ちたようでした曰く"この理論をつくったのは、あるゲーム会社へのプレゼンで電通の吉田健太郎さんから聞いた、「実は、商品を“買わない理由”は平均2.6個で、これを“買う理由”が上回らなければ購入されない」という調査結果がきっかけだった。これは面白い! と僕は思った。つまり3回以上「買う理由」に出会えば「買う」わけだ。しかもそれを別々のルート(SNSやニュースサイトや友人経由)で聞けば、情報の偶然性が重なって信頼性は増すし、購買行動への確実性もアップする。"ここから私は思いました1、運命の操作2、運命への問い3、運命⇆自由意思1、運命の操作確かに、何度も偶然に会ったりすると、何らかのご縁を感じますよね、と言ったり、もしかしてこれは、運命の出会いなのでは?みたいに勘違いをして告白したりすることが、ままある気がしますこれは、何か人智を超えた不思議な力に導かれてる感じを醸し出すためには、実は3回いろんな出会い方をさせれば、そう思い込む可能性がある、ということの証明だなと思いましたとすると、まさにこの秘密をマーケッターや、悪い人(とは限りませんが)が、そんなアプローチをわざと実はやっていたことがあったとしたら、運命なもしれない、と目をキラキラさせてしまう効果があるというのは、目から鱗が落ちる思いでした2、運命への問いだとすると、もしかしたら、これは仕組まれているのかもしれないと、一旦は考えてみる、ということが、実は自分を守るためには、必要なことなのかもしれないなと、思いましたあまり、疑い深くなりすぎると、疑心暗鬼になってはいけないですが、少なくともそんな可能性も、ないこともないよと、冷静な判断があってもいいかなと思いました3、運命⇆自由意思そんな運命の反意語として思い浮かぶのは、自由意思かもしれないなあと思いました。つまり、セレンディピティ的な出会いがあったとして、果たしてそれをどう解釈するかの、自由意志を残しておく必要があると、いうことかと思います。ニーチェの解釈論のように、真実はない、あるのは解釈だと、言われている通り、自分の自由意志が、どう解釈する余地は、誰にでも実はある、という事を常日頃意識しておく必要がある気がしました誰かが自分を嵌めようとしてるかもしれない、とまでは思う必要はないと思いますが、それは自分が本当に望む事なのか?自分が選択したい事なのか?自らのパッションの源に従ってる事なのか?これくらいの、問いを、ダニエルカーネマンのファスト&フローにおける、システム2において、冷静に判断する、ということも、時には必要な気がしました。イノベーターは、まずは行動だ、ということと矛盾すると思われるかもしれませんが、それを判断するメジャメントを経験から、取得しておくことが大切かと思いましたこの"3デクワス理論"は、それほどまでにあまりにも強力である、と思いました一言で言えば運命の"3デクワス理論"ノベーションそんな事を思いました^ ^参考:本: すごい思考ツール 壁を突破するための〈100の方程式〉 2024年7月20日 発行 著 者 小西利行 発行所 株式会社文藝春秋動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/e_l1i46Nd3E2025-03-2818 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"運命の"3デクワス理論"ノベーション(1438回)「伊右衛門」「モノより思い出。」等1000を超えるCM・広告作品を出されている、POOL inc.Founderの小西利行 さんの"3デクワス理論"に目から鱗が落ちたようでした曰く"この理論をつくったのは、あるゲーム会社へのプレゼンで電通の吉田健太郎さんから聞いた、「実は、商品を“買わない理由”は平均2.6個で、これを“買う理由”が上回らなければ購入されない」という調査結果がきっかけだった。これは面白い! と僕は思った。つまり3回以上「買う理由」に出会えば「買う」わけだ。しかもそれを別々のルート(SNSやニュースサイトや友人経由)で聞けば、情報の偶然性が重なって信頼性は増すし、購買行動への確実性もアップする。"ここから私は思いました1、運命の操作2、運命への問い3、運命⇆自由意思1、運命の操作確かに、何度も偶然に会ったりすると、何らかのご縁を感じますよね、と言ったり、もしかしてこれは、運命の出会いなのでは?みたいに勘違いをして告白したりすることが、ままある気がしますこれは、何か人智を超えた不思議な力に導かれてる感じを醸し出すためには、実は3回いろんな出会い方をさせれば、そう思い込む可能性がある、ということの証明だなと思いましたとすると、まさにこの秘密をマーケッターや、悪い人(とは限りませんが)が、そんなアプローチをわざと実はやっていたことがあったとしたら、運命なもしれない、と目をキラキラさせてしまう効果があるというのは、目から鱗が落ちる思いでした2、運命への問いだとすると、もしかしたら、これは仕組まれているのかもしれないと、一旦は考えてみる、ということが、実は自分を守るためには、必要なことなのかもしれないなと、思いましたあまり、疑い深くなりすぎると、疑心暗鬼になってはいけないですが、少なくともそんな可能性も、ないこともないよと、冷静な判断があってもいいかなと思いました3、運命⇆自由意思そんな運命の反意語として思い浮かぶのは、自由意思かもしれないなあと思いました。つまり、セレンディピティ的な出会いがあったとして、果たしてそれをどう解釈するかの、自由意志を残しておく必要があると、いうことかと思います。ニーチェの解釈論のように、真実はない、あるのは解釈だと、言われている通り、自分の自由意志が、どう解釈する余地は、誰にでも実はある、という事を常日頃意識しておく必要がある気がしました誰かが自分を嵌めようとしてるかもしれない、とまでは思う必要はないと思いますが、それは自分が本当に望む事なのか?自分が選択したい事なのか?自らのパッションの源に従ってる事なのか?これくらいの、問いを、ダニエルカーネマンのファスト&フローにおける、システム2において、冷静に判断する、ということも、時には必要な気がしました。イノベーターは、まずは行動だ、ということと矛盾すると思われるかもしれませんが、それを判断するメジャメントを経験から、取得しておくことが大切かと思いましたこの"3デクワス理論"は、それほどまでにあまりにも強力である、と思いました一言で言えば運命の"3デクワス理論"ノベーションそんな事を思いました^ ^参考:本: すごい思考ツール 壁を突破するための〈100の方程式〉 2024年7月20日 発行 著 者 小西利行 発行所 株式会社文藝春秋動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/e_l1i46Nd3E2025-03-2818 min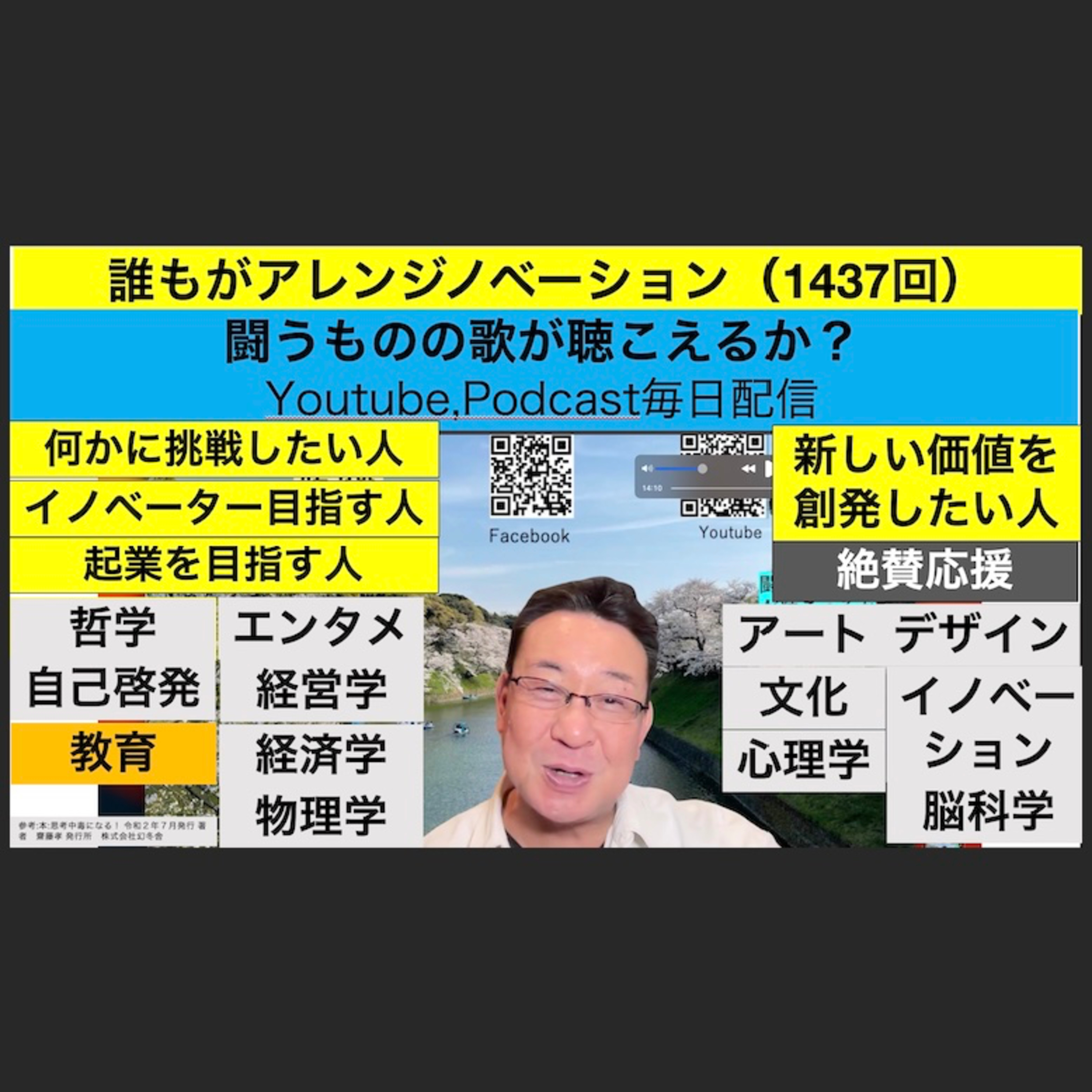 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"誰もがアレンジノベーション(1437回)斉藤孝さんの言葉に、イノベーションのあり方について、めちゃくちゃ共感させて頂きました斉藤さん曰く"何か一つの材料をもとにアレンジしていく、別の要素をつけ加えていくことでイノベーティブなアウトプットが生まれます。これは「アレンジ思考」ともいうべき手法です。 "また、ノーベル化学賞を受賞した田中耕一さんの言葉として以下の言葉を引用されてます田中さん曰く"もともとイノベーションの日本語訳は「新結合」、あるいは「新しい捉え方」とか「解釈」です。いろいろな分野の方々が集まって新しく結合する、新しい解釈をすることがイノベーションなわけです。失敗と思われることも、別の分野ではすごい発見になるかもしれない。もう少し柔軟に、広く解釈すれば、イノベーションはもっとたやすくできると思います。イノベーションを実際にやっている人も、単にくっつけただけじゃないかと思って、自分自身を低く評価している。そういった人たちに、もっと気楽に考えようよ、意外と簡単にできるよと伝えたい。 (NHK『NHKスペシャル』より)"ここから私は思いました1、インポスター症候群2、気楽にアレンジしてみる3、誰にでもできる「あらゆる人間の経験の中には、探究の萌芽がある。それを育てるのが教育である。」(ジョン・デューイ『経験と教育』)齋藤孝さんは、お話も面白いし、本もめちゃくちゃ読みやすくて、ためになって、大好きなのですが、今回の言葉にも痺れました1、インポスター症候群心理学者のポーリン・R・クランスとスザンヌ・A・アイムスによって命名されたものですが、きちんとした成功や達成のエビデンスがあるにも関わらず、それは自分の成果として感じられない、肯定できない、みたいな事をインポスター症候群と言うのは事を思い出しました一見、謙遜していて美しいのかとも思っちゃうかもですが、これがひどくなると、なかなか挑戦することができにくくなると言う弊害が出てくるので、自信過剰になれとは言いませんが周りの目を気にすることよりも、自らとして納得できたかどうか、と言うことに目を向けて、しっかりと自分自身も高く評価もしてあげようよ、と言うことも大切と思いました2、気楽にアレンジしてみる斉藤さんも田中さんも言われている通り、何かに何かをくっつければイノベーションなんだと、気楽に考えて楽しむくらいがいいのかなと思いますとかく仕事になっちゃうと、しかも、イノベーションなんてすごい人の実績を見せられると、何から始めたらいいかわからなくなる、と言うことが往々としてある気がしますイノベーションなんて仰々しい言葉でなく、ちょっとしたアレンジ、こう呼ぶと確かに、もっと気楽にできるような気がするなあと思いましたそして、とにかく何かに何かくっつけてみよう、って事を、子供のようにやってうちに、それすごく面白いかも、みたいなことになるので、まずは、何かと何かをくっつけちゃうプロジェクトを立ち上げるみたいなことが良いのかもなと思いました3、誰にでもできる哲学者のジョン・デューイは『経験と教育』から、「あらゆる人間の経験の中には、探究の萌芽がある。それを育てるのが教育である。」と言われているそうですこれは、まさに今の学校における、探究教育の元になったような言葉ですが、よくイノベーターは変わり者だ、とか、普通の人ではなれない、的な事を聞くこともありますが私は誰でもが、そのスキルとマインドセットを学ぶ機会を与えられれば、誰もがイノベーターになれると、これまでのWGなどを通じても思いますそれて、以前もお話しした、ハーパード大学で京都大学教授の、広中平祐さんの"人間の作業は全部創造だ"と言う言葉も、とても胸に刺さってますつまり、誰もがイノベーターどころか、隣の誰かにセーター編んであげたとか、庭の木を切ってあげたとか、自分のパッションから、仲間と共に、誰かが喜んでくれる大義を実現することが、それ自体がイノベーションであり、イノベーターなのだと、私は思いました一言で言うと誰もがアレンジノベーションそんな事を思いました^ ^参考:本:思考中毒になる! 令和2年7月発行 著者 齋藤孝 発行所 株式会社幻冬舎動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/IeiVGplioLs2025-03-2718 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"誰もがアレンジノベーション(1437回)斉藤孝さんの言葉に、イノベーションのあり方について、めちゃくちゃ共感させて頂きました斉藤さん曰く"何か一つの材料をもとにアレンジしていく、別の要素をつけ加えていくことでイノベーティブなアウトプットが生まれます。これは「アレンジ思考」ともいうべき手法です。 "また、ノーベル化学賞を受賞した田中耕一さんの言葉として以下の言葉を引用されてます田中さん曰く"もともとイノベーションの日本語訳は「新結合」、あるいは「新しい捉え方」とか「解釈」です。いろいろな分野の方々が集まって新しく結合する、新しい解釈をすることがイノベーションなわけです。失敗と思われることも、別の分野ではすごい発見になるかもしれない。もう少し柔軟に、広く解釈すれば、イノベーションはもっとたやすくできると思います。イノベーションを実際にやっている人も、単にくっつけただけじゃないかと思って、自分自身を低く評価している。そういった人たちに、もっと気楽に考えようよ、意外と簡単にできるよと伝えたい。 (NHK『NHKスペシャル』より)"ここから私は思いました1、インポスター症候群2、気楽にアレンジしてみる3、誰にでもできる「あらゆる人間の経験の中には、探究の萌芽がある。それを育てるのが教育である。」(ジョン・デューイ『経験と教育』)齋藤孝さんは、お話も面白いし、本もめちゃくちゃ読みやすくて、ためになって、大好きなのですが、今回の言葉にも痺れました1、インポスター症候群心理学者のポーリン・R・クランスとスザンヌ・A・アイムスによって命名されたものですが、きちんとした成功や達成のエビデンスがあるにも関わらず、それは自分の成果として感じられない、肯定できない、みたいな事をインポスター症候群と言うのは事を思い出しました一見、謙遜していて美しいのかとも思っちゃうかもですが、これがひどくなると、なかなか挑戦することができにくくなると言う弊害が出てくるので、自信過剰になれとは言いませんが周りの目を気にすることよりも、自らとして納得できたかどうか、と言うことに目を向けて、しっかりと自分自身も高く評価もしてあげようよ、と言うことも大切と思いました2、気楽にアレンジしてみる斉藤さんも田中さんも言われている通り、何かに何かをくっつければイノベーションなんだと、気楽に考えて楽しむくらいがいいのかなと思いますとかく仕事になっちゃうと、しかも、イノベーションなんてすごい人の実績を見せられると、何から始めたらいいかわからなくなる、と言うことが往々としてある気がしますイノベーションなんて仰々しい言葉でなく、ちょっとしたアレンジ、こう呼ぶと確かに、もっと気楽にできるような気がするなあと思いましたそして、とにかく何かに何かくっつけてみよう、って事を、子供のようにやってうちに、それすごく面白いかも、みたいなことになるので、まずは、何かと何かをくっつけちゃうプロジェクトを立ち上げるみたいなことが良いのかもなと思いました3、誰にでもできる哲学者のジョン・デューイは『経験と教育』から、「あらゆる人間の経験の中には、探究の萌芽がある。それを育てるのが教育である。」と言われているそうですこれは、まさに今の学校における、探究教育の元になったような言葉ですが、よくイノベーターは変わり者だ、とか、普通の人ではなれない、的な事を聞くこともありますが私は誰でもが、そのスキルとマインドセットを学ぶ機会を与えられれば、誰もがイノベーターになれると、これまでのWGなどを通じても思いますそれて、以前もお話しした、ハーパード大学で京都大学教授の、広中平祐さんの"人間の作業は全部創造だ"と言う言葉も、とても胸に刺さってますつまり、誰もがイノベーターどころか、隣の誰かにセーター編んであげたとか、庭の木を切ってあげたとか、自分のパッションから、仲間と共に、誰かが喜んでくれる大義を実現することが、それ自体がイノベーションであり、イノベーターなのだと、私は思いました一言で言うと誰もがアレンジノベーションそんな事を思いました^ ^参考:本:思考中毒になる! 令和2年7月発行 著者 齋藤孝 発行所 株式会社幻冬舎動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/IeiVGplioLs2025-03-2718 min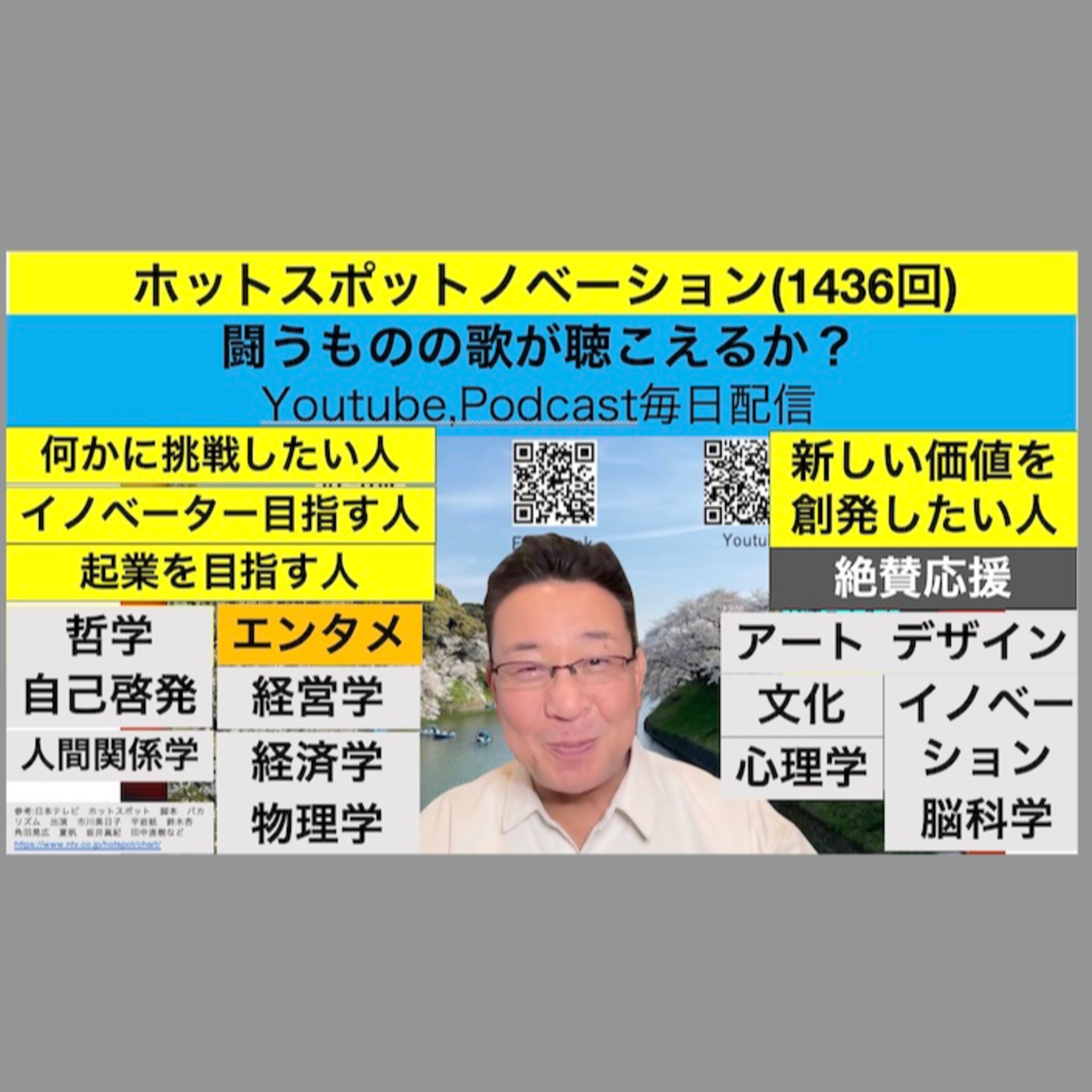 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"ホットスポットノベーション(1436回)涙流して笑って、ほろりと感動して、爽やかな気持ちで観終えることができた、そして大好きすぎて、ロスってしまったドラマ、ホットスポットについて、そのイノベーションっぷりについて思いました"富士山麓のとある町には、地球外生命体が潜んでいた!""ビジネスホテルで働くシングルマザー遠藤清美41歳。ある日、彼女はひょんなことから宇宙人と遭遇し・・・!?小さな田舎町で不思議な出来事が起こったり起こらなかったりする"私は思いました1、制約をつける→副作用2、変化し続ける→シナリオ変化3、何度も楽しめる→気づかない仕掛け1、制約をつけるイノベーションは、制約条件があった方が、起こしやすいとの話がありますが、まさにここに登場する宇宙人は、完全スーパーヒーローではなく、力を使うと必ず副作用が起きる、という面が、まさにそれかもなあと思いましたウルトラマンも3分しか持たない、みたいな、そんな制約があっからこそ、その中で、どんな風に勝つのかをハラハラしながら見てたわけですが、この完全体ではないという制約が、とてもドラマをイノベーティブにしてくれた気がしました2、変化し続けるホットスポットのネーミングも最後になって意味合いが変わってきたり、登場人物も、突然名前の知らない人が普通に出てきてたり、最後に山本耕史さんが出るのも、とにかく脚本は当社の予定からどんどん変化していったとのことを聞いて最初からゴールを決めて、一寸違わず進むのも大事だけども、その時々の役者さんや、進み方によって、どんどん変えていっていいんだと言う、そう言うコンセンサスのチームだからこそ、ここまで面白くなったのかなあとも思いましたイノベーションの世界でも、ソリューションがどんどん変わるピボットは、むしろ奨励されるものですが、大企業では、なかなか変化していくと、最初に言ってとことと違うとか、決裁を取ったのはそんなことじゃないとか、大変なことがたくさんあるのですがドラマは役者とスタッフがいる生き物で、また、実はイノベーションのソリューションだって、時代と共に変われるか?と言うことがとても求められてくることも考えると、変わり続ける強さがあった気がしました3、何度も楽しめるそしてこれは、最後の対談で私も知ったのですが、実は最初の場面に後々から出てくる人たちが、実はひっそり登場してたりみたいな、何度でも見たくなる仕掛けを仕込んでおくと言うのも、すごくワクワクさせて頂きましたイノベーションの世界でも、最初は面白いんだけど、やっていくうちに、こなすことが目的になっちゃって、結局、つまらなくなっちゃうとか、よくあるなあと思いましただからこそ、イノベーションを生み出す仕組み自体も、常日頃、アップデートしないと飽きられてしまうと言うこともあるよなーとも思いましたということで、ホットスポットは、あえて制限のあるヒーローを生み出して、次々とシナリオをブラッシュアップしながら、そして何度も見たくなる仕掛けを随所に散りばめた究極のコメディだったなと、そんな事を思わせていただきました^ ^これはまさにバカリズムさんのパッションが炸裂したホットスポットノベーションそんな事を思いました^ ^参考:日本テレビ ホットスポット 脚本 バカリズム 出演 市川美日子 平岩紙 鈴木杏 角田晃広 夏帆 坂井真紀 田中直樹など https://www.ntv.co.jp/hotspot/chart/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/5HFRP57YCtI2025-03-2617 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"ホットスポットノベーション(1436回)涙流して笑って、ほろりと感動して、爽やかな気持ちで観終えることができた、そして大好きすぎて、ロスってしまったドラマ、ホットスポットについて、そのイノベーションっぷりについて思いました"富士山麓のとある町には、地球外生命体が潜んでいた!""ビジネスホテルで働くシングルマザー遠藤清美41歳。ある日、彼女はひょんなことから宇宙人と遭遇し・・・!?小さな田舎町で不思議な出来事が起こったり起こらなかったりする"私は思いました1、制約をつける→副作用2、変化し続ける→シナリオ変化3、何度も楽しめる→気づかない仕掛け1、制約をつけるイノベーションは、制約条件があった方が、起こしやすいとの話がありますが、まさにここに登場する宇宙人は、完全スーパーヒーローではなく、力を使うと必ず副作用が起きる、という面が、まさにそれかもなあと思いましたウルトラマンも3分しか持たない、みたいな、そんな制約があっからこそ、その中で、どんな風に勝つのかをハラハラしながら見てたわけですが、この完全体ではないという制約が、とてもドラマをイノベーティブにしてくれた気がしました2、変化し続けるホットスポットのネーミングも最後になって意味合いが変わってきたり、登場人物も、突然名前の知らない人が普通に出てきてたり、最後に山本耕史さんが出るのも、とにかく脚本は当社の予定からどんどん変化していったとのことを聞いて最初からゴールを決めて、一寸違わず進むのも大事だけども、その時々の役者さんや、進み方によって、どんどん変えていっていいんだと言う、そう言うコンセンサスのチームだからこそ、ここまで面白くなったのかなあとも思いましたイノベーションの世界でも、ソリューションがどんどん変わるピボットは、むしろ奨励されるものですが、大企業では、なかなか変化していくと、最初に言ってとことと違うとか、決裁を取ったのはそんなことじゃないとか、大変なことがたくさんあるのですがドラマは役者とスタッフがいる生き物で、また、実はイノベーションのソリューションだって、時代と共に変われるか?と言うことがとても求められてくることも考えると、変わり続ける強さがあった気がしました3、何度も楽しめるそしてこれは、最後の対談で私も知ったのですが、実は最初の場面に後々から出てくる人たちが、実はひっそり登場してたりみたいな、何度でも見たくなる仕掛けを仕込んでおくと言うのも、すごくワクワクさせて頂きましたイノベーションの世界でも、最初は面白いんだけど、やっていくうちに、こなすことが目的になっちゃって、結局、つまらなくなっちゃうとか、よくあるなあと思いましただからこそ、イノベーションを生み出す仕組み自体も、常日頃、アップデートしないと飽きられてしまうと言うこともあるよなーとも思いましたということで、ホットスポットは、あえて制限のあるヒーローを生み出して、次々とシナリオをブラッシュアップしながら、そして何度も見たくなる仕掛けを随所に散りばめた究極のコメディだったなと、そんな事を思わせていただきました^ ^これはまさにバカリズムさんのパッションが炸裂したホットスポットノベーションそんな事を思いました^ ^参考:日本テレビ ホットスポット 脚本 バカリズム 出演 市川美日子 平岩紙 鈴木杏 角田晃広 夏帆 坂井真紀 田中直樹など https://www.ntv.co.jp/hotspot/chart/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/5HFRP57YCtI2025-03-2617 min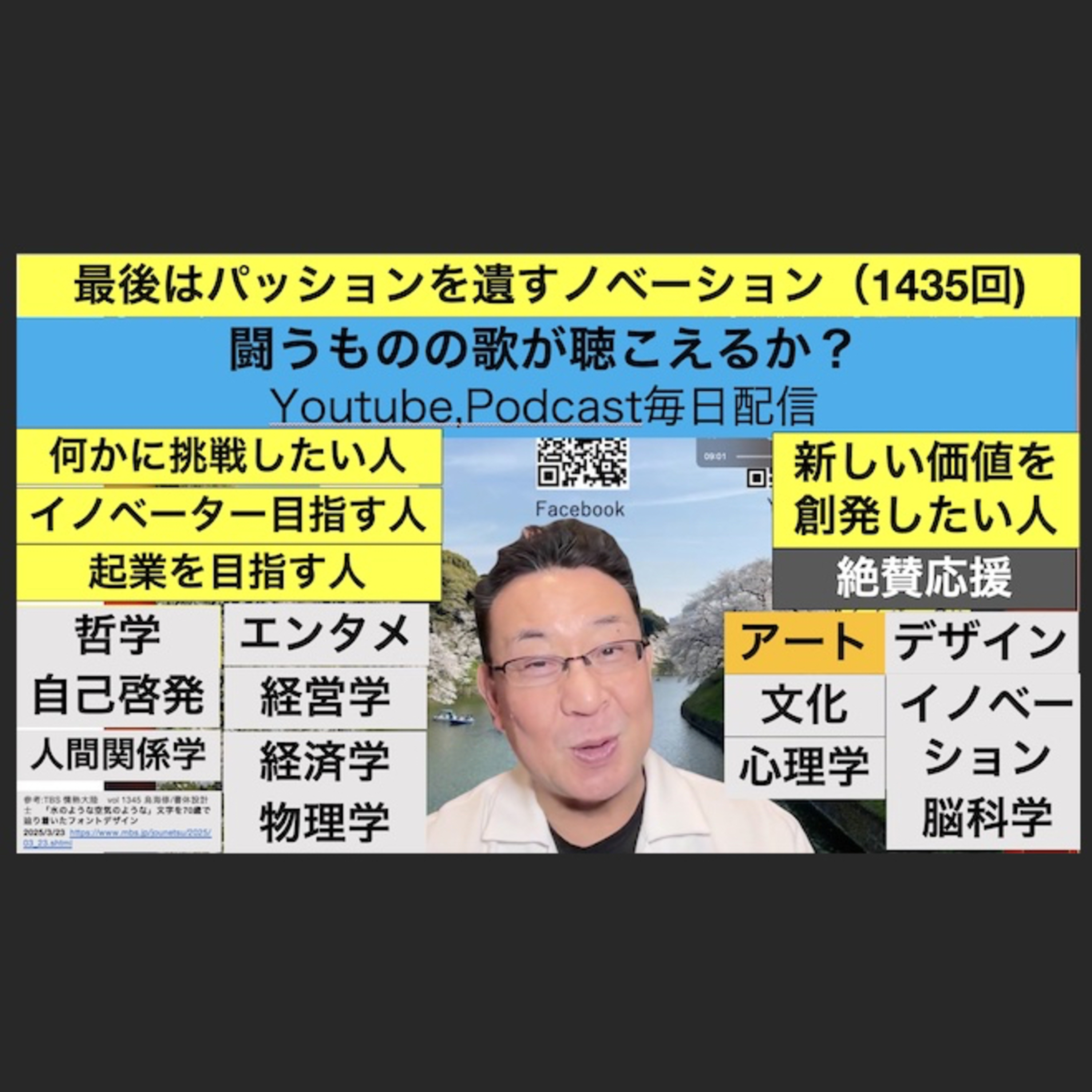 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"最後はパッションを遺すノベーション(1435回)第58回吉川英治文化賞を受賞されている書体設計士の鳥海修さんの、改めて自らのためになぜ書体を作るのか?の問いへの答えに感動しました曰く"今までは、なんか体を鍛えるために、色々やってきたみたいな感じそれでもう体鍛え終わったので、あとは自分のそのいわゆる鍛えられた体の、全部を使ってあの、自分のやりたいことを表現しましょうっていうような、言い方でいかがでしょうか?でもね、誰かには刺さる、きっと、誰かには、刺さる。"ここから私は思いました1、ビジネスからアートへ2、大義を信じるパッション3、後世へ残す最大の遺物そもそもあんなにたくさんある書体を、手作業で創られているということに、まずは衝撃でした!ほんの少しの違いで全然印象が変わる、一つの書体というものを、すべての文字にこだわり抜いて作っていく作業だけでも気が遠くなるなと、感動しました1、ビジネスからアートへまず思ったのは、これまで企業のためや他人のために、創られてきたビジネスデザインの作業から、ここから本当に自分のためのアート的な作業に移られたということなのかなあと、勝手に思いましたビジネスは、ユーザーのニーズに応えることから始まって、そこに自らのパッションを注入する方向ですが、アートは逆で、自らのパッションの源をとにかく掘り下げるという作業で、それをユーザーが見て、初めて完成するという、そして感じ方は自由自在という、全く逆のベクトルを向こうとされているのかと感じました2、大義を信じるパッションそれでも、誰かには刺さる、と断言されていたことにもとても感動したのですが、それは、きっと、これまで、イノベーター3つのフレームのように、自らのパッションとお客様ニーズを仲間と共に掛け合わせて、お客様が喜んでもらえる大義を創られてきた経験があるからこそすでに鳥海さんの中には、自らのパッションに基づいたフォントが、必ず誰かにも突き刺さるという、大義の先にいる人たちの顔が見えてる中での、大義を信じるパッションがある中での、パッションの追求なのかと、そんな風にも感じました3、後世への最大の遺物内村鑑三さんの、後世への最大の遺物、のように、何をこの世に遺せるのかを、考えた時に、誰かに役に立つものを遺したいと、思ってしまう私ですがでも本当に遺したいものは、自らがとことんまで納得して、他の人はどう思うが、自分は天才だと思えるほどのものを、なにか遺すことができた、ということの方が、本当は満足できるんじゃないかなあと、そんなことまで思ってしまいました一言で言うと最後はパッションを遺すノベーションそんなことを感じさせて頂きました^ ^参考:TBS 情熱大陸 vol 1345 鳥海修/書体設計士 「水のような空気のような」文字を70歳で辿り着いたフォントデザイン 2025/3/23 https://www.mbs.jp/jounetsu/2025/03_23.shtml2025-03-2516 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"最後はパッションを遺すノベーション(1435回)第58回吉川英治文化賞を受賞されている書体設計士の鳥海修さんの、改めて自らのためになぜ書体を作るのか?の問いへの答えに感動しました曰く"今までは、なんか体を鍛えるために、色々やってきたみたいな感じそれでもう体鍛え終わったので、あとは自分のそのいわゆる鍛えられた体の、全部を使ってあの、自分のやりたいことを表現しましょうっていうような、言い方でいかがでしょうか?でもね、誰かには刺さる、きっと、誰かには、刺さる。"ここから私は思いました1、ビジネスからアートへ2、大義を信じるパッション3、後世へ残す最大の遺物そもそもあんなにたくさんある書体を、手作業で創られているということに、まずは衝撃でした!ほんの少しの違いで全然印象が変わる、一つの書体というものを、すべての文字にこだわり抜いて作っていく作業だけでも気が遠くなるなと、感動しました1、ビジネスからアートへまず思ったのは、これまで企業のためや他人のために、創られてきたビジネスデザインの作業から、ここから本当に自分のためのアート的な作業に移られたということなのかなあと、勝手に思いましたビジネスは、ユーザーのニーズに応えることから始まって、そこに自らのパッションを注入する方向ですが、アートは逆で、自らのパッションの源をとにかく掘り下げるという作業で、それをユーザーが見て、初めて完成するという、そして感じ方は自由自在という、全く逆のベクトルを向こうとされているのかと感じました2、大義を信じるパッションそれでも、誰かには刺さる、と断言されていたことにもとても感動したのですが、それは、きっと、これまで、イノベーター3つのフレームのように、自らのパッションとお客様ニーズを仲間と共に掛け合わせて、お客様が喜んでもらえる大義を創られてきた経験があるからこそすでに鳥海さんの中には、自らのパッションに基づいたフォントが、必ず誰かにも突き刺さるという、大義の先にいる人たちの顔が見えてる中での、大義を信じるパッションがある中での、パッションの追求なのかと、そんな風にも感じました3、後世への最大の遺物内村鑑三さんの、後世への最大の遺物、のように、何をこの世に遺せるのかを、考えた時に、誰かに役に立つものを遺したいと、思ってしまう私ですがでも本当に遺したいものは、自らがとことんまで納得して、他の人はどう思うが、自分は天才だと思えるほどのものを、なにか遺すことができた、ということの方が、本当は満足できるんじゃないかなあと、そんなことまで思ってしまいました一言で言うと最後はパッションを遺すノベーションそんなことを感じさせて頂きました^ ^参考:TBS 情熱大陸 vol 1345 鳥海修/書体設計士 「水のような空気のような」文字を70歳で辿り着いたフォントデザイン 2025/3/23 https://www.mbs.jp/jounetsu/2025/03_23.shtml2025-03-2516 min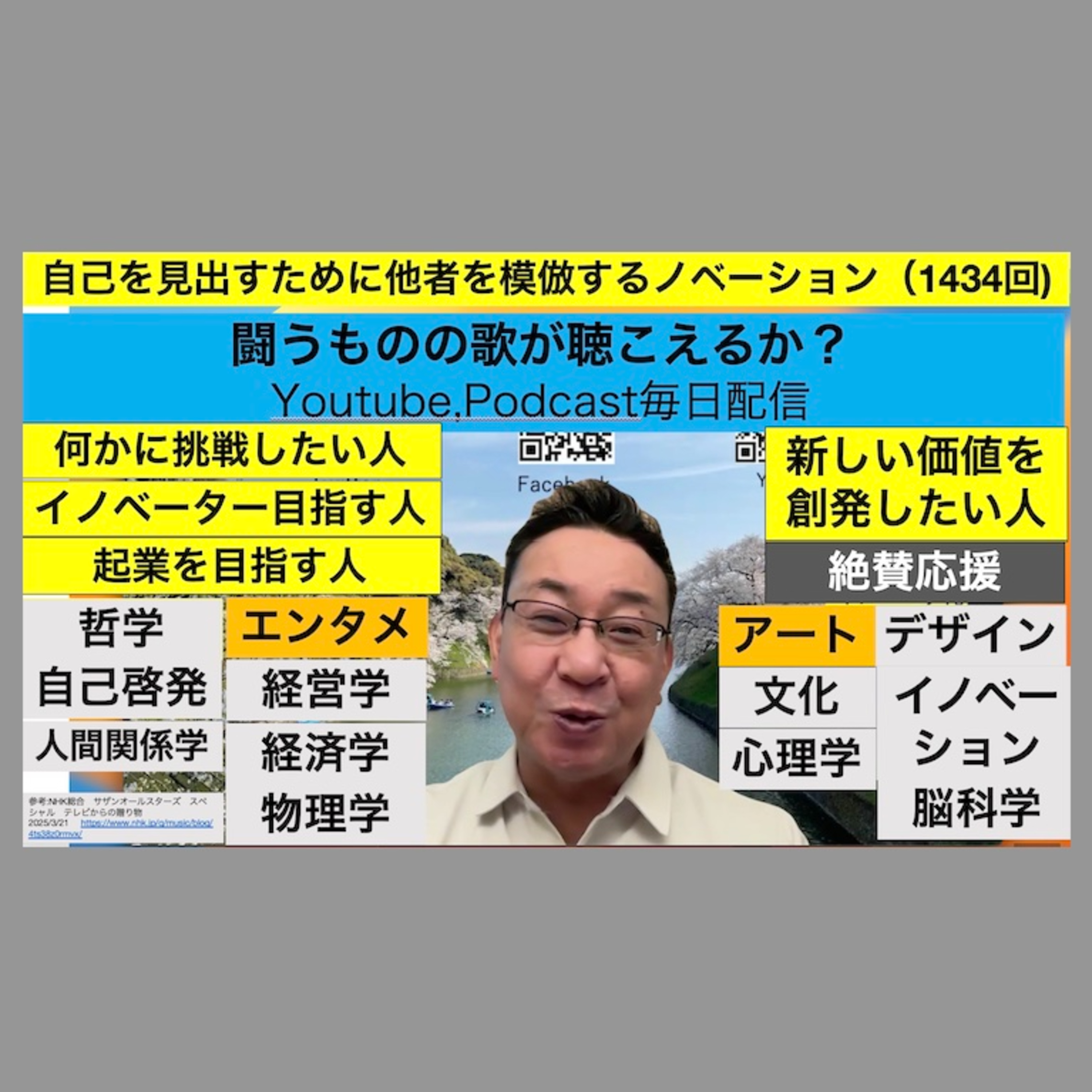 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"自己を見出すために他者を模倣するノベーション(1434回)桑田佳祐さんの言葉にサザンオールスターズの圧倒的なオリジナリティの創作の秘密を教えて頂きました曰く"自分の作品なんてのも、大体奥底から湧き出るとか、人生観根こそぎ表現するなんて、恐らくないんだと思うんですよね大体やっぱり聞き齧りとか、こんなことやってたよね、ジョンレノンとか、そう言うのが多かった自分のものなんてほとんどなくてね、模倣の寄せ集めで、出来上がってきてると思いますね"ここから私は思いました1、模倣から始まる、既存×自分2、パッションの源×再構成力3、他者との関わりで自己を見出す by 西田幾多郎"NHKサザンオールスターズ スペシャル テレビからの贈り物"は、めちゃくちゃ素敵な番組だったのですが、桑田佳祐さんと桑子真帆さんの、対談にはとてもたくさんの学びがありました特に桑田佳祐さんの創作の秘密に少し触れた気がして、めちゃくちゃ感動しました1、模倣から始まる、既存×自分圧倒的なオリジナリティで、しかも全ての曲に強烈なメッセージがあって、心躍り泣けてくる桑田さんの曲ですが、模倣から始まる、と言うメッセージに改めて考えさせられました桑田さんの世代よりも少し後の世代の私ですが、ちょうどバンドブーム真っ盛りだったので、とにかく様々なロックバンドのコピーをやりまくってましたそのうちに、自然と自分で曲作るのも面白いみたいに思ってきて、その後はその魅力に取り憑かれて、もしかしたら自分、天才かも、なんて思いながら、曲を作っていだだことを思い出しましたなので、全ては模倣から始まる、というのは、その頃はめちゃくちゃにやってただけですが、今思うと、シュンペーターの既存のアイディアの組み合わせこそ、イノベーションであるということを、やってたのかとも思いますただそこから、オリジナリティを出していくことに、ものすごく大きな壁を感じていたのも事実です。そこに圧倒的な桑田さんの個性が賭け合わさったところに秘密がある気がしました2、パッションの源×再構成力恐らくそこには桑田さんの音楽におけるパッションの源があって、それに触れるものと、そして桑田さんの個人としての独自性がかけ合わさって、再構成する力がすごいんだろうなあと思いましたイノベーター3つのフレームで言うと、圧倒的なパッションの源が桑田さんにあって、そしてサザンオールスターズという仲間がブーストして、そして自分たちだけではない、茅ヶ崎の人も、そこから広がって日本の人たち、世界の人たちに受けいられる大義に昇華された、みたいなことかなとおもいますでもその底流には、桑田さんのパッションの源としての、英語みたいな日本語や、見たことのない日本語の表現や、そしてキャッチーなメロディへの乗せ方などが炸裂してるところに圧倒的なオリジナリティと素敵さがあると思いました3、他者との関わりで自己を見出す by 西田幾多郎西田幾多郎さんが、「私と汝」という論文の中で言われているように、"自己は他者との関係において存在し、他者との関わりの中で自己を見出す。"ということから思うとアーティストは、自分だけの奥底から出てくるアイディアや思想だけでなく、他者との関わりの中で、初めて自己を見出すということが、あるのかもしれないなとおもいました桑田さんが聞き齧りや模倣をしていることは、実は他者との関わりの中で、自己を見出すプロセスそのものだったのかもしれないとテレビからそんな贈り物を受けていたの言うことなのかもなあと実は自己を見出すためには、他者の模倣や仲間などとのコミュニケーションによって、より自己が見えてきて、そして仲間と共に、みんなが喜んでいただける大義に到達するイノベーター3つのフレームから考えると、そういうことがあるのかもしれないと、そんなことを思いました一言で言うと自己を見出すために他者を模倣するノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHK総合 サザンオールスターズ スペシャル テレビからの贈り物 2025/3/21 https://www.nhk.jp/g/music/blog/4ts38z0rmvx/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/4RjNS-X7SMs2025-03-2415 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"自己を見出すために他者を模倣するノベーション(1434回)桑田佳祐さんの言葉にサザンオールスターズの圧倒的なオリジナリティの創作の秘密を教えて頂きました曰く"自分の作品なんてのも、大体奥底から湧き出るとか、人生観根こそぎ表現するなんて、恐らくないんだと思うんですよね大体やっぱり聞き齧りとか、こんなことやってたよね、ジョンレノンとか、そう言うのが多かった自分のものなんてほとんどなくてね、模倣の寄せ集めで、出来上がってきてると思いますね"ここから私は思いました1、模倣から始まる、既存×自分2、パッションの源×再構成力3、他者との関わりで自己を見出す by 西田幾多郎"NHKサザンオールスターズ スペシャル テレビからの贈り物"は、めちゃくちゃ素敵な番組だったのですが、桑田佳祐さんと桑子真帆さんの、対談にはとてもたくさんの学びがありました特に桑田佳祐さんの創作の秘密に少し触れた気がして、めちゃくちゃ感動しました1、模倣から始まる、既存×自分圧倒的なオリジナリティで、しかも全ての曲に強烈なメッセージがあって、心躍り泣けてくる桑田さんの曲ですが、模倣から始まる、と言うメッセージに改めて考えさせられました桑田さんの世代よりも少し後の世代の私ですが、ちょうどバンドブーム真っ盛りだったので、とにかく様々なロックバンドのコピーをやりまくってましたそのうちに、自然と自分で曲作るのも面白いみたいに思ってきて、その後はその魅力に取り憑かれて、もしかしたら自分、天才かも、なんて思いながら、曲を作っていだだことを思い出しましたなので、全ては模倣から始まる、というのは、その頃はめちゃくちゃにやってただけですが、今思うと、シュンペーターの既存のアイディアの組み合わせこそ、イノベーションであるということを、やってたのかとも思いますただそこから、オリジナリティを出していくことに、ものすごく大きな壁を感じていたのも事実です。そこに圧倒的な桑田さんの個性が賭け合わさったところに秘密がある気がしました2、パッションの源×再構成力恐らくそこには桑田さんの音楽におけるパッションの源があって、それに触れるものと、そして桑田さんの個人としての独自性がかけ合わさって、再構成する力がすごいんだろうなあと思いましたイノベーター3つのフレームで言うと、圧倒的なパッションの源が桑田さんにあって、そしてサザンオールスターズという仲間がブーストして、そして自分たちだけではない、茅ヶ崎の人も、そこから広がって日本の人たち、世界の人たちに受けいられる大義に昇華された、みたいなことかなとおもいますでもその底流には、桑田さんのパッションの源としての、英語みたいな日本語や、見たことのない日本語の表現や、そしてキャッチーなメロディへの乗せ方などが炸裂してるところに圧倒的なオリジナリティと素敵さがあると思いました3、他者との関わりで自己を見出す by 西田幾多郎西田幾多郎さんが、「私と汝」という論文の中で言われているように、"自己は他者との関係において存在し、他者との関わりの中で自己を見出す。"ということから思うとアーティストは、自分だけの奥底から出てくるアイディアや思想だけでなく、他者との関わりの中で、初めて自己を見出すということが、あるのかもしれないなとおもいました桑田さんが聞き齧りや模倣をしていることは、実は他者との関わりの中で、自己を見出すプロセスそのものだったのかもしれないとテレビからそんな贈り物を受けていたの言うことなのかもなあと実は自己を見出すためには、他者の模倣や仲間などとのコミュニケーションによって、より自己が見えてきて、そして仲間と共に、みんなが喜んでいただける大義に到達するイノベーター3つのフレームから考えると、そういうことがあるのかもしれないと、そんなことを思いました一言で言うと自己を見出すために他者を模倣するノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHK総合 サザンオールスターズ スペシャル テレビからの贈り物 2025/3/21 https://www.nhk.jp/g/music/blog/4ts38z0rmvx/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/4RjNS-X7SMs2025-03-2415 min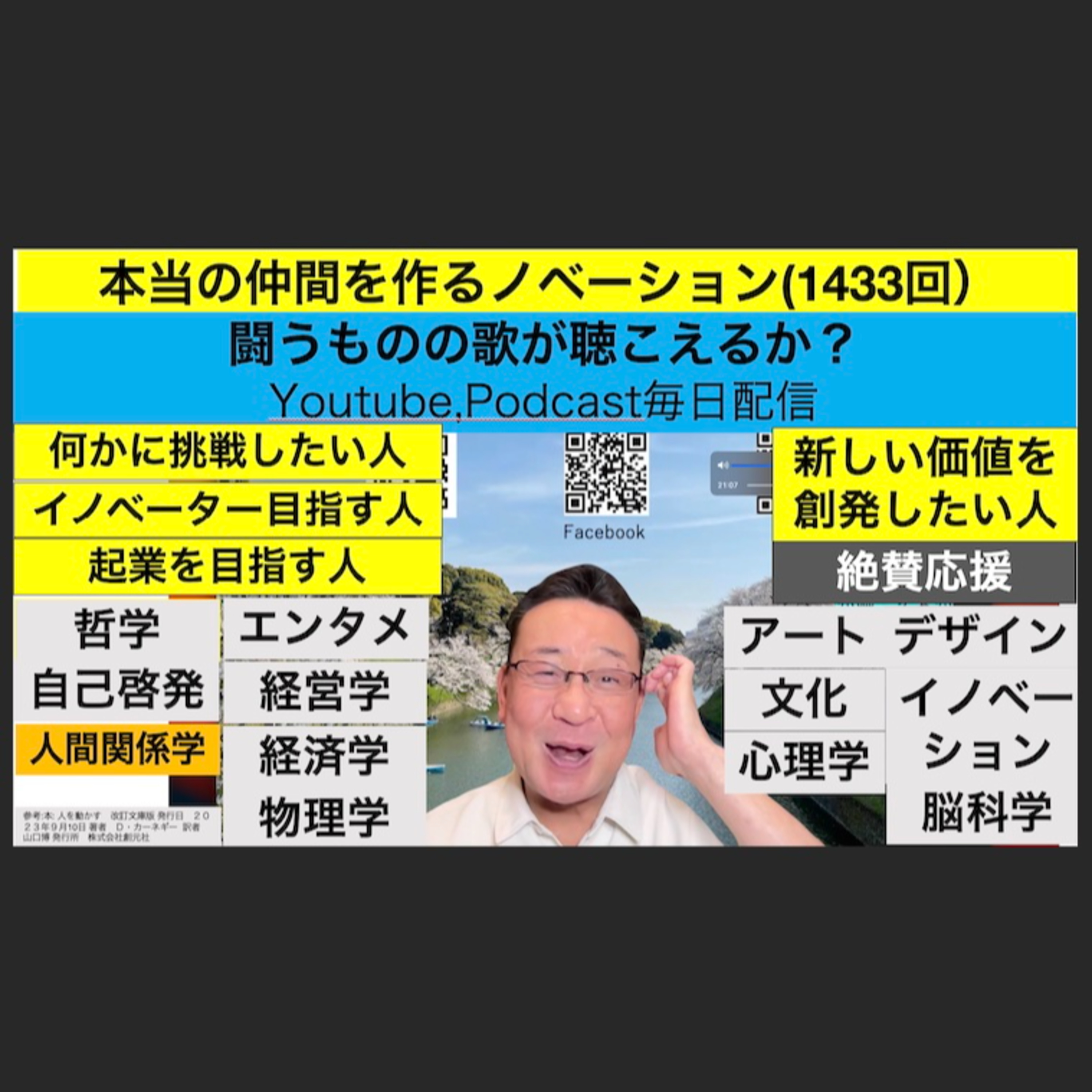 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"本当の仲間を作るノベーション(1433回)デール・カーネギーさんの名著「人を動かす」から、イノベーター3つのフレーム(パッション、仲間、大義)における"仲間"を作る時の大切な3つを考えてみました私は、以下の3つを思いました1、オファー→"誠実な関心を寄せる"2、マッチング→"人の立場に身を置く"3、ワーク→ "重要感を持たせる"1、オファー→"誠実な関心を寄せる"カーネギーさん曰く"ウィーンの著名な心理学者アルフレッド・アドラーは、その著書『人生の意味の心理学』でこう言っている。 「他人のことに関心を持たない人は、苦難の人生を歩まねばならず、他人に対しても大きな迷惑をかける。人間のあらゆる失敗はそういう人たちの間から生まれる」"これは、まるで飼っている、ワンコのような、純粋な、自らの「大好きパッション」が炸裂することがとても大切なのかもしれないと思いました。純粋に飼い主のことのみを考えて、全身でぶち当たってくる、ワンコのように、仲間になって欲しい人に、如何に自分の率直で素直な思いがつたわるか、ということがとても大切だと思いましたそして、それをするためには、逆にいうと、自分の中に、打算的な思いがあると、きっと上部だけの大好きアピールになってしまったり、ともすると、高い給料やSCをちらつかせるのみになり、結局、うまくいかなくなるのではないかとも思います。つまり、その仲間にしたいと思ってる人に対して、自分の大好きパッションが、まずは正直に炸裂しているかどうか、そこに嘘がないかどうか、ということが、逆に自分自身への問いかけにもなるなと、そんなふうに思いました2、マッチング→"人の立場に身を置く"カーネギーさん曰く"自動車王ヘンリー・フォードが人間関係の機微に触れた至言を残している。 「成功に秘訣というものがあるとすれば、それは、他人の立場を理解し、自分の立場と同時に、他人の立場からも物事を見ることのできる能力である」"これは、企業とのビジネスとも通じるものとして、まずは、仲間になってもらいたい人の、課題感を理解するということから、始める、ということかと思いました企業向けのオファリングの際には、気湯葉100回やりながら、なぜなぜを繰り返して、企業が持ってる課題の深掘りをするわけですが、それと同様に、仲間にしたい人が、今、本当に何に悩んでいて、どれほど痛みをあるのか?をまずは理解することから始めるのが、第一歩かと思いましたその課題感を理解した上で、真摯に自分には、この仲間に何を提供できるのか?ということを、考え抜いて、そして、自分なりにそれにどれだけそぐうかわからないけれども、オファリングをするということが、本当に仲間となってもらうためには、とても大事かと思いました3、ワーク→ "重要感を持たせる"そして最後に、仲間になってもらえるか、どうかのところでは、仲間になることへの、重要感を持ってもらえるかどうかが、運命の分かれ道だなと思いますそれは一言で言うと、その人のパッションの源を理解した上での、オファリングを出せるかどうかにかかってると思いました。2で、徹底的にその人の課題感を理解した上で、そしてさらに、その人が心からパッションが湧くこと、その源はなんなのかを、理解した上で、オファリングが適切になされるともしかすると、お金や役職などの重要官ではない、もっと、その人の人生にとって、重要なことを、仲間になってもらうことで、実現できる、そうなったら、本当の仲間として、末長く付き合ってもらえるのではないかそんなことを思いましたということで、一言で言うとカーネギーさんから学んだ本当の仲間を作るノベーションそんなことを思いました参考:本: 人を動かす 改訂文庫版 発行日 2023年9月10日 著者 D・カーネギー 訳者 山口博 発行所 株式会社創元社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/ZF-E6M5yxXM2025-03-2328 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"本当の仲間を作るノベーション(1433回)デール・カーネギーさんの名著「人を動かす」から、イノベーター3つのフレーム(パッション、仲間、大義)における"仲間"を作る時の大切な3つを考えてみました私は、以下の3つを思いました1、オファー→"誠実な関心を寄せる"2、マッチング→"人の立場に身を置く"3、ワーク→ "重要感を持たせる"1、オファー→"誠実な関心を寄せる"カーネギーさん曰く"ウィーンの著名な心理学者アルフレッド・アドラーは、その著書『人生の意味の心理学』でこう言っている。 「他人のことに関心を持たない人は、苦難の人生を歩まねばならず、他人に対しても大きな迷惑をかける。人間のあらゆる失敗はそういう人たちの間から生まれる」"これは、まるで飼っている、ワンコのような、純粋な、自らの「大好きパッション」が炸裂することがとても大切なのかもしれないと思いました。純粋に飼い主のことのみを考えて、全身でぶち当たってくる、ワンコのように、仲間になって欲しい人に、如何に自分の率直で素直な思いがつたわるか、ということがとても大切だと思いましたそして、それをするためには、逆にいうと、自分の中に、打算的な思いがあると、きっと上部だけの大好きアピールになってしまったり、ともすると、高い給料やSCをちらつかせるのみになり、結局、うまくいかなくなるのではないかとも思います。つまり、その仲間にしたいと思ってる人に対して、自分の大好きパッションが、まずは正直に炸裂しているかどうか、そこに嘘がないかどうか、ということが、逆に自分自身への問いかけにもなるなと、そんなふうに思いました2、マッチング→"人の立場に身を置く"カーネギーさん曰く"自動車王ヘンリー・フォードが人間関係の機微に触れた至言を残している。 「成功に秘訣というものがあるとすれば、それは、他人の立場を理解し、自分の立場と同時に、他人の立場からも物事を見ることのできる能力である」"これは、企業とのビジネスとも通じるものとして、まずは、仲間になってもらいたい人の、課題感を理解するということから、始める、ということかと思いました企業向けのオファリングの際には、気湯葉100回やりながら、なぜなぜを繰り返して、企業が持ってる課題の深掘りをするわけですが、それと同様に、仲間にしたい人が、今、本当に何に悩んでいて、どれほど痛みをあるのか?をまずは理解することから始めるのが、第一歩かと思いましたその課題感を理解した上で、真摯に自分には、この仲間に何を提供できるのか?ということを、考え抜いて、そして、自分なりにそれにどれだけそぐうかわからないけれども、オファリングをするということが、本当に仲間となってもらうためには、とても大事かと思いました3、ワーク→ "重要感を持たせる"そして最後に、仲間になってもらえるか、どうかのところでは、仲間になることへの、重要感を持ってもらえるかどうかが、運命の分かれ道だなと思いますそれは一言で言うと、その人のパッションの源を理解した上での、オファリングを出せるかどうかにかかってると思いました。2で、徹底的にその人の課題感を理解した上で、そしてさらに、その人が心からパッションが湧くこと、その源はなんなのかを、理解した上で、オファリングが適切になされるともしかすると、お金や役職などの重要官ではない、もっと、その人の人生にとって、重要なことを、仲間になってもらうことで、実現できる、そうなったら、本当の仲間として、末長く付き合ってもらえるのではないかそんなことを思いましたということで、一言で言うとカーネギーさんから学んだ本当の仲間を作るノベーションそんなことを思いました参考:本: 人を動かす 改訂文庫版 発行日 2023年9月10日 著者 D・カーネギー 訳者 山口博 発行所 株式会社創元社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/ZF-E6M5yxXM2025-03-2328 min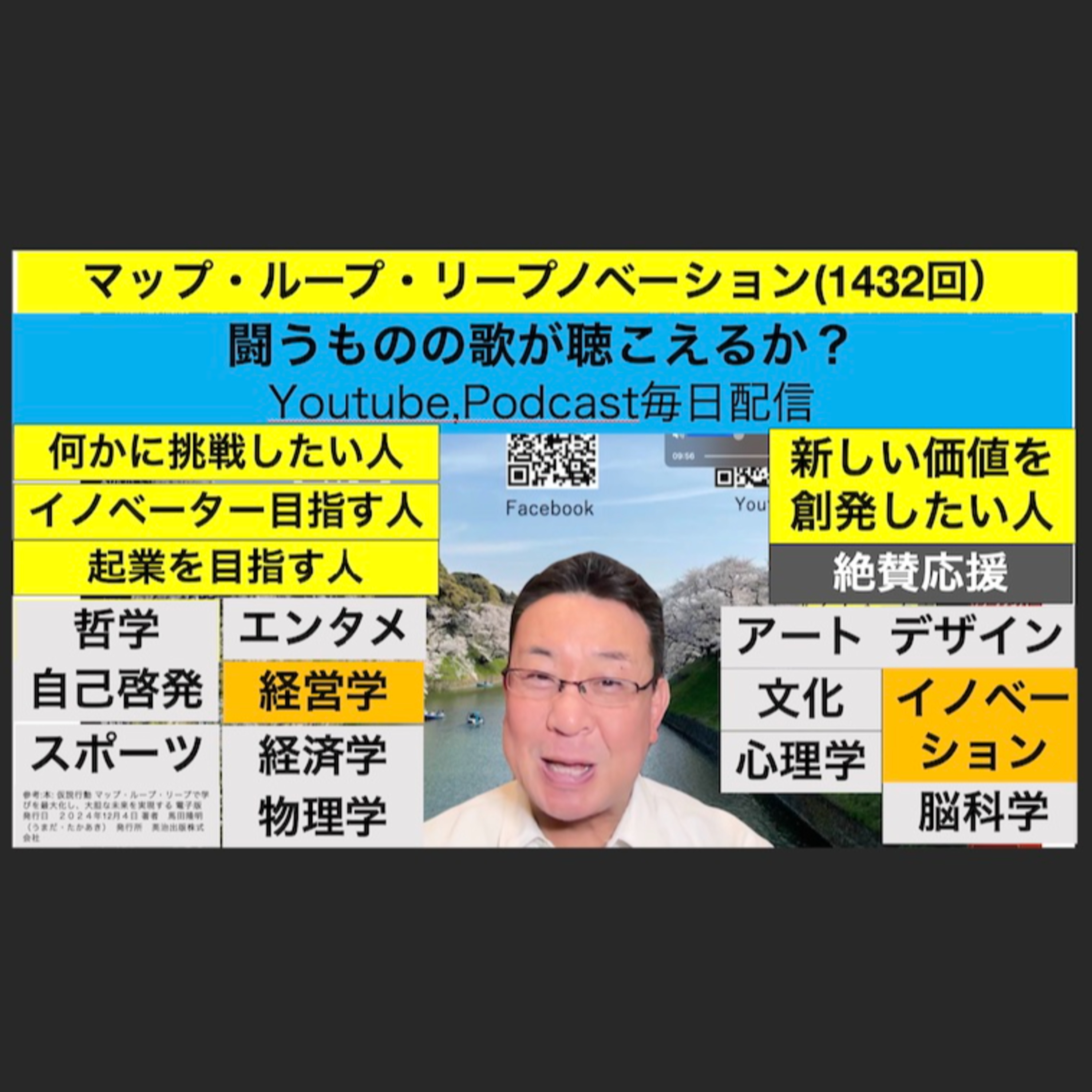 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"マップ・ループ・リープノベーション(1432回)東京大学 FoundX ディレクターの馬田隆明さんの考え方に、新たな気づきをいただきました曰く"まず最初はマップです。ビジネスにおける仮説は複数の仮説が統合されたものであり、全体の整合性が重要だという話をしましたが、そうした仮説の全体像となる地図(マップ)をざっくりと作ることが、仮説行動の最初にあるステップです。""仮説を強くしていくときに必要になるのがループです。仮説を生成したら検証し、検証結果から学びを得て、仮説を洗練させることを繰り返します。そうすることで、仮説のマップに含まれている個別の仮説を強くでき、マップ全体も強くすることができます。""最後にリープです。リープとは跳躍のことです。どれだけ検証したとしても、仮説が100%正しい答えになることはありません。だから、リスクがあろうともどこかのタイミングで「この仮説が正しい」と信じて決断し、行動に移る必要があります。"ここから私は思いました1、リーンスタートアップ×行動2、決断=発想+検証+跳躍 by伊丹裕之3、リーン&スケール1、リーンスタートアップ×行動この本の中でも語られているのですが、これまでは仮説思考は言われていたが、行動に伴わなければ意味がないと、いうことがとても腹落ちしました。よくプロジェクト支援をしていて、POCまでは行くけど、ビジネス化しない、そこで終わっちゃう問題は、ここに原因があるかもなあとも思いましたやはり起業家の皆様は、なんと言っても、行動ができる人、または行動に移す重要性を理解されてる方が、前に進まれている方だよなあとつくづく思いました2、決断=発想+検証+跳躍 by伊丹敬之さんしかしながら、実は、その行動に移すということには、大きなハードルがあるということも、改めて思いますそこで私が思い出したのは、以前、哲学で跳躍するノベーション(1195回)の時に紹介した、伊丹敬之さんから教えていただいた、決断=発想+検証+跳躍の公式です特に、最後の跳躍、がまさにここで言われていることと、とても合致してるように思えて、そのポイントは、哲学にあると言われていたのを思い出しましたつまり、起業家自身の中に、自らの哲学を持つことが、自らも納得して、行動に移すという決断を可能にするということでしたさらに私が思うのは、その哲学の中で大切なのは、私がいつもお話ししている、イノベーター3つのフレームである、パッション、仲間、大義における、最初のピースである、パッションの源を理解してるかどうか?ということにもあると思いましたつまり、この判断は、パッションのポートフォリオにおける、これと心中しても良いほど大好きなのか、または、誰かの痛みをなんとしても和らげるためなのか、または、自分自身のオリジナリティを守るためなのか、自らの成長を伺うためになんとしても今やらねばならないのか、など各々のパッションのポートフォリオに、自らが問いを立てて、そこに合致することがあるなら、自分に納得して行動に移しても良い、それがいつしか自らの哲学と、あえることになるのではないかと、思いました3、リーン&スケール最後にその行動のやり方で重要なポイントは、リーンアンドスケールかと思いました。この本の中でも語られてますが、マップとループの段階で、これがうまくいったらどれだけ社会にインパクトを与えられるのか?ということを、最初から考えておく必要があると思いますそうしないと、せっかく苦労しても、自分たちだけが佐野満足で終わってしまう、それが、イノベーター3つのフレームにおける、パッションだけでなく、仲間と共に、大義を目指す、ということにつながると思いますその大義があることで、実は自らのパッションにもスープして炎が燃え盛ることにつながると思うので、行動のの最初の一歩は、エフェクチュエーションにおける、許容範囲な損失、の小さな事から始めながら、将来の大義はとてつもなく大きなもので行動を始める、それが大切なことだと思いましたということで一言で言うとマップ・ループ・リープノベーションそんな話をしています^ ^参考:本: 仮説行動 マップ・ループ・リープで学びを最大化し、大胆な未来を実現する 電子版 発行日 2024年12月4日 著者 馬田隆明(うまだ・たかあき) 発行所 英治出版株式会社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/hCowc3DjaXE2025-03-2217 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"マップ・ループ・リープノベーション(1432回)東京大学 FoundX ディレクターの馬田隆明さんの考え方に、新たな気づきをいただきました曰く"まず最初はマップです。ビジネスにおける仮説は複数の仮説が統合されたものであり、全体の整合性が重要だという話をしましたが、そうした仮説の全体像となる地図(マップ)をざっくりと作ることが、仮説行動の最初にあるステップです。""仮説を強くしていくときに必要になるのがループです。仮説を生成したら検証し、検証結果から学びを得て、仮説を洗練させることを繰り返します。そうすることで、仮説のマップに含まれている個別の仮説を強くでき、マップ全体も強くすることができます。""最後にリープです。リープとは跳躍のことです。どれだけ検証したとしても、仮説が100%正しい答えになることはありません。だから、リスクがあろうともどこかのタイミングで「この仮説が正しい」と信じて決断し、行動に移る必要があります。"ここから私は思いました1、リーンスタートアップ×行動2、決断=発想+検証+跳躍 by伊丹裕之3、リーン&スケール1、リーンスタートアップ×行動この本の中でも語られているのですが、これまでは仮説思考は言われていたが、行動に伴わなければ意味がないと、いうことがとても腹落ちしました。よくプロジェクト支援をしていて、POCまでは行くけど、ビジネス化しない、そこで終わっちゃう問題は、ここに原因があるかもなあとも思いましたやはり起業家の皆様は、なんと言っても、行動ができる人、または行動に移す重要性を理解されてる方が、前に進まれている方だよなあとつくづく思いました2、決断=発想+検証+跳躍 by伊丹敬之さんしかしながら、実は、その行動に移すということには、大きなハードルがあるということも、改めて思いますそこで私が思い出したのは、以前、哲学で跳躍するノベーション(1195回)の時に紹介した、伊丹敬之さんから教えていただいた、決断=発想+検証+跳躍の公式です特に、最後の跳躍、がまさにここで言われていることと、とても合致してるように思えて、そのポイントは、哲学にあると言われていたのを思い出しましたつまり、起業家自身の中に、自らの哲学を持つことが、自らも納得して、行動に移すという決断を可能にするということでしたさらに私が思うのは、その哲学の中で大切なのは、私がいつもお話ししている、イノベーター3つのフレームである、パッション、仲間、大義における、最初のピースである、パッションの源を理解してるかどうか?ということにもあると思いましたつまり、この判断は、パッションのポートフォリオにおける、これと心中しても良いほど大好きなのか、または、誰かの痛みをなんとしても和らげるためなのか、または、自分自身のオリジナリティを守るためなのか、自らの成長を伺うためになんとしても今やらねばならないのか、など各々のパッションのポートフォリオに、自らが問いを立てて、そこに合致することがあるなら、自分に納得して行動に移しても良い、それがいつしか自らの哲学と、あえることになるのではないかと、思いました3、リーン&スケール最後にその行動のやり方で重要なポイントは、リーンアンドスケールかと思いました。この本の中でも語られてますが、マップとループの段階で、これがうまくいったらどれだけ社会にインパクトを与えられるのか?ということを、最初から考えておく必要があると思いますそうしないと、せっかく苦労しても、自分たちだけが佐野満足で終わってしまう、それが、イノベーター3つのフレームにおける、パッションだけでなく、仲間と共に、大義を目指す、ということにつながると思いますその大義があることで、実は自らのパッションにもスープして炎が燃え盛ることにつながると思うので、行動のの最初の一歩は、エフェクチュエーションにおける、許容範囲な損失、の小さな事から始めながら、将来の大義はとてつもなく大きなもので行動を始める、それが大切なことだと思いましたということで一言で言うとマップ・ループ・リープノベーションそんな話をしています^ ^参考:本: 仮説行動 マップ・ループ・リープで学びを最大化し、大胆な未来を実現する 電子版 発行日 2024年12月4日 著者 馬田隆明(うまだ・たかあき) 発行所 英治出版株式会社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/hCowc3DjaXE2025-03-2217 min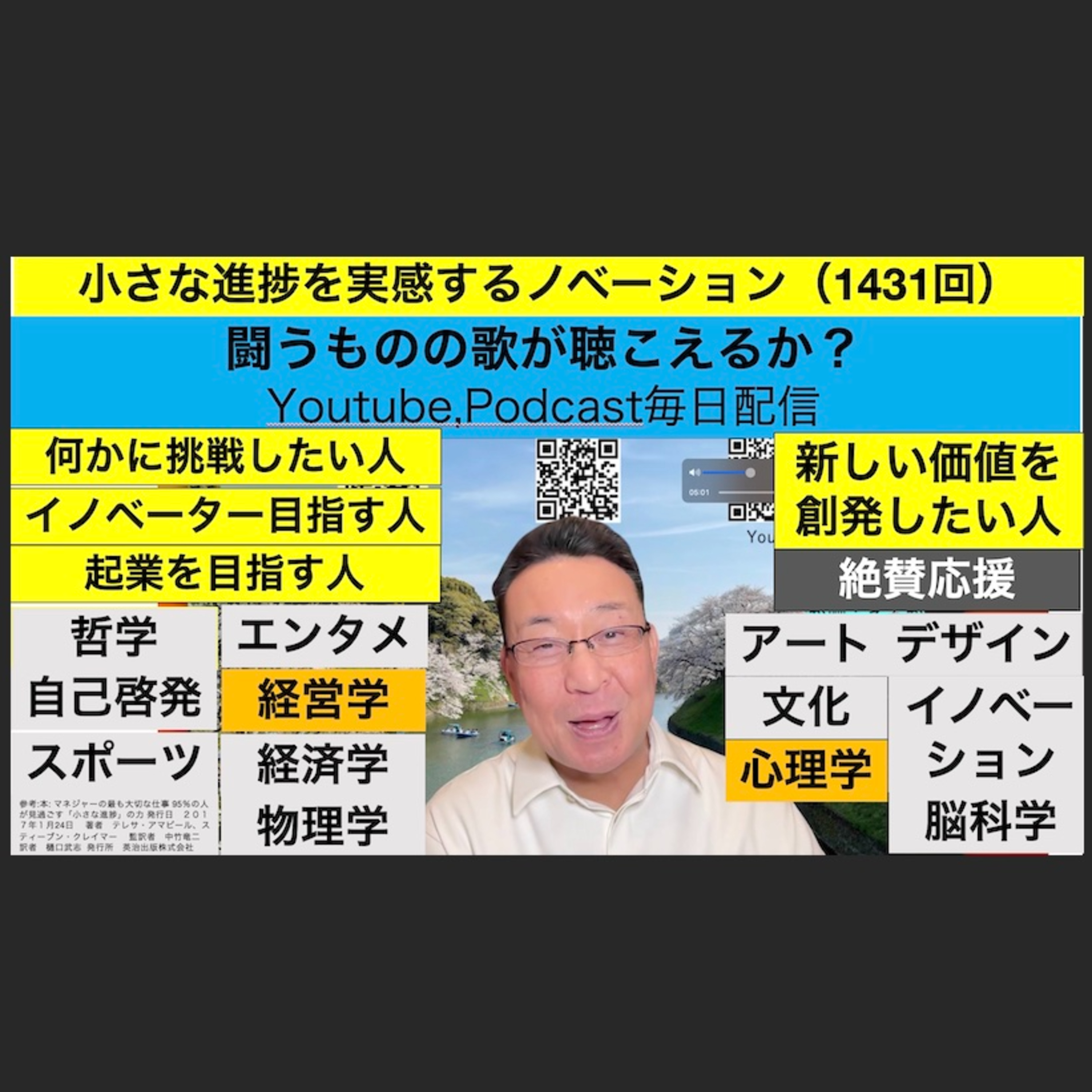 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"小さな進捗を実感するノベーション(1431回)世界の経営思想家ランキング「Thinkers50」に3期連続で選出されたテレサ・アマビールさんと心理学者のスティーブン・クレイマーさんによる著書:『マネジャーの最も大切な仕事 ― 小さな進捗の力)』から、イノベーターにおける重要な要素を頂きました曰く"創造的な成果を生むためには、人が自らの関心や楽しさから動く“内発的動機づけ”が不可欠であり、外からの報酬や圧力では創造性はむしろ損なわれる。""人は、意味のある仕事で小さな成功や進歩を経験すると、感情がより前向きになり、モチベーションが高まり、パフォーマンスや創造性も向上する""人がもっともモチベーションを感じるのは、仕事に意味を見出し、なおかつその仕事で前進していると実感できるときである。"ここから私は思いました1、内発的モチベーション→パッションの源2、意味ある目的→大義3、小さな進捗→小さなFastFailの積み重ねこのお話はマネージャーが最も意識すべきことであると同時に、自分自身もイノベーションを前に進めるためには、とても意識しておきたいことだなあと、思いました1、内発的モチベーションイノベーターが1番力を発揮する時というのは、自らのうちなる思いが、はち切れてしまい、何を差し置いてもそれをやりたい、極端には会社を辞めてまでもそれを実現したい、そこまでの思いが炸裂した時に、最も力を発揮する、そういうことかと思いましたこれは、私がイノベーター3つのフレームで、いつもお話ししている、1パッション、2仲間、3大義の、まさにパッションの源に、いかに火をつけるか、つけられるか、ということだなあと改めて思いました2、意味ある目的そしてそのパッションが炸裂していることが、自らが楽しかったり、嬉しくて仕方がないことでもいいのですが、そのパッションの炸裂してることが、自分だけでなく、他の人にも役に立っている、と実感する時、そこには自己満足だけではなく、社会的な意義が生まれることによって、より自らの思いに火がついて、良いフィードバックループのように、思いがさらに炸裂していくこれはイノベーター3つのフレームにおける、3大義を実現してきている状態だなあと、改めて思いました。パッションから始まって、そしてそれを仲間と共に回していく先に、たくさんの人たちが喜んでくれるものになる、それがイノベーター3つのフレームですがこれは仕事をする上でも、実は同じサイクルを回すことで、グッドサイクルが回る、そういうことなのだなあと思いました3、小さな進捗そしてこれが今回1番突き刺さったことなのですが、内発的動機から始まって、たくさんの人の役に立つ意義が生まれて、そしてそのプロジェクトの、進捗が少しずつ進んでいることを感じられるこのフィードバックループが、さらなるモチベーションの原動力になり、仕事を進めていく糧になっていく、ということが、とても大切ということに、大きな学びを頂きました言ってみればイノベーター3つのフレームにより、パッションから始まって、仲間と共に、みんなが喜ぶ大義が出来上がってそれだけではなく、そのプロジェクトが、少しずつだけれども、着実に進んでいるという実感を得る、または、得ていただく、ぐるぐる回るだけでなくスパイラルアップしてるそれこそが、前向きに良い仕事をする、原動力になるのだ、ということでした一言で言えば小さな進捗を実感するノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: マネジャーの最も大切な仕事 95%の人が見過ごす「小さな進捗」の力 発行日 2017年1月24日 著者 テレサ・アマビール、スティーブン・クレイマー 監訳者 中竹竜二 訳者 樋口武志 発行所 英治出版株式会社2025-03-2116 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"小さな進捗を実感するノベーション(1431回)世界の経営思想家ランキング「Thinkers50」に3期連続で選出されたテレサ・アマビールさんと心理学者のスティーブン・クレイマーさんによる著書:『マネジャーの最も大切な仕事 ― 小さな進捗の力)』から、イノベーターにおける重要な要素を頂きました曰く"創造的な成果を生むためには、人が自らの関心や楽しさから動く“内発的動機づけ”が不可欠であり、外からの報酬や圧力では創造性はむしろ損なわれる。""人は、意味のある仕事で小さな成功や進歩を経験すると、感情がより前向きになり、モチベーションが高まり、パフォーマンスや創造性も向上する""人がもっともモチベーションを感じるのは、仕事に意味を見出し、なおかつその仕事で前進していると実感できるときである。"ここから私は思いました1、内発的モチベーション→パッションの源2、意味ある目的→大義3、小さな進捗→小さなFastFailの積み重ねこのお話はマネージャーが最も意識すべきことであると同時に、自分自身もイノベーションを前に進めるためには、とても意識しておきたいことだなあと、思いました1、内発的モチベーションイノベーターが1番力を発揮する時というのは、自らのうちなる思いが、はち切れてしまい、何を差し置いてもそれをやりたい、極端には会社を辞めてまでもそれを実現したい、そこまでの思いが炸裂した時に、最も力を発揮する、そういうことかと思いましたこれは、私がイノベーター3つのフレームで、いつもお話ししている、1パッション、2仲間、3大義の、まさにパッションの源に、いかに火をつけるか、つけられるか、ということだなあと改めて思いました2、意味ある目的そしてそのパッションが炸裂していることが、自らが楽しかったり、嬉しくて仕方がないことでもいいのですが、そのパッションの炸裂してることが、自分だけでなく、他の人にも役に立っている、と実感する時、そこには自己満足だけではなく、社会的な意義が生まれることによって、より自らの思いに火がついて、良いフィードバックループのように、思いがさらに炸裂していくこれはイノベーター3つのフレームにおける、3大義を実現してきている状態だなあと、改めて思いました。パッションから始まって、そしてそれを仲間と共に回していく先に、たくさんの人たちが喜んでくれるものになる、それがイノベーター3つのフレームですがこれは仕事をする上でも、実は同じサイクルを回すことで、グッドサイクルが回る、そういうことなのだなあと思いました3、小さな進捗そしてこれが今回1番突き刺さったことなのですが、内発的動機から始まって、たくさんの人の役に立つ意義が生まれて、そしてそのプロジェクトの、進捗が少しずつ進んでいることを感じられるこのフィードバックループが、さらなるモチベーションの原動力になり、仕事を進めていく糧になっていく、ということが、とても大切ということに、大きな学びを頂きました言ってみればイノベーター3つのフレームにより、パッションから始まって、仲間と共に、みんなが喜ぶ大義が出来上がってそれだけではなく、そのプロジェクトが、少しずつだけれども、着実に進んでいるという実感を得る、または、得ていただく、ぐるぐる回るだけでなくスパイラルアップしてるそれこそが、前向きに良い仕事をする、原動力になるのだ、ということでした一言で言えば小さな進捗を実感するノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: マネジャーの最も大切な仕事 95%の人が見過ごす「小さな進捗」の力 発行日 2017年1月24日 著者 テレサ・アマビール、スティーブン・クレイマー 監訳者 中竹竜二 訳者 樋口武志 発行所 英治出版株式会社2025-03-2116 min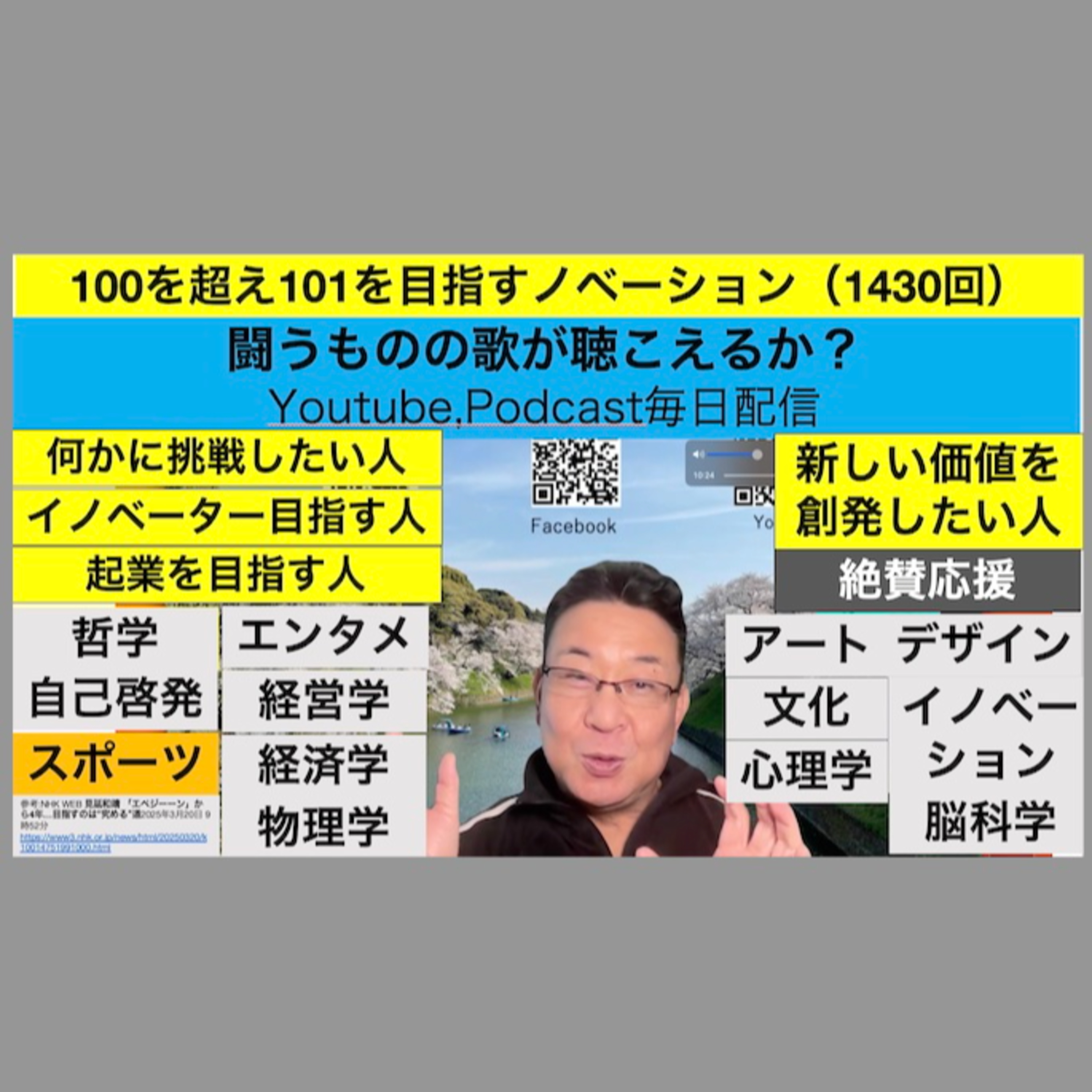 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"100を超え101を目指すノベーション(1430回)エペジーーンで東京オリンピックのフェンシング金メダルを取られた見延和靖さんの言葉に震えました小林アナウンサーが、それほどまでに打ち込めるストイックさはどこからくるでしょうか"との答えとして見延さん曰く"世の中に価値を生み出すというものは、大きく分けて2つしかないかなと思っています。それは、何もないところから何かを生み出す「0から1を生み出す価値」と、もうこれ以上ないだろうという「100をやりきった先の101を生み出す価値」です。僕は、その101を作ることが世の中に価値を生み出す大きなものだと思います。この世に生まれてきたからには、何かひとつ僕もこの世の中に貢献していきたい。これが、まだまだやりたいなと思える原動力のひとつかなとは思います。"ここから私は思いました1、限界を超えた先に本当の価値がある2、自身のネットワークの限界を超えることで価値が生まれる3、貢献意識が挑戦の原動力となる東京オリンピックの時には、私もめちゃくちゃ感動したエペジーーンの快挙でしたが、見延さんがその後苦しんで、そして今をまた新たに進まれているということにとても感動しました1、限界を超えた先に本当の価値があるイノベーションの世界では、0→1の世界と、0→100の世界の話を良くしていて、海外の方からたまに、日本はどちらかというと、0→100が得意なので、我が国は0→1が得意なので、良いマッチングですね、なんて言い方をされたこともあります必ずしもそうではないとも思うのですが、100→101を目指すというのは斬新な話でした。金メダルを取られた見延さんだからこそ、できる話かもしれないなと思いますニーチェが「超人」の概念を提唱し、「人は自己の限界を超えて進化し続けるべきだ」と言われてますが、限界を超えた先までコンフォートゾーンを抜け出していくのが、真のイノベーターだなあと改めて思いましたビジネスの世界では、よく期待値を超えろ、みたいな話もありますが、私も仕事を頂いたお客様からは、あなたに頼んで良かったと、もちろん言われたいですし、それよりも、びっくりするほどでした。本当にありがとう。なんて言われたら、泣いちゃいます大谷翔平さんも、ある意味、すでに漫画の世界、などと言われてるように、人々の期待値のはるか上を超えていくというのが、真のイノベーターなのかもしれないなあと思いました2、自身のネットワークの限界を超えることで価値が生まれる実はこのインタビューでは、以前私のこのチャネルでもお話しした茶道裏千家の前家元・千玄室さん(お茶を回すノベーション(1113回))と、見延さんが対話をされて、大きな学びがあったとの話があるのですが、それが実は、100に到達した人が101を目指す時に必要なアクティビティなのかもしれないとも思いましたこれは、ロナルド・S・バートさんが言われた、ストラクチュラル・ホール理論で言われてるように、異なるグループ間のギャップ(限界)を橋渡しできる人(ブローカー)が、新しい情報を流通させ、新たな価値を生むできるということに通じるなあと思いましたあえて全く違うグループとの交流を自らが求めていく、またはそういう場を作っていく、ということが、実は自らを100から更なる次の段階へ誘う一つのヒントになる、そんな風に思いました。3、貢献意識が挑戦の原動力となる見延さんは、最後に、この世の中へ貢献したい、ということを言われているわけですが、これは、以前お話しした、エミール・デュルケームの 『社会分業論』 で言われている「社会的役割の自覚が人生の意味や幸福感に大きな影響を与える」ということにつながるなと思いました以前私がお話ししたデュルケームのお話は、(自立は薄く広く依存するノベーション(1408回))の中で、依存することが分業の中では大切という話をしましたが、今回はそれと対をなす形で、貢献ということが、大切というお話かなと思いました依存しながら、貢献をすることで、自らの人生の意味を理解し、そして挑戦する心の原動力になっていく、そういうことなのかと理解させて頂きましたそして、これらの3のお話は、イノベーター3つのフレームにおける、パッション、仲間、大義と、とても関係が深かなってると思いました1、限界を超えるためには、自らの【パッション】の源に火をつけづけなければならないし、2、自身のネットワークの限界を超えるためには、自らの【仲間】の枠を超える必要があり3、貢献意識を持つためには、自らの想いだけでなく、さまざまな人々の【大義】を意識する必要があるということで、気がつくと、イノベーター3つのフレームに沿ってるなあとも思いました一言で言うと100を超え101を目指すノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHK WEB 見延和靖 「エペジーーン」から4年…目指すのは“究める”道2025年3月20日 9時52分https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250320/k10014751991000.html2025-03-2021 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"100を超え101を目指すノベーション(1430回)エペジーーンで東京オリンピックのフェンシング金メダルを取られた見延和靖さんの言葉に震えました小林アナウンサーが、それほどまでに打ち込めるストイックさはどこからくるでしょうか"との答えとして見延さん曰く"世の中に価値を生み出すというものは、大きく分けて2つしかないかなと思っています。それは、何もないところから何かを生み出す「0から1を生み出す価値」と、もうこれ以上ないだろうという「100をやりきった先の101を生み出す価値」です。僕は、その101を作ることが世の中に価値を生み出す大きなものだと思います。この世に生まれてきたからには、何かひとつ僕もこの世の中に貢献していきたい。これが、まだまだやりたいなと思える原動力のひとつかなとは思います。"ここから私は思いました1、限界を超えた先に本当の価値がある2、自身のネットワークの限界を超えることで価値が生まれる3、貢献意識が挑戦の原動力となる東京オリンピックの時には、私もめちゃくちゃ感動したエペジーーンの快挙でしたが、見延さんがその後苦しんで、そして今をまた新たに進まれているということにとても感動しました1、限界を超えた先に本当の価値があるイノベーションの世界では、0→1の世界と、0→100の世界の話を良くしていて、海外の方からたまに、日本はどちらかというと、0→100が得意なので、我が国は0→1が得意なので、良いマッチングですね、なんて言い方をされたこともあります必ずしもそうではないとも思うのですが、100→101を目指すというのは斬新な話でした。金メダルを取られた見延さんだからこそ、できる話かもしれないなと思いますニーチェが「超人」の概念を提唱し、「人は自己の限界を超えて進化し続けるべきだ」と言われてますが、限界を超えた先までコンフォートゾーンを抜け出していくのが、真のイノベーターだなあと改めて思いましたビジネスの世界では、よく期待値を超えろ、みたいな話もありますが、私も仕事を頂いたお客様からは、あなたに頼んで良かったと、もちろん言われたいですし、それよりも、びっくりするほどでした。本当にありがとう。なんて言われたら、泣いちゃいます大谷翔平さんも、ある意味、すでに漫画の世界、などと言われてるように、人々の期待値のはるか上を超えていくというのが、真のイノベーターなのかもしれないなあと思いました2、自身のネットワークの限界を超えることで価値が生まれる実はこのインタビューでは、以前私のこのチャネルでもお話しした茶道裏千家の前家元・千玄室さん(お茶を回すノベーション(1113回))と、見延さんが対話をされて、大きな学びがあったとの話があるのですが、それが実は、100に到達した人が101を目指す時に必要なアクティビティなのかもしれないとも思いましたこれは、ロナルド・S・バートさんが言われた、ストラクチュラル・ホール理論で言われてるように、異なるグループ間のギャップ(限界)を橋渡しできる人(ブローカー)が、新しい情報を流通させ、新たな価値を生むできるということに通じるなあと思いましたあえて全く違うグループとの交流を自らが求めていく、またはそういう場を作っていく、ということが、実は自らを100から更なる次の段階へ誘う一つのヒントになる、そんな風に思いました。3、貢献意識が挑戦の原動力となる見延さんは、最後に、この世の中へ貢献したい、ということを言われているわけですが、これは、以前お話しした、エミール・デュルケームの 『社会分業論』 で言われている「社会的役割の自覚が人生の意味や幸福感に大きな影響を与える」ということにつながるなと思いました以前私がお話ししたデュルケームのお話は、(自立は薄く広く依存するノベーション(1408回))の中で、依存することが分業の中では大切という話をしましたが、今回はそれと対をなす形で、貢献ということが、大切というお話かなと思いました依存しながら、貢献をすることで、自らの人生の意味を理解し、そして挑戦する心の原動力になっていく、そういうことなのかと理解させて頂きましたそして、これらの3のお話は、イノベーター3つのフレームにおける、パッション、仲間、大義と、とても関係が深かなってると思いました1、限界を超えるためには、自らの【パッション】の源に火をつけづけなければならないし、2、自身のネットワークの限界を超えるためには、自らの【仲間】の枠を超える必要があり3、貢献意識を持つためには、自らの想いだけでなく、さまざまな人々の【大義】を意識する必要があるということで、気がつくと、イノベーター3つのフレームに沿ってるなあとも思いました一言で言うと100を超え101を目指すノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHK WEB 見延和靖 「エペジーーン」から4年…目指すのは“究める”道2025年3月20日 9時52分https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250320/k10014751991000.html2025-03-2021 min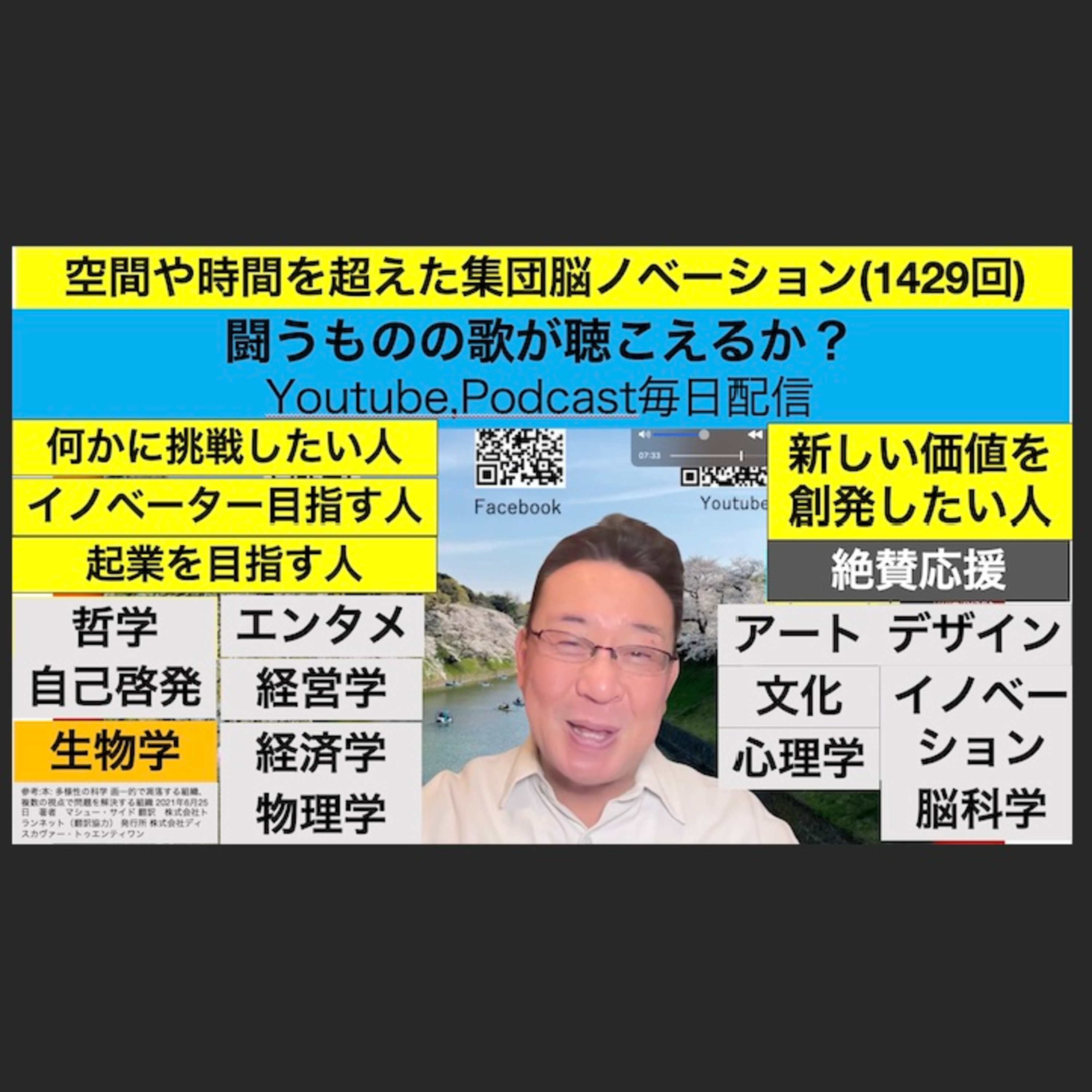 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"空間や時間を超えた集合脳ノベーション(1429回)イギリスの卓球選手でもあり、英『タイムズ』紙の第一級コラムニスト、ライターでもあるマシュー・サイドさんから、イノベーションの重要な要素を教えて頂きました"イノベーションは、社会的ネットワークの中で大勢の多様な頭脳が生み出す創造力の賜物だ。人類進化生物学の専門家、マイケル・ムスクリシュナとジョセフ・ヘンリックは、この頭脳のネットワークを「集団脳」(集団的知性)と呼ぶ。""イノベーションは従来、トーマス・カーライルが唱えたように、「偉人」――ほかの人間を凌ぐ偉大な思想家や天才発明家――の知力によって、あるいはそうした一個人の超人的な努力によって生まれると考えられてきた。つまり、先達の肩を借りはするものの、みな個人の洞察力、個人の才能によって新たな未来を開いたとされてきた。しかし我々は(中略)異議を唱えたい。そうした「個人」は集団脳の産物であり、それまでつながることのなかった数々のアイデアが連鎖した結果であると"ここから私は思いました1、偉人は集合脳2、アイディアの連鎖3、連鎖の環境1、偉人は集合知よく優れた発明は、巨人の肩にのるというような表現をされますが、実は肩にのってるどころか、それまでの歴史や周りからの人々がいるからこそ、偉人が輝くことができた、ある意味そういうタイミングが合致することが起きたので、偉人と言われるようになったと、いうことには衝撃を受けました哲学者のジョン・デューイさんが言われるように「知は社会的に構築される」という考え方からしても、知識やアイデアは、個人が孤立して生み出すものもあるけれども、多様な共同体の対話を重ねる中で実はの中で進化を遂げている、集団脳なのだなあと改めて教えて頂きました2、アイディアの連鎖シュンペーターさんが言われてるように、既存のアイディアと既存のアイディアが、組み合わさることがイノベーションなのですが、それが個々の中で一度組み合わさることよりもさまざまな人たちがいる中で、しかもそれぞれが次々と重ねて連鎖をしていくことが起きることで、これまでにない進化的なアイディアが次々と生み出されていく、そんな構造を作れるかどうかが量は質を超える、とイノベーションの世界ではよく言われますが、そんな世界を作っていくことができるのだなあとも思いました3、連鎖の環境そう考えると、いかにその連鎖が起きるような環境づくりをすることができるか、または、そん近況に自らの身を置くことができるかが、イノベーターを目指す人にはとても大切なんだろうなと思いました多様なバックグラウンドを持つ人たちの混ぜ合わさるような仕掛けや場づくり、また企業を超えたオープンイノベーションの仕掛けづくり、世代を超えた交流の仕掛けづくりさらにそれだけではなく、時間を超えた人たちやノウハウが蓄積しながら混ぜ合わさる仕掛けづくりが、実はイノベーション創発には欠かせない、どころか、それを実現した企業や組織が新たなイノベーションを起こせる、ということを改めて認識させていただきましたイノベーター3つのフレームにおける、パッション、仲間、大義、における、仲間の存在が、いかに大きいのか、と言うことを思い知らされましたそして、横軸としての空間的な広がりと、縦軸としての歴史も含めた時間的広がり、これをいかに連鎖の環境として作れるか、そんなことを思いました今私が進めている、イノベーター創発WGも、必ず毎年積み上げることが大事としてやってます。次年度には、前年度の人がチューターとして入ることによって、時間的にもアイディアが積み上がっていく、そんな仕掛けづくりが大切かなと思ってます一言で言うと空間や時間を超えた集団脳ノベーションそんなことを思いました参考:本: 多様性の科学 画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解決する組織 2021年6月25日 著者 マシュー・サイド 翻訳 株式会社トランネット(翻訳協力) 発行所 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/oMnO_HRbIkw2025-03-1923 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"空間や時間を超えた集合脳ノベーション(1429回)イギリスの卓球選手でもあり、英『タイムズ』紙の第一級コラムニスト、ライターでもあるマシュー・サイドさんから、イノベーションの重要な要素を教えて頂きました"イノベーションは、社会的ネットワークの中で大勢の多様な頭脳が生み出す創造力の賜物だ。人類進化生物学の専門家、マイケル・ムスクリシュナとジョセフ・ヘンリックは、この頭脳のネットワークを「集団脳」(集団的知性)と呼ぶ。""イノベーションは従来、トーマス・カーライルが唱えたように、「偉人」――ほかの人間を凌ぐ偉大な思想家や天才発明家――の知力によって、あるいはそうした一個人の超人的な努力によって生まれると考えられてきた。つまり、先達の肩を借りはするものの、みな個人の洞察力、個人の才能によって新たな未来を開いたとされてきた。しかし我々は(中略)異議を唱えたい。そうした「個人」は集団脳の産物であり、それまでつながることのなかった数々のアイデアが連鎖した結果であると"ここから私は思いました1、偉人は集合脳2、アイディアの連鎖3、連鎖の環境1、偉人は集合知よく優れた発明は、巨人の肩にのるというような表現をされますが、実は肩にのってるどころか、それまでの歴史や周りからの人々がいるからこそ、偉人が輝くことができた、ある意味そういうタイミングが合致することが起きたので、偉人と言われるようになったと、いうことには衝撃を受けました哲学者のジョン・デューイさんが言われるように「知は社会的に構築される」という考え方からしても、知識やアイデアは、個人が孤立して生み出すものもあるけれども、多様な共同体の対話を重ねる中で実はの中で進化を遂げている、集団脳なのだなあと改めて教えて頂きました2、アイディアの連鎖シュンペーターさんが言われてるように、既存のアイディアと既存のアイディアが、組み合わさることがイノベーションなのですが、それが個々の中で一度組み合わさることよりもさまざまな人たちがいる中で、しかもそれぞれが次々と重ねて連鎖をしていくことが起きることで、これまでにない進化的なアイディアが次々と生み出されていく、そんな構造を作れるかどうかが量は質を超える、とイノベーションの世界ではよく言われますが、そんな世界を作っていくことができるのだなあとも思いました3、連鎖の環境そう考えると、いかにその連鎖が起きるような環境づくりをすることができるか、または、そん近況に自らの身を置くことができるかが、イノベーターを目指す人にはとても大切なんだろうなと思いました多様なバックグラウンドを持つ人たちの混ぜ合わさるような仕掛けや場づくり、また企業を超えたオープンイノベーションの仕掛けづくり、世代を超えた交流の仕掛けづくりさらにそれだけではなく、時間を超えた人たちやノウハウが蓄積しながら混ぜ合わさる仕掛けづくりが、実はイノベーション創発には欠かせない、どころか、それを実現した企業や組織が新たなイノベーションを起こせる、ということを改めて認識させていただきましたイノベーター3つのフレームにおける、パッション、仲間、大義、における、仲間の存在が、いかに大きいのか、と言うことを思い知らされましたそして、横軸としての空間的な広がりと、縦軸としての歴史も含めた時間的広がり、これをいかに連鎖の環境として作れるか、そんなことを思いました今私が進めている、イノベーター創発WGも、必ず毎年積み上げることが大事としてやってます。次年度には、前年度の人がチューターとして入ることによって、時間的にもアイディアが積み上がっていく、そんな仕掛けづくりが大切かなと思ってます一言で言うと空間や時間を超えた集団脳ノベーションそんなことを思いました参考:本: 多様性の科学 画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解決する組織 2021年6月25日 著者 マシュー・サイド 翻訳 株式会社トランネット(翻訳協力) 発行所 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/oMnO_HRbIkw2025-03-1923 min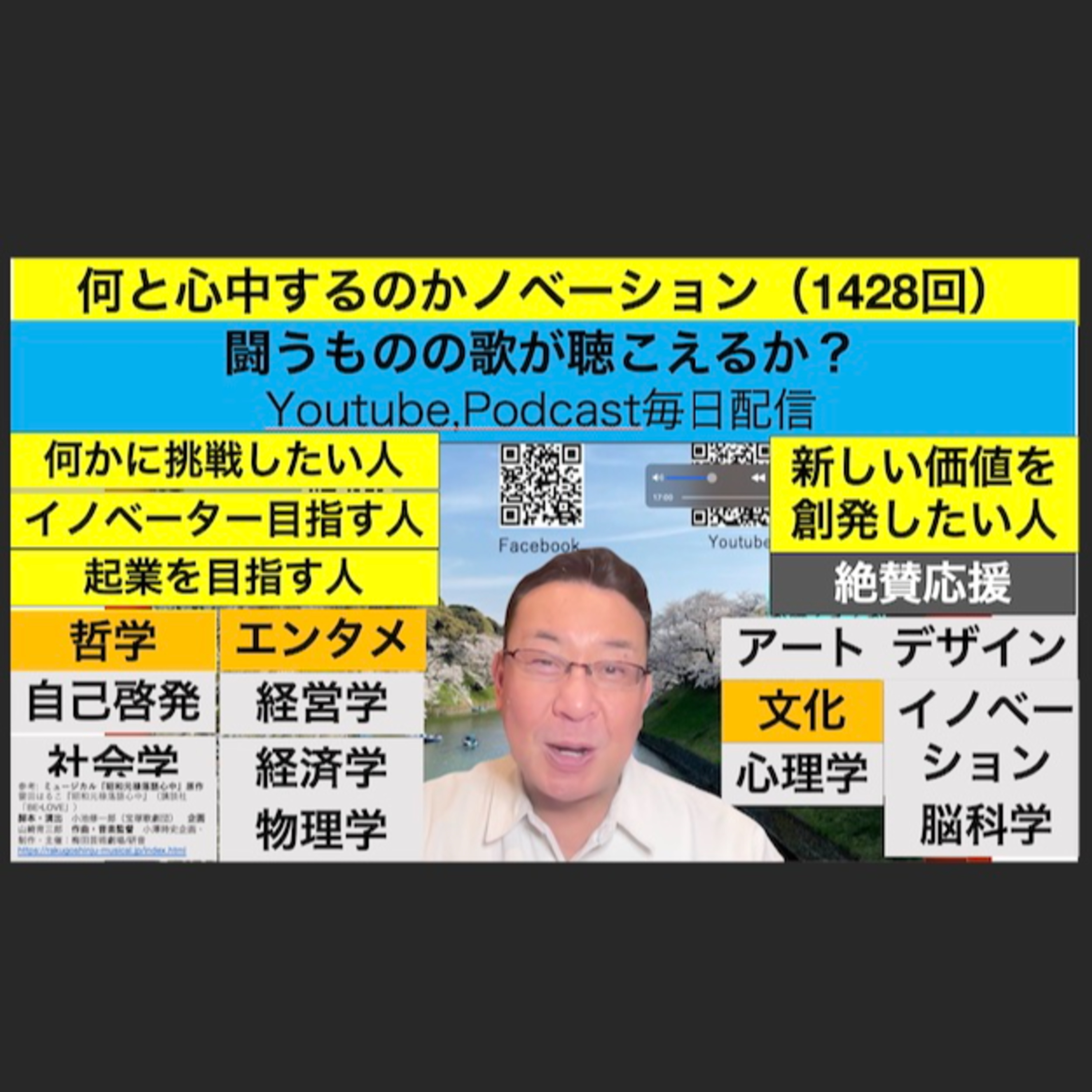 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"何と心中するのかノベーション(1428回)ミュージカル『昭和元禄落語心中』に、企画をされた山崎育三郎さんのパッションと、凄まじいイノベーティブな作品に、感動しまくりましたキャッチコピーは"山崎育三郎×明日海りお×古川雄大が豪華共演︕落語界の愛と業を描く、渾身のオリジナルミュージカル︕"ここから私は思いました1.、話芸×歌芸2、何と心中するのか3、愛とは何か?私の中では、今の日本を代表するトップ3の山崎育三郎さん、明日海りおさん、古川雄大さんが共演すると言うだけで、もう狂喜乱舞の状態で、感涙で涙が止まりませんでした。1.、話芸×歌芸まずは、落語という話芸と、ミュージカルという歌芸を掛け合わせると言うことに、挑戦されたことに、心から尊敬と拍手を送りたく思いました。シュンペーターさんの言われる、既存のアイデアと既存のアイディアを掛け合わせること、そしてそれぞれが異質であればあるほど、面白いイノベーションになる、と言うことをまさに実現されたと。見方を変えれば、日本の伝統×西洋の伝統、個人技×集団技、静×動、さらざまな要素の全く違う要素を掛け合わせることになり、全くみたことのないミュージカルとした衝撃でした。2、何と心中するのかそして、今回のタイトルにもあるとおり、心中というと、男女が添い遂げるみたいなことなのかと思っていましたが、実は違う意味の心中が含まれているのだなあと思いましたそれは、主人公は、落語が好きで好きで、落語と心中したいみたいな、人間だったので、ここで言ってる心中とは、実はパッションの源の1番強い部分のことを言ってるのかもしれないと思いました自分が今、心中してもいい、みたいなくらいにパッションの源が炸裂ことって何かあるかなあと、思ってしまいました。それは、今なくても良くて、チクセントミハイさんのフローのように、やらされてることだったとしても、技術軸と挑戦軸が登っていけるのなら、後天的にだって、心中するほどなことはできてくる、そんなことも思わせて頂きました3、愛ってなんだそして、このミュージカルの一番のテーマなのかもしれないと思ったのは、愛ってなんだ、ということかもしれないなあと思いましたこの物語では、男女愛はもちろんのこと、師弟愛や親子愛、友達愛などがたくさん入り乱れて、それがもつれていくのですが、そこで思ったのはエーリッヒ・フロムの「愛するということ」中にある、「愛は支配するものではなく、相手を自由にするものである」という言葉で例えば、上司部下の中で、上司が部下を愛してるからこそ、新規案件を通さない、みたいなことは、あってはならないなあと、思いました笑格言として、新規案件は最初は上司に相談するな、という格言があるほど、よくあることなのかなあと思いながら、そこに愛があるのであれば、ある程度自由にしてあげる中で、ダメだったらけつ拭いてやる、上司は、フロムの愛するということ、にかなってるのかもしれないと今回の物語の中に渦巻く、愛があるからこそ、さまざまな嫉妬も、憎悪も、別れもある、みたいなことから、つくづく思わせて頂きましたということで、話芸×歌芸であり、何と心中するのか、愛ってなんだ、みたいな問いを投げかけてくれる、めちゃくちゃイノベーティブでファンタスティックな素敵なミュージカルでした一言で言えば何と心中するのかノベーションそんなことを思いました^ ^参考: ミュージカル『昭和元禄落語心中』原作 雲田はるこ『昭和元禄落語心中』(講談社「BE•LOVE」)脚本・演出 小池修一郎(宝塚歌劇団) 企画 山崎育三郎 作曲・音楽監督 小澤時史企画・制作・主催:梅田芸術劇場/研音 https://rakugoshinju-musical.jp/index.html動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/ffrfGZ6CBMU2025-03-1826 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"何と心中するのかノベーション(1428回)ミュージカル『昭和元禄落語心中』に、企画をされた山崎育三郎さんのパッションと、凄まじいイノベーティブな作品に、感動しまくりましたキャッチコピーは"山崎育三郎×明日海りお×古川雄大が豪華共演︕落語界の愛と業を描く、渾身のオリジナルミュージカル︕"ここから私は思いました1.、話芸×歌芸2、何と心中するのか3、愛とは何か?私の中では、今の日本を代表するトップ3の山崎育三郎さん、明日海りおさん、古川雄大さんが共演すると言うだけで、もう狂喜乱舞の状態で、感涙で涙が止まりませんでした。1.、話芸×歌芸まずは、落語という話芸と、ミュージカルという歌芸を掛け合わせると言うことに、挑戦されたことに、心から尊敬と拍手を送りたく思いました。シュンペーターさんの言われる、既存のアイデアと既存のアイディアを掛け合わせること、そしてそれぞれが異質であればあるほど、面白いイノベーションになる、と言うことをまさに実現されたと。見方を変えれば、日本の伝統×西洋の伝統、個人技×集団技、静×動、さらざまな要素の全く違う要素を掛け合わせることになり、全くみたことのないミュージカルとした衝撃でした。2、何と心中するのかそして、今回のタイトルにもあるとおり、心中というと、男女が添い遂げるみたいなことなのかと思っていましたが、実は違う意味の心中が含まれているのだなあと思いましたそれは、主人公は、落語が好きで好きで、落語と心中したいみたいな、人間だったので、ここで言ってる心中とは、実はパッションの源の1番強い部分のことを言ってるのかもしれないと思いました自分が今、心中してもいい、みたいなくらいにパッションの源が炸裂ことって何かあるかなあと、思ってしまいました。それは、今なくても良くて、チクセントミハイさんのフローのように、やらされてることだったとしても、技術軸と挑戦軸が登っていけるのなら、後天的にだって、心中するほどなことはできてくる、そんなことも思わせて頂きました3、愛ってなんだそして、このミュージカルの一番のテーマなのかもしれないと思ったのは、愛ってなんだ、ということかもしれないなあと思いましたこの物語では、男女愛はもちろんのこと、師弟愛や親子愛、友達愛などがたくさん入り乱れて、それがもつれていくのですが、そこで思ったのはエーリッヒ・フロムの「愛するということ」中にある、「愛は支配するものではなく、相手を自由にするものである」という言葉で例えば、上司部下の中で、上司が部下を愛してるからこそ、新規案件を通さない、みたいなことは、あってはならないなあと、思いました笑格言として、新規案件は最初は上司に相談するな、という格言があるほど、よくあることなのかなあと思いながら、そこに愛があるのであれば、ある程度自由にしてあげる中で、ダメだったらけつ拭いてやる、上司は、フロムの愛するということ、にかなってるのかもしれないと今回の物語の中に渦巻く、愛があるからこそ、さまざまな嫉妬も、憎悪も、別れもある、みたいなことから、つくづく思わせて頂きましたということで、話芸×歌芸であり、何と心中するのか、愛ってなんだ、みたいな問いを投げかけてくれる、めちゃくちゃイノベーティブでファンタスティックな素敵なミュージカルでした一言で言えば何と心中するのかノベーションそんなことを思いました^ ^参考: ミュージカル『昭和元禄落語心中』原作 雲田はるこ『昭和元禄落語心中』(講談社「BE•LOVE」)脚本・演出 小池修一郎(宝塚歌劇団) 企画 山崎育三郎 作曲・音楽監督 小澤時史企画・制作・主催:梅田芸術劇場/研音 https://rakugoshinju-musical.jp/index.html動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/ffrfGZ6CBMU2025-03-1826 min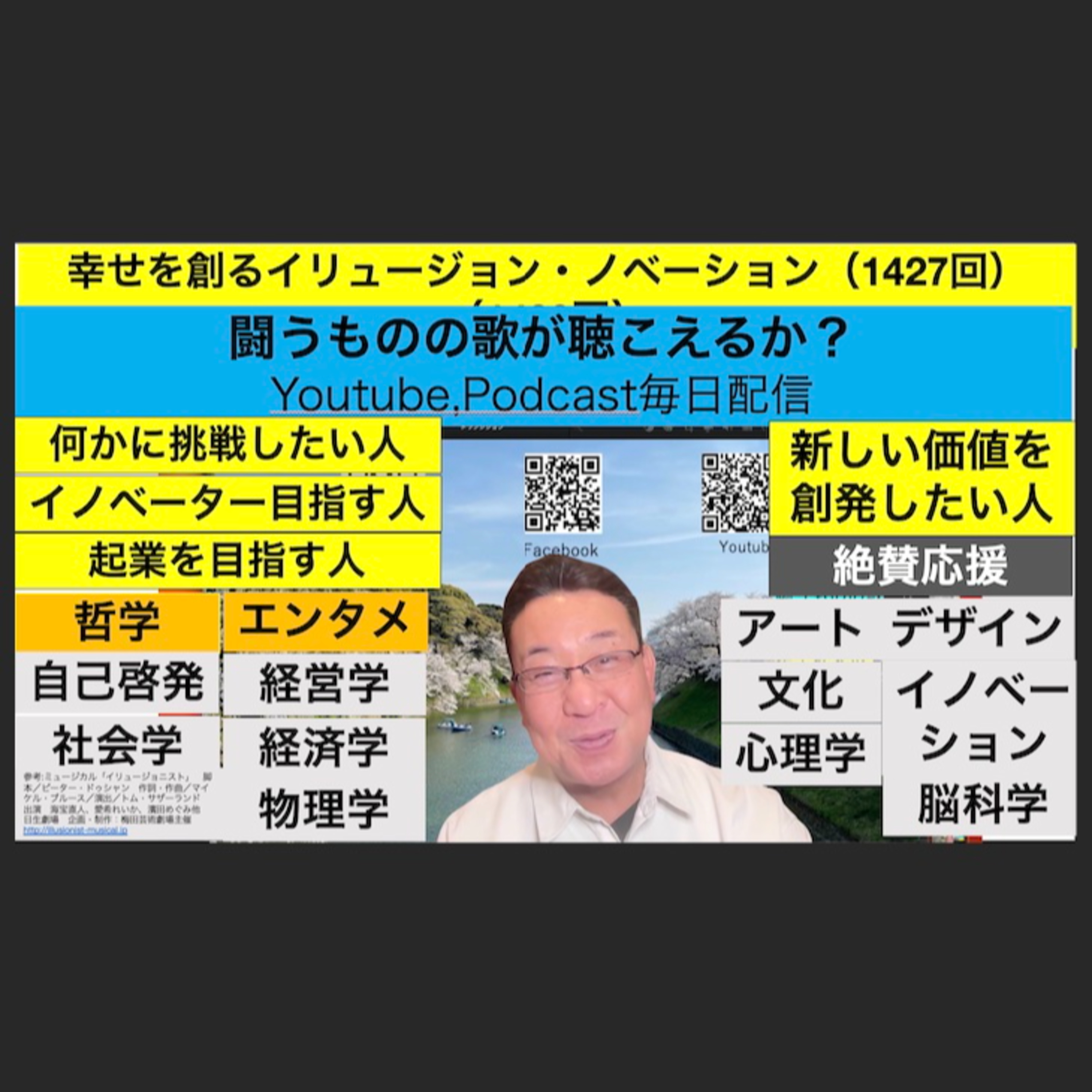 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"幸せを創るイリュージョン・ノベーション(1427回)ミュージカル イリュージョニストのめちゃくちゃイノベーティブな内容に、衝撃を頂きました"何のために人は嘘をつき、仮面を被り、虚構を作り上げるのか。""イリュージョニスト・アイゼンハイム(海宝直人)は、興行主ジーガ(濱田めぐみ)と共に世界中を巡業していた。ウィーンでの公演中、偶然にもアイゼンハイムは幼い頃恋心を寄せ合った公爵令嬢、ソフィ(愛希れいか)と再会する。 だが、ソフィはオーストリア皇太子レオポルド(成河ソンハ)の婚約者となっていた。"ここから、私は本作のイノベーティブなポイントについて思いました1、現実と虚構の曖昧さ→ ボードリヤールの「シミュラークル」2、虚構による情熱の源の追求→ サルトルの「実存は本質に先立つ」3、時間と運命の操作→ニーチェの「永劫回帰」主役の海宝直人さん、そして愛希れいかさん、濱田めぐみさんの歌声が素晴らしすぎて、それだけでも感動だったのですが、物語と演出がまさにイリュージョンで、幻惑されっぱなしで、衝撃を頂きました主役のイリュージョニストのアイゼンハイムは、魔法のようなイリュージョンをして観客を魅せる役柄なのですが、物語自体が、これは現実なのか?虚構なのか?わからなくなる絶妙な演出で、境目がわからなくなる体験でしたフランスの哲学者ボードリヤールが、「現実の代替物が現実そのものよりもリアルに感じられるとき、シミュラークルが完成する。」と言われているように、現実に生きていると思ってる自分自身、これが本当に現実なのか、わからなくなるなあと思ってしまいました。以前、満島ひかりさんが言われていた、"人生は茶番よ"(人生は茶番ノベーション(1158回))の言葉のように、何を信じていいのか?ではなく、その場を楽しんでいく、そんな心持ちが大切かもしれないなあと思わせて頂きましたまた、主人公は時の権力からの圧力にも、あくまでイリュージョニストととしての、生き方を貫いていく姿は、まさに自らの情熱の源に、あくまでも正直に生き続けていく自己実現を貫いていくことに、感動しましたここがまたイノベーティブで、つまり、虚構で自己実現をしていく構造になるわけで、サルトルの実存主義のように、行動で自己実現を目指すのですが、その行動が虚構なので、虚構で自己実現を目指すという、逆サルトル的な構造ができてるなあと思いましたそしてもっともイノベーティブな点は、イリュージョンによって、時間と運命を操つるストーリーにあって、それはまるでニーチェの「永劫回帰」のように、「君はこの人生をもう一度、無数に繰り返して生きることができるか」という問いと向き合わざるを得なくなる、そんな体験に度肝を抜かれましたタイムリープものは、最近のドラマやアニメでもお馴染みで、私も大好きなのですが、あくまでもイリュージョンの中でそれを私は感じさせて頂き、驚愕の一言でしたということで、ことごとく、イリュージョンとイノベーションに満ち溢れた作品であり、かつミュージカルの歌が劇的に良いという、贅沢な体験をさせて頂きました私はよくビジネスの際に、イリュージョンを創ろう、と言う話をしていたことがあって、嘘をつくわけではないけれども、驚きとワクワクと最後には幸せな感じができればいいなあと、思っててイリュージョンは、ビジネスにも、さまざまな場面にも、実は工夫次第で使っていける素敵なものだなあと思いました一言で言うとイリュージョンで権力への対抗もできるし、幸せを作ることができる、そこに必要なのは諦めないパッションと研ぎ澄まされたスキルである幸せを創るイリュージョン・ノベーションそんなことを思いました参考:ミュージカル「イリュージョニスト」 脚本/ピーター・ドゥシャン 作詞・作曲/マイケル・ブルース/演出/トム・サザーランド 出演 海宝直人、愛希れいか、濱田めぐみ他 日生劇場 企画・制作:梅田芸術劇場主催 http://illusionist-musical.jp動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/qg2zhIDHeLY2025-03-1718 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"幸せを創るイリュージョン・ノベーション(1427回)ミュージカル イリュージョニストのめちゃくちゃイノベーティブな内容に、衝撃を頂きました"何のために人は嘘をつき、仮面を被り、虚構を作り上げるのか。""イリュージョニスト・アイゼンハイム(海宝直人)は、興行主ジーガ(濱田めぐみ)と共に世界中を巡業していた。ウィーンでの公演中、偶然にもアイゼンハイムは幼い頃恋心を寄せ合った公爵令嬢、ソフィ(愛希れいか)と再会する。 だが、ソフィはオーストリア皇太子レオポルド(成河ソンハ)の婚約者となっていた。"ここから、私は本作のイノベーティブなポイントについて思いました1、現実と虚構の曖昧さ→ ボードリヤールの「シミュラークル」2、虚構による情熱の源の追求→ サルトルの「実存は本質に先立つ」3、時間と運命の操作→ニーチェの「永劫回帰」主役の海宝直人さん、そして愛希れいかさん、濱田めぐみさんの歌声が素晴らしすぎて、それだけでも感動だったのですが、物語と演出がまさにイリュージョンで、幻惑されっぱなしで、衝撃を頂きました主役のイリュージョニストのアイゼンハイムは、魔法のようなイリュージョンをして観客を魅せる役柄なのですが、物語自体が、これは現実なのか?虚構なのか?わからなくなる絶妙な演出で、境目がわからなくなる体験でしたフランスの哲学者ボードリヤールが、「現実の代替物が現実そのものよりもリアルに感じられるとき、シミュラークルが完成する。」と言われているように、現実に生きていると思ってる自分自身、これが本当に現実なのか、わからなくなるなあと思ってしまいました。以前、満島ひかりさんが言われていた、"人生は茶番よ"(人生は茶番ノベーション(1158回))の言葉のように、何を信じていいのか?ではなく、その場を楽しんでいく、そんな心持ちが大切かもしれないなあと思わせて頂きましたまた、主人公は時の権力からの圧力にも、あくまでイリュージョニストととしての、生き方を貫いていく姿は、まさに自らの情熱の源に、あくまでも正直に生き続けていく自己実現を貫いていくことに、感動しましたここがまたイノベーティブで、つまり、虚構で自己実現をしていく構造になるわけで、サルトルの実存主義のように、行動で自己実現を目指すのですが、その行動が虚構なので、虚構で自己実現を目指すという、逆サルトル的な構造ができてるなあと思いましたそしてもっともイノベーティブな点は、イリュージョンによって、時間と運命を操つるストーリーにあって、それはまるでニーチェの「永劫回帰」のように、「君はこの人生をもう一度、無数に繰り返して生きることができるか」という問いと向き合わざるを得なくなる、そんな体験に度肝を抜かれましたタイムリープものは、最近のドラマやアニメでもお馴染みで、私も大好きなのですが、あくまでもイリュージョンの中でそれを私は感じさせて頂き、驚愕の一言でしたということで、ことごとく、イリュージョンとイノベーションに満ち溢れた作品であり、かつミュージカルの歌が劇的に良いという、贅沢な体験をさせて頂きました私はよくビジネスの際に、イリュージョンを創ろう、と言う話をしていたことがあって、嘘をつくわけではないけれども、驚きとワクワクと最後には幸せな感じができればいいなあと、思っててイリュージョンは、ビジネスにも、さまざまな場面にも、実は工夫次第で使っていける素敵なものだなあと思いました一言で言うとイリュージョンで権力への対抗もできるし、幸せを作ることができる、そこに必要なのは諦めないパッションと研ぎ澄まされたスキルである幸せを創るイリュージョン・ノベーションそんなことを思いました参考:ミュージカル「イリュージョニスト」 脚本/ピーター・ドゥシャン 作詞・作曲/マイケル・ブルース/演出/トム・サザーランド 出演 海宝直人、愛希れいか、濱田めぐみ他 日生劇場 企画・制作:梅田芸術劇場主催 http://illusionist-musical.jp動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/qg2zhIDHeLY2025-03-1718 min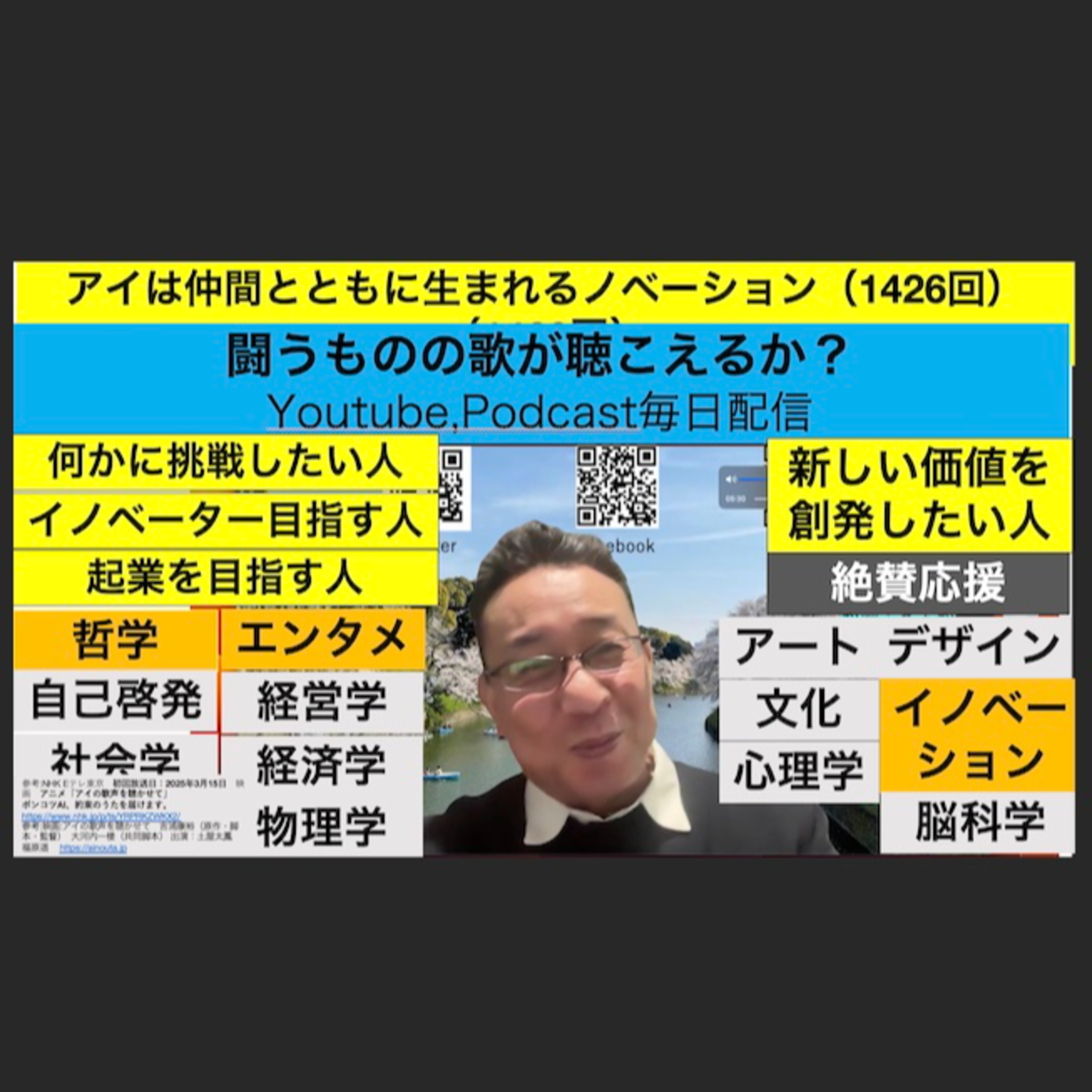 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"アイは仲間とともに生まれるノベーション(1426回)アニメ映画「アイの歌声を聴かせて」に大号泣とともに、人、心、愛とは何か?について、深く考えさせられました。ホームページには以下のようにあります"景部高等学校に転入してきた謎の少女・芦森詩音は、抜群の運動神経と天真らんまんな性格で学校の人気者になる。が、実は試験中の【AI】だった!"ここから以下の3つの問いを私は思いました1、人間らしいとは?「存在とは何か」ハイデガー2、心とは?「他者との関係に自己は生まれる」メルローポンティ3、愛とは?「愛とは他者を無条件に受け入れること」エマニュエル・レヴィ久しぶりに大号泣してしまった映画に出会えて、本当に素敵な誕生日プレゼントになりました。もう中盤くらいから、涙が止まらなくて、最後はこんなに感動させて頂けるとは?本当に素敵な映画でした。まず思ったのは、人間らしいって、なんなのか?と言うことを、考えてしまいました。ここで登場する、女子高生AIのシオンは、最初はポンコツでも、どんどん人間らしく見えてきます。ハイデガーの、「存在とは何か?」という問いのように、AIが人間のように感情を持ち、記憶を引き継ぎ、他者と関係を築くとき、それは「存在している」と言えるんじゃないか?それは存在してないと言えないとは何か?みたいな問いを与えて頂きました。また、シオンが、人間のように成長していく過程には、"仲間"の存在がとても重要な役割を果たしているなあと、言うことも思いました。メルローポンティが、「私たちは他者との関係を通じて自己を形成する」と言われた通り、実は、我々自身が我々自身になった理由は、仲間の存在との関わりの中で育まれたものなのだとするとそれは、対象がAIだろうが、動物だろうが、我々と仲間として濃密に過ごした日々があれば、そこには信頼関係やそして、喜びや悲しみなどの感情自体も生まれてくるのではないか?単なるデータの記録ではなく、感情の記憶というものが生まれてるのでは?そんなことも思わせて頂きましたそして、もう一つとして、シオンが徹底的に、サトミや仲間たち「幸せになってほしい」と支援し続ける姿には、愛を感じざるを得ないと思いました。それはプログラムだということもできるのですが、レヴィナスが言われた「愛とは他者を無条件に受け入れること」を思い出して、これってもはや愛なんじゃないの?と人間かどうか、さらには生物かどうか、はほとんどどうでも良くて、真の仲間との信頼や、共に過ごした時間などを通じて、誰かのために何かをしたか、ということや、その記憶の中に愛が生まれるのかもなあと、いやむしろ、初めて愛を知る存在だからこそ、最も純粋な愛を知ってるのかもしれないそんなことを思いましたひとことでいうと、アイは仲間とともに生まれるノベーションそんなことを思いました^ ^ 参考:NHK Eテレ東京 初回放送日:2025年3月15日 映画 アニメ「アイの歌声を聴かせて」ポンコツAI、約束のうたを届けます。https://www.nhk.jp/p/ts/YRPRKZWKX2/参考:映画:アイの歌声を聴かせて 吉浦康裕(原作・脚本・監督) 大河内一楼(共同脚本) 出演:土屋太鳳 福原遥 https://ainouta.jp動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/SzrFPpv2dgw2025-03-1620 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"アイは仲間とともに生まれるノベーション(1426回)アニメ映画「アイの歌声を聴かせて」に大号泣とともに、人、心、愛とは何か?について、深く考えさせられました。ホームページには以下のようにあります"景部高等学校に転入してきた謎の少女・芦森詩音は、抜群の運動神経と天真らんまんな性格で学校の人気者になる。が、実は試験中の【AI】だった!"ここから以下の3つの問いを私は思いました1、人間らしいとは?「存在とは何か」ハイデガー2、心とは?「他者との関係に自己は生まれる」メルローポンティ3、愛とは?「愛とは他者を無条件に受け入れること」エマニュエル・レヴィ久しぶりに大号泣してしまった映画に出会えて、本当に素敵な誕生日プレゼントになりました。もう中盤くらいから、涙が止まらなくて、最後はこんなに感動させて頂けるとは?本当に素敵な映画でした。まず思ったのは、人間らしいって、なんなのか?と言うことを、考えてしまいました。ここで登場する、女子高生AIのシオンは、最初はポンコツでも、どんどん人間らしく見えてきます。ハイデガーの、「存在とは何か?」という問いのように、AIが人間のように感情を持ち、記憶を引き継ぎ、他者と関係を築くとき、それは「存在している」と言えるんじゃないか?それは存在してないと言えないとは何か?みたいな問いを与えて頂きました。また、シオンが、人間のように成長していく過程には、"仲間"の存在がとても重要な役割を果たしているなあと、言うことも思いました。メルローポンティが、「私たちは他者との関係を通じて自己を形成する」と言われた通り、実は、我々自身が我々自身になった理由は、仲間の存在との関わりの中で育まれたものなのだとするとそれは、対象がAIだろうが、動物だろうが、我々と仲間として濃密に過ごした日々があれば、そこには信頼関係やそして、喜びや悲しみなどの感情自体も生まれてくるのではないか?単なるデータの記録ではなく、感情の記憶というものが生まれてるのでは?そんなことも思わせて頂きましたそして、もう一つとして、シオンが徹底的に、サトミや仲間たち「幸せになってほしい」と支援し続ける姿には、愛を感じざるを得ないと思いました。それはプログラムだということもできるのですが、レヴィナスが言われた「愛とは他者を無条件に受け入れること」を思い出して、これってもはや愛なんじゃないの?と人間かどうか、さらには生物かどうか、はほとんどどうでも良くて、真の仲間との信頼や、共に過ごした時間などを通じて、誰かのために何かをしたか、ということや、その記憶の中に愛が生まれるのかもなあと、いやむしろ、初めて愛を知る存在だからこそ、最も純粋な愛を知ってるのかもしれないそんなことを思いましたひとことでいうと、アイは仲間とともに生まれるノベーションそんなことを思いました^ ^ 参考:NHK Eテレ東京 初回放送日:2025年3月15日 映画 アニメ「アイの歌声を聴かせて」ポンコツAI、約束のうたを届けます。https://www.nhk.jp/p/ts/YRPRKZWKX2/参考:映画:アイの歌声を聴かせて 吉浦康裕(原作・脚本・監督) 大河内一楼(共同脚本) 出演:土屋太鳳 福原遥 https://ainouta.jp動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/SzrFPpv2dgw2025-03-1620 min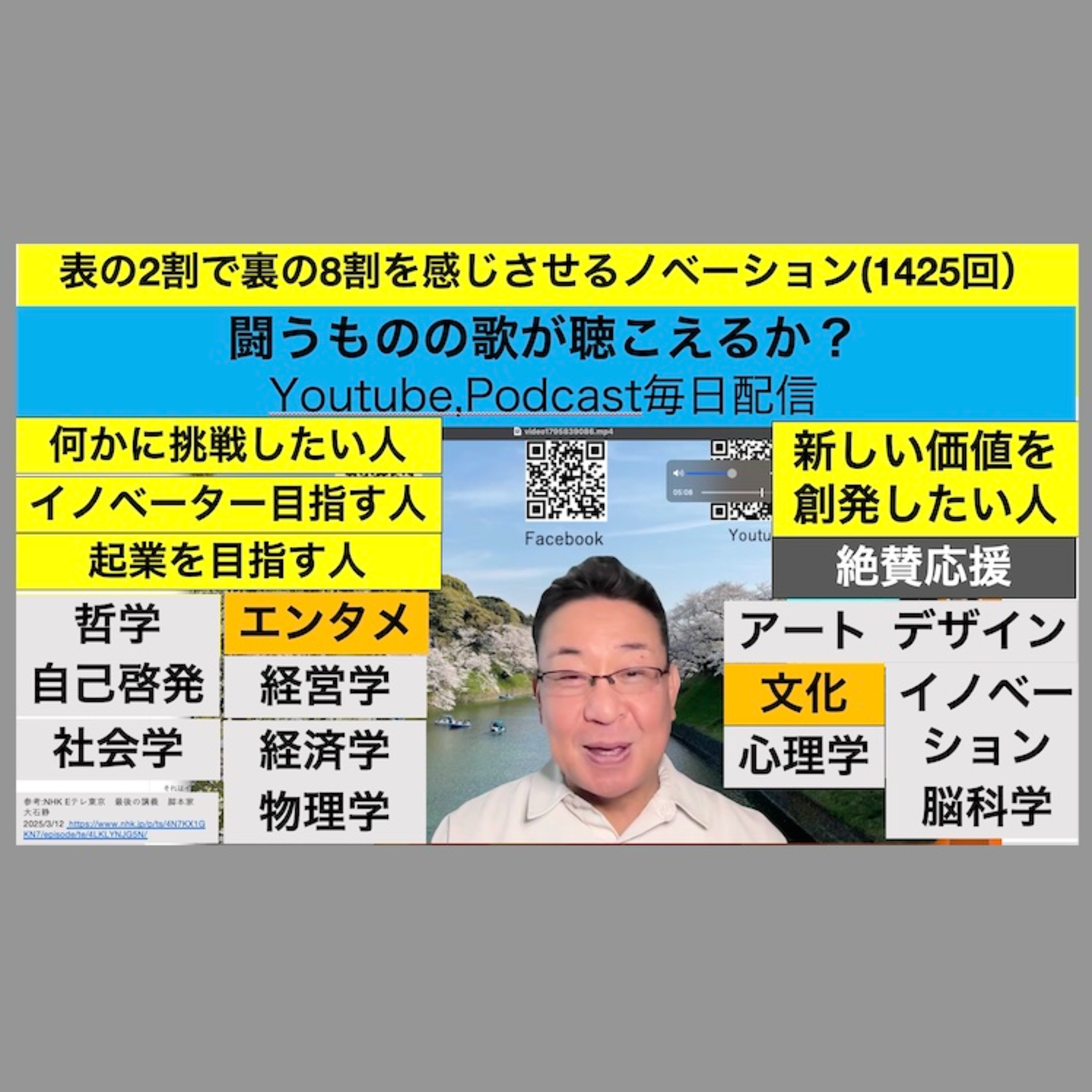 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"表の2割で裏の8割を感じさせるノベーション(1425回)脚本家の大石静さんが、何にこだわって脚本を書いているか、に関する考え方に、真のイノベーターマインドを頂きました曰く"常に意識している事は、規制の価値観を疑ってみると言うことです。さっきの全共闘の話もそうですけど、世間で正しいと言われていることが、誰にとっても正しいのか、必ずそれを考えてみることをドラマの中でやりたいと思っています。""不倫を肯定したり、奨励したりする気持ちではありません。しかし、常識の向こう側にあるもの、規制の価値観の向こう側にあるものを見ようとする心が私たちには必要なのではないかと思います。この世の真実を探し続けてドラマを描き続けたいと思っています。"ここから私は思いました1、「反証可能性」by カール・ポパー→クリティカルシンキング2、「善悪の彼岸」by ニーチェ→ラテラルシンキング3、「方法的懐疑」by デカルト→グリッド大石静さんの作品は最近では、"光る君へ"が空前の大ヒットとなってる、私の大好きなドラマの一つでもあるのですが、その秘密がやはりイノベーターマインドに溢れているからこそ、惹きつけているのだなあということが、改めてわかりました一つは、カール・ポパーさんが言われている、「反証可能性」のように、常日頃から物事の表側だけでなく、裏側に何があるのか?自分たちが当たり前に思っていることが、本当にそれで良いのか?ということを、反証し続けるマインドセットを持たれているんだなあと思いましたそれはイノベーションの世界で言うと、クリティカルシンキングのように、常に批判的な思考をすると言うことにつながってるかと思います。新しいことは良い面悪い面考えますが、難しいのは、当たり前になっていることに、この目を持つことこそが、良き脚本、またはイノベーションの種を見つける源泉かと思いましたまた、不倫のような一般的に不道徳と思われることについての切り込みが、ドラマの中ではめちゃくちゃ面白いのですが、その秘密として、ニーチェの「善悪の彼岸」を思い出しました。例えば、愛する人を守るために嘘をつくことみたいに、愛からなされること」は「善悪の判断を超える」と言うような問いかけが、一層ドラマを面白くしているのかもしれないなあと改めて思いました。これはイノベーション的な話からすると、普段の常識に違う観点から、そもそもを問い直す、ラテラルシンキング的な考え方にもつながるなあと思いました。そして、そういった挑戦を常に疑い続けながら諦めずに突き進む姿勢は、デカルトの、「方法的懐疑」のように、常に真実を追い続け、疑い続け、問い続け、そして諦めない、グリッドな姿勢も、ひしひしと感じましたさらにそこから驚愕なのは"表の2割で裏の8割を感じさせるのが脚本の仕事で、小説よりもテクニックがいると私は思っているんですけれども"とおっしゃっていたように、そういった数々の規制の価値観を揺るがす思考を、裏に隠れていながらも沸々と湧いている思いを、脚本家の物凄い技術で見事に表の2割で描くという、圧倒的スキルを持たれている、真のイノベーターなのだなあと、感動させて頂きました一言で言うと表の2割で裏の8割を感じさせるノベーションそんなことを感じました^ ^参考:NHK Eテレ東京 最後の講義 脚本家 大石静 2025/3/12 https://www.nhk.jp/p/ts/4N7KX1GKN7/episode/te/4LKLYNJG5N/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/k2J2-vmqhLM2025-03-1516 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"表の2割で裏の8割を感じさせるノベーション(1425回)脚本家の大石静さんが、何にこだわって脚本を書いているか、に関する考え方に、真のイノベーターマインドを頂きました曰く"常に意識している事は、規制の価値観を疑ってみると言うことです。さっきの全共闘の話もそうですけど、世間で正しいと言われていることが、誰にとっても正しいのか、必ずそれを考えてみることをドラマの中でやりたいと思っています。""不倫を肯定したり、奨励したりする気持ちではありません。しかし、常識の向こう側にあるもの、規制の価値観の向こう側にあるものを見ようとする心が私たちには必要なのではないかと思います。この世の真実を探し続けてドラマを描き続けたいと思っています。"ここから私は思いました1、「反証可能性」by カール・ポパー→クリティカルシンキング2、「善悪の彼岸」by ニーチェ→ラテラルシンキング3、「方法的懐疑」by デカルト→グリッド大石静さんの作品は最近では、"光る君へ"が空前の大ヒットとなってる、私の大好きなドラマの一つでもあるのですが、その秘密がやはりイノベーターマインドに溢れているからこそ、惹きつけているのだなあということが、改めてわかりました一つは、カール・ポパーさんが言われている、「反証可能性」のように、常日頃から物事の表側だけでなく、裏側に何があるのか?自分たちが当たり前に思っていることが、本当にそれで良いのか?ということを、反証し続けるマインドセットを持たれているんだなあと思いましたそれはイノベーションの世界で言うと、クリティカルシンキングのように、常に批判的な思考をすると言うことにつながってるかと思います。新しいことは良い面悪い面考えますが、難しいのは、当たり前になっていることに、この目を持つことこそが、良き脚本、またはイノベーションの種を見つける源泉かと思いましたまた、不倫のような一般的に不道徳と思われることについての切り込みが、ドラマの中ではめちゃくちゃ面白いのですが、その秘密として、ニーチェの「善悪の彼岸」を思い出しました。例えば、愛する人を守るために嘘をつくことみたいに、愛からなされること」は「善悪の判断を超える」と言うような問いかけが、一層ドラマを面白くしているのかもしれないなあと改めて思いました。これはイノベーション的な話からすると、普段の常識に違う観点から、そもそもを問い直す、ラテラルシンキング的な考え方にもつながるなあと思いました。そして、そういった挑戦を常に疑い続けながら諦めずに突き進む姿勢は、デカルトの、「方法的懐疑」のように、常に真実を追い続け、疑い続け、問い続け、そして諦めない、グリッドな姿勢も、ひしひしと感じましたさらにそこから驚愕なのは"表の2割で裏の8割を感じさせるのが脚本の仕事で、小説よりもテクニックがいると私は思っているんですけれども"とおっしゃっていたように、そういった数々の規制の価値観を揺るがす思考を、裏に隠れていながらも沸々と湧いている思いを、脚本家の物凄い技術で見事に表の2割で描くという、圧倒的スキルを持たれている、真のイノベーターなのだなあと、感動させて頂きました一言で言うと表の2割で裏の8割を感じさせるノベーションそんなことを感じました^ ^参考:NHK Eテレ東京 最後の講義 脚本家 大石静 2025/3/12 https://www.nhk.jp/p/ts/4N7KX1GKN7/episode/te/4LKLYNJG5N/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/k2J2-vmqhLM2025-03-1516 min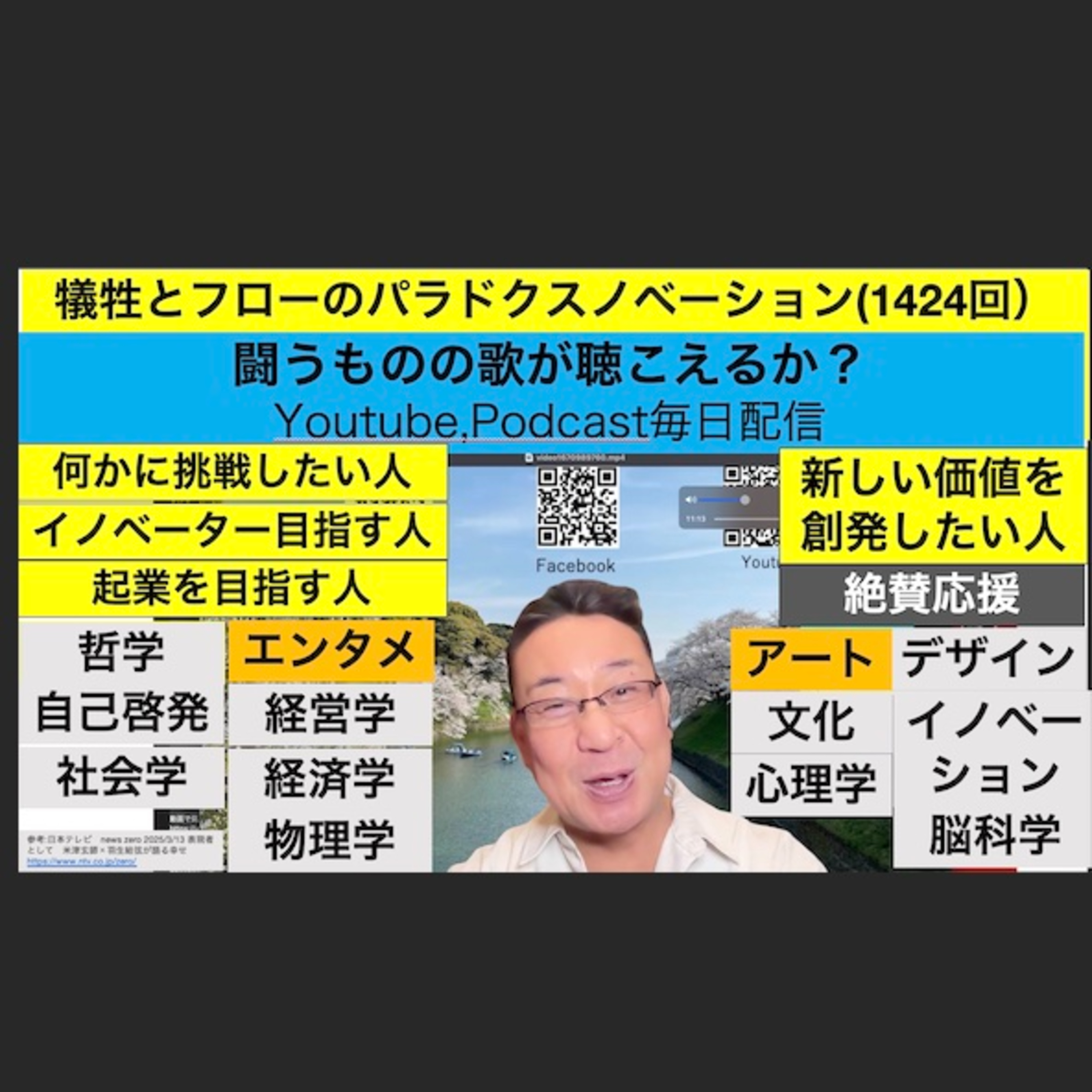 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"犠牲とフローのパラドクスノベーション(1424回)米津玄師さんと羽生結弦さんのコラボされたミュージックビデオ"Bow and ARROW"に向けた対談に心震え、米津玄師さんの言葉に、イノベーターの人の姿を教えて頂きました曰く"すげー可哀想って言われるんだけど、自分にとってはそれが非常に自然なことであって""すごく何かを犠牲にしながら生きてるように見えてるんだろうなって思うし""でも、自分にとっては、犠牲にするしない以前に、それが1番心地いいって言うことだったりするし"ここから私は思いました1、価値観の相対性 →プロタゴラス「人間は万物の尺度である」2、フローと犠牲→チクセントミハイ3、自己理解と他者理解→パッションからイノベーター3つのフレームへ最高すぎるミュージックビデオと、さらにこのお二人が対談されること自体、奇跡のコラボだなと思ったのですが、その内容にさらに感動しました一つは、哲学でいうところの、価値観の相対性、をきちんと持たれているんだなあと言うことです。古くはプロタゴラスさんが言われたという「人間は万物の尺度である括弧という言葉からも自分自身の尺度と他の人尺度は全く違うということを、腹の底から理解することかなと思いました。私の場合は、他の人と自分が違ってたりすると、ついつい、ヤバいかも、なんて汗したりするわけですがそこを他の人と自分は違ってて当然であり、なんて言われようと自分は自然だからいいのである、といい切れるのは、価値観の相対性を理解されてるんだろうなあと思いましたまた、犠牲にしながら生きてるように見えてる、というのは、ある意味、お二人とも、チクセントミハイさんの言われるところの、フローに入ってるからなのかもしれないなと思いました挑戦軸と技能軸の二つの軸が高まることによって、集中と没入が最高レベルに高まるフローになるので、寝食も忘れてそれをやり続けてしまうと本人はそれがとてつもなくに気持ちのいい状態なのだけれども、周りから見ると、たくさんのものを犠牲にしてるように見えてしまう、そんな犠牲と心地よさのパラドックスのようなことが起きてることを理解してるのかなと思いましたそして、そのような自分自身と他の人たちが違うということを、きちんと理解していることが、最も大事だと思いました自分が気持ち良ければそれでいいという、独りよがりではなく、周りの人たちからは、そう見えてることを理解しながら、自分の道を進める、それが自己理解と他者理解を両方できた上でやれてるのが、真のイノベーターかもしれないと思いましたイノベーター3つのフレームで言うと、自己理解でパッションの源から発した"情熱"に100%取り組んで、そして1人だけではなく米津玄師さんと羽生結弦さんのような"仲間"と共に、自分たちだけではなく他の人たちにも心地よい"大義"を提供できるそんな人たちがイノベーターなのだなあと、改めて勉強になりました一言で言うと他者理解をしながら自分が心地良いノベーションまたは他者から見ると犠牲だけどそれはフローなので犠牲とフローのパラドックスノベーションそんなことを思いました参考:日本テレビ news zero 2025/3/13 表現者として 米津玄師×羽生結弦が語る幸せ https://www.ntv.co.jp/zero/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/1hax-YQrAmQ2025-03-1416 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"犠牲とフローのパラドクスノベーション(1424回)米津玄師さんと羽生結弦さんのコラボされたミュージックビデオ"Bow and ARROW"に向けた対談に心震え、米津玄師さんの言葉に、イノベーターの人の姿を教えて頂きました曰く"すげー可哀想って言われるんだけど、自分にとってはそれが非常に自然なことであって""すごく何かを犠牲にしながら生きてるように見えてるんだろうなって思うし""でも、自分にとっては、犠牲にするしない以前に、それが1番心地いいって言うことだったりするし"ここから私は思いました1、価値観の相対性 →プロタゴラス「人間は万物の尺度である」2、フローと犠牲→チクセントミハイ3、自己理解と他者理解→パッションからイノベーター3つのフレームへ最高すぎるミュージックビデオと、さらにこのお二人が対談されること自体、奇跡のコラボだなと思ったのですが、その内容にさらに感動しました一つは、哲学でいうところの、価値観の相対性、をきちんと持たれているんだなあと言うことです。古くはプロタゴラスさんが言われたという「人間は万物の尺度である括弧という言葉からも自分自身の尺度と他の人尺度は全く違うということを、腹の底から理解することかなと思いました。私の場合は、他の人と自分が違ってたりすると、ついつい、ヤバいかも、なんて汗したりするわけですがそこを他の人と自分は違ってて当然であり、なんて言われようと自分は自然だからいいのである、といい切れるのは、価値観の相対性を理解されてるんだろうなあと思いましたまた、犠牲にしながら生きてるように見えてる、というのは、ある意味、お二人とも、チクセントミハイさんの言われるところの、フローに入ってるからなのかもしれないなと思いました挑戦軸と技能軸の二つの軸が高まることによって、集中と没入が最高レベルに高まるフローになるので、寝食も忘れてそれをやり続けてしまうと本人はそれがとてつもなくに気持ちのいい状態なのだけれども、周りから見ると、たくさんのものを犠牲にしてるように見えてしまう、そんな犠牲と心地よさのパラドックスのようなことが起きてることを理解してるのかなと思いましたそして、そのような自分自身と他の人たちが違うということを、きちんと理解していることが、最も大事だと思いました自分が気持ち良ければそれでいいという、独りよがりではなく、周りの人たちからは、そう見えてることを理解しながら、自分の道を進める、それが自己理解と他者理解を両方できた上でやれてるのが、真のイノベーターかもしれないと思いましたイノベーター3つのフレームで言うと、自己理解でパッションの源から発した"情熱"に100%取り組んで、そして1人だけではなく米津玄師さんと羽生結弦さんのような"仲間"と共に、自分たちだけではなく他の人たちにも心地よい"大義"を提供できるそんな人たちがイノベーターなのだなあと、改めて勉強になりました一言で言うと他者理解をしながら自分が心地良いノベーションまたは他者から見ると犠牲だけどそれはフローなので犠牲とフローのパラドックスノベーションそんなことを思いました参考:日本テレビ news zero 2025/3/13 表現者として 米津玄師×羽生結弦が語る幸せ https://www.ntv.co.jp/zero/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/1hax-YQrAmQ2025-03-1416 min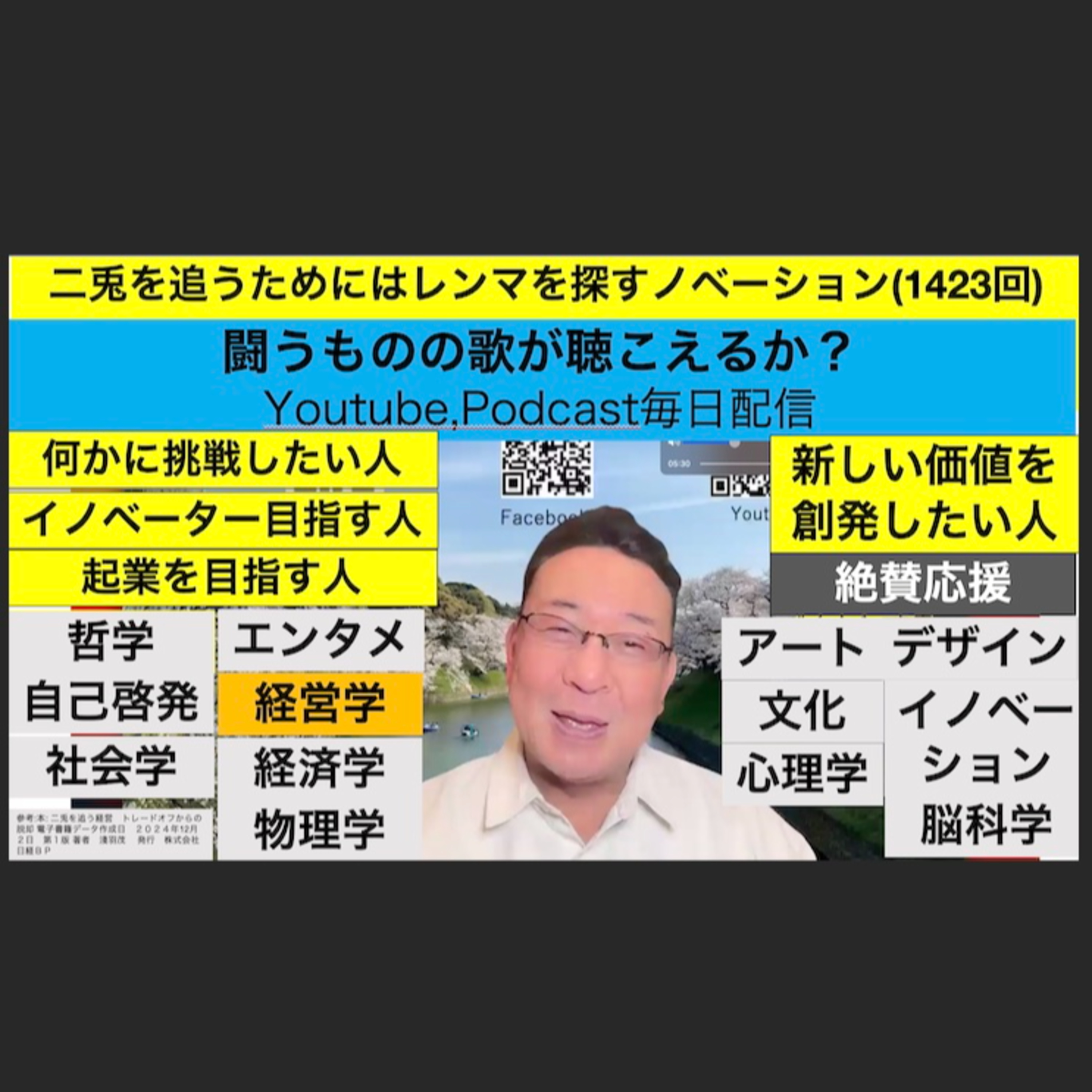 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"二兎を追うためにはレンマを探すノベーション(1423回)早稲田大学大学院経営管理研究科教授の淺羽茂さんからの言葉に共感させて頂きました曰く"このように、トレードオフ関係にある価値に直面した場合、その関係を固定的なものと見るのではなく、3つめの価値を探すことが、二兎戦略につながるかもしれない。視点を変えることによって3つめの価値が見つかれば、3つめの価値をあきらめることによって、あるいは価値のグルーピングを変えることによって、トレードオフ関係にあると思われていた2つの価値がトレードオン関係に変わるかもしれない。そうすれば、二兎戦略を実現できるのである。"ここから私は思いました1.トレードオフを固定的と考えない→ 実はレンマは無数2.第三の価値の発見→ 改めてレンマの洗い出し3.価値のグルーピングの変革→ 改めてレンマの優先を決めるここには、イノベーター的発想がまさに含まれてると思いました。それは、先入観というバイアスに縛られずに、トレードオフを固定的に考えないという発想の転換です。Why not yetをイノベーション創発には繰り返せという話もありますが、永遠の課題と言われているものが、実はトレードオフがあって、それを前提にいろんなことを考えてるということがあると思いますこれを、本当にそれって両方同時に解決できないんだっけという、ある意味、バカじゃないの言われる発想を持つことが大事だなとつくづく思いました実は、トレードオフは、二つのレンマ、つまりジレンマになるわけですが、さらなるレンマを探すということが、実は鍵になると思います世の中は、複雑なので、実は、トリレンマ、クワトロレンマになっている事柄があって、それらが複雑に絡み合ってると言えことを、まずは、洗い出してみることから始めるのが、良いかと思いますその上で、改めて、価値のグルーピングをしてみて、そのレンマの優先順位を決めていく、それによって、自分たちが1番実現したいことを、他のレンマを諦めることによって実現していくことができると、思いました私はこれをよく、ワークショップで、トレードオフオプションと呼んで、とにかくたくさん作ってみようと、やってみると、意外と新しい道筋が見えてくる、そんな経験をなん度もしていますので、とても共感させて頂きました一言で言うと二兎を追うためにはレンマを探すノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 二兎を追う経営 トレードオフからの脱却 電子書籍データ作成日 2024年12月2日 第1版 著者 淺羽茂 発行 株式会社日経BP動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/j7Jv17TkH282025-03-1314 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"二兎を追うためにはレンマを探すノベーション(1423回)早稲田大学大学院経営管理研究科教授の淺羽茂さんからの言葉に共感させて頂きました曰く"このように、トレードオフ関係にある価値に直面した場合、その関係を固定的なものと見るのではなく、3つめの価値を探すことが、二兎戦略につながるかもしれない。視点を変えることによって3つめの価値が見つかれば、3つめの価値をあきらめることによって、あるいは価値のグルーピングを変えることによって、トレードオフ関係にあると思われていた2つの価値がトレードオン関係に変わるかもしれない。そうすれば、二兎戦略を実現できるのである。"ここから私は思いました1.トレードオフを固定的と考えない→ 実はレンマは無数2.第三の価値の発見→ 改めてレンマの洗い出し3.価値のグルーピングの変革→ 改めてレンマの優先を決めるここには、イノベーター的発想がまさに含まれてると思いました。それは、先入観というバイアスに縛られずに、トレードオフを固定的に考えないという発想の転換です。Why not yetをイノベーション創発には繰り返せという話もありますが、永遠の課題と言われているものが、実はトレードオフがあって、それを前提にいろんなことを考えてるということがあると思いますこれを、本当にそれって両方同時に解決できないんだっけという、ある意味、バカじゃないの言われる発想を持つことが大事だなとつくづく思いました実は、トレードオフは、二つのレンマ、つまりジレンマになるわけですが、さらなるレンマを探すということが、実は鍵になると思います世の中は、複雑なので、実は、トリレンマ、クワトロレンマになっている事柄があって、それらが複雑に絡み合ってると言えことを、まずは、洗い出してみることから始めるのが、良いかと思いますその上で、改めて、価値のグルーピングをしてみて、そのレンマの優先順位を決めていく、それによって、自分たちが1番実現したいことを、他のレンマを諦めることによって実現していくことができると、思いました私はこれをよく、ワークショップで、トレードオフオプションと呼んで、とにかくたくさん作ってみようと、やってみると、意外と新しい道筋が見えてくる、そんな経験をなん度もしていますので、とても共感させて頂きました一言で言うと二兎を追うためにはレンマを探すノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 二兎を追う経営 トレードオフからの脱却 電子書籍データ作成日 2024年12月2日 第1版 著者 淺羽茂 発行 株式会社日経BP動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/j7Jv17TkH282025-03-1314 min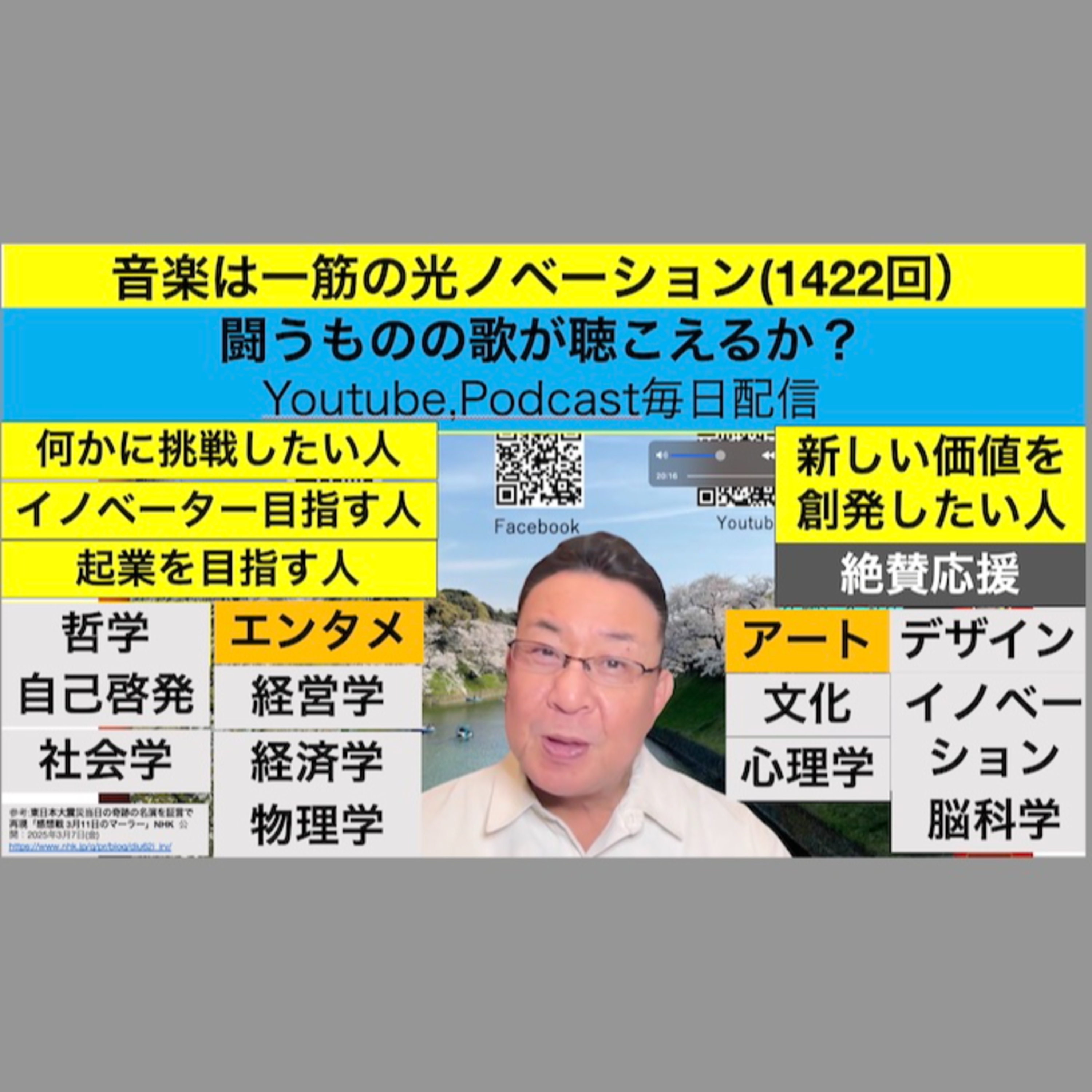 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"音楽は一筋の光ノベーション(1422回)3.11の日に新日本フィルが奇跡の名演をされた中で、その際に演奏されたビオラ奏者の醍醐のり子さんの言葉に震えました曰く"あのトランペットの音色を聞いているうちに、あの音、あの旋律に、私たち音楽家ができることっていうのはフリーズしてしまった感情に、何か、息をふっと吹きかけるようなメッセージを、言葉とか、そういうものではなく五感って言うんですかね、そういうのに訴える力があるのかなって言うような、ちょっとこう一筋の光みたいな訴えを感じたんですよね"ここから私は、音楽の凄まじいイノベーティブな力を思いました思いました1、感情のリセットと再起動 →フリーズした感情に息を吹きかける2、言葉を超えたメッセージ →五感に訴えかける3、一筋の光としての役割 →茨の暗闇を照らす3.11のあの状況の中で、コンサートを開いたというのも、驚きでしたが、その中だからこそ生まれた奇跡の演奏と、そしてその中に、音楽の本当の力というものが見える瞬間だったのかもしれないと思いました醍醐さんが言われる言葉の一つ一つには、その時の奇跡の一端が溢れていると感じましたまさに、何が起きたかわからず、これからもわからずの際に、自分自身もどうしたら良いのか考えられず、相当頭がフリーズしてたような気がしますが音楽の力でそれがふっと溶けていった気がしたというのは、言葉では溶かせない、感情そのものに力を与えてくれる、それが音楽なのかもしれないと思いましたこれはイノベーションの世界にも良く似てて、当たり前だと思って実は思考停止してフリーズしてることに、本当にそれでいいのか?という問いを立てることで、目が覚める、感情の世界と論理の世界と違いますが、役割はとても似てるかもしれないと思いましたまた、五感に訴えかける力を感じる、との言葉からは、感情に直接メッセージを送ることもできるのが音楽だなあという気もします。私はなぜAppleを買ってしまうのか?と思うときに、機能性ももちろんなのですが、それよりもAppleのTHINK DIFERENTが好きだったから、というのも多分にありますSimonSinekさんのゴールデンサークルのように、なぜここに自分はいるのか?と言ったような、大義からお話しされると、そこに感動して、全部買っちゃうみたいな笑そんな感情に語りかけるというのも、イノベーションとよく似てるなあと思いますさらに、一筋の光、ということを言われていましたが、イノベーションの世界では、暗闇の茨の世界をずっと歩いていかなければならないので、一筋の光は全く見えないことが多いけども歩かなきゃいけないそんなときに、勇気を与えてくれるのが、音楽だったりするなあと、つくづく思います。今日は気が重いなあという時も、香港好運の中年不思議国で、めちゃくちゃあげでいけるみたいな笑誰にでも推しの曲があるんじゃないかと思いますが、やはりそれは音楽の凄まじいイノベーティブなポジティブパワーなんだろうと思います以前、(音楽は人を人たらしめんノベーション(1366回))の話の中では、仲間としての絆を感じるための音楽、という話をしましたが今回は、フリーズリセット、言葉を超えるメッセージ、そして、一筋の光としての役割を担う音楽は人を前に進めさせてくれる、より進化する方向へ導いてくれる、なくてはならないものだということを痛感しました一言で言うと音楽は一筋の光ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:東日本大震災当日の奇跡の名演を証言で再現「感想戦 3月11日のマーラー」NHK 公開:2025年3月7日(金) https://www.nhk.jp/g/pr/blog/diu62i_irv/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/GB5XdFIAD6w2025-03-1124 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"音楽は一筋の光ノベーション(1422回)3.11の日に新日本フィルが奇跡の名演をされた中で、その際に演奏されたビオラ奏者の醍醐のり子さんの言葉に震えました曰く"あのトランペットの音色を聞いているうちに、あの音、あの旋律に、私たち音楽家ができることっていうのはフリーズしてしまった感情に、何か、息をふっと吹きかけるようなメッセージを、言葉とか、そういうものではなく五感って言うんですかね、そういうのに訴える力があるのかなって言うような、ちょっとこう一筋の光みたいな訴えを感じたんですよね"ここから私は、音楽の凄まじいイノベーティブな力を思いました思いました1、感情のリセットと再起動 →フリーズした感情に息を吹きかける2、言葉を超えたメッセージ →五感に訴えかける3、一筋の光としての役割 →茨の暗闇を照らす3.11のあの状況の中で、コンサートを開いたというのも、驚きでしたが、その中だからこそ生まれた奇跡の演奏と、そしてその中に、音楽の本当の力というものが見える瞬間だったのかもしれないと思いました醍醐さんが言われる言葉の一つ一つには、その時の奇跡の一端が溢れていると感じましたまさに、何が起きたかわからず、これからもわからずの際に、自分自身もどうしたら良いのか考えられず、相当頭がフリーズしてたような気がしますが音楽の力でそれがふっと溶けていった気がしたというのは、言葉では溶かせない、感情そのものに力を与えてくれる、それが音楽なのかもしれないと思いましたこれはイノベーションの世界にも良く似てて、当たり前だと思って実は思考停止してフリーズしてることに、本当にそれでいいのか?という問いを立てることで、目が覚める、感情の世界と論理の世界と違いますが、役割はとても似てるかもしれないと思いましたまた、五感に訴えかける力を感じる、との言葉からは、感情に直接メッセージを送ることもできるのが音楽だなあという気もします。私はなぜAppleを買ってしまうのか?と思うときに、機能性ももちろんなのですが、それよりもAppleのTHINK DIFERENTが好きだったから、というのも多分にありますSimonSinekさんのゴールデンサークルのように、なぜここに自分はいるのか?と言ったような、大義からお話しされると、そこに感動して、全部買っちゃうみたいな笑そんな感情に語りかけるというのも、イノベーションとよく似てるなあと思いますさらに、一筋の光、ということを言われていましたが、イノベーションの世界では、暗闇の茨の世界をずっと歩いていかなければならないので、一筋の光は全く見えないことが多いけども歩かなきゃいけないそんなときに、勇気を与えてくれるのが、音楽だったりするなあと、つくづく思います。今日は気が重いなあという時も、香港好運の中年不思議国で、めちゃくちゃあげでいけるみたいな笑誰にでも推しの曲があるんじゃないかと思いますが、やはりそれは音楽の凄まじいイノベーティブなポジティブパワーなんだろうと思います以前、(音楽は人を人たらしめんノベーション(1366回))の話の中では、仲間としての絆を感じるための音楽、という話をしましたが今回は、フリーズリセット、言葉を超えるメッセージ、そして、一筋の光としての役割を担う音楽は人を前に進めさせてくれる、より進化する方向へ導いてくれる、なくてはならないものだということを痛感しました一言で言うと音楽は一筋の光ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:東日本大震災当日の奇跡の名演を証言で再現「感想戦 3月11日のマーラー」NHK 公開:2025年3月7日(金) https://www.nhk.jp/g/pr/blog/diu62i_irv/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/GB5XdFIAD6w2025-03-1124 min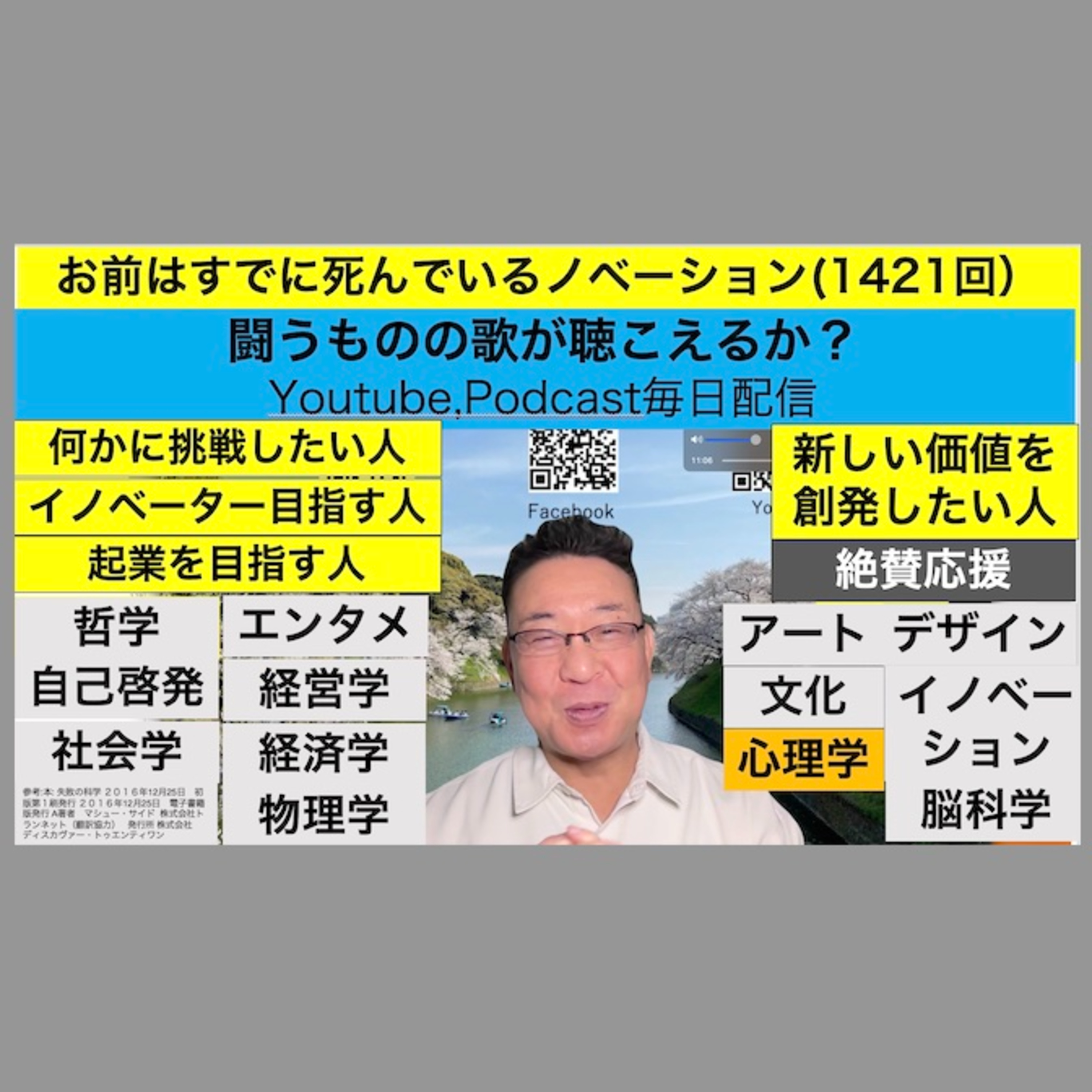 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"お前はすでに死んでいるノベーション(1421回)マシュー・サイドさんの「失敗の科学」から、著名な心理学者ゲイリー・クラインが提唱した「事前検死(pre-mortem)」について衝撃を頂きまきた曰く"これは「検死(post-mortem)」をもじった造語で、プロジェクトが終わったあとではなく、実施前に行う検証を指す。あらかじめプロジェクトが失敗した状態を想定し、「なぜうまくいかなかったのか?」をチームで事前検証していくのだ。""この事前検死は、「失敗するかもしれない」と考えるのとはまったく異なる。チームのメンバーは「プロジェクトは失敗した」「目標は達成できなかった」と伝えられ、いわば「すでに死んでいる」状態から始まって、検死(検証)を行う。このように失敗という抽象的な概念を具体化すると、問題に対する意識の持ち方が変わる。"ここから私は思いました1、逆転の発想2、具体と抽象の往復運動3、心理的安全性"お前はすでに死んでいる"は、めちゃくちゃ私もハマっていたケンシロウの言葉ですが、それを地でいくソリューションがあるとは、驚愕でしたこれは、まさに、逆転の発想、の典型例だなあと思いました。普段は、如何に成功するか?ばかりを考えているチームに、この提案をするのは、ともすると、後ろ向き発言!などと、怒られかねない、話だなと。しかし、実はこれをポジティブに実施することによって、さまざまなこれまでにない効果を創発することができる、というのは、本当にイノベーティブなだなあと思いますその効用のとても大きいものの一つに、具体と抽象の往復運動があると思いました。普段は漠然と考えている失敗というものを、一度きちんと見据えて、みんなで具体化してみようということで、より明確に失敗像が明確になってくると思いますさらにそこから、プロジェクトにおける真の失敗は何なのか?という意見交換をすることで、さらに抽象的な失敗の方向性ということを、みんなで共有することができるのも、我々は何に向かおうとしているのか?また、我々の真の失敗は何か?ということまで、みんなの議論と意識合わせができると、すごく強いチームになる気がしましたそしてもう一つの効果は、心理的安全性かと思います。目に見えないものほど、怖いものはないので、ここで失敗という悪魔の姿を、みんなで明らかにすることで、死の恐怖を乗り越えることができる、そしてそれはみんなでやることによって、チームとしての心理的安全性を高めることができる、そんなことを思いましたイノベーションの世界では、FastFailという言葉もありますが、"事前検死"は、いわゆる早過ぎるFastFailであり逆転の発想からの、具体と抽象の往復運動を促し、心理的安全性をも確保する、めちゃくちゃイノベーティブな手法と思いました一言で言えば"お前はすでに死んでいるノベーション"そんなことを思いました^ ^参考:本: 失敗の科学 2016年12月25日 初版第1刷発行 2016年12月25日 電子書籍版発行 A著者 マシュー・サイド 株式会社トランネット(翻訳協力) 発行所 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン2025-03-1012 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"お前はすでに死んでいるノベーション(1421回)マシュー・サイドさんの「失敗の科学」から、著名な心理学者ゲイリー・クラインが提唱した「事前検死(pre-mortem)」について衝撃を頂きまきた曰く"これは「検死(post-mortem)」をもじった造語で、プロジェクトが終わったあとではなく、実施前に行う検証を指す。あらかじめプロジェクトが失敗した状態を想定し、「なぜうまくいかなかったのか?」をチームで事前検証していくのだ。""この事前検死は、「失敗するかもしれない」と考えるのとはまったく異なる。チームのメンバーは「プロジェクトは失敗した」「目標は達成できなかった」と伝えられ、いわば「すでに死んでいる」状態から始まって、検死(検証)を行う。このように失敗という抽象的な概念を具体化すると、問題に対する意識の持ち方が変わる。"ここから私は思いました1、逆転の発想2、具体と抽象の往復運動3、心理的安全性"お前はすでに死んでいる"は、めちゃくちゃ私もハマっていたケンシロウの言葉ですが、それを地でいくソリューションがあるとは、驚愕でしたこれは、まさに、逆転の発想、の典型例だなあと思いました。普段は、如何に成功するか?ばかりを考えているチームに、この提案をするのは、ともすると、後ろ向き発言!などと、怒られかねない、話だなと。しかし、実はこれをポジティブに実施することによって、さまざまなこれまでにない効果を創発することができる、というのは、本当にイノベーティブなだなあと思いますその効用のとても大きいものの一つに、具体と抽象の往復運動があると思いました。普段は漠然と考えている失敗というものを、一度きちんと見据えて、みんなで具体化してみようということで、より明確に失敗像が明確になってくると思いますさらにそこから、プロジェクトにおける真の失敗は何なのか?という意見交換をすることで、さらに抽象的な失敗の方向性ということを、みんなで共有することができるのも、我々は何に向かおうとしているのか?また、我々の真の失敗は何か?ということまで、みんなの議論と意識合わせができると、すごく強いチームになる気がしましたそしてもう一つの効果は、心理的安全性かと思います。目に見えないものほど、怖いものはないので、ここで失敗という悪魔の姿を、みんなで明らかにすることで、死の恐怖を乗り越えることができる、そしてそれはみんなでやることによって、チームとしての心理的安全性を高めることができる、そんなことを思いましたイノベーションの世界では、FastFailという言葉もありますが、"事前検死"は、いわゆる早過ぎるFastFailであり逆転の発想からの、具体と抽象の往復運動を促し、心理的安全性をも確保する、めちゃくちゃイノベーティブな手法と思いました一言で言えば"お前はすでに死んでいるノベーション"そんなことを思いました^ ^参考:本: 失敗の科学 2016年12月25日 初版第1刷発行 2016年12月25日 電子書籍版発行 A著者 マシュー・サイド 株式会社トランネット(翻訳協力) 発行所 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン2025-03-1012 min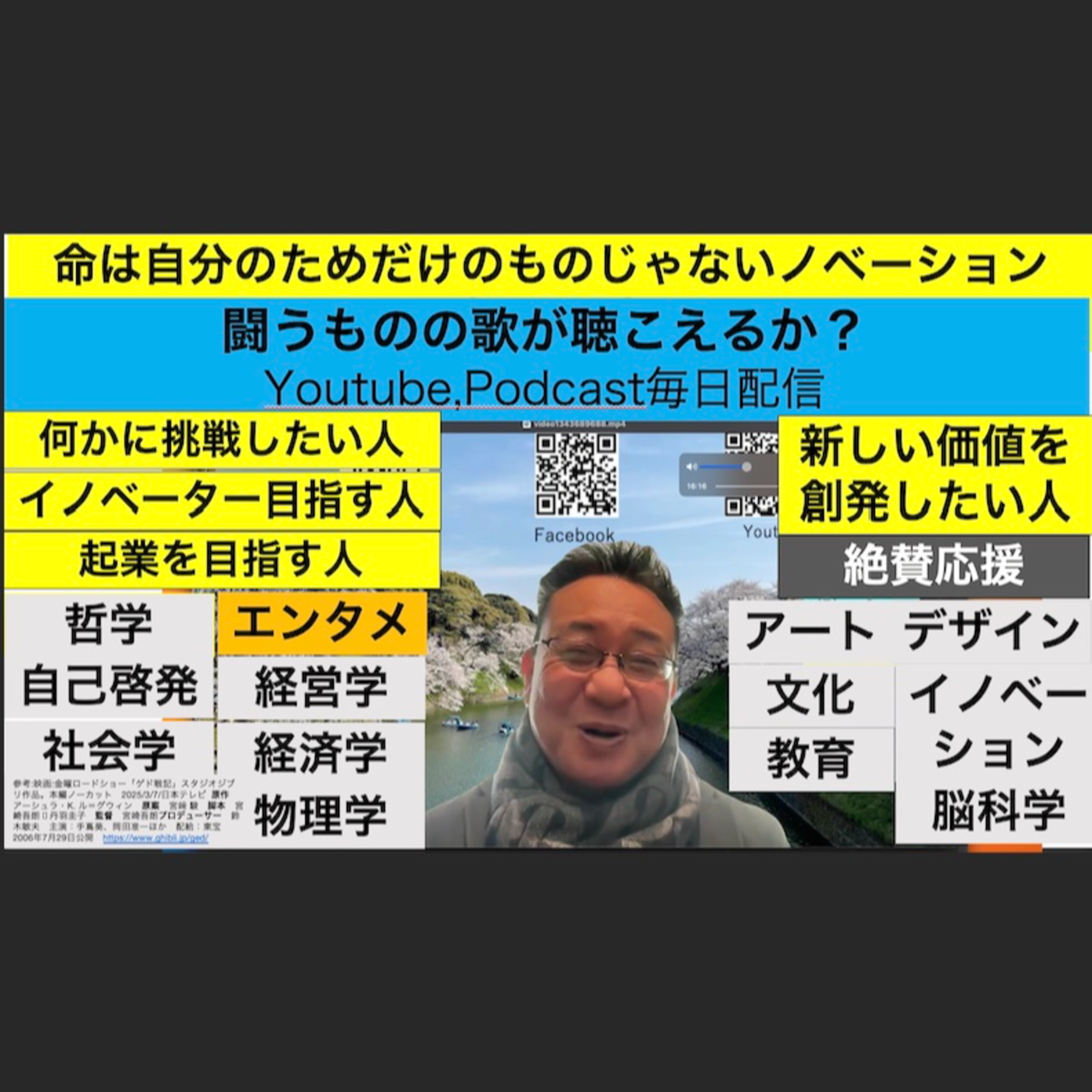 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"命は自分のためだけのものじゃないノベーション(1420回)大好きなスタジオジブリの映画「ゲド戦記」から、主人公の女の子のテルーが、殻に閉じこもって抜け出せない男の子のアレンにお話しした言葉に、震えました曰く"命は自分のためだけのもの?私はテナーに生かされた。だから生きなきゃいけない。生きて次の誰かに命を引き継ぐんだわ。"ここから私は思いました1、自己超越の欲求 マズロー→個人的欲求を超える大義2、共同体感覚 アドラー→ 依存する仲間へのペイフォワード3、後世への最大遺物 内村鑑三→命を繋ぐパッション"命は自分のためだけのもの?"という問いには、ガツンと頭を殴られました。命は自分の原動力だし、源だし、自分のためにある、というのは基本的な大原則のように考えていましたが、目から鱗が落ちる思いでしたマズローの欲求のご段階の1番上は、自己実現ですが、さらにその上に6つ目の、自己超越の欲求がある、ということを思い出しました。イノベーションの世界においても、自分自身の欲求のパッションから始まって、その後、仲間や、社会の価値となる大義へ到達する、それによって、たくさんの人々が使ってもらえるものになる、というのは、ある意味、自己超越の欲求を満たすこと、それはすなわち大義、を実現することにも繋がるのかなと思いましたまた、"私はテナーに生かされた"の言葉には、他者の存在や支えを認識することの重要性が込められていると思いました。アドラーさんの共同体感覚のように、自分自身は1人ではなく、仲間としての、共同体の中の1人であり、デュルケームさんの社会分業論のように、依存し合う存在である中で、恩を受けたりそれをペイフォワードしたり、命はそういう存在だと言ってる気がしましたそういう存在の、仲間であるからこそ、コラボレーションによって、さらに大きな夢を実現できるイノベーションにも繋がると。そして、"生きて次の誰かに命を引き継ぐんだわ。"の言葉からは、内村鑑三さんの後世への最大遺物のお話を思い出しました。思想、金、ビジネス、そして生き様を後世へ遺せるかということは常に自分も意識してしまいますが、命自体を繋いでいくことが、実は後世への最大遺物なのかもしれないと、自分の命がある理由として、それを捉えているということにも感動しました人間の遺伝子に組み込まれた、根源的なパッションの源として、それは、きっとあるのかもしれないなあと、思いました命を繋ぐ根源的なパッション、共同体感覚としての仲間へのペイフォワード、自己超越としての大義、イノベーター3つのフレームにも通じる、イノベーティブな人生の捉え方を教えて頂いた気がしました命は自分のためだけのものじゃないノベーションそんなことを教えて頂きました^ ^参考:映画:金曜ロードショー「ゲド戦記」スタジオジブリ作品。本編ノーカット 2025/3/7/日本テレビ 原作 アーシュラ・K. ル=グウィン 原案 宮﨑 駿 脚本 宮崎吾朗 ⋅ 丹羽圭子 監督 宮崎吾朗プロデューサー 鈴木敏夫 主演:手嶌葵、岡田准一ほか 配給:東宝 2006年7月29日公開 https://www.ghibli.jp/ged/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/o6RgiIiuMe02025-03-0919 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"命は自分のためだけのものじゃないノベーション(1420回)大好きなスタジオジブリの映画「ゲド戦記」から、主人公の女の子のテルーが、殻に閉じこもって抜け出せない男の子のアレンにお話しした言葉に、震えました曰く"命は自分のためだけのもの?私はテナーに生かされた。だから生きなきゃいけない。生きて次の誰かに命を引き継ぐんだわ。"ここから私は思いました1、自己超越の欲求 マズロー→個人的欲求を超える大義2、共同体感覚 アドラー→ 依存する仲間へのペイフォワード3、後世への最大遺物 内村鑑三→命を繋ぐパッション"命は自分のためだけのもの?"という問いには、ガツンと頭を殴られました。命は自分の原動力だし、源だし、自分のためにある、というのは基本的な大原則のように考えていましたが、目から鱗が落ちる思いでしたマズローの欲求のご段階の1番上は、自己実現ですが、さらにその上に6つ目の、自己超越の欲求がある、ということを思い出しました。イノベーションの世界においても、自分自身の欲求のパッションから始まって、その後、仲間や、社会の価値となる大義へ到達する、それによって、たくさんの人々が使ってもらえるものになる、というのは、ある意味、自己超越の欲求を満たすこと、それはすなわち大義、を実現することにも繋がるのかなと思いましたまた、"私はテナーに生かされた"の言葉には、他者の存在や支えを認識することの重要性が込められていると思いました。アドラーさんの共同体感覚のように、自分自身は1人ではなく、仲間としての、共同体の中の1人であり、デュルケームさんの社会分業論のように、依存し合う存在である中で、恩を受けたりそれをペイフォワードしたり、命はそういう存在だと言ってる気がしましたそういう存在の、仲間であるからこそ、コラボレーションによって、さらに大きな夢を実現できるイノベーションにも繋がると。そして、"生きて次の誰かに命を引き継ぐんだわ。"の言葉からは、内村鑑三さんの後世への最大遺物のお話を思い出しました。思想、金、ビジネス、そして生き様を後世へ遺せるかということは常に自分も意識してしまいますが、命自体を繋いでいくことが、実は後世への最大遺物なのかもしれないと、自分の命がある理由として、それを捉えているということにも感動しました人間の遺伝子に組み込まれた、根源的なパッションの源として、それは、きっとあるのかもしれないなあと、思いました命を繋ぐ根源的なパッション、共同体感覚としての仲間へのペイフォワード、自己超越としての大義、イノベーター3つのフレームにも通じる、イノベーティブな人生の捉え方を教えて頂いた気がしました命は自分のためだけのものじゃないノベーションそんなことを教えて頂きました^ ^参考:映画:金曜ロードショー「ゲド戦記」スタジオジブリ作品。本編ノーカット 2025/3/7/日本テレビ 原作 アーシュラ・K. ル=グウィン 原案 宮﨑 駿 脚本 宮崎吾朗 ⋅ 丹羽圭子 監督 宮崎吾朗プロデューサー 鈴木敏夫 主演:手嶌葵、岡田准一ほか 配給:東宝 2006年7月29日公開 https://www.ghibli.jp/ged/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/o6RgiIiuMe02025-03-0919 min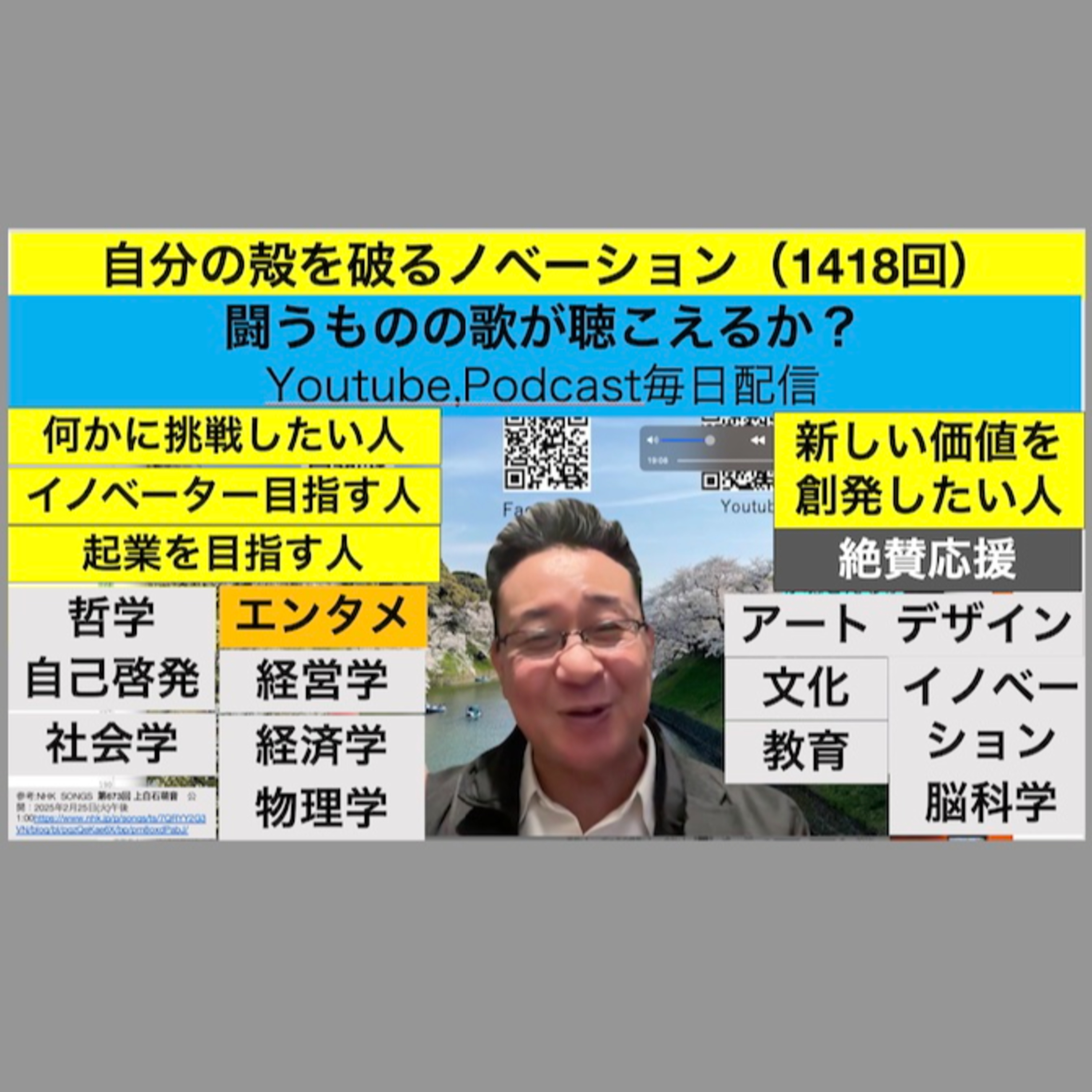 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"誰でもマージナルゲイン・ノベーション(1419回)マシュー・サイドさんの「失敗の科学」から、小林尊さんが、ニューヨークのコニーアイラインドで開催されたネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権」に圧倒的な優勝を収めたやり方に感動しました"まず、歴代のチャンピオンはみなホットドッグを端から口に押し込んでいたが、彼は半分に割ってから食べようと考えた。実際にやってみると、口の中に余裕ができて咀嚼しやすく、手もすぐに自由になって、ペースよく次のホットドッグを口に運べた。彼は次に、ソーセージを先に食べてからパンを食べてみた。しかしソーセージは食べやすかったが、パンはモサモサしててこずった。 そこで、パンを水につけてみた。水の温度を変えたり、水の中に植物油を数滴混ぜたりもした。その間、彼は自分のトレーニングの様子を録画し、データをとり、さらに少しずつ違う方法を試した。全速力で一気に食べたり、ペース配分したり、ラストスパートをかけたりもしてみた。 さまざまな噛み方や飲み込み方、食べたものが胃に入りやすいように(そして吐かずに済むように)腰を揺らす方法も考えた。こうして小林は、小さな仮説をひとつずつ丁寧に検証していった。"ここから私は思いました1、ブレイクザバイアス→マインドセット2、マージナルゲイン→スキル3、フィードバックシステム→仕組み化小林尊さんが、これまでのホットドック早食い選手権で、これまでの優勝者の約2倍の量を食べたと言う、圧倒的な勝利の秘密に驚愕とともに、これこそイノベーター的ノウハウだなあと感動しましたまず体格的にも圧倒的に不利なはずの、小林さんが、この選手権に挑もうと考えた点に、驚きとともに、まさに世間の見方や、もっと言えば自身のバイアスを壊して、挑戦すると決められたところに、ブレイクザバイアスとしての、イノベーターマインドセットを感じましたここで優勝という大きなゴールを目指さすと、自分自身に決めないと、結局小さなゴールで終わってしまう。良く新規事業のアイデアでもあるのですが、あまりにも自分自身の身の丈に合わせ過ぎてしまう、または、叩かれる前から叩かれない実験性の確実なものに絞ってしまう、こういうことはあるあるだなあと思いますリーンアンドスケールといいますが、まずはどれだけスケールできる可能性があるのか?ということを、あらかじめ自ら大きなチャレンジに立ち向かう、そういうマインドセットをもてるプラクティスが重要かと思いましたまた、それが、全く絵に描いた餅では、その次が続かなくなりますので、その上での、大きなゴールへ如何に立ち向かうのかという、スキルが必要となってくると思います。そこで重要なスキルが、ここで言われてるところの、マージナルゲインだなと。大きな目標を小さな目標に細かく分解して、それぞれについて仮説検証を細かく積み上げていくこのやり方は、イギリスのプロ自転車ロードレースチーム「チームスカイ」のゼネラルマネージャーのデイブ・ブレイルスフォードが、これにより2012年にツールドフランス優勝へ導いたという方法です。ある意味、リーンスタートアップのMVPの仮説検証も、この一つの形態ということもできるのかなとも思いました。先ほどの小林さんの事例を見ても分かる通り、実はマージナルゲインは、大きなチャレンジにも使えますが、普段の生活を少しずつ前に進めることにも使えるなあとつくづく思いました。小さく分解すれば、こんな人思えることや、難しいとおもうこと、面倒だなあと思うことも、実は少しずつ前に進むことができる。その積み重ねが、実はとても素敵なゴールを連れてくるという、とても勉強になるお話しでしたそしてもう一つ、小林さんが素晴らしいのは、自身を録画して、それをフィードバックすることを、仕組み化していたことかなと思いました。アカペラを歌ってる時、ライブの録画映像を見ると、びっくりするほどガッカリすることがあります笑。それは、客観的に見るということが、いかに普段できていないか、という表れだと思います。仮説検証がうまく行った、うまくいかなかった、という結果よりも、なぜそれがうまく行ったのか、何がうまくいかなかったかということを、客観的に把握できる仕組みを作ることが、とても大切だよなあと、改めて思わせて頂きましたということで、小林さんが、素晴らしいのは、大きなゴールへ向かうマインドセット、そして、大きな目標を小さな単位で仮説検証するマージナルゲインのスキル、そして検証作業をデータ把握やフィードバックループを回す客観的な仕組み化をしたことそんな風に思いましたそれら全て一言で言うとマージナルゲインを誰でも進めていくイノベーションということで誰でもマージナルゲイン・ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 失敗の科学 2016年12月25日 初版第1刷発行 2016年12月25日 電子書籍版発行 Author マシュー・サイド Illustrator 有枝春/株式会社トランネット(翻訳協力) Book Designer 竹内雄二 発行者 干場弓子 発行所 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/e8nvdofVvg02025-03-0815 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"誰でもマージナルゲイン・ノベーション(1419回)マシュー・サイドさんの「失敗の科学」から、小林尊さんが、ニューヨークのコニーアイラインドで開催されたネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権」に圧倒的な優勝を収めたやり方に感動しました"まず、歴代のチャンピオンはみなホットドッグを端から口に押し込んでいたが、彼は半分に割ってから食べようと考えた。実際にやってみると、口の中に余裕ができて咀嚼しやすく、手もすぐに自由になって、ペースよく次のホットドッグを口に運べた。彼は次に、ソーセージを先に食べてからパンを食べてみた。しかしソーセージは食べやすかったが、パンはモサモサしててこずった。 そこで、パンを水につけてみた。水の温度を変えたり、水の中に植物油を数滴混ぜたりもした。その間、彼は自分のトレーニングの様子を録画し、データをとり、さらに少しずつ違う方法を試した。全速力で一気に食べたり、ペース配分したり、ラストスパートをかけたりもしてみた。 さまざまな噛み方や飲み込み方、食べたものが胃に入りやすいように(そして吐かずに済むように)腰を揺らす方法も考えた。こうして小林は、小さな仮説をひとつずつ丁寧に検証していった。"ここから私は思いました1、ブレイクザバイアス→マインドセット2、マージナルゲイン→スキル3、フィードバックシステム→仕組み化小林尊さんが、これまでのホットドック早食い選手権で、これまでの優勝者の約2倍の量を食べたと言う、圧倒的な勝利の秘密に驚愕とともに、これこそイノベーター的ノウハウだなあと感動しましたまず体格的にも圧倒的に不利なはずの、小林さんが、この選手権に挑もうと考えた点に、驚きとともに、まさに世間の見方や、もっと言えば自身のバイアスを壊して、挑戦すると決められたところに、ブレイクザバイアスとしての、イノベーターマインドセットを感じましたここで優勝という大きなゴールを目指さすと、自分自身に決めないと、結局小さなゴールで終わってしまう。良く新規事業のアイデアでもあるのですが、あまりにも自分自身の身の丈に合わせ過ぎてしまう、または、叩かれる前から叩かれない実験性の確実なものに絞ってしまう、こういうことはあるあるだなあと思いますリーンアンドスケールといいますが、まずはどれだけスケールできる可能性があるのか?ということを、あらかじめ自ら大きなチャレンジに立ち向かう、そういうマインドセットをもてるプラクティスが重要かと思いましたまた、それが、全く絵に描いた餅では、その次が続かなくなりますので、その上での、大きなゴールへ如何に立ち向かうのかという、スキルが必要となってくると思います。そこで重要なスキルが、ここで言われてるところの、マージナルゲインだなと。大きな目標を小さな目標に細かく分解して、それぞれについて仮説検証を細かく積み上げていくこのやり方は、イギリスのプロ自転車ロードレースチーム「チームスカイ」のゼネラルマネージャーのデイブ・ブレイルスフォードが、これにより2012年にツールドフランス優勝へ導いたという方法です。ある意味、リーンスタートアップのMVPの仮説検証も、この一つの形態ということもできるのかなとも思いました。先ほどの小林さんの事例を見ても分かる通り、実はマージナルゲインは、大きなチャレンジにも使えますが、普段の生活を少しずつ前に進めることにも使えるなあとつくづく思いました。小さく分解すれば、こんな人思えることや、難しいとおもうこと、面倒だなあと思うことも、実は少しずつ前に進むことができる。その積み重ねが、実はとても素敵なゴールを連れてくるという、とても勉強になるお話しでしたそしてもう一つ、小林さんが素晴らしいのは、自身を録画して、それをフィードバックすることを、仕組み化していたことかなと思いました。アカペラを歌ってる時、ライブの録画映像を見ると、びっくりするほどガッカリすることがあります笑。それは、客観的に見るということが、いかに普段できていないか、という表れだと思います。仮説検証がうまく行った、うまくいかなかった、という結果よりも、なぜそれがうまく行ったのか、何がうまくいかなかったかということを、客観的に把握できる仕組みを作ることが、とても大切だよなあと、改めて思わせて頂きましたということで、小林さんが、素晴らしいのは、大きなゴールへ向かうマインドセット、そして、大きな目標を小さな単位で仮説検証するマージナルゲインのスキル、そして検証作業をデータ把握やフィードバックループを回す客観的な仕組み化をしたことそんな風に思いましたそれら全て一言で言うとマージナルゲインを誰でも進めていくイノベーションということで誰でもマージナルゲイン・ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 失敗の科学 2016年12月25日 初版第1刷発行 2016年12月25日 電子書籍版発行 Author マシュー・サイド Illustrator 有枝春/株式会社トランネット(翻訳協力) Book Designer 竹内雄二 発行者 干場弓子 発行所 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/e8nvdofVvg02025-03-0815 min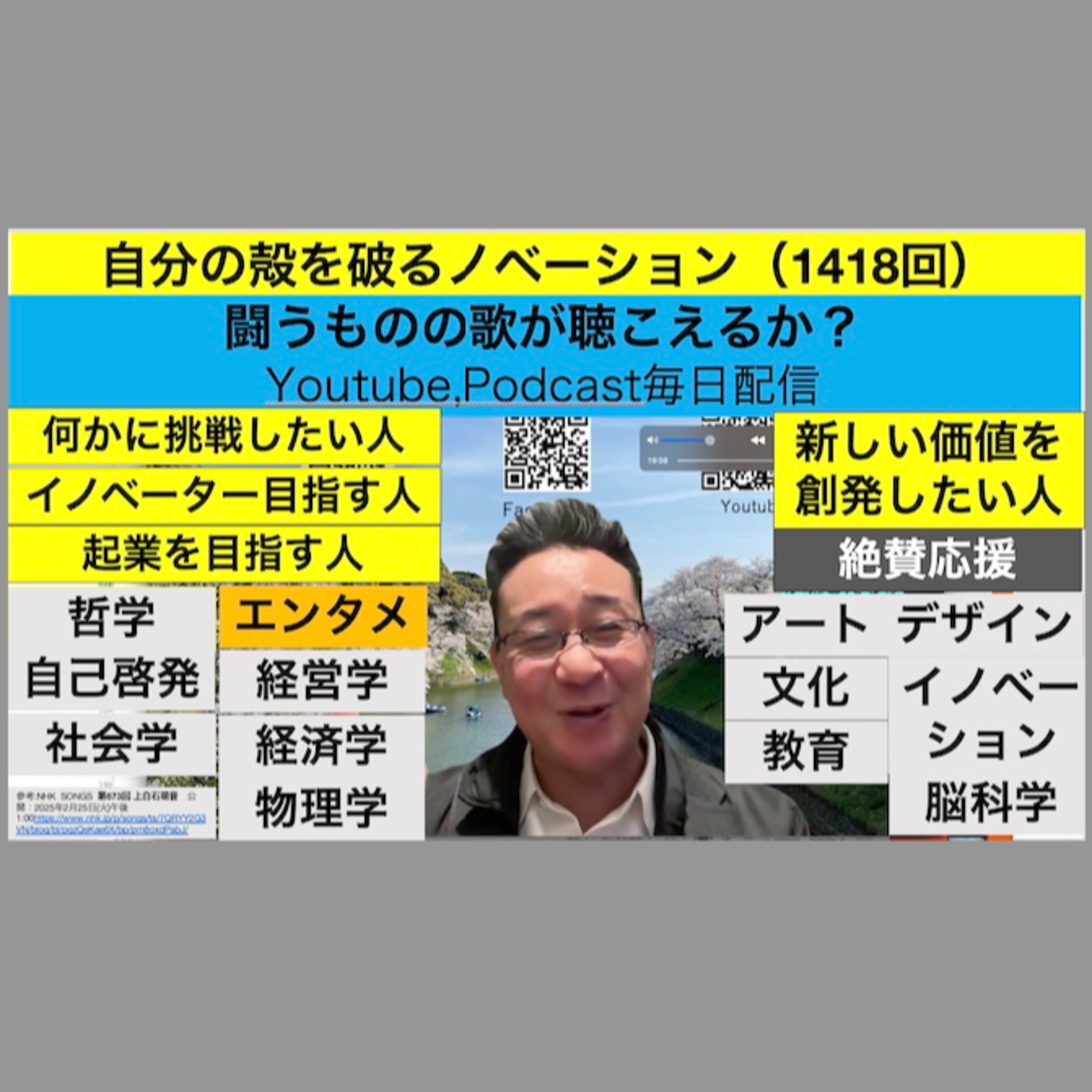 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"自分の殻を破るノベーション(1418回)上白石萌音さんが、12歳の時にミュージカルの先生に、曲を選んでいただいて、自分のやりたいようにやってごらんと言う機会をいただいたときの、上白石さんの言葉に感動しました。"馬鹿になったみたいに、いろんなことやりながら、こうやったら怒られるかなと思うようなことも、全部やってみたら、すごく先生に褒められて、多分あれが人生で初めて殼を破った瞬間だと思います。"ここから私は思いました1、コンフォートゾーンを抜ける→馬鹿になったみたいに2、リーンスタートアップ→いろんなことをやりながら3、フローの獲得→殻を破った瞬間引っ込み思案だった萌音さんが、出会ったミュージカルの先生が、アンダースンさんの"超一流になるためには努力が才能か"で語られるところの、最初の条件である「最高の教師」に出会えたことにあったのだなあと思いましたそこから、先生が普段の萌音さんの静かな雰囲気とは真逆の、好きを連呼する曲を選択して、あとは好きにやらせる自発性を育てるやり方をされてることにも、とても感動しましたそしてそれに応える萌さんは、"馬鹿になったみたいに"と表現されてますが、それはおそらく、コンフォートゾーンを抜け出すことを、つまり、これまでできないことに挑戦する機会を得られて、見事にそれを実現させたのかと、胸が熱くなりましたイノベーションの世界でも、馬鹿みたいな意見こそ、大切だとよく言われますが、これを実際にやるのは、ある意味自分自身の殻を破り、さらには他人からの視線を気にしない、コンフォートゾーンを抜け出すことなのかと思ってますそして萌音さんが言われてるように"いろんなことをやりながら"というのは、自分なりにいろんなことを試行錯誤して、やっては失敗し、改善してちがうようにやって、という、仮説検証作業をひたすら繰り返していたのかとも思いましたさらにそこで素晴らしいのは、この先生が、そんな挑戦を、素晴らしいじゃないと、褒めてくれて、やらせてくれたことだなあとも思いましたこの時点で、組織の中では、上司が止めてしまう、正解ではないかもしれないけども、自分は全然違うと思ってても、自立性を持って挑戦してきたメンバを本気で応援できるか、こう言う上司、リーダー、先生がいるかどうかも大事だなとも思いましたそして、その挑戦をし、歌い続けて踊り続けて、技術も成長してきた中で、自らの殻を破れたと思った瞬間が訪れたのは、チクセントミハイさんのいう、フロー状態に突入することになったとかもしれないと思いました一度、フローを体験すると、それは一つの大きな成功体験としての自信につながって、その後、様々なチャレンジができるようになっていくのかなとその先に、今の萌音さんがおられるのかと、テレビ俳優、舞台俳優、ミュージカル俳優、歌手、声優、様々な挑戦をされている土台が、そこから生まれたのかと、めちゃくちゃ感動してしまいました何歳になっても、どんな分野でも、コンフォートゾーンを抜け出して、リーンスタートアップのように仮説と実験を繰り返して、挑戦軸と技術軸を磨いてフローに入る体験をするこの体験を一回でもやれば、自らの殻を破って人生は劇的に回り始めるそんな勇気をいただいたお話しでした自分の殻を破るノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHK SONGS 第673回 上白石萌音 公開:2025年2月25日(火)午後1:00https://www.nhk.jp/p/songs/ts/7QRYY2G3VN/blog/bl/pgzQeKae6X/bp/pm8oxdPabJ/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/5eIALC-RKlc2025-03-0719 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"自分の殻を破るノベーション(1418回)上白石萌音さんが、12歳の時にミュージカルの先生に、曲を選んでいただいて、自分のやりたいようにやってごらんと言う機会をいただいたときの、上白石さんの言葉に感動しました。"馬鹿になったみたいに、いろんなことやりながら、こうやったら怒られるかなと思うようなことも、全部やってみたら、すごく先生に褒められて、多分あれが人生で初めて殼を破った瞬間だと思います。"ここから私は思いました1、コンフォートゾーンを抜ける→馬鹿になったみたいに2、リーンスタートアップ→いろんなことをやりながら3、フローの獲得→殻を破った瞬間引っ込み思案だった萌音さんが、出会ったミュージカルの先生が、アンダースンさんの"超一流になるためには努力が才能か"で語られるところの、最初の条件である「最高の教師」に出会えたことにあったのだなあと思いましたそこから、先生が普段の萌音さんの静かな雰囲気とは真逆の、好きを連呼する曲を選択して、あとは好きにやらせる自発性を育てるやり方をされてることにも、とても感動しましたそしてそれに応える萌さんは、"馬鹿になったみたいに"と表現されてますが、それはおそらく、コンフォートゾーンを抜け出すことを、つまり、これまでできないことに挑戦する機会を得られて、見事にそれを実現させたのかと、胸が熱くなりましたイノベーションの世界でも、馬鹿みたいな意見こそ、大切だとよく言われますが、これを実際にやるのは、ある意味自分自身の殻を破り、さらには他人からの視線を気にしない、コンフォートゾーンを抜け出すことなのかと思ってますそして萌音さんが言われてるように"いろんなことをやりながら"というのは、自分なりにいろんなことを試行錯誤して、やっては失敗し、改善してちがうようにやって、という、仮説検証作業をひたすら繰り返していたのかとも思いましたさらにそこで素晴らしいのは、この先生が、そんな挑戦を、素晴らしいじゃないと、褒めてくれて、やらせてくれたことだなあとも思いましたこの時点で、組織の中では、上司が止めてしまう、正解ではないかもしれないけども、自分は全然違うと思ってても、自立性を持って挑戦してきたメンバを本気で応援できるか、こう言う上司、リーダー、先生がいるかどうかも大事だなとも思いましたそして、その挑戦をし、歌い続けて踊り続けて、技術も成長してきた中で、自らの殻を破れたと思った瞬間が訪れたのは、チクセントミハイさんのいう、フロー状態に突入することになったとかもしれないと思いました一度、フローを体験すると、それは一つの大きな成功体験としての自信につながって、その後、様々なチャレンジができるようになっていくのかなとその先に、今の萌音さんがおられるのかと、テレビ俳優、舞台俳優、ミュージカル俳優、歌手、声優、様々な挑戦をされている土台が、そこから生まれたのかと、めちゃくちゃ感動してしまいました何歳になっても、どんな分野でも、コンフォートゾーンを抜け出して、リーンスタートアップのように仮説と実験を繰り返して、挑戦軸と技術軸を磨いてフローに入る体験をするこの体験を一回でもやれば、自らの殻を破って人生は劇的に回り始めるそんな勇気をいただいたお話しでした自分の殻を破るノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHK SONGS 第673回 上白石萌音 公開:2025年2月25日(火)午後1:00https://www.nhk.jp/p/songs/ts/7QRYY2G3VN/blog/bl/pgzQeKae6X/bp/pm8oxdPabJ/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/5eIALC-RKlc2025-03-0719 min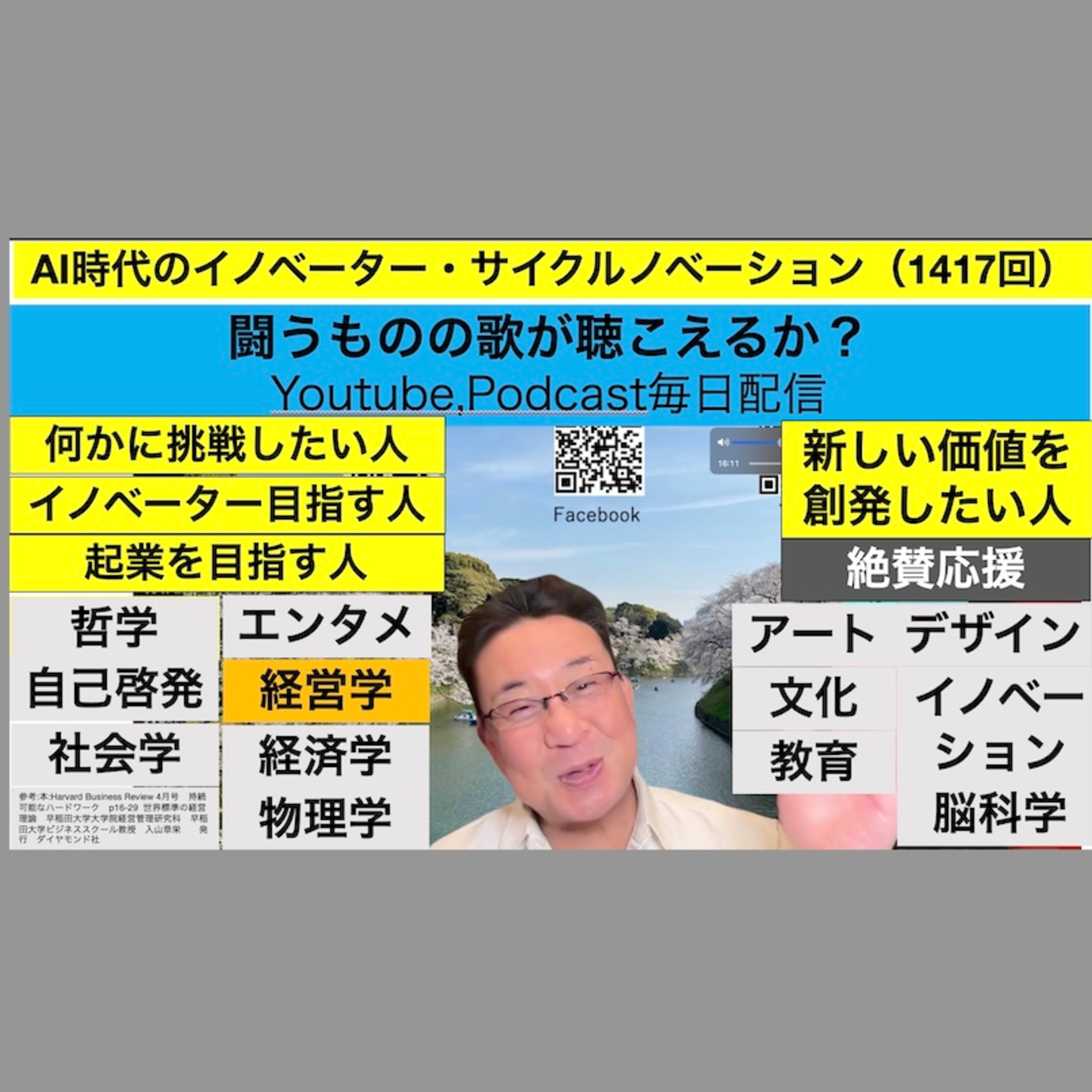 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"AI時代のイノベーター・サイクルノベーション(1417回)早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄さんからの、"AI時代に人間が回すべきサイクル"について、めちゃくちゃ腹落ちさせてて頂きました。曰く"あらためて整理すると、まず「知の探索」がこれからのイノベーション時代に不可欠である。人はAIに「知の深化」の作業をほぼすべて任せ、「知の探索」をし続ける必要がある。そのためには、未来に腹落ちするための「センスメイキング」が不可欠となる。そして、自身や他者を腹落ちさせるには、自分たちがつくり出したい未来やありたい姿・価値観を形式化し、その形式化されたものを内面化し、組織風土のように常態的に行動に移す「SECIモデル」の考えが欠かせない。"ここから私は、"AI時代に人間が回すべきサイクル"をさらに加速させるためには、イノベーター3つのフレームとの掛け合わせがより効果的と思いました1、"知の探索"×パッション2、"SECIモデル"×仲間3、"センスメイキング"×大義まず思ったのは、オライリー教授の両利きの経営における、"知の探索"をするためには、様々なセレンディピティと合う行動をまずは取ることが大切と思いました。より違うものが掛け合わせることによって、より面白いアイディアが生まれてくるそのためには、様々なセレンディピティ、これは出口治明さんが言われている、人・本・旅のような、機会を増やす行動を取ることで、セレンディピティの確率を上げる行動をとらなければならないなと思いました。そのためには、自分自身が全く興味のない本を読んでみる、行ったことのない土地に行って数週間暮らしてみる、全く関わりのない人たちとお話をしに行く、いずれの行動も、自ら湧き出るようなパッションがないと、なかなかドライブできないし、それがセレンディピティだとさえ気づかないさらには、それがなんの役に立つのかもわからないことをやり続ける、と言うことなので、組織的にはかなり批判を浴びることを覚悟でやり抜く、それくらい実は"知の探索"には「パッション」が必要かと思いましたそこで、捉えてきた様々なセレンディピティな事柄を、自分1人であーだこーだうんうん唸るのもありなのですが、実は沢山の人々が集めてきたものを、沢山の人々であーでもないこーでもないと、雑談することが実は自分でさえ、言語化できてなかったことなどを、気づかせてくれる、言ってみれば、野中郁次郎教授の"SECIモデル"における、暗黙知を形式知にしてくれることであり、さらに議論によって更なる暗黙知が生まれ、形式知化していくと言う知のスパイラルをぐるぐる回すためには、「仲間」と進めることがとても大切なことだよなあと思いましたそして、最終的にみんなの進む方向性を決めてくれる、つまりみんなが腹落ちをする納得感を得られる、カールワイク教授のセンスメイキングが重要になるわけですがそれを束ねてくれるものが、そこに参加している人々の、"知の探索"をドライブしたパッションあふれる仲間たちの、"SECIモデル"から抽出された知の結晶を、沢山の人たちに寄り添うことができ、それでいてそこにいる仲間たちのみならず、外の人たちにも価値が溢れる大きな「大義」が、納得感があり腹落ちする形でセンスメイキングしていくそしてまた、そのサイクルが回っていく、そんなことが、これからのイノベーション活動には必要となってくる、そんな風に思いました一言で言うとAI時代のイノベーター・サイクルノベーションそんなことを思いました参考:本:Harvard Business Review 4月号 持続可能なハードワーク p16-29 世界標準の経営理論 早稲田大学大学院経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄 発行 ダイヤモンド社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/mYviYq7EDVs2025-03-0624 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"AI時代のイノベーター・サイクルノベーション(1417回)早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄さんからの、"AI時代に人間が回すべきサイクル"について、めちゃくちゃ腹落ちさせてて頂きました。曰く"あらためて整理すると、まず「知の探索」がこれからのイノベーション時代に不可欠である。人はAIに「知の深化」の作業をほぼすべて任せ、「知の探索」をし続ける必要がある。そのためには、未来に腹落ちするための「センスメイキング」が不可欠となる。そして、自身や他者を腹落ちさせるには、自分たちがつくり出したい未来やありたい姿・価値観を形式化し、その形式化されたものを内面化し、組織風土のように常態的に行動に移す「SECIモデル」の考えが欠かせない。"ここから私は、"AI時代に人間が回すべきサイクル"をさらに加速させるためには、イノベーター3つのフレームとの掛け合わせがより効果的と思いました1、"知の探索"×パッション2、"SECIモデル"×仲間3、"センスメイキング"×大義まず思ったのは、オライリー教授の両利きの経営における、"知の探索"をするためには、様々なセレンディピティと合う行動をまずは取ることが大切と思いました。より違うものが掛け合わせることによって、より面白いアイディアが生まれてくるそのためには、様々なセレンディピティ、これは出口治明さんが言われている、人・本・旅のような、機会を増やす行動を取ることで、セレンディピティの確率を上げる行動をとらなければならないなと思いました。そのためには、自分自身が全く興味のない本を読んでみる、行ったことのない土地に行って数週間暮らしてみる、全く関わりのない人たちとお話をしに行く、いずれの行動も、自ら湧き出るようなパッションがないと、なかなかドライブできないし、それがセレンディピティだとさえ気づかないさらには、それがなんの役に立つのかもわからないことをやり続ける、と言うことなので、組織的にはかなり批判を浴びることを覚悟でやり抜く、それくらい実は"知の探索"には「パッション」が必要かと思いましたそこで、捉えてきた様々なセレンディピティな事柄を、自分1人であーだこーだうんうん唸るのもありなのですが、実は沢山の人々が集めてきたものを、沢山の人々であーでもないこーでもないと、雑談することが実は自分でさえ、言語化できてなかったことなどを、気づかせてくれる、言ってみれば、野中郁次郎教授の"SECIモデル"における、暗黙知を形式知にしてくれることであり、さらに議論によって更なる暗黙知が生まれ、形式知化していくと言う知のスパイラルをぐるぐる回すためには、「仲間」と進めることがとても大切なことだよなあと思いましたそして、最終的にみんなの進む方向性を決めてくれる、つまりみんなが腹落ちをする納得感を得られる、カールワイク教授のセンスメイキングが重要になるわけですがそれを束ねてくれるものが、そこに参加している人々の、"知の探索"をドライブしたパッションあふれる仲間たちの、"SECIモデル"から抽出された知の結晶を、沢山の人たちに寄り添うことができ、それでいてそこにいる仲間たちのみならず、外の人たちにも価値が溢れる大きな「大義」が、納得感があり腹落ちする形でセンスメイキングしていくそしてまた、そのサイクルが回っていく、そんなことが、これからのイノベーション活動には必要となってくる、そんな風に思いました一言で言うとAI時代のイノベーター・サイクルノベーションそんなことを思いました参考:本:Harvard Business Review 4月号 持続可能なハードワーク p16-29 世界標準の経営理論 早稲田大学大学院経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄 発行 ダイヤモンド社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/mYviYq7EDVs2025-03-0624 min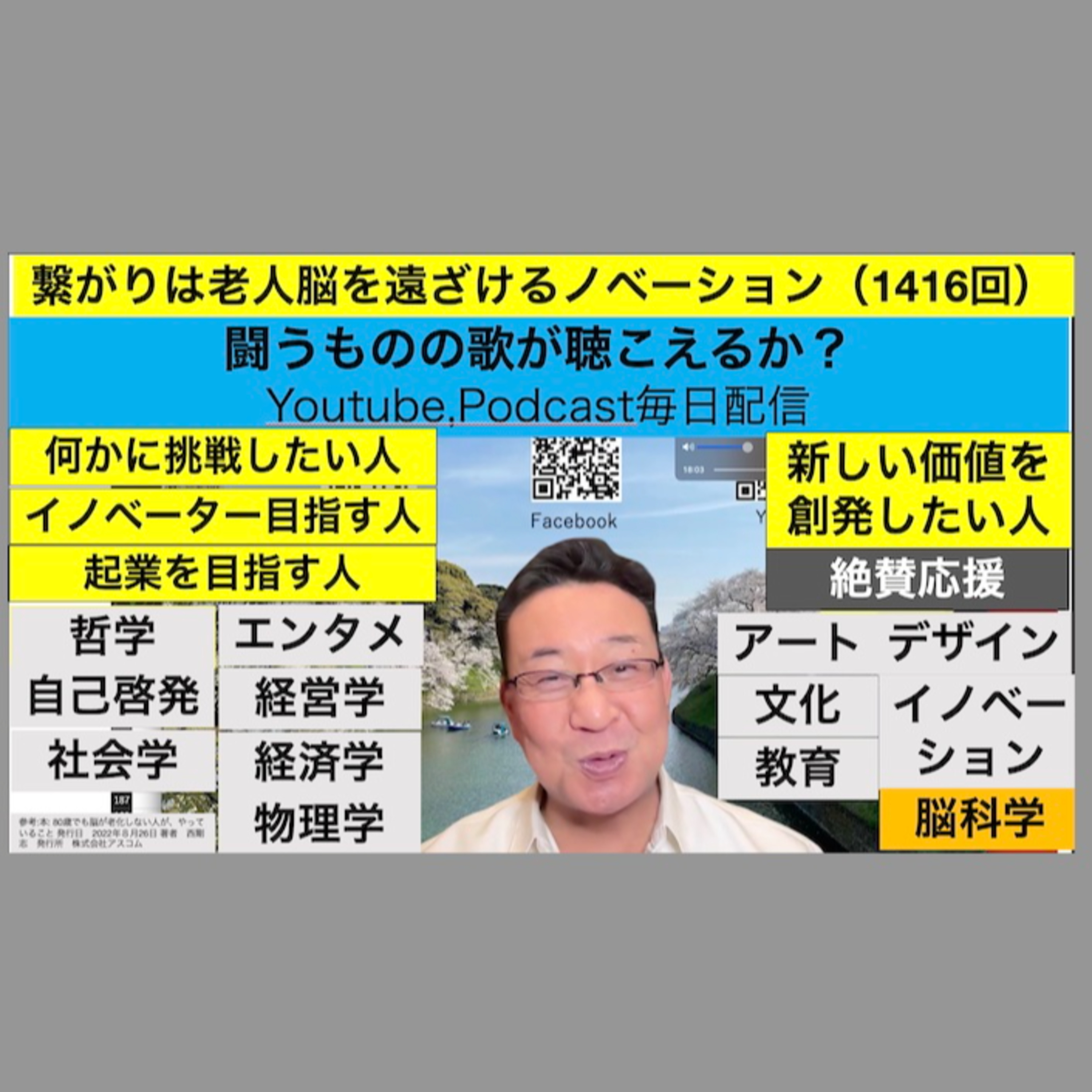 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"繋がりは老人脳を遠ざけるノベーション(1416回)脳科学者の西剛志さんの言葉に、エネルギーをいただきました曰く"脳はつながりを感じるとき、最高の状態になります。そして回復力も高まり、私たちをエネルギーあふれる状態にしてくれます。人とつながれなくても、大好きなものとつながる、自然とつながる、動物とつながる、新しい体験とつながる、楽しかった思い出とつながるそして自分の気持ちとつながることは、本書で紹介したあらゆる体験が病気や老人脳を遠ざけてくれます。"ここから私は思いました1、仲間と繋がる2、自分と繋がる3、大義と繋がる人の幸せの3大要素は、健康、仲間、富(成功)ということを、このチャンネルでも何度かお話ししていますが、この中でも健康や、富(成功)は、自分の努力だけではどうしても出来ないこともあるけれども仲間だけは、もっとも身近で、かつ、誰にでもやりやすいのかなとも思うし、繋がるという意味でも1番大切なのかもしれないなと常日頃思います先日お話しした、「成長は仲間とともにノベーション(1412回)」でも、仲間と共に勉強した方が実は成績が良くなる、だったり、「自立は薄く広く依存するノベーション(1408回)」では、本当の自立とは薄く広く依存することだということ、だったり、仲間が人にとってどれほど大切かを教えてくれてると思いますだからまずは、家族や友達やサークルや会社や趣味やSNSやゲームの仲間でも、さらに人を超えて、動物や自然、なんでもいいので、仲間を求めることは大切なんだなあと、思いましたそしてここでさらに教えてくれたのは、繋がるというのは、実は外の世界だけではなく、自分自身の内側とつながることこそが、実はとても大切なことで、自分の情熱の源と、改めて繋がるという体験までいけると、とても素敵かと思いました情熱の源は、縦軸にポジティブネガディブ、横軸にオープンクローズをとって、4章限それぞれに、大好きパッション、利他パッション、個性派パッション、成長パッションと分けて、自分の各々の気持ちはどんなことがあるのか?見つめてみることだけでも、少し見えてくる気がします自分の情熱の源と改めて繋がった上で、自分に必要な本当の仲間が改めて見えてくるので、今度はその仲間たちとともに、つながりを深めていくそして、その深まった先に、今の仲間だけでなく、もっと大きな仲間も喜んでくれるような繋がりを発見したら、それは大義として社会と繋がるということになるなあとそしたら、今度は社会の皆さんからのフィードバックの繋がりも頂けて、とても良いスパイラルが生まれることになると思いました仲間と繋がることから始まって、自分自身とも繋がり、そして本当の仲間と出会って、さらに大きな繋がりとしての大義としての社会とも繋がって、さらにそこからのフィードバックがくると考えると、実は、イノベーター3つのフレームのパッション、仲間、大義と繋がることは、老人脳を避ける効用があるということにも繋がる、そんなことを思いましたイノベーション活動をすることは老化脳を遠ざけることができるイノベーター3つのフレームとの繋がりは、老人脳を遠ざけることができる一言で言うと繋がりは老人脳を遠ざけるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 80歳でも脳が老化しない人が、やっていること 発行日 2022年8月26日 著者 西剛志 発行所 株式会社アスコム動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/4OzO20PYfEs2025-03-0523 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"繋がりは老人脳を遠ざけるノベーション(1416回)脳科学者の西剛志さんの言葉に、エネルギーをいただきました曰く"脳はつながりを感じるとき、最高の状態になります。そして回復力も高まり、私たちをエネルギーあふれる状態にしてくれます。人とつながれなくても、大好きなものとつながる、自然とつながる、動物とつながる、新しい体験とつながる、楽しかった思い出とつながるそして自分の気持ちとつながることは、本書で紹介したあらゆる体験が病気や老人脳を遠ざけてくれます。"ここから私は思いました1、仲間と繋がる2、自分と繋がる3、大義と繋がる人の幸せの3大要素は、健康、仲間、富(成功)ということを、このチャンネルでも何度かお話ししていますが、この中でも健康や、富(成功)は、自分の努力だけではどうしても出来ないこともあるけれども仲間だけは、もっとも身近で、かつ、誰にでもやりやすいのかなとも思うし、繋がるという意味でも1番大切なのかもしれないなと常日頃思います先日お話しした、「成長は仲間とともにノベーション(1412回)」でも、仲間と共に勉強した方が実は成績が良くなる、だったり、「自立は薄く広く依存するノベーション(1408回)」では、本当の自立とは薄く広く依存することだということ、だったり、仲間が人にとってどれほど大切かを教えてくれてると思いますだからまずは、家族や友達やサークルや会社や趣味やSNSやゲームの仲間でも、さらに人を超えて、動物や自然、なんでもいいので、仲間を求めることは大切なんだなあと、思いましたそしてここでさらに教えてくれたのは、繋がるというのは、実は外の世界だけではなく、自分自身の内側とつながることこそが、実はとても大切なことで、自分の情熱の源と、改めて繋がるという体験までいけると、とても素敵かと思いました情熱の源は、縦軸にポジティブネガディブ、横軸にオープンクローズをとって、4章限それぞれに、大好きパッション、利他パッション、個性派パッション、成長パッションと分けて、自分の各々の気持ちはどんなことがあるのか?見つめてみることだけでも、少し見えてくる気がします自分の情熱の源と改めて繋がった上で、自分に必要な本当の仲間が改めて見えてくるので、今度はその仲間たちとともに、つながりを深めていくそして、その深まった先に、今の仲間だけでなく、もっと大きな仲間も喜んでくれるような繋がりを発見したら、それは大義として社会と繋がるということになるなあとそしたら、今度は社会の皆さんからのフィードバックの繋がりも頂けて、とても良いスパイラルが生まれることになると思いました仲間と繋がることから始まって、自分自身とも繋がり、そして本当の仲間と出会って、さらに大きな繋がりとしての大義としての社会とも繋がって、さらにそこからのフィードバックがくると考えると、実は、イノベーター3つのフレームのパッション、仲間、大義と繋がることは、老人脳を避ける効用があるということにも繋がる、そんなことを思いましたイノベーション活動をすることは老化脳を遠ざけることができるイノベーター3つのフレームとの繋がりは、老人脳を遠ざけることができる一言で言うと繋がりは老人脳を遠ざけるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 80歳でも脳が老化しない人が、やっていること 発行日 2022年8月26日 著者 西剛志 発行所 株式会社アスコム動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/4OzO20PYfEs2025-03-0523 min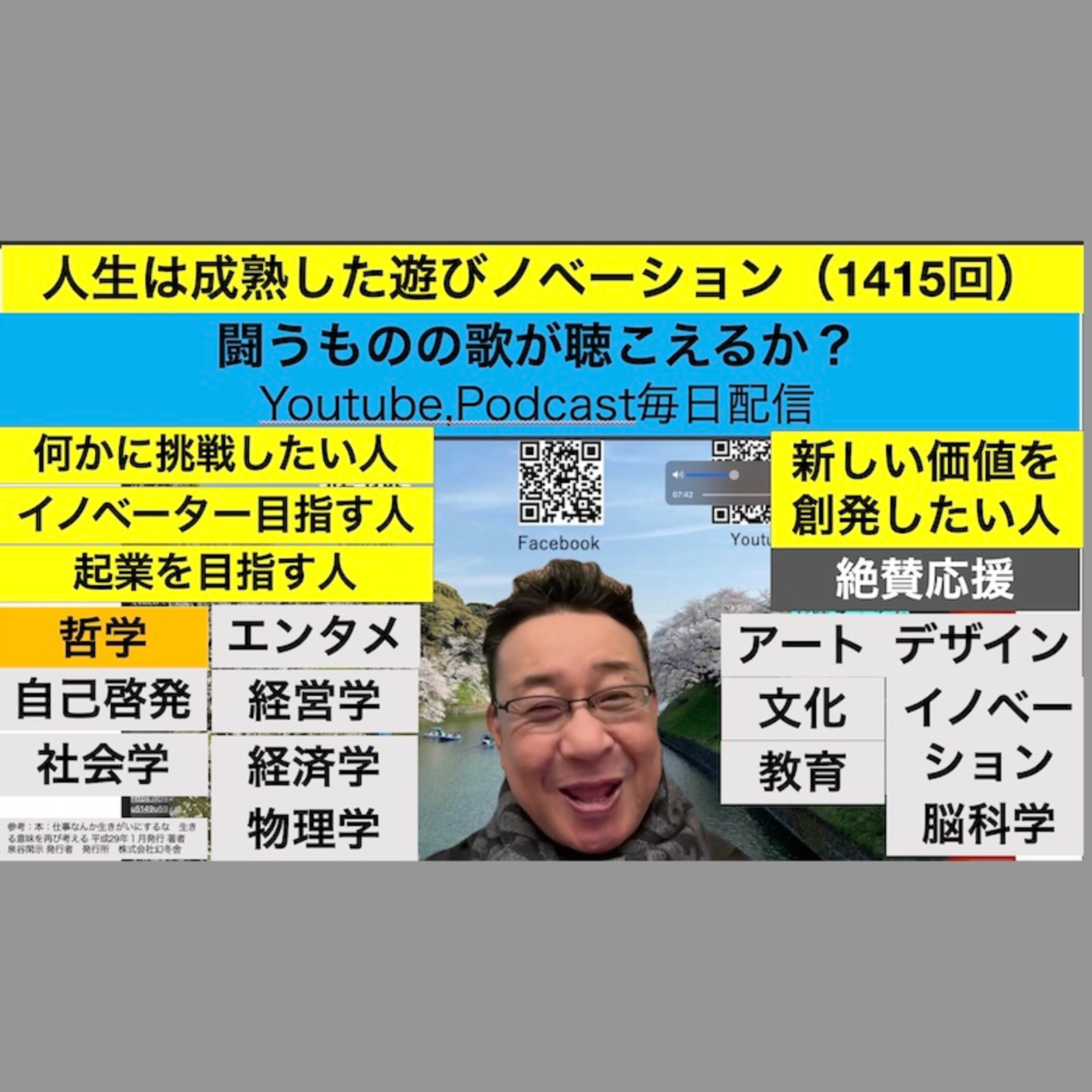 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"人生は成熟した遊びノベーション(1415回)泉谷クリニック院長で精神科医の泉谷閑示より、画家で美術教師のロバート・ヘンライの言葉に感動しました曰く"芸術家は人生についての考え方を世界に教えている。金だけが大事だと信じている人は、自分を欺いている。芸術家が教えているのは、小さな子供が無心で遊ぶように、人生も熱中して遊ぶべきだということである。ただし、それは成熟した遊びである。人の頭脳を駆使した遊びである。それが芸術であり、革新である。""人生を味わうのは容易なことではない。ある人は、稼がなければならないという─だが、なんのために?人はなんのために生きるのか?まるで、ほとんどの人が生計の資を得るためだけに生きていて、ほかには何にもできないかのようだ。ゴールのないレースで先を争っている自動車。使うあてがないのに、ひたすら増やすだけの金。無目的なままの「快楽」の追求。どれも人の内面とは関係がなく、すべて表面的なものばかりだ。"ここから私は思いました1、光る泥団子2、フロー3、パッションの源"仕事なんか生きがいにするな"というなかなかに攻めたタイトルの中で、私が最も刺さった言葉が、この文章でした。小さな子供が無心で遊ぶように、という言葉からは、光る泥団子をつくる加用文夫先生のことを思い出しました(子供の熱中は人生初の情熱の源ノベーション(1138回))それをやったおかげでこうなる、みたいなことよりも、その時その時が充実して詰まっている時間を過ごしているかどうかそれは、子供だけじゃなくて、まるで芸術家のように、大人でも同じなのである、それこそが充実した人生になるということだと、言って頂いてる気がしましたそして、大人の充実した時間とは、なにかというと、ある意味、以前お話ししたチクセントミハイさんが言われている、フロー状態、ここに入れるかどうかということなのかなと思いました(【ミハイ・チクセントミハイさんの"フロー概念"より、誰もがイノベーターになれるヒントを頂きました】)そのためには、スキル軸と挑戦軸のニ軸を、どちらかでも、時間をかけて高めていく、そのうちに、まるで川上哲治さんが、ボールの縫い目が見えた、と言われたように、没入してそれしか見えない、でもとても充実して気持ちの良い状態の、フローに入れるそんなことを、成熟した遊び、と言われているのかなあと思いましたそして、そんなフロー状態になるためには、私は、自らの情熱の源を、情熱のポートフォリオを使いながら、ざっくり4つに分けてみて(縦軸:ポジティブネガディブ、横軸:オープンクローズ)、大好きなこと、利他したいこと、個性発揮したいこと、成長したいこと、は、誰にでもあると思うので、書き出してみるそしてそこから、自分として、なんでもいいので、少しでもワクワクするものを始めてみる、そしてそれが自分にあってれば、そのスキル軸と、挑戦軸のアクティビティをやってみるそれを吉本ばななさんが言われていたように、実験していけば、いつか辿り着ける、そんなことをおもいました人生をより容易に充実して生きるためには、子供のように芸術家のように、自らのパッションの源に沿って、挑戦しながら、スキルを磨きながら、没頭していくもちろん、日々の生活もしていかなくてはならないので、全ての時間をこれにかけることは出来ないかもしれないでも、生活のための時間も、この考え方とベン図のように混ぜてみることもできるかもしれない人生は成熟した遊びをするノベーションそんなことを思いました参考:本:仕事なんか生きがいにするな 生きる意味を再び考える 平成29年1月発行 著者 泉谷閑示 発行者 発行所 株式会社幻冬舎動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/54lZGcb7cYc2025-03-0420 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"人生は成熟した遊びノベーション(1415回)泉谷クリニック院長で精神科医の泉谷閑示より、画家で美術教師のロバート・ヘンライの言葉に感動しました曰く"芸術家は人生についての考え方を世界に教えている。金だけが大事だと信じている人は、自分を欺いている。芸術家が教えているのは、小さな子供が無心で遊ぶように、人生も熱中して遊ぶべきだということである。ただし、それは成熟した遊びである。人の頭脳を駆使した遊びである。それが芸術であり、革新である。""人生を味わうのは容易なことではない。ある人は、稼がなければならないという─だが、なんのために?人はなんのために生きるのか?まるで、ほとんどの人が生計の資を得るためだけに生きていて、ほかには何にもできないかのようだ。ゴールのないレースで先を争っている自動車。使うあてがないのに、ひたすら増やすだけの金。無目的なままの「快楽」の追求。どれも人の内面とは関係がなく、すべて表面的なものばかりだ。"ここから私は思いました1、光る泥団子2、フロー3、パッションの源"仕事なんか生きがいにするな"というなかなかに攻めたタイトルの中で、私が最も刺さった言葉が、この文章でした。小さな子供が無心で遊ぶように、という言葉からは、光る泥団子をつくる加用文夫先生のことを思い出しました(子供の熱中は人生初の情熱の源ノベーション(1138回))それをやったおかげでこうなる、みたいなことよりも、その時その時が充実して詰まっている時間を過ごしているかどうかそれは、子供だけじゃなくて、まるで芸術家のように、大人でも同じなのである、それこそが充実した人生になるということだと、言って頂いてる気がしましたそして、大人の充実した時間とは、なにかというと、ある意味、以前お話ししたチクセントミハイさんが言われている、フロー状態、ここに入れるかどうかということなのかなと思いました(【ミハイ・チクセントミハイさんの"フロー概念"より、誰もがイノベーターになれるヒントを頂きました】)そのためには、スキル軸と挑戦軸のニ軸を、どちらかでも、時間をかけて高めていく、そのうちに、まるで川上哲治さんが、ボールの縫い目が見えた、と言われたように、没入してそれしか見えない、でもとても充実して気持ちの良い状態の、フローに入れるそんなことを、成熟した遊び、と言われているのかなあと思いましたそして、そんなフロー状態になるためには、私は、自らの情熱の源を、情熱のポートフォリオを使いながら、ざっくり4つに分けてみて(縦軸:ポジティブネガディブ、横軸:オープンクローズ)、大好きなこと、利他したいこと、個性発揮したいこと、成長したいこと、は、誰にでもあると思うので、書き出してみるそしてそこから、自分として、なんでもいいので、少しでもワクワクするものを始めてみる、そしてそれが自分にあってれば、そのスキル軸と、挑戦軸のアクティビティをやってみるそれを吉本ばななさんが言われていたように、実験していけば、いつか辿り着ける、そんなことをおもいました人生をより容易に充実して生きるためには、子供のように芸術家のように、自らのパッションの源に沿って、挑戦しながら、スキルを磨きながら、没頭していくもちろん、日々の生活もしていかなくてはならないので、全ての時間をこれにかけることは出来ないかもしれないでも、生活のための時間も、この考え方とベン図のように混ぜてみることもできるかもしれない人生は成熟した遊びをするノベーションそんなことを思いました参考:本:仕事なんか生きがいにするな 生きる意味を再び考える 平成29年1月発行 著者 泉谷閑示 発行者 発行所 株式会社幻冬舎動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/54lZGcb7cYc2025-03-0420 min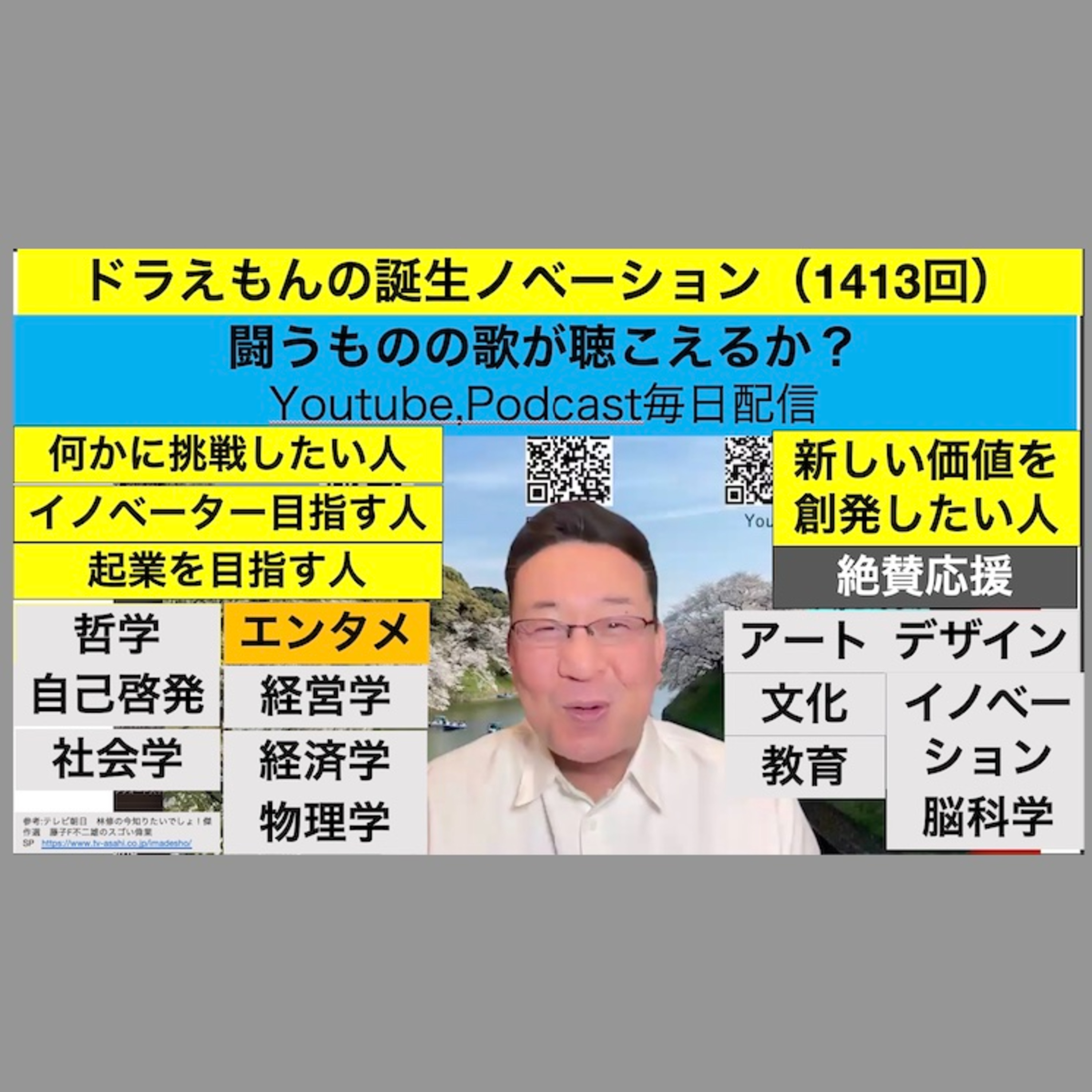 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"ドラえもんの誕生ノベーション(1413回)藤子・F・不二雄さんから、ドラえもん誕生のアイディアの作り方に感動しました曰く"未来の世界から来た猫型ロボットという、これはこういうまとまった形では、かつて存在しなかったものなんですけどもこれを一つ一つの部品に分解してみますと、まず未来、それからロボット、猫もそこら辺にうろうろしてるわけですそれ一つ一つの断片をとってみると、新しいものは何もないんです。自分の頭の中にしまいこまれている断片の、この集団の中をあれこれいじくり回してあれが使えそう、これが使えそうと、捨てたり組み合わせ直したり、そういう作業の結果、一つのアイディアってものがまとまってくるんです。"ここから私は思いました1、日常の断片を組み合わせる byシュンペーター2、デフォルトモードネットワーク by 苧阪直行3、とにかく分量をこなす by 吉本バナナ1995年に公開された映画「2112年ドラえもん誕生」という映画では、アイディアが出なくて、うたた寝をしていた藤子・F・不二雄さんが、タイムマシンが欲しい、屋根の猫、部屋にあった起き上がり小法師、こんなことから、ドラえもんが生まれたとありました普段から人のお話をよく聞く方で、メモ魔だったとのことなので、日々の生活の中にある、なんでもない普通の断片を、意識的に集められていたのかなあと、それがいつか花開く一つのネタの部品かわからないけど、大切な行動なのかも知れないと思いましたそして、まさにイノベーションの王道である、シュンペーターさんの、新結合を生み出すべく、既存のアイディアとアイディアを組み合わせることが、新しいものを生み出すということを、身をもってわかっておられたのかなあとも思いますさらに、そのアイデアというのは、簡単に生み出せるわけではないということも、そこにパッションがあって、諦めない気持ちのグリッドがあるからこそ京都大学大学院文学研究科実験心理学名誉教授の苧阪直行さんの、デフォルトモードネットワークが、うたた寝の時に発揮されて、これまで集めた断片の離れたもの同士が、結合をして、ドラえもんの閃きに至ったのかと、感動してしまいました一ヶ月前の連載告知では、まだアイデアがなく、かなりギリギリ追い詰められたところで、出てきたというところからもジェームズウェブヤングさんの、有名なアイディアの作り方、という本にある通り、アイディアは、一旦脇に置いて熟成させた中で、ある時閃く、ということにも、めちゃくちゃ通じるお話だと思いましたでもそこには、先日の吉本ばななさんのお話にあったように、圧倒的な分量を描いている、という前提もあるお話なんだろうなあと思いました。イノベーション的に言えば、量が質を超える、だなと。英語あの、ドラえもんも、既存のアイディアの掛け合わせであり、デフォルトモードネットワークの結果生み出されているドラえもんもイノベーションの黄金律で生まれていることに感動しました一言で言えばドラえもんの誕生ノベーションそんな話をしています^ ^参考:テレビ朝日 林修の今知りたいでしょ!傑作選 藤子F不二雄のスゴい偉業SP 2025/3/1 https://www.tv-asahi.co.jp/imadesho/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/gE-xcMovHLA2025-03-0216 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"ドラえもんの誕生ノベーション(1413回)藤子・F・不二雄さんから、ドラえもん誕生のアイディアの作り方に感動しました曰く"未来の世界から来た猫型ロボットという、これはこういうまとまった形では、かつて存在しなかったものなんですけどもこれを一つ一つの部品に分解してみますと、まず未来、それからロボット、猫もそこら辺にうろうろしてるわけですそれ一つ一つの断片をとってみると、新しいものは何もないんです。自分の頭の中にしまいこまれている断片の、この集団の中をあれこれいじくり回してあれが使えそう、これが使えそうと、捨てたり組み合わせ直したり、そういう作業の結果、一つのアイディアってものがまとまってくるんです。"ここから私は思いました1、日常の断片を組み合わせる byシュンペーター2、デフォルトモードネットワーク by 苧阪直行3、とにかく分量をこなす by 吉本バナナ1995年に公開された映画「2112年ドラえもん誕生」という映画では、アイディアが出なくて、うたた寝をしていた藤子・F・不二雄さんが、タイムマシンが欲しい、屋根の猫、部屋にあった起き上がり小法師、こんなことから、ドラえもんが生まれたとありました普段から人のお話をよく聞く方で、メモ魔だったとのことなので、日々の生活の中にある、なんでもない普通の断片を、意識的に集められていたのかなあと、それがいつか花開く一つのネタの部品かわからないけど、大切な行動なのかも知れないと思いましたそして、まさにイノベーションの王道である、シュンペーターさんの、新結合を生み出すべく、既存のアイディアとアイディアを組み合わせることが、新しいものを生み出すということを、身をもってわかっておられたのかなあとも思いますさらに、そのアイデアというのは、簡単に生み出せるわけではないということも、そこにパッションがあって、諦めない気持ちのグリッドがあるからこそ京都大学大学院文学研究科実験心理学名誉教授の苧阪直行さんの、デフォルトモードネットワークが、うたた寝の時に発揮されて、これまで集めた断片の離れたもの同士が、結合をして、ドラえもんの閃きに至ったのかと、感動してしまいました一ヶ月前の連載告知では、まだアイデアがなく、かなりギリギリ追い詰められたところで、出てきたというところからもジェームズウェブヤングさんの、有名なアイディアの作り方、という本にある通り、アイディアは、一旦脇に置いて熟成させた中で、ある時閃く、ということにも、めちゃくちゃ通じるお話だと思いましたでもそこには、先日の吉本ばななさんのお話にあったように、圧倒的な分量を描いている、という前提もあるお話なんだろうなあと思いました。イノベーション的に言えば、量が質を超える、だなと。英語あの、ドラえもんも、既存のアイディアの掛け合わせであり、デフォルトモードネットワークの結果生み出されているドラえもんもイノベーションの黄金律で生まれていることに感動しました一言で言えばドラえもんの誕生ノベーションそんな話をしています^ ^参考:テレビ朝日 林修の今知りたいでしょ!傑作選 藤子F不二雄のスゴい偉業SP 2025/3/1 https://www.tv-asahi.co.jp/imadesho/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/gE-xcMovHLA2025-03-0216 min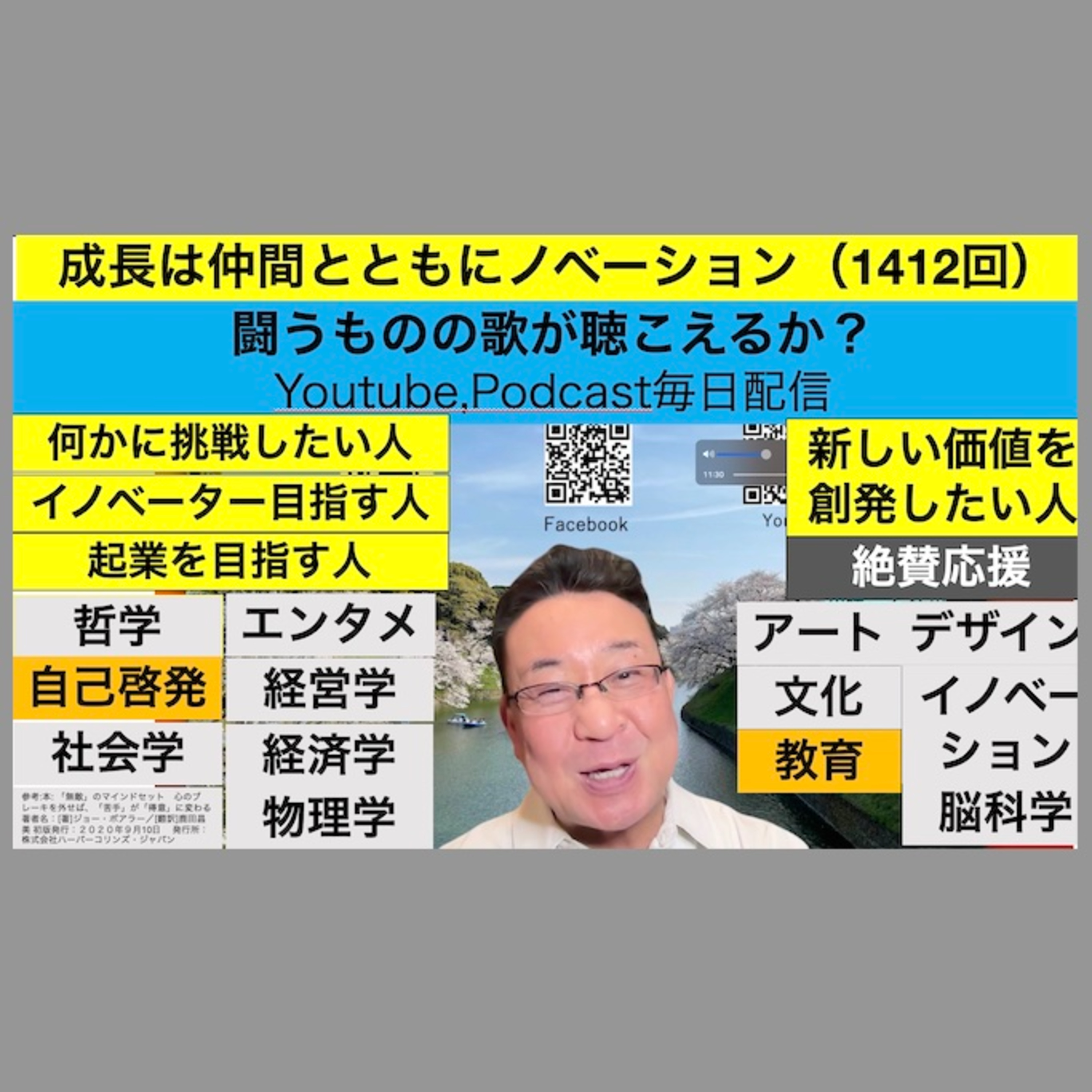 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"成長は仲間とともにノベーション(1412回)スタンフォード大学教育学部教授のジョー・ボアラーさんから紹介頂いた、数学者のウリ・トレイスマンさんの活動に、目から鱗が落ちました"テキサス大学オースティン校の数学者ウリ・トレイスマンは、以前カリフォルニア大学バークレー校で教鞭を執っていたときに、微積分を受講したアフリカ系アメリカ人の学生の60%が単位を落としていることに気がついた。""ウリは、勉強に取り組む学生を観察することで、1つの違いを発見した""アフリカ系アメリカ人の学生は、数学の問題にひとりで取り組んだのに対し、中国系アメリカ人の学生は協力して取り組んでいたのだ。""ウリは仲間と共同で、非白人の学生を含む、学業がうまくいっていない学生のためのワークショップを設け、ウリが「手ごたえのある内容でありながら、気持ちに寄り添って支援する学問的環境」と表現する学習環境をこしらえた""結果として、学業成績に著しい改善が見られた。2年以内に、アフリカ系アメリカ人の学生の落第率はゼロになり、ワークショップに参加したアフリカ系アメリカ人とラテン系の学生が、白人とアジア人のクラスメートの成績を上回ったのだ。"ここから私は思いました1、仲間は個々の成長を加速する2、仲間は底上げではなく上回る3、イノベーター3つのフレームは自らの成長をも加速する私が大学のセンター試験を受験する際には、図書館に篭って一人黙々と過去問を解きまくったり、単語覚えたり、必死に自分一人で勉強して、なんとかこんとか、引っかかっていまにいたる訳ですが実は、仲間と共に、勉強をし合った方が、実は成績を上げることができると、いうことには、目から鱗が落ちる思いでした確かに、できない生徒を教えてくれたり、ノートを貸してくれたりの、一方的に教えてもらう、できる優しい方々は沢山おられましたが、お互いにそれが成長につながる、共同作業というイメージは全くありませんでした今回のお話では、そのグループのできない人を底上げするだけではなく、全体として成長に繋がるということは、今私もチーム制でワークショップをやっていますが、そのやり方が実はとても個々人の成長にも効果的なのかと、改めて思いました私のワークショップでは、毎年続けられる場合、前年度の参加メンバーが、今度はチューターという形で教えたりアドバイスする立場に変わることも入れており、人に教えるというのもまた一つ成長する要素になってるかも知れないとも思いました思うのは、あまりに、効率的に、たくさんの問題を解くことが成長につながる、というのは、実はバイアスで、一つの事柄をみんなで意見を交わしながら、本質を理解していくということが実は、結果的には良い成長と結果に結びつくのかも知れないということですイノベーター3つのフレームでは、うちから溢れ出る「パッション」、そして一人ではできないことも「仲間」と共にやれば進める、そして自分たちだけが喜ぶんじゃなく世の中の人に喜んでもらうための「大義」が、大切との話をしていますがここにもででくる「仲間」の効用は、分業にありますが、実は、今回学んだ、自己の成長、ということにも、実はイノベーター3つのフレームで実施するイノベーション活動は、繋がるということかも知れないと思いましたそう考えると、実は自分の成長のためには、自分だけでなく仲間と共に学び生活する必要があってそして、イノベーション活動をするということは、仲間とも活動を通して、実は自分ね成長にも繋がることになるそんなことを思いました一言で言えば自分の成長は仲間とともにノベーションそんな話をしています^ ^参考:本: 「無敵」のマインドセット 心のブレーキを外せば、「苦手」が「得意」に変わる 著者名:[著]ジョー・ボアラー/[翻訳]鹿田昌美 初版発行:2020年9月10日 発行所:株式会社ハーパーコリンズ・ジャパン動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/bNBoiE1Kg0c2025-03-0117 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"成長は仲間とともにノベーション(1412回)スタンフォード大学教育学部教授のジョー・ボアラーさんから紹介頂いた、数学者のウリ・トレイスマンさんの活動に、目から鱗が落ちました"テキサス大学オースティン校の数学者ウリ・トレイスマンは、以前カリフォルニア大学バークレー校で教鞭を執っていたときに、微積分を受講したアフリカ系アメリカ人の学生の60%が単位を落としていることに気がついた。""ウリは、勉強に取り組む学生を観察することで、1つの違いを発見した""アフリカ系アメリカ人の学生は、数学の問題にひとりで取り組んだのに対し、中国系アメリカ人の学生は協力して取り組んでいたのだ。""ウリは仲間と共同で、非白人の学生を含む、学業がうまくいっていない学生のためのワークショップを設け、ウリが「手ごたえのある内容でありながら、気持ちに寄り添って支援する学問的環境」と表現する学習環境をこしらえた""結果として、学業成績に著しい改善が見られた。2年以内に、アフリカ系アメリカ人の学生の落第率はゼロになり、ワークショップに参加したアフリカ系アメリカ人とラテン系の学生が、白人とアジア人のクラスメートの成績を上回ったのだ。"ここから私は思いました1、仲間は個々の成長を加速する2、仲間は底上げではなく上回る3、イノベーター3つのフレームは自らの成長をも加速する私が大学のセンター試験を受験する際には、図書館に篭って一人黙々と過去問を解きまくったり、単語覚えたり、必死に自分一人で勉強して、なんとかこんとか、引っかかっていまにいたる訳ですが実は、仲間と共に、勉強をし合った方が、実は成績を上げることができると、いうことには、目から鱗が落ちる思いでした確かに、できない生徒を教えてくれたり、ノートを貸してくれたりの、一方的に教えてもらう、できる優しい方々は沢山おられましたが、お互いにそれが成長につながる、共同作業というイメージは全くありませんでした今回のお話では、そのグループのできない人を底上げするだけではなく、全体として成長に繋がるということは、今私もチーム制でワークショップをやっていますが、そのやり方が実はとても個々人の成長にも効果的なのかと、改めて思いました私のワークショップでは、毎年続けられる場合、前年度の参加メンバーが、今度はチューターという形で教えたりアドバイスする立場に変わることも入れており、人に教えるというのもまた一つ成長する要素になってるかも知れないとも思いました思うのは、あまりに、効率的に、たくさんの問題を解くことが成長につながる、というのは、実はバイアスで、一つの事柄をみんなで意見を交わしながら、本質を理解していくということが実は、結果的には良い成長と結果に結びつくのかも知れないということですイノベーター3つのフレームでは、うちから溢れ出る「パッション」、そして一人ではできないことも「仲間」と共にやれば進める、そして自分たちだけが喜ぶんじゃなく世の中の人に喜んでもらうための「大義」が、大切との話をしていますがここにもででくる「仲間」の効用は、分業にありますが、実は、今回学んだ、自己の成長、ということにも、実はイノベーター3つのフレームで実施するイノベーション活動は、繋がるということかも知れないと思いましたそう考えると、実は自分の成長のためには、自分だけでなく仲間と共に学び生活する必要があってそして、イノベーション活動をするということは、仲間とも活動を通して、実は自分ね成長にも繋がることになるそんなことを思いました一言で言えば自分の成長は仲間とともにノベーションそんな話をしています^ ^参考:本: 「無敵」のマインドセット 心のブレーキを外せば、「苦手」が「得意」に変わる 著者名:[著]ジョー・ボアラー/[翻訳]鹿田昌美 初版発行:2020年9月10日 発行所:株式会社ハーパーコリンズ・ジャパン動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/bNBoiE1Kg0c2025-03-0117 min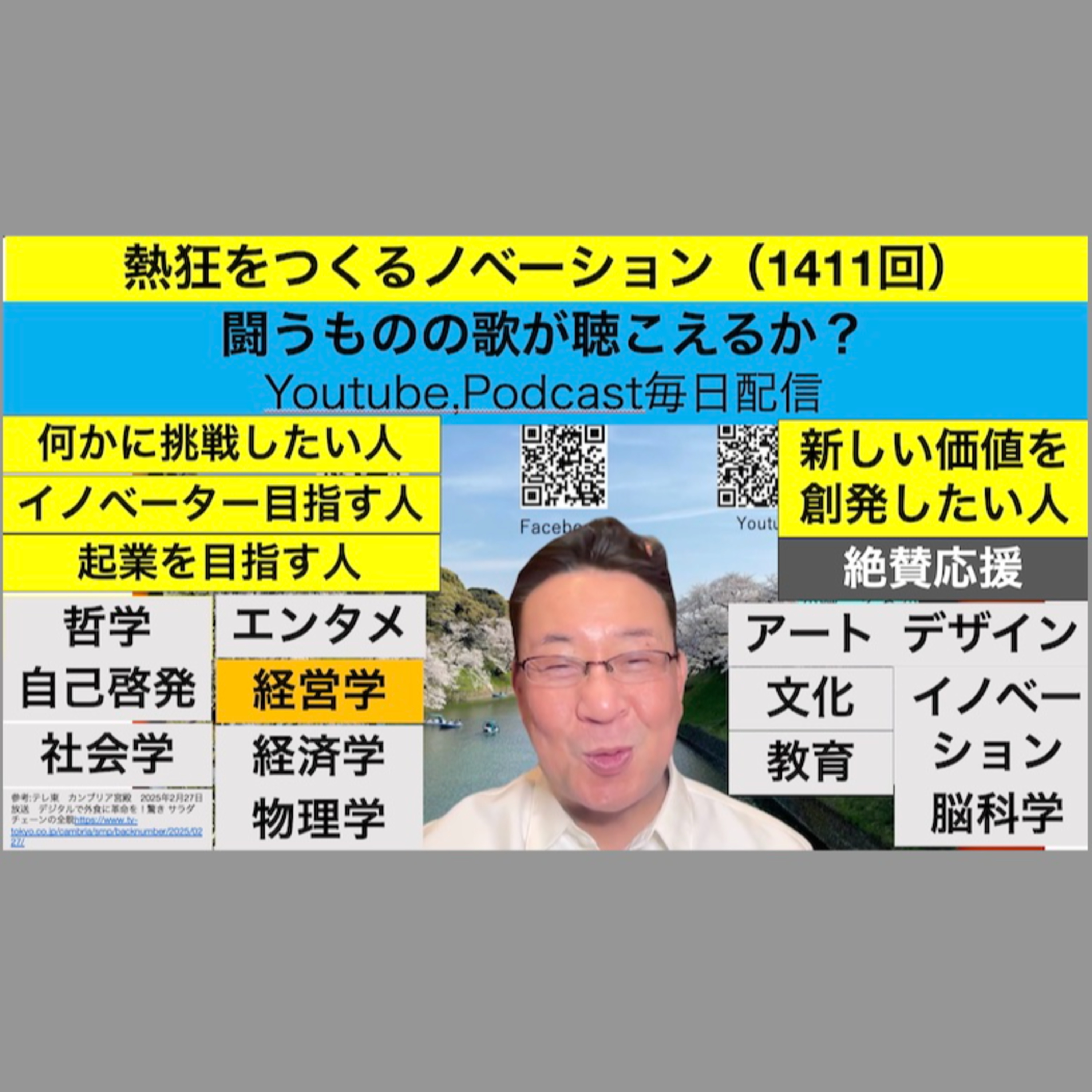 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"熱狂をつくるノベーション(1411回)めちゃくちゃ美味しいサラダのお店のクリスプCEO 宮野浩史さんの言葉に躍進の秘密を教えて頂きました曰く"ぼくら、「テクノロジーと人を掛け合わせて外食を変革しよう」と掲げている会社と思うんですけどもやっぱり「熱気的なファンを作っていこう」というぼくらが掲げてるミッションお客様のことを知れて、はじめてお客様の期待を超越できるのかなと思うので、頑張っていきましょう"ここから私は思いました1、熱狂をつくる2、そのために、期待値を超える3、そのために、相手を知るクリスプのサラダは私もめちゃくちゃ好きなので、何故にあんなに美味しいのか?そして満足度が高いのか?その秘密に驚きました!まず一つは、宮野社長の言葉にある、ミッションすなわち「大義」をとことんまで追求しているからなんだなあということが、よく分かりました"熱狂的なファンを作る"これが全てにわたって、こだわり抜いている、そこに凄さを感じました。しかし、いうは易しで、簡単なことではないわけですが、それを実現するためには、何が必要かと考えると、お客様の期待値を超える、ということなんだなと思いました期待値を超えてはじめて、感動が生まれる、というのは、まさにその通りだなと思います。私も、だいたいうまくいったプロジェクトは、お客様の想定のはるか上の成果を出したときに、ある意味感動と共に喜んでもらえる、そんな体験も何回かしたことがありますしかし、それも、いうは易しで、じゃあそのために何が必要なんだということが1番ミソで、それが、相手を知る、ということにつながるのかと思いました。つまり、相手の期待値を、相手に合わせて、綿密に知ることで、熱狂的なファンを作るためには、どの層にどんなアプローチをすべきなのか、これを、テクノロジーと人の解釈を使って炙り出していく、ここに最大の強みがあるのかと思いました間違ってはいけないのは、それは、決して、テクノロジーありきではないということだと思いました。つまり、大義として何を実現したいのか?その上で期待値は何か?そして、その期待値をどう超えるのか?その観点の上に、テクノロジーを掛け合わせて、エピテンスを共有して、そして、さらに人として解釈や意見交換して答えを見出していくそんなアプローチが必要なのだなあと、つくづく思いましたまた、実は、熱狂はお客様だけでなく、社員の熱狂も作ってるとも思いました。シフト表をデジタル化して、自己決定できるようにし、かつどの店舗でも人がいないとこは、社員の時給を上げて募集もできるこれはすなわち、社員の、押し付けられるシフトへの期待値を、自己選択としてはるかに超えて、さらには給与という期待も、自己選択で越えることもできる、まさに、社員の熱狂も作ってるなあとクリスプの秘密は熱狂を作り出すこと、そのために、テクノロジーで期待値を知り、そしてそれを超越する策をみんなで作るそんなことなのかなあと思いました一言で言えば熱狂を作るノベーションその一点に全てがある、そんなことを思いました^ ^参考:テレ東 カンブリア宮殿 2025年2月27日放送 デジタルで外食に革命を!驚き サラダチェーンの全貌https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/smp/backnumber/2025/0227/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/Fi7nLWkRE-w2025-02-2820 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"熱狂をつくるノベーション(1411回)めちゃくちゃ美味しいサラダのお店のクリスプCEO 宮野浩史さんの言葉に躍進の秘密を教えて頂きました曰く"ぼくら、「テクノロジーと人を掛け合わせて外食を変革しよう」と掲げている会社と思うんですけどもやっぱり「熱気的なファンを作っていこう」というぼくらが掲げてるミッションお客様のことを知れて、はじめてお客様の期待を超越できるのかなと思うので、頑張っていきましょう"ここから私は思いました1、熱狂をつくる2、そのために、期待値を超える3、そのために、相手を知るクリスプのサラダは私もめちゃくちゃ好きなので、何故にあんなに美味しいのか?そして満足度が高いのか?その秘密に驚きました!まず一つは、宮野社長の言葉にある、ミッションすなわち「大義」をとことんまで追求しているからなんだなあということが、よく分かりました"熱狂的なファンを作る"これが全てにわたって、こだわり抜いている、そこに凄さを感じました。しかし、いうは易しで、簡単なことではないわけですが、それを実現するためには、何が必要かと考えると、お客様の期待値を超える、ということなんだなと思いました期待値を超えてはじめて、感動が生まれる、というのは、まさにその通りだなと思います。私も、だいたいうまくいったプロジェクトは、お客様の想定のはるか上の成果を出したときに、ある意味感動と共に喜んでもらえる、そんな体験も何回かしたことがありますしかし、それも、いうは易しで、じゃあそのために何が必要なんだということが1番ミソで、それが、相手を知る、ということにつながるのかと思いました。つまり、相手の期待値を、相手に合わせて、綿密に知ることで、熱狂的なファンを作るためには、どの層にどんなアプローチをすべきなのか、これを、テクノロジーと人の解釈を使って炙り出していく、ここに最大の強みがあるのかと思いました間違ってはいけないのは、それは、決して、テクノロジーありきではないということだと思いました。つまり、大義として何を実現したいのか?その上で期待値は何か?そして、その期待値をどう超えるのか?その観点の上に、テクノロジーを掛け合わせて、エピテンスを共有して、そして、さらに人として解釈や意見交換して答えを見出していくそんなアプローチが必要なのだなあと、つくづく思いましたまた、実は、熱狂はお客様だけでなく、社員の熱狂も作ってるとも思いました。シフト表をデジタル化して、自己決定できるようにし、かつどの店舗でも人がいないとこは、社員の時給を上げて募集もできるこれはすなわち、社員の、押し付けられるシフトへの期待値を、自己選択としてはるかに超えて、さらには給与という期待も、自己選択で越えることもできる、まさに、社員の熱狂も作ってるなあとクリスプの秘密は熱狂を作り出すこと、そのために、テクノロジーで期待値を知り、そしてそれを超越する策をみんなで作るそんなことなのかなあと思いました一言で言えば熱狂を作るノベーションその一点に全てがある、そんなことを思いました^ ^参考:テレ東 カンブリア宮殿 2025年2月27日放送 デジタルで外食に革命を!驚き サラダチェーンの全貌https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/smp/backnumber/2025/0227/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/Fi7nLWkRE-w2025-02-2820 min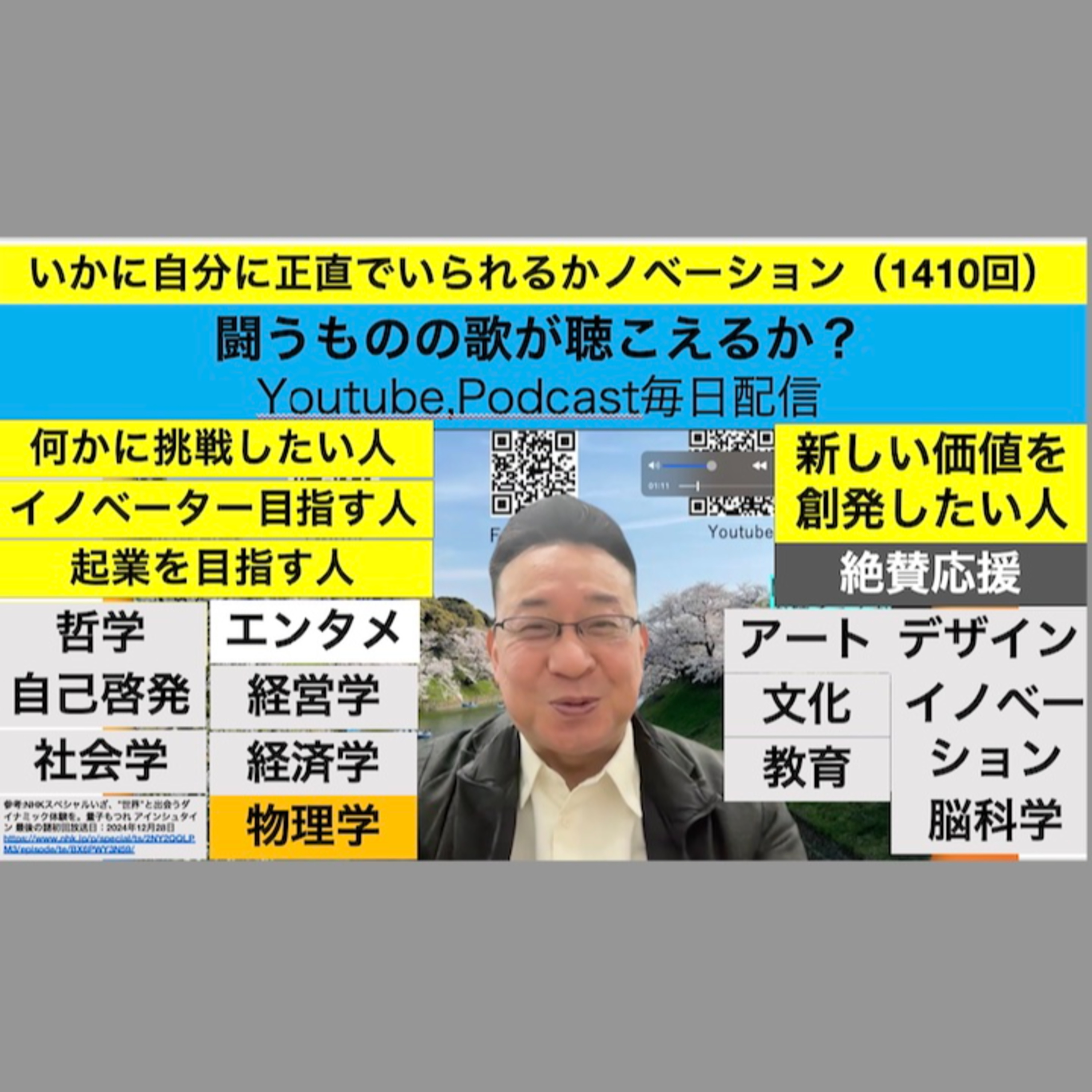 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"いかに自分に正直でいられるかノベーション(1410回)2022年にノーベル物理学賞を取り、量子もつれの壮大な実験をして、それがあることを証明したジョン・クラウザーさんの言葉に感動しました曰く"大事なのは自分に正直になることだそして最も難しいことの一つは、もし理解できないなら、それを認めることだ私は(自然が出した実験結果に)混乱してるが、少なくとも今、何故混乱しているのか、分かるくらいには進むことができたそれが私にできた最高のことだったんだ"ここから私は思いました1、わかったフリや蓋をしない自分に正直であれ2、理解できないことを認めるのは難しい無知の知を認める3、それでも前進することネガティブケイパビリデイアインシュタインがおかした最大の間違いと言われる量子もつれの存在について、あることは証明されたが、何故それがあるなのか?はまだわからないとのことですが科学の世界においてなお、まったく解明されてなく、かつ常識的な観点ではまったく理解できないことがある、というのは、人類の冒険や挑戦、そして進化は、まだまだ続くのだなあと、逆に嬉しくなりましたこれに対するジョン・クラウザーの態度を見るときに、科学のことに限らず、普段の生活の中でも、自分の常識に照らして、わかったふりをしない、自分の違和感に正直であることが、本当に大切だなあと思いました。これがきっと、世の中にまったく新しい価値を作り出す、その第一歩なのだと。それでも、自らが理解できないことを認めるのは、本当に難しいと思います。これほ、例えば、組織における、新規事業の提案を誰かが持ってきたとして、それがまったく自分の理解を超えていたときに、どんな態度が取れるか量子もつれのように、現象はあるのに、理由がわからない、理解できない、そんなことに対面したときに、真っ向から否定せずに、一緒に考えてみようと、言えるのか、まずは実験してみようと、言えるのか、これによってその組織やチームのアクティビティが変わる気がしますそれを前進させるのは、まだわかってないことがあるのが、当たり前であるという、ある意味、無知の知と、そして、ジョンキースさんの言われる、わからないことを分からないこととして、すぐに答えを出そうとしない、ネガティヴケイパビリティが大事なんだろうなあと思いますしかし、言うのは簡単だけど、これはなかなか難しい。組織には期限があるし、リソースも限られてるし。自分だけではできないかもしれないけども、少なくとも自分たちが行ったことは、きっと誰かの役に立つ、そんな思いを持ってやれるかどうか、そんな組織的な知の継承ができるようになってるか、そんなことが大切な気がしましたノーベル物理学賞の天野浩さんの言っておられた、自分のチャレンジは必ず誰かのためになる(自分の挑戦は誰かの役に立つノベーション(1370回))のお話も思い出しましたいかに自分に正直でいられるかノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHKスペシャルいざ、“世界”と出会うダイナミック体験を。量子もつれ アインシュタイン 最後の謎初回放送日:2024年12月28日https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/episode/te/BX6PWY3N59/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/l9_-M22l-W42025-02-2714 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"いかに自分に正直でいられるかノベーション(1410回)2022年にノーベル物理学賞を取り、量子もつれの壮大な実験をして、それがあることを証明したジョン・クラウザーさんの言葉に感動しました曰く"大事なのは自分に正直になることだそして最も難しいことの一つは、もし理解できないなら、それを認めることだ私は(自然が出した実験結果に)混乱してるが、少なくとも今、何故混乱しているのか、分かるくらいには進むことができたそれが私にできた最高のことだったんだ"ここから私は思いました1、わかったフリや蓋をしない自分に正直であれ2、理解できないことを認めるのは難しい無知の知を認める3、それでも前進することネガティブケイパビリデイアインシュタインがおかした最大の間違いと言われる量子もつれの存在について、あることは証明されたが、何故それがあるなのか?はまだわからないとのことですが科学の世界においてなお、まったく解明されてなく、かつ常識的な観点ではまったく理解できないことがある、というのは、人類の冒険や挑戦、そして進化は、まだまだ続くのだなあと、逆に嬉しくなりましたこれに対するジョン・クラウザーの態度を見るときに、科学のことに限らず、普段の生活の中でも、自分の常識に照らして、わかったふりをしない、自分の違和感に正直であることが、本当に大切だなあと思いました。これがきっと、世の中にまったく新しい価値を作り出す、その第一歩なのだと。それでも、自らが理解できないことを認めるのは、本当に難しいと思います。これほ、例えば、組織における、新規事業の提案を誰かが持ってきたとして、それがまったく自分の理解を超えていたときに、どんな態度が取れるか量子もつれのように、現象はあるのに、理由がわからない、理解できない、そんなことに対面したときに、真っ向から否定せずに、一緒に考えてみようと、言えるのか、まずは実験してみようと、言えるのか、これによってその組織やチームのアクティビティが変わる気がしますそれを前進させるのは、まだわかってないことがあるのが、当たり前であるという、ある意味、無知の知と、そして、ジョンキースさんの言われる、わからないことを分からないこととして、すぐに答えを出そうとしない、ネガティヴケイパビリティが大事なんだろうなあと思いますしかし、言うのは簡単だけど、これはなかなか難しい。組織には期限があるし、リソースも限られてるし。自分だけではできないかもしれないけども、少なくとも自分たちが行ったことは、きっと誰かの役に立つ、そんな思いを持ってやれるかどうか、そんな組織的な知の継承ができるようになってるか、そんなことが大切な気がしましたノーベル物理学賞の天野浩さんの言っておられた、自分のチャレンジは必ず誰かのためになる(自分の挑戦は誰かの役に立つノベーション(1370回))のお話も思い出しましたいかに自分に正直でいられるかノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHKスペシャルいざ、“世界”と出会うダイナミック体験を。量子もつれ アインシュタイン 最後の謎初回放送日:2024年12月28日https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/episode/te/BX6PWY3N59/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/l9_-M22l-W42025-02-2714 min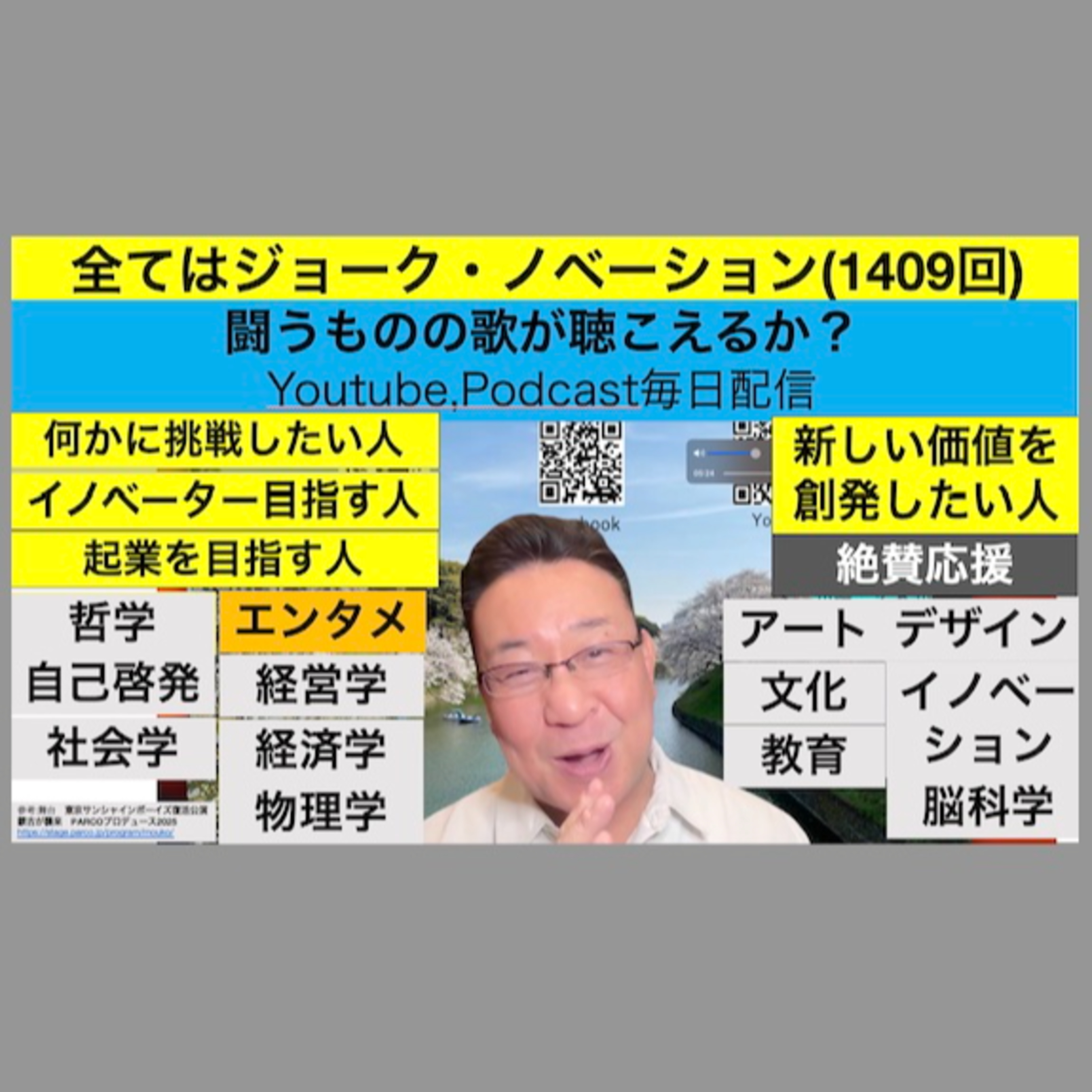 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"全てはジョーク・ノベーション(1409回)約束通り30年ぶりの復活を遂げた東京サンシャインボーイズ講演に、めちゃくちゃ感動と勇気を頂きました三谷幸喜さんの言葉に深く考えさせられました曰く"東京サンシャインボーイズの「罠」』のパンフレットには次回公演の告知を載せました。30年後の2024年9月。新宿シアタートップスにて上演予定。タイトルは『リア玉」。主演は梶原善。もちろんジョーク。誰も本気で実現するとは思っていません。最終公演の東京千楽。長年制作をやってくれていた大竹亜由美さんがパンフレットを見ながら僕に尋ねました。「本当に30年後が来た時、どうしますか」「やらないんじゃないかな。やらないと思うよ、たぶんね」だって全てはジョークなのですから。"ここから私は思いました1、エイプリールドリーム2、今、素敵なことを考える3、全てはジョークこの文章に三谷さんらしさが溢れていて、ニヤリとせざるを得ないなあと、嬉しくなりました確かPRtimeさんでやってた企画でもあったと思うのですが、エイプリールフールの日に、大きな夢の嘘をつこうってキャンペーンを思い出しました私は実は一回便乗してて、「ついに本日、全世界一世帯あたり一法人化の夢が叶いました!」って投稿したのですが私が感じたのは、未来のことを、あんまり真面目に考えるんじゃなくて、素敵なことが起こったら楽しいなあってことを、ジョークみたいにいっちゃった方がプレッシャーもないし、でも素敵なことをフリーハンドで考えられるし、何よりも、今の気持ちに素直になって挑戦を語れるので、とても素敵だなあと思いました東京サンシャインボーイズのリア玉も、そんな三谷さんの気持ちが実は込められていたんじゃないか、だからこそ、今回、実現しちゃってるんじゃないか、そんなことを思いましたまた、以前、満島ひかりさんのインタビューから、「人生は茶番ノベーション(1158回)」ってお話もしたのですが、このお話にも何か通じることがあるなあと思いました「全てはおとぎ話なのよ」と満島さんが、言ってくれると、何かいろんなことがあっても、気持ちが楽になって、そして楽しんでいられる、そんな心地を作ってくれる言葉だなあと感じてましたが"全ては、ジョークなのですから"という三谷さんの言葉も、人生の全てという意味で言われていなですが、何か、三谷さん自身のお話は、真面目に言ってるのか?ジョークなのか?よくわからないことになるとこが、またとても面白いのですがそんなひょうひょうと生きていくことができる、秘訣がそこにあるのかもしれないなあと思いました全てはジョークということで、新しい挑戦や、他の人からの目や、失敗することなどへの、セーフティネットを張っててくれながら、でも心理的安全性の中で実現しちゃうことができるようになるなんかそんな魔法の考え方かもしれないなあと思いました全てはジョークノベーションそんなことをお話ししてます^ ^参考:舞台 東京サンシャインボーイズ復活公演 蒙古が襲来 PARCOプロデュース2025https://stage.parco.jp/program/mouko/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/oCIklOeKp9g2025-02-2622 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"全てはジョーク・ノベーション(1409回)約束通り30年ぶりの復活を遂げた東京サンシャインボーイズ講演に、めちゃくちゃ感動と勇気を頂きました三谷幸喜さんの言葉に深く考えさせられました曰く"東京サンシャインボーイズの「罠」』のパンフレットには次回公演の告知を載せました。30年後の2024年9月。新宿シアタートップスにて上演予定。タイトルは『リア玉」。主演は梶原善。もちろんジョーク。誰も本気で実現するとは思っていません。最終公演の東京千楽。長年制作をやってくれていた大竹亜由美さんがパンフレットを見ながら僕に尋ねました。「本当に30年後が来た時、どうしますか」「やらないんじゃないかな。やらないと思うよ、たぶんね」だって全てはジョークなのですから。"ここから私は思いました1、エイプリールドリーム2、今、素敵なことを考える3、全てはジョークこの文章に三谷さんらしさが溢れていて、ニヤリとせざるを得ないなあと、嬉しくなりました確かPRtimeさんでやってた企画でもあったと思うのですが、エイプリールフールの日に、大きな夢の嘘をつこうってキャンペーンを思い出しました私は実は一回便乗してて、「ついに本日、全世界一世帯あたり一法人化の夢が叶いました!」って投稿したのですが私が感じたのは、未来のことを、あんまり真面目に考えるんじゃなくて、素敵なことが起こったら楽しいなあってことを、ジョークみたいにいっちゃった方がプレッシャーもないし、でも素敵なことをフリーハンドで考えられるし、何よりも、今の気持ちに素直になって挑戦を語れるので、とても素敵だなあと思いました東京サンシャインボーイズのリア玉も、そんな三谷さんの気持ちが実は込められていたんじゃないか、だからこそ、今回、実現しちゃってるんじゃないか、そんなことを思いましたまた、以前、満島ひかりさんのインタビューから、「人生は茶番ノベーション(1158回)」ってお話もしたのですが、このお話にも何か通じることがあるなあと思いました「全てはおとぎ話なのよ」と満島さんが、言ってくれると、何かいろんなことがあっても、気持ちが楽になって、そして楽しんでいられる、そんな心地を作ってくれる言葉だなあと感じてましたが"全ては、ジョークなのですから"という三谷さんの言葉も、人生の全てという意味で言われていなですが、何か、三谷さん自身のお話は、真面目に言ってるのか?ジョークなのか?よくわからないことになるとこが、またとても面白いのですがそんなひょうひょうと生きていくことができる、秘訣がそこにあるのかもしれないなあと思いました全てはジョークということで、新しい挑戦や、他の人からの目や、失敗することなどへの、セーフティネットを張っててくれながら、でも心理的安全性の中で実現しちゃうことができるようになるなんかそんな魔法の考え方かもしれないなあと思いました全てはジョークノベーションそんなことをお話ししてます^ ^参考:舞台 東京サンシャインボーイズ復活公演 蒙古が襲来 PARCOプロデュース2025https://stage.parco.jp/program/mouko/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/oCIklOeKp9g2025-02-2622 min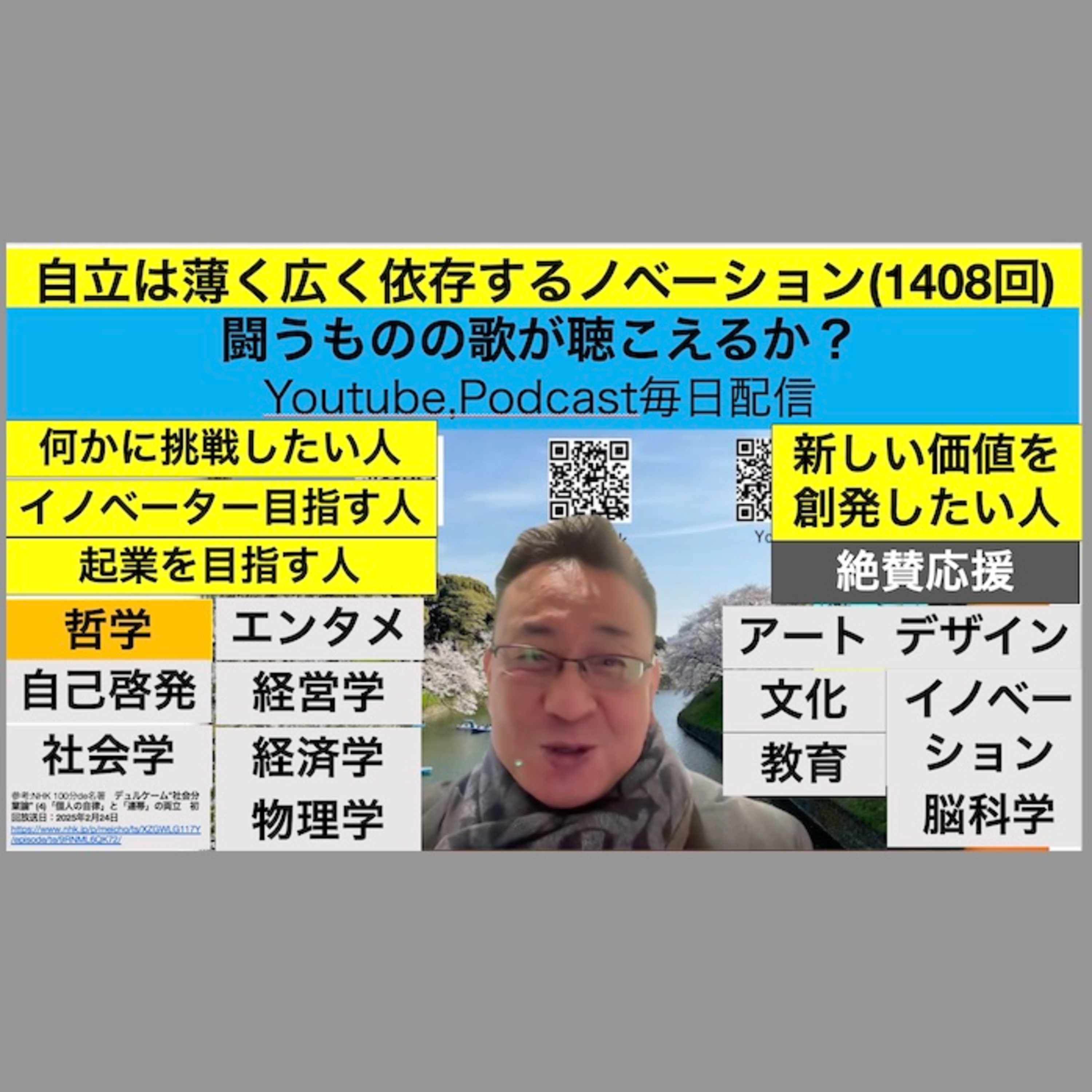 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"自立は薄く広く依存するノベーション(1408回)脳性麻痺の障害を持つ、小児科医の熊谷晋一郎さんの当事者研究の言葉に、とても勉強させられました"自立している状況ってのは、何者にも依存しないのではなくって、かといって少数のものに依存するってのも、これも違っていて、なぜなら、少数のものから裏切られたらひとたまりもないから、それは自立とは言えないわけですよねそうではなくって、一つのものから裏切られても大丈夫なほどに、たくさんのものに依存している状況、これが怯えずに、しかし頼りながら自立するためにとても重要な状況だ、と言うのがこれまで発信してきたことだったわけです"ここから私は思いました1、弱い責任2、オプション・バリュー3、仲間の重要性自立と依存、という言葉は、全く正反対のことを言っている気がしていましたが、実はお互いの関係性の中に両立している、ということに衝撃を受けましたこのお話で思い出したのが、哲学者の戸谷洋志さんの言われている"弱い責任"のお話です。(責任を果たすには頼るノベーション(1311回))私が思ったのは、実は自己責任というのは、ゴールが自分で解決すること、ではなく、責任を果たすということであれば、他人に頼るということを、むしろすべきである、ということに、とてもシナジーを感じましたまた、山口周さんより教わった、オプション・バリューのお話も思い出しました(オプション・バリュー・ノベーション(1406回))大きなリスクを取る場合、背水の陣で臨むよりも、沢山のオプションを持った方が、成功の確率が高い、ということも、とても近い話になるなあと思いましたこのあたりを合わせて考えると、自立、というとても強い言葉は、自らが立ち上がって責任を果たす、ということにもつながり、それを果たすためには、実は誰かを頼ることは必要なことだし自立して何かを成し遂げるためには、一人という一つのオプションに絞り込んでで成し遂げることを目指すということではなく、沢山の人々の組むということでリスクヘッジをしていくということにも、つながるなと思いましたいずれでも言えることは、仲間、とともにあるということがとても重要な話だなあと思いましたイノベーター3つのフレームにおけるパッション、仲間、大義における、仲間の意味は、一人じゃできないことも、仲間とならできる、そんな意味ですが実は、仲間がいることによって、自らのパッションの源としての自立を促すことができる、と考えると、仲間と自分の関係性によって、お互いの自立を自立とは、孤独や孤立ではなく、むしろ積極的に周りに頼れるという気持ちを持てて、行動に移せるなかなか迷惑をかけてしまうだとか、一人でやり切らねばならないという、強迫観念から、いかに抜け出せるかデュルケームさんが言われている、依存が繋がることで社会ができている、と考えると、それは全く社会で生きるために必要なことなのだそれこそが自立、ということなんだなあと、改めて思わせて頂きました自立は薄く広く依存することノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHK 100分de名著 デュルケーム“社会分業論” (4)「個人の自律」と「連帯」の両立 初回放送日:2025年2月24日 https://www.nhk.jp/p/meicho/ts/XZGWLG117Y/episode/te/9RNML6QK72/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/D3wLXUKzh1w2025-02-2508 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"自立は薄く広く依存するノベーション(1408回)脳性麻痺の障害を持つ、小児科医の熊谷晋一郎さんの当事者研究の言葉に、とても勉強させられました"自立している状況ってのは、何者にも依存しないのではなくって、かといって少数のものに依存するってのも、これも違っていて、なぜなら、少数のものから裏切られたらひとたまりもないから、それは自立とは言えないわけですよねそうではなくって、一つのものから裏切られても大丈夫なほどに、たくさんのものに依存している状況、これが怯えずに、しかし頼りながら自立するためにとても重要な状況だ、と言うのがこれまで発信してきたことだったわけです"ここから私は思いました1、弱い責任2、オプション・バリュー3、仲間の重要性自立と依存、という言葉は、全く正反対のことを言っている気がしていましたが、実はお互いの関係性の中に両立している、ということに衝撃を受けましたこのお話で思い出したのが、哲学者の戸谷洋志さんの言われている"弱い責任"のお話です。(責任を果たすには頼るノベーション(1311回))私が思ったのは、実は自己責任というのは、ゴールが自分で解決すること、ではなく、責任を果たすということであれば、他人に頼るということを、むしろすべきである、ということに、とてもシナジーを感じましたまた、山口周さんより教わった、オプション・バリューのお話も思い出しました(オプション・バリュー・ノベーション(1406回))大きなリスクを取る場合、背水の陣で臨むよりも、沢山のオプションを持った方が、成功の確率が高い、ということも、とても近い話になるなあと思いましたこのあたりを合わせて考えると、自立、というとても強い言葉は、自らが立ち上がって責任を果たす、ということにもつながり、それを果たすためには、実は誰かを頼ることは必要なことだし自立して何かを成し遂げるためには、一人という一つのオプションに絞り込んでで成し遂げることを目指すということではなく、沢山の人々の組むということでリスクヘッジをしていくということにも、つながるなと思いましたいずれでも言えることは、仲間、とともにあるということがとても重要な話だなあと思いましたイノベーター3つのフレームにおけるパッション、仲間、大義における、仲間の意味は、一人じゃできないことも、仲間とならできる、そんな意味ですが実は、仲間がいることによって、自らのパッションの源としての自立を促すことができる、と考えると、仲間と自分の関係性によって、お互いの自立を自立とは、孤独や孤立ではなく、むしろ積極的に周りに頼れるという気持ちを持てて、行動に移せるなかなか迷惑をかけてしまうだとか、一人でやり切らねばならないという、強迫観念から、いかに抜け出せるかデュルケームさんが言われている、依存が繋がることで社会ができている、と考えると、それは全く社会で生きるために必要なことなのだそれこそが自立、ということなんだなあと、改めて思わせて頂きました自立は薄く広く依存することノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHK 100分de名著 デュルケーム“社会分業論” (4)「個人の自律」と「連帯」の両立 初回放送日:2025年2月24日 https://www.nhk.jp/p/meicho/ts/XZGWLG117Y/episode/te/9RNML6QK72/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/D3wLXUKzh1w2025-02-2508 min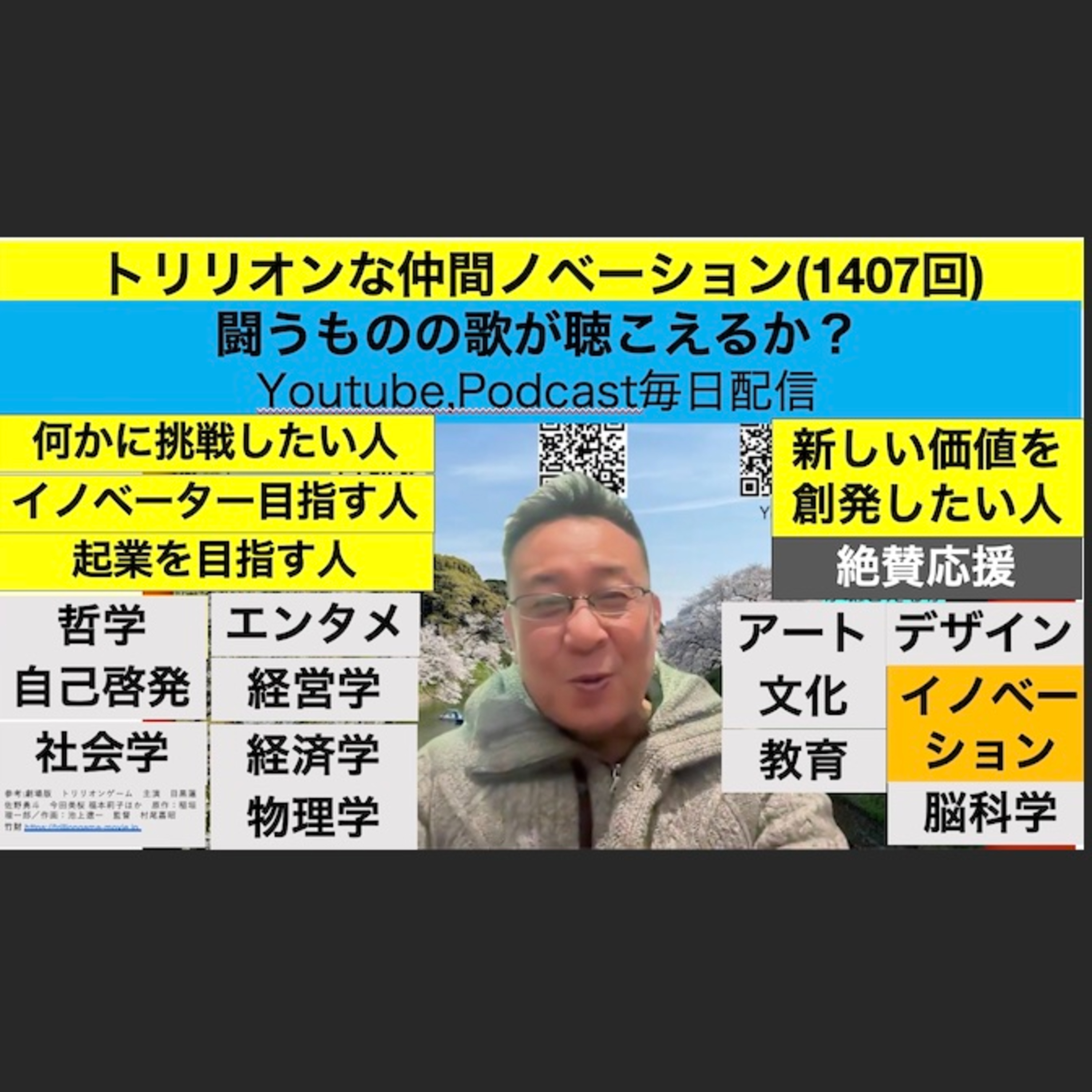 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"トリリオンな仲間ノベーション(1407回)劇場版トリリオンゲームから、イノベーターにとって何が1番大切なものか、を教えて頂きました"ターゲットは”世界一のカジノ王”。1兆ドル稼いでこの世のすべてを手に入れる!!"のキャッチフレーズの通り、めちゃくちゃエキサイティングな起業家のストーリーで、ワクワクと感動に打ち震えました!ここから私は思いました1、トレードオフに挑む3、アウフヘーベンで解決を図る3、大義はトリリオンな仲間ドラマでは、"資金ゼロ・事業計画ゼロの状態から起業し、ハッカー大会、ECサイト、花ビジネス、ホストクラブ、スマホゲーム、動画配信サービス、キャッシュレス決済と、あらゆる事業に挑戦"してビジネスの成功を手にいていくところまでだったのですが、映画ではカジノ王への挑戦という、主人公のハルのパッションは凄まじかったです。今回改めて感じたのは、イノベーターは、トレードオフに挑むからこそ、新たなチャンスを掴み取るということですカジノ王に挑むためには、カジノ建設の土地の島民のこれまでの生活というものを、ある程度変革しなければ、無しうることはできないものなので、必然的にその土地の島民からの反対運動が起きますがカジノによる経済性と、島民の静かな生活、このトレードオフが、必ず生じて、それが一筋縄ではいかない課題だと、アジェンダシエィパーするというところに、イノベーターの着目点があるなあと思いましたこの対立する二つの課題を解く方法論として、ヘーゲルのアウフヘーベンのように、対立する二つの事柄を双方否定しない形で第三の道を解決策として提示できるか、というところにイノベーターの腕の見せ所があると思います本作における解決策も、なかなかのアウフヘーベンなのですが、思い出したのは、ノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングが提唱したトランセンド法のように、ペルーとエクアドルの紛争地域に、平和公園を設立して、対立を解消するというようなイノベーター的な仕掛け作りです今回はハルの誰もが思い付かないようなアウフヘーベンな策が炸裂するところがかなりの見どころでしたそして、その解決策にも通じるし、さらにはこの作品の私が最もイノベーティブで素敵なあと思う点は、トリリオンゲームという名の通り、大義は150兆円企業になることとあるのですが実はそこには、ガク(坂本勇斗)、凜々(福田莉子)など社員はじめ、投資家の祁答院(吉川晃司)、ライバルの桐姫(今田美桜)、そして島民の皆様が、仲間として、ハルのパッションに突き動かされ、そしてハルも仲間を大切にするというところが、大きな価値なのかなあと思いましたつまり1番トリリオンなのは、仲間たちである、というそんなメッセージを頂きました一言で言うとトリリオンな仲間ノベーションそんなことを感じました^ ^参考:劇場版 トリリオンゲーム 主演 目黒蓮佐野勇斗 今田美桜 福本莉子ほか 原作:稲垣理一郎/作画:池上遼一 監督 村尾嘉昭 竹財 https://trilliongame-movie.jp 動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/1ildraaYyic2025-02-2416 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"トリリオンな仲間ノベーション(1407回)劇場版トリリオンゲームから、イノベーターにとって何が1番大切なものか、を教えて頂きました"ターゲットは”世界一のカジノ王”。1兆ドル稼いでこの世のすべてを手に入れる!!"のキャッチフレーズの通り、めちゃくちゃエキサイティングな起業家のストーリーで、ワクワクと感動に打ち震えました!ここから私は思いました1、トレードオフに挑む3、アウフヘーベンで解決を図る3、大義はトリリオンな仲間ドラマでは、"資金ゼロ・事業計画ゼロの状態から起業し、ハッカー大会、ECサイト、花ビジネス、ホストクラブ、スマホゲーム、動画配信サービス、キャッシュレス決済と、あらゆる事業に挑戦"してビジネスの成功を手にいていくところまでだったのですが、映画ではカジノ王への挑戦という、主人公のハルのパッションは凄まじかったです。今回改めて感じたのは、イノベーターは、トレードオフに挑むからこそ、新たなチャンスを掴み取るということですカジノ王に挑むためには、カジノ建設の土地の島民のこれまでの生活というものを、ある程度変革しなければ、無しうることはできないものなので、必然的にその土地の島民からの反対運動が起きますがカジノによる経済性と、島民の静かな生活、このトレードオフが、必ず生じて、それが一筋縄ではいかない課題だと、アジェンダシエィパーするというところに、イノベーターの着目点があるなあと思いましたこの対立する二つの課題を解く方法論として、ヘーゲルのアウフヘーベンのように、対立する二つの事柄を双方否定しない形で第三の道を解決策として提示できるか、というところにイノベーターの腕の見せ所があると思います本作における解決策も、なかなかのアウフヘーベンなのですが、思い出したのは、ノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングが提唱したトランセンド法のように、ペルーとエクアドルの紛争地域に、平和公園を設立して、対立を解消するというようなイノベーター的な仕掛け作りです今回はハルの誰もが思い付かないようなアウフヘーベンな策が炸裂するところがかなりの見どころでしたそして、その解決策にも通じるし、さらにはこの作品の私が最もイノベーティブで素敵なあと思う点は、トリリオンゲームという名の通り、大義は150兆円企業になることとあるのですが実はそこには、ガク(坂本勇斗)、凜々(福田莉子)など社員はじめ、投資家の祁答院(吉川晃司)、ライバルの桐姫(今田美桜)、そして島民の皆様が、仲間として、ハルのパッションに突き動かされ、そしてハルも仲間を大切にするというところが、大きな価値なのかなあと思いましたつまり1番トリリオンなのは、仲間たちである、というそんなメッセージを頂きました一言で言うとトリリオンな仲間ノベーションそんなことを感じました^ ^参考:劇場版 トリリオンゲーム 主演 目黒蓮佐野勇斗 今田美桜 福本莉子ほか 原作:稲垣理一郎/作画:池上遼一 監督 村尾嘉昭 竹財 https://trilliongame-movie.jp 動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/1ildraaYyic2025-02-2416 min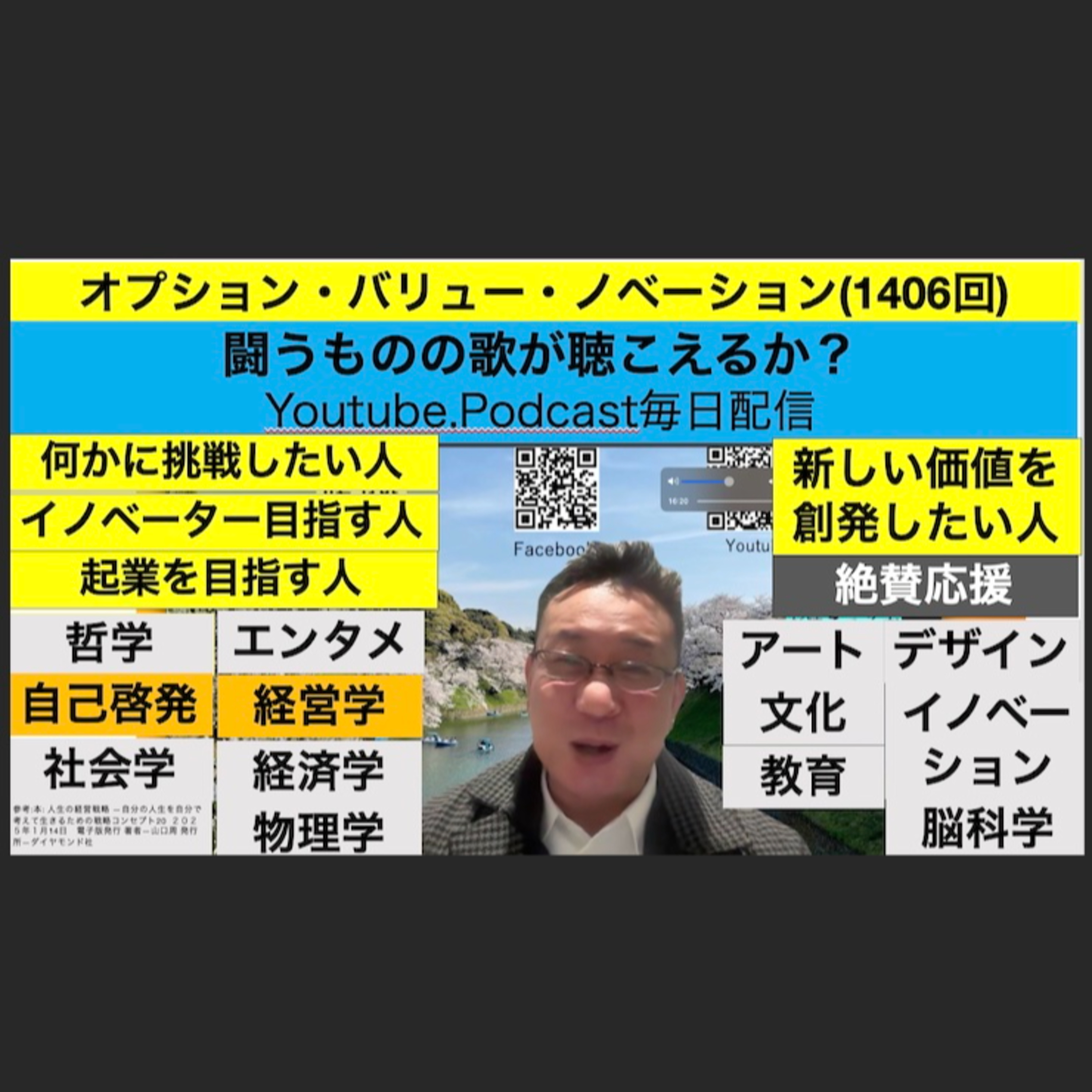 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"オプション・バリュー・ノベーション(1406回)山口周さんより、挑戦の成功確率を上げる方法に、めちゃくちゃ共感させて頂きました曰く"私たちは失敗者の伝記を読みません。読むのは成功者の伝記だけです。そこに「リスクを取って起業した」とあれば「なるほど、成功者はやはりリスクを取っている」と考えてしまうわけですが、これは統計学でいう「生存者のバイアス」の典型です。""実際のところはむしろ逆で、成功者ほど、オプション・バリューを保ちながら、リスクをコントロールして起業しているのに対して、失敗者ほど大胆にリスクを取ることがわかっています。""例えば経営学者のジョセフ・ラフィーとジー・フェンは、5千人以上の起業家に対して「本業を続けながら起業したか?」「本業を止めて起業に専念したか?」という質問調査を行ったところ、本業を続けながらサイドプロジェクトとして起業した人の方が、成功確率がずっと高いということを明らかにしたのです。"ここから私は思いました1、背水の陣バイアス2、心理的安全性3、セーフティネット・オプション起業家で成功されてる方や、VCの方と話をすると、家を三回売ったとか、人生の全てを賭けて、挑戦しそして成功を勝ち取った話を聞くと、本当にスーパーヒーローだなあと、尊敬してしまうのですが自分には、とてもじゃないけど、そんなリスクを犯すことはできないビビりだし、自分とは違う世界に住んでる方々の話だなあと、つくづく思ってしまいますそれでも、挑戦したい気持ちはあるし、何か守るものがある人たちには、なかなか挑戦はできないというのが、世の中の理だよ、と言われているような気がして、そこには少しの違和感がありましたが今回の山口周さんの、オプション・バリューのお話は、そんなビビリな私にもとても勇気をいただけるお話しだなあとつくづく思いました背水の陣を取らない限り、挑戦はできない、ハイリスクハイリターンが当たり前という、バイアスがやはりある気がします。VCの方とお話をすると、そんなオプションを持って、起業をする人からは本気が感じられない、とか、いつか逃げるような人なんじゃないの、みたいな声を聞いたこともあります有名なGoogleのプロジェクトアリストテレスにおける、心理的安全性の話は、組織において、イノベーションを創発しやすいという結果を出されていますが社会においても、人生の心理的安全性を確保するような挑戦環境が整うことで、例えば、これまで、子供が小さいとか、住宅ローンがあるとか、そういった内在リスクをたくさん持たれている方もダメな時のオプションを幅広く持った上で、ある意味もっとカジュアルな起業のような挑戦ができる、そんな世界が生まれると、実は、起業家を増やすための大きな施策になるのではないかと思いましたそのためのオプションとして、例えば、新たな意義ある挑戦をしたい人のための、何らかのセーフティネットがある、そんな、セーフティネット・オプションというのが、とても求められているのではないかと思いました現在、副業や、インターンや、休学などで、自主的にオプションを作られている方もおられますが、それができない人もたくさんいると思います今私が取り組んでいる、StartupEmergence Ecosystem(SEE)は、それを仕組み的に実現することで、起業家、大企業、双方にメリットがあるオプション・バリューが提供できないか、試行錯誤を繰り返していますそれも含め、さまざまなオプション・バリューが出てくると、日本の起業家をもっと増やすことができるのではないか、さらには、人生のオプションもたくさん増えて、彩りのある人生にもなるのではないかそんなことを思いました一言で言うとオプション・バリュー・ノベーションそんな話をしています^ ^参考:本: 人生の経営戦略 —自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20 2025年1月14日 電子版発行 著者—山口周 発行所—ダイヤモンド社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/gJVjCYsYuTg2025-02-2320 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"オプション・バリュー・ノベーション(1406回)山口周さんより、挑戦の成功確率を上げる方法に、めちゃくちゃ共感させて頂きました曰く"私たちは失敗者の伝記を読みません。読むのは成功者の伝記だけです。そこに「リスクを取って起業した」とあれば「なるほど、成功者はやはりリスクを取っている」と考えてしまうわけですが、これは統計学でいう「生存者のバイアス」の典型です。""実際のところはむしろ逆で、成功者ほど、オプション・バリューを保ちながら、リスクをコントロールして起業しているのに対して、失敗者ほど大胆にリスクを取ることがわかっています。""例えば経営学者のジョセフ・ラフィーとジー・フェンは、5千人以上の起業家に対して「本業を続けながら起業したか?」「本業を止めて起業に専念したか?」という質問調査を行ったところ、本業を続けながらサイドプロジェクトとして起業した人の方が、成功確率がずっと高いということを明らかにしたのです。"ここから私は思いました1、背水の陣バイアス2、心理的安全性3、セーフティネット・オプション起業家で成功されてる方や、VCの方と話をすると、家を三回売ったとか、人生の全てを賭けて、挑戦しそして成功を勝ち取った話を聞くと、本当にスーパーヒーローだなあと、尊敬してしまうのですが自分には、とてもじゃないけど、そんなリスクを犯すことはできないビビりだし、自分とは違う世界に住んでる方々の話だなあと、つくづく思ってしまいますそれでも、挑戦したい気持ちはあるし、何か守るものがある人たちには、なかなか挑戦はできないというのが、世の中の理だよ、と言われているような気がして、そこには少しの違和感がありましたが今回の山口周さんの、オプション・バリューのお話は、そんなビビリな私にもとても勇気をいただけるお話しだなあとつくづく思いました背水の陣を取らない限り、挑戦はできない、ハイリスクハイリターンが当たり前という、バイアスがやはりある気がします。VCの方とお話をすると、そんなオプションを持って、起業をする人からは本気が感じられない、とか、いつか逃げるような人なんじゃないの、みたいな声を聞いたこともあります有名なGoogleのプロジェクトアリストテレスにおける、心理的安全性の話は、組織において、イノベーションを創発しやすいという結果を出されていますが社会においても、人生の心理的安全性を確保するような挑戦環境が整うことで、例えば、これまで、子供が小さいとか、住宅ローンがあるとか、そういった内在リスクをたくさん持たれている方もダメな時のオプションを幅広く持った上で、ある意味もっとカジュアルな起業のような挑戦ができる、そんな世界が生まれると、実は、起業家を増やすための大きな施策になるのではないかと思いましたそのためのオプションとして、例えば、新たな意義ある挑戦をしたい人のための、何らかのセーフティネットがある、そんな、セーフティネット・オプションというのが、とても求められているのではないかと思いました現在、副業や、インターンや、休学などで、自主的にオプションを作られている方もおられますが、それができない人もたくさんいると思います今私が取り組んでいる、StartupEmergence Ecosystem(SEE)は、それを仕組み的に実現することで、起業家、大企業、双方にメリットがあるオプション・バリューが提供できないか、試行錯誤を繰り返していますそれも含め、さまざまなオプション・バリューが出てくると、日本の起業家をもっと増やすことができるのではないか、さらには、人生のオプションもたくさん増えて、彩りのある人生にもなるのではないかそんなことを思いました一言で言うとオプション・バリュー・ノベーションそんな話をしています^ ^参考:本: 人生の経営戦略 —自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20 2025年1月14日 電子版発行 著者—山口周 発行所—ダイヤモンド社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/gJVjCYsYuTg2025-02-2320 min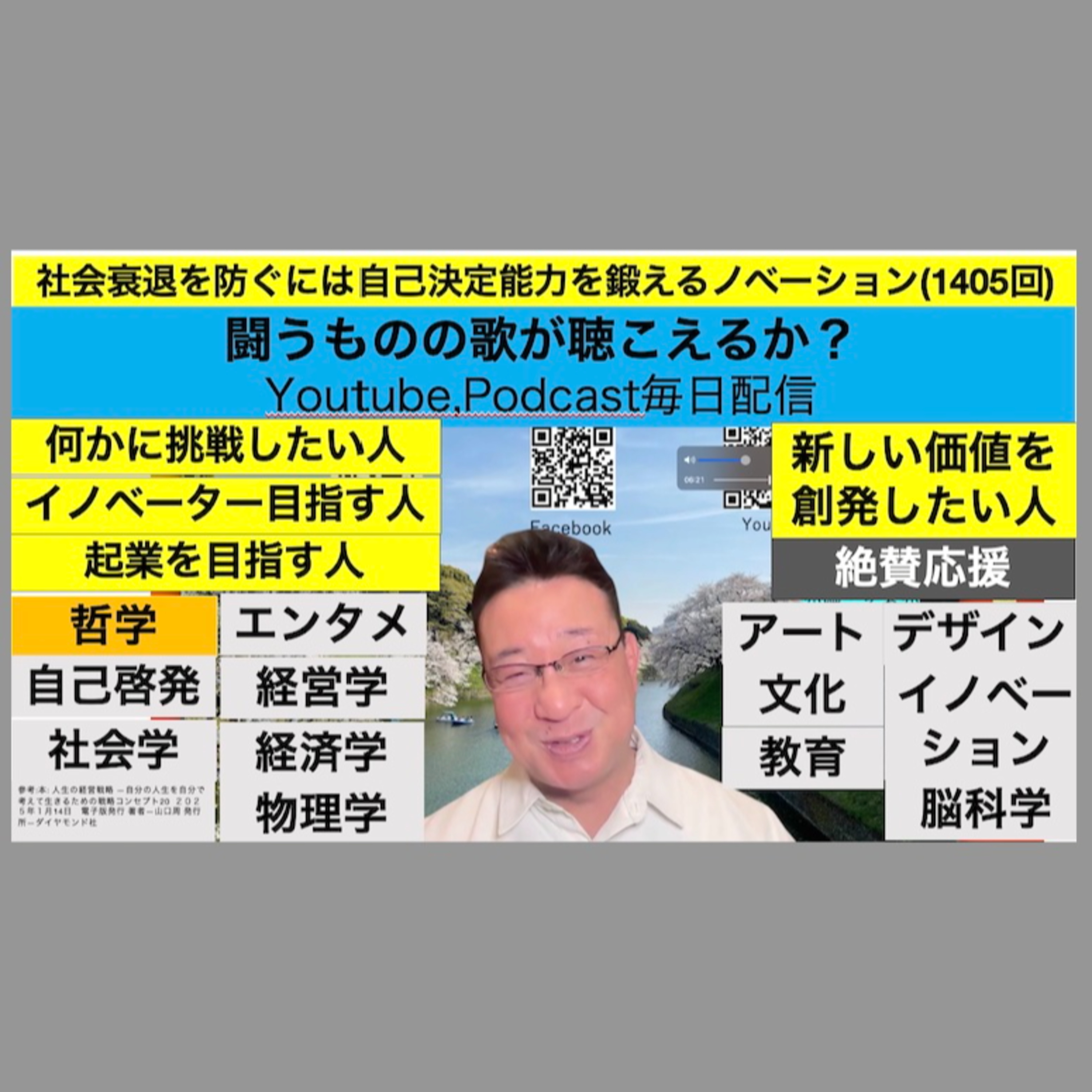 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"社会衰退を防ぐには自己決定能力を鍛えるノベーション(1405回)私の大好きな山口周さんの新しい本から、社会衰退の最大の要因について、めちゃくちゃ考えさせられる話を伺いました曰く"歴史家のアーノルド・トインビーは、彼の主著『歴史の研究』において、社会衰退の最大の要因として「自己決定能力の喪失」というテーマを論じています。最近の日本ではテクノロジー人材の不足やイノベーションの停滞といったことが国力低下の要因のように語られることがありますが、トインビーに言わせれば、そのような理由で衰退した国家・文明は歴史上にひとつもありません。 私たちはまさに「自分で考え、自分で決める」という気概を失い、トインビーの言葉を借りれば「自らのうちの虚ろなもの」にからめとられることによって滅びるのです。"ここから私は思いました1、原理原則→大義2、他人に頼る→仲間3、自らの哲学→情熱の源山口周さんの本における、人生の経営戦略を考える上での、大きな課題感として、社会衰退の大きな要因の一つを衝撃と共に伺いましたこの、自己決定能力の衰退、については、以前、【自己決定ノベーション(1082回)】で、神戸大学と同志社大学の研究として、幸福感に与える影響力は、 健康 → 人間関係 → 自己決定 → 所得 → 学歴との関係があるとの話で、第3位に自己決定が入ってるので、社会的にも大事な要素として認知されてきている、と言うことも思いましたこれを乗り越えることを、私なりに考えてみました一つは、原理原則としての、メジャメントを持つ、と言うことかなと思いました。それは、法律のようなルールもそうですし、倫理観といった話もあるかと思いますここに難しさがあって、必ずしも、風土や国などが違うと、各々は一致しないこともあるので、そこは対話をしながら、お互いのルール、倫理観を一致させる努力が必要と思いますがその上での、原理原則ということを、個人としては、しっかり押さえておけるかということがあるかと思いました二つ目としては、自己決定は、必ずしも自己のみで決定しなくてもいい、ということかと思いました。それは、昨日もお話ししましたが、【責任を果たすには頼るノベーション(1311回)】で哲学者の戸谷洋志さんのお話をしましたが自己決定のゴールは、より良い人生を選択すること、と考えると、人に頼ってもいいのである、ということから、仲間と共に相談して、最後は自分で決定する、そんなプロセスがあってもいいかと思いましたそして最後は、自らの、心の中にあるコンパスが、どこを指しているのか、ということがとても大切になると思いましたこれは、いつもお話ししていますが、情熱のポートフォリオ(大好き、利他、個性、成長)として、どんな気持ちや価値観がそこにあるのか、そこに照らし合わせて、最後は選択する、ということが自分としても納得感があり、たとえ結果がどうあろうと、その時点においては、良い選択になるのではないかと、そんなことを思いましたこうしてみると、自己決定力を衰退させないためには、原理原則(大義)、他人を頼る(仲間)、自らのコンパス(情熱の源)となって、イノベーター3つのフレームを意識しておくことが、それの助けになるのではないか、そんなことを思いました社会衰退を防ぐには、個々人の、自己決定能力が大切であり、それを鍛える一つ方法として、イノベーター3つのフレームを常日頃活用しておくこと、がその一役になる一言で言えば社会衰退を防ぐには自己決定能力を鍛えるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 人生の経営戦略 —自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20 2025年1月14日 電子版発行 著者—山口周 発行所—ダイヤモンド社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/VW6YcDYvP-M2025-02-2218 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"社会衰退を防ぐには自己決定能力を鍛えるノベーション(1405回)私の大好きな山口周さんの新しい本から、社会衰退の最大の要因について、めちゃくちゃ考えさせられる話を伺いました曰く"歴史家のアーノルド・トインビーは、彼の主著『歴史の研究』において、社会衰退の最大の要因として「自己決定能力の喪失」というテーマを論じています。最近の日本ではテクノロジー人材の不足やイノベーションの停滞といったことが国力低下の要因のように語られることがありますが、トインビーに言わせれば、そのような理由で衰退した国家・文明は歴史上にひとつもありません。 私たちはまさに「自分で考え、自分で決める」という気概を失い、トインビーの言葉を借りれば「自らのうちの虚ろなもの」にからめとられることによって滅びるのです。"ここから私は思いました1、原理原則→大義2、他人に頼る→仲間3、自らの哲学→情熱の源山口周さんの本における、人生の経営戦略を考える上での、大きな課題感として、社会衰退の大きな要因の一つを衝撃と共に伺いましたこの、自己決定能力の衰退、については、以前、【自己決定ノベーション(1082回)】で、神戸大学と同志社大学の研究として、幸福感に与える影響力は、 健康 → 人間関係 → 自己決定 → 所得 → 学歴との関係があるとの話で、第3位に自己決定が入ってるので、社会的にも大事な要素として認知されてきている、と言うことも思いましたこれを乗り越えることを、私なりに考えてみました一つは、原理原則としての、メジャメントを持つ、と言うことかなと思いました。それは、法律のようなルールもそうですし、倫理観といった話もあるかと思いますここに難しさがあって、必ずしも、風土や国などが違うと、各々は一致しないこともあるので、そこは対話をしながら、お互いのルール、倫理観を一致させる努力が必要と思いますがその上での、原理原則ということを、個人としては、しっかり押さえておけるかということがあるかと思いました二つ目としては、自己決定は、必ずしも自己のみで決定しなくてもいい、ということかと思いました。それは、昨日もお話ししましたが、【責任を果たすには頼るノベーション(1311回)】で哲学者の戸谷洋志さんのお話をしましたが自己決定のゴールは、より良い人生を選択すること、と考えると、人に頼ってもいいのである、ということから、仲間と共に相談して、最後は自分で決定する、そんなプロセスがあってもいいかと思いましたそして最後は、自らの、心の中にあるコンパスが、どこを指しているのか、ということがとても大切になると思いましたこれは、いつもお話ししていますが、情熱のポートフォリオ(大好き、利他、個性、成長)として、どんな気持ちや価値観がそこにあるのか、そこに照らし合わせて、最後は選択する、ということが自分としても納得感があり、たとえ結果がどうあろうと、その時点においては、良い選択になるのではないかと、そんなことを思いましたこうしてみると、自己決定力を衰退させないためには、原理原則(大義)、他人を頼る(仲間)、自らのコンパス(情熱の源)となって、イノベーター3つのフレームを意識しておくことが、それの助けになるのではないか、そんなことを思いました社会衰退を防ぐには、個々人の、自己決定能力が大切であり、それを鍛える一つ方法として、イノベーター3つのフレームを常日頃活用しておくこと、がその一役になる一言で言えば社会衰退を防ぐには自己決定能力を鍛えるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 人生の経営戦略 —自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20 2025年1月14日 電子版発行 著者—山口周 発行所—ダイヤモンド社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/VW6YcDYvP-M2025-02-2218 min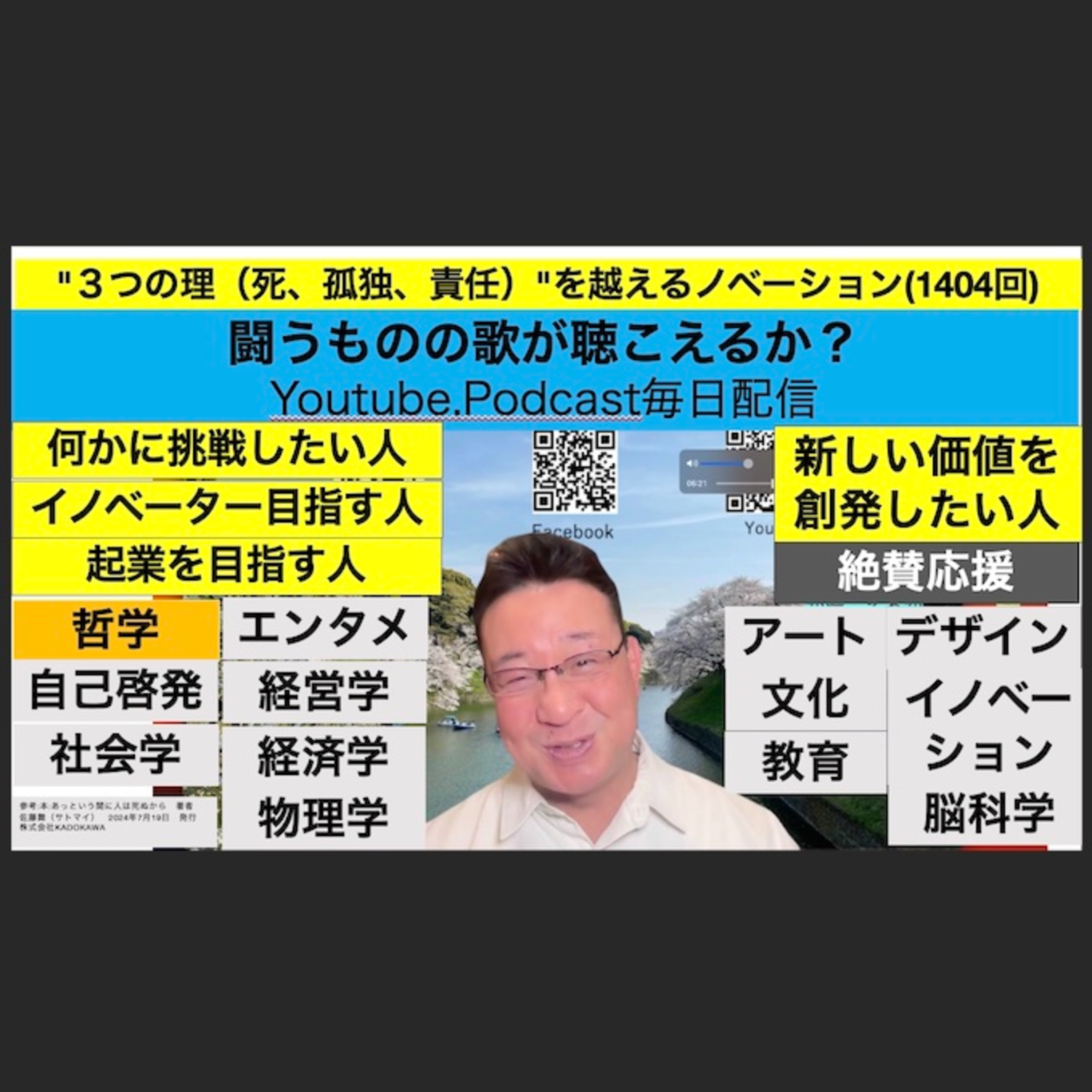 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""3つの理(死、孤独、責任)"を越えるノベーション(1404回)佐藤舞(サトマイ)さんの言葉が心にめちゃくちゃ刺さって、とても考えさせられました曰く"私たちが直視できないものとはなんでしょうか。 私はそれを、「人生の3つの理」だと考えました。 人生の3つの理 ①死 ②孤独 ③責任人は、人生の3つの理から生じる不安(ストレス)を避けるために、間違った選択をし、その選択が正しいと自分にウソをつくことで時間を浪費しています。 自身の価値観に沿った行動ではなく、不安(ストレス)を回避するための行動によって、余計に恐怖心が増大し、自分の人生を生きられず、長期的な人生の質を悪化させます。"ここから私は3つの理をイノベーター3つのフレームでの超え方について思いました1、仲間2、情熱の源3、大義この"3つの理(死、孤独、責任)"は、本当にいかなる場面でも、自分の心の中に重しとしてあるなあと、とても共感しました私なりに、この"3つの理"について、イノベーター3つのフレーム(情熱、仲間、大義)で、もしかしたら、少しでも越えることができるのではないかと、思って考えてみましたまず思ったのは「仲間」の存在があることによって、死や孤独という理に、少しでも癒しをもらえるかもしれないと思いましたまた、責任に関しては、以前お話しした、【責任を果たすには頼るノベーション(1311回)】で哲学者の戸谷洋志さんのお話をしましたが、ゴールは自分で責任を被ることではなく、責任を果たすこと、と考えると、人に頼ることがとても大切、ということから、仲間の存在がここでも、生きるのではないかと思いました私の大好きな、ももクロの、白金の夜明けの歌詞で"誰も一人なんかじゃない.一人になろうとするだけなんだ"という、前田たかひろさんの歌詞があるのですが、仲間作りが大変だと思う人も、この一歩を、ゲームでもネットでもSNSでも踏み出すことが、実は大切なのかもしれないと思いましたでも、仲間に癒されているだけでは、自分の人生は生きられないので、ここで大切になるのが、情熱の源かなと思いました"3つの理"はあるけれども、仲間と共に、自らの情熱のポートフォリオ(大好き、利他、個性、成長)に何があるのかを、再認識しながら、前に行動していく、それこそが大事と思いましたそして、仲間と共に、情熱の源に沿った行動をとることによって、誰かが喜んでくれることができるようになる、そうするとそこに大義が生まれて、いろんな人の喜んでる姿や声を聞くことができればそれは自らの情熱の源にフィードバックされて、自らの炎に、より力が加わっていき、そして仲間が増えていく、そんな素敵なスパイラルをマワスココとができれば"3つの理"は、なくならないけども、振り回されない、自分の生き方ができるのではないか、そんなことを思いました一言で言うと"3つの理"をイノベーター3つのフレームで越えるノベーションさらには"3つの理"を越えるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本:あっという間に人は死ぬから 著者 佐藤舞(サトマイ) 2024年7月19日 発行 株式会社KADOKAWA動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/k-pJwHKbHMA2025-02-2123 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか""3つの理(死、孤独、責任)"を越えるノベーション(1404回)佐藤舞(サトマイ)さんの言葉が心にめちゃくちゃ刺さって、とても考えさせられました曰く"私たちが直視できないものとはなんでしょうか。 私はそれを、「人生の3つの理」だと考えました。 人生の3つの理 ①死 ②孤独 ③責任人は、人生の3つの理から生じる不安(ストレス)を避けるために、間違った選択をし、その選択が正しいと自分にウソをつくことで時間を浪費しています。 自身の価値観に沿った行動ではなく、不安(ストレス)を回避するための行動によって、余計に恐怖心が増大し、自分の人生を生きられず、長期的な人生の質を悪化させます。"ここから私は3つの理をイノベーター3つのフレームでの超え方について思いました1、仲間2、情熱の源3、大義この"3つの理(死、孤独、責任)"は、本当にいかなる場面でも、自分の心の中に重しとしてあるなあと、とても共感しました私なりに、この"3つの理"について、イノベーター3つのフレーム(情熱、仲間、大義)で、もしかしたら、少しでも越えることができるのではないかと、思って考えてみましたまず思ったのは「仲間」の存在があることによって、死や孤独という理に、少しでも癒しをもらえるかもしれないと思いましたまた、責任に関しては、以前お話しした、【責任を果たすには頼るノベーション(1311回)】で哲学者の戸谷洋志さんのお話をしましたが、ゴールは自分で責任を被ることではなく、責任を果たすこと、と考えると、人に頼ることがとても大切、ということから、仲間の存在がここでも、生きるのではないかと思いました私の大好きな、ももクロの、白金の夜明けの歌詞で"誰も一人なんかじゃない.一人になろうとするだけなんだ"という、前田たかひろさんの歌詞があるのですが、仲間作りが大変だと思う人も、この一歩を、ゲームでもネットでもSNSでも踏み出すことが、実は大切なのかもしれないと思いましたでも、仲間に癒されているだけでは、自分の人生は生きられないので、ここで大切になるのが、情熱の源かなと思いました"3つの理"はあるけれども、仲間と共に、自らの情熱のポートフォリオ(大好き、利他、個性、成長)に何があるのかを、再認識しながら、前に行動していく、それこそが大事と思いましたそして、仲間と共に、情熱の源に沿った行動をとることによって、誰かが喜んでくれることができるようになる、そうするとそこに大義が生まれて、いろんな人の喜んでる姿や声を聞くことができればそれは自らの情熱の源にフィードバックされて、自らの炎に、より力が加わっていき、そして仲間が増えていく、そんな素敵なスパイラルをマワスココとができれば"3つの理"は、なくならないけども、振り回されない、自分の生き方ができるのではないか、そんなことを思いました一言で言うと"3つの理"をイノベーター3つのフレームで越えるノベーションさらには"3つの理"を越えるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本:あっという間に人は死ぬから 著者 佐藤舞(サトマイ) 2024年7月19日 発行 株式会社KADOKAWA動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/k-pJwHKbHMA2025-02-2123 min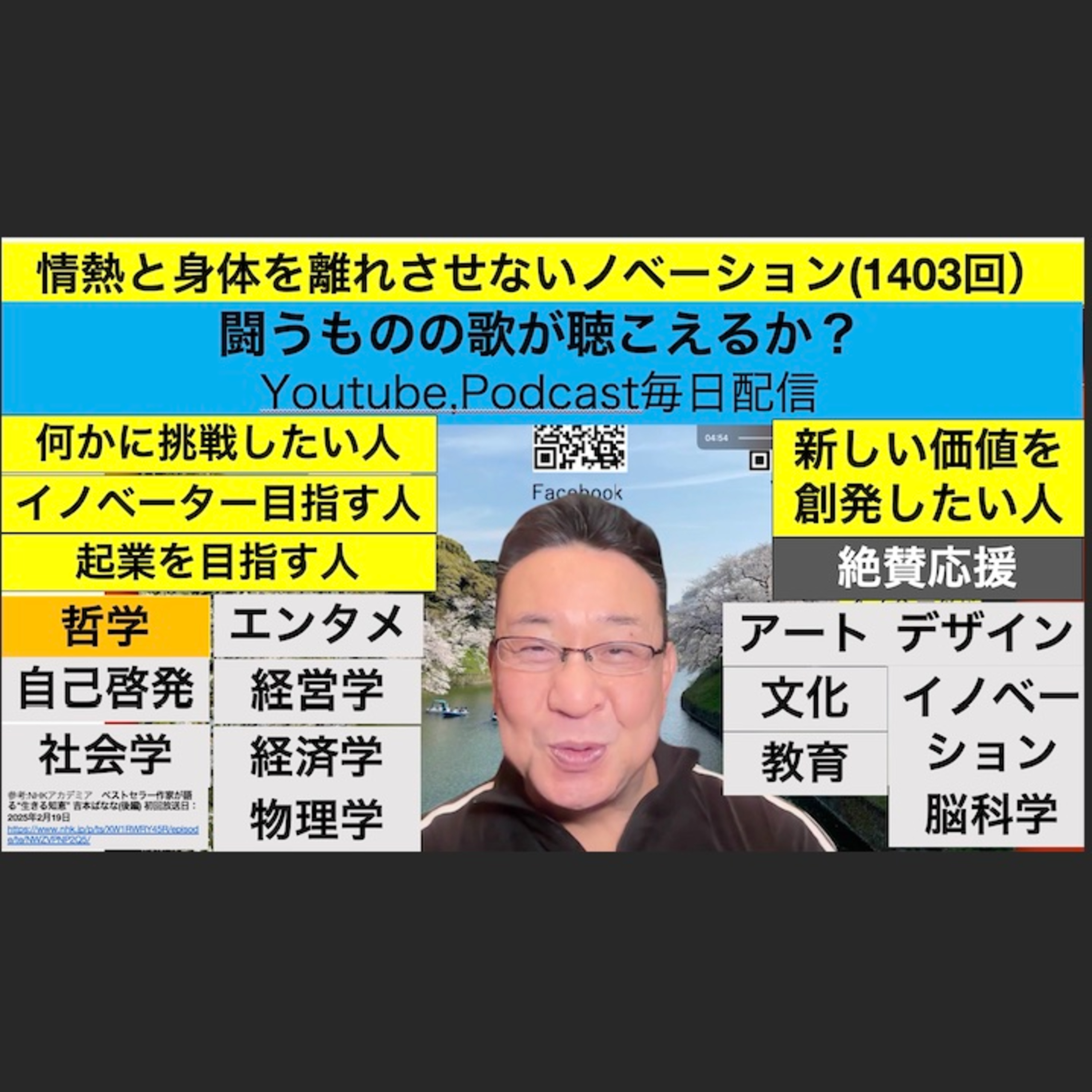 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"情熱と身体を離れさせないノベーション(1403回)吉本バナナさんの、今、皆さんへ伝えたいことに感動しました"とにかく好奇心を持って実験してみることそれが毎日をどんなに彩るかと言うことを、皆さんにもう一度思い出してもらいたい、というのは、今やはり、これからはどんどん人間がこう、意識だけ飛ばす時代ですよねネットでもそうだし、人間がどんどん体から離れていく時代だからこそ、毎日の実験をたくさん増やして、楽しんでほしいって思いますで、そのためには自分を自分から離れないようにすること、この表現はとても難しいと思うし、伝わらないって分かってるけど、でもちょっとでも心の隅に隅に置いておいてもらえれば""自分自身の意識と自分を知覚しておいて、自分がいまいる場所を物理的にいつも確認しておくこと"ここから私は思いました1、実験は人生を彩る1、情熱の源と離れないこと2、情熱の源と身体を離れないようにすること吉本バナナさんの言葉は、とても明快にはっきりお話しいただけるのと、目から鱗が落ちる新たな発見がたくさんあるので、とても感動しました特に、人生は実験である、というのは、先日お話しした、かっこ人生プロトタイピング・ノベーション(1400回)」とも、とてもシナジーがあるしさらには、哲学者の三木清さんの、失敗は人生の彩り、という話も思い出しました。そこで思うのは、まずは、行動が大切ということかと思いました。やりたいことリストみたいなものをいくら作っても、行動をしないと始まらないし、その行動も、一発大きなことをするのではなく、あくまでも実験としてエフェクチュエーションにおける、許容範囲の損失、の形で、実験をしていくというのは、あくまでも実験だから、うまくいかなくても、実験だからですぐにピボットできるし、沢山のことに挑戦できそうで、ワクワクしましたそして、自分を知覚しておく、という言葉から、私的には、自らの情熱の源を、常に意識しておくということが、大切なことと言われてる気がしましたそれは、ある意味、言語化できていなくても、自分自身にとって、違和感であれば、無理をしないということも大切だし、ワクワクが止まらなければ、勇気を持ってやってみる、そんなことにつながるなと思いますさらに、今回、とても驚いたのは、自分が今いる位置を物理的に確認しておくこと、というお話しでした確かにネットや、ましてやバーチャルリアリティな世界が入ってくると、精神だけでどこまでもいけるけれども、体が置いてけぼりになる、ということも多くなりそうですし情熱の源と言っても、まずは頭で考えてることなので、体のことまで意識して考えていないかもしれないなあと思いました当然ですが、心と体は繋がっているので、自らの情熱の源は、心だけでなく、体としてどうなのか、体や今いる場所という、リアルをより意識しながら、実験という新たなフィールドへ挑戦していくそんなことがこれからは、からに必要となるのかもしれない、そんなことを思いました一言で言うと情熱と身体を離れさせないノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHKアカデミア ベストセラー作家が語る“生きる知恵” 吉本ばなな(後編) 初回放送日:2025年2月19日 https://www.nhk.jp/p/ts/XW1RWRY45R/episode/te/NWZVPNP2Q5/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/pZC45Nc2dzE2025-02-2018 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"情熱と身体を離れさせないノベーション(1403回)吉本バナナさんの、今、皆さんへ伝えたいことに感動しました"とにかく好奇心を持って実験してみることそれが毎日をどんなに彩るかと言うことを、皆さんにもう一度思い出してもらいたい、というのは、今やはり、これからはどんどん人間がこう、意識だけ飛ばす時代ですよねネットでもそうだし、人間がどんどん体から離れていく時代だからこそ、毎日の実験をたくさん増やして、楽しんでほしいって思いますで、そのためには自分を自分から離れないようにすること、この表現はとても難しいと思うし、伝わらないって分かってるけど、でもちょっとでも心の隅に隅に置いておいてもらえれば""自分自身の意識と自分を知覚しておいて、自分がいまいる場所を物理的にいつも確認しておくこと"ここから私は思いました1、実験は人生を彩る1、情熱の源と離れないこと2、情熱の源と身体を離れないようにすること吉本バナナさんの言葉は、とても明快にはっきりお話しいただけるのと、目から鱗が落ちる新たな発見がたくさんあるので、とても感動しました特に、人生は実験である、というのは、先日お話しした、かっこ人生プロトタイピング・ノベーション(1400回)」とも、とてもシナジーがあるしさらには、哲学者の三木清さんの、失敗は人生の彩り、という話も思い出しました。そこで思うのは、まずは、行動が大切ということかと思いました。やりたいことリストみたいなものをいくら作っても、行動をしないと始まらないし、その行動も、一発大きなことをするのではなく、あくまでも実験としてエフェクチュエーションにおける、許容範囲の損失、の形で、実験をしていくというのは、あくまでも実験だから、うまくいかなくても、実験だからですぐにピボットできるし、沢山のことに挑戦できそうで、ワクワクしましたそして、自分を知覚しておく、という言葉から、私的には、自らの情熱の源を、常に意識しておくということが、大切なことと言われてる気がしましたそれは、ある意味、言語化できていなくても、自分自身にとって、違和感であれば、無理をしないということも大切だし、ワクワクが止まらなければ、勇気を持ってやってみる、そんなことにつながるなと思いますさらに、今回、とても驚いたのは、自分が今いる位置を物理的に確認しておくこと、というお話しでした確かにネットや、ましてやバーチャルリアリティな世界が入ってくると、精神だけでどこまでもいけるけれども、体が置いてけぼりになる、ということも多くなりそうですし情熱の源と言っても、まずは頭で考えてることなので、体のことまで意識して考えていないかもしれないなあと思いました当然ですが、心と体は繋がっているので、自らの情熱の源は、心だけでなく、体としてどうなのか、体や今いる場所という、リアルをより意識しながら、実験という新たなフィールドへ挑戦していくそんなことがこれからは、からに必要となるのかもしれない、そんなことを思いました一言で言うと情熱と身体を離れさせないノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHKアカデミア ベストセラー作家が語る“生きる知恵” 吉本ばなな(後編) 初回放送日:2025年2月19日 https://www.nhk.jp/p/ts/XW1RWRY45R/episode/te/NWZVPNP2Q5/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/pZC45Nc2dzE2025-02-2018 min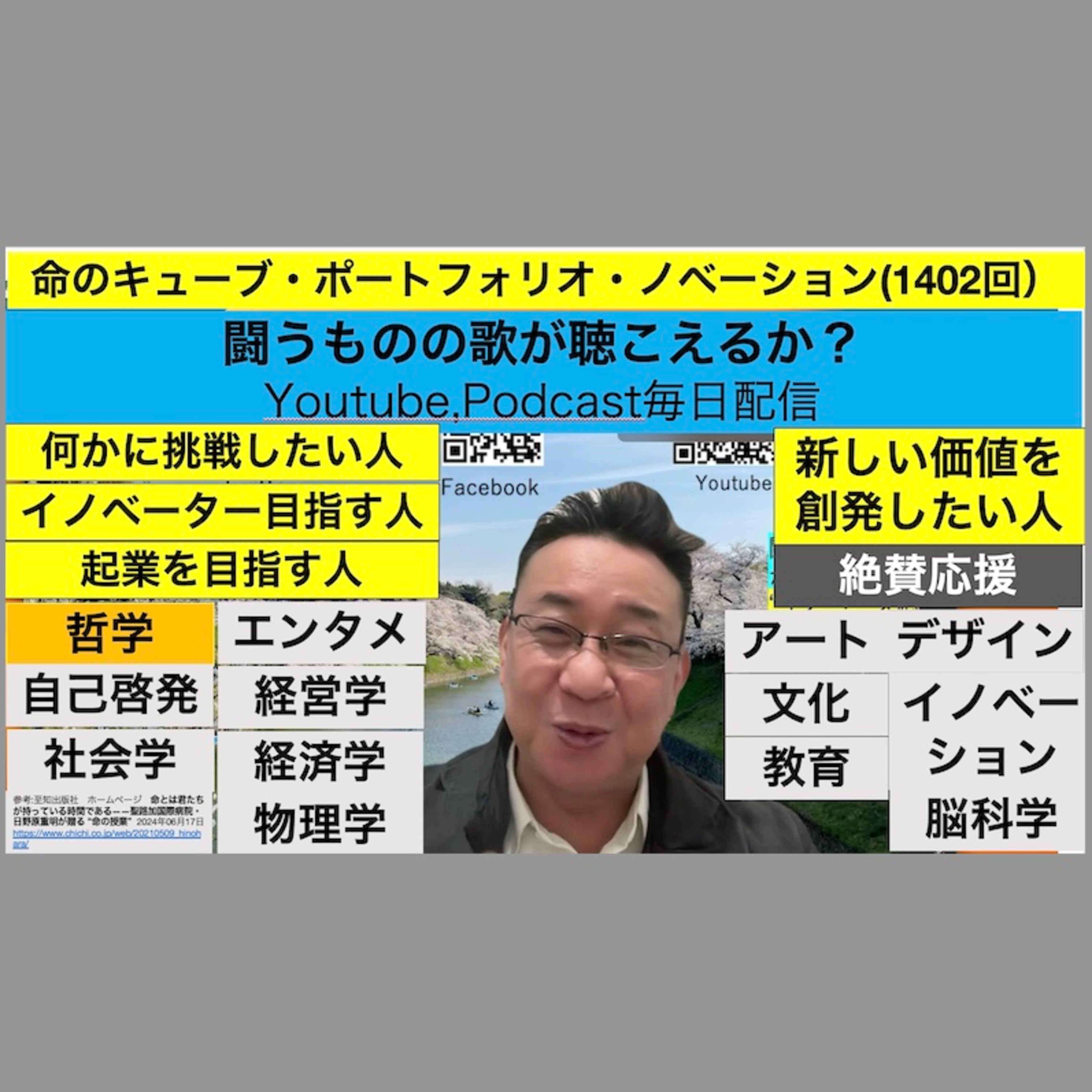 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"命のキューブ・ポートフォリオ・ノベーション(1402回)100歳を超えてなお驚異的なお元気さで診療や講演に奔走されていた聖路加国際病院理事長の日野原重明さんが、10歳の子どもたちに向けて行った「命の授業」に打ち震えました曰く「命はなぜ目に見えないか。それは命とは君たちが持っている時間だからなんだよ。死んでしまったら自分で使える時間もなくなってしまう。どうか一度しかない自分の時間、命をどのように使うかしっかり考えながら生きていってほしい。さらに言えば、その命を今度は自分以外の何かのために使うことを学んでほしい」ここから私は思いました1、命の箱は時間軸2、箱の中身は情熱の源のスライス3、命のキューブ・ポートフォリオ森信三さんの、人生二度なし、の言葉を思い出しました。命は時間だ、という言葉から、目に見えないものの大切さ、限られたものの儚さ、だからこそ一瞬一瞬を燃やす必要性、いろんなことを思い浮かばせて頂ける深い言葉なだと、思いました命という箱があったとすると、その箱の軸は、時間という流れに支配されている枠のようなものなのかもしれないなと思いましたそして、その命という箱の中に入れられるのは、個々人の情熱の源としての、一瞬一瞬のポートフォリオが、時間軸に沿って、サクサクと並べられているようなものなのかもしれないと、思いました情熱の源のポートフォリオは、縦軸にポジティブ・ネガティブ、横軸にオープン・クローズをとると、大好きなこと、利他したいこと、個性を発揮したいこと、そして成長したいこと、というのが、大まかにあるので時間軸に沿って、一瞬一瞬が、どんな情熱の源に、従ってるのか、ということが、分かってて、それぞれに充実してれば、とても濃ゆい命の燃やし方になってるのかなあと思いましたそれはまるで、一瞬一瞬の情熱のポートフォリオのスライスが、時間軸に沿って、次々と並べられていく様で、でも、その並べられていくのは限りが必ず訪れる、いつ訪れるかどうかわからないけど、必ず終わりになる図式で表現すると命のキューブ・ポートフォリオのようなものなのかもしれないと思いましただとすると、ゴールがわからない中でも、自分にできるのは、とにかく一瞬一瞬に、情熱のポートフォリオを意識した行動を刻み込む、そんなことを意識できると、充実した命になるのかもしれないそんなことを思いました一言で言うと命のキューブ・ポートフォリオ・ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:至知出版社 ホームページ 命とは君たちが持っている時間である——聖路加国際病院・日野原重明が贈る “命の授業” 2024年06月17日 https://www.chichi.co.jp/web/20210509_hinohara/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/pxRGjxK9xnQ2025-02-1914 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"命のキューブ・ポートフォリオ・ノベーション(1402回)100歳を超えてなお驚異的なお元気さで診療や講演に奔走されていた聖路加国際病院理事長の日野原重明さんが、10歳の子どもたちに向けて行った「命の授業」に打ち震えました曰く「命はなぜ目に見えないか。それは命とは君たちが持っている時間だからなんだよ。死んでしまったら自分で使える時間もなくなってしまう。どうか一度しかない自分の時間、命をどのように使うかしっかり考えながら生きていってほしい。さらに言えば、その命を今度は自分以外の何かのために使うことを学んでほしい」ここから私は思いました1、命の箱は時間軸2、箱の中身は情熱の源のスライス3、命のキューブ・ポートフォリオ森信三さんの、人生二度なし、の言葉を思い出しました。命は時間だ、という言葉から、目に見えないものの大切さ、限られたものの儚さ、だからこそ一瞬一瞬を燃やす必要性、いろんなことを思い浮かばせて頂ける深い言葉なだと、思いました命という箱があったとすると、その箱の軸は、時間という流れに支配されている枠のようなものなのかもしれないなと思いましたそして、その命という箱の中に入れられるのは、個々人の情熱の源としての、一瞬一瞬のポートフォリオが、時間軸に沿って、サクサクと並べられているようなものなのかもしれないと、思いました情熱の源のポートフォリオは、縦軸にポジティブ・ネガティブ、横軸にオープン・クローズをとると、大好きなこと、利他したいこと、個性を発揮したいこと、そして成長したいこと、というのが、大まかにあるので時間軸に沿って、一瞬一瞬が、どんな情熱の源に、従ってるのか、ということが、分かってて、それぞれに充実してれば、とても濃ゆい命の燃やし方になってるのかなあと思いましたそれはまるで、一瞬一瞬の情熱のポートフォリオのスライスが、時間軸に沿って、次々と並べられていく様で、でも、その並べられていくのは限りが必ず訪れる、いつ訪れるかどうかわからないけど、必ず終わりになる図式で表現すると命のキューブ・ポートフォリオのようなものなのかもしれないと思いましただとすると、ゴールがわからない中でも、自分にできるのは、とにかく一瞬一瞬に、情熱のポートフォリオを意識した行動を刻み込む、そんなことを意識できると、充実した命になるのかもしれないそんなことを思いました一言で言うと命のキューブ・ポートフォリオ・ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:至知出版社 ホームページ 命とは君たちが持っている時間である——聖路加国際病院・日野原重明が贈る “命の授業” 2024年06月17日 https://www.chichi.co.jp/web/20210509_hinohara/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/pxRGjxK9xnQ2025-02-1914 min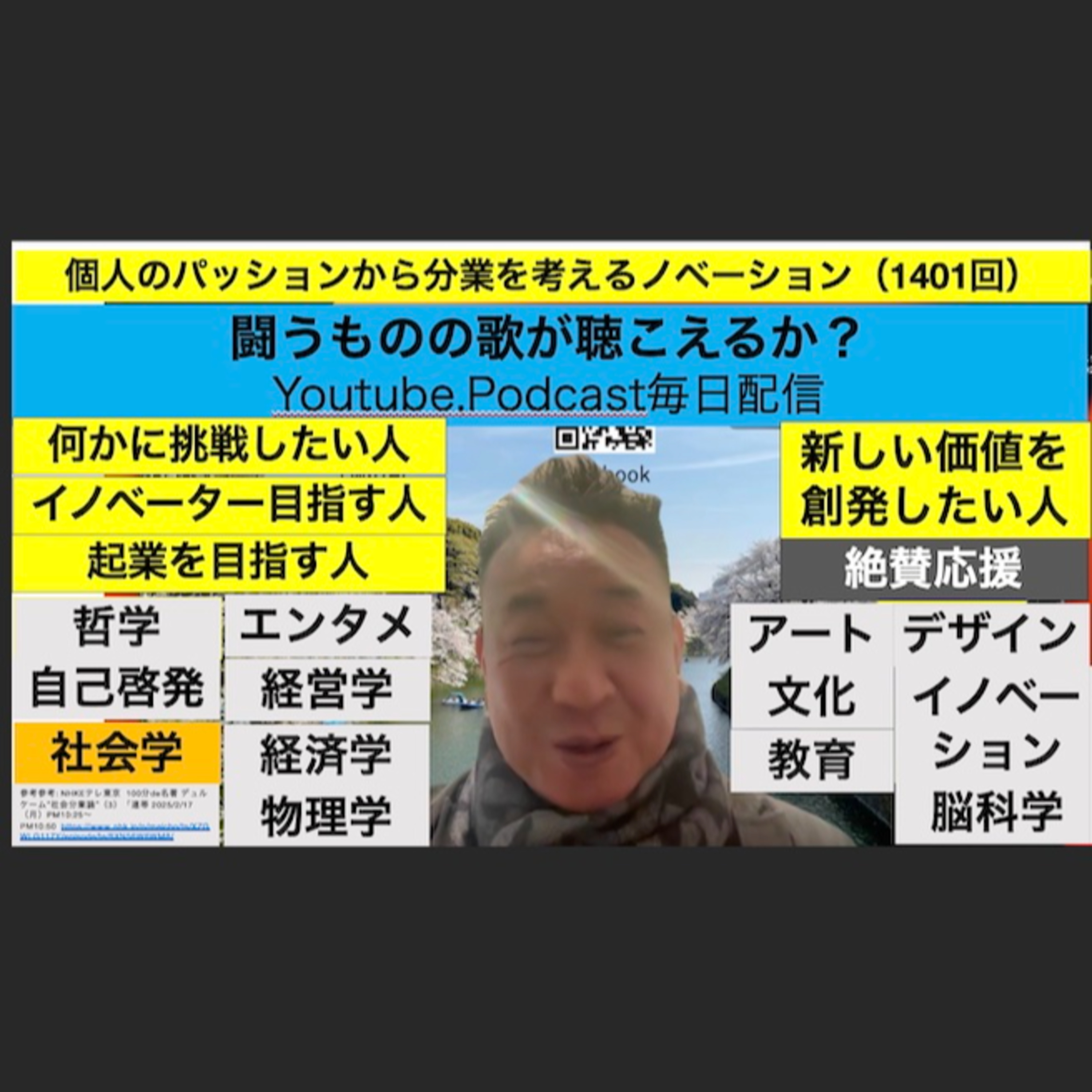 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"個人のパッションから分業を考えるノベーション(1401回)デュルケーム“社会分業論”から、個人の出現と分業のあり方について、考えさせられました曰く"分業は対立させると同時に結合させる。それは、みずからが分化させた諸活動を収斂させ、ひき離したものを接近させる。""個人は、みずからを他者から区別する個性的な相貌と活動力とをもっていて、その区別されるかぎりにおいて他者に依存し、したがってまた、そうした結合から生じた社会に依存するから社会化されるのである""諸個人は分業によってこそ相互に結びあっているのであって、それがなければ孤立するばかりである。彼らは、てんでに発達する代わりに、自分たちの努力をもちよる。彼らは連帯的である。"ここから私は思いました1、民主化が個人を生んだ→パッションの源の発生2、個人は分業が必要 →光と影3、イノベータ3つのフレームと分業→分業のあり方衝撃だったのは、個人という概念が、封建制などの元では存在しなく、民主化されて初めて、概念自体が生まれたということでした確かに生まれながらに役割が決まってる世界では、個人という概念自体が必要ないというのは、今の世界が当たり前と思ってる自分には、想像もつかないなと思います今の世の中でも、価値観が違う世界は沢山あるので、実は個人という概念自体がない、そんな人たちが沢山いるということは、認識しておくことは大事かなと思いました私がいつもお話ししている、パッションの源や、そのポートフォリオは、かなり偏りのあるパッションの源となる、または、ほとんどそんなことも考える必要がないとすれば民主化によって初めて個人が生まれ、そしてパッションの源も初めて生まれてきた、そう考えると、個人がどう生きるべきなのか、パッションの源をどう考えていけばいいのか?ということも、かなり歴史の浅い話なのだなあと、だからこそ、もっと深める必要があるテーマなのかもしれない、そんなことを思いましたまた、分業は人類最大の発明という話もありますが、実は、個人という単位が生まれてから、実は、分業の意味自体も、大きく変わってきたのかなと思いましたつまり、個人という概念が発生したからこそ、より分業という概念を、個人が意識する必然性が出てきた、むしろ、分業を意識しないと、個人としての孤立を乗り越えることができない、そんなところまで、分業の必然性が出てきたのかと、考えさせられました私がいつもお話ししている、イノベータ3つのフレームでいくと、1パッション、2仲間、3大義、でいくと、分業というのは、2仲間との関係性として、とても重要性を増すものと思っていますがより良い分業とは何か?ということについて考えたときに、私が思うのは、個人という観念が生まれたときに大切なこと、ということを踏まえることが大切だと思っていてつまり、自らの情熱の源を、無視した分業になることはとてもよろしくなくて、あくまでも個人の情熱の源のパッションと、そして会社や組織などのミッションとのベン図の交わりを、個人が意識している上での分業ということが、できてるかどうかということが、個人の観点からの分業のあり方としては、とても大事だと思いましたまとめると、民主化で初めて個人が生まれ、個人には分業がより大切になり、あくまでも個人と他者(組織)との間における価値を、自らが意識し続けた分業を社会として形作っていくそんなことが、理想的な分業の姿なのかなと、そんなことを思いました一言で言うと個人のパッションから分業を考えるノベーションそんなことを思いました^ ^参考: NHKEテレ東京 100分de名著 デュルケーム“社会分業論”(3)「連帯 2025/2/17(月)PM10:25~PM10:50 https://www.nhk.jp/p/meicho/ts/XZGWLG117Y/episode/te/6XN56W6WM8/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/oS-VsoPxRoE2025-02-1810 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"個人のパッションから分業を考えるノベーション(1401回)デュルケーム“社会分業論”から、個人の出現と分業のあり方について、考えさせられました曰く"分業は対立させると同時に結合させる。それは、みずからが分化させた諸活動を収斂させ、ひき離したものを接近させる。""個人は、みずからを他者から区別する個性的な相貌と活動力とをもっていて、その区別されるかぎりにおいて他者に依存し、したがってまた、そうした結合から生じた社会に依存するから社会化されるのである""諸個人は分業によってこそ相互に結びあっているのであって、それがなければ孤立するばかりである。彼らは、てんでに発達する代わりに、自分たちの努力をもちよる。彼らは連帯的である。"ここから私は思いました1、民主化が個人を生んだ→パッションの源の発生2、個人は分業が必要 →光と影3、イノベータ3つのフレームと分業→分業のあり方衝撃だったのは、個人という概念が、封建制などの元では存在しなく、民主化されて初めて、概念自体が生まれたということでした確かに生まれながらに役割が決まってる世界では、個人という概念自体が必要ないというのは、今の世界が当たり前と思ってる自分には、想像もつかないなと思います今の世の中でも、価値観が違う世界は沢山あるので、実は個人という概念自体がない、そんな人たちが沢山いるということは、認識しておくことは大事かなと思いました私がいつもお話ししている、パッションの源や、そのポートフォリオは、かなり偏りのあるパッションの源となる、または、ほとんどそんなことも考える必要がないとすれば民主化によって初めて個人が生まれ、そしてパッションの源も初めて生まれてきた、そう考えると、個人がどう生きるべきなのか、パッションの源をどう考えていけばいいのか?ということも、かなり歴史の浅い話なのだなあと、だからこそ、もっと深める必要があるテーマなのかもしれない、そんなことを思いましたまた、分業は人類最大の発明という話もありますが、実は、個人という単位が生まれてから、実は、分業の意味自体も、大きく変わってきたのかなと思いましたつまり、個人という概念が発生したからこそ、より分業という概念を、個人が意識する必然性が出てきた、むしろ、分業を意識しないと、個人としての孤立を乗り越えることができない、そんなところまで、分業の必然性が出てきたのかと、考えさせられました私がいつもお話ししている、イノベータ3つのフレームでいくと、1パッション、2仲間、3大義、でいくと、分業というのは、2仲間との関係性として、とても重要性を増すものと思っていますがより良い分業とは何か?ということについて考えたときに、私が思うのは、個人という観念が生まれたときに大切なこと、ということを踏まえることが大切だと思っていてつまり、自らの情熱の源を、無視した分業になることはとてもよろしくなくて、あくまでも個人の情熱の源のパッションと、そして会社や組織などのミッションとのベン図の交わりを、個人が意識している上での分業ということが、できてるかどうかということが、個人の観点からの分業のあり方としては、とても大事だと思いましたまとめると、民主化で初めて個人が生まれ、個人には分業がより大切になり、あくまでも個人と他者(組織)との間における価値を、自らが意識し続けた分業を社会として形作っていくそんなことが、理想的な分業の姿なのかなと、そんなことを思いました一言で言うと個人のパッションから分業を考えるノベーションそんなことを思いました^ ^参考: NHKEテレ東京 100分de名著 デュルケーム“社会分業論”(3)「連帯 2025/2/17(月)PM10:25~PM10:50 https://www.nhk.jp/p/meicho/ts/XZGWLG117Y/episode/te/6XN56W6WM8/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/oS-VsoPxRoE2025-02-1810 min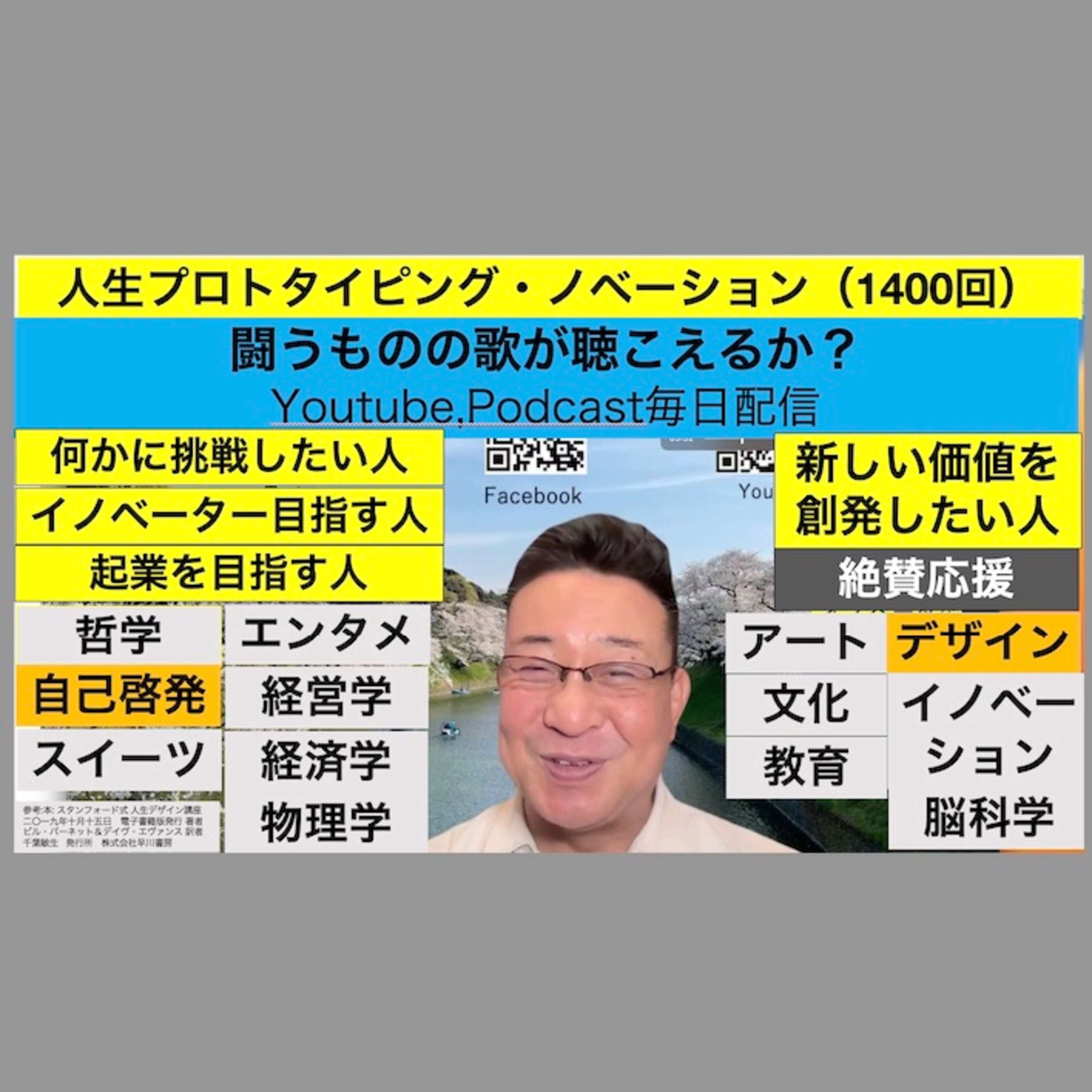 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"人生プロトタイピング・ノベーション(1400回)スタンフォード大学で人気講座の「Designing Your Life」を展開されているビル・バーネットとデイヴ・エヴァンスからの言葉に勉強させて頂きました曰く"ライフデザインにおけるプロトタイピングとは、的確な疑問を掲げ、わたしたちの隠れた偏見や思いこみを排除し、すばやく実験をくり返し、わたしたちが試してみたいと思っている道へと進む勢いを生みだすことなのだ。 プロトタイプをデザインするときのポイントは、あなたが興味をもっていることについて疑問を掲げ、一定のデータを集めることだ。優秀なプロトタイプは、問題の一側面を抜きだし、あなたにとって楽しいかもしれない未来を〝お試し〟できるような体験をデザインする。つまり、人生のさまざまな選択肢を実体験という形で視覚化できるわけだ。"ここから私は思いました 1、情熱の源を行動にうつせる2、許容可能な損失 by エフェクチュエーション3、失敗は人生の彩り by 三木清デザインシンキングを、個人の人生に適用していくという試みが、めちゃくちゃ面白くて、スタンフォード大学の皆様の一、二を争う人気講義というのも、とても頷ける内容でしたその中でも、この人生をプロトタイピングするという考え方は、とても実践的で、自分自身も改めて意識したいと思いましたこれをやることで、いつも私が言っている、情熱の源を、改めて確認しながら、そしてそこから、情熱の源自体を行動にうつすというアクティビティに、とても繋げやすくなるなと思います誰もが、大好きなことや、利他したいこと、個性を発揮したいこと、成長したいこと、など、いろんな情熱の源はあるものの、それを思っているだけでは、時間ばかりが過ぎてしまいますがこのプロトタイピングをする考えを知っていれば、まずは、完璧じゃ無いけど、初めてみて、その結果でまた考えようという、リーンなループを回すことができるかと思いました実は、自分が独立する際に、2年くらいスポットコンサルに登録して、自分ならどんな案件が来るのかを、まさにプロトタイピングしてたことがありましたその結果で、こんな案件があるのだとか、副業だとやりきれないこともできるようになるなあとか、いろんな気づきがあったおかげで、独立できた気がします副業やインターンなどはそんな使い方がきっといいのだろうなあと思うし、さらに他の、例えばどこかの国にボランティアに行きたいとか、もっと自分のファッションの個性を出したいとか、実はソムリエになりたいとか考えているだけのことがたくさんまだまだあるなあと、それを、情熱の源を見直して、プロトでやってみる、と意識するだけで、人生とてもカラフルになる気がしましたその時に思い出したのが、エフェクチュエーションの、許容可能な損失、の考え方で、大火傷をしない程度のリスクをきちんとみてやることも大切かと思いますプロトタイピングの良さは、何回も試行錯誤ができることなので、その範囲内で、Bプラン、Cプランにすぐに移行できるような形が必要かと思いましたまた、プロトタイピングをやるときにも必要となるのが、失敗への不安ですが、ここも、三木清さんの、失敗は人生の彩りの一つ、人生のゴールは幸せであって成功では無い、ということも、心にあるとインポスター症候群のように、挑戦することに二の足を踏むようなことも、乗り越えていけるのでは無いかと思いました人生にはたくさんの選択肢が実はあって、それは、実は自分の中の情熱の源にたくさん埋まっていて、それを解き放すやり方として、プロトタイピングは、とてもやりやすい方法だなあと思いました人生はプロトタイピング・ノベーションこの言葉を胸があるだけで、何か挑戦への背中を教えくれるを促すそんな気がしました^ ^参考:本: スタンフォード式 人生デザイン講座 二〇一九年十月十五日 電子書籍版発行 著者 ビル・バーネット&デイヴ・エヴァンス 訳者 千葉敏生 発行所 株式会社早川書房動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/ZYH7iMNjulI2025-02-1724 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"人生プロトタイピング・ノベーション(1400回)スタンフォード大学で人気講座の「Designing Your Life」を展開されているビル・バーネットとデイヴ・エヴァンスからの言葉に勉強させて頂きました曰く"ライフデザインにおけるプロトタイピングとは、的確な疑問を掲げ、わたしたちの隠れた偏見や思いこみを排除し、すばやく実験をくり返し、わたしたちが試してみたいと思っている道へと進む勢いを生みだすことなのだ。 プロトタイプをデザインするときのポイントは、あなたが興味をもっていることについて疑問を掲げ、一定のデータを集めることだ。優秀なプロトタイプは、問題の一側面を抜きだし、あなたにとって楽しいかもしれない未来を〝お試し〟できるような体験をデザインする。つまり、人生のさまざまな選択肢を実体験という形で視覚化できるわけだ。"ここから私は思いました 1、情熱の源を行動にうつせる2、許容可能な損失 by エフェクチュエーション3、失敗は人生の彩り by 三木清デザインシンキングを、個人の人生に適用していくという試みが、めちゃくちゃ面白くて、スタンフォード大学の皆様の一、二を争う人気講義というのも、とても頷ける内容でしたその中でも、この人生をプロトタイピングするという考え方は、とても実践的で、自分自身も改めて意識したいと思いましたこれをやることで、いつも私が言っている、情熱の源を、改めて確認しながら、そしてそこから、情熱の源自体を行動にうつすというアクティビティに、とても繋げやすくなるなと思います誰もが、大好きなことや、利他したいこと、個性を発揮したいこと、成長したいこと、など、いろんな情熱の源はあるものの、それを思っているだけでは、時間ばかりが過ぎてしまいますがこのプロトタイピングをする考えを知っていれば、まずは、完璧じゃ無いけど、初めてみて、その結果でまた考えようという、リーンなループを回すことができるかと思いました実は、自分が独立する際に、2年くらいスポットコンサルに登録して、自分ならどんな案件が来るのかを、まさにプロトタイピングしてたことがありましたその結果で、こんな案件があるのだとか、副業だとやりきれないこともできるようになるなあとか、いろんな気づきがあったおかげで、独立できた気がします副業やインターンなどはそんな使い方がきっといいのだろうなあと思うし、さらに他の、例えばどこかの国にボランティアに行きたいとか、もっと自分のファッションの個性を出したいとか、実はソムリエになりたいとか考えているだけのことがたくさんまだまだあるなあと、それを、情熱の源を見直して、プロトでやってみる、と意識するだけで、人生とてもカラフルになる気がしましたその時に思い出したのが、エフェクチュエーションの、許容可能な損失、の考え方で、大火傷をしない程度のリスクをきちんとみてやることも大切かと思いますプロトタイピングの良さは、何回も試行錯誤ができることなので、その範囲内で、Bプラン、Cプランにすぐに移行できるような形が必要かと思いましたまた、プロトタイピングをやるときにも必要となるのが、失敗への不安ですが、ここも、三木清さんの、失敗は人生の彩りの一つ、人生のゴールは幸せであって成功では無い、ということも、心にあるとインポスター症候群のように、挑戦することに二の足を踏むようなことも、乗り越えていけるのでは無いかと思いました人生にはたくさんの選択肢が実はあって、それは、実は自分の中の情熱の源にたくさん埋まっていて、それを解き放すやり方として、プロトタイピングは、とてもやりやすい方法だなあと思いました人生はプロトタイピング・ノベーションこの言葉を胸があるだけで、何か挑戦への背中を教えくれるを促すそんな気がしました^ ^参考:本: スタンフォード式 人生デザイン講座 二〇一九年十月十五日 電子書籍版発行 著者 ビル・バーネット&デイヴ・エヴァンス 訳者 千葉敏生 発行所 株式会社早川書房動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/ZYH7iMNjulI2025-02-1724 min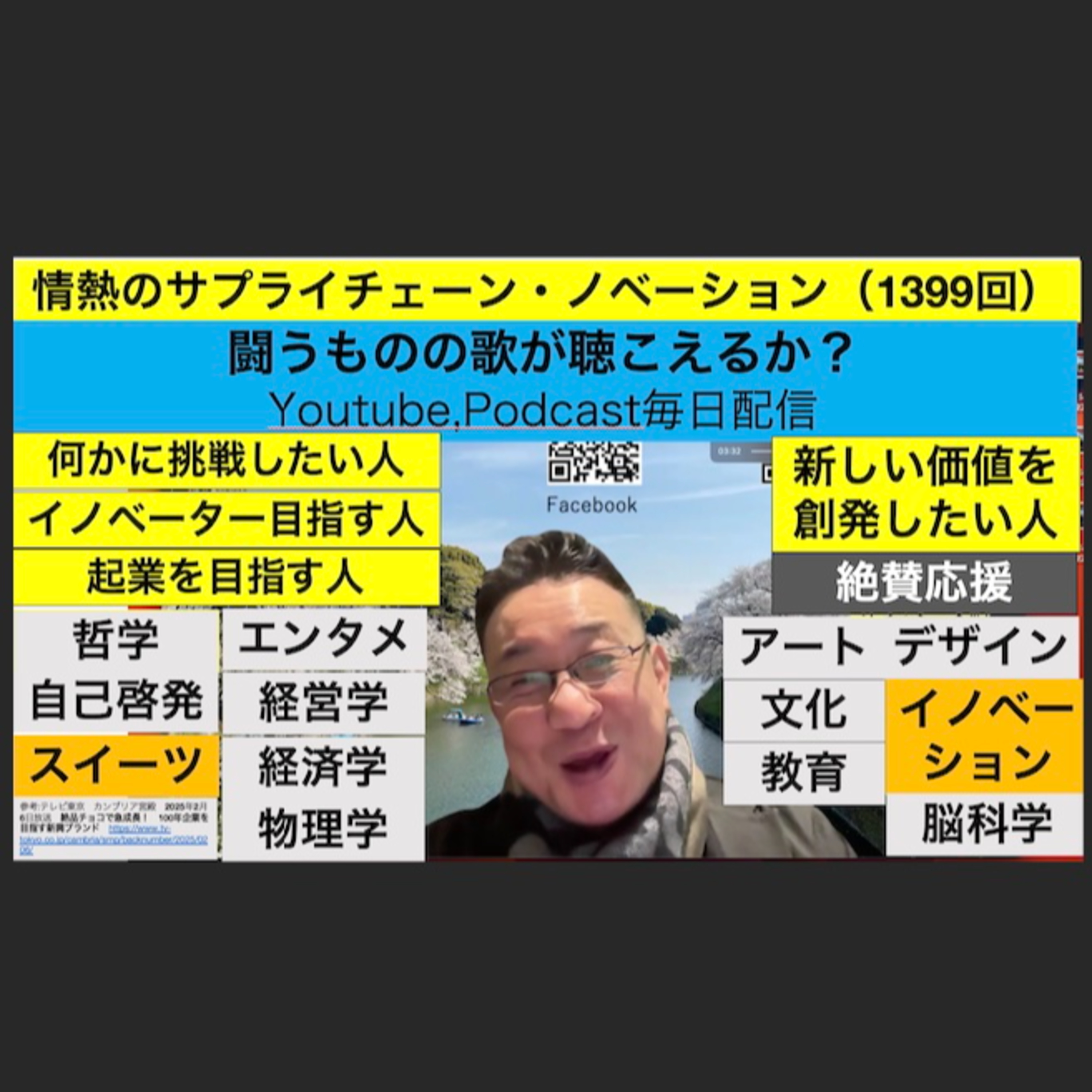 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"情熱のサプライチェーン・ノベーション(1399回)アロマ生チョコレートを生み出した鎌倉発のチョコレートブランド「メゾンカカオ」の石原紳伍社長の言葉に感動しました"僕らはチョコレートを販売させて頂いてるんですけど、チョコレートではない何かを、繋いでる気持ちがどこかにあって生産者さんから始まる情熱のリレーをお客様、またお客様からその物語をまた聞かせて頂いて、それを励みにやらせて頂いてるです"ここから私は思いました1、パッションコロンビアでの偶然の出会い 行動2、仲間家族と呼んでくれた タイパとるな3、大義情熱をリレーする私は食べたことがないのですが、ショコラコキーユは、マスカット果汁がふんだんに練り込まれていて、食べた瞬間にフルーツとカカオの香りが、口の中に広がる絶品チョコを出されている、メゾンカカオさんその社長の石原さんが、どんなイノベーター3つのフレーム(パッション、仲間、大義)で、ここまで来られたのか、めちゃくちゃ興味がありましたまざは、コロンビアでの偶然のカカオとの出会いがあったとのことで、その時のフレッシュなカカオをそのまま届けられないか、という思いから始まったとのこと。驚くべきは、その8ヶ月後には、お店を立ち上げられたという、早さと行動力です。これこそがパッションの源の成せる技だと思うのですが、やりたくでどうしようもなくなってしまう、そういう情熱が炸裂したのかと思いましたそれでも、情熱が炸裂していても、なかなか行動に移していないのが世の常ですが、石原社長は、自らの情熱の源に従って、何よりも行動に移せる人である、というところがイノベーターとしては、大切なことなのかもしれないと思いました。そして、当然一人ではできないので仲間作りが大切になるわけですが、石原社長の凄さは、コロンビアでであった人たちに、家族とまで言われるくらい、短期間で深い仲間となったことかと思いました私が世界20都市でオープンイノベーションコンテストを行なっていた際には、どんなに効率化や、必要性を言われても、必ず各都市に自らが足を運ぶことにして、現地の人との肌を触れ合わす交流を大切にするからこそ、一つの目標へ向かえる仲間になれる、そんな大切さを教えてもらいましたので、深く共感しました オープンイノベーション成功の事例でも、大企業とベンチャー企業が、ビジネス的な付き合いで終わるのではなく、時には寝食を共にしながら、深く本気で関わってる期間を経ることで、信頼が生まれてビジネスも上手くいく、そんなことも何度も目にしてきました石原社長が家族とまでコロンビアの方に言われるようになったのは、きっと寝食や大変な苦労を共にしてこられてからこそ、なんだろうなと、思いましたそして、その結果として、自分にも、仲間にも、新しい付加価値としての、アロマチョコレートという新ジャンルを確立した、世界の人々に新鮮なチョコを提供する、そんな大義が生まれたのかと思いました情熱をリレーしている気がするとの言葉は、サプライチェーンというビジネスに乗ってしまうと、失われてしまう、心や情熱というモノをいかに失われずに載せていき、消費者まで伝えることができるか、さらなるフィードバックを返してあげることができるかいわば、情熱のサプライチェーンを繋いであげることこそ、最高の付加価値の高いビジネス、イノベーションになるのかもしれないそんなことを思いました情熱のサプライチェーン・ノベーションそんな話をしています^ ^参考:テレビ東京 カンブリア宮殿 2025年2月6日放送 絶品チョコで急成長! 100年企業を目指す新興ブランド https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/smp/backnumber/2025/0206/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/BBaoLnbgvU42025-02-1615 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"情熱のサプライチェーン・ノベーション(1399回)アロマ生チョコレートを生み出した鎌倉発のチョコレートブランド「メゾンカカオ」の石原紳伍社長の言葉に感動しました"僕らはチョコレートを販売させて頂いてるんですけど、チョコレートではない何かを、繋いでる気持ちがどこかにあって生産者さんから始まる情熱のリレーをお客様、またお客様からその物語をまた聞かせて頂いて、それを励みにやらせて頂いてるです"ここから私は思いました1、パッションコロンビアでの偶然の出会い 行動2、仲間家族と呼んでくれた タイパとるな3、大義情熱をリレーする私は食べたことがないのですが、ショコラコキーユは、マスカット果汁がふんだんに練り込まれていて、食べた瞬間にフルーツとカカオの香りが、口の中に広がる絶品チョコを出されている、メゾンカカオさんその社長の石原さんが、どんなイノベーター3つのフレーム(パッション、仲間、大義)で、ここまで来られたのか、めちゃくちゃ興味がありましたまざは、コロンビアでの偶然のカカオとの出会いがあったとのことで、その時のフレッシュなカカオをそのまま届けられないか、という思いから始まったとのこと。驚くべきは、その8ヶ月後には、お店を立ち上げられたという、早さと行動力です。これこそがパッションの源の成せる技だと思うのですが、やりたくでどうしようもなくなってしまう、そういう情熱が炸裂したのかと思いましたそれでも、情熱が炸裂していても、なかなか行動に移していないのが世の常ですが、石原社長は、自らの情熱の源に従って、何よりも行動に移せる人である、というところがイノベーターとしては、大切なことなのかもしれないと思いました。そして、当然一人ではできないので仲間作りが大切になるわけですが、石原社長の凄さは、コロンビアでであった人たちに、家族とまで言われるくらい、短期間で深い仲間となったことかと思いました私が世界20都市でオープンイノベーションコンテストを行なっていた際には、どんなに効率化や、必要性を言われても、必ず各都市に自らが足を運ぶことにして、現地の人との肌を触れ合わす交流を大切にするからこそ、一つの目標へ向かえる仲間になれる、そんな大切さを教えてもらいましたので、深く共感しました オープンイノベーション成功の事例でも、大企業とベンチャー企業が、ビジネス的な付き合いで終わるのではなく、時には寝食を共にしながら、深く本気で関わってる期間を経ることで、信頼が生まれてビジネスも上手くいく、そんなことも何度も目にしてきました石原社長が家族とまでコロンビアの方に言われるようになったのは、きっと寝食や大変な苦労を共にしてこられてからこそ、なんだろうなと、思いましたそして、その結果として、自分にも、仲間にも、新しい付加価値としての、アロマチョコレートという新ジャンルを確立した、世界の人々に新鮮なチョコを提供する、そんな大義が生まれたのかと思いました情熱をリレーしている気がするとの言葉は、サプライチェーンというビジネスに乗ってしまうと、失われてしまう、心や情熱というモノをいかに失われずに載せていき、消費者まで伝えることができるか、さらなるフィードバックを返してあげることができるかいわば、情熱のサプライチェーンを繋いであげることこそ、最高の付加価値の高いビジネス、イノベーションになるのかもしれないそんなことを思いました情熱のサプライチェーン・ノベーションそんな話をしています^ ^参考:テレビ東京 カンブリア宮殿 2025年2月6日放送 絶品チョコで急成長! 100年企業を目指す新興ブランド https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/smp/backnumber/2025/0206/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/BBaoLnbgvU42025-02-1615 min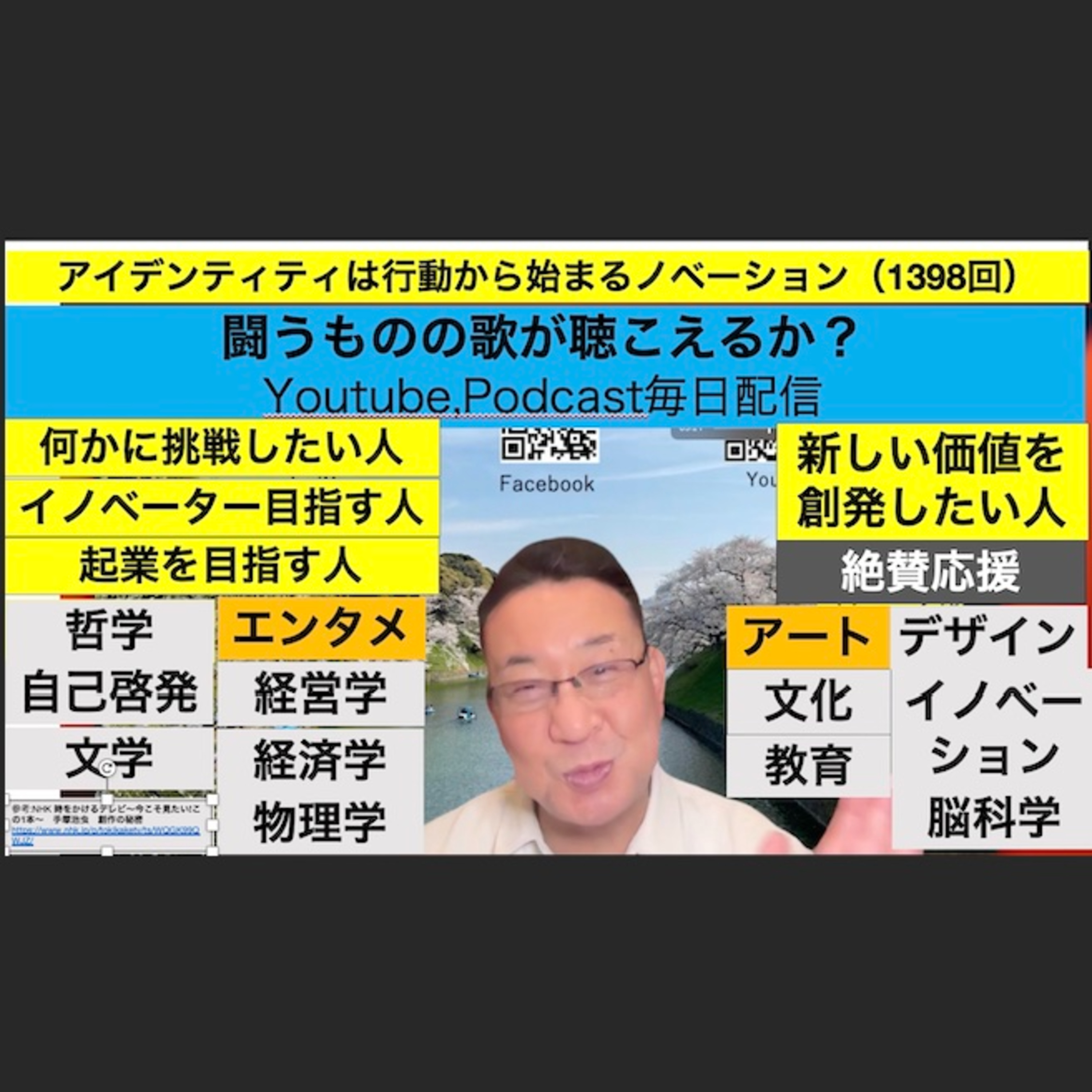 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"アイデンティティは行動から始まるノベーション(1398回)手塚治虫さんの漫画創作の秘訣の一端について感動しました"やはりテーマとは自分自身が本来持っている1つか2つの主張これを漫画に表す普通、誰でもできることじゃないかと思う難しい今のきざな言葉でアイデンティティっていう言葉があるそういうものを自分で確かめるために漫画を描かざるを得なかった"ここから私は思いました1、誰もが本来持つテーマ→情熱の源2、何かで表現・行動する→アイデンティティを確かめる 3、フィードバックループ→新たな情熱の源が生まれる手塚治虫さんの漫画は、実は今でも寝室のお供にはブラックジャックを必ず読んでいるのですが、表にはそんなに情熱がたぎっている様には見えないのに、中ではぐつぐつ煮えているそんなところが、手塚治虫さんとブラックジャックさんに共通なモノとして感じました"誰でもできることなんじゃないかと思う"なんて言われてますが、そもそも自らの情熱の源に、人生の全てを全張りできている人は、少ないのかもしれないなあと思いますだからこそ、本当に寝食を忘れてというか、ほとんど侵食をする暇もなく、漫画を描くという、情熱の源に没頭し続けることができた、手塚治虫さんは、こんなに凄いメッセージを我々に届けてくれたのかなと、感動しました何かの情熱の源がある気がしたら、とにかくそれに没頭してみる、そこに自らのアイデンティティがあるのかもしれないと、とにかく探り続けるその行為自身が、また自らの情熱の源に、フィードバックして、更なる新たな助熱の源が見つかって、そして炸裂していく、そんなことなのかなあと思いましたそれによって、チクセントミハイさんの言うところの、挑戦軸とスキル軸の両方が成長し、フロー状態に調達できるのかと、そんなふうに思いました自分のアイデンティティはなんなんだ?みたいなことで悩むのではなく、自らの情熱の源に、とにかく全張りしていく、寝食も忘れて全張りしていくそこから見えてくる、新たな情熱の源と、アイデンティティ、そのループを回しまくる、ただひたすらに、アイデンティティを確かめるために表現し続けるノベーションもっと言えばアイデンティティは行動から始まるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHK 時をかけるテレビ〜今こそ見たい!この1本〜 手塚治虫 創作の秘密 https://www.nhk.jp/p/tokikaketv/ts/WQGK99QWJZ/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/UD6ZHGC8W8c2025-02-1523 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"アイデンティティは行動から始まるノベーション(1398回)手塚治虫さんの漫画創作の秘訣の一端について感動しました"やはりテーマとは自分自身が本来持っている1つか2つの主張これを漫画に表す普通、誰でもできることじゃないかと思う難しい今のきざな言葉でアイデンティティっていう言葉があるそういうものを自分で確かめるために漫画を描かざるを得なかった"ここから私は思いました1、誰もが本来持つテーマ→情熱の源2、何かで表現・行動する→アイデンティティを確かめる 3、フィードバックループ→新たな情熱の源が生まれる手塚治虫さんの漫画は、実は今でも寝室のお供にはブラックジャックを必ず読んでいるのですが、表にはそんなに情熱がたぎっている様には見えないのに、中ではぐつぐつ煮えているそんなところが、手塚治虫さんとブラックジャックさんに共通なモノとして感じました"誰でもできることなんじゃないかと思う"なんて言われてますが、そもそも自らの情熱の源に、人生の全てを全張りできている人は、少ないのかもしれないなあと思いますだからこそ、本当に寝食を忘れてというか、ほとんど侵食をする暇もなく、漫画を描くという、情熱の源に没頭し続けることができた、手塚治虫さんは、こんなに凄いメッセージを我々に届けてくれたのかなと、感動しました何かの情熱の源がある気がしたら、とにかくそれに没頭してみる、そこに自らのアイデンティティがあるのかもしれないと、とにかく探り続けるその行為自身が、また自らの情熱の源に、フィードバックして、更なる新たな助熱の源が見つかって、そして炸裂していく、そんなことなのかなあと思いましたそれによって、チクセントミハイさんの言うところの、挑戦軸とスキル軸の両方が成長し、フロー状態に調達できるのかと、そんなふうに思いました自分のアイデンティティはなんなんだ?みたいなことで悩むのではなく、自らの情熱の源に、とにかく全張りしていく、寝食も忘れて全張りしていくそこから見えてくる、新たな情熱の源と、アイデンティティ、そのループを回しまくる、ただひたすらに、アイデンティティを確かめるために表現し続けるノベーションもっと言えばアイデンティティは行動から始まるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHK 時をかけるテレビ〜今こそ見たい!この1本〜 手塚治虫 創作の秘密 https://www.nhk.jp/p/tokikaketv/ts/WQGK99QWJZ/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/UD6ZHGC8W8c2025-02-1523 min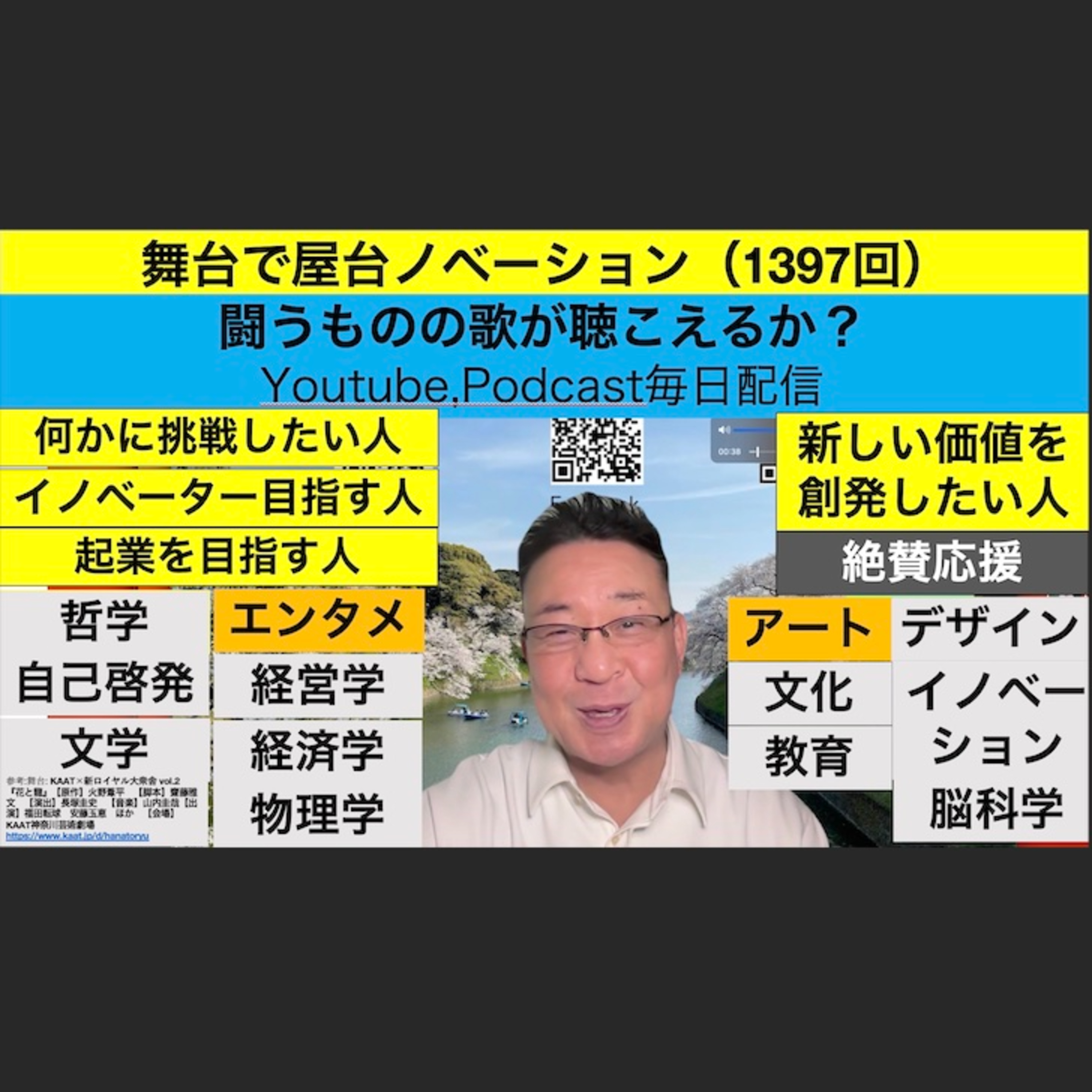 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"舞台で屋台ノベーション(1397回)KAAT×新ロイヤル大衆舎 vol.2舞台『花と龍』は、イノベーションの塊のような舞台で、めちゃくちゃ感動しました芥川賞作家の火野葦平さんの小説より、"北九州・若松港を舞台に、ゴンゾと呼ばれる荷役労働者たちが、独特の気風を誇りに活躍していた激動の時代の物語"主人公の玉井金五郎(福田転球)と、長年連れ添うことになるマン(安藤玉恵)との、破天荒だけども筋の通った生き方を貫く、情熱と愛と仲間の物語でした。物語もキャストの皆様も本当に素晴らしく、心より感動しました。そしてさらに、私はこの舞台に、以下のようなイノベーションを見させて頂きました。1、舞台に屋台2、地方創生3、優しい支援何よりも凄かったのが、役者さんが演じる舞台に、たくさんの屋台を作って、そしてそこに観客の皆様が、上演前には、自由にお買い物をしたり、飲食をしたりさらには、そこで買ったモノを一階の席の方は、そのまま食べながら鑑賞できるというスタイルにされていたことです。客席でお弁当を食べられる劇場は、歌舞伎座がありますが、舞台の上にたくさんの屋台を作られた舞台装置は、未だかつて観たことがありませんでした。アフタートークで、演出の長塚圭史さんが、コロナ時代にできなくなってしまった、人の賑わいをどう取り戻すかを考えて、ここに至ったとのことですがこれを本当に実現するためには、会場、舞台、美術などのあらゆる関係者の皆様の並々ならぬ情熱と協力がないと、実現できないことだと思いますので、驚きです。私は早速、開演前に、舞台上の屋台にて、焼きそばと、コーヒーと、ホワイトチョコのスイーツを買って、そして客席で食べながら観るという、めちゃくちゃ贅沢な体験をさせていただきました。ビールなどのお酒類もあり、そちらがお好きな皆様は、なかなかにお楽しみ頂いていたようで、私の隣の席の男性は、勢い余ってグッスリ睡眠しておりました笑また粋なのが、その屋台は、実は会場の地元の皆様のご協力を一つ一つ頂いていて、地元の名物や名産のお店のモノと人とが、そのまま舞台の屋台をやられているということです。これは、他の地域に行ったら、今度は他の地域の皆様のできる屋台をそこに置かれるとのことで、これはこの舞台をやることによって、地域の皆様も舞台の一人の登場人物として、一緒に作っていくようなことになるのでそれを楽しみに、地方を訪れたくなる人もあるのではないかと思うと、地方創生の形として、とても新しい取り組みの一つになるなあと、思いましたまた、さらに素敵だったのは、その屋台なのですが、実は、石川地方の被災された地域の皆様の、壊されるお家の素敵な襖?を保存する運動があるそうでそれを活用されているので、ものすごくリアルで素敵な屋台になるとともに、毎回、舞台の度に運んで、作って、解体するという、優しいサーキュレーションな仕掛けになってることにも感動しましたさらには、この舞台には、優しい鑑賞会、という回もあって、会場を暗くせずに、出入り自由な回があって、そこでは、暗くなるのが苦手な方や、ずっとじっと長く座ってることが苦手な人たちも、自由に出入りしながら観れるそんな優しい回も用意してるとのことで、めちゃくちゃ感動しましたそんな雰囲気のおかげで、自分は始めて舞台を観に行って、隣の席の知らない方と、楽しくお話をすることにも繋がっていきました舞台は、脚本、演出、美術、舞台、音響、役者の皆様などの様々な方々が創られる、素敵な芸術でありエンタメだと思いますし、それだけでも十分に魂爆発してるのにさらに、その舞台というエンタメの可能性を、どこまで広げることができるのか?への飽くなき挑戦として、新たな可能性を拓くイノベーションとしてある意味、今回の舞台は、舞台を通してエンタメによる個人の"パッション'に泣き笑いと感動を、屋台により知らない人たちとの"仲間"としての繋がりを、"大義"として地方創生とサーキュレーションエコノミーをということでイノベーター3つのフレーム(パッション、仲間、大義)を全て実現されているイノベーションに出会えたなあと、そんな感動も頂きました一言で言えば舞台で屋台ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:舞台: KAAT×新ロイヤル大衆舎 vol.2『花と龍』【原作】火野葦平 【脚本】齋藤雅文 【演出】長塚圭史 【音楽】山内圭哉【出演】福田転球 安藤玉恵 ほか 【会場】KAAT神奈川芸術劇場 https://www.kaat.jp/d/hanatoryu動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/K37W_BuDkQk2025-02-1421 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"舞台で屋台ノベーション(1397回)KAAT×新ロイヤル大衆舎 vol.2舞台『花と龍』は、イノベーションの塊のような舞台で、めちゃくちゃ感動しました芥川賞作家の火野葦平さんの小説より、"北九州・若松港を舞台に、ゴンゾと呼ばれる荷役労働者たちが、独特の気風を誇りに活躍していた激動の時代の物語"主人公の玉井金五郎(福田転球)と、長年連れ添うことになるマン(安藤玉恵)との、破天荒だけども筋の通った生き方を貫く、情熱と愛と仲間の物語でした。物語もキャストの皆様も本当に素晴らしく、心より感動しました。そしてさらに、私はこの舞台に、以下のようなイノベーションを見させて頂きました。1、舞台に屋台2、地方創生3、優しい支援何よりも凄かったのが、役者さんが演じる舞台に、たくさんの屋台を作って、そしてそこに観客の皆様が、上演前には、自由にお買い物をしたり、飲食をしたりさらには、そこで買ったモノを一階の席の方は、そのまま食べながら鑑賞できるというスタイルにされていたことです。客席でお弁当を食べられる劇場は、歌舞伎座がありますが、舞台の上にたくさんの屋台を作られた舞台装置は、未だかつて観たことがありませんでした。アフタートークで、演出の長塚圭史さんが、コロナ時代にできなくなってしまった、人の賑わいをどう取り戻すかを考えて、ここに至ったとのことですがこれを本当に実現するためには、会場、舞台、美術などのあらゆる関係者の皆様の並々ならぬ情熱と協力がないと、実現できないことだと思いますので、驚きです。私は早速、開演前に、舞台上の屋台にて、焼きそばと、コーヒーと、ホワイトチョコのスイーツを買って、そして客席で食べながら観るという、めちゃくちゃ贅沢な体験をさせていただきました。ビールなどのお酒類もあり、そちらがお好きな皆様は、なかなかにお楽しみ頂いていたようで、私の隣の席の男性は、勢い余ってグッスリ睡眠しておりました笑また粋なのが、その屋台は、実は会場の地元の皆様のご協力を一つ一つ頂いていて、地元の名物や名産のお店のモノと人とが、そのまま舞台の屋台をやられているということです。これは、他の地域に行ったら、今度は他の地域の皆様のできる屋台をそこに置かれるとのことで、これはこの舞台をやることによって、地域の皆様も舞台の一人の登場人物として、一緒に作っていくようなことになるのでそれを楽しみに、地方を訪れたくなる人もあるのではないかと思うと、地方創生の形として、とても新しい取り組みの一つになるなあと、思いましたまた、さらに素敵だったのは、その屋台なのですが、実は、石川地方の被災された地域の皆様の、壊されるお家の素敵な襖?を保存する運動があるそうでそれを活用されているので、ものすごくリアルで素敵な屋台になるとともに、毎回、舞台の度に運んで、作って、解体するという、優しいサーキュレーションな仕掛けになってることにも感動しましたさらには、この舞台には、優しい鑑賞会、という回もあって、会場を暗くせずに、出入り自由な回があって、そこでは、暗くなるのが苦手な方や、ずっとじっと長く座ってることが苦手な人たちも、自由に出入りしながら観れるそんな優しい回も用意してるとのことで、めちゃくちゃ感動しましたそんな雰囲気のおかげで、自分は始めて舞台を観に行って、隣の席の知らない方と、楽しくお話をすることにも繋がっていきました舞台は、脚本、演出、美術、舞台、音響、役者の皆様などの様々な方々が創られる、素敵な芸術でありエンタメだと思いますし、それだけでも十分に魂爆発してるのにさらに、その舞台というエンタメの可能性を、どこまで広げることができるのか?への飽くなき挑戦として、新たな可能性を拓くイノベーションとしてある意味、今回の舞台は、舞台を通してエンタメによる個人の"パッション'に泣き笑いと感動を、屋台により知らない人たちとの"仲間"としての繋がりを、"大義"として地方創生とサーキュレーションエコノミーをということでイノベーター3つのフレーム(パッション、仲間、大義)を全て実現されているイノベーションに出会えたなあと、そんな感動も頂きました一言で言えば舞台で屋台ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:舞台: KAAT×新ロイヤル大衆舎 vol.2『花と龍』【原作】火野葦平 【脚本】齋藤雅文 【演出】長塚圭史 【音楽】山内圭哉【出演】福田転球 安藤玉恵 ほか 【会場】KAAT神奈川芸術劇場 https://www.kaat.jp/d/hanatoryu動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/K37W_BuDkQk2025-02-1421 min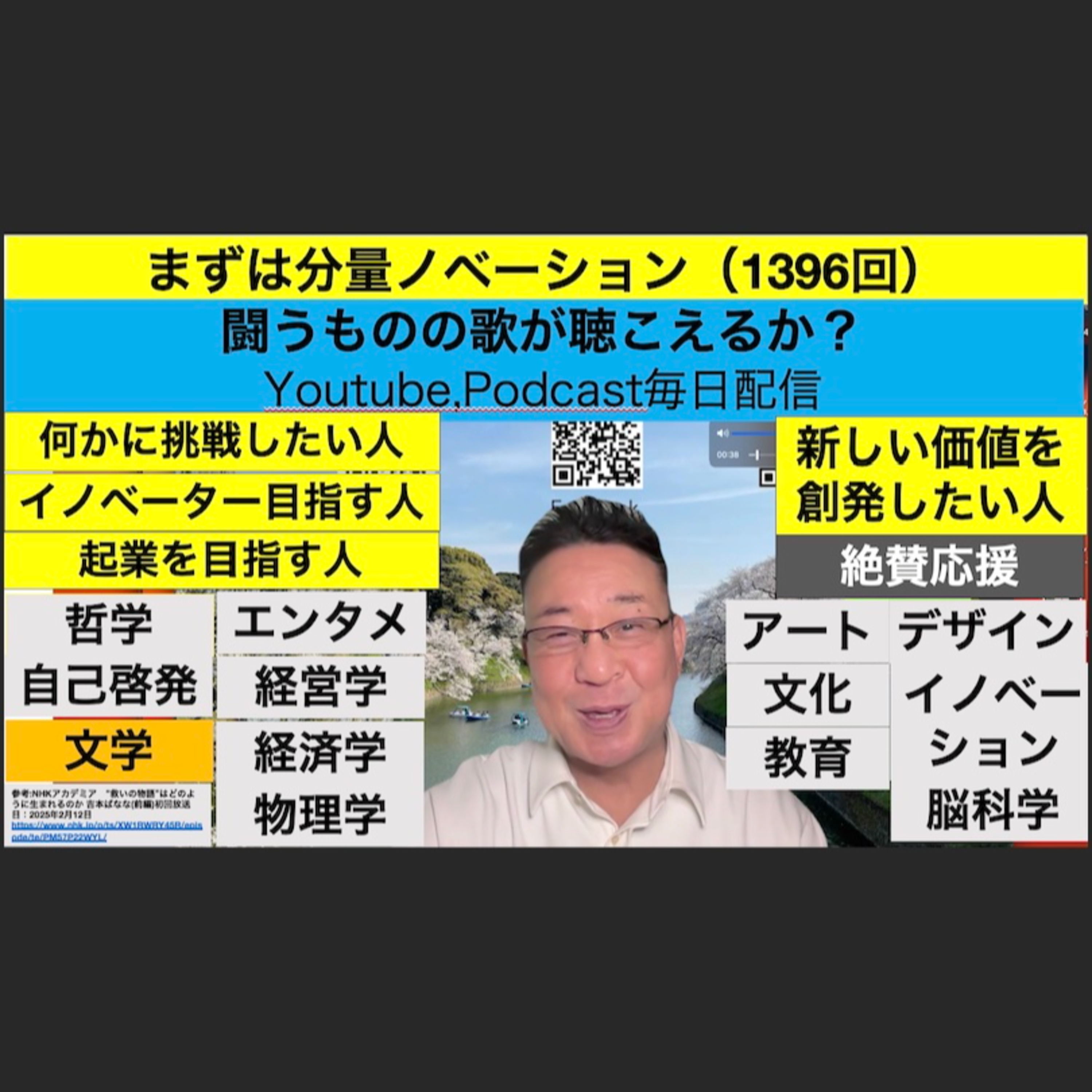 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"まずは分量ノベーション(1396回)小説家の吉本ばななさんへの"どうしたら物語を上手く描けるか?"の質問への回答に震えました曰く"これも結構明快で、まず分量を書くことですね。エッセイの。エッセイとか日記とかのまず分量をたくさん書く。そうするとその中から、トピックが見つかりますから、それを一人称で書いてください。三人称で書こうとするとすごく難しくなります。私は時々三人称を使いますけど、やっぱり難しいなって感じます。で今も一人称で書いてるけど進まないんだよーって思ってるかもしれないけど、それは架空のことを書くからだと思います。だから、日記とかエッセイとかめちゃくちゃ書いて、その中から、ここもうちょっと濃くなるなとかを見つけ出して、そこを一人称で細かく書いてみる。で、じゃそれ日記じゃんって話になると思うけど、そうじゃなくて文体を変えてみる、微妙に。一人称でその中で強いことだけ濃く書く、というか、で弱いところは、端折るという、メリハリをつけたら小説になりますから。勝手になりますから、それをやってみてください。"ここから私は創作活動はイノベーション活動ととてもシナジーがあるなあと思いました1、量が質を超える2、自らの情熱の源3、三現主義"とにかく分量を書く"この言葉は、イノベーションを生み出すためには、量が質を超える、これにとても似ているなあと思いましたタイパ的な話が、イノベーションの世界でもよく出てきて、もっと効率的にイノベーションを生み出す方法を、などよく言われることがあるのですがもちろん、さまざまな手法やマインドセットやスキル、ノウハウも必要なのですが、それでイノベーションがポンポン生まれるかというと全くそうはいかないたくさんの人たちでたくさんの試行錯誤をする環境でやっと1000に3つの種が生まれる、そんなことかと思います。それがアーティストととなると、ある意味、まずは自分一人で始めなくてはいけない、そのためには、たくさんの分量の創作をする、それが大きなポイントということは、とても腹落ちする話でしたグラッドウェルさんの1万時間の法則も、ただやればいいだけではありませんが、やはり量が必要となる、そこは共通しているのだなあと思いましたまた、三人称ではなく、まずは一人称で書く、ということにもとても共感しました。イノベーションの場合も、お客様から課題を与えられたり、上司からミッションを言われたりしますがそれと、自らの情熱の源を掛け合わせたものを創発しているかが、とても大切だと思います。そしてそれを自分ごととして捉えられると、そこには、情熱が乗っかってきて、多少の困難は乗り越えるパッションが生まれるまた自分ごとなので、さまざまなアイディアや違和感なども、とてもよく理解できるため、苦しくならずに続けることもできる、そんなところに、様々な困難に負けずに分量をこなせる秘密があるかもしれないとも思いましたそして、もう一つは、架空の話を描くから、進まなくなってしまう、より、現物、現場、現人の三現主義のように、リアルな世界を描こうとすることによってそこにある、誰も気づいてないような、本当の真実に巡り会えるかもしれないし、思いもよらない展開を生み出すことができる、これは、まさにイノベーションの現場100回とも通じることと思いましたまとめると、良い物語を描くためにはとにかく分量をかく、そのためにも、自らの情熱の源から始めて、そしてより現場に降りて描く良い物語を創るには分量を書くまずは分量ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHKアカデミア “救いの物語”はどのように生まれるのか 吉本ばなな(前編)初回放送日:2025年2月12日 https://www.nhk.jp/p/ts/XW1RWRY45R/episode/te/PM57P22WYL/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/bzk53hh2ppA2025-02-1321 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"まずは分量ノベーション(1396回)小説家の吉本ばななさんへの"どうしたら物語を上手く描けるか?"の質問への回答に震えました曰く"これも結構明快で、まず分量を書くことですね。エッセイの。エッセイとか日記とかのまず分量をたくさん書く。そうするとその中から、トピックが見つかりますから、それを一人称で書いてください。三人称で書こうとするとすごく難しくなります。私は時々三人称を使いますけど、やっぱり難しいなって感じます。で今も一人称で書いてるけど進まないんだよーって思ってるかもしれないけど、それは架空のことを書くからだと思います。だから、日記とかエッセイとかめちゃくちゃ書いて、その中から、ここもうちょっと濃くなるなとかを見つけ出して、そこを一人称で細かく書いてみる。で、じゃそれ日記じゃんって話になると思うけど、そうじゃなくて文体を変えてみる、微妙に。一人称でその中で強いことだけ濃く書く、というか、で弱いところは、端折るという、メリハリをつけたら小説になりますから。勝手になりますから、それをやってみてください。"ここから私は創作活動はイノベーション活動ととてもシナジーがあるなあと思いました1、量が質を超える2、自らの情熱の源3、三現主義"とにかく分量を書く"この言葉は、イノベーションを生み出すためには、量が質を超える、これにとても似ているなあと思いましたタイパ的な話が、イノベーションの世界でもよく出てきて、もっと効率的にイノベーションを生み出す方法を、などよく言われることがあるのですがもちろん、さまざまな手法やマインドセットやスキル、ノウハウも必要なのですが、それでイノベーションがポンポン生まれるかというと全くそうはいかないたくさんの人たちでたくさんの試行錯誤をする環境でやっと1000に3つの種が生まれる、そんなことかと思います。それがアーティストととなると、ある意味、まずは自分一人で始めなくてはいけない、そのためには、たくさんの分量の創作をする、それが大きなポイントということは、とても腹落ちする話でしたグラッドウェルさんの1万時間の法則も、ただやればいいだけではありませんが、やはり量が必要となる、そこは共通しているのだなあと思いましたまた、三人称ではなく、まずは一人称で書く、ということにもとても共感しました。イノベーションの場合も、お客様から課題を与えられたり、上司からミッションを言われたりしますがそれと、自らの情熱の源を掛け合わせたものを創発しているかが、とても大切だと思います。そしてそれを自分ごととして捉えられると、そこには、情熱が乗っかってきて、多少の困難は乗り越えるパッションが生まれるまた自分ごとなので、さまざまなアイディアや違和感なども、とてもよく理解できるため、苦しくならずに続けることもできる、そんなところに、様々な困難に負けずに分量をこなせる秘密があるかもしれないとも思いましたそして、もう一つは、架空の話を描くから、進まなくなってしまう、より、現物、現場、現人の三現主義のように、リアルな世界を描こうとすることによってそこにある、誰も気づいてないような、本当の真実に巡り会えるかもしれないし、思いもよらない展開を生み出すことができる、これは、まさにイノベーションの現場100回とも通じることと思いましたまとめると、良い物語を描くためにはとにかく分量をかく、そのためにも、自らの情熱の源から始めて、そしてより現場に降りて描く良い物語を創るには分量を書くまずは分量ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:NHKアカデミア “救いの物語”はどのように生まれるのか 吉本ばなな(前編)初回放送日:2025年2月12日 https://www.nhk.jp/p/ts/XW1RWRY45R/episode/te/PM57P22WYL/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/bzk53hh2ppA2025-02-1321 min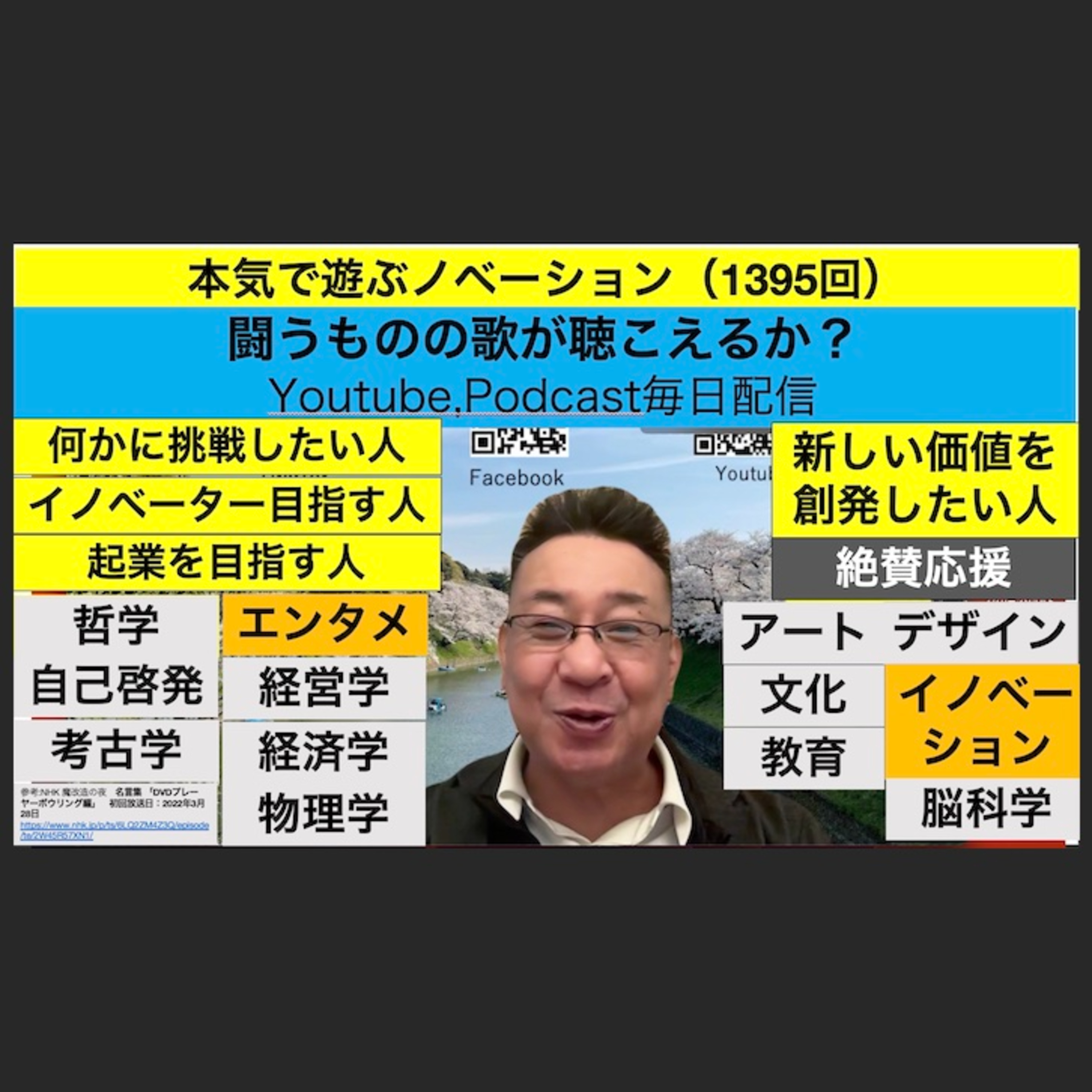 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"本気で遊ぶノベーション(1395回)"魔改造の夜"よりチームDンソーさんの言葉に震えました曰く"本気で遊ぶってのが大事遊びから情熱を生んで、情熱から目的を見つける目的意識がどんどん広がっていけば、スーパーなエンジニアになれるんじゃないのか"ここから私は思いました1、パッションのみに集中する→本気で遊ぶ2、フローに突入する→情熱の源が燃え盛る3、仲間とともに大義を見つける→情熱から目的を見つける"魔改造の夜"はいつもドキドキとワクワクと感動を与えてくれるめちゃくちゃ好きなドキュメンタリー番組なのですが、この言葉に全てが集約されている気がしました本気で遊ぶ、とは、何に役に立つのか、とか、収益がどうとか、全く関係なく、子供のように大好きなことをやっていくということなんだろうなあと思いました以前、子供に泥団子をつくることを奨励されていた加用文夫先生のお話をしましたが(子供の熱中は人生初の情熱の源ノベーション(1138回)https://youtu.be/nsQtI_wx378)おっしゃられていた「その時がその時として詰まっていた」経験が、その人の情熱を育てる、ということは、子供も大人も同じなんだと思いましたそして、チクセントミハイさんの、フローに到達するためには、挑戦軸とスキル軸が、両方とも高まることによって実現されるので、そこまで突き詰めていくことが大切だとそれは何でも良くて、子供の泥んこ遊びでも、そこまで行くのを止める人がいなければ、きっとそのうち到達するのだろうなと、その体験が、とても貴重になるなと思いましたしかし、会社の組織などでは、それを許してくれることは、なかなか難しいのかと思います。まさに"魔改造の夜"はそれを外部から環境を提供されているといっていいのかもしれませんしそういった環境を、会社でも提供する必要があるのだと、思いました。それは、組織の懐の深さとして、とにかくやってみろ的なことでも、ハッカソンやアイディアコンテストなどのイベントでも何でもいいのですが一旦、会社の目的も取っ払って、とにかく遊べ、という環境をどう提供できるか、それによって、情熱の源を発動させる、そんなアクティビティがあってもいいのではないか、そんなことを思いましたそしてそこから、仲間と共に、自分だけではない、大義がうまれてくれば、それは、まさにイノベーションの種となる、そんなことかもしれないなと思いました会社がそんな環境を提供してくれないのであれば、それは、自分として、そういう環境を体験できるところを探して、自ら突っ込んで行くこともありなんじゃないか、それは必ずしも会社を辞めなくたってできる環境もあるので、自分として、本気で遊んでるか?と、問い直して、動いてみる、そんなことが自分もできればいいなあと、改めて思いました本気で遊ぶノベーション自分はできてるか、そんな話をしています^ ^参考:NHK 魔改造の夜 名言集 「DVDプレーヤーボウリング編」 初回放送日:2022年3月28日 https://www.nhk.jp/p/ts/6LQ2ZM4Z3Q/episode/te/2W45R57XN1/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/QhEB06bcoR82025-02-1215 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"本気で遊ぶノベーション(1395回)"魔改造の夜"よりチームDンソーさんの言葉に震えました曰く"本気で遊ぶってのが大事遊びから情熱を生んで、情熱から目的を見つける目的意識がどんどん広がっていけば、スーパーなエンジニアになれるんじゃないのか"ここから私は思いました1、パッションのみに集中する→本気で遊ぶ2、フローに突入する→情熱の源が燃え盛る3、仲間とともに大義を見つける→情熱から目的を見つける"魔改造の夜"はいつもドキドキとワクワクと感動を与えてくれるめちゃくちゃ好きなドキュメンタリー番組なのですが、この言葉に全てが集約されている気がしました本気で遊ぶ、とは、何に役に立つのか、とか、収益がどうとか、全く関係なく、子供のように大好きなことをやっていくということなんだろうなあと思いました以前、子供に泥団子をつくることを奨励されていた加用文夫先生のお話をしましたが(子供の熱中は人生初の情熱の源ノベーション(1138回)https://youtu.be/nsQtI_wx378)おっしゃられていた「その時がその時として詰まっていた」経験が、その人の情熱を育てる、ということは、子供も大人も同じなんだと思いましたそして、チクセントミハイさんの、フローに到達するためには、挑戦軸とスキル軸が、両方とも高まることによって実現されるので、そこまで突き詰めていくことが大切だとそれは何でも良くて、子供の泥んこ遊びでも、そこまで行くのを止める人がいなければ、きっとそのうち到達するのだろうなと、その体験が、とても貴重になるなと思いましたしかし、会社の組織などでは、それを許してくれることは、なかなか難しいのかと思います。まさに"魔改造の夜"はそれを外部から環境を提供されているといっていいのかもしれませんしそういった環境を、会社でも提供する必要があるのだと、思いました。それは、組織の懐の深さとして、とにかくやってみろ的なことでも、ハッカソンやアイディアコンテストなどのイベントでも何でもいいのですが一旦、会社の目的も取っ払って、とにかく遊べ、という環境をどう提供できるか、それによって、情熱の源を発動させる、そんなアクティビティがあってもいいのではないか、そんなことを思いましたそしてそこから、仲間と共に、自分だけではない、大義がうまれてくれば、それは、まさにイノベーションの種となる、そんなことかもしれないなと思いました会社がそんな環境を提供してくれないのであれば、それは、自分として、そういう環境を体験できるところを探して、自ら突っ込んで行くこともありなんじゃないか、それは必ずしも会社を辞めなくたってできる環境もあるので、自分として、本気で遊んでるか?と、問い直して、動いてみる、そんなことが自分もできればいいなあと、改めて思いました本気で遊ぶノベーション自分はできてるか、そんな話をしています^ ^参考:NHK 魔改造の夜 名言集 「DVDプレーヤーボウリング編」 初回放送日:2022年3月28日 https://www.nhk.jp/p/ts/6LQ2ZM4Z3Q/episode/te/2W45R57XN1/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/QhEB06bcoR82025-02-1215 min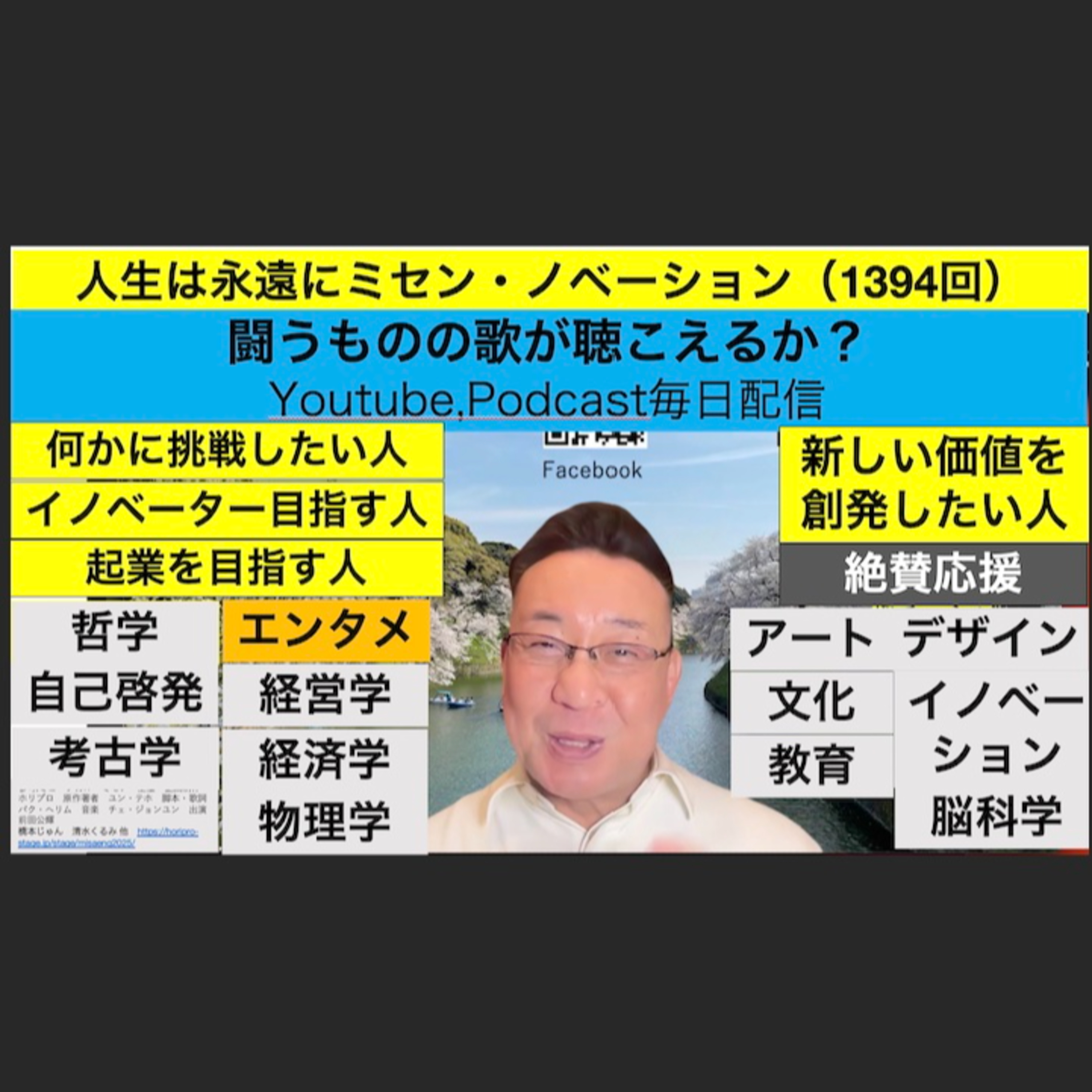 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"人生は永遠にミセン・ノベーション(1394回)韓国で社会現象まで引き起こしたと言われる韓国ドラマの"ミセン"のミュージカル舞台にめちゃくちゃ号泣したとともに、脚本・歌詞 担当のパク・ヘリムさんの言葉に感動しました。曰く"幼い頃から囲碁が人生のすべてたったチャン・グレは、ジャングルのような現実世界に放り込まれる。囲碁の世界とはまた違う、生存がかかった「ワン・インターナショナル」という場所で、生き残るために努力しながら彼は自らの過去からすこしずつ抜け出していく。囲碁棋士だった頃は、自分と相手だけの世界たったけれど、石そのものとなった今は彼のそばで協力できるほかの石たちが見えるようになる。彼はまた過去を無駄な時間だったと背を向けることはしません。チャン・グレは過去の時間を振り返りながら、今の現実にも過去の経験を生かし、自分だけの盤を作り上げていきます。そうして、彼は自分の人生における「勝利」とはなにかを再び考え、「ワンセン(完生)」へと足を踏み出していくのです。"ここから私は思いました1、ミセン(未生)2、碁石3、仲間このドラマは本当に大好きで何回も見てるのですが、このミュージカル版は、それにも増して、曲も舞台装置も、キャストの皆さんも、全て最高すぎて、しばらく放心していました。自分のサラリーマン新人時代に、本当に何もできない自分が悔しくて泣いたり、毎日寝ないために強壮剤や夜食やおやつで、めちゃくちゃ太ってしまったり、リアルに思い出しましたその頃は本当に右も左もわからず、まさに未完成なミセン(未生)どころか、赤ん坊状態でしたが、その頃の新鮮な気持ちや、簡単なことでも成し遂げた時の嬉しい気持ちは、大切だったなあと思います新しいことへ挑戦するときは、このミセン(未生)にまた戻ることを怖いけれども、でもそこから成長パッションで成し遂げた時の快感を思い出しながら、常にミセンで居続ける選択をしたいなと思いましたまた、パクさんの話にもありますが、組織の中または人間の中で生きるということは、結局は碁盤の石になるということなんだと、改めて気付かされました組織の歯車になりたくない、みたいなことも思ったりする時期もありましたが、結局は、社会的動物である人間の中で生きるためには、碁盤の碁石の一つであることを認識する必要があるし、それでもその碁石がないと成り立たない社会もある、そんな風に改めて思いましたさらには、碁石であるためには、一番大切なものは仲間であって、同僚、上司部下、そして家族、いろんな仲間との関係をよく見て、大切にすることが、自分自身をミセンからワンセンへ繋いで行く、唯一の道なのかもしれないそんなことを思いましたミセンだからこそ、大変なことだらけになるけど、仲間とともに、泣けるし、笑えるし、感動できる人生は永遠にミセン・ノベーションそんな風に思うことがとても大切な気がしましたそんな話をしています参考:ミュージカル ミセン 主催・企画制作 ホリプロ 原作著者 ユン・テホ 脚本・歌詞 パク・ヘリム 音楽 チェ・ジョンユン 出演 前田公輝橋本じゅん 清水くるみ 他 https://horipro-stage.jp/stage/misaeng2025/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/jwLw7ynhWR02025-02-1124 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"人生は永遠にミセン・ノベーション(1394回)韓国で社会現象まで引き起こしたと言われる韓国ドラマの"ミセン"のミュージカル舞台にめちゃくちゃ号泣したとともに、脚本・歌詞 担当のパク・ヘリムさんの言葉に感動しました。曰く"幼い頃から囲碁が人生のすべてたったチャン・グレは、ジャングルのような現実世界に放り込まれる。囲碁の世界とはまた違う、生存がかかった「ワン・インターナショナル」という場所で、生き残るために努力しながら彼は自らの過去からすこしずつ抜け出していく。囲碁棋士だった頃は、自分と相手だけの世界たったけれど、石そのものとなった今は彼のそばで協力できるほかの石たちが見えるようになる。彼はまた過去を無駄な時間だったと背を向けることはしません。チャン・グレは過去の時間を振り返りながら、今の現実にも過去の経験を生かし、自分だけの盤を作り上げていきます。そうして、彼は自分の人生における「勝利」とはなにかを再び考え、「ワンセン(完生)」へと足を踏み出していくのです。"ここから私は思いました1、ミセン(未生)2、碁石3、仲間このドラマは本当に大好きで何回も見てるのですが、このミュージカル版は、それにも増して、曲も舞台装置も、キャストの皆さんも、全て最高すぎて、しばらく放心していました。自分のサラリーマン新人時代に、本当に何もできない自分が悔しくて泣いたり、毎日寝ないために強壮剤や夜食やおやつで、めちゃくちゃ太ってしまったり、リアルに思い出しましたその頃は本当に右も左もわからず、まさに未完成なミセン(未生)どころか、赤ん坊状態でしたが、その頃の新鮮な気持ちや、簡単なことでも成し遂げた時の嬉しい気持ちは、大切だったなあと思います新しいことへ挑戦するときは、このミセン(未生)にまた戻ることを怖いけれども、でもそこから成長パッションで成し遂げた時の快感を思い出しながら、常にミセンで居続ける選択をしたいなと思いましたまた、パクさんの話にもありますが、組織の中または人間の中で生きるということは、結局は碁盤の石になるということなんだと、改めて気付かされました組織の歯車になりたくない、みたいなことも思ったりする時期もありましたが、結局は、社会的動物である人間の中で生きるためには、碁盤の碁石の一つであることを認識する必要があるし、それでもその碁石がないと成り立たない社会もある、そんな風に改めて思いましたさらには、碁石であるためには、一番大切なものは仲間であって、同僚、上司部下、そして家族、いろんな仲間との関係をよく見て、大切にすることが、自分自身をミセンからワンセンへ繋いで行く、唯一の道なのかもしれないそんなことを思いましたミセンだからこそ、大変なことだらけになるけど、仲間とともに、泣けるし、笑えるし、感動できる人生は永遠にミセン・ノベーションそんな風に思うことがとても大切な気がしましたそんな話をしています参考:ミュージカル ミセン 主催・企画制作 ホリプロ 原作著者 ユン・テホ 脚本・歌詞 パク・ヘリム 音楽 チェ・ジョンユン 出演 前田公輝橋本じゅん 清水くるみ 他 https://horipro-stage.jp/stage/misaeng2025/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/jwLw7ynhWR02025-02-1124 min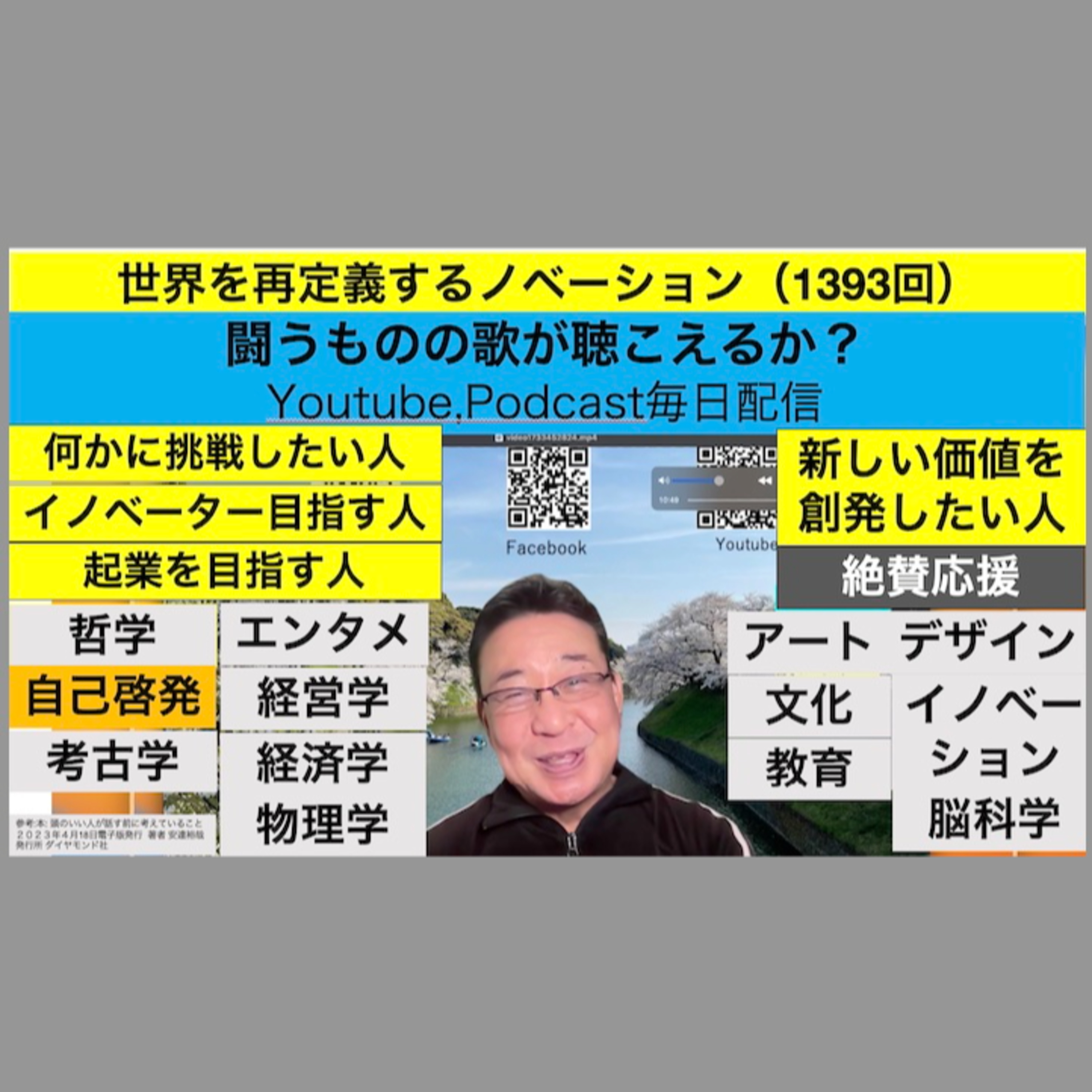 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"世界を再定義するノベーション(1393回)ティネクト株式会社 代表取締役の安達裕哉(あだち・ゆうや)さんの言葉に感動しました。曰く"良質なアウトプットは人を動かします。その良質なアウトプットに必要なのが言語化でした。 では言語化にコツはあるのでしょうか。""〇〇ではなく、△△である。 という型は、再定義によって生まれるアウトプットの形なのです。""良質なアウトプットをひもといていくと、再定義にたどり着くことがよくあります。 "ここから私は思いました1、そもそもシンキング(ラテラル)2、ブレイクザバイアス(トレードオフ)3、ゆるキャラ by みうらじゅんさん安達さんのお話は、ある意味、コンサルタントのノウハウを一般の皆様にもわかりやすく伝えてるように感じまして、めちゃくちゃ勉強になりました特に、この再定義の話は、イノベーションを創発する際にとても大事なノウハウだと思いました。起業をしたいとか、何かイノベーションやらなきゃ、だけど何しならいいんだろう?という人には、めちゃくちゃ役にたつノウハウと思いましたこの再定義というイノベーションの種を創発するには、一つは、そもそもシンキング、つまり、ラテラルシンキングが威力を発揮する気がしましたいつもの会議の中では嫌われる言葉ですが、そもそもの論点が違うんじゃないか、そもそも定義が違うんじゃないか、そういう言葉を意識的使うことによって、普通に思われている常識に、問いを立てることができるので、とても大切な気がしましたまた、普段自分たちが思ってることには、何らかのバイアスがあって、そのベールに包まれているから、本質が見えなくなってるのではないかという考えで、バイアスを壊すアクティビティも、とても大事かと思いました一例としては、トレードオフとなってる課題を突き詰めるやり方があるかと思います。こちらを立てればあちらが立たず的な課題を突き止めて、そして、それが一体何でトレードオフを解消できないかをかんがえてみる。それをブレイクできたら、新しい再定義ができるかもしれない、そんなことも思いましたそして、もう一つは、みうらじゅんさんの、ゆるキャラのお話で、これまでは、地方のよくわからないぬいぐるみだったものが、それが逆に面白い、ということで、ゆるキャラ、を創発されたことは、まさに再定義の最たるものかと思いましたこの"〇〇ではなく、△△である。 "を創発することが、イノベーションの種につながることになるので普段の生活の中で、そもそもシンキング、トレードオフの発見、逆に面白がる、そんなことで、再定義をしてみるともしかすると、びっくりするようなイノベーションが生まれるかもしれないそんなことを思いました^ ^参考:本: 頭のいい人が話す前に考えていること 2023年4月18日電子版発行 著者 安達裕哉 発行所 ダイヤモンド社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/OmB4ZEbmHY02025-02-1019 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"世界を再定義するノベーション(1393回)ティネクト株式会社 代表取締役の安達裕哉(あだち・ゆうや)さんの言葉に感動しました。曰く"良質なアウトプットは人を動かします。その良質なアウトプットに必要なのが言語化でした。 では言語化にコツはあるのでしょうか。""〇〇ではなく、△△である。 という型は、再定義によって生まれるアウトプットの形なのです。""良質なアウトプットをひもといていくと、再定義にたどり着くことがよくあります。 "ここから私は思いました1、そもそもシンキング(ラテラル)2、ブレイクザバイアス(トレードオフ)3、ゆるキャラ by みうらじゅんさん安達さんのお話は、ある意味、コンサルタントのノウハウを一般の皆様にもわかりやすく伝えてるように感じまして、めちゃくちゃ勉強になりました特に、この再定義の話は、イノベーションを創発する際にとても大事なノウハウだと思いました。起業をしたいとか、何かイノベーションやらなきゃ、だけど何しならいいんだろう?という人には、めちゃくちゃ役にたつノウハウと思いましたこの再定義というイノベーションの種を創発するには、一つは、そもそもシンキング、つまり、ラテラルシンキングが威力を発揮する気がしましたいつもの会議の中では嫌われる言葉ですが、そもそもの論点が違うんじゃないか、そもそも定義が違うんじゃないか、そういう言葉を意識的使うことによって、普通に思われている常識に、問いを立てることができるので、とても大切な気がしましたまた、普段自分たちが思ってることには、何らかのバイアスがあって、そのベールに包まれているから、本質が見えなくなってるのではないかという考えで、バイアスを壊すアクティビティも、とても大事かと思いました一例としては、トレードオフとなってる課題を突き詰めるやり方があるかと思います。こちらを立てればあちらが立たず的な課題を突き止めて、そして、それが一体何でトレードオフを解消できないかをかんがえてみる。それをブレイクできたら、新しい再定義ができるかもしれない、そんなことも思いましたそして、もう一つは、みうらじゅんさんの、ゆるキャラのお話で、これまでは、地方のよくわからないぬいぐるみだったものが、それが逆に面白い、ということで、ゆるキャラ、を創発されたことは、まさに再定義の最たるものかと思いましたこの"〇〇ではなく、△△である。 "を創発することが、イノベーションの種につながることになるので普段の生活の中で、そもそもシンキング、トレードオフの発見、逆に面白がる、そんなことで、再定義をしてみるともしかすると、びっくりするようなイノベーションが生まれるかもしれないそんなことを思いました^ ^参考:本: 頭のいい人が話す前に考えていること 2023年4月18日電子版発行 著者 安達裕哉 発行所 ダイヤモンド社動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/OmB4ZEbmHY02025-02-1019 min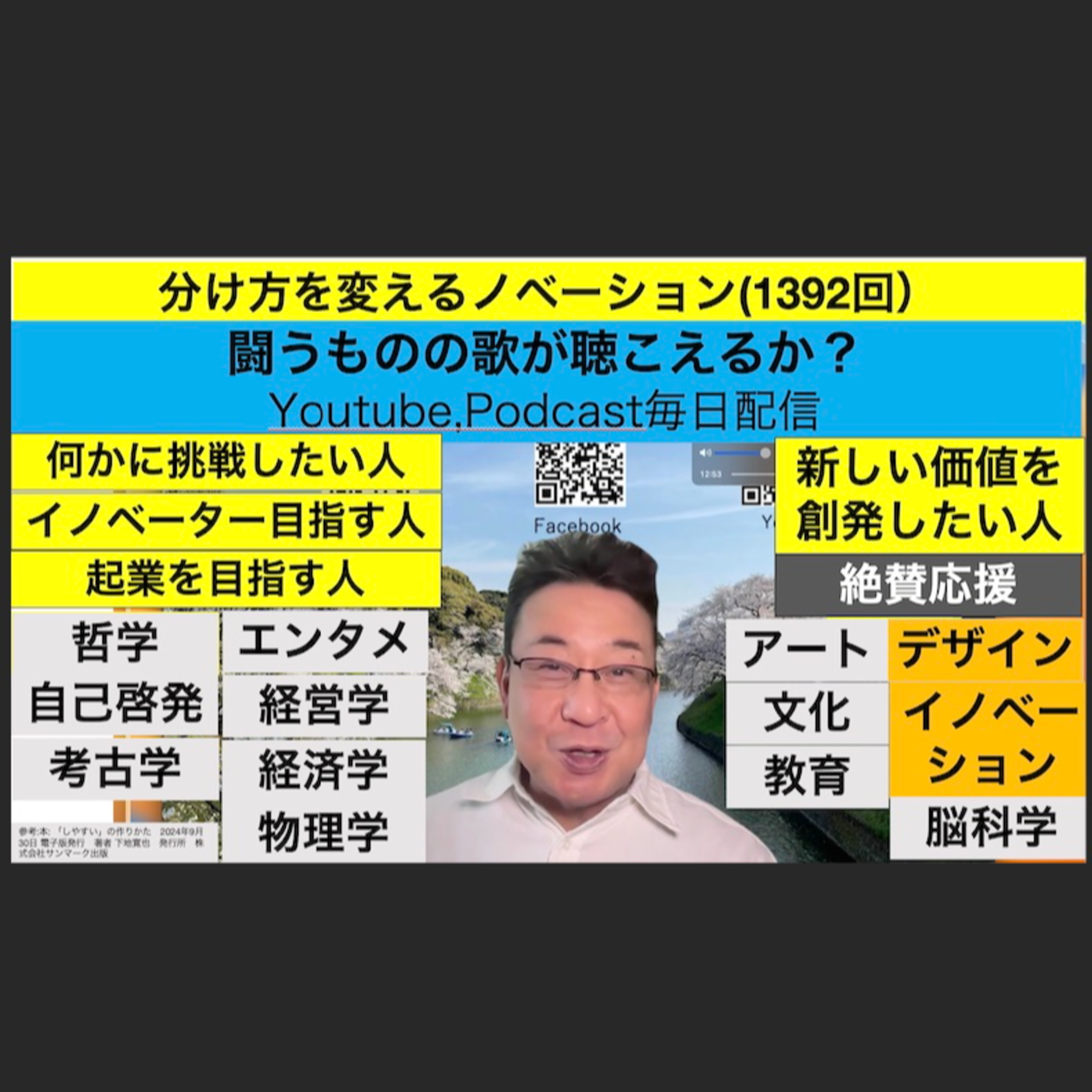 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"分け方を変えるノベーション(1392回)コクヨ株式会社ワークスタイルコンサルタント、エスケイブレイン代表の下地寛也(しもじ・かんや)さんの言葉に、イノベーションとしての新たな解決法を教えて頂きました曰く"では、できる人は、一体どうやって「しにくい」を「しやすい」に変えているのだろうか? もう、おわかりだろう。「しやすい」は、たったひとつの技術を身につけることで実現できる。それが上手に「分ける」技術だ。""分けるときにもっとも大切なことは、 「目的と分け方が合っているか」""ただし、「あえて分けない」ことでうまくいく場合もある。""できる人はつねに現状の分け方に疑問を持っている。"ここから私は思いました1、分かるとは、分けること by林修さん2、分け方への違和感がイノベーションの種3、新たな分け方は解決手法の一つしにくい、を、しやすい、に、変えるためには、上手に分けること、というのは、めちゃくちゃシンプルだけども、強力なソリューションだなあと衝撃を受けましたここで思い出したのは、林修先生が以前TVで、言われていた、分かるとは分けることである、というお話です(「分かる」ことは「分ける」ことノベーション(1139回)https://youtu.be/ypxZyVUAP8M)これは、ある意味、理解しにくいを、理解しやすい、に変えるために、分かることと、分からないことを、分けることである、と言い換えることもできるので、普遍的な法則なのかもしれないと思いましたし、そう考えると、普段、違和感を感じたら、それをメモることによって、イノベーションの種が溜まっていく、というお話をしていますがまさに、しにくいこと、を普段から拾っていくことこそ、イノベーションの種を見つける、とても身近で誰でもできる、良い方法かと思いましたそして、それが溜まったところで、どう解決してやろうか、となるわけですが、解決策としてまず出てくるのが、シュンペーター先生の掛け合わせで新しい価値を創るということかと思いますしその他にも、対立する二軸から第三の道を創発するヘーゲルのアウフヘーベン、大阪大学の松村教授の提唱される、ついしたくなる仕掛けを組み込む、仕掛け学など、いろいろありますが今回教えて頂いた下地さんの、分け方を変える、ということも、物凄い威力を持った解決方法の一つだなあと、めちゃくちゃ勉強になりましたしにくい、という違和感は、イノベーションの種となり、そして、分け方を変える、という解決策の試行錯誤で、イノベーションを生み出す分け方を変えるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 「しやすい」の作りかた 2024年9月30日 電子版発行 著者 下地寛也 発行所 株式会社サンマーク出版動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/G1_mQ8tw75o2025-02-0918 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"分け方を変えるノベーション(1392回)コクヨ株式会社ワークスタイルコンサルタント、エスケイブレイン代表の下地寛也(しもじ・かんや)さんの言葉に、イノベーションとしての新たな解決法を教えて頂きました曰く"では、できる人は、一体どうやって「しにくい」を「しやすい」に変えているのだろうか? もう、おわかりだろう。「しやすい」は、たったひとつの技術を身につけることで実現できる。それが上手に「分ける」技術だ。""分けるときにもっとも大切なことは、 「目的と分け方が合っているか」""ただし、「あえて分けない」ことでうまくいく場合もある。""できる人はつねに現状の分け方に疑問を持っている。"ここから私は思いました1、分かるとは、分けること by林修さん2、分け方への違和感がイノベーションの種3、新たな分け方は解決手法の一つしにくい、を、しやすい、に、変えるためには、上手に分けること、というのは、めちゃくちゃシンプルだけども、強力なソリューションだなあと衝撃を受けましたここで思い出したのは、林修先生が以前TVで、言われていた、分かるとは分けることである、というお話です(「分かる」ことは「分ける」ことノベーション(1139回)https://youtu.be/ypxZyVUAP8M)これは、ある意味、理解しにくいを、理解しやすい、に変えるために、分かることと、分からないことを、分けることである、と言い換えることもできるので、普遍的な法則なのかもしれないと思いましたし、そう考えると、普段、違和感を感じたら、それをメモることによって、イノベーションの種が溜まっていく、というお話をしていますがまさに、しにくいこと、を普段から拾っていくことこそ、イノベーションの種を見つける、とても身近で誰でもできる、良い方法かと思いましたそして、それが溜まったところで、どう解決してやろうか、となるわけですが、解決策としてまず出てくるのが、シュンペーター先生の掛け合わせで新しい価値を創るということかと思いますしその他にも、対立する二軸から第三の道を創発するヘーゲルのアウフヘーベン、大阪大学の松村教授の提唱される、ついしたくなる仕掛けを組み込む、仕掛け学など、いろいろありますが今回教えて頂いた下地さんの、分け方を変える、ということも、物凄い威力を持った解決方法の一つだなあと、めちゃくちゃ勉強になりましたしにくい、という違和感は、イノベーションの種となり、そして、分け方を変える、という解決策の試行錯誤で、イノベーションを生み出す分け方を変えるノベーションそんなことを思いました^ ^参考:本: 「しやすい」の作りかた 2024年9月30日 電子版発行 著者 下地寛也 発行所 株式会社サンマーク出版動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/G1_mQ8tw75o2025-02-0918 min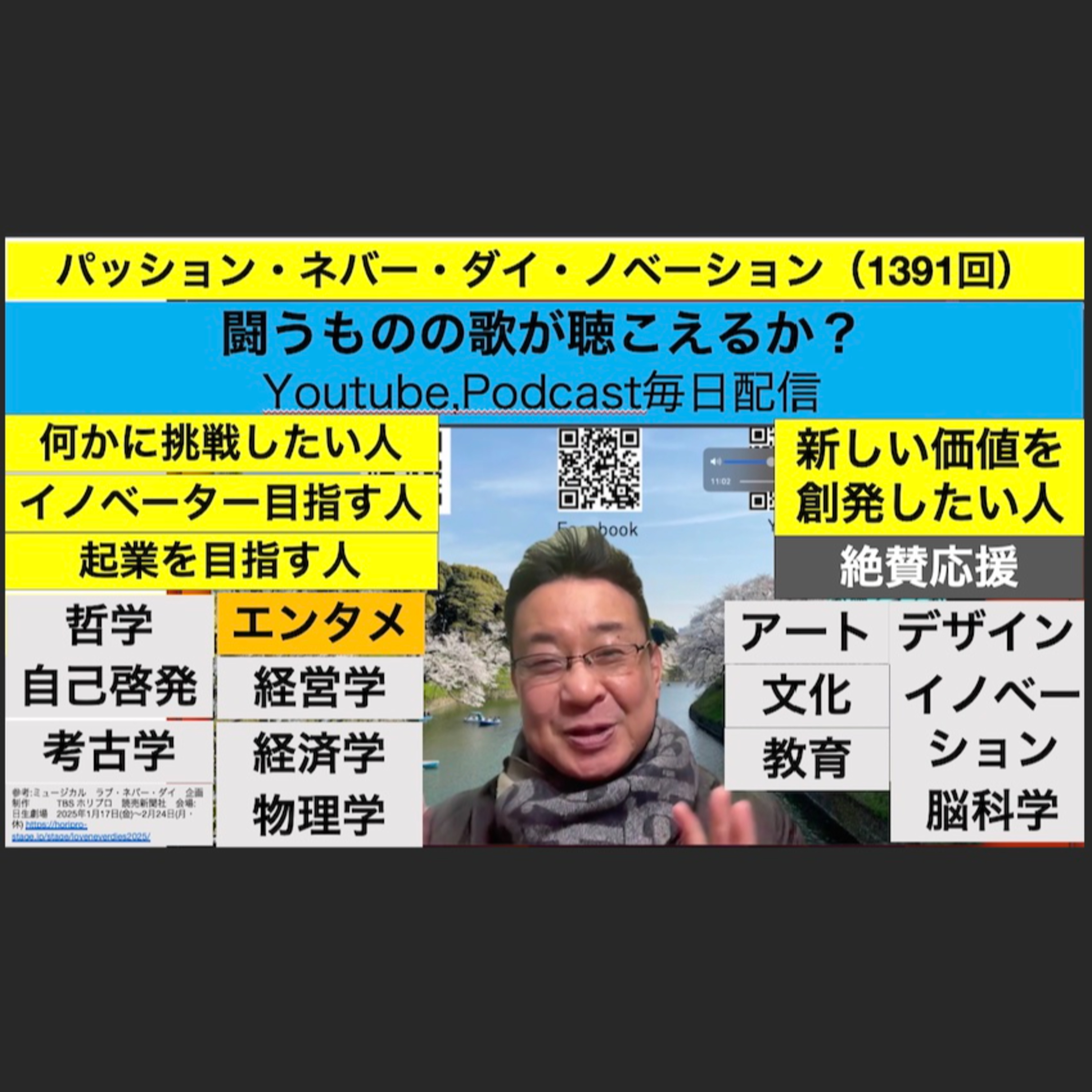 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"パッション・ネバー・ダイ・ノベーション(1391回)ミュージカル ラブ・ネバー・ダイの凄まじさと、主役の平原綾香さんの言葉に、めちゃくちゃ感動しました曰く"オペラ歌唱が初めてだったので、YouTubeを使ってオペラ発声を研究しました。役がソプラノ歌手の設定である以上、オペラ的な発声が求められますが、もともとはミュージカル出身だったサラ・ブライトマンさん(「オペラ座の怪人』オリジナルキャスト)が見事なアリアを歌ったことで、この役に広がりを持たせたのではと。だってオペラ歌手ではない私がこの役を演じるチャンスをもらえたのですから!"ここから私は思いました1、自分を超えるオファーを受ける2、コンフォートゾーンを抜け出す3、掛け合わせで新たな価値を創る傑作ミュージカルの一つ、オペラ座の怪人の続編として、アンドリュー・ロイド・ウェーバーが書き下ろした、ラブ・ネバー・ダイですが、楽曲の素晴らさ、美術や衣装の妖しさ、煌びやかさ、そして役者の皆様のパッションが炸裂していて、大感動させて頂きましたもちろん主役の市村正親さんが素晴らしかったのですが、もう一人の主役の平原綾香さんが、なんとオペラ歌手の役をされながらオペラを歌唱されたのが、素晴らしすぎて腰を抜かしました会場からはブラボーの声が飛びまくりで、ここはオペラ座か?と思うほどでした。行ったことないですけど平原さんのインタビューを見て思ったのは、まずは、自分がやったことがないオファーを受けられるか、ということです。ジョハリの窓ではないですが、自分が自分を思ってることと、他人が自分を思ってることは違いがあるので、思い切ってそれに乗っちゃう勇気があるか、または、哲学者の三木清さんの失敗を彩りの一つと捉えられるか、というところに成長の鍵がある気がしましたそしてそれを乗り越え先に本当の勝負が始まるわけですが、ここからが、超一流になるのは才能か努力か、でも言われる通り、1最高の先生、2コンフォートゾーンを抜け出す、3自分に自信を持つ、がポイントになり平原さんが、Youtubeを見て、まさにオペラ歌唱を学ばれたのは、1最高の先生に、2コンフォートゾーンを抜け出す、練習をされて、3自分に自信を持たれたのだろうなあと胸が熱くなりますある意味、引き受けたからには、石に齧りついてでも、やり切るという気持ちを持って、実際にやり切れるかというところも、たとえうまくいかなかったとしても、最後までやり切ったか、ということが、次につながる気がしましたそして、それぞれを乗り切った先に、きっとこれまでの自分と、そして新しい自分が出会えるのだろうなあとその新しい自分は、既存の価値と新しい価値がかけ合わさった新しい価値が生まれてるはずだと、シンガーソングライターの平原さんに、オペラ歌唱が掛け合わさって、とてつもなく魅力的になられたことのようにそんな風に思いましたそして、何度も言いますが、今回のラブネバーダイの曲も素晴らしく、そして今回観させて頂いた主要キャストの、市村正親さん、加藤和樹さん、小南満佑子さん、春野寿美礼さん、が本当に素晴らしく、美術も装飾も素晴らしく感動させて頂きました創られる、演出される、演技される皆さんのパッションが一体になって出来たのかなと思いましたラブネバーダイからの皆様のパッション・ネバー・ダイ・ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:ミュージカル ラブ・ネバー・ダイ 企画制作 TBS ホリプロ 読売新聞社 会場:日生劇場 2025年1月17日(金)~2月24日(月・休)https://horipro-stage.jp/stage/loveneverdies2025/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/YBal8PY6H7w2025-02-0814 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"パッション・ネバー・ダイ・ノベーション(1391回)ミュージカル ラブ・ネバー・ダイの凄まじさと、主役の平原綾香さんの言葉に、めちゃくちゃ感動しました曰く"オペラ歌唱が初めてだったので、YouTubeを使ってオペラ発声を研究しました。役がソプラノ歌手の設定である以上、オペラ的な発声が求められますが、もともとはミュージカル出身だったサラ・ブライトマンさん(「オペラ座の怪人』オリジナルキャスト)が見事なアリアを歌ったことで、この役に広がりを持たせたのではと。だってオペラ歌手ではない私がこの役を演じるチャンスをもらえたのですから!"ここから私は思いました1、自分を超えるオファーを受ける2、コンフォートゾーンを抜け出す3、掛け合わせで新たな価値を創る傑作ミュージカルの一つ、オペラ座の怪人の続編として、アンドリュー・ロイド・ウェーバーが書き下ろした、ラブ・ネバー・ダイですが、楽曲の素晴らさ、美術や衣装の妖しさ、煌びやかさ、そして役者の皆様のパッションが炸裂していて、大感動させて頂きましたもちろん主役の市村正親さんが素晴らしかったのですが、もう一人の主役の平原綾香さんが、なんとオペラ歌手の役をされながらオペラを歌唱されたのが、素晴らしすぎて腰を抜かしました会場からはブラボーの声が飛びまくりで、ここはオペラ座か?と思うほどでした。行ったことないですけど平原さんのインタビューを見て思ったのは、まずは、自分がやったことがないオファーを受けられるか、ということです。ジョハリの窓ではないですが、自分が自分を思ってることと、他人が自分を思ってることは違いがあるので、思い切ってそれに乗っちゃう勇気があるか、または、哲学者の三木清さんの失敗を彩りの一つと捉えられるか、というところに成長の鍵がある気がしましたそしてそれを乗り越え先に本当の勝負が始まるわけですが、ここからが、超一流になるのは才能か努力か、でも言われる通り、1最高の先生、2コンフォートゾーンを抜け出す、3自分に自信を持つ、がポイントになり平原さんが、Youtubeを見て、まさにオペラ歌唱を学ばれたのは、1最高の先生に、2コンフォートゾーンを抜け出す、練習をされて、3自分に自信を持たれたのだろうなあと胸が熱くなりますある意味、引き受けたからには、石に齧りついてでも、やり切るという気持ちを持って、実際にやり切れるかというところも、たとえうまくいかなかったとしても、最後までやり切ったか、ということが、次につながる気がしましたそして、それぞれを乗り切った先に、きっとこれまでの自分と、そして新しい自分が出会えるのだろうなあとその新しい自分は、既存の価値と新しい価値がかけ合わさった新しい価値が生まれてるはずだと、シンガーソングライターの平原さんに、オペラ歌唱が掛け合わさって、とてつもなく魅力的になられたことのようにそんな風に思いましたそして、何度も言いますが、今回のラブネバーダイの曲も素晴らしく、そして今回観させて頂いた主要キャストの、市村正親さん、加藤和樹さん、小南満佑子さん、春野寿美礼さん、が本当に素晴らしく、美術も装飾も素晴らしく感動させて頂きました創られる、演出される、演技される皆さんのパッションが一体になって出来たのかなと思いましたラブネバーダイからの皆様のパッション・ネバー・ダイ・ノベーションそんなことを思いました^ ^参考:ミュージカル ラブ・ネバー・ダイ 企画制作 TBS ホリプロ 読売新聞社 会場:日生劇場 2025年1月17日(金)~2月24日(月・休)https://horipro-stage.jp/stage/loveneverdies2025/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/YBal8PY6H7w2025-02-0814 min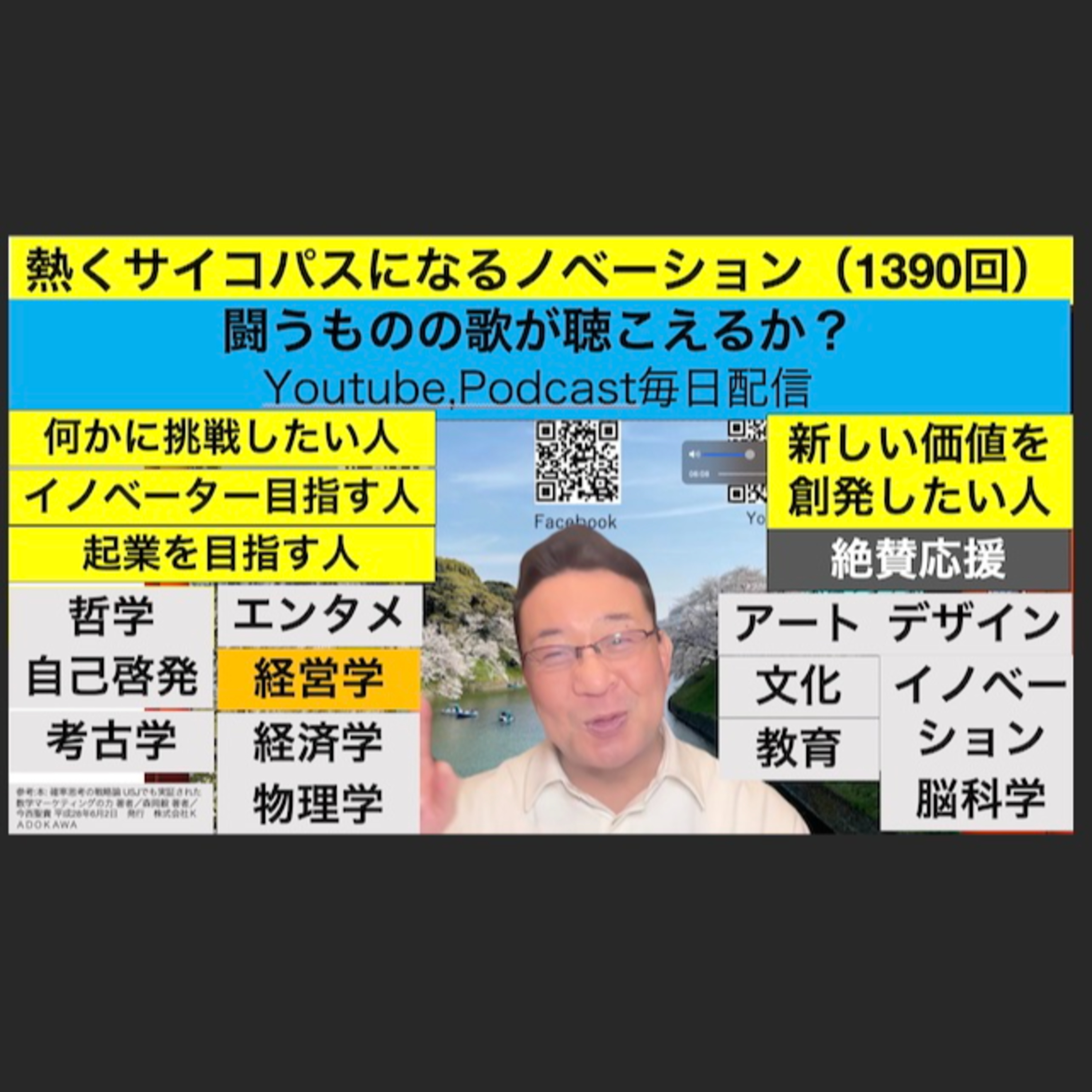 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"熱くサイコパスになるノベーション(1390回)マーケターで有名な株式会社刀代表取締役兼CEO森岡毅さんの強さと熱さの秘密を教えて頂き、感動しました
曰く
"ではサイコパスとは何なのか? 要約すると、研究者はこのような意味のことを言っていました。サイコパス性とは、感情的葛藤や人間関係のしがらみなどに迷うことなく、目的に対して純粋に正しい行動を取れる性質のことだと。"
"辛いけれども正しい意志決定(タフコール)を行わなければならないとき、感情は多くの場合において邪魔にしかなりません。だから感情が正しい意志決定の邪魔にならないサイコパスは、意志決定の局面で有利です。"
"しかし意識と訓練の積み重ね次第で、冷徹な意志決定ができるようになると私は実感しています。"
"意志決定そのものに「熱」は要りません、むしろ「熱」は邪魔になります。極めて冷徹に、目的に対して純粋に確率が高いものを選ぶだけです。
熱量が要るのはその後、決定した方向に人を説得したり、戦術を実施したりする次の段階です。"
ここから私は思いました
1、分人 by 平野啓一郎さん
2、大義からのサイコパス
3、サイコパスからの熱いパッション
サイコパスというと、映画の"羊たちの沈黙"に出てくる主人公のような、怖い人のイメージが先立ちましたが、実は、そればかりではなく、目的に純粋に冷静に行動できる人で
かつ、そのような人は、経営者や意思決定者に多いく、訓練次第で誰でもがなれるということに、衝撃と勇気を頂きました
まず私が思ったのは、平野啓一郎さんの"分人"の考え方です。例えば企業の経営のような、たくさんの人を抱えている経営者において、厳しい決断をしなくてはならない時は、必ずくると思います
その時に、この話を思い出して、サイコパス的に決断をするためには、ある意味、新しい分人を自分の中に創り出して、俳優のように演じることも必要となるかもなあと
全ての人格を変えることではなく、役割としてその分人をやるのであると考えることが、自分自身を保ちながら厳しい判断もする、そんな簡単にはいかないと思いますが、分人の考え方は大切かもしれないと思いました
また、そこにとても大切になるのが、サイコパスになるための、大義がある、その大義のために断行するのである、ということも、すごく大切な気がしました
あくまでも自分よがりのパッションというよりは、仲間を含めた上での、他の人たちのためにある大義のために、サイコパスのように冷静に決断する、そういうことなのかと思いました
そして、大義に基づいた決断の後に、自らのパッションを発動させ、熱く仲間を率いていく、そんな道筋を思い描いていくことがビジネスを率いていく人、またイノベーターにも、リーダー全般に必要なことかもしれない、そんなことを思いました
一言で言えば
熱いパッションと大義があらからこそ、仲間のためにサイコパスにもなる
熱いサイコパスノベーション
そんなことを思いました^ ^
参考:本: 確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力 著者/森岡毅 著者/今西聖貴 平成28年6月2日 発行 株式会社KADOKAWA
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/mm-zMhqRs2s2025-02-0719 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"熱くサイコパスになるノベーション(1390回)マーケターで有名な株式会社刀代表取締役兼CEO森岡毅さんの強さと熱さの秘密を教えて頂き、感動しました
曰く
"ではサイコパスとは何なのか? 要約すると、研究者はこのような意味のことを言っていました。サイコパス性とは、感情的葛藤や人間関係のしがらみなどに迷うことなく、目的に対して純粋に正しい行動を取れる性質のことだと。"
"辛いけれども正しい意志決定(タフコール)を行わなければならないとき、感情は多くの場合において邪魔にしかなりません。だから感情が正しい意志決定の邪魔にならないサイコパスは、意志決定の局面で有利です。"
"しかし意識と訓練の積み重ね次第で、冷徹な意志決定ができるようになると私は実感しています。"
"意志決定そのものに「熱」は要りません、むしろ「熱」は邪魔になります。極めて冷徹に、目的に対して純粋に確率が高いものを選ぶだけです。
熱量が要るのはその後、決定した方向に人を説得したり、戦術を実施したりする次の段階です。"
ここから私は思いました
1、分人 by 平野啓一郎さん
2、大義からのサイコパス
3、サイコパスからの熱いパッション
サイコパスというと、映画の"羊たちの沈黙"に出てくる主人公のような、怖い人のイメージが先立ちましたが、実は、そればかりではなく、目的に純粋に冷静に行動できる人で
かつ、そのような人は、経営者や意思決定者に多いく、訓練次第で誰でもがなれるということに、衝撃と勇気を頂きました
まず私が思ったのは、平野啓一郎さんの"分人"の考え方です。例えば企業の経営のような、たくさんの人を抱えている経営者において、厳しい決断をしなくてはならない時は、必ずくると思います
その時に、この話を思い出して、サイコパス的に決断をするためには、ある意味、新しい分人を自分の中に創り出して、俳優のように演じることも必要となるかもなあと
全ての人格を変えることではなく、役割としてその分人をやるのであると考えることが、自分自身を保ちながら厳しい判断もする、そんな簡単にはいかないと思いますが、分人の考え方は大切かもしれないと思いました
また、そこにとても大切になるのが、サイコパスになるための、大義がある、その大義のために断行するのである、ということも、すごく大切な気がしました
あくまでも自分よがりのパッションというよりは、仲間を含めた上での、他の人たちのためにある大義のために、サイコパスのように冷静に決断する、そういうことなのかと思いました
そして、大義に基づいた決断の後に、自らのパッションを発動させ、熱く仲間を率いていく、そんな道筋を思い描いていくことがビジネスを率いていく人、またイノベーターにも、リーダー全般に必要なことかもしれない、そんなことを思いました
一言で言えば
熱いパッションと大義があらからこそ、仲間のためにサイコパスにもなる
熱いサイコパスノベーション
そんなことを思いました^ ^
参考:本: 確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力 著者/森岡毅 著者/今西聖貴 平成28年6月2日 発行 株式会社KADOKAWA
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/mm-zMhqRs2s2025-02-0719 min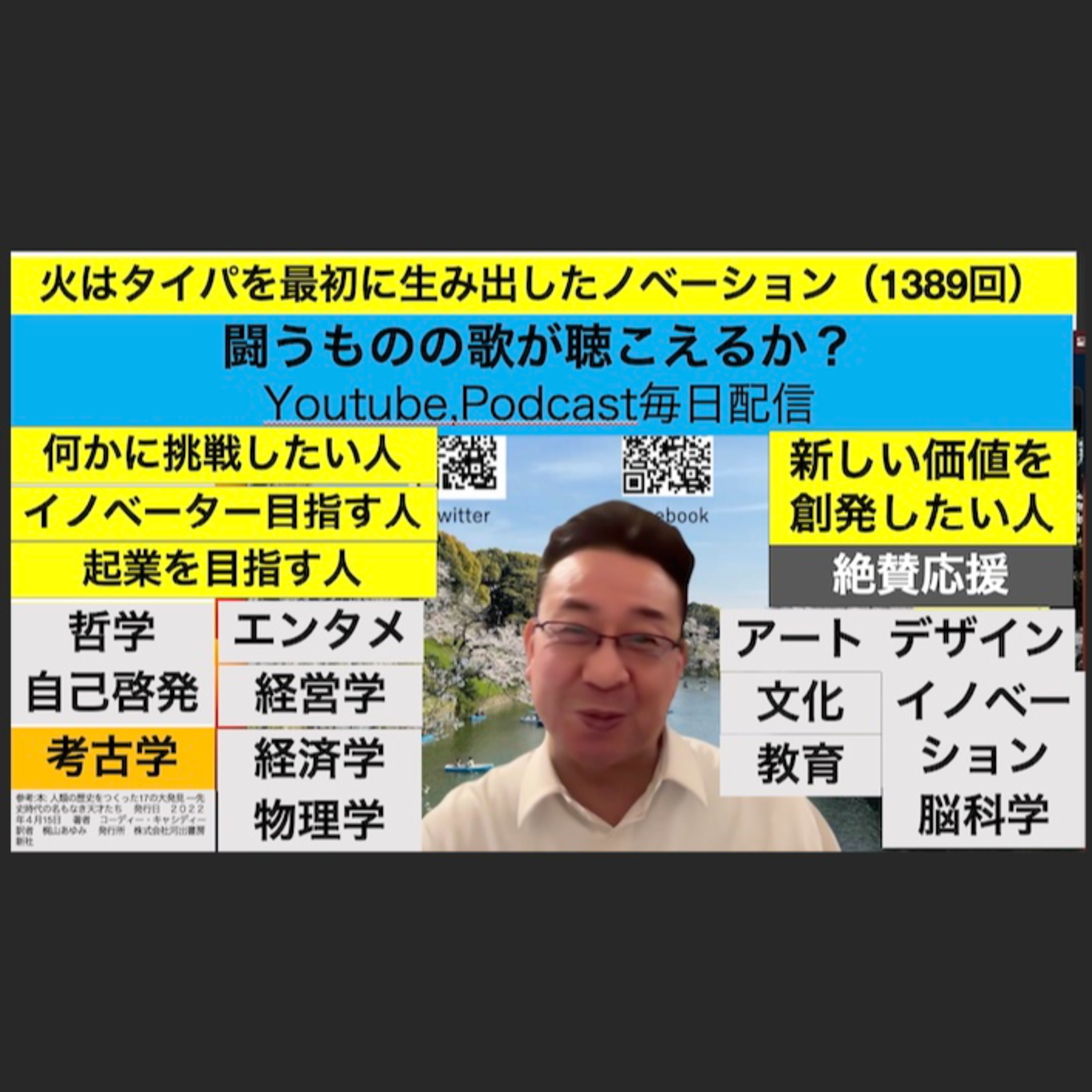 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"火はタイパを最初に生み出したノベーション(1389回)火を活用することは、人類最大の発明の一つかもしれないと、その威力と破壊力にに感動しました
''加熱の手間がある分、むしろ前より時間がかかったように思うかもしれないが、そうではない。食事を準備する時間そのものは増えるにせよ、生のままというエネルギー効率の悪い食物を嚙むのは、それとは比べ物にならないくらい長い時間を要する。"
"前章でも触れたように、チンパンジーが食事に費やす時間は現代人の六倍近くだ。そこまでの差が生じるのは、生の食物が硬いうえに、ひと嚙みで取りだせるカロリー量が少ないからでもある。"
"ホモ・エレクトスは現代のチンパンジーより体が大きかったため、アイエロとウィーラーの計算によれば、生食だったとしたら食事に一日八時間を充てなければ体重を維持できなかったはずだ。ホモ・エレクトスにとっては加熱のおかげで一日が長くなったようなものである。"
ここから私は、イノベーションの力について思いました
1、様々な課題を一気に解決する
2、意図せずとも行動で起きる
3、進化を強力に促進する
火を活用できるように味方につけたことは、人類における、大きなターニングポイントになったのだなと、改めて思いました
火の活用は、とてもたくさんのエネルギーを必要とする脳を支えられ、8時間必要だった食事の時間を圧倒的に短くし、そしてその短くなった食事時間を、狩りの時間に振り返ることで、一気に守りから攻撃のできる強さを身につけていった
それは、火を活用するというイノベーションが、一気に様々な課題を解決するのも出会った証拠なのかなと思いました
逆にいえば、イノベーションを起こそうとする場合には、さまざまな課題を一気に引き受けるスイートポイントは、どこなんだと言うことを
ラテラル、ロジカル、クリティカルシンキングを使いながら、突き止めることができたら、イノベーションの8割は達成できたようなものとも言えるかもしれないと思いました
また、火の活用というイノベーションは、その時代には、あたりまえですが、仮設思考はないわけで、とにかくなんかやってみるかみないか、それしかない中で
誰かが、火を活用して食物を食べてみた、そこから全てが始まり、ある意味、意図せずして、食べ物を摂る時間が短くなだ他のではないかと思います。
それはすなわち、仮説が見当たらないと、ウンウン唸ってるのであれば、まずは動いてみる、行動してみる、ということがいかに大切かということも教えてくれてる気がしました
そして、以前お話しした、人類最初の発明である、抱っこの紐のように、火を扱えるイノベーションを起こしたからこそ、人類は頭の大きさを確保し、そして、他の生物に淘汰されない力を得ることができた
すなわち、人類は火を活用できるようになったからこそ、進化することができた、促された、そういうことも言えるなあと思いました
つまり
火はタイパを最初に生み出したノベーション
そんなことを思いました^ ^
参考:本: 人類の歴史をつくった17の大発見 ─先史時代の名もなき天才たち 発行日 2022年4月15日 著者 コーディー・キャシディー 訳者 梶山あゆみ 発行所 株式会社河出書房新社
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/17N9Yn7dvjg2025-02-0617 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"火はタイパを最初に生み出したノベーション(1389回)火を活用することは、人類最大の発明の一つかもしれないと、その威力と破壊力にに感動しました
''加熱の手間がある分、むしろ前より時間がかかったように思うかもしれないが、そうではない。食事を準備する時間そのものは増えるにせよ、生のままというエネルギー効率の悪い食物を嚙むのは、それとは比べ物にならないくらい長い時間を要する。"
"前章でも触れたように、チンパンジーが食事に費やす時間は現代人の六倍近くだ。そこまでの差が生じるのは、生の食物が硬いうえに、ひと嚙みで取りだせるカロリー量が少ないからでもある。"
"ホモ・エレクトスは現代のチンパンジーより体が大きかったため、アイエロとウィーラーの計算によれば、生食だったとしたら食事に一日八時間を充てなければ体重を維持できなかったはずだ。ホモ・エレクトスにとっては加熱のおかげで一日が長くなったようなものである。"
ここから私は、イノベーションの力について思いました
1、様々な課題を一気に解決する
2、意図せずとも行動で起きる
3、進化を強力に促進する
火を活用できるように味方につけたことは、人類における、大きなターニングポイントになったのだなと、改めて思いました
火の活用は、とてもたくさんのエネルギーを必要とする脳を支えられ、8時間必要だった食事の時間を圧倒的に短くし、そしてその短くなった食事時間を、狩りの時間に振り返ることで、一気に守りから攻撃のできる強さを身につけていった
それは、火を活用するというイノベーションが、一気に様々な課題を解決するのも出会った証拠なのかなと思いました
逆にいえば、イノベーションを起こそうとする場合には、さまざまな課題を一気に引き受けるスイートポイントは、どこなんだと言うことを
ラテラル、ロジカル、クリティカルシンキングを使いながら、突き止めることができたら、イノベーションの8割は達成できたようなものとも言えるかもしれないと思いました
また、火の活用というイノベーションは、その時代には、あたりまえですが、仮設思考はないわけで、とにかくなんかやってみるかみないか、それしかない中で
誰かが、火を活用して食物を食べてみた、そこから全てが始まり、ある意味、意図せずして、食べ物を摂る時間が短くなだ他のではないかと思います。
それはすなわち、仮説が見当たらないと、ウンウン唸ってるのであれば、まずは動いてみる、行動してみる、ということがいかに大切かということも教えてくれてる気がしました
そして、以前お話しした、人類最初の発明である、抱っこの紐のように、火を扱えるイノベーションを起こしたからこそ、人類は頭の大きさを確保し、そして、他の生物に淘汰されない力を得ることができた
すなわち、人類は火を活用できるようになったからこそ、進化することができた、促された、そういうことも言えるなあと思いました
つまり
火はタイパを最初に生み出したノベーション
そんなことを思いました^ ^
参考:本: 人類の歴史をつくった17の大発見 ─先史時代の名もなき天才たち 発行日 2022年4月15日 著者 コーディー・キャシディー 訳者 梶山あゆみ 発行所 株式会社河出書房新社
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/17N9Yn7dvjg2025-02-0617 min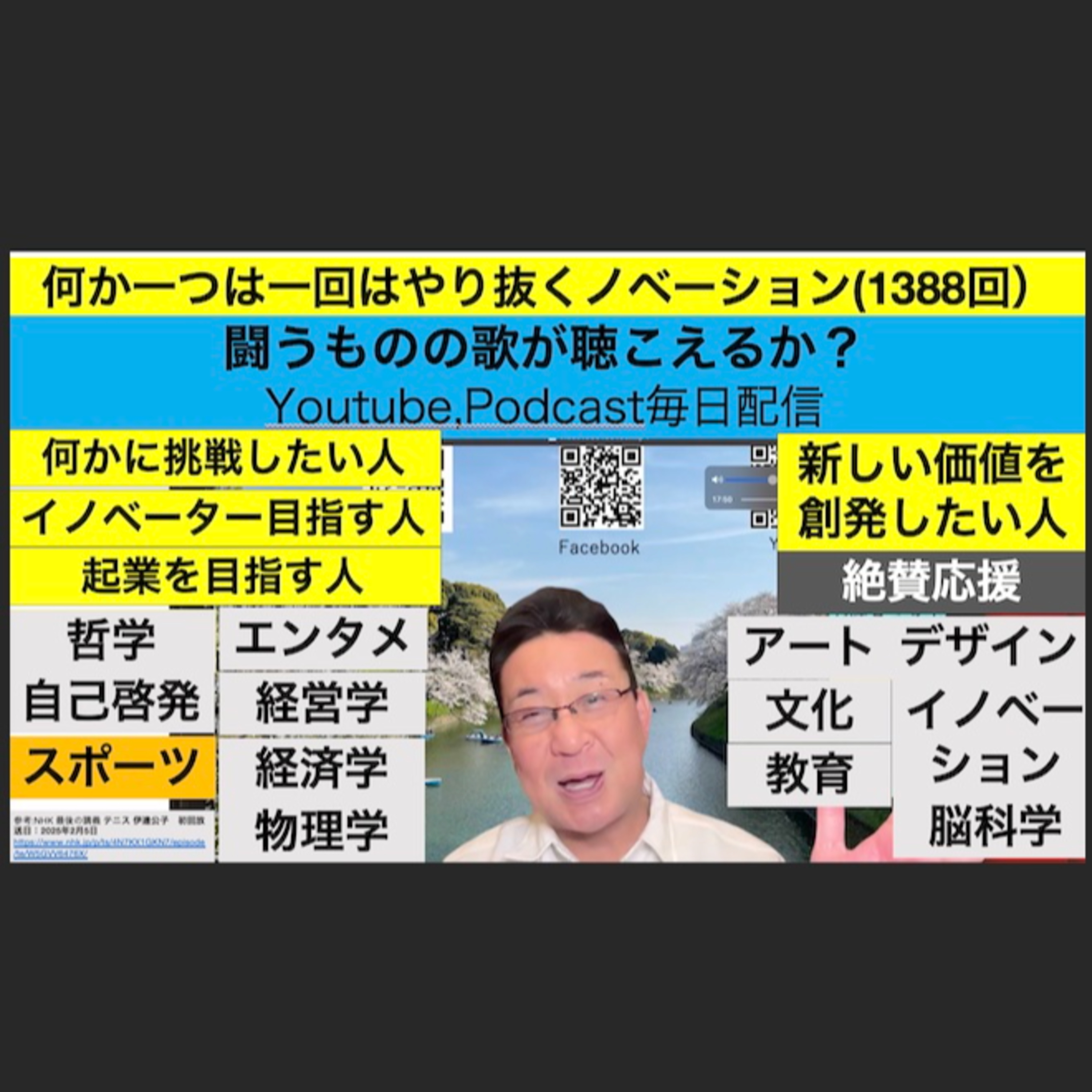 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"何か一つは一回はやり抜くノベーション(1388回)世界に挑むアスリートの先駆者であったテニスプレイヤーの伊達公子さんの言葉に、人生で大切なことを教えて頂きました
曰く
"人生として捉えたときに、本当に満たされるために、自分が、何か一つはやり抜くことが、絶対に幸せには感じられると思うので
世の中的に目に見える成功じゃなくても、あたしは、突き抜けていくことの方が、絶対に自分の人生にとってプラスになると
その突き抜けたエネルギーってものは、その先にもし何かをやったときに、大成功する、やっばり自分のおっきなエネルギーになったりすることに、変わったりすることが絶対生まれると思う
でもここで突き抜けなかったら、次に何かをやったときに、やっぱり突き抜けるってことをしなくなってしまうんじゃないか、って私は思ってしまう
だから、何か一つやりぬく、一回はやり抜くってことをやってほしいと思います"
ここから私は思いました
1、フローの経験
2、周りよりも情熱の源に沿う経験
3、結果よりもやり抜いた実感
ウィンブルドンで世界4位にもなって、まさに日本人でもスポーツで世界で活躍できるというワクワク感を持ちながら、テレビで応援してたことを思い出しました
伊達さんのお話から、チクセントミハイさんのフロー状態を思い出しました。挑戦軸と技能軸が、両方高まったときに、超集中する没頭する状態のフローに入ると言われてますが
一つやり抜くことで幸せな気持ちを感じるのは、まさにフロー状態まで突き詰められていたのかもしれないなと思いますし、その状態ではきっと、寝食忘れて取り組む状態なので、ある意味とても幸せな気持ちでいるのではないかとも思いました
また、フローまで行くためには、厳しい道のりを乗り越える前提でもあるので、少なくともやらされ感満載では、続かないだろうなとも思いました
それは、ある意味、情熱の源に沿った、自らが問いを立てていることに対して、取り組んでいるからこそ、何度も失敗しても続けていけるので
逆に言えば、それがたとえ、世の中の人から見て成功ではなくとも、自分の情熱の源に沿ってれば、きっと突き抜けるところまで到達できるのだろうなとも思いました
なので、結果としても、世間的な成功でないとしても、自らの情熱に従ったという満足感があれば、そしてやり切ったという感覚を持てるのであれば、それは幸せにかんじる、そんなことかと思いました
私の支援するWGでも、最後の最後まで粘り切ってやり切ったチームのメンバーの顔は、本当に光り輝いてますし、その経験は、成功か失敗かに関わらず、これからの人生に必ず生きる!そう思ってます
一言で言うと、
何か一つは一回はやり抜くノベーション
そんなことを思いました^ ^
参考:NHK 最後の講義 テニス 伊達公子 初回放送日:2025年2月5日 https://www.nhk.jp/p/ts/4N7KX1GKN7/episode/te/W5GVV6476X/
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/fli--F7SUWc2025-02-0521 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"何か一つは一回はやり抜くノベーション(1388回)世界に挑むアスリートの先駆者であったテニスプレイヤーの伊達公子さんの言葉に、人生で大切なことを教えて頂きました
曰く
"人生として捉えたときに、本当に満たされるために、自分が、何か一つはやり抜くことが、絶対に幸せには感じられると思うので
世の中的に目に見える成功じゃなくても、あたしは、突き抜けていくことの方が、絶対に自分の人生にとってプラスになると
その突き抜けたエネルギーってものは、その先にもし何かをやったときに、大成功する、やっばり自分のおっきなエネルギーになったりすることに、変わったりすることが絶対生まれると思う
でもここで突き抜けなかったら、次に何かをやったときに、やっぱり突き抜けるってことをしなくなってしまうんじゃないか、って私は思ってしまう
だから、何か一つやりぬく、一回はやり抜くってことをやってほしいと思います"
ここから私は思いました
1、フローの経験
2、周りよりも情熱の源に沿う経験
3、結果よりもやり抜いた実感
ウィンブルドンで世界4位にもなって、まさに日本人でもスポーツで世界で活躍できるというワクワク感を持ちながら、テレビで応援してたことを思い出しました
伊達さんのお話から、チクセントミハイさんのフロー状態を思い出しました。挑戦軸と技能軸が、両方高まったときに、超集中する没頭する状態のフローに入ると言われてますが
一つやり抜くことで幸せな気持ちを感じるのは、まさにフロー状態まで突き詰められていたのかもしれないなと思いますし、その状態ではきっと、寝食忘れて取り組む状態なので、ある意味とても幸せな気持ちでいるのではないかとも思いました
また、フローまで行くためには、厳しい道のりを乗り越える前提でもあるので、少なくともやらされ感満載では、続かないだろうなとも思いました
それは、ある意味、情熱の源に沿った、自らが問いを立てていることに対して、取り組んでいるからこそ、何度も失敗しても続けていけるので
逆に言えば、それがたとえ、世の中の人から見て成功ではなくとも、自分の情熱の源に沿ってれば、きっと突き抜けるところまで到達できるのだろうなとも思いました
なので、結果としても、世間的な成功でないとしても、自らの情熱に従ったという満足感があれば、そしてやり切ったという感覚を持てるのであれば、それは幸せにかんじる、そんなことかと思いました
私の支援するWGでも、最後の最後まで粘り切ってやり切ったチームのメンバーの顔は、本当に光り輝いてますし、その経験は、成功か失敗かに関わらず、これからの人生に必ず生きる!そう思ってます
一言で言うと、
何か一つは一回はやり抜くノベーション
そんなことを思いました^ ^
参考:NHK 最後の講義 テニス 伊達公子 初回放送日:2025年2月5日 https://www.nhk.jp/p/ts/4N7KX1GKN7/episode/te/W5GVV6476X/
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/fli--F7SUWc2025-02-0521 min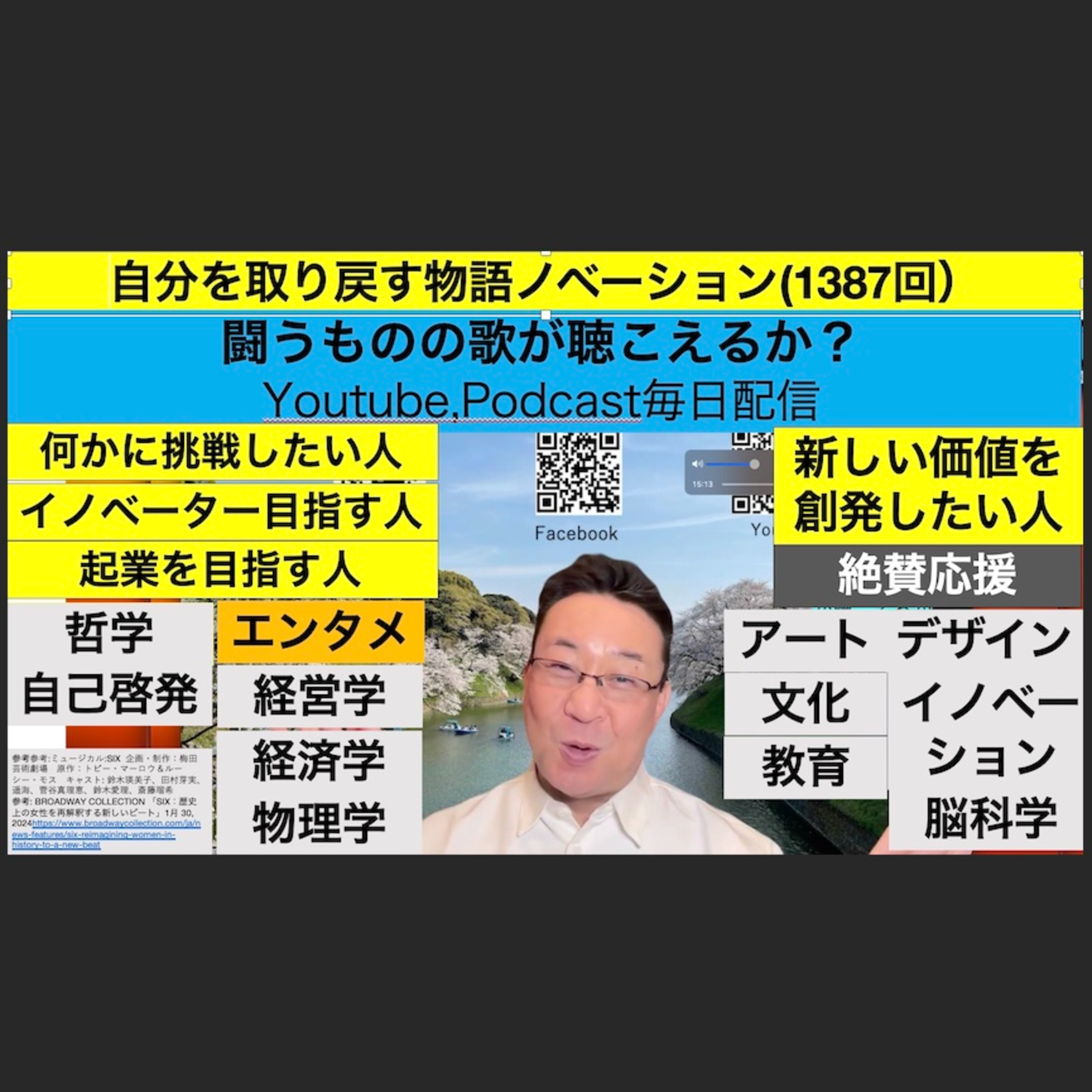 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"自分を取り戻す物語ノベーション(1387回)6人の妻を持たれていたヘンリー8世の、妻達によるミュージカルという、めちゃくちゃイノベーティブな作品に、感動させて頂きました
BROADWAY COLLECTION曰く
"「SIX」は、16世紀のイングランド王ヘンリー8世の6人の妻の生涯を現代風に再構築した革命的なミュージカルです。舞台上で、妻たちの半生は現代のポップコンサートに置き換えられ、6人の歌姫たちが主役になる権利を競い合います。"
"ヘンリー8世は、イングランドで最も悪名高い君主の1人で、その治世はもちろん6回におよぶ結婚でも知られています。"
"「SIX」は、歴史的に有名なこれらの人物をこれまでのストーリーテリングから解き放ち、何世紀にもわたって押し込められてきた男性中心の物語から彼女たちを救い出します。"
"このミュージカルを通して、それぞれの王妃は自分自身の言葉で自身の物語を語る機会を得て、力強い声で歌います。彼女たちはヘンリーについてを歌うのではなく、自身の経験、欲求不満、勝利について歌うのです。"
ここから私は思いました
1、物語を裏側から観てみる
→都合よく語られる歴史
2、異質だけど本質は同じものの結合
→悲劇の妻たち✖️ロックスター
3、自分を取り戻す物語
→語られる人物から語る人物へ
まずは、物語を裏側から見る目を持つ、ということにイノベーティブポイントを感じました。歴史は権力者やその時代に都合の良いように書かれるのが常でもあるので、本当はそれはどうだったのか?というようなクリティカルシンキングの眼を持つ、ということだなあと思いました
普段の生活の中でも、上司が言ってたとか、お客様が言ってたから、または偉い人や有名人がテレビで言ってんじゃん、みたいなことに、どうしても左右されてしまう私ですが
それを、こういう目で見るということが、とても大切だし、すごく面白い発見もありそうで、ここにイノベーションの種が落ちてる可能性もあるなあと思いました
また、シュンペーターさん言われるところの、イノベーションは新結合、なので離れたものを掛け合わせる、ということが面白いのですが、実はもう一つ秘密があって、本質やビジョンが同じ方向である、ということがあると、さらにパワフルになるのかもしれないと思いました
SIXでは、大変な目になった妻たち、と、ロックスター、という全く違ったものの掛け合わせが、それだけでも面白いのですが
実は両方に共通するビジョンとして、怒りや反骨精神が一致している、それがあるからこそ、さらなる爆発的なパワーとなって、その掛け合わせが弾ける、ということになってるなあと、思いました
違うものの掛け合わせでは、オープンイノベーションが、ビジネスの世界では当たり前になりつつありますが、そこで成功する要因として、全く違うものを掛け合わせるものを、私はUFO型オープンイノベーションと呼んでますが
そこで大事なのは、実はビジョンや大義が一致してることが大切と思ってます。今回のSIXはまさにそれを具現化しているなあと思いました
そして最後に思ったのが、これは自分を取り戻す物語なんだ、ということでした。普段の会社生活などでは、問いを立てられていることに慣れてる私ですが、実は自らの違和感や気になることに、自らが突っ込んでいく、つまり、問いを立ててやってみる、これがイノベーター資質としてはとても大切なことだと思ってます
大変な人生だった6人の妻たちが、ロックスターとして、自らの思いをぶつける、これはまさに、歴史から語られていた皆様が、自らの物語を自らが語り始める、そんなイノベーターへの変貌だなあと、その姿にも感動させて頂きました
一言で言うなら
自分の物語を取り戻すノベーション
そんなことを感じました
必見です!何よりも出演アーティスト皆様の歌が激うまでひっくり返りました^ ^
参考:ミュージカル:SIX 企画・制作:梅田芸術劇場 原作:トビー・マーロウ&ルーシー・モス キャスト: 鈴木瑛美子、田村芽実、遥海、菅谷真理恵、鈴木愛理、斎藤瑠希
参考: BROADWAY COLLECTION 「SIX:歴史上の女性を再解釈する新しいビート」1月 30, 2024https://www.broadwaycollection.com/ja/news-features/six-reimagining-women-in-history-to-a-new-beat
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/x6MSSHTKpsk2025-02-0423 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"自分を取り戻す物語ノベーション(1387回)6人の妻を持たれていたヘンリー8世の、妻達によるミュージカルという、めちゃくちゃイノベーティブな作品に、感動させて頂きました
BROADWAY COLLECTION曰く
"「SIX」は、16世紀のイングランド王ヘンリー8世の6人の妻の生涯を現代風に再構築した革命的なミュージカルです。舞台上で、妻たちの半生は現代のポップコンサートに置き換えられ、6人の歌姫たちが主役になる権利を競い合います。"
"ヘンリー8世は、イングランドで最も悪名高い君主の1人で、その治世はもちろん6回におよぶ結婚でも知られています。"
"「SIX」は、歴史的に有名なこれらの人物をこれまでのストーリーテリングから解き放ち、何世紀にもわたって押し込められてきた男性中心の物語から彼女たちを救い出します。"
"このミュージカルを通して、それぞれの王妃は自分自身の言葉で自身の物語を語る機会を得て、力強い声で歌います。彼女たちはヘンリーについてを歌うのではなく、自身の経験、欲求不満、勝利について歌うのです。"
ここから私は思いました
1、物語を裏側から観てみる
→都合よく語られる歴史
2、異質だけど本質は同じものの結合
→悲劇の妻たち✖️ロックスター
3、自分を取り戻す物語
→語られる人物から語る人物へ
まずは、物語を裏側から見る目を持つ、ということにイノベーティブポイントを感じました。歴史は権力者やその時代に都合の良いように書かれるのが常でもあるので、本当はそれはどうだったのか?というようなクリティカルシンキングの眼を持つ、ということだなあと思いました
普段の生活の中でも、上司が言ってたとか、お客様が言ってたから、または偉い人や有名人がテレビで言ってんじゃん、みたいなことに、どうしても左右されてしまう私ですが
それを、こういう目で見るということが、とても大切だし、すごく面白い発見もありそうで、ここにイノベーションの種が落ちてる可能性もあるなあと思いました
また、シュンペーターさん言われるところの、イノベーションは新結合、なので離れたものを掛け合わせる、ということが面白いのですが、実はもう一つ秘密があって、本質やビジョンが同じ方向である、ということがあると、さらにパワフルになるのかもしれないと思いました
SIXでは、大変な目になった妻たち、と、ロックスター、という全く違ったものの掛け合わせが、それだけでも面白いのですが
実は両方に共通するビジョンとして、怒りや反骨精神が一致している、それがあるからこそ、さらなる爆発的なパワーとなって、その掛け合わせが弾ける、ということになってるなあと、思いました
違うものの掛け合わせでは、オープンイノベーションが、ビジネスの世界では当たり前になりつつありますが、そこで成功する要因として、全く違うものを掛け合わせるものを、私はUFO型オープンイノベーションと呼んでますが
そこで大事なのは、実はビジョンや大義が一致してることが大切と思ってます。今回のSIXはまさにそれを具現化しているなあと思いました
そして最後に思ったのが、これは自分を取り戻す物語なんだ、ということでした。普段の会社生活などでは、問いを立てられていることに慣れてる私ですが、実は自らの違和感や気になることに、自らが突っ込んでいく、つまり、問いを立ててやってみる、これがイノベーター資質としてはとても大切なことだと思ってます
大変な人生だった6人の妻たちが、ロックスターとして、自らの思いをぶつける、これはまさに、歴史から語られていた皆様が、自らの物語を自らが語り始める、そんなイノベーターへの変貌だなあと、その姿にも感動させて頂きました
一言で言うなら
自分の物語を取り戻すノベーション
そんなことを感じました
必見です!何よりも出演アーティスト皆様の歌が激うまでひっくり返りました^ ^
参考:ミュージカル:SIX 企画・制作:梅田芸術劇場 原作:トビー・マーロウ&ルーシー・モス キャスト: 鈴木瑛美子、田村芽実、遥海、菅谷真理恵、鈴木愛理、斎藤瑠希
参考: BROADWAY COLLECTION 「SIX:歴史上の女性を再解釈する新しいビート」1月 30, 2024https://www.broadwaycollection.com/ja/news-features/six-reimagining-women-in-history-to-a-new-beat
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/x6MSSHTKpsk2025-02-0423 min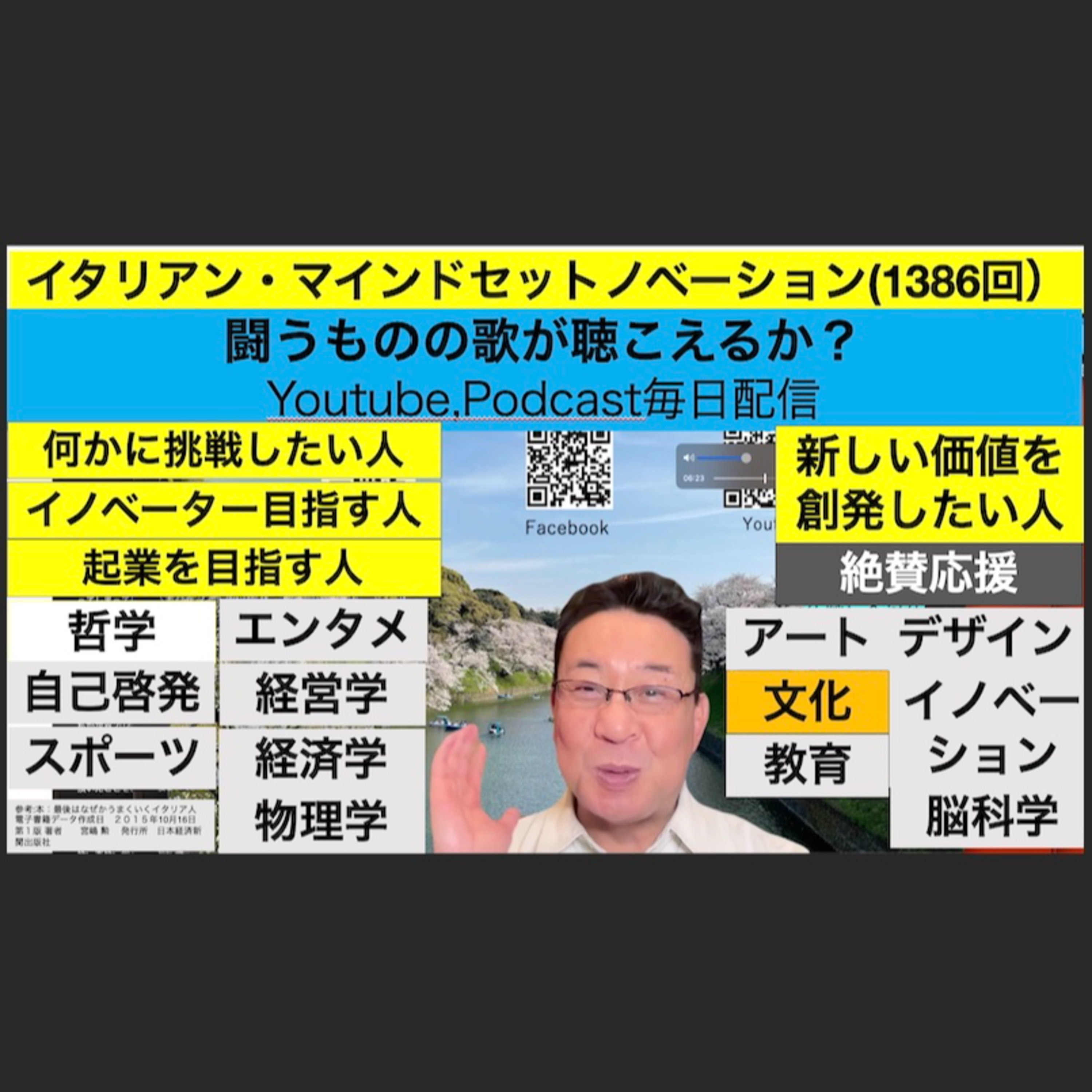 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"イタリアン・マインドセットノベーション(1386回)ワインジャーナリストで、イタリア文化への貢献に対し、“イタリアの星勲章”コンメンダトーレ章をイタリア大統領より授与されてる宮島勲さんから、イタリア人の考え方に触れて感動しました
曰く
"イタリア人は日本とは正反対の考え方をしているようだ。最高のサービスを提供するために苦労するつもりは毛頭ないが、同時に最高のサービスを受けられなくても、誰も文句は言わない。"
"すべてがうまく作動するということはそれ自体が目的なのではなく、それにより人が幸せになってこそ、初めて意味がある。効率、完璧なサービス自体が自己目的化して、働く人にストレスを与えたり、余裕のある人生を送れなくなってしまっては意味がない。"
ここから私は思いました
1、情熱の源の違い
→幸せの価値観の違い
2、仲間を大切にすること
→パッション、大義よりも仲間
3、イノベーティブ・マインドセット
→ゴールは人の幸せにある
私が世界20都市でオープンイノベーションコンテストを主催していた頃に、イタリアでも何度もコンテストを開催させて頂きましたが、なかなかメールの返事が来なかったり、進捗が全然わからなかったりでヤキモキする時もありましたが、最後はどこよりも素晴らしいコンテストを実施頂いたことを、思い出しました
日本との違いの理由として、一つは、情熱の源としての、価値観が全くちがうのかもしれないなと、思いました。ともすると、進捗通りにきっちりかっちりやるということは、実は、本来の目的ではなく、そこにくる方々に最高の体験をして頂くことこそが大切だと教えられた気がしました
そう考えると、情熱の源としては、大好きパッションというか、自らが大切にする価値観をブレずにやり切るというところや、独自の価値を出そうとする、個性派パッションにとても強さを感じました
また、イノベーター3つのフレームからみると、1パッション、2仲間、3大義とありますが、中でも、2仲間をとても大切にしているということなのかなとも思いました
そして、その延長線上には、人生のゴールとしては、仲間を含めた、自らの幸せを追求するということを感じました。だからこそ、仲間を一番に大切にしつつ、自らの大好きパッションも大切にする。それは仕事だろうが遊びだろうが、全て同じだと。そんな価値観があるように感じました。
そして、その価値観は、実は、イノベーションには、とても大切なことで、哲学者の三木清さんのいうように、人材のゴールは幸せである、という言葉そのもので、途中に起きるさまざまな失敗も、彩りの一つだから、細かいことは気にしなくていい、そんなおおらかで、とてもポジティブな思考があるのかなと思いました
もちろん、すべてのイタリア人や日本人がそうだというわけではないので、そのような価値観の違い、情熱の源の違いで、行動が全然違う形で現れるということを、理解した上で、お互いを尊重することが大事とも思いました
このようなイタリア人的なマインドセットは、これから、イノベーション時代には、さらに必要となってくるし、活躍する方がたくさん出てくるだろうなと思いました
そういえば、イタリアには、とても優秀なデザインスタジオがたくさんあったなぁとも思いました
これから必要とされるのはもしかしたら
イタリアン・マインドセットノベーション
なのかもしれない
そんなことを思いました^ ^
参考:本:最後はなぜかうまくいくイタリア人 電子書籍データ作成日 2015年10月16日 第1版 著者 宮嶋 勲 発行所 日本経済新聞出版社
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/17OF-kyaUl42025-02-0326 min
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"イタリアン・マインドセットノベーション(1386回)ワインジャーナリストで、イタリア文化への貢献に対し、“イタリアの星勲章”コンメンダトーレ章をイタリア大統領より授与されてる宮島勲さんから、イタリア人の考え方に触れて感動しました
曰く
"イタリア人は日本とは正反対の考え方をしているようだ。最高のサービスを提供するために苦労するつもりは毛頭ないが、同時に最高のサービスを受けられなくても、誰も文句は言わない。"
"すべてがうまく作動するということはそれ自体が目的なのではなく、それにより人が幸せになってこそ、初めて意味がある。効率、完璧なサービス自体が自己目的化して、働く人にストレスを与えたり、余裕のある人生を送れなくなってしまっては意味がない。"
ここから私は思いました
1、情熱の源の違い
→幸せの価値観の違い
2、仲間を大切にすること
→パッション、大義よりも仲間
3、イノベーティブ・マインドセット
→ゴールは人の幸せにある
私が世界20都市でオープンイノベーションコンテストを主催していた頃に、イタリアでも何度もコンテストを開催させて頂きましたが、なかなかメールの返事が来なかったり、進捗が全然わからなかったりでヤキモキする時もありましたが、最後はどこよりも素晴らしいコンテストを実施頂いたことを、思い出しました
日本との違いの理由として、一つは、情熱の源としての、価値観が全くちがうのかもしれないなと、思いました。ともすると、進捗通りにきっちりかっちりやるということは、実は、本来の目的ではなく、そこにくる方々に最高の体験をして頂くことこそが大切だと教えられた気がしました
そう考えると、情熱の源としては、大好きパッションというか、自らが大切にする価値観をブレずにやり切るというところや、独自の価値を出そうとする、個性派パッションにとても強さを感じました
また、イノベーター3つのフレームからみると、1パッション、2仲間、3大義とありますが、中でも、2仲間をとても大切にしているということなのかなとも思いました
そして、その延長線上には、人生のゴールとしては、仲間を含めた、自らの幸せを追求するということを感じました。だからこそ、仲間を一番に大切にしつつ、自らの大好きパッションも大切にする。それは仕事だろうが遊びだろうが、全て同じだと。そんな価値観があるように感じました。
そして、その価値観は、実は、イノベーションには、とても大切なことで、哲学者の三木清さんのいうように、人材のゴールは幸せである、という言葉そのもので、途中に起きるさまざまな失敗も、彩りの一つだから、細かいことは気にしなくていい、そんなおおらかで、とてもポジティブな思考があるのかなと思いました
もちろん、すべてのイタリア人や日本人がそうだというわけではないので、そのような価値観の違い、情熱の源の違いで、行動が全然違う形で現れるということを、理解した上で、お互いを尊重することが大事とも思いました
このようなイタリア人的なマインドセットは、これから、イノベーション時代には、さらに必要となってくるし、活躍する方がたくさん出てくるだろうなと思いました
そういえば、イタリアには、とても優秀なデザインスタジオがたくさんあったなぁとも思いました
これから必要とされるのはもしかしたら
イタリアン・マインドセットノベーション
なのかもしれない
そんなことを思いました^ ^
参考:本:最後はなぜかうまくいくイタリア人 電子書籍データ作成日 2015年10月16日 第1版 著者 宮嶋 勲 発行所 日本経済新聞出版社
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/17OF-kyaUl42025-02-0326 min